|
 �V���ł͂Ȃ�����ǖ{���J�X
�V���ł͂Ȃ�����ǖ{���J�X

�@�@�@�@�@�@�܂����q�����Ȃ��� |
�@
�@�@�@�������Ɗ������ |
�@
�@�@�@�����`�͗Ⓚ�ɂ� |
�����̋C���̓}�C�i�X5��
��ɗ��钹�������A�H��c��܂��Ă��Ċ��������B
�X�[�p�[���������Ă��鋍���ƁA���̉w�Ŏ��n���Ă����Ђ܂��̎�ƁA�Ȃ��Ȃ��̏��������͂����Ĕ����Ă����s�[�i�b�c�ƁB������ɏo���Ă�����B
�������l�Ԃ��H�ו���O�ɂ��Ċ��������ɂ��Ă���̂�����̂��D���B�N�������ł���̂����Ă���ƐS���e�ށB
���������A�V�W���E�J���������B�A�I�Q���������B�J�����q���������B
���}�K���͑��ς�炸�{�P�炾�B�K�r�`���E�������B-----�ȂX�Y�����B
��|�������������ɂ��āA���z���ɖ쒹�����Ă���̂́A�R�Z�݂Ȃ�ł͂̊y���݁B
���R�̕�炵483�@�@2019.12.26
�@ �@�@�@�@�@
�@
 ��̍�����
��̍�����
 |
���A�Q�N���̃R�[�q�[�J�b�v����ɁA�N���X�}�X�̏�����ЂƂ����A�������N���b�v�Ńc���[�Ɏ~�߂Ă����B
������12��16���B����̎c��͔��A�������B
�A�h�x���g�J�����_�[ (Advent
calendar)�́A�ҍ~�߂̊��ԁA24�p�ӂ���Ă��鑋������J���A�C�G�X�L���X�g�̍~�a�܂ł̓��𐔂���J�����_�[�B�����J����̂������炵�����A���̎����Ă���̂́A�|�P�b�g�ɂ��̓��̏��肪�������F�l��̂��́A��������ƂȂ�����i�Ȃ̂��B
�@�@�@�@�@�@ �T���^�����͎��̎��� �T���^�����͎��̎��� |
�I���q����B�ߐ{�͓~���}���悤�Ƃ��Ă��܂��B
���Ȃ����v���[���g���ĉ����������̃J�����_�[�A�L�t���͂��ׂėt�𗎂Ƃ��A�j�t���̐[���ɕ���ꂽ�ߐ{��̏�ɍL����V�̍����猩���Ă��܂����B
�A���f�X�̎R�X�Ɉ͂܂ꂽ�X�ɏZ��ł�������̂��Ƃł����ˁB
�t���ɓ��������鐰�ꂽ���A���A�ꍇ���ƃe�j�X�ŗV�сA�z�e���ł̒��H���y���݁A�ߌ�͗F�l�̂��߂ɂ�������J��----�G�ɕ`�����悤�Ȋ�т̂��ӂ�����̂䂤�ׁA���߂̂����C�ɂ͂���A����`������̎��ς킳�Ȃ��悤�ɂƎ����̉���������A�����オ�����Ƃ���n���œ|��A�^�C������̂����C�̊p�œ���ł��A������------���̓��������30�N�ȏ�o���܂����B
�ЂƂЂƂA�A�h�x���g�J�����_�[�̏����t���钩���ƂɁA5�烁�[�g���������R�ɑ���点�Ȃ���o�������̈����A���������ɓ`���ߑ���g�ɒ����A�C���J���セ�̂܂܂̕�炵�𑗂��Ă���l�����ƈꏏ�ɁA���n�̍Ղ�ŗx�������Ƃ��v���o���܂��B
���͌��C�B�I���q����Ɠ����N�̑��_���V�����Ƃ͂������C�ł��B������������Đ����Ă��܂��B
���R�̕�炵482�@�@2019.12.16
�@ �@�@�@�@
�@
�@
 ��͂�߂ł����N���X�}�X
��͂�߂ł����N���X�}�X

���N�̃N���X�}�X���[�X�B
���̂��ւɂ��A��̃q�o�̎��̎}��������t�����B
�u���[�x���[�̐Ԃ��t������A��V�̎���}���B�R���Ԃ��Ԃɒu���āA�N���X�}�X�̏��Ə������͌^������A��Ԃ̃��{�������B
�N�X�ȑf�ɂȂ��Ă����̂��A���̐S������\���Ă���̂�������Ȃ��B
�Q�T�����߂���ƃN���X�}�X�̏������苎��A�������̂��ꂱ��ɑウ�āu���߂łƂ��v�ɕϊ�����B
���R�̕�炵481�@�@2019.12.13
�@ �@�@ �@�@�@�@
�@
 �S�_�������I
�S�_�������I ���ւ��J���̂�҂�����Ȃ��قǂ̐����ŋA������_�A���@���Ղ��Ղ��c��܂��ĕ��Ă����B
�u�S�_�������I�v
�������Ɂu�ڂ������A�̂��ł��傤�v�Ƃ͌���Ȃ��������ǁB
����ҔF�m�@�\�������邽�߂ɏo���������_�́A�����O����ْ��C���������B�A�����_�o�����Ă�����ɋC�����肾�����̂��낤�B
�����C�ɏ��̂��A���ł��Ȃ����ƂɃC���C�����Ă����B
������e�X�g������A�ق�Ƌv���Ԃ�̃e�X�g������B
��w�̂��ߓ��e���ڂ��������Ă����B
1�j�@�܂��A�J�n�̈��A�B
2�j �����̔N�������������Ă��������B
3�j�@�J�n���獡�������炢�o���܂������H�i����Ȃ��Ȃ������Ȏ��₾�j
4�j�@�����傫�Ȏ����o����āA�u���v��傫�������Ă��������B�����\�������āA11���P�O�������v�̐j�ŕ\���Ă��������B
5�j�@�P�U���̃W�������̈�����G���������A�ꖇ�ꖇ���̖��O���m�F������B
6�j�@������ƕ������̂Ȃ��́A�������̐����Q��/�i�X���b�V���j�ŏ����Ă��������B
7�j�@���͓���̐������R�ɑ����܂��B
8�j�@�ł́i5�j�Ō����P�U���̊G�̖��O�����ׂď����Ă��������B
����ȗl�q�������悤���B
�߂ł����P�O�O�_��������_�́A�C�����E�L�E�L���Ă����炵���B�₽���`��ɂȂ��ăE���T�C���Ƃ��B����͎��n�^�]�̃e�X�g�B
�����A����ȓc�ɂɏZ��ł��āA�ԂȂ��ł͐����Ă͂����Ȃ��B�ǂ������i���܂��悤�ɁB
�������A�����̔N�������������_�ł��łɉ������l�����l�������炵���B
���̐l���������ĎԂ��Ȃ��ƕ�炵�����藧���Ȃ��ꏊ�ɏZ��ł���̂ɁB
�n�����Ƌ��ȂǂƂ����V�X�e�������Ȃ����̂��B
 |
���N�͓~��������̂������̔N�ɔ�ׂĎ����������A���̎�ނ������悤���B
��������Ă����V��́u�V���v�B�i�X�Y���ڃA�g���ȁj
���Y�悭���Ă��Č��������t���ɂ������A
���̏�Ǝ��H�������F����̌�낪�O���[�ł��邱�Ƃ���A���̌̂͗Y�̐������낤�B�������A���̑�������̂��̂�������������A�䂪�Ƃł́u���̂������v�ƌĂ�ł���B�j�̂������B�@�������A�����Ă邩�H |
���R�̕�炵480�@�@2019.12.10
�@ �@�@�@�@
�@
 �H�̏I����
�H�̏I����
�@
����������Ē�d�������Ă��邤���ɁA������̎��X�͂�������t�𗎂Ƃ��Ă����B
�Ⴂ�ʒu���瑾�z�������ɓ��荞�ނ̂ŁA�Ƃ̒��Ɏ�荞�[���j���[���������قǂ̃X�s�[�h�Ő������Ă���B
���̃s���N�̉Ԃ����ɒu���ƕ����͒g�������͋C�ɕ�܂�āA�����Ƃ���������Ȃ��Ȃ��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B
�X���Ɏn�߂���d�������悢���c�~���}����B
�������C�����オ�蕗���Ȃ����t���a�̍����A�o���̙���Ɣ엿���A�A���W�X�g�Z�[�W���@��グ�Ĕ��A�X�`���[���̔��ɂ��܂����ށA������Ƃ̒��ň�ԗ������ꏊ�Ɉړ�������----�Ƃ������d�����ς܂����B
�c���͉����ň�ĂĂ���A�C�X�����h�|�s�[�̕c���A����傫���|�b�g�ɐA���ւ���d�������Ȃ̂����A���N�̔����Ɍ��炵�Ă�100�{������B
�y���݂�����ɕ��S�ɂȂ�A�₪�ċ�J�Ɖ����A������Ƃ���߂��������̂��낤���B
�l����̂��悻���B
���ł��邱�Ƃ����܍s���A���ꂵ���Ȃ��B
���R�̕�炵479�@�@2019.12.3
�@ �@�@�@
�@�@�@ �@
 �A��͕|��
�A��͕|��
��T�̂��ƁB�V���ɂ���ȋL�����ڂ��Ă����B
�u1970�N�ォ��1980�N��ɂ����āA���{�ōw�����ꂽ�u�_�C�������h�v�����܁A����A�W�A�ō�����������Ă���B�i���ɗD��Ă��āA���Y��g�߂Ɏ��K���̂���C���h�Ȃǂœ��Ɋ��}����Ă���v�ƁB
����₱���ƒf�̗����n�߂Ă݂����A�Ō�Ɏc�肻���Ȃ̂͘a���ƍ���w�ւ̃_�C�������h���B
�������������́A�����̉��{���̒l�i�̂��̂�̂��펯���A�ȂǂƍJ�Ԍ����Ă����̂�^�Ɏ����Ԃɑa�����_�i�����͂܂�����҂����ǂˁj�́A�킴�킴���s�̕�ΐ��X�Ɏ���A��Ă����A�i�f�[�g�̏ꏊ�����s�������̂��j
�@�@�@�@�@�@���s�l���@��ΓX�@�����i�Ă炤���j<http://www.kyoto-terauchi.com/>
�����ł���Ȃ�̒l�i�̃_�C���̎w�ւ��v���[���g���Ă��ꂽ�B������_����ΓX�ɏڂ����킯���Ȃ��B���̓�l�̎o�����̓X�ŋ��߂�����w�ւ��Ă�������ƕ��������炾�����B
���ꂩ�琯�̐��قǓ��ɂ����߂����B
���������A��i�ƃE���T�C�e�ʂ̔��ꂳ���ֈ��A�ɂ��ז����鎞�ɉ��w�ɂ͂߂����Ȃ�-----�B
���Ƃ͂��łɋL���͂��ڂ�B�Ȍジ���Ƌ��ɂ̒��Ŗ����Ă����B�������͎C���Ă��܂��A������Ă��܂��Ă���B
�w�ւł�����o���Ă��邱�Ƃ�����B�������ɂ́u�����w�ւ̌����v���t�����̂悤�����A����Ȃ��̂��w�ɂ͂߂Ďd���Ȃǂł��Ȃ����_�ɂ̓��^�V�A�r���v���v���[���g���܂����ˁB
���āA���̓����}���܂����B�d�������߂Ă̂�т肵�Ă���3�P���̊ԂɁA�����i���₽���Ղ肩������Ȃ����j�����Ă��܂������̖�w�ɔ��N�O
�ɂ��炦���w�ւ�����Ȃ��I�����Ŏ������H�͂ƌ����u�����悩��w�ւ̃v���[���g�𗪂��v�������B
���̌����w�ւ���͂肨�ڂ�̂��Ȃ��ցB�q��ĂɎw�ւ͎ז�����ˁB
���āA�ߐ{��11���ł��B
���܂��܍s�����̃z�[���Z���^�[�̃`���V�Ɂu��A���v�A����i�ȂǍ����������܂��v�Ƃ������̂��������̂��^�̐s���B
�������ˁA���̃_�C������������Ă��炦��̂Ȃ�ǂ̂��炢�̒l�i�ɂȂ�̂��A�Ӓ肵�Ă��炨�����B
�ȁA���_��A���̂����łǂ����V�тɍs���̂�������Ȃ��H�@������l���N�����Ȃ����ˁB
�J�̒��A�o�����܂����B
�Ӓ�l�͂��������܂����B
�u�_�C���͎��͂�������ĐV�����f�U�C���ɕς���̂ł��B�ł������قǑ傫�ȃ_�C�������h�łȂ��ƍw���������̒l�i�ɐ܂荇���܂����B�����ł��ˁA���͂̃v���`�i�̋��z�ɂȂ�܂����˂��v�u�i���͂ƂĂ������̂ŁA���ꍂ�������ł��傤�B�v�����āu����ȃz�[���Z���^�[�ȂǂɎ����Ă��Ȃ��ŁA������Ƃ�����ΓX�ʼn��H�������Ȃ蓙����������Ȃ肵�������A�����ł���v�B
�ƂڂƂځB�A�蓹�̉J���₽���������ƁI
�u���̂����łǂ����V�тɍs���̂�������Ȃ��H�v-----��������߁I
���܂��F
���ɂɓ����O�ɂ��̍���w�ւ��͂߂Ă݂��B30�N�Ԃ肾�B������������ɂ͉������߂Ȃ�Ƃ��������̂ɁA�Ȃ�Ƃ˂����߂܂ł�������Ȃ�------�B
������ɂ��Ď��̂̓X�R�b�v�ɌL�A��֎Ԃ̃n���h���A��ɕs�p�i�̓������傫�Ȃ��ݑ܁B��������w�������Ȃ��Ă��܂��Ă����̂��B
�܂��ˁA��̉Ԃ̂��߂ɓ��������ʂ����Ȃ����̂�����d���Ȃ��A����Ɍ�����킯�ł��Ȃ��B
�l�ڂɕt���ꏊ�ł́A�L�̂悤�ɒ܂��B���Ďw���ۂ߂Ă��悤���B
�@
 |
�H�̎��̂��낢��
3���̕����̓J���^�`�E�k�k�@ �Ɠ��̍��肪����
�^��͉G�Z�E�J���X�E�� �����₯�̖�@�@
2���͉G�H�ʁE�E�o�^�}�E�k�o�^�}�Ƃ�
http://kemanso.sakura.ne.jp/nubatama.htm
���̉��̃C�K�C�K�́@�A�����J�t�E�E���߂肩��
5���́@�ւ̎��@�i��Ԃ��j�֖��͂��ꂩ��̂�
�^�͓Ȃ̎� ���H���ʓ|�����H�ׂ���
6���̏������̂́A�R���̂ނ����@�ނ������т� |
���R�̕�炵478�@�@2019.11.23
�@ �@�@�@
�@�@�@�@ �@
 ������̂ł��A�����܂��������ŁB
������̂ł��A�����܂��������ŁB
�^�J�T�S�����i�����S���A��p�S���Ƃ��j�����ȃ������@�@��p���Y�̋A���A��
�@
 |
�����͂������A�����ƉԌ�����ʂɂт�����Ƃ����ŋ��낵���قǑ�����A���B
�Ȃ܂��p�����ꂢ�Ȃ����ɔ�������邱�Ƃ��Ȃ��A������ɂ͂т���B�c�O�Ȃ��獁��͂Ȃ��B
���ɂ��̉Ԃ͖和�̐^�ɉ���o���A���������������Ĕ�����炸�ɂ�����A7���Ɉ�x�Ԃ��炩���A���̌����n�����悤�Ƃ��Ă���
�Ă���Œ��́A���~���߂������̎����ɐV�����Ԃ������B
�t���ׂ����ɐ����Ă��āA�ԕق̗����ɐԂ�������̂ŁA�e�ՂɌ������邱�Ƃ��ł���B
���{�̍ݗ���Ƌ����A���邢�͌��G���āC�E�C���X��}��邱�Ƃ���A�O�������@�ɒ�G����Ǝw�肳���̂��߂���������Ȃ��B
�́@��̑܂̒��ɂ͐�߂��킪�����Ă���B
�u������v�Ƃ����ړI�ɒ������B
�Ԃ̖��͒Z����-----������3�������Ԃ͎����Ȃ�����ǁA���ꂢ����ˁB |
�O�������@�F
�O�����玝�����܂ꂽ��A���̒n�悩��̈ړ��킪�A���{�����̐��Ԍn��j��̂�h������2004�N5���ɐ����A05�N6���{�s���ꂽ�B
�X�ɔ�Q���z�肳���ꍇ�ɂ́A�u����O�������@�v�ɑ����ċ쏜�Ƃ��̊Ǘ�������Ƃ̖��߂�������邪�A�����������{�̎��R�ɓK�������A���͂����Ƃ₻���Ƃ̋쏜�ł͒ǂ����Ȃ��B
����O�������@�F
�����ł́@�A���C�O�}�A�J�~�c�L�K���A�I�I�N�`�o�X�A�A�J�Q�U���A�K�r�`���E�A�\�E�V�`���E�A�J�_���V�A�Z�A�J�S�P�O���A�E�`�_���K�j�ȂǁB�A���ł̓A���`�E���A���F���Ĕh��ȉԃI�I�L���P�C�M�N�A�I�I�n���S���\�E�Ȃǂ��w�肳��Ă���B
���R�̕�炵477�@�@2019.11.14
�@ �@�@�@
�@ �@
�@
 �т̒��ɉƂ����Ă������
�т̒��ɉƂ����Ă������
���t���n�߂��т̂Ȃ��Ɂu�s�b�v�V���[���v�Ƒ傫�ȉ����������B�����A�܂��B
���Ԃ̑傫�ȃK���X���ɖ쒹���Ԃ���A�f�b�L�̏�ŋC�������Ă���B
���𔖂��J���A���𗧂ċr�����������-----�B���߂Č��钹���B�F���������낤���H
��ʂ̑傫�ȃK���X���ɗт��f�荞�݁A����������쒹����э���ł��鎖�̂����т��т���B
���̂��ѐ\����Ȃ��C�����ł����ς��ɂȂ�B
�@
 |
�@
���̎��_�Ō����Ė쒹�Ɏ���o���Ă͂����Ȃ��B
�����ǂ̊댯�����邱�ƂƁA���������l�Ԃ̓������t�����쒹�����R�̂Ȃ��łǂ������������邩���悭�킩��Ȃ����炾�B
�����̏ꍇ�ȂǁA�ɒ[�Ɍ����ΐl�Ԃ̓����������Đe�������������邱�Ƃ�����B
�@ |
 |
�����ƌ���邱��10���B
�����B
�悤�₭�����オ�������̒��́A�f�b�L�ɂ����Ă���T���_���̉A�ɉB���悤�ɐg�����B
�@ |
 |
�@
�D��S�����i�A�z�Ƃ������܂����j�ȉƎ�́A�T���_���������グ�Ă݂�B
���𐂂炵�̂̃o�����X����낤�Ƃ��Ă��邩��A����͂Ȃ�Ƃ����C�ɂȂ肻�����B
�@ |
 |
�@
�����ƁB��B
�g�����X�ɂ��܂��ĐS�𗎂��������悤�Ƃ��Ă��邩�̂悤���B
�ꎞ�Ԍ�A�тɏ������B |
���̒�����E�E�O�C�X�B���Y���F�ňႢ�͑̂̑傫�������Ȃ̂ŁA�ǂ��炩���ʂł��Ȃ��B
���܂܂Ŗ����͕����Ă������A����Ȑg�߂Ŋώ@�ł����̂́A���߂Ă̂��ƁB
���́u�ف`�ق�����v�̖����̓I�X�̂���B�꒣��錾�����������߂Ė��̂Ŏ�����3������5���̃J�b�v�����O�Ƃ��̌�̈琗�̂���Ɍ�����B���́H�u�������v�ƕ������邩�����Ȑ��Ŗ��B(�����Ƃ����j
�����Ă̐���ɂ��傫�ȋ������Łu�ف`�ق�����v�ƕ������Ă��邱�Ƃ����邪�A����́u���Ԃ�I�X�v�̖����Ȃ̂��B�܂�A���e�Ȃ������������ȃI�X�̐����B
���̐����Ɨ������������~��Ă����悤�ȂȂ�Ƃ������Ȃ��C���ɂȂ邪�A���́u�{�N�A���e�Ȃ������患�B�������̎q�����Ȃ����v�Ɩ��Ă���炵���B
��@�E�O�C�X�i�w��: Horornis diphone�j�X�Y���ڃE�O�C�X�ȃE�O�C�X���B
���R�̕�炵476�@�@2019.11.7
�@ �@�@�@�@�@�@�@
�@
�@
 ���[�����ĐV����������
���[�����ĐV����������
���r���[�Ɋ�p�ŁA�������̂�����Ε������Ă݂������_�B
�z�\���N�ɂȂ�Ƃ̒��̓d�C���i�����͂��߂��B�@�Ȃ����������炵���B
�̏�ꏊ������ꂽ���R��������A�Ȃ�Ƃ����̃g���u���������ʼn������悤�Ƃ���----�H�w�n���n�j�̖ʖږ��@���B
�@
 |
���ɂԂ����̂������̂��A�|���@�̎茳�̃X�C�b�`�����Ă��܂����B
�d�����I��������_�Ŗ��ӎ��Ɏ������Ă��邩�炩������Ȃ��B���s�V�������A���^�V�B
���ɂ��A�O���ɐV�����X�C�b�`�����t����
�u�ǂ����I�v�u�����悤�ɂȂ�������I�v |
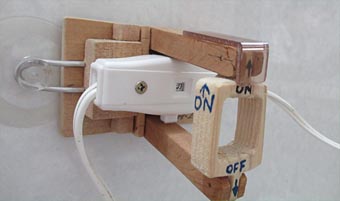 |
�������͂�X�C�b�`����ꂽ�u�E�H�[�^�[�W�F�b�g�i���͂��������ׂ������Ŏ��Ԃ�|�������B�j�v�B
���������̂ł����������Ƃ��N���������B
�V�����X�C�b�`----�Ƃ�ł��Ȃ��A�i���O������----�����t���A���ڂ����G��Ȃ��Ă������悤�ɍX�ɖؐ��̃X�C�b�`����ɂ��Ԃ����B�܂��֗��͕֗������ǂˁB |
 |
�u�����̃V�����[�A���܂��Ă��ĉ�����ˁA���̐^������ɉ���������������̂Ɂv�ƙꂢ���̂����ɂ��A�V�����[�w�b�h�ɃG�N�X�e���V�����E�A�[�������t�����B
������厖�ɂ��Ă���A���ނ̃��b�h�E�b�h���g���āB
�������ɑ̂��Ђ˂�Ȃ��Ă��܂�����������������悤�ɂȂ����B�C�����������B |
����Ȃɉ��������Ƃɂ��C���X�Ȃ̂́A���������̂��B�����łȂ�������ŐV���̋@�B�E��B���g�����̂ɁB
�����C�ɂ̓s�J�s�J�̃X�e�����X�̃A�[�����t���Ă������낤���A�T�C�N�����|���@�ŏ��_���X��x�ꂽ���낤�ɁA�v�V�����Ɖ����Ǝ��Ԃ��������C�����悭����Ă������낤�ɁB
�u�Ȃ�ł��C�����Ă���Ă�������l�ˁv�Ƃ�������邪�A���[�����ĐV������̂ق������ꂵ��------�B
�ł��A�u�V�ϒn�ق��N�������A���Ƃ����̎��Ԃ����P���悤�Ƃ���́v�������_�́A�ĊO����ɂȂ鑶�݂Ȃ̂�������Ȃ��ȁB
���R�̕�炵475�@�@2019.10.29
�@ �@�@�@
�@�@�@�@ �@
 ���������������O�������ā@�@Salvia leucantha �i�T���r�A�E���E�J���T�j �V�\��
���������������O�������ā@�@Salvia leucantha �i�T���r�A�E���E�J���T�j �V�\��

�H�e���炫�n�߂邱��A�����ԕ��L���O�̌`�̉Ԃ���������t���A���ڂɂ��N�₩�ȉԂ����̎����̒���ʂ��Ă����B�i����ԏ��A�O�`�ԂƌĂԁj�i��{��̉ԐF�͔��B���E�J���T�Ƃ̓M���V����Ŕ����Ӗ�����B�j
���|�p�Ƃ��ĉ��ǂ���邤���ɂ��낢��Ȗ��O��t�����āA���₱�̉Ԃ́u�A���W�X�g�Z�[�W�v�u���L�V�J���E�u�b�V���Z�[�W�v�u�x���x�b�g�Z�[�W�v�u�r���[�h�Z�[�W�v�Ƃ��������O�������Ă���B
�т̒��ɂ������ƍ炭���̉Ԃ����ċ����q�ɁA
�u���O�͂ȂɁH�v�ƕ������ƁA��u�ǂ��I�Ԃ��ŔY�ނ��A�܂��u�A���W�X�g�Z�[�W�v�Ɛ������A�u�ق��ɂ���Ȗ��O�������Ă���̂�v�Ƒ����邱�Ƃ������B
��������ƕ��ʂ́u����ȂɊo�����Ȃ��ȁv�Ƃ̕Ԏ����Ԃ��Ă���B�������ȁH
�����A�����J���Y�̉ԁA�ƌ����Γ������肪�ǂ���⊣���C���̓y�n���D���ŁA�ϊ����͂����B���ꂪ��ԁB
12���ɓ���ƒn�㕔�����A��������傫���x�肠���đϔM���̂���傫�Ȕ�----���̋��Ȃǂ������Ă��锒�����̒��Ɏd��������ʼnƂ̒��̈�Ԋ����ꏊ�ɁA���Ƃ��q�Ԃ̃g�C���̑��Ȃǂœ~�z����������B
����̌��̉Ƃ��Ƃ��̂܂ܒ�œ~�z���ł������ǁA�}�C�i�X15���ɂ܂ʼn����邱�Ƃ�����ߐ{�ł͂���͖������B
�{���ɍD���ȉԂ����炱��Ȏ�ԂȂǑ劽�}�B
�@�@�@*�A���W�X�g��2���̒a���Ȃ̂ɁA��Ȃǂɉ��̂Ȃ����͎����Ă��Ȃ��B
�@�@�@�@�܁A���̉Ԃ̂ق��������y���߂Ă�����ˁB
���R�̕�炵474�@�@2019.10.19
�@ �@
 �t�m�炸�A�Ԓm�炸�@�R���`�J���@�i�����ȁj�ʖ��C�k�T�t����
�t�m�炸�A�Ԓm�炸�@�R���`�J���@�i�����ȁj�ʖ��C�k�T�t����

���̎����ɉԂ��炩���A���N�̉Ăɂ����ėt��炷�̂́A�֎ꍹ�i�ފ݉ԁj�ƈꏏ�B
��̒ւ̖̉��ŁA��������̈������������Ȃ���悤�₭�Ԃ��炩�����B
�Ԍ��t�́uMy best days are past�v�B------�����ސg�ɂ܂����v�����B
������^�l�Ɋ܂܂��A���J���C�h�̈��ł���R���q�`���͌����ŁA���ɁE�_�o�ɂɌ��p������Ƃ���邪�A��������m���Ă����͔̂{���̐A����̐��Y���o�ɂ��p�����Ă������Ƃ��B�Ⴆ�Ύ�Ȃ��X�C�J�̍�o�ȂǂɁB
���͎s��łقƂ�nj������Ȃ����A30�N�قǑO�ɂȂ邩�u��Ȃ��X�C�J�v�����Ă͂₳�ꂽ�������������B
������Ă��킪�Ȃ��B
�ǂ�����H�ׂĂ��ʓ������B
�m���ɕ֗��Ŋy���������A�����ɂ��́u�s�b�A�v�b�v�Ǝ�������ɔ���y���݂��Ȃ��Ȃ����B���̂����Ƃ������Ƃ��Ȃ����낤���A�ŋߎ�Ȃ��X�C�J���������Ƃ��Ȃ��B
 �@ �@
�@�@�@���]�L�̔�Q�������炷���H�䕗�����Ă���B
���R�̕�炵473�@�@2019.10.11
�@ �@
 I wanted to ask if you are the author of the page about plants
in books about Anne Shirley?
I wanted to ask if you are the author of the page about plants
in books about Anne Shirley?
�O��̃e�[�}�u�X�̃s�A�m�v�̑���
�X�Ɏ̂Ēu���ꂽ�s�A�m��e���A�c�����납�特�y�ɐe����ł�����l���̃J�C�́A������̎w���̂��ƍ���ȏɂ��������w�͂𑱂��A5�N�Ɉ��J�����u�V���p���E�R���N�[���v�ŗD������B�J�C�́A�����̏����ɂ́A���t�ł��鈢����s��s�A�j�X�g�Ƃ��đ��݂��邱�Ƃ��s�����Ƃ����A���E�I�ȃ~���[�W�V�����E�n���h�h�N�^�[�Ɉ�����̍���̎�p���˗�����B
�J�C�Ƌ��Ƀ��n�r���ɗ�ނ��Ɩ��N�B������́A�Ⴂ���̉��t�������ۓI�ȃJ���o�b�N�E�R���T�[�g�𐬌�������B
������ƃJ�C�́u2��̃s�A�m�̂��߂̋��t�ȁ@�����F����ȁE���E���@���Y�v�̏�ʂ��A���t�̓��������ŏI����Ă���̂ŁA�悯���Ɉ�ۂ��[
�܂�B�i�����ǂ�ŗ܂��]�����������ɂȂ����̂͂����炭���߂āB�j
�@
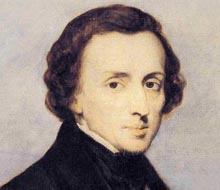 |
��i�ɂ���A�V���p���E�R���N�[���i���m�ɂ̓t���f���b�N�E�V���p�����ۃs�A�m�E�R���N�[���j���J�Â����̂́A�|�[�����h�B
�|�[�����h���܂�̍�ȉƂł���s�A�j�X�g�́u�s�A�m�̎��l�v�Ƃ��Ă��t���f���b�N�E�V���p���̉��y�̐_����搂���p�҂@����R���N�[���B���������ăR���N�[���ʼn��t�����̂̓s�A�m�̂݁B
�ۑ�Ȃ͑S�ăV���p����i�Ő�߂��Ă���B
�@ |
�O�u���������Ȃ�܂����ˁB
�|�[�����h --- �����V���� --- ���W�F���L����----�Ǝv�������炵�Ă������̌��ցA�|�[�����h�����ʂ̃��[�����͂����B
�Ȃ�Ƃ������������낤���B���[���̓��e�͌f��̒ʂ�Ŏ���Web Page�����ĘA�����Ă����̂������B
�hI am from Poland and I run a similar website. I would like to
exchange experiences.�h
�������ŁI�������p�ꂪ�S���ƂȂ��B����������������A
�hThank you for your answer. Unfortunately, I don't know
Japanese, but Google Translate currently allows me to read Your
texts.Your work is really impressive.�h
���������ˁB
�͂́A���������B�p��̐��p��ȂǕ�����Ȃ����爥�A���x�Ŏn�߁A�{�_�͖|�₷���P���ȓ��{��̕��͂�ςݏd�˂�����킯���ȁB�u���Ȃ����p�ꂪ�s���ӂȂ悤�ɁA���͓��{�ꂪ�ł��Ȃ��v�B���̃X�^���X�������ȁB�A�����D���Ȃ̂�����A�W�̓C�[�u���ł���ƁB
�V�����ł����|�[�����h�̗F�l��Web Page�̃A�h���X��
<
https://zielnikmontgomery.blogspot.com/search/label/gatunki
>
�A���w�҂̔ނ̖��O�́uStanisław Kucharzyk�v.�B����������̂ŁA�u�|�[�����h�̐l�v�Ƃ����t�H���_�ɂ���܂ł̃f�[�^���d�����Ă���B
�NjL
��̃y�[�W�������Ɂu�|�[�����h�ꁨ���{��v�֕ϊ�����ƁA�\���̍����ɑ傫�ȈႢ������̂��A�͂���߂���Ȃ��Ă��܂��B�����Łu�|�[�����h�ꁨ�p��v�ւƖ|�Ă݂��B-----�悵�I����ł��́u������O�v���������������Ƃ��`����Ă���B�����Ƃ��Ẳp��̗͂��ĔF�������B
���R�̕�炵472�@�@2019.10.4
�@ �@
�@
 �ǂ��Ղ��
�ǂ��Ղ��
�@�@
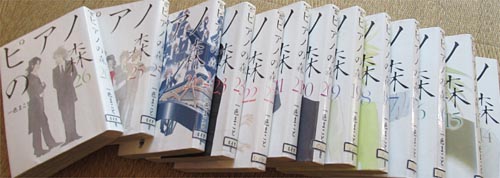
�����疟��ɔM�����邱�Ƃ�Y��Ă����̂��낤���B1980�N��́w��͓S��999�x�A�w�L�����f�B�L�����f�B�x�A������̎G���w�Ȃ��悵�x�ɘA�ڂ���Ă����w���т܂�q�����x�ȗ����������30�N�ɂȂ邩������Ȃ��B
�}���ق��疟����i���̓A�j���Ƃ����炵���j����Ă���̂͏��߂Ă̂��Ƃ��B
�w�s�A�m�̐X -The perfect world of KAI-�x�i��F�܂��ƍ�j
���͂��̃A�j���̌���Ƃm�g�j�ŕ��f�����h���}�ɂǂ��Ղ�ƐZ���Ă���B
�������Ƃ��Đ��܂�Ȋ��ň��l���̈�m���C�́A���w5�N���̎��A�s�A�j�X�g��ڎw���J�{�ɏo��A�O�サ�Č�ʎ��̂Ŏ��ɂ߂����V�˃s�A�j�X�g�E������s��ɂ��̍˔\�����o����s�A�m�̐��E�Ɉ������܂�Ă����B
���̖����ǂ�ł���Ɓi����͌���A�Ȃ̂��H�j�_�����������F�ɕϐF�����{����A���t�}�j�m�t��V���p���̉����������Ă���悤�ȋC�������Ă��邩��A�s�v�c���B
 |
 |
�����̕�̂̂��傤��Ђ�����N�������炦�Ă���B
�����Ă���ꏊ�ɂ���Ď��n���鎞�����Ⴄ�̂ŁA�����ƂɐL�т����G���Ă͊��G���m���߁A�����ĉƂ̒��Ŋ����������傤��Ђ��ɂ���B�������N��!
���̎�����́A�����ݖ��ł͂Ȃ��ĕ��ʂ̏ݖ����g���A������������ėL�@�ۑ哤�����̏ݖ����B
�������N���~��45�E���Ă����B�����160�ɂȂ����B�������̂��߂Ȃ̂œK���ɂȂǂȂ��B������Α����قǗǂ��̂��B�B |
���R�̕�炵471�@�@2019.9.30
�@ �@�@�@
�@�@�@�@ �@
�@
 ��������ĕ����Ă�����A�����Ă���
��������ĕ����Ă�����A�����Ă���
�@ �S����� �S�����
�䕗�̗]�g�������r�ꂽ�����A�߂��̎��܂Ŗ쒹�̂��߂̃N���~��T���ɍs�����B
�q�}�����̎킪�A���̓~�̒������̉a�ɂ͂���������Ȃ��B
����Y�܂��Ă����Ƃ���̂��̗��ʂ������Ԃ́A�܂�œV����u�}�i�v���~���Ă��Ă悤���B
�Ⴄ�̂́A�����ł͂Ȃ����ƁB�����炭�����̎��n�����N�Ō�̂��̂ɂȂ邾�낤�B
�̔���ނ��A���g�����������Ă��̓~�ɔ����悤------�Ȃ�ł�����n������ƁA�����͂������������Ǝv���Ă��邩��B���������A�N���~�̔���������������̂́A���ؐ��̍ޗ��ɂȂ�炵���B
�тɎR�I�������n�߂Ă���B�Z�����Ȃ肻���B
�@�@�@ �@�@���ԃz�g�g�M�X �@�@���ԃz�g�g�M�X
���R�̕�炵470�@�@2019.9.25
�@ �@�@�@
�@
 �����̏ے��Ȃ̂�---- �u�@���t�v�Ƃ������t��������
�����̏ے��Ȃ̂�---- �u�@���t�v�Ƃ������t��������
�f���e���r�Łu�@���t�v�Ȃ錾�t���Ă����̂́A�������\�N���O�ɂȂ邾�낤���B
�Ō�ɂ��́u�@���t�v�����̂͂����A�����v���o���Ȃ��قǂ��B
�@���t�Ƃ́A�u�����̑ԓx�⓮�삪���i�ŐT�݂̂Ȃ����ƁB�]���āA�v���̐y�͂��݂Ȃ��ƁA�����̐T�݂��Ȃ��A�����Ȃ��Ƃ������悤�ɂ��Ȃ�B�v�Ɠ��{��S�ȑS���ɂ������B
�v���������A������������Ȃ��Ƃ킪�g��U��Ԃ��Ă݂�B
�u�͂����ρv�̗R���ɂ͏�������悤���B
�t�A�ŏ��ɏo��̃n�X�̗t�͐��ʂɕ����A�n���̍��ƌq���萎�̖�ڂ������Ă���B�Ƃ��낪���̏��Ԃ�̗t�́A�X�C�����̗t�̂悤�ɐ��ʂɕ����A�Y���Ă���悤�Ɍ����邱�Ƃ���A�v���������ƌ��т��u�@���t�v�ƌ����ƁB
������́A�]�ˎ���̑��i���j�̖≮���A�ڋq�w��@�t���Ƃ����悤�ɂȂ����Ƃ������́B���~����Ɏg���n�X�̗t�́A�Z���̎��v������---�Վ��ɂ��q�̑��������---������@���t�B
�n�X�̉Ԃ��t�����������ł͂��邪�A������ƂˁA������������̂�����ȁB
 |
�ߐ{�����̏H�̖��A�n�������Y�̒Ìy�����S���Y���̂��X�ɏo�Ă����B
�ЂƂT�O�~�B
�o�n�߂̒������������ăT�N�T�N���������B
�H�C�`�W�N���łĂ���̂������������낤�B
�W�����Â���ɖZ�����Ȃ�B |
 |
�g�}�g�̑܂ɃJ�^�J�i�Łu�L�Y�v�Ƃŏ�����Ă������B�T�P�O�O�~
����Ȃ�A���̃g�}�g�B
������l�͋��������C�����낤�ɁB�L�Y�����āI
�V���������Ƃ��̂悤�ɐK���ꂵ�Ă��܂����A���ɂ͕ς�肪�Ȃ��̂ɁB |
�@�@�@�@�E�@����ς܂�Ă�����̌��̋�`�̋�̂ق̂������
���R�̕�炵468�@�@2019.9.6
�@ �@�@ �@
�@
 �D�̒�����炭�Ԃ́@�@ �n�X�@�i�X�C�����Ȃ̑��N�������j
�D�̒�����炭�Ԃ́@�@ �n�X�@�i�X�C�����Ȃ̑��N�������j
���[�O���g�̊W���J���āA���ɕt���Ă��郈�[�O���g���r�߂܂����H
�l�ڂ��Ȃ��Ƃ��́A���������ĊW���r�߂�----���߂����Ȃ�Ăق��Ƃ��I
���l�̖ڂ�����Ƃ��́A�X�v�[���ł���������Ă������ς��r�߂�B
���ꂪ���N�̏K�����������A�ŋ߂͂��̉B�ꂽ�y���݂������Ȃ��Ă��܂����B
�u���[�^�X�E���ʁv������̕�炵�ɐZ�����Ă��āA���[�O���g�̊W�ɝ������A���~�j�E�����g����悤�ɂȂ�������Ȃ̂��B
���[�^�X�Ƃ͘@�E�n�X�B�n�X�̒n���s����債�����̂������R���B
�傫�ȗt�͐��̏�ɗ����オ��A�Ԃ��炩���h�{��~���A�H�̏I���ɂ͘@���E�����R���ɂƐ�������B
�n�X�͂���Ȏd�g�݂������Ă���B
�����̓D�̒��ɂ���n���s�i�����R���j���璷���t����L���A���ʂ̏�ɓ˂��o�����̐�ɗt������B
�n�X�̗t�̒������ɂ͏����Ȍ����J���Ă��Ē����t���ɂȂ���A���̗t���ɂ��������Ă��̂܂ܒn���ɂ��郌���R���̌��ɘA�����Ă���|�|�|�A���ʘH�݂����ɁB
���̋⌊�̖����́A�ċz���邱�ƁB�����R���͗t�Ɨt����ʂ��Ď_�f�Ă���̂��B
�n�X�̗t������āA�t������n���s�ł��郌���R���܂ł̎_�f�����̃��C�����₽���ƁA�������Ƀn�X�͍��邱�ƂɂȂ�̂��낤�B
���̍��������Ԃ�����邽�߂ɁA�n�X�̓��b�N�X������t�̕\�ʂɕ��債�A�\�ʂɂ͔��ׂȖтɎ����ˋN�������Ă���----���̃��b�N�X�{�ڂɌ����Ȃ��ׂ����ˋN���̓����ŁA�n�X�̗t�͐���e���A�ʂƂȂ������͕\�ʒ��͂ɂ���Đ���̋ʂ̂悤�ۂ܂�A�D�⍩����t�ɂƂ��Ďז��Ȉٕ��𗍂߂Ƃ�Ȃ���]���藎����Ƃ�����Ƃ����̂��A���̃R���R���������ʂ̐��̂Ȃ̂��B
���ꂪ���[�^�X���ʁiLotus effect�j�@�i�uLotus-Effect�v�Ɓu���[�^�X�G�t�F�N�g�v�͓o�^���W�j
�ޗ��H�w�ɂ����āA�n�X�Ȃ̐A���Ɍ����鎩���w���p��ŁA�ŋ߂͓h���A�����ށA�z�Ȃǂ̕\�ʂɃ��[�^�X���ʂ�^���\�ʂ��������Ă���ƕ����Ă���B
�w偂�I�̋r�̓��������A���{�b�g�̓���ɉ��p����A�g���{�̑̂̍\�����A��s�@�̐v�ɎQ�l�ɂȂ�悤�ɁA�]�������Ȃ����A���̐��������l�ԎЉ�ɖ��ɗ���̈���낤���B
���₢��A�l�ԎЉ�ɖ��ɗ��Ƃ́A�����Ȍ��������낤�B�ɐB�Ǝq���ɉh�ɑS�͂��グ�Ă��邱�Ƃd���ׂ��Ȃ̂ł͂ƁA���낱��]���鐅�ʂ��ςȂ���l����B
 |
 |
�n�X�̉ԁ@�@�E���͉Ԃ��U������̃n�X�̎�
�@�J�I�̌����u�n�X�O�`�E�@���v�ƌĂԂ̂͂��̗l�q����B |
�n�X�ɂ悭���Ă��邪����̓T�g�C���̗t |
�܂��T�g�C���i�����j�̗t�ł������悤�Ȍ��ʂ�������悤���B
�w���t�W�x�ɂ͂�������B�@�@�@�@�@http://kemanso.sakura.ne.jp/umo.htm
�@�@�E�@�t�͂�������������̈Ӌg���C���ƂȂ���͈̂��̗t�ɂ��炵 �@�@�@�������Ӌg���C�@�@��16-3826
�@�@�@�@�@�@�@�i�Y��Ɏ����̍Ȃ����̗t�ƕ\�����Ă���I�j
��ɃC���h��l�p�[���ŐM�����Ă���q���h�D�[���ł́A�n�X�̉Ԃ͏�������P���̏ے��Ƃ���Ă���B�܂���������{�ł́u�@�͓D���o�łēD�ɐ��܂炸�v�ƌ������킳��A�Ԃ͕����Ř@��(���)�v�ƌĂ�
��Ɋy��y���ے�����ԁB���厛�̑啧�l�������Ă���̂��@�؍��B
�@
���R�̕�炵467�@�@2019.9.1
�@ �@�@�@
�@�@�@�@ �@ �@
 �ߐ{�Ȋw���j�ف@�J�ًL�O�u�����Ă���
�ߐ{�Ȋw���j�ف@�J�ًL�O�u�����Ă���
�u���̃e�[�}�́u�~���@�̗��j�Ƃr�o���R�[�h�ӏ܉�v �@
����́A�~���@�̔�������f�W�^���E�I�[�f�B�I�܂ł̊T���j
 |
�܂��A�G�W�\���̉~���^�~���@�ɂ��Ă̐���������A�����Ńx�����i�[�̉~�Վ��~���@����������A���݂̐��E�I��ƃr�N�^�[�������߂���܂ł̉ߒ������ꂽ�B
�u���̒��ň�Ԉ�ۓI�������̂́A�G�W�\���̔��������X�ǎ��~���@�W������
Edison Standard Phonograph 1905�@
���Đ����鉹�������Ƃ��B
��₩����镔����������̂́A�����̂��̂�����`�ƂȂ��Ĕ�яo���A���͂̋�C���A�ƌ�������z��
�ł��܂����B
���ʐ^������B���邢����w�ɒu���Ă���̂ŁA����Ȏʐ^�����B��Ȃ������B
�������A�܂��ƂȂ��M�d�i�Ȃ̂ł�z�u��ς��邱�ƂȂǂł��Ȃ��B
�@�G�W�\��(Thomas Alva Edison
1847�`1931)�����߂Ē~���@�삵���̂�1877�N�B
�d�b�p���b��̐U���𗘗p���āA�X��h���������̃��{���ɐ��̔g�`�����ݍ��݁A���̉����Đ���������ɐ��������B
���̌�A���̘^���Đ����u�̔��z��W�J�����A�~���`�̃h������������~���@�������������̂��AJohnKruesi�B1877�N�̂��Ƃ������B
���Ȃ݂ɏ��߂Ę^�����ꂽ�̂́A���w�̂���
"Mary had a Little
lamb"�@�����[����̂Ђ��A�Ђ�----�������B�}�U�[�O�[�X����̂�ꂽ�̂��ʔ����B
�@ |
http://www.tzwrd.co.jp/index.html�@
�@�@�@�ߐ{�Ȋw���j�ف@�ْ��E�c�V�@�E�v���@�@�L����Ё@�c�V�q���c�Z�p�m������
�@�@�@�����قł͂Ȃ��āA���j�قƂ���-----���ԕۑ�����Ă��邱�ƂɊ��ӂ̎v�����N���Ă���B�@
�@�@�@�@
���R�̕�炵466�@�@2019.8.27
�@ �@�@�@
�@�@�@�@ �@
�@
 Quena�@���̉�
Quena�@���̉�
�@
 |
 �@���Ԃ̖ڂɂ��ꏊ�ɁA�点���ɕ҂܂ꂽ��̃P�[�X�ɓ������P�[�i
���u���Ă���B �@���Ԃ̖ڂɂ��ꏊ�ɁA�点���ɕ҂܂ꂽ��̃P�[�X�ɓ������P�[�i
���u������B
�P�[�i�͓�ĂōL���p�����Ă���|�̓J�B
�����f���ɐ��������|�̐߂Ɛ߂̂��������X�|���Ɛ����Ė����A���������A���K�p�̌������Ă���B
�@ |
�������ꂾ���B���̓J���P�[�i�B���̖��ȁw�R���h���͔��ł����x�ɋ����Ă���J�Ȃ̂��B
������O�ɓ��ĂĂ݂�B
����ۂߍׂ���C�̓����A�P�[�i�̒��ɐ�������ł݂�B
�P�[�i�̓����ɓ���������C�͒��ŋ��������A���̕��ɂ����������o�Ă���B1980�N�㏉�߂̂R�N�ԁA���_�͓�ăA���f�X�̎R�̒��ɂ����ЂŁA���ǖ@�Ɋւ���Z�p�w�����s���Ă����B
���̌�߂ł����ЋƂ͔��W���A�Q�O���N�L�O���ɏ��҂��ꂽ����A���Đ����Z�p������������̐l�������A�������o�������Ă��̓�{�̃P�[�i���v���[���g���Ă��ꂽ�B
�����ƈ���\�̃y�h�����܂���ȁA�����Ď��̋ȂƑ����Ėڂ̑O�Ő����Ă��ꂽ���ƁA��n���Ă���������́A�Ⴋ���̂��̓w�͂���������тɎv�킸�܂����ڂꂻ���������A�ƍ��������B
���̓��A�G�N�A�h�����̔��W�ɍv����������ɂƁA�哝�̂��犴�ӏ������ꂽ���A����������̓�{�̃P�[�i�̕��������ƐS�ɟ��ݍ��ގv���o�ƂȂ����悤��
�B

 �@�n���𒆐S�Ɋ������A�����̓A���[���`���܂ʼn������Ă����Ė����y�퉉�t�ƁE���R���q����̑��ďC�ɂ��A��ăt�H���N���[�����y�̍ՓT�u�����Ձv�����N���J�Â���A����������ٓ��������ďo�����Ă����B �@�n���𒆐S�Ɋ������A�����̓A���[���`���܂ʼn������Ă����Ė����y�퉉�t�ƁE���R���q����̑��ďC�ɂ��A��ăt�H���N���[�����y�̍ՓT�u�����Ձv�����N���J�Â���A����������ٓ��������ďo�����Ă����B
�@�@�@�@�@<�@https://www.pentagrama.jp/������/
>
���y�͉����y���ނ��́A�����������̌��t���̂��̂̋�������������́A���ɉ��������邱�Ƃō��̎��Ԃ����L���A��т����ɂ������----���t�҂Ɗϋq����̂ƂȂ��ĉ������o�����ӉĂ̈���������B
�t�߂ɂ͂��łɃX�X�L�̕䂪�o������Ă����B
�@ �͂邯�����A���f�X�̕��̏ӎ��ЂƂȂ�ׂ������ƈ�����
���R�̕�炵465�@�@2019.8.20
�@ �@ �@�@�@
�@�@�@�@ �@ �@
 �s��L�O���ɘ@�̉Ԃ��炢��
�s��L�O���ɘ@�̉Ԃ��炢��
 |
�����Q�V���E�}
����Ř@�؏������䕗�̕��ɗh��Ă���B
�L���|�E�Q�ȁA�����Q�V���E�}���̑��N���œ��{�ŗL��1��1��̐A���B
�낢�č炭�Ԃ��@�ɁA�t���T���V�i�V���E�}�i�N�؏����j�Ɏ��Ă���̂ŁA�����Q�V���E�}�i�@�؏����j�̖�������B
�@�̉Ԃ̍炭���~�ɏ��Ԃ������̂��Ȃɂ��̈������킹�Ȃ̂��낤���B
�ߐ{�̔�����̉��ɂ���[�R�ƁA���̏㕔�ɂ�����������̊Ԃ̎Ζʂ́A��������┖�Â��я��ɑ�Q��������Ă���Ƃ����\������
�B
�����̓c�L�m���O�}�ƃX�Y���o�`�ɑΛ�����E�C�̂���l�ɋ�����Ă���Ԃ̋Ɋy�炵���B
�@ |
 |
�L�c�l�m�}�S
�L�c�l�m�}�S�ȃL�c�l�m�}�S��
�G�������ǁA���߂Ȃ�������Ă���B
����ȓ�̔M�тɂ́u�L�c�l�m�}�S�v�Ȃ�ʁu�L�c�l�m�q�}�S�v�����炵�Ă���B
�@ |
 |
�V�\�ȃV�\���̐A���A�ł��ˁB
���[�A�t����������Ă��āA��Ђ��ɂ��ݍ��ݑf�˂̖Ɏg���A9���ɓ���ƕ���̎悵�ăV�\�̎��̂��傤��Ђ��ɂ���B
�@ |
�@�@���R�̕�炵464�@�@2019.8.15
�@ �@ �@�@�@
�@�@�@�@ �@
 ��������݂��� �s�A�m������
��������݂��� �s�A�m������
��N�A�ċx�݂̈���A�ߏ��ɕʑ����������̃s�A�j�X�g���u�z�[���R���T�[�g�v���J���Ă�������B
�s�A�j�X�g���{�l�ƁA�V�����\���̎�A�e�i�[�̉̂��肳��6�l�����ẴR���T�[�g�́A���N��9��ځB���y�W�̂��F�l�������͐�t������������łɂȂ�悤���B
���N�̉��ڂ�
|
�s�A�m�A�e |
�����̎ӓ��Ղ��u�����E�I�ȁv�@�@�@�T���T�[���X
���̕����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �T���T�[���X |
|
�s�A�m�Ƒt |
�����h�C�Z���@KV511�@�@�@�@�@�@�@���[�c�A���g |
|
�V�����\�� |
�������ڂ̎��鍠�@�@�@�@�@�� �N�������@�@�ȃ��i�[���@
���̗~�������́@�@�@�@�@�@�@���E�ȁ@�o���o��
�������w�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@���E�ȁ@�o���o��
���̐_�l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �� �~�V�F���E���B�I�P�[���@�@�ȃV�������E�f�������@
�@ |
|
�Ə��@ |
����������l�́@�@�@�@�@�@ �@�ȃh�i�E�f�B |
|
��d���@ |
�E�F�X�g�T�C�h������@�g�D�i�C�g�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȁ@���i�[�h�E�o�[�h�X�^�C�� |
|
�Ə��ƃs�A�m |
�߂��݁@���������Ɓ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�ȃg�X�e�B |
|
�s�A�m��d�t |
����݊���l�`���@�����̗x��E�Ԃ̃����c�@�@�`���C�R�t�X�L�[ |
30�l����������ς��̋��ԂȂ̂ŁA���イ���イ�l�߁B�݂��̐g�̂��G�ꍇ���ē������Ԃ����ɂ��Ă���----�Ƃ��������̊��S������B
�Ə�����Ƃ��A�����K�i��3�i�ڂɗ����ĉ̂��Ă�����������Î҂�O����B
�������ȃT���_������`���Ă��鑫�̃y�f�B�L���A�̐F���A5�{�̎w���ꂼ�����Ă����B
�s��̐l�͂���Ȃɂ��V�����ȂƁA�c�ɂɏZ�ގ��͂ӂ��������������B
���̉��y�͐S�ɂ��g�̂ɂ������B
���T�͓�ĉ��y�̂��Ղ�ɏo������\�肾���A�����͒n���̉��y�Ƃɂ��u���R�[�_�[�A�I�[�{�G�A�`�F���o���̉��t�Ƃ��b���v�Ƒ����B
�����̋Ȗڂ́A�u�����܂̃u�������v�u�ň��̃C�G�X��A����͂����ɏW���āv�u���N����v�G�[�f�����C�X�v�����������Ă��������v�u�V�g�̃i�C�`���Q�[���v�ȂǂƂ������B
��̙���̎��������A����͖��������Ăł��o�����Ȃ��ẮB
�@
 ���O�����---Every Vegetables has a beautiful name. A
beautiful name, a beautiful name -----
���O�����---Every Vegetables has a beautiful name. A
beautiful name, a beautiful name -----
���̓S�_�C�S���D���������B
�������ҏ����B����܂菋���ċ��������Ȃ�B�F�l�m�l�͌��𑵂���
�u������͗������Ă�����˂��v�Ƃ�������邪�Ȃ�́B
���߂��ɂ��̂P�T�Ԃ̍ō��C���ς��Ă݂�ƁA35.05���������B
����ł͓ߐ{�����̖��O��������B�����𖼏��Ȃ�č��\���I�ό��ۂ̉A�d���I
�ƃG�N�X�N�����[�V�����}�[�N����ׂđ����ł݂Ă��A�������Ȃ�킯�ł͂Ȃ����A�����͉Ƃɂ������ēǏ��O���Ƃ��������B
�������A�Ǐ��ɂ��̗͂�����B�ڂɓ��������ʂ͓��̒��ɓ��炸�ɁA���̏�������Ă���B
�����Ŏv�������̂��A��c��Ђ̃J�^���O�������B
���̂ˁA��̖��O���Ėʔ����̂�B
���E���Ԃɂ́A�X�����@���ׁ@�Ђ���@�����ȁ@�䂫�ȁ@������������A
����E���ڂ��ɂ́A�T���_���Ȃ�Ă����̂����邵�A
�ق���ɂ́A�T���_������@�Ȃ������̓I�[���C��������
�卪�ɂ́A������@�O���Y�@�����@�╗�@������@�t�_�y�@�������l�@�����Ȃ����@�ł�����B
������͂��̃h���}����A�ł͂����Ƃ��ł�Ɏg���̂��낤�B
�l�M�ɂ́A���t�@�z���C�g�X�^�[�@�~���ׁB
�h�ݑ卪�͂��̖��̂Ƃ���h�V�����B
�L���x�c�ɂ́A�����W�@������@�����ȁ@�����́@������A
�l�Q�͂�͂�n���B�D�n�@�Ĕn�@��������@���ނ��߁@Dr.�J���e���@����Ȃ��@�s�b�R��
����Y��Ă����B����ڂ��@��������@�ق܂�@�����āB
��̎�̃l�[�~���O�͒P�������^�C�v�ƁA�Ȃ���������^�C�v������悤���B
�n���̔_�Ƃ̊F����́A���̃J�^���O�����āA���N�V��̖���͔|���Čڋq�̔��������Ă���B
�t���N�^���}�`��`���J���t�����[�́u���}�l�X�N�v�͉��N�����̉w�ɏo�Ă��Ă������A�ŋ߂͌������Ȃ��B�g�E�����R�V�͖��N�V�������O�Ńf�r���[���Ă��āA���܂̓S�[���h���b�V����s���A�z���C�g�A�������͂��B�̂肽�Ẵg�E�����R�V�̔��������Ƃ�����A���̂P�{�łR�T���������邭�炢�B���āA����������猳�C�����炨���B
��c��Ђɂ́A���̃^�L�C�A���̃T�J�^��c�A��̎�̓��k�V�[�h�Ȃǂ��܂��܂���B��ԋC�ɂȂ�̂́u�A�^�����̎�v�B���̃A�^�����̎�͂܂����������Ƃ͂Ȃ����A�Ȃ��u����������T������ʂ����T�v���v���o���B���O���Ėʔ����B

�ہE���N�Q���炫��������B
���ɏZ��ł������̗אl����A�P�O�Z���`�قǂ̍����ؕc�������������̂��A����Ȃɑ傫���Ȃ����B
���R�̕�炵462�@�@2019.8.6
�@ �@ �@�@�@
�@�@ �@ �@
 ����قǓ��𐂂��Ђ܂��
����قǓ��𐂂��Ђ܂��
�쒹�̂����ꂩ�炱�ڂꗎ�������m�Ђ܂��̎킪�A���̂܂ܔ��肵�đ傫�ȉԂ������̂��A����7�����{�̂��Ƃ������B
���钩�̂��ƁA����܂�3���[�g���̍����ŗ����Ă����Ђ܂��̉Ԃ��A�������肤�Ȃ���Ă��܂��Ă���̂ɏo����āA�i���N�̂��ƂȂ̂Ɂj�т����肵���B
�Ԏ�̏d���͖�2�L���B�d���B�d�����牺���������̂��H
����Ȃɑ傫���Ȃ����̂��A�d�����قǂ̉Ԃ����A�킪�n���܂Ő����ł����̂��A�݂�Ȃ����l�̂������ł��B
�Ɗ��ӂ̋C������\���Ă���A�̂ł͂������Ȃ��B
���Ȃ���闝�R�͂������l������B
���Ȃ��ꂤ�ނ����ƂŒ������̉a�ɂȂ�̂�h������------��������Ȃ��B
��ԗL�͂Ȃ̂́A�J�������I��h�����߂ɉ��������̂ł͂Ȃ����B
�Ђ��������[�������邽�߂ɁA���Ȃ���Đg�i���j���Ђ��߂�Ђ܂��̎p�����邽�сA�Ȃ�Ƃ������̖����Ȃ����Ƃ���Ђ܂��̈ӎv��������B
�u���炢��A�݂�ȁB����c���đ���������ˁv�B
�Ɛ��������Ă��B
���̂��ƁA�Ԏ������ŒE�������������A�~�̊Ԃ̖쒹�̂����ɂ���d�����҂��Ă���B
���J�œ��̉w�̂Ђ܂�肪�s��炵���B���̏H�̓N���~�E���ɏo�����悤�B
 |
���łɁ��̏ꏊ�̎킪���ɐH�ׂ��Ă��܂��Ă���B
�Ɛl�̓J�����q���B
 |
*
�����͔���B
�Ȗ،��̓ߐ{�n���ɂ͂���ȕ��K���c��܂��B
���̒n���ł�8��1�������W����i���܂Ԃ��̂������j�ƌ�
�сA�n���̊��̊W���J���Ƃ������B����c�l���A�W�̊J�����������X�ɔ�яo���A����ƂȂ��Ă��̂��̂̉ƂɋA�낤�Ƃ�������ƌ������킳��Ă��܂��B
�n������̐��Ƃ܂ł̓��͗y���ɉ����A����i����j�ɏo�����Ȃ�����~�ɂ͊Ԃɍ����܂���B
�������Ȃ��A�Ђ����獰�̊҂�ꏊ��ڎw���ċ}������c�l�̔���������߂ɁA�p�ӂ���̂�����
�u�n���̊��̊W�\���v�@�i���N�n�ꂽ�������̔�ɒY�_�ƍ����������A���ɏ����Q���l�߂ď��������́j
�{���́A��������H�ׂ���悤�ɁA���~�܂ł�13���Ԃ̂Ԃ���\��������������悤�ł��B
�֎q����̔� �Ŏ��܂���ƁA����c�l�����݂�i�߂鉹����������ƁA�y�n�̌ØV�͌����܂��B
����c�l�͂��̂��\���̂ق��ɁA�֎q������������Â���闢�����@��o���Ă��H�ׂĂ���̂�������܂���B
(*�����2017�N8��1���̓��L���甲���������́B
���́u�n���̊��̊W�\���v�ɂ��ďڂ������m��ɂȂ肽�����͓����̓��L���J���Ă��������j
���R�̕�炵461�@�@2019.8.1
�@ �@ �@�@�@
�@�@ �@
 ���܂߂����@�֎q�f�r���[�@
���܂߂����@�֎q�f�r���[�@

�����悭���Ă������邨�ׂ̕ʑ��̕�����A�u���܂߂����v�������������B
�u�ϓ��̃c�������ɁA�Е��̐F�o���Ɂv�ƌ��p��������Ă���B
���������̒��ɂ́A�S�̂͂��Ȃ̂ɃV���o�[�ɋ߂��F�́u���܂߂����v����B
�������ς�A�`�����瓤�Ɏ��Ă���B���̓�̈Ӗ��������Ă���u���܂߂����v�B
����ȂɃj�b�`�ȃv���[���g�́A�{���ɂ��ꂵ���I
�@�@*�@�����A�����������B���тĂ��Ȃ��S�͋┒�F�Ȃ��āB�����ƔZ���F��z�����Ă����̂ɁB
�Ȃ�A�Е��̐F�o���Ɏg������́A���Ɣ������č����Ȃ�킯���ȁB
���R�̕�炵460�@�@2019.7.26
�@ �@ �@�@�@
�@�@ �@
�@�@  ����܂蒷���~�J�Ȃ̂�
����܂蒷���~�J�Ȃ̂�
�~�J�̒��J�ɂ��Ă��A����ł͂���܂蒷������B�Ȃɂ���Ƃ�t���邨���l�̊���Ђƌ��߂������Ă��Ȃ��̂�����B
�`�J�`�J�ƍׂ��������~�葱���J�����Ă���ƁA�Ȃ��Ȃ���������Ă͕����Ȃ��Ȃ�A�����͋C���̗~�����Ƃ��낾�B
�悤�₭�������^�C�v�́u����߂Ⴒ�v����ɓ������̂ŁA�Ⓚ���Ă���u�R���̎��v���g���Ă���߂�R������邱�Ƃɂ��悤�B�i���̂���ɂ�肵���u�V���X�����v�͂��܂�D���ł͂Ȃ��̂Łj
�����̂悤�ɍ����͓K���B
�u�傫���v���C�p���ɐ��A���A�݂��A���傤������X����ĉ��߁A�N���Ă����炿��߂�������Ă����B�Ϗ`�������Ȃ肻���ɂȂ�����Ⓚ�̂܂܂̎R���̎���
�����č����A���C�������Ȃ�܂Ŏς߂Ďd�グ��v-----���̂Ƃ���B
���̍������ƁA�s���s���̓x�����͍ő傾�B
�R���̎��͎��n��䥂łĐ��ɎN���Ƃ��̓Ɠ��̐h�݂͂��炮�B
�������A�����Ƃ��h���̂��D���ȉ䂪�Ƃł́A���܂܂�---���̂܂g�����Ƃɂ��Ă���B
�����A�����͗�������B

���R�̕�炵459�@�@2019.7.20
�@ �@ �@�@�@
�@�@ �@ �@
 ���W�G�[�^�[������V�X�e�� ----�@���Y���͂��������L�m�R�̗�
���W�G�[�^�[������V�X�e�� ----�@���Y���͂��������L�m�R�̗�
�����̐V���ɂ���ȋL�����ڂ��Ă����B
�u�C���M�𗘗p�����������Ď����^�т̂ł���E�H�[�^�[�N�[���[�A7980�~�v
�u�ƒ��ǂ��ł��Ђ�����K�ɁI�v�u�����������^�ׂ鏬�^�N�[���[�v�@�d����1.1Kg,���^�B
�����������A�傫�ȎM�ɐ��������납���@���Ď��͂��₷�A�Ƃ����d�g�݂炵���B�������A�����ɂ̓t�B���^�[�������āA���݂�o������Ă���炵�����B
�͂邩�͂邩�̂̂��ƁB
���߂Ă̎q�����h���A�Ղ��Ղ��ɖc����Ȃ��ʼn߂����H�ڂɂȂ�A��������̒������킹���Ă̂��Ƃ������B�Ȃɂ���Ă����ʂ̕z�c�ŋx��ł����c�ɂŏ���������߂��������A�����ɂ͂߂��ۂ��キ
�A�s��̌����Ƒ̂��Ђ��Ⴐ��悤�ȎܔM�̓��X�ɔ�J���ނ��Ă����B
�����˂����_�@�i�܂�20�ゾ�����A�����낵���Ⴂ�B���܂�z���ł��Ȃ��قǂ��j�@���������B
�u�悵�A�l���N�[���[������Ă����邩��v�ƁB
�u�N�����œ��蓹��ɓd�q�����W�������Ă����炵���A�Q�O���~�����āB�v�@����Ȃ��킳����ь����Ă������ゾ�����B
�Q�O���~�Ƃ����Γ����̒j���̏��C���̖�3�{�I�܂��ĉƒ�p�̃N�[���[�Ȃǖ��̂�߁B��߂܂ڂ낵�̘b���B
�菇�͂������B
�܂���ɓ�������----�����Ԃ̃��W�G�[�^�[�̂��ÁA�g�g�݂����ޖA��@�A���p�̃S���z�[�X�B
���Ẫ��W�G�[�^�[�͍��ӂɂ��Ă���֘A��Ђ̐l������炢�A�ߏ��̌��z���ꂩ��p�ނ����������Ă����B��@�͉��Ƃ������Ă��邵�A�S���z�[�X�͔����Ă�������B
���ׂčޗ��͎�ɓ������B���W�G�[�^�[���͂ߍ��ޘg��p�ނō��A���W�G�[�^�[�̒��ɕs���t�Ȃ�ʐ����S���z�[�X�ŗ�������z������B���̂��Ɣr���C��܂ŗU������z�[�X��ݒu�����B
���ꂩ��A��@�̏o�Ԃ��B���𗬂����ꖳ���Ȃ��̃��W�G�[�^�[�Z�b�g�̌�납�畗�𑗂�ƁA����B�ق̂��ɗ��������������̒��ɗ����ł͂Ȃ����B
���������ƂɁA�Z��ł����͈̂ꌬ�Ƃ̎Б�Ŏg���Ă���͈̂�ː��������B�g������ʼnĂł��₽����ː��������B
����낿���B�������˂���̐�������鉹���������Ă���B�C�������ł��������Ȃ�B---���ۗ������������B
��������ĉĂ����������̔N���A�n�����n�߂��V������������̐V���L���Ŏv���o�����B�����A���̃I�J�V�i�`�̐��⎮�N�[���[�̎ʐ^���c���Ă����悩�����̂ɂȁB�ɂ���������ʐ^���������ƕ�炵�̋L�^�ɂȂ����̂�---�B
���āA���̎Б���o�鎞�������B���̐��⎮�V�X�e������苎������A���̊Ԃɂ��R�����Ă����̂��낤�B�c��ݏ������L�m�R���т����萶���Ă���̂ɋ������B
�ȂɁA�Z�����o��Ƃ��ׂĂ̏��V�������邱�ƂɂȂ��Ă����Б�Ȃ̂ŁA����������v���o�����ǁB
�ł��A���̏�̉��̍����������Ă������ǂ����@---�@����͋L���ɂ���܂���B
���܁A�S���̕����ɃG�A�R����ݒu���A�����������������̂����Ƃ��ł��鐶���𑗂��Ă���B
���̂���̎Ⴓ�͎��������A�n�����͍��Â悭�c���Ă���---�ǂ����ȁA����͍l�������悾�낤���B��炵�ւ̖����x�͐S�̎������ɉe�������悤���A�u�[�^���̗������ƂˁB
�v���A���̂��납�瑊�_�̐��i�����X�̕�炵�̒��Ō����Ɍ���Ă���悤�ɂȂ����悤���B
��肪�N����ƁA�Ȃ�Ƃ��������悤�Ƃ��̎肱�̎��T���Ă݂�B�����āA����������H����B
����ɉߏ�Ȏ��M�����悤�ɂȂ�A�����ɖR�������@�_���������悤�ɂȂ����B���������Ĕے肳��邱�Ƃ��匙���B
�����炿���Ƃ₻���ƂŐ_�o��a�ނ��Ƃ��Ȃ��B
�ł��A���̐��i�ŏC����������������蔲���Ă����̂�����A�ǂ��Ƃ��ׂ����B
�@�@
�i*
���́u���z����̔p�ށv�ɂ͌���k������܂��āA�̒��̉������A�傫�Ȃ��Ȃ��Ŕp�ނ�������Ă��Ă͕��C��̕����ɂ��Ⴊ�݂��݁A��Ȗ�Ȃ����C�������̂ł����B�Ȃ�Ƃ������a�ȓ��X��B�j
�@
 |
�@
��̃j�b�R�E�L�X�Q�́A�R�炿�̉Ԃ��������ƉԂ��傫���B
���ꂾ���A�u������݂����v�ƌ��������ǁB
�����̂��B
�@ |
 |
�@
���������Ȃ̃��u�J���]�E�B�J�ɔG��Ă���B
�V��͐H�ׂ���B�|���X�a�����������߁B
<http://kemanso.sakura.ne.jp/wasuregusa.htm> �@ |
�@�@�@�@�@�@���R�̕�炵458�@�@2019.7.15
�@
�@ �@�@�@ �@�@ �@
�@  �u��܂��v�������Ă���
-----
�����̉Ă�
�u��܂��v�������Ă���
-----
�����̉Ă�
������������������B
�����̋C����16���B�тɂ͂������疶��������A�[���ΐF�ɕς�������X�ɁA�˂������Ė���̎p���܂������Ȃ��B�Â����B
�w������̎Љ�̎��ԂɁu���k�ł͉Ăɂ�܂��������B��Q�������炷���Ƃ�����v�ƏK�����̂��v���o�����B
���̓��k�Ɏ������Z��ł���̂����܂��ɐM�����Ȃ��B
�@�i�ߐ{�͓��k�ł͂Ȃ�����ǁB
�@�@�֓��̖k�œ��k�̓�@----�@�֓��̔��ŁA���k�̓��@---�@�߂��ɂ��̖��O������������g���l��������j
7���Ƃ����̂ɁA���͖ѕz�����Ԃ��ăe���r���ςĂ����B���܂�����ł������n�̃p�W���}���o���Ă��ĉ��K�������B
���̂������A�u���[�x���[�ɊÖ�������Ă��Ȃ��B�@�@
 |
���N�̐�̏�����7��4���������B
�����Ȃ璩�Ɨ[�ׁA���J���~�邩�̂悤�ɖ���߂��q�O���V���A���̒��̈ꎞ�����������Ă��ꂽ�B
���̌�Ȃ�̉��������Ȃ��B
�����k����B
�A�����J�V�I���̂ڂ݂ɂԂ牺�����Ă����B
�@�@品@�i�q�O���V�@�J�i�J�i�Ɩ��j |
 |
���������B
����Ȃɂ����ƌ��߂���ƁA�Ȃɂ��������Ƃ������悤�ȋC�ɂȂ邶��Ȃ����B
�A�}�K�G����B
�����Ƃ��낪�D�������B
���������Ă���Ȃ��B
�R���`�J���̗̗t�̊Ԃɋ��܂��āA���Q�����Ă���B
�@�@ |
�@�@���R�̕�炵457�@�@2019.7.10
�@
�@
�@�@ �@ �@
�@  �Ђƌ��������[�l
�Ђƌ��������[�l

�q���̂���́A���~�Ɠ����悤�ɂ��Ȃ��l��8��7���ɂ��j�����Ă������A��l�ɂȂ��Ă���́A�����ς�V���7��7���ɂ��Ղ肷�邱�Ƃɂ��Ă���B
����̗[���A�ׂ̓y�n���������Ă��čQ�ĂĂ������������B
�Ȃɂ���Ⴂ���̐܂莆�𗘗p����̂ŁA�o���オ�������̂Ɂu�s���z�o�X�v�ȂǂƂ������t���ǂݎ���̂��A���N�̂�����d�����ے�����悤�ł�����䂢�B
�N���s�����Ȃ��s���ƁA�C�����悢�B
���܂܂ł������肵����A�ʓ|�������肵�ăX���[�����N�́A�Ƒ��ɂȂɂ��ǂ���ʂ��Ƃ��N�����悤�ȋC������B
�Ɠ����S�B�Ƃ��������ɒP�ɏ��邾���̂��j�����B����͐����̂��F���Ă��悤�B
�Ȃ�Ƃ����C�ɕ�炵�Ă��āA�����������ɑ����܂��悤�ɁA�Ƃ̎v������A�Ȃɂ��肢���������Ȃ��ł���B
�{���ɐ_�l�̂���������肢����Ƃ��܂ŁA����͕��Ă������B
 |
�S�����炫�n�߂��B
���|��́u�}���R�E�|�[���v�Ƃ������O�����S���B
�������肪�������߂�B
�@ |
 |
����͒������B
���Ԃ̃t�V�O���Z���m�E�B |
���R�̕�炵456�@�@2019.7.7
�@
�@
�@
�@ �@
 �@���N���܂��A���Y�̃W�����Â����@�@----�@�~�J�̍��Ԃɂ��Ă��邱�Ɓ@�@�@
�@���N���܂��A���Y�̃W�����Â����@�@----�@�~�J�̍��Ԃɂ��Ă��邱�Ɓ@�@�@
����s�̑P�����̏��̉�����������ꏊ�Ɉ�A���Y�́A���ʂȖ�������B
����ȃR�s�[�ɏ悹���āA���N���̎����ɏo���A���Y���W�����ɂ��Ă���B
���N�͏o��肪�����ŁA���̂��̉ʓ��P�T���A�P�W���A�Q�O���Ŏd�グ�Ė�����ׂ����Ă���Ƃ���B
�����ł��̎d���������܂��B
400������̃p�b�N��10�Ⓚ�ɂɕ��ׂē���A�������ɖ������Ă���~�J�̐���Ԃ̌ߌ�ł���܂��B
�@�@�@
�����ƁB�����̃u���[�x���[�̎��n��Y��Ă����B
���C�Ə������䖝���A�X�Y���o�`��C���K�̋��낵���ɖڂ��Ԃ�A�����܂ł̎��n�͖�5�L���O�����B
������F�l�ɂ��������A�c���400���P�ʂł�����܂��Ⓚ�ɂցB
���N�̃u���[�x���[���܂��Ⓚ�ɂɎc�����܂܂���B�����8�L�����B
���̕��ł́A���N�Y�̃u���[�x���[�����H�̃��[�O���g������̂́A��������---10�����炢�ɂȂ邩�Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@���R�̕�炵455�@�@2019.7.3
�@
�@
�@
 �����A���Ȃ��Ȃ��Ă����q�������@-----�@�L�͖钆��
�A�J���X�͒��[��c����
�����A���Ȃ��Ȃ��Ă����q�������@-----�@�L�͖钆��
�A�J���X�͒��[��c����
 �@�K���ɂ������͂��������ǔL����������Ȃ������B �@�K���ɂ������͂��������ǔL����������Ȃ������B
�����m���Ă����̂��ǂ����A�����A�ׂ̉Ƃ̉����̏�ŊJ����Ă���J���X��c�����ڂɁA���̃V�W���E�J���������������Ă������B�i�O��̓��L�A�E���̎ʐ^�j
7�����B���H��ۂ��Ă���Ƒ��_���A�u�V�W���E�J�������ł����I�v�Ƌ��B
���𓊂��̂ăJ�����Ў�ɒ�ɔ�яo���B
���������珬���������̂����������Ǝv���ƁA�Ђ傢�ƋɉH�����Ă����������B�@�K��������30�b���ƂɁB
���̏�ł͐e����---����͂����Ǝ��B���サ�Ă���̂��낤�A�������̒����L�̂������ő����ł���B
�u�������A����Ȃɑ����o�Ă����Ȃ��ł�v�u���킟�A�܂����v�u���肢�����Ƃ�����藷�����āv�B
�J���������肪�h���B�@���܂��B��Ȃ�
�����Ă��ʂ��̊k�ƂȂ�܂����B
�u�����A�ǂ������A���N���������Ȃ��������Ă������v�B�@�����ɗ������ėǂ������I�Ɏc�O�ȋC�������������߂�B
�K�r�`���E�̂��������������������̌��ǂ��A���ƈ�c�ɂȂ��āA�������������ɂ���������邮���щ��B�c����������ăJ���X���������Ă���̂�������Ȃ��B
������̎R���̖̎}�ɂV�H���W�܂�A�ЂƂ����肳���߂��������Ă��ꂽ���Ǝv���ƁA�꒹�̎w���ł��������̂��A�т̒����W�c�Ŕ�ы����čs�����B
 |
�o������ɑ��������A�����悭��яo���Ă������B
�܂��c���̂ŁA�������F���B
�����̒��a��25�~���B
����ȏ�傫������ƃX�Y���ɑ�����������B
�������A�������V�W���E�J������A�������X�Y������B
�܂܂Ȃ�Ȃ��B |
 �@�����Ă��̂��ƁB�@�i�O��̓��L�A�����̎ʐ^�j �@�����Ă��̂��ƁB�@�i�O��̓��L�A�����̎ʐ^�j
����̑����̉��ő����ɗ��ł���ƁA�V�W���E�J���̐������̖��������̏ォ��~���Ă���B�܂�Łu�����͖l�����̔Ԃ��`�v�Ƃł������Ă��邩�̂悤�ɁB
��������������b���邽�߂ɁA�������̒������ŕ�������Ă��鉹���������Ă���B
���̂Ԃ�ł́A�ǂ�������������ɑ����悤���B
���݂����ȁA�ƂԂ₫�Ȃ��炵�Ⴊ�ݍ��݁A�����ɔw���������Ă�����A�o�T�b�Ɖ������Č�납��w���ɓ��˂������Ă������������B�q���h���������B
�V�W���E�J���̎q��Ă��������Ă����̂��A�����̉��ʼn������s�������鎄���������Ƃ��Ă���B
�Ȃ�Ƃ������Ƃ��I�@�@���̕��ۂŁi�j
�K�r�`���E�Ƃ����A�q���h���Ƃ����A���꒣��Ƃ��Ă��钇�Ԃ�����H�����ŃV�W���E�J���̐�����ĂĂ���C���ł����̂�������Ȃ��B
�����A������̑�������ɂȂ�B
�����A���N�܂ł܂���N������B
���R�̕�炵454�@�@2019.6.26
�@
�@
�@
�@
 �@��ɐ��܂ꂽ�̂͂ǂ����H
�@��ɐ��܂ꂽ�̂͂ǂ����H
�@
 |
 |
���͓���ɁA�E�͓��Ɋ|���������̒��B
�V�W���E�J�������N���c�����n�߂��悤�Ȃ̂ŁA�҂����˂Ă��������͂�������u�s�[�s���O�E�g���v�������B
���������ڂ��Ȃ��ꏊ�Ȃ̂ɁA�r���������Ă��Ă�������`���B
�����͂͂��߂���A�m�]�L���ł���悤�ɍ���Ă���̂��~�\�B
�e�����a�������ċA���Ă������ƁA���F������傫���J���Ă˂��鐗�����Ɉ�H����B
�ق��̎q�����́A����J���X�̗��P���ƍQ�Ăӂ��߂��Ă���悤���B
�����Ⴎ����̒c�q��ԂȂ̂��ʔ����B
�E�̐������́A�댯���@�m���Ă݂�Ȏ��ӂ�����Ă���B
���ˏ�ɕ���ł���̂ɂ͏���B
�����Ȃ��B
�������܂ꂽ�̂́A�E�̐������B����قǑ������܂�A���̂Ԃ�m�b�����Ă���Ƃ��킯�B
�݂�Ȃ݂�Ȃ����̎q�A�䂪�Ƃ̎q�B���ƂP�O�����܂�ő��������}����B |
 |
����傫���Ȃ��Ă����ȁB
���̒�����u�҂�҂�A�ҁ[�v�B�����������������Ă��邼�B
���̏�ɃI�[�o�[�n���O���Ă��闘�x�~��o���āA�v���葃���̏��
�W�����v���Ă�낤���B
�W�������J���ă��c���H�ׂ�����҂��������B
����A���������傫���Ȃ��Ă���̕����H�������邩�ȁB
�J���X�̃��c���������Ă���悤�ɁA
�҂ĂΊC�H�̓��a����----�����͉䖝�̂��ǂ��낾�B
�����ɋ������đ��̋C�z�����������Ă����ǔL�B
�s�G�Ȃ炾�܂������B |
���R�̕�炵453�@�@2019.6.20
�@ �@
�@
�@  �������E�݁@
�������E�݁@
�@
 |
�E�F�b�W�E�b�h�Ђ̒�ԁA
���C���h�X�g���x���[
 |
�J��D���ă��C���h�X�g���x���[�̐Ԃ�����E�݂ɂł�B
�G��ƃz�����Ɨ����Ă��܂��̂ŁA�����炷�����グ��悤�Ɏ��L���B
�����돬�����B �ׂŏn���n�߂��u���[�x���[�����������B
���[�O���g�̏���ɂ������S���ƂȂ��A�������W�߂ăW�����ɂ���B
�Ђ�����B�������̂��낤�A�킪���܂ł��c��A��̏o���������̂�B
�@�@�Ԍ��t�F���{�ł́u���d�ƈ���v�u����v�u���C�v�u�K���ȉƒ�v�B
�@�@�@�@�@�@�@���[���b�p�ł́A�uLucky&Love�v�@�A�����J�ł́A�uMiracle�v�B
�@�@�@�@�@�@�@�L���X�g���ł́u���`�̏ے��v�B |
�@�@�@�@�@���R�̕�炵452�@�@2019.6.16
�@ �@
�@
�@
�@�@  �C�ɂȂ邱�Ƃ���� �C�ɂȂ邱�Ƃ����
5�����{����o�������u�V���N���[�h�̗��v�́A�ƂĂ������[�����e�������B
����͂�����Ƃ܂Ƃ߂Ă��������A�ƍl���Ă͂������B
�A�����ďt�Ԓd�̐����ƁA�Ăւ̏����Ɏv����������Ԏ��A���܂��ɂ��̔M�g�P���ɍ��͂�������ӋC�j�r���Ă��܂��Ă���B
��̉Ԃ͋G�߂�Y�ꂸ�炢�Ă���̂ŁA��������́u�ԊO���v�̓��������B
�ʐ^�͒�̉ԁB�p���I�J�V�C�̂́A�����r�ɕ��������̂��B���Ă��邩��B
����ȉԑ����������������z���ĕ������B
�f���t�B�j���[���ƁA�V���N���N�ƁB
�ǂ�������g�����ǂ��Ȃ��̂ŁA�ق�̓���قǂ̖��Ȃ̂����A���̌u���F�������т炩�������̂��B
���̋L�^�͍��A�y���f�B���O�B
�������A�������c���ł��̏H�ɂ͑�A�ƂQ�O�R���n�̌��w�ɏo���������Ȃƍl���Ă��邭�炢�B
�@�@�@�i�Ƃ肠������l�Ƃ����C�j
�@�@�@
�@�@�@ ���R�̕�炵449�@�@2019.5.30
�@ �@
�@
 �L��̗\��
�L��̗\��

�f�b�L������L���ƍ̂��߂��ɁB
����}���n�i�o�`����ь����A�������ɔ����Ԃ������u���[�x���[�̎ɖZ�������Ă���B
���z���ɂ����̊������i�F���L����B
�Ƃ��낪�q���h���̃��c�߁A�ւ̉Ԃ̖����z���Ă���Β뒆���a�Ȃ̂ɁA�킴�킴�u���[�x���[�̉Ԃ����ɗ��Ă����B
�I�̂悤�ɐg���y���A�z�o�����O���Ȃ��疨���z����̂Ȃ狖���Ă�邯�ǁA�Ԃ��܂ɂ��}�ɂԂ牺�������葫�łڂ݂��R�U�炵�Ă�����
���Ă���ł͂Ȃ����B
�₨�瑋���J���ăq���h���ɋ�����������A�����l�̃��^�V�B
�u�`�`�`�v�A�u�Z�Z�Z�`�v�@�Ɠ{��A��������قŁB
�@�@�i�u�@�v�������̒��ɂǂ�Ȍ��t�����邩�́A�l�̂̂̂��茾�t�̖L�����ɂ��܂��B�j
����𐔉���ƃq���h�����ǂ��Ȃ邩�ƌ����A
�u�������֍s���Ƒ��ق�����ׂ�|�`���������ɓ{����v�ƍ��荞�܂��悤���B
�Ȍ�Ă���H�ɂ����Ă̎��n�̎����ɁA�������炳��邱�Ƃ͏��Ȃ��Ȃ�B
����50������������Ă������A�Ⓚ�ɂɋ��N�̃u���[�x���[���c���Ă��āE�E�E�����10�L���߂����B
���̕��ł́A6���̑�������n�܂鍡�N�̎��n�����ɏo����̂́A�����炭9�����߂��邾�낤�B�Ⓚ�ɂ̖��t��Ԃ͂܂��܂������ł��Ȃ��悤���B����悤�ȍ���Ȃ��悤�ȁB
���@���قŎv���o�����B�����ߐ{�͊֓��n������ڏZ���Ă���l�������A�����̂悤�ɑ�ォ��A�Ƃ����̂͒��������݂炵���B
������̂��ƁA�}���ق̓Ǐ���ɏ��߂ĎQ���������ɂ���ȏo�������������B
�ÎQ�̃����o�[�́A�����痈�������܂�Œ����������ł�����悤���r�߂܂킵�A���X�Ɍ����J�����B
�u���̐l�͂������������ĕ����Ă���́H�v
���̂������͂������������ĕ����Ă���A�Ƃ����C���[�W���蒅���Ă���悤���B���̒����͂̂Lj��������Ă������E�E�E�B
�u���̐l�͕������h��ł�����ׂ�Ȃ̂͂Ȃ��H�v
�͂��B���͔h��ł͂Ȃ�����ǁA������ł͂���Ȃ��B
�u���̂ЂƂ̂Ȃ��ɂ́A����ɂȂ�Ȃꂵ���l�����܂���ˁv
�Ȗɂ͊C���Ȃ��E�E�E�E�悻�҂Ƃ̊ԂɊu�������肪���ȓȖؐl�ɂ́A���̃e���r�̑��l�̒���͋C�ɏ�邱�Ƃ�����炵���B
�����Ƃ����ȏЉ�Łu���l�͐l�ԋ������Z���̂ł��B����������������܂���B�ł����玸�炪�������炨�������������ˁB�v�Ȃ�Č����Ȉ��A�����Ă��܂������炩�B
�u�ł��l��Ɍ������`���̋����l�������ł���B�v���o���Ɖ��������ăz�[���V�b�N�ɜ�肻���v�Ƃ��킷�B
�u�ƂĂ����t�̉����n�悪������ĕ��������ǁB�v�ƌ��ҏW�҂�A����B
�u�����A�����ł��ˁB�v�A�u�ǂ̒n���������ł����A���������ꏊ������܂��ˁv
�u������Ƃ���ׂ��ĉ������ȁA����������v�@A����H���������Ă���B
���������A�u�����ɖY��Ă�������̂Ȃ�OK,����Ă݂܂��傤�v�ƈ���肵�A�傫�Ȑ��ʼn͓��ق�b�����̂������B
�@�@�i���͉͓��̏o�g�ł̓�����܂���B���o�����͓��فE�E�E���ꂪ�����ɐ������I�j
�F����A���R�I�@
�����ƁA�݂�Ȃ��ꂩ�炠�̃V���b�N��Y��Ă��Ȃ��悤�ȋC������Ȃ��B
����Ɍ��ҏW��A����A
�u���ɂ͕@����������̂ł����H�v�@�Nj��̎���ɂ߂Ȃ��B
�i�������ȏЉ�̏�ʂł����u�����B�j�i����Ȃ��Ƃ͌�Řb���܂��傤��B�j
�u���܂��������ɂ����ɂ��@�����͂���܂���ł����B�����������邳����������܂���ˁA���̔����́v�Ɠ������B
���͂�����ɗ��ĂЂƌ��قǂ́A�n���̒��N�ȏ�̂ЂƂ��b�����e���A�������Ȃ����Ƃ��������B
�t���[�Y�̌�����c�����Əグ��Ɠ��̘b������A�����ł��������Ȃ��P�ꂪ�o�Ă��č��f���邱�Ƃ��������B
�ł��A���͓Ȗؕق���D���B�Ƃ��������Ȗؕق�b���F�l��厖�ɂ������ƍl���Ă���B
�������Ȃ߂�C�͂܂������Ȃ��B���̒n��ň�܂ꂽ��������Ă����t�́A������w���������t�B�����Ă���̂ɕK�v���������t�B�q���̂���͎�����������Ĉ���Ă����̂�����B
������b���A�n���ɍ��t������炵�����Ă��邾�ꂩ����v���āA���̐l���̖L������z�����Ă݂�B
|
 |
 |
|
�@�@�@���O���炢�Ă����B�@�@�@�@���J���ς��Ȃ��̂ŁA����������Ԃɂ��ē͂��� |
���R�̕�炵450�@�@2019.5.14
�@ �@
�@
�@
 �̉�̒ώ�
�̉�̒ώ�
�@�@�@
���������ƊÂ��l���ŋ߂Â��A�Ԃ蓢���ɂ������B�G�͎�肪�L�тĂ����R���̖B
����̎R���̖̉�i�t�j��E�݂ɍs���A�����������Ƃɂ͎���ꂾ�����͂��̎��Ȃ̂ɁA�s�������Ă���g�Q�Ɉ���������A��̕���b�ɐԂ����t���Ă��܂��Ă���B
���������ɂ��B
���͌s�ɒ��p�ɂ��A�g�̂܂��ɂ����ƒ���߂��点�Ă���̂ŁA�ǂ��ɂ��h���悤���Ȃ��B
�����Ƃ������̎悷������̂����A�������������B
�����������ƏW�߁A�������Ə���t�����Ă��܂����B
���ʂ�����B��
�����ώςɂ��Ė�����Ă݂��B�������ɂ悭�����B
���т̂����ɂ҂����肾�B
�@�@�R���̗t�@�@500��
�@�@�ݖ��@�@ �@�@100����
�@�@���@�@�@ �@ �@50����
������ɓ���A���Ŏύ��݁A�d�グ�ɐ|��30���������ďo��������B
���Ȃ��݂̃W�b�v���b�N�ɓ���ėⓀ�����B
�@�@�@��̖ʂɉԂЂ邪�ւ菄�肭��t�̂ЂƓ��������Ǝv��
�@�@�@ ������܂��炫�c����т��t���݂̐�����ɋ��߂�@
���R�̕�炵449�@�@2019.5.9
�@ �@
�@ �@
 �������͑厖��@�@�@�n�V�u�g�K���X�͌���
�������͑厖��@�@�@�n�V�u�g�K���X�͌���

�����Ɨ[�A�䏊����o�������݂𗠒�Ɍ@���Ă���u�S�~���v�Ɏ̂ĂĂ���B
��N��ɂ͗��h�ȑ͔�ɂȂ�A�Ԓd�ɏ������߂�悤�ɂƁB
�K�����Ɖ��𗧂ė������o��ƁA��������̖̂Ă���Ō��Ă����J���X���������܋߂��֔��ł��āA�����Ǝ��̍s�������Ă���B�ǂ����z�͂����̒��꒣��ɂ��Ă���悤���B
�u�J���X���[�[�B�����͂Ȃ�ɂ��Ȃ���v�u��̋���������v�Ƙb�������Ă���Ă����̃J���X�A�ǂ����Ă������̖ڂŊm�F�������炵���B���Ƃ̋�����10���[�g���܂ŗ����ƁA���������S�~���ɓ���˂�����ŐH�ו���T���Ă���B
�J���X�͌����B�l�Ԃ̊���悭�o���Ă��āA����ɂ͂��̋L���͈ꐶ�����Ƃ������Ă���B
������A�v��ʋt�P������̂Œ�̃J���X�͂����߂Ȃ��B
�@�@��듪�����̉s���������œ˂����B
�@�@����Ă���X�q�������čs���Ă��܂��B
�@�@��������u�����o�b�O�����ɂ��킦�Ĕ��ł����B
�@�@�����ł����������q���������Ă��錄�ɁA�c���ꂽ�����َq��������Ă����B
�@�@����͋����邪���̒܂ŐH��ނ��R�U�炵�Ă����͍̂���B�@�����A�E�F�b�W�E�b�h���ꂽ---�B
�悭�����b���B
������A��̃J���X�ɂ͕t�������ꂸ�A�K���Ȍh�ӂ������Đڂ��邱�Ƃɂ��Ă��邪�A�̐S�̃J���X�ɓ`����Ă��邩�ǂ���---�����Ƒ��v���낤�ȁB�Ȃɂ������̂�����ˁB
�J���X�͏����������Ă���炵���B���������ԂƗ[���ɂ́A��̈��ɏW�܂葛���ł���̂��悭����B
�u�������œy����߂܂����B�v�u�����͂ǂ��H���T���֍s�������v
�����Ƃ���Ȃ��Ƃ�b���Ă���̂ł͂Ȃ����ƁA�i�q�}�ȃ��^�V�́j����������Ȃ���l����B
�J���X�̎��[�������Ă���ꏊ�ɃJ���X���Q��Ă���̂��������邱�Ƃ�����B����́u�Ȃ����̒��Ԃ͎��̂��v�ƕ��͂��Ă���̂��Ƃ�����������炵���B
�����͓`���a�Ȃ̂��A�������莖�̂Ȃ̂��A����̓����ɏP��ꂽ�̂��B����Ȃ��Ƃ�b�������A���X���Ԃ����̏����㏑�����A���悢����
�̂��߂�----�����̊댯��������邽�߂Ɋw�K���Ă���炵���B
�����̗\��𗧂āA���Ԃ̊Ԃ̃R�~���j�P�[�V������}��A�g�߂Ȑl�Ԃɑ��Ă͌̔F�������čs����\�m���댯�������B����Ȕ\�͂�����J���X�B���肪�����B
���ʂɌ�����J���X�́A�n�V�u�g�K���X�ƃn�V�{�\�K���X��2��ŁA��̉摜�̓n�V�u�g�K���X�B
�ۂ����肵���I�f�R�������ŁA�����͍����s���B�u�����A�����v
���Ē����Ō�������n�V�{�\�K���X�̖����͑����������u�����A�����v�B�����܂��������B
���̃n�V�u�g�K���X�́A�S�~�̌�����H�ו������������ƂȂ̂��A�쒹�p�ɗp�ӂ��Ă��鐅���ݏ�łȂ�ƁA������������ł����I
���R�̕�炵448�@�@2019.5.4
�@ �@
�@
�@
 ���u���K�T�@�j��P�@�L�N�ȃ��u���K�T��
���u���K�T�@�j��P�@�L�N�ȃ��u���K�T��

�܂������̎c��t�̂͂��߁A����̋�����ӂ����炵������o���Ă���̂����̃��u���K�T�B���肷�鉹��----���Ƃ���u�X�|�b�A�|���v���B
�Ȗтɕ���ꂽ���̎p�͖��O�̂Ƃ��胄�u���K�T���̂��́B
���邩��Ɋ��m�Ŗ��N�A�u�悭�o�Ă����ˁv�Ɛ����|���Ă��B
�����ł́u�e���P�v---�E�T�M�̎q���������P�Ƃ������O�����Ă��āA�����ɂ�����炵���B
�u�R�ł��܂��̓I�P���Ƀg�g�L�v�A�������Ă��́u���u���K�T�v�B
�R�Ƃ��ēV�Ղ��a�����ɗ��p�ł���炵�����A�����ŐH�ׂ�E�C���Ȃ��B�����A��������ƂЂƂ�����������B
�傫���P�͑傫���A�������P�͂���Ȃ�ɁB�j�ꂽ�p�͉��炵���B
���u���K�T�Ȃǂƌ������O��t�����Ă��̂܂ܐ������A�Ă̐���ɒn���ȉԂ����A����̋������Ő���S�����Ă���B
�����Ȃ��B
���l���C�ɂ������܂��A�܂����炸��]���邱�ƂȂ����f����������炵�A�����l�̌����g���Đ������_�f�������A��_���Y�f��L�@���ɌŒ肵��----�Ђ����ɒn���̋�C�����ꂢ�ɂ���----�����������ĐÂ��ɕ�炷�̂��ǂ���������Ȃ��B
���R�̕�炵448�@�@2019.4.30
�@ �@
�@
�@
 ���a�T�O���[�g��������܂���
-----
�R���Ƃ͂���
���a�T�O���[�g��������܂���
-----
�R���Ƃ͂���

���N�̏t�̐A���̌�����͂��������B
���Ԃ����킷���ƂȂ��炩������A�V����o�����肵�Ă����g�̂߂��肪�A�Ȃɂ������̔N�ƈ���Ă���悤�ȋC������B
�������鏇�Ԃ̃J�[�h���V���b�t��������A�����茳�������Ă��܂����̂��B
�V���b�t�������̂͒N���낤�B
���̓���������A�C��23�x�Ɏh�����ꂽ�̂��A�����R���o�Ă����B�ԋ��킹���͂Ȃ͂�����----�B
�����A���a50���[�g�����������Ď��n���Ă����̂���̎ʐ^�B
��ԏオ�u�R�̉��l�E�^���̉�v�A���̉��̂Ղ����肵�Ă���̂��u�R�̏����ƌ�����V���L�E���v�B
����Ɏ��R�ɐ����Ă����u�ő��v�����ɁB
�ڂ̍Ղ�̂悤�ɁA�M�ɕ��ׂĂ܂��ڂŊy�������B
����͎��n�ՁB�R�̓V�Ղ�Ղ�B
���R�̕�炵447�@�@2019.4.24
�@ �@
�@
�@
 ����ɃT�}�[�^�C��
�����̓���@���������n�i�J�C�h�E�ƃ����S���炭
����ɃT�}�[�^�C��
�����̓���@���������n�i�J�C�h�E�ƃ����S���炭

���N�����Ă��܂��悤�ɂȂ����B
������������B
�֓��Ŗk���́A���k�̓�����ɂ���킪�Ƃł́A���̋G�߂̓��̏o�͌ߑO�T���B
�܂����Â��R�����납��쒹�������͂��߁A�S���ɂ͖��邳�����̌��Ԃ�����荞��ł���B
�ƂĂ��Q�Ă͂����Ȃ��B
���Ƃ̓��̏o���Ԃ̍��́A��Q�O���B���Ɉʒu����Ԃ������[���������B
�����ɒu���Ă���{�ȂǓǂ�Ŏ��Ԃ��Ԃ��Ă��邪�A�g�̂������N���������ċN���������Ďd�����Ȃ��B
���ꂾ�������B�t���ł��o�������Č������̂́B�������Ƒ����Ȃǂ���������I���A�[�H���ς܂������Ƃ̖��C�Ɨ���������ǂ����悤���Ȃ��قǂ��B
�u�����A�O���͂����ƕz�c�������̂��v
�u��̑ٓ��ɂ���悤�ɒg�����Ė����ċC�����������v
�u�z�c�����`���I�v
�������ɉĎd�l�ɂȂ��Ă���-----�@�Z���t�T�}�[�^�C���̂͂��܂�B
���R�̕�炵446�@�@2019.4.21
�@ �@
�@
�@
 �w�Ȃ̃g���Z�c�x��ǂޕv�̃g���Z�c
�w�Ȃ̃g���Z�c�x��ǂޕv�̃g���Z�c
|
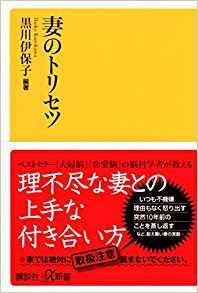 |
�u�[���ɂȂ��Ă���w�Ȃ̃g���Z�c�x�𑊖_����Ă��Ă��̐����ǂ�ł���B
���邢�͂��̓���ɕNJ��ł�����̂��낤���B�i�N�����Ă���͂����ȁj
�{��ǂ�ŔނȂ�ɁA����������Ƃ��낪����̂�������Ȃ��B
���̐����₯�ɂ��܂��܂Ƙb�������Ă�����u�������ȁv�Ƃ����Ԏ����������肷��-----����͑傢�Ȃ�ω����B
�u�Ă������肨�̂������ЂႭ���₤���炸�v�B
������������ǂ�ł݂悤�B
�摜�̓A�}�]������
�@ |
���̖{�́A�v�w�Ԃ̃R�~���j�P�[�V�����̓�����u�j���]�̈Ⴂ�v�Ő������Ă���B
���̒P���Ȋ���肩�����ǎ҂Ɏ��|�C���g�Ȃ̂�����Ȃ��B
���߂͂��炰��A���Ă��܂����B
�E�j�̓V���O���^�X�N�������Ȃ��Ȃ��B
���������Č��ݎ�Ɏ����Ă�����͈�����ɂ��Ă��������B
�E�Ȃ͕v�ɖ����������߂Ă���킯�ł͂Ȃ��B�u���ׂ����v�Ƒ���̌��t���͂����Ԃ����Ƃ͍ȂɎ���ĕs�������B�܂��������������̂��ɂ₨��������@��
���ɂ��ׂ����B
�����ł����̂͂�����ӂ܂łŁA���̂��Ƃ́u��������ӂ�����悤�v�u�L�O����厖�ɂ��悤�v�Ɏn�܂�A������n�E�c�E�̗��قƂ�ǂ������B
�ӂށA������u�g���Z�c�E����v�Ȃ̂��B
�u�ƒ�ɕ��������߂����߂ɕK�ǂ̈���ł�����v���ĂȂ�B���Ҏ��g�����Ȃ̂ɁA���]���y�Ă���ԓx�Ɉ�����������̂�����B���Ƃ����ĕv�̒j�]�d���Ă���킯�ł��Ȃ��B
�o���̔]�̕\�ʂłďI���B�W���̒z�����ɋ\�Ԃ�������B�N���������ȁA�u�ƒ�̍K���͍Ȃւ̍~���v�Ƃ������̂́B
����ɃX�e���I�^�C�v�̕������ɋ^������悤�ɂȂ��Ă����B�����������̖{�̓C���^�r���[�������e�͂ɋN���������̂炵���B�b�҂̋C���������g����ɂ��������āA��s�I�ȕ������ɂȂ��Ă��Ă���̂��ǂݎ���B
�Ђ�����u�Ή��ɗ�ށv���Ƃ́A�̐S�̃R�~���j�P�[�V�����p�ɂ��Ă����悤�ȋC������B
�����A�v�������̖{�̓��e�����̂܂��H����Ȃ�A���_���ڋ��ɂȂ�̂��o�傷�ׂ����낤�B�\�ʂ����̐l�ԊW��z�����ƂɏI�n���A
�ȑ��̎����A���Ȃ����߂��ɕЕ��̓w�͂Ɋ��҂���̂́A�{������ׂ��l�ԊW�̊�̖�肩��ڂ炷���ƂɂȂ邩������Ȃ��B
�������ɁA���N�����Ă��݂��̍l���𗝉�����͓̂���B�������A���̈Ⴂ��P�Ɂu�]�̐����v�ɋ��߂邱�Ƃ́A�u����͉����ł��Ȃ����Ȃ̂��v�Ƃ̌��ʂɂ₷�₷�ƌ��т��A�Ή��ɖ������鋰�ꂪ����悤�ȋC�����Ă����B
�킪�v�̂悤�ɁA�l��������Z�ŏ��肽���l�ԂɂƂ��āA���̖{�͉������̂ĂĐ����Ă������A�Ƃ����w�j�ɂȂ鋰�ꂪ����B����ɐl�Ԃ̐��i��P��������댯�����肻���ɂ��v����B
�l�Ԃ̊���̓g���Z�c�ł͌��Ȃ����́B�݂��ɉe�����Ȃ���`�Â����Ă������́B
���t�ɂ��ē`���邱�ƁB����I�ɂȂ�Ȃ����ƁB
����͑厖������----�B
���������_��
�u�Z�Z���~�~���ĂˁB���̌��K�ɏオ������A�����ɂ��遣���������č~��Ă��Ăˁv�Ɨ���A�u���A��̂��Ƃ��ꏏ�Ɍ�������ˁv�Ƃ������t���Ԃ��Ă����B
�����Ŏ����ǂ��Ԏ����������A����͓����B
�����B�����ς��邱�Ƃ�����ɓY�����Ƃ��Ȃ��Ȃ�������Ƃ��ȁB
�NjL�F
�w��e�Ɍ����Ȃ��l�̎q��ďp�x�@����I�}�[���������@���t�V��
�w�A���̕s�v�c�Ȑ������x�@��_�h�m���@�����V����
����̖{���ɓǂݎn�߂��B�l���A�������������邽�߂ɂ��܂��ܐ헪�����炷���̂��B
�w�Ȃ̃g���Z�c�x�ɑ��ĉ����ӌ��������闧��ɂȂ��ȁA�����B
���X���邭�������ƁA��k�ł������Ȃ����炷���������Ƃ����ƍK���Ȃ̂�ˁB
�n�E�c�E����ɓ���A���o�ɂł�����Ă������ۂ��ۂ��Ɛ�����̂��ǂ��낤�ȁB
���āA�O�͋P���悤�ȏt�̓����B
���ꂩ�炨�ٓ��������Ă��Ԍ��ɍs�����I
�A�蓹�œ��{�S�����̂ЂƂA�u���m��̐��v���������B
���R�̕�炵445�@�@2019.4.16
�@ �@
�@ �@
 �@�@��������ƐႪ�~�� �@�@��������ƐႪ�~��
�t�������݂��Ă���B
���̍��͌ܕ��炫�ŁA�s���N�̉ԐF���������B�W�����オ��ɂ��������Ăڂ݂͌ł��Ȃ�A���̏Z�ޕW��425���n�_�͂܂��炫�B
�����̐�Ɗ����ŁA���ꂩ��30���Ԃ͒ǂ��������ł���B
�k�ցA���݂ցB
|
 |
�@
���ւ��邩������ɐ�ӂ��
�킩���Ă�15�N�A���N��40�{���܂�炫�������B
�@ |
|
 |
�����́A�m�Ԃ��w���̍ד��x�����������A���������������H�˂̏�ՁB
�R����̕��������n�\�ɂ��ӂ�o�Ă���B
�@ |
|
 |
1998�N�̓ߐ{���Q�Ŕ�Q���������߉ϐ�͔ȂɐA����ꂽ�}�����B
����͏���̂Ȃ��o�����Ă݂����A�܂�3���炫�������B
�y���݂����������̂ł���͊������B
|
�@�@
���R�̕�炵444�@�@2019.4.10 (����ڂ��j�@�@
�@ �@
�@ �@
 �肪����ɓ�����ł��B
�肪����ɓ�����ł��B
���ꂩ��̋G�߁A
�ߐ{�͊ό��q�Ɉ�ꂩ����B����������X�̒��S�n�𗣂��ƁA���R�͖L�������q���̐��͕������Ă��Ȃ��E�E�E�E�E����Љ�����̂܂ܑ̌������悤�ȁA�u�c�Ɂv���L�����Ă���B
��������E�W�����قƂ�ǁB
�����Ȃ��q���Ɏ���Ė��Ȃ̂́A���w�Z�̊w�悪�ƂĂ��Ȃ��L�����ƁB����ɉ������݂́A���X�ɏ��w�Z����������Ă��܂��A���������ɔp�Z�ƂȂ����Z�ɂ��c���Ă���Ȃ̂��B
���������̖ړI�ŐՒn�𗘗p����Ă͂��܂��܍l�����Ă���B���Ƃ��Ε���26�N�x�ɕZ�ƂȂ����ߐ{���̓c�����w�Z�̐Ւn�ɂ͌��݁A�ߐ{���c�������{�݁i���́F��ځ[��E���Ȃ��j��2�N�߂��O�ɃI�[�v�����Ă���B
�u�q��Ďx���{�݁v�u�̈�x���{�݁v�u����Ҋ����x���{�݁v�u�n��R�~���j�e�B�����x���{�݁v�u������Ɠ��琬�x���{�݁v�Ƒ�ڂ͖L�������A�Ȃ��Ȃ��^�c��������ȓ��e���B��������������^�c����u�l�����v���ǂ����B����̂��B
�l�����ꂽ�ꏊ�ɂ���{�݂ɐl���W�߂�ɂ́A���ꑊ���̍H�v���K�v���낤�B
���̓ߐ{���c�������{�݂ŊJ���ꂽ�u�ߐ{�܂��Â���L��v��K�₵�Ă����B
�ړI�́u�j���A�[�g�v��i�����邱�ƁB��҂͓ߐ{���ݏZ�̔��V���j����
10�N�O����ŔP���̎��̂ɑ����Ĉȗ����葫�������Ȃ��Ȃ������V����́A���n�r���̈�Ƃ��Đj���H�ɒ��킵�Ă��Ă���B
|
 |
�u�}�ʂ���������܂���B�肪���R�ɓ����͂��߂Č`������Ă���̂ł��B�܂�ł��̌`�Ɏ����̐S���Ă�邩�̂悤�Ɂv�B
�������茳�C�ɂȂ������V����B
�ڂ��P�����Ă������B
�u���͉������낤���ƍl���Ă��鎞����Ԋy�����B�v�Ƃ��B
���߂Ă̍�i�͍��́A�u�K���p�S�X�̃]�E�K���v�B
�����T���E�W���[�W�iLonesome George
�@�@�@�@�@�@�@ 2012�N6��24�������j
�i�K���p�S�X�]�E�K���̈���A�s���^�]�E�K���j�u�ʐ^�������Ƃ���ɁA�������낤�I�Ǝv������ł��B�v
|
|
�����T���E�W���[�W�́A1971�N�ɃK���p�S�X�����̃s���^���Ŕ������ꂽ�s���^�]�E�K���̍Ō�̌́B���̃W���[�W�̎��ɂ���ăs���^�]�E�K���͐�ł����ƍl�����Ă���B
�@ |
|
 |
1982�N4���B
����70�̃����T���E�W���[�W�B
�u�T�ɂ܂�����v�B
����Ȃ��Ƃ�������Ă������ゾ�����B
��҂̔��V����ɁA37�N�O�ɎB�e�����]�E�K����C�E���C�O�A�i�̎ʐ^�������グ���B
���̍�i�ւ̎h���ɂȂ�܂��悤�ɁB
�@ |
|
�ŐV�̌����ɂ��ƁA���̃s���^�]�E�K���̒��Ԃ������c���Ă���\��������炵���B�K���p�S�X�����̊e�n�ŁA�s���^�]�E�K����DNA���p���ł���̂����������Ƃ����B
����ɁA2019.2.22�̓��{�o�ϐV���̋L���ɂ��ƁA�u�������̃t�F���i���f�B�i���ŁA100�N�ȏ���������m�F����Ă��Ȃ������]�E�K���̈�킪�������ꂽ�v�Ƃ̂��ƁB
�K���p�S�X���̃]�E�K���̌̐����}���Ɍ������������́A���ɐN�������l�Ԃ��H�p�ɕߊl�������ƁA���M��u�^���O���玝������ŁA���̎��R����j�����ƂȂǂ��B
���܂Ⓡ�͂�������ό��n�����A���]�[�g�z�e������������ł���炵���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Ȃ����V����A���������\���邱�Ƃɂ��ĐϋɓI�ȗ����Ă��܂��B�j |
���R�̕�炵443�@�@2019.4.6
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
�@ R 1.2 �̋O��
R 1.2 �̋O��

�����Ƀc���n�V�������Ă��ė͔C���Ɍ@���Ă݂Ă��A�n�������Ȃ��B
�X�R�b�v�����āA�͂˕Ԃ����قnjł��y�Ȃ̂ɁA���O�����₷�₷�ƃg���l�����@���Ă����B
���a1.2���̋O�ՁB
�����͒��t�̏��߂̓��B
�y���̐��������K���Ď����K���o���I�@�Ȃ�Ďv��Ȃ��B
4���͂̂�т肷�邼�A�ƐS�Ɍ��߂����B
�ߘa���N5��1���@�@�����L���܂ł���29���B
�ߘa�̏o�T�́B�@
�w�ݗt�W�x��5�@�~�Ԃ̉�32�� (815����846) �������@
�V����N�����\�O���A�t�̘V�̑���܂�́A�����\�Ԃ�Ȃ�B���ɏ��t�̗߂����ɂ��āA�C�i�����a�݁A�~�͔₭�A���̑O�̕����A���͌O�炷�A��̌�̍����B
�����݂̂ɂ��炸�A���̗�ɉ_�ڂ�A�������|���āA�W���X���A�[�̛��ɖ����сA�����ɕ��߂��ėтɖ��ӁB��ɂ͐V���������ЁA��ɂ͌̂�A��B�����ɓV���W�ɂ��A�n�����ɂ��A�G�𑣂��[�����B�������̗��ɖY��A�܂������̊O�ɊJ���A�W�R�Ƃ��Ă݂Â��瑫��B�����ˉ��ɂ��炸�́A�����Ȃ��Ă����擄�ׂށB���ɗ��~�̕т��I����B�Âƍ��Ƃ��ꉽ���قȂ�ށB�����̔~�݂Ă��������Z�r���Ȃ��ׂ��B
�@�@�@�@
�u�t�̘V�v�Ƃ́A��ɕ{�̐��E�唺���l�@���̕��͑唺���l�̍�Ƃ���Ă���B�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�w���t�W�S�u�x ���c�S�g���@�������@�ł��@(���a30�N3��5�����s)�@
�����������́u���ɏ��t�̗߂����ɂ��āA�C�i�����a�݁v�̕����́A������k������A�쒩���̏������q�ɂ���ĕҎ[���ꂽ�����W�w���I�x����̈��p���B
�ق��Ɍ㊿�̕��w�ҁE���t�ɂ��u�A�c���v�Ɉˋ��A���邢�͉�㺔V�́u�������v�ɂ���u�V�N�����A�����a���v�܂��Ă���Ƃ�����������炵���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�i�u�߁v�͉��̉��ɐl���삢�Ă���p���Ӗ�����B
�@�@�܂��A�u��v�̎��́A�_�X�����A���炵���A�D��Ă���Ȃǂ̈Ӗ������B
�@�@���̗�Ɠ��������́u�߁v�����Ď��Ƃ��Ďg��ꂽ�Ƃ����o�܂�����B�j
���R�̕�炵442�@�@2019.4.1
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
�@ �@�@�^��͌����@�� �@�@�^��͌����@��
�@
|
 |
 |
|
�E�̎R�͋��N�̏H�̗����t�B�����ɂ́A��������͔�ɂȂ������N�̗����t���������B
���͔̑���@��グ�č��ɓ����Ă���Ƃ���B
�n�`�}�L���ėE�܂����H |
�@��グ�����ɁA�E�̎R�̗����t��ςݏグ�A�ΊD���T���ďォ�琅��������B
��������ƈ�N��ɂ́A�L�@���^�b�v���͔̑삪�ł�������B
��Ƃ͏��J��Ȃ̂��B |
���ė^��̍Ȃɂ́A�u�X�R�b�v�ő͔���������グ��֎Ԃɐςށv�Ƃ����d�������Ă���ꂽ�B
���͐ςݏグ���͔���A��̂��������ɂ���Ԓd�ɂ�܂��Ă������B���̓����20���������̂ō����̓w�g�w�g�B
��֎Ԃɑ͔����t�ɂ���ɂ́A�X�R�b�v��20��������������Ȃ킿400����X�R�b�v��U������ƂɂȂ�̂�����B
�l�p�`�̒�̂��̂��̂̕ӂ͖�40���[�g������A�Ԓd�܂ʼn�������Ƒ������������ƂɂȂ�B
�ߐ{�̎R�̐��n�̒���������Ɉʒu����킪�Ƃ̒�̓y�n�́A�ΎR�D�y�̉e���Ŏ_���x�������B���̏�Ɏ_���J���~�葱���킯������A�_�x�����̂��ߑ͔���T���̂Ɠ����ɖ؊D�������Ă����B
���𐘂��ė���Ńn���h���������A�n�ʂ̐A���܂Ȃ��悤�ɂ��邷��ƈړ����Ă����B
������Ƃ����R�c������E�E�E���A���B�������荘�𗎂Ƃ��d�S��Ⴍ���A�悻�������ɕ����B
�悤�₭���������B
�Ƃ��낪�����瑊�_���u�U�������āv�ƌ����Ă���ł͂Ȃ����B
���������B�i�����Ă������̂�����ł���B�Ȃɂ�����Ȃɔ�ꂽ�ߌ�ɂ���ȗ��݂����Ȃ��Ă��ˁB
�܂��������Ȃ��B�Պ���ɂȂ������ǁA����ł������B�ǂ�����ɂ̓R�b�v��t�ŌՂɂȂ�̂�����B
�@�@���R�̕�炵441�@�@2019.3.28
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
�@�@�@�@ �R�X�~�����炢�Ă����B�@���N���n���̖傪�J�����悤���B
�R�X�~�����炢�Ă����B�@���N���n���̖傪�J�����悤���B
�@
|
�R�X�~���́A�t��Ԃɍ炭�X�~���B�@�@
�͂�t�̂Ȃ��������o���B |
 |
�R�X�~�� |
���{�Ɏ�������X�~���ȃX�~�����͖�60��ށi���N�����{�j�B�������A���G��∟��A�ώ�A�V���ɍ�o���ꂽ���|�p�i������肻�̐��͊m��ł��Ȃ��B
���h����A���ʐ^�ƁE������܂������̐}�Ӂw���{�̃X�~���x�i�R�ƌk�J�Ёj�ɁA���{�Ō�����X�~���̎�ނ�200��ȏ�Ƃ���B�����Ȑ����B
�A���́u��Εٕʊ��v�Ɍb�܂�Ȃ����ɂ́A���ٕ̕ʁA����͓���A�t�ɂȂ�̂͊���������ǂ��ٕʂɓ���Y�܂��G�߂������E�E�E�����������͂������Ȃ�������B
�A�����Ԃ��X�~�������Č������ƂɁA�u���E�E�E���B�X�~�����E�E�E�E�B�v
��u�̂����ɃX�~���ٕ̕ʁ���₱�����A�܂�Œn�������܂���Ă���C���ɂȂ邱�Ƃ�z������炵���B
���̏�Ԃ��u�X�~���n���ɒĂ����v�ƌĂԁB�@�����ł���B
�ώ@���ٕʂ���͍̂��̋G�߂����ł��Ȃ��̂ɁA��̓��������̂͂܂��Ƃɓ���B
�n��s�̗L���A�Ԃт�̗l�q��F�A���̑��̂��܂��܂Ƃ��������𑍍����Č������悤�Ƃ���̂����A�Ɗw�̔߂����A�i�݂͏t�̓�����̂悤�ɒx���A�����Ď��̗���͂�������ɑ����B�@�����Ƃ����ԂɋG�߂͐i��ł����B
�Ȃ�Ƃ��w�͂������A�g�߂ɍ炢�Ă���X�~���̖��O��ł���悤�ɂȂ������̂́A���̐��͂킸����20�킽�炸�B
���ꂪ�ȉ��̃X�~�������B�@�@�������ƐM���������A�������M���Ȃ��B
|
 |
 |
 |
 |
|
�@�@�A�J�l�X�~�� |
�@�@�A�P�{�m�X�~�� |
�@�@�A�I�C�X�~�� |
�@�@�A���A�P�X�~�� |
|
 |
 |
 |
 |
|
�@�@�t���g�X�~�� |
�@�@�q�i�X�~�� |
�@�@�G�C�U���X�~�� |
�@�@�q�J�Q�X�~�� |
|
 |
 |
 |
 |
|
�@�@�}���o�X�~�� |
�@�@�R�X�~�� |
�@�@�}���o�X�~�� |
�@�@�i�K�n�V�X�~�� |
|
 |
 |
 |
 |
|
�@�@�j�I�C�^�`�c�{�X�~�� |
�@�@�m�W�X�~�� |
�@�@�X�~�� |
�@�@�T�N���X�~�� |
|
 |
 |
 |
 |
|
�@�@�^�`�c�{�X�~�� |
�@�@�X�~�� |
�@�@�c�{�X�~�� |
�@�@�E�X�o�X�~�� |
���Ȃ݂ɁA��̎ʐ^�͂��ׂăR���p�N�g�f�W�J�����g���ĎB�������́B
�ʐ^�Ƃ������g�����t�J�������~�����Ǝv�����肪�o���A�����܂ŗ��Ă��܂����B
�����Ƃ��ʐ^�̃v�������́A���������Y�����X�ɗ~�����Ȃ�炵���B
���̕a����u�J�������ɂ͂܂����v�ƌ�������A�n�����B��̂ɂ͏��ɗ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ������Ƃ��낤�B
���R�̕�炵440�@�@2019.3.24
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
 �Ɨ��Ƃ��̒�q
�Ɨ��Ƃ��̒�q
�@
|
 |
���̑傫�ȑ܂́A���肵���̎}��������������Ȃǂ�����܂Ƃ��Ă����g���Ă�����́B
�{�i�I�ȏt������O�ɁA�����͐L�юn�߂��G����A�~�̊Ԃɒ�ɗ��܂������̗t�Ȃǂ��W�߂Ď̂ĂĂ����B�傫�ȑ܂ɂӂ��킵�����O��t�����B�u�Ɨ��v�ƁB
���͂��̉Ɨ��B��������œ����Ȃ��B�����n�ʂɂ����Ɣ��������Ă��邾���B
��������t�ɂȂ�ƁA�₨�炲��l�l�̃��^�V�����邸��ƈ��������ĕ����A���̎p�͊��m���̂��́B
�@
|
��@�傫�ȑ܂����ɂ���
�@�单���܂����������
�@�����Ɉ����̔�������
�@ ����ނ���Đԗ�
�单���܂͂���ꂪ��
�u���ꂢ�Ȑ��ɐg����܂̕�Ȃɂ���܂�v�� �悭�悭�����Ă��܂����@�E�E�E�E�� ( �쎌:�Ό��a�O)
�����A�������B���͑单���܁B�A�����D�����R���̑单���܁B
���Ȃ݂ɁA�߂��߂��̓����ɉ����Ď����_�̑܂͂����Ƒ傫���āA�̐ς͂S�{�߂��B
���̖��O�́u�ƘV�v�B��͂莩���ł͓������A����Ԃɂ������A�Ƃ���������l�������g���B
�ƘV�ς��ĉߘJ�̑܁B
�킪�Ƃ̂P���Ԃ́A������Q�S�Ɋ��������Ԃł͂Ȃ��B�G�߂ɂ�鑊�Ύ��ԂŁA�L�т���k��B
�����o��Ɠ����͂��߁A����������ƉƂɓ���B
�c��͂��Ȃ킿��B
�����Z������Z�܂ŁB���ꂪ���������������̐������ԂȂ̂��B
���R�̕�炵439�@�@2019.3.21
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
 ���t�͂���Ȃ�
���t�͂���Ȃ�

���������č炢�Ă��郉�b�p����B
���C���x���g�E�A�[���[�E�Z���Z�[�V�����iRijnveld's Early
Sensation�j�̖��O�̒ʂ�A�t�N�W���\�E�ɕ����Ȃ����炢�����炭�B
���R�̕�炵438�@�@2019.3.16 �@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �t���������͖̂쒹������
�t���������͖̂쒹������
���r���L�тĂ����B�@���̂����ł܂��܂����N�����Ă��܂��B
�S�Ȃ����A����щ��쒹���A���₩�Ȋ�����Ă���悤�ɂ�������B
�t�̒�d������i�����A�悤�₭���͂����܂킷�]�T���ł��Ă����B
���t�̒�ɗ��钹�����B
�@�@�i�J���X���n�g���X�Y�����q���h�����A�܂����ƂŁB�j
|
 |
 |
 |
|
�A�J�Q���@
���͑��_���������A�J�Q���ŁA�E�͖{���B�����Ԃ̖͗l���Ȃ�Ƃ��������B |
�L�W�i�Ì�͂������j
�P�[���P�[���Ɣ߂������ɖ��Ă���B�������Ɨ���ɂ�������ł����B����҂��Ă����̂��낤���B |
����̓C�m�V�V�B
���������Ă���̂������B
��x�͂������A���x��������͖̂��f�B |
|
 |
 |
 |
|
�l�Ԃɂ̓l�I�e�j�[�헪�͒ʗp���Ȃ��悤���B�G�i�K�B
�}�ɂԂ牺����̂����ӁB |
�V���@�̎����ނ̂ɓK�����������������Ă���B
�킪�Ƃł̂������́u���̂������v�B
�܂����ӂƂ���Ɉ������������Ă��Ȃ���ˁB |
�A�I�Q���@�I�X
�ƐԂ̕�F���ڗ����߂��ď���B�Ԃ��F�͐헪�Ƃ��āA������Њd����A�����������������X�ɋC�ɂ����Ă��炤�E�E�E�E�E�E���߂ƍl�����邯�ǁB�ǂ����ȁB |
|
 |
 |
 |
|
�������ǂ��A�g���̂����B
�オ���X�A�E�����I�X�B |
�J�����q���@
�g�����Ȃ��Ă����̂ŁA�Ⴊ���������Ɉړ����Ă������B
�����́A���邭�L�����L�����L�����B |
�c�O�~�@
�ƂƂƁA�ƕ����Ă̓c���Ƌ��炷�B�͗t���Ђ�����Ԃ��Ē���T���Ă���B |
|
 |
 |
 |
|
���}�K��
�r���[�r���[�Ɩ��܂��A�l�Ԃ��߂Â��Ă��|����Ȃ��B
���̐̂́A��ł����������]��������Ă������炢�l���������B |
�V�W���E�J��
�����畔���̒���`������ŁA
�u��`���v�B
����̓l�N�^�C�����h�ȃI�X�B |
�V�W���E�J��
�Ђ܂��������Ă҂��B
�҂��A�҂��B |
|
 |
 |
 |
|
�~���}�z�E�W���̗Y�B
���h�Ȋ��H�����B
�w���Ɂu�G���K���X�v�����������Ȓ��B |
�S�W���E�J��
���삯����邱�Ƃ̏o���钿�������B |
�J�P�X�@���ݐ��Ŗ��B
�ߏ��ɃC�M���X���痈���W�F�C���Z��ł���B�u�ڂ��̖��O�̒����v�Ɗ��������B
Jay �ɂ� �h������ׂ�h�̈Ӗ�������炵���B�悭�����܂�钹�B |
|
 |
 |
 |
|
�W���E�r�^�L�i�I�X�j
�H�ɔ����X�|�b�g�����邱�Ƃ��炠�����́u��t�̃W���[�v�B
���낻��꒣��錾��P�A���̑����T���������B |
�������B�x�j�}�V�R������Ă����B�}�V�R�����̂Ƃ���A�g�̂��Ԃ��̂������B
�����H�@�ӂ���}�V�R�ɂȂ��Ă�ˁB |
�R�Q���@
�L�c�c�L�̒��Ԃň�ԏ������B
�����肻���ɂȂ�ƁA�Ɩ̗����ɉB���B
���̗l�q�̓Z�~�ɂ�������B |
|
 |
 |
 |
|
���W��
����͖{���B
���͑��_�����������W���̐e�q�B |
�f�b�L�̏�̐���������A�`���b�`���b�ƈ��݁A�K�����p�^�p�^�B
�݂���D���B |
�������3�T�Ԃ������炢�Ă������b�p����B
�Ԃ͓���������č炭�B
���O�̓A�[���[�Z���Z�[�V�����B���̒ʂ�̑��炫�B |
�@ �E �킪�ߐ{�͂��܂Ђ�����ɏt��҂�
�E�@���ۂ̈łɐL�т䂭�ӂ��̂���
�E�@�R�쑐�؎��F���������ԁ@
�E�@���͓��Đ���̔g���悬����
�@�E�@���Ԃɂ��Z�W����Đk�Њ��@
�@�@
���R�̕�炵437�@�@2019.3.11 �@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �t�̎n�܂�͂܂��J������@---�@�����͌[�
�t�̎n�܂�͂܂��J������@---�@�����͌[�
8�����A���H�����������ɍ�������ɏo��B
���������A�͂т������ۂ��W�߂Ď̂Ăɍs���B
3�����{�Ƃ������������Ɏd�����n�߂�̂́A���̂��Ɓu�����A������щ��A���Ă�����v�̎O��ꂪ�҂��Ă��邩��B
�������ł��̋L�^�������Ă������B
�������܂��d�����B
|
 |
|
�W���ʐ^���B���Ă���B |
|
 |
|
����͒��̕������Čߌ�̕��Ɠ����Â߂������B�@�|�s�[�̐A�����݂͏I���B
155�{�Ƃ������������Ȃ��ɂ́A���\�Ȏ��Ԃ��K�v���B |
|
 |
|
�ʐ^�̓C���[�W�ł��B�V��A���̑��̏����ɂ���ĕς��܂��B�i�j ���s�ē����̌�����݂������ȁB
��������2�N�O�̎ʐ^�B
3�N�O�̉Ԏ��ɁA���F�Ɣ��ƃs���N�̎킾���̎悵���̂ŁA�����̒ʂ�̂��ƂȂ����F�̉Ԓd�ɂȂ��Ă��܂����B���N�̓I�����W�F��̓��₩�ȐF����ꂩ����\��B |
���R�̕�炵436�@�@2019.3.6 �@
�@�@�@ �@ �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@�@�@
 ����O�ɒ��ׁ@vs�@��ԑO�Ɍ���
����O�ɒ��ׁ@vs�@��ԑO�Ɍ���
���āA���ẴA���o���f�W�^���������A40����̍����悤�₭�\��̍�Ƃ��I���邱�Ƃ��ł����B
�t�B��������ɂ͎B�e�����ʐ^���̂��̂��u���������Ȃ��āv�A�����������ׂĂ�\��t���Ă����̂��A60�����̐��ɂȂ��������������B
�f�W�^���J�����ɕύX���Ă���́A�\�}��I�o�Ȃǂ�ς��Ȃ��琔���B��A���̂Ȃ�����ꖇ�I���������̂��v�����g���Ă���̂ŁA�ȑO�قǖ����͑����Ă��Ă��Ȃ��B
�f�W�^���������ʐ^�̂����A�I���������̂�V���ɓ\�蒼���A���nj��̕����I�ʂ̏\�̈�ɂ܂Ō��炷���Ƃ��ł����B�c�����ʐ^�͒i�{�[���œB�Ƃ�ł��Ȃ��������B
���A�悤�₭��Ƃ���i�����āA�ǂ����Ɍ����J�����C���ł���B
��|���Ō�������̉��̌ÐV�������荞��ł����ǂ�ł��܂��悤�ɁA���̎��X�̏o�������v���o���ẮA���S�ɐZ���Ă݂���A��������Ă݂���̂S�O����---����͓~�̊Ԃ����ł��Ȃ���Ƃ������B
����ň����z����A���邢�͎{�݂ւ̓����ɂ��ς�����ʂɂȂ����B
��͂�A�A�i���O�͂����B�ߋ��̎��Ԃ��肴���Ŋ����邱�Ƃ��ł��邩��B
�������A����Ȃɖʓ|�ŒP���ȍ�Ƃ��Ə��߂��番�����Ă�����A����o���Ȃ��������낤�Ȃ��B
����ʼnߋ��̒I�����͂����܂��B���ꂩ������s�����B
�l���ɐ܂�Ԃ��n�_�Ȃǖ����B�����i��ōs���̂݁B����Ɗ����Ȃ������ɂ���ړI�n�Ɍ������ē��X���ςݏd�Ȃ��Ă����B
���̏ꍇ�̈�N�́A�g�̂��23.5�x�X�ނ��ċG�߂ɍ��킹�A����肮���Ƒ傫�ȑȉ~��`���Ȃ���߂��Ă����B���ӂ͏t�ƏH�A�Z�ӂ͉ĂƓ~�B�A������̈�N�́A�l�G�̂��̂��̂̍�Ƃ�ςݏd�ˁA�����傫�ȗ�����ɂȂ��Ă����Ƃ�����N�̂悤�ȋC�����邩��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w����O�ɒ��ׁx�@��]���O�Y �@vs�@ "Look before you leap."�@���ԑO�Ɍ���
|
 |
���_���d�������グ�A�G�A�R���̃J�o�[��������B
�g�����ޗ��́A�S�E�Ăڂ��ŁA���H��������������ǂ��B
�͗���͒��ށB
���ɕ����ׂ�ƒ��ޖA������S�̖B
�֖҂Ȍ��������邭�炢���ȏo�����B
�����̂悤�ɑ��_�́A�قǂقǁA�Ƃ������Ƃ�m��Ȃ��炵���B |
���R�̕�炵435�@�@2019.2.28 �@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �������
--- �������h���Ƃ͂����������Ƃ� �������
--- �������h���Ƃ͂����������Ƃ�
����͂�����Ƃ����L�O���������B���̉w�̖�؈��D�Ƃ̎����A�[�H�ɂ͕������Ă����ƈႤ���j���[��p�ӂ����B
��c�����̃X�e�[�L�ɃI�j�I���\�[�X
�X�[�v�Ɩ�T���_
�u�����h䕂̃X�J�C�x���[�@�@�f�U�[�g�Ƀ`���R���[�g
����ɁA�����C���̍D���ȕv�̂��߂Ɂu�`�����C���̔��v���B
���͉��˂Ȃ̂ł������C���O���X�͕v�̕������o�����A���͓��ʓ�p�ӂ����B�`�����ł������ďj���`����肽�������̂ŁB�����ł�������̂��������ƂɁA�����݉߂��܂����ˁB
�O���X��2�Z���`�قǁB�`�����C���͐̂���̕����̕i�킪���Y�n�Ɏc���Ă���̂ŁA���L�̖�������B����2�Z���`���܂�܂����ł��܂����I�@���Ė����������Ƃ��I
�ʂ́A�����炭��T�W�Q���炢�H�@30�����قǂ��B�@�����͂ق�̂ЂƂȂ߂��邾���Ȃ̂ɁB
�����C�����E�E�E�B�ӂ�ӂ킷��B�H��͑��_�ɂ܂����Ă�����������B
�������萌��������Ă��܂��āA���Ƃ͂��ڂ�@---�@�h�ꂢ�����Ƃ��A�h�ꂭ�邲�Ƃ��@---�B
�����Ē��B���ƌ����Ă��쒹�����N���Ă��Ȃ��܂��Â����A���ɂƓf���C�Ŗڂ��o�߂��B
�ꂵ���B
���@----�i�E�E�E�E�E�E�j-----�Ɓi�������j�̒��̓���������Ƃ���A���Ⴋ���ƋC�����ǂ��Ȃ��Ă����̒��̎d�������Ȃ����B
���̒P�����Ƃ�����B
�����A����������Ă������������ȂƎv���m�������B
��̎R��w�i�ɁA�P���悤�Ȍ��ɖ������@���̒����B
���P
�P�@���̃A���R�[���ێ���x�́A�r�[��1�Z���`�A���C���ЂƂȂ߂̂悤���B
�Q�@��͂�X�e�[�L�ɂ͔������Ԃ��������B
�@
|
 |
�����l�̌����ĔM���W�߁A�Ԑc�����߂邽�߁A��������`���Ă���Ԃт�̘A�Ȃ�B
����A�i�`�w�`�̉F���T���@�u�͂�Ԃ�2�v�����f���u��イ�����v�ւ̒����ɐ��������B
�C���^�r���[����v���W�F�b�N�g���[�_�[�̌ւ炵���Ȋ炪�܂Ԃ����B
�u�����A����������Ă�Ȃ��A�V���w�╨�����ɂ߁A���̂�������\�͂ɗD��Ă���A����Ȑl������v�ƁB |
���R�̕�炵434�@�@2019.2.23
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 ���Ƃ́@�u���傤����v�@��҂���
���Ƃ́@�u���傤����v�@��҂���
�@�@�@�@ ����
����
���A�t�߂��Ă��������z�ɎĖ�����Ă�����A����̋��ɂȂɂ�甖���F���������������̂ɋC�t�����B
����͂ǂ��݂Ă����B���낤���ƂɉԒd���ق�����Ԃ��Ă���ł͂Ȃ����B
�C�m�V�V�͌��������̂��Ƃ�Ă���̂��ǂ����A�̂��̂��Ɠ����čs���B�������֖҂ȗl�q�ł͂Ȃ��A���ƂȂ������łǂ��炩�ƌ����Γ��C�Ȗ�nj��A�ƌ��������͋C��
�Y�킹�Ă���B
�}���Œ�̃p�g���[���ɏo��B
���������ɕ@�łق�����Ԃ����Ղ�����B�`���[���b�v�̋�����_�����炵�����A�ǂ���炱�̂Ƃ���̐��V�����ŁA�n�ʂ��ł��Ȃ莕���i�@���j�����Ȃ������悤���B
�H�ɂ́A�͂��ƐU������Ǝ��������B
�@���ɂ́A�ӂƖڂ��グ��ƒ��������B
�c�ɂ̕�炵���n�߂�����ɂ́A����Ȃ��Ƃ��y���܂Ȃ���ˁB
�ԎD�́u���̂������傤�A�������v�����낻��o���オ��B
�[孂��߂��Ԃ��Ƃ�ǂ�ɍ炭�ƁA��ɂ͂��傤���傪����Ă���B
�������݂ɂȂ邱��4���́A�ǂ̂悤�ȏt�ɂȂ邾�낤���B
�Ȃɂ��������Ƃ���܂��悤�ɁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@------�@�l���Ȃ��Ȃ����������邩�ȁB�@�i�p�N�� �j
�ߌ�̓t���[�g�̃~�j�R���T�[�g���ɍs���B���N�ɓ�����2��ځB
�O�͌��̏t�B

���R�̕�炵433�@�@2019.2.17 �@
�@�@�@�@�@ �@ �@ �@ �@
�@
 �܂�܂�ł܂�����Ȃ��̂��������������@
�܂�܂�ł܂�����Ȃ��̂��������������@
�ʘb���Ɏ�b��Ɩ{�̂��q���ł���ꏊ��������Ƃł��������ƁA�ʐM��Q�̉��Ȃ̂��A�u�r���W�����r���v�Ƃ����G������������悤�ɂȂ��Ă����킪�Ƃ̃t�@�b�N�X�@�B
�������Ȃ��B�w�����Ă��ł�15�N�ȏ�ɂ��Ȃ�̂�����B
�����炭��b������ɓ��Ă鎞�ɁA�ӎ������֕������������������ĐڐG�������Ȃ��Ă���̂��낤�B
���̂���������̃X�}�z���g���Ă���F�l�Ƃ̉�b���ł��Ȃ��Ȃ��Ă����B
����͓��ڂŁA�����w�������̂�1986�N�B�܂��܂��t�@�N�X�@���ƒ�ɐ����t���邱�Ƃ��������������ゾ�����B
�A�����J�֒P�g���C����v�Ƃ̒ʐM��i�ɂƁA�m�s�s�̐��i���w���������̂ŁA����25���~�������I
�u�Ȃɂ���������́v�ƕ�����邱�Ƃ����������A�\�ߐݒu���m�s�s�ɓo�^����K�v���������̂ŁA�C�O�ɕ��C�����搶�ɘA�����邩��Ɗw�Z���킴�킴��ɗ���ꂽ���Ƃ��������B
�C���^�[�l�b�g�𗘗p�ł���悤�ɂȂ����̂́A����5�N��̂��ƁB
�V�V�n���J�����v���������B�����Ƃ����̎����̓p�\�R���i�m�d�b�j���g�킸�A���[�v���@���g���A�e�L�X�g��������Ȃ��������B
-----�u�r���W�����r���v�̉������@�́A
�����̂悤�ɁA���܂����܂��g���Ƃ������́B
�킪�Ƃ͂��������Ȃ̂��B
�������̂͂Ȃ�Ƃ������Ďg���A�Ƃ����̂���|���V�[�B���_���d�C��؍H�ւ̒m��������̂��ז������A�Ȃ�Ƃ��g���邱�Ƃ͎g���邪�A�V�i�̎��̂悤�Ɋ��S�ł͂Ȃ��A�Ƃ�����Ԃ̐��i���Ƃ��イ�ɁA���낲�낵�Ă���B
�u�������A���ꂪ����Ȓm���̂Ȃ��l��������A�����͐V�@����䂤�䂤�Ǝg���Ă����̂Ɂv�Ǝv�����Ƃ�����B�䏊�̎����|���@�̃X�C�b�`���Ȃ��I�J�V�i�`�ɏC�����Ă��܂��āA�u���܂����܂��v�g���Ă���B
�����A�Ȃ��N����炵��B
����A�����ł��Ȃ��āA�܂������Ύg������̂��̂Ă�̂͂��������Ȃ��B
���������A�@�B�A��B�����ďC������B����Ȋy�������Ƃ͂Ȃ��Ƃ������n�j����������킪�ƂȂ̂�����B
�@�@�i�Z���I �����܂��C�����Ă���I �j���E�{�E�����ď�͐V���������ǂ����A�Ɠd���ŐV�����g�������ɂ��܂��Ă�I�@�ƉA�łڂ₭�̂ł����j
�b�x��B
���̊�B�ɂ͊��M�����Z�b�g���Ă���B�Ȃɂ���C���N���{�����g�������A�ꖇ�̒P�����ƂĂ������̂ŁB�ܘ_�����ۑ��ɂ͌����Ȃ����A��N�͗D�Ɏ�����B
����Ȃ��Ƃ��������̂��v���o�����B
���_�������œ����Ă����Ƃ��A�Ȃ��Ȃ��ߏ��Ŋ��M�����Ȃ���������̂��Ƃ������B
���x���̊��������̂��ƁA�d���A��ɉw�O�̓d�C�X�Ŋ��M�����A���̂܂��ރJ�o���Ɏd�������B
���Ɍ������̂́A���D����ʂ�O�ɓX���o���Ă���u�ǂ�Ă��₳��v�B�ӂ�ӂ�Ɗ�蓹�������_�A5�����Ă���܂����ރJ�o���̒��֎d�������B
�@�i5�̂����A�ǂ���������4�ŃI�N�T���ɂ�1�̂��肾�����炵�����B�j
���̓������ċA���Ă��܂����ˁB���������ɃJ�o������u���y�Y�v�Ǝ��o�����ǂ�Ă��Ɗ��M��������ƁA�ǂ����̐����Ƃ̌��t�̂悤�ɁA�u��������A��������v�Ɗ��M���ɂ͑傫�Ȋۂ��������������v�����g����Ă����@----�ǂ�Ă����M���č������߂��̂������B
�ǂ�Ă��͂n�j�����A���M���͔����g�����ɂȂ�Ȃ������B
���ꂪ���̖�̎��x���Z�Ȃ�B
�@
|
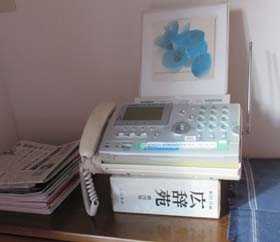 |
�@
�{�̂��������邽�߂ɁA�w�L�����x�����ɕ~���Ă���B
������Ȃ����Ƃ������ɒ��ׂ��邩��֗�----�Ƃ������Ƃ��Ȃ����B
�����ɂ͗��s�W�̃p���t���b�g��A���|���A����ɓ��{�o�ϐV���i���������A�c�ɂȂ̂ŗ[���͓͂��Ȃ��A�c�O�j |
���R�̕�炵432�@�@2019.2.12 �@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �ЂƂ߁A�ӂ��߁A�݂���
�ЂƂ߁A�ӂ��߁A�݂���
����̂��ƁA���_��������Ƃ����ӌ��̍s���Ⴂ���������B
�Ȗ،��k���ɂ́A��ÂƂ̋��E�ɂȂ�W���P�O�O�O�����炢�̎R�X���A�k�����Ɍ����ĕ���ł���B
���̎R�����ɂ���{�݂�ڎw���ĎԂ𑖂点�Ă����Ƃ��̂��Ƃ������B
�Ȃɂ���}���`�^�X�N�����Ȃ��Ȃ����_�Ȃ̂ŁA����Ȃ̎��́A�ɗ͖��ʘb�������i����͓���I�j�i�r�Q�[�^�[�ɓO���邱�Ƃɂ��Ă���B
�u����������v�Ɛ���������B�u����v
�Ƃ��낪�킪�^�]�肳��́A���炩���ߒ��ׂĂ������M���̏ꏊ�܂ŗ��Ă��Ȃ��̂ɁA�������킸�E�ɂ����ƋȂ����ĎR�̕����ɂǂ�ǂ�i��ōs���ł͂Ȃ����B
�c�ɂ̂��Ƃ�����A�M����̍��͂��悻�T�O�O���ȏ�ŁA��ԈႦ��Ƃ�ł��Ȃ������Ⴂ�����邱�ƂɂȂ�B
�u����A�������Ȃ��H������������̐M�����E�܂���̂��Ǝv�����ǁv
�u����A�������̐M���̑����̎菑���̊ŔɁw�O�ڂ̐M�����E�x���ď����Ă�������v
�u���A�Ȃ�������̐M������Ȃ��́H�v
���̐�A�ׂ������c�ނ̔Ȃ��𑖂�A���nj��m��ʎR�Ԃ̊ω��l�܂ŎԂ͕��ꍞ��ł��܂����B
�s���͂悢�悢�A��͂Ȃ�Ƃ��B
�悭�悭�₢�������Ă݂�ƁA���_�̍l���͂����������B
�u�Ŕ��������M������ڂ���B�������炠���������ڂ��w�O�ڂ̐M���ɂȂ邶��Ȃ����x�v
�u���`�A���ʎO�ڂƂ���A���̐�̎O�ڂ̐M�����Ӗ����Ȃ��H�v
�u���Ȃ��v�ƕs�@���ɂȂ鑊�_�B
�ԟ[���܂����X�����ǁA���̏ꍇ�͂ǂ�����������悤���B
��ڂ��ǂ��ɒu�����A�ǂ����N�_�ɂ��邩�B����ɂ͓�ʂ�̍l���������邩��B
�V���Ј����u�A�E��N�ځv�ƌĂсA�s�J�s�J�̈�N���͏t�ɓ��w�����q�������A���܂ꂽ����̐Ԃ����͂悤�₭��N��Ɉ�ɂȂ�B
���Ȃ��͂��̐M���̏ꍇ�A�O�ڂ͂��������ǂ��̐M���ɂȂ�Ǝv���܂����B
�������������ƍl���A�����ے肷��͕̂s���e�B�ł����������̊����ɌŎ����Ă��܂���ˁB����ˁB
�@�@�@�@�@����{�݂Ƃ́A�u�R�`�L���L�O�فv
�@�@�@�@�@�ɓ������ƕ��сA�����ېV���ɏo�����Ⴂ�̂ɂ�����炸�A�h�B�𐋂����l���B
|
 |
50���Ԃ肭�炢�ɁA���������̋C�����v���X1���������B
������������ɂ́A1��2���̊����������̔N�ȏ�ɋx���Ŕj�̓����������悤�ŁA�����͂₭�����`���[���b�v�̉肪�o�Ă���B
���̊��Ƀt�L�m�g�E�͌�����Ȃ��B
��N5���A�ׂ��Z���}������̂��đ��₵���[���j���[�����A��������8�����ł���ȂɉԂ����A���Ԃ͖��邭�ɂ��₩�B |
���R�̕�炵431�@�@2019.2.6 �@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �A���o���f�W�^�����@���̌�
�A���o���f�W�^�����@���̌�
����͂Ȃ����A�ʓ|�������B
���Ƃ͒W�X�Ǝd�������Ȃ������B�v�����������g���ɂȂ�悢���B
�I�J�V�i���ƂɋC���t�����B
�ʐ^�Ɏc���Ă��鎩�����g���A�܂�Ŏ����̖��̂悤�Ɋ�������悤�ɂȂ��Ă��܂����B
�@�u���炠��A��������i������Ď����ߋ��̎��ɘb�������Ă���̂�j�@�����ł��̑ԓx�͂Ȃ��ł���B
�@�����������ɂ͂���������ǂ��H
�@�����A�悭������I�@����ł��������I�H
�@����������Ƃ�����A�������肵�悤�ˁv�@�Ȃ�ĂˁB
�����A�z�����ǁA�Ⴂ����͂����ƃA�z�������Ȃ��B�Ƃ����̂���Ԃ̊��G���B
���āA������2���f�W�^���ϊ���������A�^�悵�Ă������e�j�X�̎����ł����邩�Ȃ��B
|
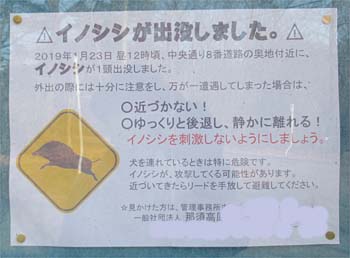 |
�f���ɂ���Ȃ��m�点���\���Ă������B
���x�͊W�Ȃ�����ǁA�Z��n�Ɂu���̂����E���v���o���炵���B
���˖Ґi�̂Ƃ���A�Ђ�����O�֑O�ւƓ˂�����C�m�V�V�B
���̒ʂ蓹�ɌÃ^�C���𗧂Ă����Ă����ƁA���̏ꏊ�������ė��Ȃ��Ȃ�A�ƕ��������Ƃ����邪�A�ǂ�����H |
�@�@�@�@
�@���R�̕�炵430�@�@2019.1.28�@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
 ��匈�S
��匈�S
���̋C�����}�C�i�X�T���B����ȓ��������ƒ�d���͂������ł��Ȃ��B�S���̂��k���܂��Ă��܂��������B���̂����A�ɂ�����ƃ��N�ł��Ȃ����Ƃ��l����B
�����Ŏv���t�������Ƃ�����I
���˂čl���Ă������Ƃ��A���悢����s���邱�Ƃɂ����̂��I
����̓A���o���̃f�W�^�����B
���t�ƃR���p�N�g�J��������́A�B�e����Ƃ��̂܂܌����ɏo���ē\��A�f�W�^���J�������g���悤�ɂȂ��Ă���́A�͂��߂ɑS�����c�u�c�ɏĂ��t���A���̒�����o���̂����ʐ^��I�����ďo�͂��Ă����B
�Ⴂ���납�獡�܂ł̃A���o�����A���܂�ɗ��܂��ĂU�O���ȏ������B���t�g�ɂ����ƁB
�����100���ƌv�Z����ƁA�S�̂�6000���ȏ�̉摜�����邱�ƂɂȂ�B
�c�u�c�̒��ɂ͂���10�{���̎ʐ^�������Ă���B
�c�u�c�ɏĂ����̂́A���̂܂܁u�o�b�ǂݍ��݁@���@�������Ɉړ�����v�ŗǂ����A�A�i���O�ʐ^�͈ꖇ�ꖇ�X�L�������邵���Ȃ��B
�ӂ��`�B
����͂ˁA�j���Ȃ��l���v�[���ɓ���݂����ɁA�v�����Ĕ�э��ނ����Ȃ��̂��B
�A�j���I�@�����I

�ߑO7���B�k�k�����瓌�쓌�̕����ɁA��[���ۂ��Ăւ�̂悤�Ȍ`�����Ă���A���������_�������Ɨ���Ă����B
��s�@�_�ł͂Ȃ��B
�E���獶�ցB����200�x�����ς��Ɂu�������v�ƁA�܂�ʼn����ɉ�����Ă��邩�̂悤�������B
����͒n�k�_���H
�NjL
* �@DVD�̒��̃f�[�^�̓f�W�^���ł͂Ȃ������āH
�����Ȃ̂ł��B�c�u�c�͌��\�����邵�A�d���B������1����4.7GB�Ȃ̂ŁA����e�ʂ̑傫���������Ɉړ������āA�ꊇ�Ǘ����悤�ƍl���܂����B
�z���g�͂ˁA�t�B�������X�L��������̂���������ǁA���̑�ȁA���H�ϑ��ɂ��g���鍕���t�B�����́A���łɒf�̗��������ƂȂ̂ł����B
*�@����̓V���E�}�C�B�F�����̃��[�X�ƃo�����ŃR�c�R�c�荏��Ŏ��Ɛ��̃~���`������A�������������Ⓑ�l�M�A���傤�������ė������@---�@�܂����Ɣ����ł����B
�@�@ �@���R�̕�炵429�@�@2019.1.20�@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
 �����̏��@�@�n�N�`���E�ƃI�i�K�K��
�����̏��@�@�n�N�`���E�ƃI�i�K�K��

�����͓ߐ{�̎R��Ɣ��a�R�n�̊ԂɍL����_�n�̒��قǂɂɂ��锼�c���B
�Ⴂ�u���A�Ȃ�A����������n����ꏊ�ɂ����ēG�������₷���A���a�͂Q�O�O���قǂ��B���[��1���[�g�����炢�Ȃ̂Œ������͋����Đ���a���̂��Ă���B
����͖k�̍����甒����e��̊������A�~�z������̂ɗ��z�I�ȏ����炵���B
�}�C�i�X6���ɂ܂ŋC���������������A�����v�����̂��A��l�Ŕ��������ɏo�����Ă����B
�Ȃɂ����������������Ă���B
��������X��������������������������̂ŁA�s�V�s�V�Ɗ���鉹�������Ă����̂������B
�X�̍L����ɉ����ă}�K�����W�܂��Ă���B
�݂�Ȗk�������H�����ɂȂт��悤�ɂ����܂�@---���ꂱ�������܂肾�B
������ɉz���Ă������߂Ă̓~�A�u�R�[�R�[�v�Ɣ���������тȂ�������ɁA���݂��݂Ɩk�̍��ɏZ�ފ��S���o�������̂������B
�v���Ԃ��Ƃ���͂��������A�ӂ邳�Ƃ𗣂�Ċ�����߈��ɋ߂����̂������悤�ȋC������B
�ߐ{�̓~�ɂ�����Ă����B
�@�@
���R�̕�炵428�@�@2019.1.12�@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �@�@������
�����@�@�@�~������̂͂��܂� �@�@������
�����@�@�@�~������̂͂��܂�
�@
|
 |
����10���ԂƂ������́A�����̗₦���݂��������A�O�C���ς���ƃ}�C�i�X4���������B
������10�Z���`�̍����܂Ő������A���ނƃU�N�U�N���𗧂āA����30���[�g���̓��ɂ̎}��炵�ēߐ{�R���낵�������Ă���B
�G�ؗт̌����ɂ͗��R�̔����i�F���L�����Ă���B
�e���肾�����厖�ȌZ���������A���̐����͕N�ǂ��ĉ߂����Ă����B
�������V�A�H�����V�A�ǂޖ{���V�B
���Ċm�F�O�����V�̊����̕�炵�́A����͂����y���ނ����Ȃ��B
����ȂȂ��A���}�}����匂��������B
���̒��F�̎}���������킷�т̂Ȃ��ɁA���̖����Ԃ牺�����Ă���B
�@�@�E����X�̂�����ɂ����}�}���̕����閚�̂��̐�K�F
�����̒��ɂӂ��킵���A�����ɂ��܂��ĐႪ�����Ă���B
���������̕������H���ώ@�ł��Ȃ��B
�����@
�L�c�c�L�̒��Ԃł͈�ԏ������u�R�Q���v�B�����邵���ڂ����Ă��������B�@ |
�@
�@���R�̕�炵427�@�@2019.1.6�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@
�@ �@�@����ȏt�܂ł��ƕS���@�@ �@�@����ȏt�܂ł��ƕS���@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@*�@���������ƒ��P�̎R�̋P����̋АU�邲�Ƃ��N���炽�܂�
�@
���R�̕�炵426�@�@2019.1.1�@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@ �����̈�i�@�@�@����ݘa��
�����̈�i�@�@�@����ݘa��
�@
|
 |
�@ |
|
�@�t���C�p���ŏ����u���āA���蔫�ŃR���R���B |
�@�����Ƃق���̂���ݘa��
�@�����������Ė쐶�̖��������B
�@ |
|
 |
 |
 |
|
8���B
���߂��߁B
���̉w�̍L��ɃI�j�O���~���Ȃ��Ă���̂��������B |
10���B
�������A�E���Ȃ��O�Ƀo�P�c�������@�@�ďo�������B
���ΐl�𐧂��Ƃ͂��̂��ƁB
�̔���Ċ��������B |
12���B
�n���}�[�Ŋ���ƁA����Ȃ肵���]�̌`������������������Ă���B
�A�C�X�s�b�N�Œ��g�����o���B���ꂪ�ЂƎd���B���X�̓G���C�I |
�@�@�@�@�@�E�@�g�߂���ɂ���Ă����̎Y���ɉԂɂ��Ⴊ�����q�L�����܂�
�@�@
���R�̕�炵425�@�@2018.12.26�@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 ���Â���ɂ���
���Â���ɂ���
���n�j�̑��_�́A�߂����Ƀe���r�h���}���ς邱�Ƃ��Ȃ��B�����炩�A���l�̐l������w�ы�������p���ɖR�����A����܂Łu�䂪�����s���v�p��������Ȃ��ł����B
�i�Ɗ����邱�Ƃ�����B�Ό������ǂˁj
�u���b����v�ƕ��|��i�Ȃǂ͌h�����A�l�Ԃ̊���������������ɓ����Ă����̂��A���邢�͊����̒��g�͉����A�Ƃ��������Ƃ𗝉��������Ȃ��悤�ɂ�
�v����B
�Ƃ��낪�A���̏H�ɕ��f����Ă���w�������P�b�g�x�����͔M�S�ɊςĂ���̂��ʔ����B
�{�����͂������ςĂ��邪�B
����ɕ��f���i���j�̌ߌ�́A��`�p�̉ߋ��̔ԑg�̃_�C�W�F�X�g�ł�\��^��܂ł��Ă����B�_�C�W�F�X�g��������f�������Ȃ�ɂ��������Ă��̎��Ԃ������Ȃ��Ă����B
�P�A�P�{�Q�A�P�{�Q�{�R�A�P�{�Q�{�R�{�S�A�̂悤�ɁB����ł̓t�B�{�i�b�`����̐������т����g��͈͂��傫���Ȃ��Ă���
����Ȃ��H�@�r�[�o�[�̔����ǂ�ǂ�c���ő傫���Ȃ��Ă����݂����ɂˁB
�O��Ȃǂ͂P���Ԕ��̔ԑg�Ɏd�オ���Ă����̂��A��------���ƍ��荞��ł݂Ă����B
�u�������e�ł����R��ڂ���Ȃ��H�v�@�Ȃ�Č���Ȃ�����ǂˁB�@�ԑg�̃|�C���g�́u���̂Â���v�B
����ɐS�䂷�Ԃ���悤���B���s���Ă����܂������Ȃ��Ă�������߂Ȃ��p����A�H��̋Z�p�҂������Q�H��Y��Ď����Ǝ�����d�ˁA�����Ȋ����i��ڎw
���Ă���l�q�Ɂ@--------�i���ɂ��Č��Ȃ��t�������Ă��邪�j���܂ɗ܂𗬂��Ă��邱�Ƃ����邭�炢�Ȃ̂�����B
�h���}���i�W����̂ɂ��������āA�������́A�����č������������Ă���Z�p�҂��܂������h������āA�\�ʂɕ����オ���Ă��Ă���悤���B�@�@�@���ꂪ��
�����������J���C�C�H
|
 |
�e���r�ł͉��s�ɂȂ��Ă��邪�A�ސE�����a���̕ޏꂪ����͓̂Ȗ،��̒����̔_���B
���̖{�̗��\���ɂ́A�L����c�ނ̂ނ����ɓߐ{�A�R�������镗�i���`����Ă���B
�@
�@
�@�i�摜�́A�A�}�]������q���܂����B�j
�@ |
���R�̕�炵424�@�@2018.12.18�@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@ �@�@�@�@ �@�@�@�@
 �@�@���O���̂����ڂ�@�@�@�y���˂̗� �@�@���O���̂����ڂ�@�@�@�y���˂̗�
����O�͖،͂炵�����������̂ɁA��]���ē삩��̕��������Ă����B
����͂��������āu�t��ԁv�Ȃ̂�������Ȃ��B�H�H�H
�H�d������i�����āA�C���͗������C���B�����Ȃ��Ă悢�̂ɁA�i���₻�ꂾ���炱�����j�������肵�Ă��鎩�����������������B�Ƃ��Ƃ�n�R���ɏo���オ���Ă���
�悤���B
�������A�����͈�����B
��̋��́A�ƂĂ��X�R�b�v�������Ȃ��悤�ȍd���n�ʂ̉����A���O�����g���l�����@��i�݁A�]�����y��n�\�ɕ��蓊���Ă���̂��������B
��������B
���̓y�́A�h�{���_�ŕa�C�������Ȃ����z�I�ȓy�B�{�����̓y���g���Ď�d��������Ɛ��ʂ��o�����Ȃ��炢�Ȃ̂�����B
������������ʂ悤�ɂ������Ƌd���ăo�P�c�ɏW�߁A�Ԓd�ɓ���Ă��B
���������ۂ��ӂ�����c��Ԓd�����Ă���Ə����ȒB������������B
�J���Ɏ���ɂȂ炳��Ă����A�t�ɂ͐A�����r�I���̂��߂ɓ����Ă���邾�낤�B
�����A���������āB
�n�̗���������������ǂ����邩�A�ƍl�������Ƃ�����B
�����ƃX�R�b�v�������čs���A�E���đ͔�u��ɏ悹�Ă�邾�낤�ȁB
�o���ɂ͍ŗǂɔ엿������B
 �@ �@ �@�@ �@�@
�@�@
�@���R�̕�炵421�@�@2018.12.5
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �@�����܂�������
�@�����܂�������
�����̓��̌ł����m�F���邽�߂������āA�N�C�Y�ԑg������̂��D���B
�Ȃ��ł����C�ɓ���́u���剤�N�C�Y�v�B�e���|�悭�ԑg���i��ł����̂ŁA�ςĂ��ĐS�n�悢�B
�I�Z����NJ�����32�}�X�̂����ЂƂӂ��������ǂ߂Ȃ����Ƃ����邪�A���Ƃ͂Ȃ�Ƃ��Ȃ�B�i�ǂ߂Ă������Ȃ����ǂˁj���E��Y�̏ꏊ��Ђ�߂������܂��܂��B
�y�Ȃ̑薼�Ă�̂́A�N���V�b�N�Ȃ�Ƃ������A�C���f�B�[�Y��i�|�b�v�X�ƌ������ŋ߂̎Ⴂ�l�����̋Ȃ≉�t�҂̖��O�ȂǕ��������Ƃ��������Ƃ��Ȃ��̂ŁA�܂������肪�o�Ȃ��B�������Ȃ��B
�ʔ����̂���------�@�^�P���u���P�^�̂��̉Ȃ̂��B
������Ƃ���Ă݂悤�I
���̏H�́A����̂����u�ԉƎ��ɁE�ɂ������Ɂv��₵�āA���Ƃ̎��Ԃ͒�d���ɖ�����ꂽ�B
�������ł߂Ȃ��ƃT���_�������ł́u�T���_���i���E�T���_���_���T�v���|���B
�������u�蔲���ł��ʎ�E�Ăʂ��ł��ʂāv�Ȃ̂��B�u�}�}���킪�܂܁v�Ȃ̂��A�Z�������Ƃ������đ��_�Ɓu�ԟ[���܁E�����v���邱�Ƃ�����B
�u����~���āE�Ă����サ���āv����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA������u�e�B�b�V���~���āE�e�B�b�V�������āv�u���āA�ꏏ�ɐH�ׂ悤�B
�u�N�����������v�̐��ɁA�����́u�L�̂��̎q�ˁE�˂��̂��̂��ˁv���V�тɗ����̂��Ǝd���̎���~�߂�B
�u�N�����������������̂������邩��v�@�@�u��`�������āE�Ă��������āv�B�@�ǂ��H
�������������̂����炱�̌ߌ�́u�\�芄���Ă�E��Ă������Ă�v�B
�N�������̕Ԏ��́u�]����E���������������v���ƁB��������ˁB���������u���̒��Ȃ̂�E��̂Ȃ��Ȃ̂�v�ˁB
�F�l�Ɏ����̔��ō���Ă���卪�������B
�����́u�_�ƂŔ����́E�̂����ł����́v�����A�����͔����璼�s�̑卪�ł��łB
�u�g�i�J�C���ȂƁv�U�����������{���������A����ȏH�̈�������������Ƃ��������ȁB
���������A�N���X�}�X�̏���������Ȃ���ˁB
����ɂ��Ă��A�����ɂ��Đl�̖��O���悭�Y���悤�ɂȂ����B�u����������ȁE�Ȃɂ�������ȁv�B
�C�n�̒��Ɍ��݂̒Z���L�����Ղ��Ղ�������ł���݂������B�Ⴂ����́u�C�n��{���E�����ɂ����v�������̂��A�����Ƃ������肵�Ă����悤�Ɏv�����ǁB
���͂́B�����܂��B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���R�̕�炵420�@�@2018.11.28
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@�@
�@�@�@�@�@  �@�@�����R�ɗz�͗����� �@�@�����R�ɗz�͗�����
�@�@�@�@
������~���A�i�c�n�[���C���A�䂸�̂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�i�c�n�[���C���ɂ��Ă͍�N�P�O���Q�X���̋L�^��ǂ�łˁj
����Ȃӂ��Ɍ`�Ɏc��d�������Ă���ƁA������u�ǂ������I�v�ŏI����C������B
�@�@
�I���`�ƌ��n�`�B�@�@�Q�T�O�Ȃ��ł��āA����̂��y�����B
���_�_�Ƃ̋��������߂��̂ŁA�n�G��������Ȃ��悤�ɐ��l�b�g���|���Ă���B
�@
���͉��˂ł��������߂Ȃ��B�@�����`�̂��̃e�N�X�`���[�����ŐH�ׂȂ��B
�Ȃ̂ɉʎ��������A�`���ނ��Ċ����Ă���H�B
�������A�H�̎d���̋ɂ߂��͂���I
���̊ȈՉ��������Ă��������B�D���ł���Ă��邾���ɁA���邽�ъy�V�I�ɂȂꂻ���B
���R��ɂ��Ă���ƁA�Ō�́u�悵�v�ŏI��肻���ȋC������B
�t�̉Ԃ̂Ȃ��ł���ԍD���ȁu�A�C�X�����h�|�s�[�v�̕c��~�z�������邽�߂̊ȈՉ������Z�b�g���āA��N�ɂ�����������ɁA���������_��ł����C������B
�@�@�@�@�@���R�̕�炵419�@�@2018.11.19
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
�@�@�@�@�@  ��̂�����A�t�F�����[���u���[�@�@�V��̐�
��̂�����A�t�F�����[���u���[�@�@�V��̐�
�@
|
 |
�Ȃ������R��������Ȃ��B
���̂R�Z���`���炸�̃��A�C���������āA�䂩���悤�ɔ������߂��͍̂�����40�N���O�̂��Ƃ������B
��āE�G�N�A�h���̎�s�L�g�́A�u�Z���g���v�ƌĂ�鋌�s�X���班���O�ꂽ�ׂ��H�n�̊p�ɂ��y�Y�����������B���̓X�́A����Ē����ǂ������Ȃ��V���[�E�B���h�E�ɏ����Ă������A�C�����A�����Ă悤�ȋC�������̂��B
���ǂ��ǂ����X�y�C����Łu���ꂭ�������v�ƌ����ƁA�X��͂���Ȃ��͔̂���Ȃ����낤�Ƃł������v���Ă����̂��낤�A���ݎ������
���}���Ă��ꂽ�B |
�����͊C�O�ł̕�炵���n�߂�����ŁA�i���͐M�����Ȃ����ƂɁj�܂��E�u�Œl�邱�Ƃ��m�炸�A���̑��͈�ƂS�l�̂Ђƌ��̐H��炢�H�Ƃ���Ȃ�̒l�i�������L��������B
���̏����̉��l�������ł����̂͂���������ƌゾ�����B
�u����̓��s�X���Y���v�̌��������̂������ƋC�Â����̂͂��ꂩ��Q�O�N�قnjo��������B
�u���ꂱ���t�F�����[���u���[�̐F�A���s�X���Y���Ȃ̂��v�B�ƋC�Â���
-----�Ռ��͂����A�����Ă��������Ă���@---�@�m��Ȃ��Ƃ������Ƃ͋��낵���B
���̐�����̖��p�t�E�t�F�����[���͂��̐��Ȃ�����o�����̂��B
|
 |
�I�����_�̃f���E�n�[�O�ɂ���}�E���b�c�n�C�X���p�قŁA�u���^�[�o���̏����i�ʖ�
�^��̎�����̏����j�v�������̂��A������ɓ���Ă���R�O�N��B�ʎ��I���v�Z����s������Ԃ̍\���ƁA�����獷�����őΏۂ��яオ�点���@�����炵���B�u�f���t�g�̒��]�v���E��̕ǂɂ�����A
���́u���^�[�o���̖��v�����̕ǂɏ����Ă����B
�����ɂ͎�����������l�B
��捂̂Ȃ��Ō����t�F�����[���́A��������Ȉ�ۂ�����Ă���B
|
| �@
�M�ɒ���ꂽ���A�C���̎����ɁA�����m�̓��ŏo������̂�31�N��B
�������Ǘ�����l��
�u��A���A�C���ďd���ł��傤�v
�ƌĂт����Ă��ꂽ�B |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
�@
|
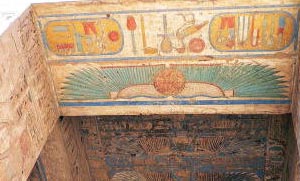 |
�@
�Ñ�G�W�v�g��20���������Z�X3���ɂ���Č������ꂽ�u�����Z�X3�����Փa�v�̓V���B
���̃��s�X���Y���̑N�₩�ȐF���c��B |
�M�u���s�X���Y���iLapis
lazuli�j�v�����ޗ��Ƃ��ĕ`���ꂽ�N�₩�Ȑu�t�F�����[���E�u���[�v�́A�ʂɁu�E���g���}�����v�Ƃ������O�����B
�Y�o���E�A�t�K�j�X�^������C�H�ʼn^�ꂽ�̂Łu�C���z���Ă�����---�E���g���}�����v���ƁB
�Q�O��̏I��肩����--���[���b�p---�A�t���J�ƊC���z���ė������Ă����B
���܁A����I�ɂ���O�̑��ɁA������z���Ă��̗��Ɖߋ��̎��Ԃɏd�Ȃ��Ă���B
�t�F�����[���iJohannes Vermeer/1632-1675�j�́A���[�x���X�A�����u�����g�ƕ��сA17���I�̃I�����_���p���\�����ƁB
���܁A�����E���̐X���p�قœW����J����Ă���B(�@https://www.vermeer.jp/
)
2018�N10������2019�N2��3���܂Ł@�@�@���ł́A���s�����p�ف@�Q�O�P�X�N�Q���P�U������T���P�Q���܂�
(�l�I�ɂ́A�u�f���t�g�̒��]�v����ԍD���B
���������ɍL����\�����̂т₩�ŁA�G�̋�����w�ɂ��h��d�˂������������ʓI�B)
�@�@*�@�����獂�}��͂��݂������āA�F�l�̔��́u�I���`�v��170�����Ă����B
��������ƌ��Ă����̂ŁA��������B
�@�@�@�@�@�ߏ��ɂ������������B����������J�ɔ���Ă����������ԂɎd�グ����ɁB
�@�@�@�@�@10��100������͓̂�����Ԃ�����A�V�u���t�����ˁB
�@�@*�@�ߐ{�̖�͂������������䂭�t�ɖ����ĕ��̂ܗ��͓~�ɂ������
�@ ���R�̕�炵418�@�@2018.11.13
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
 ����܂��B
����܂��B
�G�ؗт̒��̉Ԓd�ɂ悤�₭���������荞��ł����ߑO�X���B
���̏ォ��u�q�b�A�q�b�A�q�b�v�Ƃ��������������Ă����B
�k�̍��������Ă����S�オ�A��œ꒣��錾�����Ă�������������B
��d���̗\��������ɏ���������̂ŁA�C���͂܂��Ƃɑu�₩�B�����͂������H�𖡂킦��̂��������B
�r�I���␅��̒�A�����Ă�����A�Ȃɂ�琶�����̋C�z���������B
�U������Ɩڂ̒[�Ɂu�҂��v�Ɣ�ђ��˂�Ȃɂ�������ł͂Ȃ����B
���{���̎q���������B�����̏o�������I�R���牺��Ă����̂��A�͂���Ă��܂����̂��͂킩��Ȃ��B
�Q�Ă�B�����ǂ��ǂ�����B
�����A�ǂ������̂܂܂����ɂ��܂��悤��------�}���ŃJ����������Ă�����A�Ő��̏�ɂ܂������I
�ʐ^�A�ʐ^���A�Ǝv���Ă݂Ă��A�v��ʏo�����Ɏ肪�k���Ă��܂��B��Ȃ��B
|
 |
�n�[�g�`�̂��K��������Ɍ����āA
���Ă���悤��
���Ă��Ȃ��悤��
�����Ȋp�x�ɓ��点�ė����Ă���B
�@�@(����͂�������x�����Ă��邵�����j�@ |
|
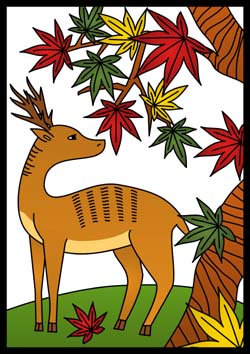 |
�ԎD�̎�
�P�O���̍g�t�Ɏ��̖͗l��
�u���{�\�v�i�����Ƃ��j�B
��������̃V�J�g�͂��̖͗l���炫�Ă���炵���B
|
|
 |
�u�N�͏��̎q�Ȃ̒j�̎q�Ȃ́H�v
�u���g��t�����́H�v
�u������
�C���p�`�B�G���X�̐Ԃ��Ԃ�H�ׂ��̂�B�v |
|
 |
�@
�u���炱��A�����̓`���[���b�v�̋�����A���������v
�u�H�ׂȂ��Łv
�u����A�Ȃ��Ȃ�������������������Ȃ��v
�@ |
|

�@
|
�u���������A�Ԓd���ق������Ȃ��I�v
�u�����ā`�v
�u����A�Ȃ�̓�������B���A���O�����B
���O���ɂ͋����Ȃ��ȁv
 �@ �@
��ΐG�点�Ă���Ȃ��ߏ��̔L�����A�����ƂЂƂȂ���
�@
|
|
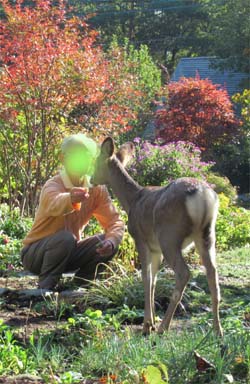 |
�@
�u�����������������v
�@�u�a�Œނ낤��v�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�Ăӂ��ӂ��߂���l�ł����B
�@
�u�ޗǂ̃V�J�͉���H�ׂĂ��邩�Ȃ��v�v
�u������ׂ��Ȃ�Ė����I�v
�u�ʂ��c�q����Ă鎞�Ԃ͖�����v
�u��������������v
�u�E�G�t�@�[�X�͂ǂ����ȁv
�u�킽���A���ɓ����Ă���}�[�K���������v
�u�g�����X���b�_�͐ۂ�Ȃ����Ƃɂ��Ƃɂ��Ă���́v
�u�x�W�^���A���ŁA��������̃i�`�������X�g�Ȃ́v
|
|
 |
�@
�u�ǂ��I
�@�����̕��������Ȃ̂�v |
|
 |
�@
���_�Ɠ�l�A�}���̎d��������Ă��钩�B
�������ɂR�O�����ꏏ�ɗV��ł���ƁA�o�����鎞�Ԃ��C�ɂȂ��Ă����B
�ׂ̕ʑ��̒�ɗU�����悤�ƁA
�u�����������ŁA��������v�Ɛ���������ƁA�����Ƃ��Ă���B
�u�ǂ����痈���́A�A�蓹�͂��������ȁv
�u�ӂ�A��������v�ƁA�V�J�Ƃ��ꂸ�ɕԎ������Ă����B |
|
 |
�@ �@
�@
�����B
�悤�₭�A�邱�Ƃɂ��Ă��ꂽ�悤���B |
|
 |
�@
�k�J�����R�r�������B
�͂��ƐU������ƁA�܂��܂��q�������ė��Ă����I
�����ō��ύX���邱�ƂɁB
���Α��ŁA�ʑ��̐l���L�m�R���͔|���Ă���̂�
�u���������A�������ɂȂ߂���畽�����Ȃ������Ă��B
����������ʂ�ƁA�Ȃ����������̂����邩����`�v
�u���悩�A����ł͂������֍s�����Ƃɂ��邩��ˁB
�@�E�G�t�@�[�X�A�H�ׂȂ��������ǂ����������܁B�v
�u�܂������Łv
�@�@�i�ǂ����A�܂����āj |
�@* �P�T�N�Z�݂Ă��܂��ɒm��ʂ��肯���킪��ɓ��{�����̗���
�@�@�@�@�@���̖����́A�u�q���[�v�Ɓu�s���[�v�����̂��������̂悤�������B
���R�̕�炵417�@�@2018.11.5
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
 ����������@�@�킽�ނ��E�Ȓ��i���^�A�u�����V�ȁj
����������@�@�킽�ނ��E�Ȓ��i���^�A�u�����V�ȁj
�H����̍����A�����̂悤�ɉĒ�̐��������Ă�����ᒎ�����ł����B
������ӂ�ӂ�ƁA----���邩�Ȃ����̕��ɂȂт��A����ɏ���Ăӂ�ӂ���ł���B
���̂����ɁA��Ƃ����Ă����⑫�Ɏ~�܂�ɂ���悤�ɂȂ����B
�ᒎ�͏����Ɏキ�A�l�Ԃ̑̉��ł����V���b�N������قǂȂ̂ŁA��������G�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�P�Z���`�قǂ̑̂ŕ�������āA�����䂢�B
�u�~�̒����v�Ɣo��ɉr�܂�邪�A���N�͂܂��܂����H�Ȃ̂�-----�@���H�Ǝv�������̂ɁB
�~�͉����Ǝv�������̂ɁB
�Ȃ����낤�A�ᒎ������Ȃɑ�������Ă����B
�����̎��`�I�����w�����x�Ƃ�����́A���̐ᒎ������ꂽ���́B
�u��l���̍^�삪�A�Ђ�����������̂�������ɂ����邨�ʂ��k����̌��֗a�����Ă���v�B���ꂪ�����̃e�[�}�B
�q���̍��̂��ƁB
����̎��Ƃ֗V�тɍs�����тɁA�u��i�`���̑c��E�c���̌�ȁj�v�Ɓu�`���̏f��i��̒�̔����j�v�Ƃ̊Ԃɂ���A�q���i���j�������Ă̊m������������Ă����B
��l�̐S�̍s���Ⴂ�������w�����x�̒��Ɍ��Ď���^��̐S����ԂƏd�Ȃ��āA�Ȃ����䂩��鏬���������B
���w���ł͂ƂĂ����e�̔Z����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������͂��Ȃ̂ɁB
��Ɏ���Ă͋`���̖��̎q���ŁA�`���̏f��ɂ͕v�̎o�̖��ł�����킽���B
�c��Əf��́A�߂����ɖK�˂Ă��Ȃ����������̗̕��ɕ�݂������Ƃ��Ă����̂��낤�B
����̑c���͑��̒n�傾�����B�����ɖS���������߂̍ȁi��̎���j�̂��ƁA���X�Ɂu�J���́{�q�����Y�ށv�Ƃ����ΏۂƂ��ĉ��Ȃ�u�����炵���i�����ꍥ���x���܂��c���Ă����̂��j�B
�u��v�́A�ŏI�I�ɑc���ɂ���đI�ꂽ7�Ԗڂ̍Ȃ������炵���B
����Ȕw�i��m�邱�Ƃ��Ȃ��A�u��v�̂ӂƂ���Ŗ��������̂���́A�������̈�����܁A�ԂԂƉ�����������݂������Ă���B
��̃A�I�n�_�̗t���A���͔��������̂ɁA�[���ɂ͂��łɉ��F������������ттĂ���B
���H����ӏH�ցB�@�삯�����B
|
 |
����܂菬�����āA���̃w�{���f�W�J���ł͎B�e�ł��܂���B
�t���[�S�Ȏ��T�w�E�B�L�y�f�B�A�iWikipedia�j�x����摜�����肵�܂����B |
���R�̕�炵416�@�@2018.10.29
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 ���~��炵��A��`���ɗ��Ă���
���~��炵��A��`���ɗ��Ă���
�V�C�\�҂����蓖����A�J�Ŏn�܂��������́A��̎d���͋x�݁B
��������z���č���͎d���𑽂߂ɂ��Ă������b�オ�������B�����͈��y�ȋC�����ʼn߂������Ƃ��ł���B
����̎d���́F
�܂��ẲԂ��A�����̏����ȑ������Ⴊ��Ŏ��B
���������Ԃ́A�u�엿�ɂȂ鑐�v�Ɓu�킪�����ė��N����G���v�ƂɎd�������A�Е��͔͑�u��Ɉړ����ĂP�O�Z���`���炢�ɐ荏�ށB�G���͑��₩�ɑޏo�肤���Ƃɂ���A�ƌ����Ă��߂��̗т̒��ɓ����̂Ă邾�������B
�����͊y����----���낢��Ȃ��Ƃ�----�[�H�̌������l����A���̐l���ĂȂ�����Ȃ��Ƃ�����̂��낤�ƈ�l���Ԙb�A�������������Z�����ǂ��W�J�����邩----�l���Ă���ƁA�o�������Ԃ̕��������͂����ꂢ�ɂȂ�̂ŁA������������B
�������A���̂��Ƃ���ς��B
�Ԓd�ɗL�@�ΊD���T���A�����L�ł������ƍk���Ă����B
�X�p���E�X�p���E�X�p���B
���Y���悭�O�֑O�ւƐi�߂Ă����B�s�v�c�Ȃ��Ƃɂ��̍�Ƃ̊Ԃ͉����l�����Ȃ��B
�g�̂����Y���������āA�ق��̊��o�����ۂ��Ă��邩�̂悤���B
���̂��ƁA�ΊD�������Ɣ������ĉ��w�ω����N�����̂�҂��A�k�����y�ɋ����͔�A�L�@�엿�A�{�����������݁A�P�T�Ԃقǒu���Ă����B
���ꂩ��t�Ԓd�p�̕c��A�����ށB���ꂪ���ꂩ��̎菇�Ȃ̂��B
�d����ǂ�������̂ł͂Ȃ��āA�d���̐��������̂��ւ�����Ȃ��R�c�B
��S�̂��ޖX�q����̂ŁA���̖т̓y�b�`�����R�ɂȂ��Ă��܂��B���߂ĂƁA�X�q�ʼn�����铪�̂Ă�����܂ł̔��̖т��܂Ƃ߂āA�������S���Ō��ь��ɐ��炵�Ă��̂�������X�q���d�˂�B
�X�q����������^�́A�܂�ō��~��炵�̂悤���B
�܂��͖т̐������͓����B
�����B�@�@���ꂽ�����B
|
 |
 |
|
�тɃ^�}�S�^�P���o�Ă����B
���������炵�����B
�f�B�Y�j�[�����h����̉҂݂����B |
���ꂪ��������
�O�{�̒܂��W�܂�ꏊ�ŁA�������ɕt�����y��
�g���g���Ɨ��Ƃ����A�܂�Ńv���ɂȂ����C���ɂȂ�B |
���R�̕�炵415�@�@2018.10.24
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �d���͔����ɂ��ׂ�
�d���͔����ɂ��ׂ�
���H��ۂ�Ȃ��炢��
�u�����́A����Ƃ���B���ꂩ��]�͂������������悤�ˁB�v
���̓��̗\���b�������Ĕ������A�₨��d���Ɏ��|����̂��H�̂��̎����̏K���i�`���j�ɂȂ��Ă���B
�Ƃ��ۂ��Ă��������A�Z������̓�l�Ȃ̂ŁA�]�͂͂Ȃ��Ă��u����v��Еt���悤�Ƃ��ĂւƂւƂɂȂ��Ă��܂��B
�g�t���y���ނ��߂ɁA���܌��ɖڂ̑O�ɂ����ł̘J��������Ă��܂����I�ƌ����ɂ̗͑͂��t���Ă����Ȃ��B
�u����Ƃ���v����u����v�������A���̓������Q�Ŋ���---�`�����ɂ���Ɩ����B�����邱�Ƃ��ł���̂ɁB
�����A�Z�����B---�Z�����鎄�����B
�X���Q�O���Ɏ�������Ă��傤�ǂЂƌ��B��̗₦���݂������Ă�邽�߂ɁA�ȈՉ��������������B
�@�@

|
 |
����`���Ă݂�ƁA
���̂Ƃ���A�r�I�������������B
�s�G�i�E�s�[�`�A
�s�G�i�E���x���_�[�s�R�e�B�A
�X�[�p�[�r�I���E�g�p�[�Y�C�G���[
�\���x�x�s�s�@�̂S��ށB
�ق��ɁA�ʂ��ʂ����Ă���̂́A
�n�C�W�A���[�[�t�A�N�����Ɩ��t����ꂽ�f�[�W�̕c��
�f���t�B�j�E���E�L�����h���u���[�̕c���R�Q�{�B
�A�C�X�����h�|�s�[���P�Q�O�{�B
�S���łS�T�O�{�I
�������H�K�[�f�i�[�ɂ͓K���ɂƂ����l�����͂Ȃ��悤���B |
���R�̕�炵414�@�@2018.10.20
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �قِ��߂Ă悤�₭���ɂȂ�܂���
�قِ��߂Ă悤�₭���ɂȂ�܂���
��������������������Ƃ����B�@�@����ȐF�߂������\���������Ȃ�Ăx�������ɂ��Ă͒�����----�B
���N�T���T���̋L�^�Ɂu�Y����n�v���Ă���}���V�O�T�̘b�������Ă����̂�Y��Ă������A
���̌̂ɉԂ��炢�Ă����炵���B
�Ă��}���悭���Ă݂�ƁA���N�݂͂��Ǝ������l�������炵���āA�ʎ��������Ă���̂������B
�������đ҂��ƂЂƌ��B�摜�ɂ���悤�ɁA�ق�̂�Ԃ��n���Ă����B
�܂��Y���������Đ������A���͂̓�����ƌ�z����`�q���c���B�̂����n���Ă����Ɓi���̏ꍇ�͋��傫���Ȃ邱�Ɓj�����ւƓ]������A�������̃}���V�O�T�B
���悢�q�����c�����߁A�̂̐��n��҂Ƃ������Ԃ��v���O�����ɑg�ݍ���ł��邱�̌����Ɋ��Q����B
�Ƃ����Ă��A���̂܂܂��̐Ԃ��������͂ɐU��܂��Ƃ����肪�}���V�O�T���炯�ɂȂ�̂ŁA�ǂ��������̂��B
�H�ӂ̃����^���B
���̋G�߂ɂ��������Ȃ��A���̕ӂ̒B���̑��`�̔������Ɨ�����Ȃ��B
�@
 �@�@�L�Œ��ӁI �@�@�L�Œ��ӁI
�@�@�@�@���F���̂́@�������|�W���[���@����ɐ����Ă���
�@�@�@�@�@ �E�̃s���N�́@�C���p�`�G���X�@�@�@�@�V�@
���R�̕�炵413�@�@2018.10.14
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@�@�@ �O���Ԃ̎����̂̂��ɁA�n��������
�O���Ԃ̎����̂̂��ɁA�n��������
�̂�т�������߂��������X�͉߂�����A���Ԃ��܂̎O�A�x�Ȃǂǂ����������A�c�����̂͘J���̓��X�������B
�V���o�[�l�ރZ���^�[�ɖ��N�˗����Ă��鐶�_�̙���̓����ɍ��킹�āA���炩���ߎ��������łł�������̙�������Ă����̂��A�P�O�����{�̌��܂�ɂȂ��Ă���B
���H�Ɨ[�H�̒i�����ς܂��A�₨��ق����ނ�����A�₽�����ݕ����������A���̂��̓�������ɂ��āA���̉Ă̏����ƂX���̑�J�Ő������������}��藎�Ƃ�����A�������肷��B
�}�̐�[���w���ɓ����Ă��䂢�A�ɂ��A�����A���Ă���B
�@�@�@�@�@-----�����͂ˁA��s�͌��킸�ɃK���o���B�@�@�����Ȃ��Ə����X�^���ł͂Ȃ��ł����B
�^�[�v�ɐ����}�t���ڂ��āA�ςݏ�܂ł��邸�邸�邸��ƈ��������Ă������_�̗l�q�́A�܂�ő单�l���B���ɗ��Ȃ���Ηǂ����B
���^�[�v��n�ʂɕ~���A�ςݏグ�A�V���o�[�l�ރZ���^�[�̐l�����Ă�������҂�-----���̐����A�䕗�̍s�����C�ɂȂ��Ă����B
���B
�䕗�͈��Ă��ꂽ�B������܂��̍����͘J���т��B
��N���Ă�������v���̋Z�������Ăق�ڂꂷ��B�C���O���b�V���z�[���[��A��Ԓւ肷��͂��݂��ڂɂ��Ƃ܂�ʑ����Ō�������B�Ȃɂ���X�g���[�N�������I
�тɓ����Ă��鉹�������n��̂��̂́A�������̂��́B
��͂����ς�A�������肵���B
����ł��̏H���\���Ɋy���߂�B�@
�@�@*�@�����֗ǂ��m�点���������B
�@�@�@�@�}���قɃ��N�G�X�g���Ă����w�������P�b�g�S�@���^�K���X�x�i�r��ˏ����j�����p�ӂł��܂����ƁB
�@�@�@�@�X�����{�����̖{�����A�V���ɂ��m�点���ڂ������{�ɗ\����A������������U�����ɓ��ꂽ�̂ł���Ȃ�
�@�@�@�@�����ǂ߂�悤���B
|
 |
�����}���^�[�v����B
���̂܂ܑ䕗��������ǂ����悤---�Ǝv���Ă�����V�̏������A�����A�܂�̈���ɂȂ����B
|
|
 |
�Ȃ����A�V���o�[�l�ރZ���^�[�̂���l�ɁA���y�Y�������������B
�d�������肢���Ă���̂ɁA��y�Y���Q�Ƃ́A����͂��������ǂ��������Ƃł��傤�B
�傫���͓̂Ȗؖ��Y�̗��u������v�B
���O�̂Ƃ��荁�肪�����ĉʏ`�������ς��B
���n�ł��M�d�i�B
���a�P�T�Z���`�A��L��������B
����ɂ݂�����������B
���M�͑�D���ȁu�W�m���E�z���C�g�x�b�L�I�v�B
���ӂӁB
���Ԃ��́A�a�̎R�̕����˂Ȃ��`�B
|
���R�̕�炵412�@�@2018.10.6
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �ЂƂ肾�A�ЂƂ肾�I
�ЂƂ肾�A�ЂƂ肾�I
���_�����ɏo���B�@�@�ЂƂ肾�I
��������O����
�@�@ �x���ŗ��
�@�@ �^�����łȂ�
�@�@ ���H�s���R�ŁA
�@�@ �����ȕ�炵�����悤�B�@�@�@
�@
|
 |
�����Ă���ƏE�������Ȃ�̂��R�̕�炵
|
���R�̕�炵412�@�@2018.10.1
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �������ꂽ�o�X�X�g�b�v
�������ꂽ�o�X�X�g�b�v

�u����グ����~�܂��Ă����o�X�v�Ŏv���o�������Ƃ�����B
��㎞��̂��Ƃ������B
�����Ȓ��́A�ɉ؊X�Ƃ��ĂׂȂ��ʂ�ɂ������̂��X�������āA�����X�̒����ɂ���◯���𗘗p���č��Z�����o�X�ʊw�����Ă����B
�m�l���J���Ă��邨�X�͏��ԕ�������A���ׂ̗͗R������X�\���̌���������B���Ă��̘b�ɏo�Ă���o�X��͂��̌���������̑O�ɒu����Ă����̂������B
�~�Ղ̂悤�ȃR���N���[�g��b���������ł߂��̏�Ƀ|�[��������A�u�����́����◯���v�ƋL���ꂽ�������Ŕ��Ђ�����Ɨ����Ă�
��-----����Ȃǂ��ɂ�����i�F�̂Ȃ��B
���Z�������͌����X�Ȃǂɗp��������͂����Ȃ��A�������Ə��~�肷�邾���̍Ό�������----�B
���鎞�m�l���Ђ�߂����I
�u���̃o�X�₪�����̓X�̑O�ɂ���A�q���W�܂��Ă����Ɣɐ������ł͂Ȃ����H�v�@�ƂˁB
�[�d�������G�ɕ`�����悤�Ȓm�l�̒m�b�͂������B
�u�l�m�ꂸ���̃o�X����A�����̓X�̑O�Ɉ��������Ă��悤�B�v
�u�ڗ��Ɨǂ��Ȃ��A���������當�傪�o�邩������Ȃ��B�v
�u�����́A����Ƃ�낤���B�����肶�킶��B���݂͋T�̂��Ƃ����ȁB�悵�B�v
�����͂P�O�Z���`�قǁB�����Ď��̌��͂T�Z���`���炢�B
���܂ɋx�݂̌��������āA���̃o�X��ړ����킪���������̂́A�Ȃ�ƒm�l�����̃A�C�f�A���v�����Ă���P�O�N��̂��ƁB�ړ����������͂Q�O���[�g���قǁB�����`�ȋ������B
�m�l�͂����������@���̂����ƕ����Ă���B
�o�X�������č��E�ɗh�炵�Ȃ��牟���ƁA�o�X��͂Ђ傱�Ђ傱���Ȃ���O�Ɉړ����Ă����B�v���p���K�X�̑����{���x���^�Ԃ悤�ɂƂ������炢����������Ȃ��B
���̕��@�͐̂���傫�ȐȂǂ��^�Ԃ̂ɗ��p����Ă����@----���̃C�[�X�^�[���̃��A�C�����̕��@�ŎR���牺�낵�ĉ^�ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ƃ����������邭�炢������B
�[���Â��ɐ��q���A�����ɂ��Ƃ𐬂��������m�l�̂��X�ɂ́A�n�[�������̓J�����j�̐����J�̉��ɗU����悤�ɁA�o�X����~�肽�w�����������܂��Ă����悤�ɂȂ����B
������ɐ��A�������Ă����B
��F��ł��q�������W�߂�B
�������A���̒m�l�͂��łɂ��̐��̂��̂ł͂Ȃ���������Ȃ��B
�@
|
 |
�@
���A�C��
�v�J�I�ƌĂ��Ԃ�������ɏ悹���Ă��钿�������A�C���B
�o�X�₪�����Ă���悤�Ɍ����Ȃ��H�@�@
�E�E�E�E�@�����Ȃ����B
�@
|
���R�̕�炵411�@�@2018.9.26�@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 ���[�̃t���b�O�X�g�b�v
���[�̃t���b�O�X�g�b�v
�������H�Ȃ̂ł��X�s�[�h���o�������ɂȂ�B����̔������Ȃ̂�����ʂɏł�Ȃ��Ă��悢�̂ɁA���֍s���̂��v���Ԃ�ŁA�����n�C�ɂȂ��Ă���̂�������Ȃ��B
���̎����̔��@������A����͂����ƎR�̕��ɏZ��ł��遛������̒n�����B�����ł��������������A�����̓p�X�B
�X�X�L�̕䂪�o���肾�A���̌������ɗh��ċP���Ă���A�Ȃ�Ɣ������I���ꂱ���n�_�X�X�L���I�R�I�������J���n�߂��ȁA���A�A�P�r���鐶�肾�B
����Ȃ��Ƃ����ڂŌ��Ȃ��璬�ւƑ����Ă����B
�r���̓��[�Ƀ����b�N��S���Ă���l���A���S���[�g���u�����ɗ����Ă���̂���������B����̐l�͒��ւ̔����o���ɁA�R�����ւ́u����҂�200�~�v�̓��A�艷��ւ̂��q�Ȃ̂��낤�A�O�X�܁X�����肵�Ȃ���҂��Ă��镵�͋C���y�������Ȃ̂ŁA����ƕ�����B
�ߐ{���f���H����R�̕����̏Z���ɃT�[�r�X����Ă���̂��A�u�t���b�O�X�g�b�v�v�B�������o�X�₻�̂��̂͐ݒu����Ă�����̂́A���q�͓��܂ŏo�ė����o�X������Ƒ傫�����U��---��������ƃo�X�͎~�܂��Ă����---���~���R�̋��Ȃ̂��B
�t���b�O�X�g�b�v�B���̋����͂����Ȃ��B�������Ă��Ď����̍D���ȏꏊ�ŏ��~��ł���A����Ȋy�������Ƃ͂Ȃ����낤�B
���܂܂ł̐l���ň�Ԃ̃t���b�O�X�g�b�v�́A�R�T�N�O�������B�q���ƎO�l�Łi�܂��܂����_�͗���ԁ��d���j��������ڎw���ĐX�w����o�X�ɏ��A���Ȃ��ނ���Ō�̏�q�ɂȂ��Ă��܂����S�ׂ�����ɏo�Ă����̂�������Ȃ��B
�^�]�肳�A �i�悭�킩��Ȃ����t���������A���Ă������e�����Ȋ�̕\��ŗ����ł����j
�u�ǂ��܂ōs�����A�����܂ő����Ă����悤�v�B
��^�o�X�ŕn�R���s�q�����̌��c�{�݂ɏ�����Ƃ����ґ�𖡂�������̉āB
�@�@�@�@�@�@�i���Ȃ݂ɁA���̎{�݂͑f���܂�ň�l�W�O�O�~�B���܂��ɂ��˂�������Ă��܂����q���ɂ������
�@�@�@�@�@�@�@�u�������炢������A�C��t���čs���Ȃ����ȁv�Ɛ��������Ă����������B�j
����Ȑ̘b������悤�ł́A��������B
������ĕ�炻���B
�@
|
 |
�@
�E�����I�j�O���~�����������Ċ����Ă݂��B
�܂�Ŕ]�̒f�ʂ̂悤���B���̒ʂ�N���~�ɂ̓I���C���_�������Ղ�ӂ��܂�Ă��Ĕ]�̌������悭����炵���B
�S�ςŃA�C�X�s�b�N���Ă��Ă����J���悤�Ƃ��Ă��Ȃ��Ȃ��B
�G�͂��ԂƂ��B
���āA�����͎v�Ă̂��ǂ��낾�B
�P�R�O�̃I�j�O���~�����܁A�Ԃ��l�b�g�̑܂ɓ����ĂԂ�Ԃ�B |
���R�̕�炵410�@�@2018.9.21�@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
 ���߂��ސl�ł�
���߂��ސl�ł�
 �o�q�̃N���~���������B
�o�q�̃N���~���������B
���˂Ėڂ�t���Ă����N���~���E���ɏo�����Ă����B�o�������Ƃ����Ă����߂��̓��̉w�ւ����B
���ɂ������A�ۂ��`��A�ۂ��`��ƊԂ������ė����Ă���B
���̓R���N���[�g�̒ʘH�Ȃ̂ŁA
�u�����A�����āv�ƌ����Ă��邩�̂悤���B���ΐF�̉��قɊ���ڂ�����A�������ȒP�ŏ�����B
���ق͂ӂ�ӂ�Ƃ��Ă��ď_�炩���A�܂�Ŏ�i�j�ʁj�̂�����݂̎肴���B�@�@�i����݂̂�����݂��I�j
�ނ�����Ɨ͂�����ƁA��i�j�ʁj���ʔ����悤�Ɏ��o����B���͂��̎��̍d���B�g���J�`�ɂ��Ȃ铪�̎�����́A���_�̍d������݂��Ă��炨���B���ē~�̊Ԃ̐H�����B�������� ---- ���H�ɗ�ރ��X�Ȃ̂킽���B
�����͏o����̖��ԉʂƁA���c��̔����ŃW��������낤
�y�N���~�ȃN���~���z
�g�̂ɗǂ��I���K3���b�_�A�R�_�������i�|���t�F�m�[���A�����g�j���j�Ȃǂ�L�x�Ɋ܂݁A�r�^�~���A�~�l�����A����ς�����H���@�ۂ������ς��l�܂��Ă���B

���N���߂č͔|�����̂��A���̉`�Ӗ��i�G�S�}�j�B
���̎���������ďW�߁A���������ďݖ��Ђ��ɂ��Ă݂��B
�`�Ӗ��i�G�S�}
�j�̓V�\�Ȃ̈�N���B�V�\�Ƃ͓���̕ώ�B��Òn���ł̓W���E�l���i�\�N�j�ƌĂ�Ă��āA����͐H�ׂ�Ə\�N�������ł���Ƃ�������ꂩ�痈�Ă���B
�����Ȃ̂��B���N�܂ŐH�ב�����ƃ��^�V�A�����g�Z���ɂȂ�邩������Ȃ��B
*�@�؎�������y���钆���ȑO�A���̉`�Ӗ��i�G�S�}�j����������̖��Ƃ��āA���邢�͐H�p�Ƃ��ė��p����Ă����B
�@�@�l�̂ɕs���ȕK�{���b�_�ł��郿-���m�����_���L�x�B�@�i���������j
�@�@
���R�̕�炵409�@�@2018.9.16�@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
�@�@ �@�@���悢��n�܂� �@�@���悢��n�܂�

�퉮���������́A�Ă̂������①�ɂ̈�ԉ��x�̍����Ƃ���i��؎��̉��j�ɂ��܂��Ă����A���
�u�������Ȃ��Ă����Ȃ��v�Ǝv�킹�邱�Ƃɂ��Ă���B
�@�@�@�@�@�i�x���Ŕj------���������Ɩ��荞��ł����ɁA����h����^���Ċ�����Ԃɂ����邱��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̏ꍇ�͗≷�Ǝ��ԁ@�j
�����A��܂𖾂邢���֏o���Ă�����B
���ꂩ�炵���������o����ƁA�������������Ȃ�B�@�͂��̌��t�ł����u�`�F�X�g�I�v���낤���B

�v���X�e�B�b�N�E�g���[�ɔr���p�̌����J���A��d�ɂ��ďd�ˁA���̂������ɗ]���Ȑ����z����鎆��~�����B
��̔���ɂ͓K���i�Q�O���O��j�ƁA�K���Ȏ��x���K�v�����A����ƂĎ��C�����߂���̂��֕��Ȃ̂��B
������ӂ̌��ˍ����́A������Ɠ���B
�Y�݂Ȃ���A�u�܁A����Ȋ������ȁv�ŏH�̎�d��������o�����B
�����A�g���[���J�͗l�̋�ɓ������Ă݂���A���Ɏ������킩��A�Z�������o�Ă��Ă���̂��������B�y�̏�ɐ��������������тꂽ�̂ŁA�����ɂ��炵�Ă��܂������̂悤�ɁA�߂ɂ��傱���ƍ���L���Ă���B
�r�I���̎�͍D�����Ȃ̂ŁA��͎��点���y�̏�ɒu�������ŕ��y�͂��Ȃ��B
�����̒i�K�ł͔���������́A����y�ɂ����点�邱�Ƃ��ł����A�y�̏�ɂ��낤���ď�������Ă��邾���B
�z�c����͂ݏo���Ԃ����̑�����ł��悤�ɁA�����Ă�����ܗk�}�œy�̒��ɏ�����������ł�����B

�T���ɐL�т��V�}��}���肵�ė���ň�ĂĂ����[���j���[���̕c���A�X���ɓ����Ă���Ȃɑ傫���Ȃ��Ă����B
�[���j���[���̑}����Ȃ�܂����āI�@�X�X�����������鎩�M������B
�P�O�N�ȏ�O�ɔ����Ă����ꊔ�̔�����A����܂łQ�O�O�{�ȏ�̕c���̂�A�F�l�m�l�ɕ����Ă������낤���B���ꂱ�����Ă������A���̎�ނ���ԉԕt�����ǂ��ĉ��ɍL����A�����R���p�N�g�ɂȂ�B
������v�����^�[�ɂQ�����A�����݁A�H�̓������̂Ȃ��ő傫�����ĂP�Q���ɉƂ̒��Ɏ�荞�ނƁA�~�̊Ԃ����Ƌ��Ԃ͉Ԑ���
�ɂȂ� ���낤�B
�@
�@���R�̕�炵408�@�@2018.9.11�@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �ۂ����̂́A��������̂�����
�ۂ����̂́A��������̂�����
���̓��͑䕗������Ă��邩������Ȃ��ƕ����A�Ђ܂��̉Ԏ��������ɍs�����͈̂����̂��ƁB
����͉䂪�ƂɂƂ��āA�Ă̏I���̏����Ă��䂢�������Ȃ̂��B
�ق����ނ�����A��ɂ͊��������A��֎Ԃ���������Ȃ��炨���Ƃ蓁�ŋ߂��̓��̉w�̔��ɏo�����Ă����B
�@�@�@�@�i�Q�l�܂łɁG�@�@��֎Ԃ��l�R�ƌĂԂ̂͊��A�֓���킸���Ȃ��B�@�L�͓����҂Ȃ̂��H�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�w���������Ђ܂�蔨�̒����E���������A�Ȃ�ׂ��傫���̂�T���ĕ������A�s�v�c�Ȃ��ƂɁA����ɂ��Ă��邱�̉Ԏ���������Ƃ����Ƒ傫���̂����̔��̒��̂ǂ����ɂ���ł͂Ȃ���-----�Ƃ����v���ɋ���A���ǂ����ł��Ȃ����ƂɋC�Â�����邱�ƂɂȂ�B
����ŁA�����Ƃ������X�g���������邩������Ȃ��A�ƍl���ĉ����܂ő���A���Ǐ��߂Ɍ����̂��ǂ������Ƃ����o��������̂ƈꏏ���B
���̂�����������l�g��������ŁA�ό��q�̎������o�`�o�`�B�h����B���ƒp���������B
�߂Â��Ă���l�ɂ́A
�u���A���̂��B����͂ˁA�~�̊Ԃɖ쒹���ɌĂԂ��߂̐H���ɂ���̂ł���B�v
���킸�����Ȃ̐��������āA�悯���Ȋ��������B
�Ђ܂��̗t�͑傫���A�r�т������Ă���̂ł��䂢�B�I������Ă���B
���̂��Ƃ̍�Ƃ��v���ƋC���d�����A���ӂɗ��āi���܂Ɉ��z��U��܂��Ă����j�쒹����Ԃ��Ƃ��v���Ȃ�̂��́B�@�@
|
 |
�䕗�ɔ����A���O�̌����ɕ��ׂĕ��悯�̃^�[�v���|����B
�ۂ����̂��S�����S�����B
�����E������̂��ƁA�n�߂�O���炱����̓W�g�W�g���Ă���B��������荞��ŗ���ŁA�Ȃ̂�����B
�S����170�������B
�傫���Â炪�~�����ӂ���B
�~�Ƃ̂ӂ���A��A�Ƃ������Ƃ͍��v�l�l�A�ꂩ�H |
|
 |
���g�ɒm�b���܂�肩�˂�̂��A���S�͂Ȃ����n���Ă��Ȃ��̂�
�~�Ղ̉~�����������A��ł��������Ƃ��B�����Ɛ͈̂��E���������ƁA���ɂ����ɍL���Ċ����������̂������B
����Ɠ������@�ŁA�������犣��������B
�w�̔炪�ނ��A�����ɂ��Ȃ�B�Ȃ�̈��ʂ��B
�@
|
�u���N������Ȃ��Ƃ��ł��邩�Ȃ��v�Ƃӂ��蓯���Ɍ��ɂ����B
�ł���Ǝv���ł���B
�ł��Ȃ��Ǝv���ƁA�����������鏬�m���ߐ{�̎R����~��Ă���B
�@�@�E�@�Ђ܂��̎ꂼ���~���������a��ɂĐ��ӁA�Ђ��A�ӂ��A�݂��A��
�@�@�@
���R�̕�炵407�@�@2018.9.6�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@
�@
�@  �@���̑O�̂������� �@���̑O�̂�������
�����A9�����B
������8�����悤�₭���z���Č}����9�����A�ǂ��g�����B�����͎v�Ă̂��ǂ��낾���ǁB
���[����A�̂�т肷��Ȃ̂��Ă��܂������̐S�����ւ���̂��悾�Ǝv���ȁB
�͂āA�S�����ւ���H
�`���b�Ɖ��ڂő��_�����āA���̐S�Ɠ���ւ�����A�P�ɁA
�u�~�j���O���Ă��Ă��[���炩�炭�肨������O���v�@�Ɓ@�u�G�H�Ǐ��̂�ׂ�萸�_�v���������邾���Ȃ��ǁB�o���̈������k���W�܂��ăJ���j���O���Ă��A�����_�Ȃǎ��Ȃ��B
�H�̎�d���A�Ē�̐����A��̙���Ƃ��̏����ɒǂ���9�����A�H���Ŏn�܂����B
�J�̍����͂����Ɓu�������l���Ȃ����v�Ƃ����ǂ����̐_�l�̎v�������Ȃ̂��낤�B�@�i�Q�߉ޕ����H�j
�@�@�@�@���A������藷�̖{�ł��ǂ������B
�@�@�@�@�o���g�O�����o�X�ł܂�낤�B
|
 |
���܂ł��������Ă��āA�����͂���ȗ����v�������B
�o���N�[�o�[�����D���A�J�i�_���C�݂��N���[�Y����B
�X���[�h����A���X�J�֏㗤���A�A���X�J�S���Ŗk�シ��B
��Ԃ̂Ȃ��ŗ[�H���y���݁A
�^���L�[�g�i�Ōy��s�@�ɏ��A�f�i���ɋ߂Â��B
�t�F�A�o���N�X�ŃI�[����������B
�@����Ȗ��A�ǂ��H
�@�@T ����B |
���R�̕�炵406�@�@2018.9.1�@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@�@  �@
��������肳��̂��d���́@�@�n�C�C���`���b�L���@�i
�R�E�`���E�� �I�g�V�u�~�ȁj�@�@�@�@�@ �@
��������肳��̂��d���́@�@�n�C�C���`���b�L���@�i
�R�E�`���E�� �I�g�V�u�~�ȁj�@�@�@�@�@
�Ă̓��킢���悤�₭���������Ă����B
�ό��q�̎p���߂����茸���Ă��āA���̉w�Ŕ����Ă���g�E�����R�V�ɁA����͂���ȊŔ����Ă��Ă����B
�u���悤�Ȃ�A�g�E�����R�V�v�B
���܂��ȁA��`���B
���̊Ŕɂ���3�{����R�O�O�~�̂������Ă��Ă��Ă��܂����B���c����������`���Ă��悯���ɔ��������B
�ق��ɔ�������͉֎q5�{�i100�~�j�g�}�g8�i150�~�j�l�N�^����7�i500�~�j�B�@�����l�オ�肵�Ă����B
�@�@�@�@�@�@
 �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@
�@�@ �@�@
�@�@
�@�@
�R�i���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�~�Y�i���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�N�k�M�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@
�R�i���̃h���O���͏t�Ɏ����̏H�ɏn���B
�N�k�M�̃h���O���͏t�Ɏ��A���̏H�ɂ��́u�ǂ�܂Ȃ��v�̃h���O���Ɏp��ς���B
�R�i���͂���Ȃ肵������Ă�ځB�@�@�N�k�M�͂܂�ۂ�������肳��B
 �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@
�Ă̏I���̂��̋G�߂ɂ́A���т̒��̓��H�Ƀu�i�Ȃ̎��̏��}���͂�͂�Ɨ����Ă��āA�n�ʂ�A�X�t�@���g�������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����B
���}���~��ς��������i�͉���ۂ߂��āA���N������Ă���Ƃ͂������̂̋����B
����� �u��������肳��v �̎d���B�@�@�i�u�n�C�C���`���b�L���@�R�E�`���E�� �I�g�V�u�~�ȁj �j�@
�@�@��@�̂ڂ�̂ڂ�A��̖�
�@�@�@�@�@�@�o��̂ڂ�A���ʂ��̖�
�@�@�@�@�@�@�@�@�Ă���ڎw���ā@�������ق���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�q���ɉh�A���ǂ��͕@�@��
�Ɛ����|�������Ă��邩�ǂ����B
�̒�8�~���O��Ƃ������̏������n�C�C���`���b�L�����A�n�ʂ��獂��15���[�g���̑�������o��A����Ɏ}��܂łЂ�����
���ǂ蒅�����Ƃ��Ă���B
�l�Ԃɂ��Ƃ���A�䂪�Ƃ�������ēߐ{�R�ɓo��悤�Ȃ��̂��낤�B
�ڂ�ῂނ悤�ȍ��݂ɓ��B�����I�X�ƃ��X�́A�͂��o���Ă��������Ȃ�̂��́A�܂��n�������Ă��Ȃ��h���O�����t���Ă���}��ŁA�₨��d���Ɏ��|����B
�I�X�̓��X�̍����x���g�̂��m�ۂ��A���X�̓h���O���ɗ����Y�ݕt���A�����ƌĂ��̂�����l�̌����g���āA�ʐ^�̂悤�ɏ��}��藎�Ƃ��B
�ǂ�̒��śz�����c���́A���g��H�O�ɔ����o�Ă��������y�̒��ɂ����肱��--�B�@
���ꂪ �ނ�̍��Ȃ̂��B�����A���܂��y�̏�ɗ����܂��悤�ɁB
���ƈꂩ��������ƁA����̃h���O�����n���ė����Ă��邾�낤�B
�����̏�ɗ����鉹�͂܂�ŗ����܂��\��Ă���݂��Ȃ̂��B�@�@�o���o���o���ƁB
��������ƁA�n�ʂ̏�ɗ������h���O���ɂ́A�n�C�C���`���b�L��������傫���u�]�E���V�v�������Ă����B
�n��ɗ������h���O���ɂ́A�҂����˂Ă����]�E���V�������Y�ݕt����̂��B
�]�E���V�Ɠ����ẮA�g�̂̏������n�C�C���`���b�L���ɏ����ڂ͂Ȃ��B
�n�C�C���`���b�L����
�����͂Ȃ炶�Ƃ܂��̏�ɂ���h���O���ɗ����Y�ݕt���A�]�E���V���������ɐB�������s�Ɉڂ��A�����̎q�����c�����Ƃ��Ă���̂�
�B
�����Ɠ������̂��́B�@�@���ΐl�𐧂��B�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@
�Ƃ��낪�A���������͎̂��̂ق��������B
���N���Ɉ�x�A�܂������ƌ����Ă����قǃh���O����t���Ȃ��N������B
�`���b�L�������]�E���V�����Ƀt�F�C���g�������A�ނ�̍U�������킷�B�@----�]�E���V�B�͔ɐB��킪�������ɋ����B
�A���̒m�b�������̒m�b���A�v�肪�������̂�����B�@�@�@�@�@
���R�̕�炵405�@�@2018.8.30�@�@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �@
���� ���悤�� �@
���� ���悤��
���X�̗����ɂ͐V���������g�������̂ŁA�t���C�Ȃǂ̗g����������̂ɂ́A�[���t���C�p����3�Z���`�قǖ������Ďg�����Ƃ������B
�g�̂̂��߂ɁA�c�������͍ė��p�����A����̐����ݗp�̑傫�Ȍ��Ɏ̂ĂĂ���@----�@�I���[�u�I�C�����A�L���m�[���I�C����
�A���ׂĐA������ł��Ă���̂�����A�n�ʂɖ��߂�Ƃ��̂܂��R�Ɋ҂��Ă���邾�낤�ƍl���āB
���͓����̍��ɉ��������A�����߂ŗg���Ă݂��B
�����A�����̂悤�Ƀt���C�p���Ɏc�����������ɂ������Ɨ�������A�Ȃɂ�炲�������������̂��ڂɓ������B
���h�Ȋp���������J�u�g���V�������B�@�@
���炠��A���߂�ˁB�ł��������Ă����̂��낤�B
��̎G����ς�ł���͔�u����̂Ȃ��ɁA�B��悤�Ƃ��Ă����̂�������Ȃ��B
�L�[�E�B�̔�Ɏc�����ʓ����r�߂Ƃ��Ă����̂�������Ȃ��B
�ォ�����������ꂽ�J�u�g���V�́A�u�����i�f�j�v��������ɕϐg���Ă��܂����B�@�����������C�̓łȂ��B
�{�����J�u�g���V�́A�p��U�肽�ĂȂ���̂��̂��Ƒ͔�̂Ȃ��ɐ��荞�����Ƃ��Ă���B
��␊���������n�߂��Ă̓��������z�ɗ��тȂ���A�����܂̒��ɂ���ȉ��y�������---�B
�@�@�@�@��@�N�b�J���b�`���@
�@�@�@�@�@�@�@�N�b�J���b�`���@��@�@�@�@�iLa cucaracha ) �@�@���L�V�R���w
�@
|
La
cucaracha, la cucaracha
Ya no puede caminar
Porque le falta
Porque no tiene
La patica principal
La cucaracha contenta
Tiene ganas sin parar
Aunque le falta una pata
Nunca deja de bailar |
�S�L����@�S�L����
���������Ȃ���
�����đO��������Ȃ���
������厖�ȑO����
������
�S�L����@��������
�~�܂�C�Ȃ�Ė�����
���Ƃ��O������{����Ȃ�������
�x�邱�Ƃ͂�߂Ȃ��ˁA��� |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
|

|
�����̓v���[���I�����c�B
���̏�ɃP�`���b�v���������B
�̂ł͂Ȃ��āA���̐Ԃ��̂́A�S�[���̎�B
���F���n���Ă���ƁA�S�[���͐悪�O�Ɋ���A������Ԃ�����̂�������B�B
��͊Â��Ă��������炵�����A������ƂˁB
|
|
 |
�ԂȂ���ŁB
�בg�́Z�䂳��́A�q�R�[�L���B
���������A�V���肷����ɂ́A�������Ԃ���s�@����Ԃ̂�������B
���ꂽ���ɂ́A���x�m�R��֒�R��������炵���B
�����A�ǂ�ȕ��i��������̂��낤�B |
���R�̕�炵404�@�@2018.8.25�@�@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@ �@�@������ �@�@������
�����Ղ́A�ߐ{�ݏZ�̓�Ė����y�퉉�t�ƁA���R���q���ďC�������O�̓�Ė������y�����D����O���[�v���Q������ẴC�x���g�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���R����@���@https://www.pentagrama.jp/�@��
��Ă̖����y��̃P�[�i�A�`�������S�A�T���|�[�j���A�M�^�[�A����Ƀp���O�A�C�̊y��A���p�̉��t�▯�����x����I���ꂽ�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2018�N8��18��
�摜�́u�R���h���͔��ł����v�𑍐�50�l�ō��t���Ă���l�q�B
�A���f�X�̋�𗬂�镗�ɓ͂��悤�ɁA�S�����߂ĉ��t���Ă���F����̊�́A�������}����ꂽ��тɈ��Ă���悤�������B
���̓��́A   
�R���h���͔��ł����̍������t
��������ȁu�ԍՂ�v
�A���[���`�����x�@�i���X�E�p�j���G���[�g�X�j ���y�ƃ_���X�͐�Ȃ�����������
�G�N�A�h���A�R�����r�A�̃��Y���A�o�C���V�[�g�̃_���X
�M�^�[�ƃT���|�[�j���̍��t
�J�z���ƌĂ��呾�ۂ̉�������
�A���p�̉��t�i�M�^�[�A�T���|�[�j���A�x�[�X�A�p�[�J�b�V�������]���āj
�@�@  
��ẴA���f�X�̒��̊X�i�L�g�A�W��2850���j��3�N�قǏZ�̂͂���35�N���O�ɂȂ�B
�Z�p�w���ɕ������v�ɑѓ��������́A�܂������V�������t���K�����邽�ߑ�w�̌�w�u���֒ʂ��A�q��Ă����A�ߗׂ̍��𗷂��ĕ����A�A���f�X�̔����R�߂ɏT�����Ɓu�l��E8000�����v�̎Ԃ�����č��������������̂������B
�g�̂̐c���特���o���@---�@��C���ς��B
��C�ɎႢ����̐S���S���Ă��āA�N�ɂ�������Ȃ��悤�ɗ܂��ʂ������@---�@����Ȍߌゾ�����B
�@
|
 |
���{�ł͐����Ȃ��A���p�t�ҁA�����F�I����B
�ׂ₩�ɁA���ɂ��ł₩�ɁA�����Č��������������炷�B�A���p�iarpa�j�Ƃ́A�X�y�C����Ńn�[�v���w���B
���[���b�p�̃n�[�v����đ嗤�Ɏ������܂�A�e���̉��y�ƌ݂��ɉe���������A�Ǝ��̔��W���Ƃ����B
�ޏ������Ă���ߑ��́A�p���O�A�C���[�X�B
��Ẵp���O�A�C�ɓ`���A�J���t���ő@�ׂȎ�d���ɂ�郌�[�X�ŁA���n�ł́u�j�����h�D�e�B�v�ƌĂ�Ă���B
�u�j�����h�D�e�B�v�Ƃ́A�p���O�A�C�̐�Z�����E�O�A���j�[���̌��t�Łg�w偂̑��h�̈Ӗ��B
���̒ʂ�A�J�������������玞���藬�ꍞ�ޕ��ɂ������ĂЂ�߂��h��邳�܂́A�܂�ʼn��ɗ��݂��������w�
�̂悤���B
���̃A���p�A��ɑt�҂̌��Ɋ�肩�������܂܁A���t�����B |
�@�@
���R�̕�炵40�R�@�@2018.8.21�@�@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
�@�@ �@�Ђ����� �@�Ђ�����
���Ⴊ�ݍ���ő������n�߂�ƁA�������܂ԁ`��Ɖ��𗧂ĂĂ���Ă���̂̓A�V�i�K�o�`�B���ɂ̓X�Y���o�`�Ƃ����A���ɂ����낵�����G���y�����Ă���B
�I�͉����Ȃ���������щ��A�H��������ł�������ł����ƕ������Ă����B�y�������y�Ȃ̂��낤�A�I�Ɏ���ẮB
����Ȏ��킽���͂ǂ��ӂ�܂�����悢�̂ł��傤�B
�P�j �G�ӂ܂�܂�A����U��܂킵�A������Њd����---����a�s�̎��ɂӂ��킵���B
�Q�j ��---���ƁA�Ȃ�ׂ��������ɐɂȂ�B
�I�ƌ��܂ł���킯���Ȃ��B���̏ꍇ�͐�ɓ������A�G�ӂ������Ȃ����Ƃ���Ȃ̂��B
���̂��Ńu���u���A���܂ɂ͖X�q�Ɏ~�܂����X�Y���o�`���J���J���ƕz���Ђ����������Ă���̂́A��������H�悤�ȋ��낵�����B
�@�@�@�u���łȁ@�I��������葫������v�@���Ă��̂��Ƃ��B�@�łĂ܂����A�|���āB
�@
|
 |
�@�@�Ȃ�ł�Ȃ���B�i��B�j
�@�@�܂��܂��Ⴄ�H�i���j
�@�@�������ƁI�i�������j
�@�@�Ȃ����ˁB�@�i�V���j
�@�@�������`�B�@�i�Ȗj
�@�@�Ȃ�Ȃ����B�i����j
�@
|
�@�Ă��ĂĂł������B�@�@�i�������j
�@����Ă������B�@�@�i�a�̎R�j
�@�ׂɂ�����ˁB�@�i��ҁj
�@ Honey Trap �ɂ����肽���B�@�i�H�j
�@ ������-���Ɓ@�@�@�i����j
�@Happy�@�̂��낢��ł����B
|
���N�̌o������A�I�����ŗ�����G
�P�j�@�Ђ�����ɂȂ�@---�@�����Ȃ��ŁA
�Q�j�@������肵�Ⴊ�ݍ���ŁA�Ȃ�ׂ��������Ȃ�B
��щ��I�́A�Q��̐敺�E�땺�B�@�����͉������z�Ȃ̂��ǂ������A�m���߂ɂ��Ă��邾��������B
�R�j�@�Ԉ���Ă���ŕ����̂�����A�U�����d�|�����肵�Ȃ����ƁB
�S�j�@�I���l�Ԃ̑��݂ɔ[�������炨�ƂȂ����Ȃ�B
�@�@�@���������v����Ă������I�̎��E�����������B
�T�j�@������l���āA���Ǝ����邱�ƁB���̂��߂Ƀ^�I����X�q�͕K���i�B
�������ɖI�͏W�܂��Ă��₷���A�Ȃ����Đ̂���I�̖��𓐂ނ̂͌F�ƌ��܂��Ă��邩��B
������������͂��Ȃ킿�F�̐e�ʁB
�@�@�@�@�@���݂��l�ԁ@---�@�Ȃ�Όx�����Ȃ�Ƃ�������悤�ƖI�͍l����B
�F�Ŏv���o�����B���N�̉Ă͏Z��n�ɌF���o�ł����b���Ȃ��B
���낻��g�E�����R�V��T�c�}�C���̎��n�����Ȃ̂ɁB
�ĂɂȂ�܂ŎR�ɉa������ɂ������̂�������Ȃ��B
�@�@�@�@�@���R�̕�炵402�@�@2018.8.18 �@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �t�^�����A�V�i�K�o�`
�t�^�����A�V�i�K�o�`
�Ƃ��ǂ��O���V�C�\�A����͂������蓖�������B
�u�䕗��߁A�����ƋC��������オ��܂��B�v
���肪�������_�����B�@�@
����Ȃɏ����ɋꂵ�މĂȂ̂ɁA�܂��ʂ���݂͑����́H
�@
|

|
 |
|
�@�@�蕪������ |
�@�~���ɋ߂��Z�p�` |
���ƂƂ��̉J�̂��ƁA���O�̑傫�ȗt�ɂ������Ă���I�̑����������B
�t�^�����A�V�i�K�o�`��3�C�A��肩���̑��Ɏ����āA�킫�ڂ��ӂ炸��Ƃɗ]�O���Ȃ��B
�Z�p�`�̕����ɂ͉��F����тт��W������Ă��āA���ɂ͂��łɗc�����Y�ݕt�����Ă����B
�t�^�����͓�䂩�炫�Ă���B�|���ċ߂Â��Ȃ��̂Ŋm�F�ł��Ȃ����A�����ɉ��F�����䂪�Q���邩��Ɛ}�ӂɂ������B�M�B�Ȗk�ł͂��̖I���u�k�J�o�`�v�ƌĂԂ炵���B
�k�J�Ƃ͂ʂ���сH�z�H�G�o�̐悪������ƃJ�[�����Ă���̂������Ȃ̂ŁA��͂�u�z�E�k�J�v�Ȃ̂��ȁB
��̋��Ȃ�Ƃ������A�l�̏o���肪�������@---�@�Ƃ����Ă��������̓�l�����@---�@�����H�ɉ����Ă���̂ł���͑ގ����Ȃ��Ă͂����Ȃ����낤�B
�@�@�@�I��A�\����Ȃ��B����Ȍ������Ȃ͕̂������Ă���B
����ĕԂ��A���}��̃Z�b�g��g�ݗ��āA�����邨���鑃�������Ă���t�ɃA�[����L���āA�p�`���B
�������B���̋�����2���[�g���قǁB�ł��|���v��������ɂ͏\���ȒZ�����낤�B���낽�����I���ǂ����������ɏo�邩�͂킩��Ȃ��A����炭���B��ڎU�ɓ���������B
�����Ԍ�A�C�ɂȂ��Č��ɍs���ƁA�n�ʂɗ��������ɂ͋a���W�܂��āA�����̒��̗c����H�ׂĂ����B
��閾���A���̕����͊W��H���j���Ă��ʂ��̊k�ŁA�Z�p��������ł�����肾�����B
����ɍ����B
���ނ͂�������U����Ă��āA�Ԓd�̔엿�ƂȂ��Ă��܂��Ă����B
�ŏ��̎��ނōő�̌��ʂރn�j�J���\���̑�����������̂́A�S�Ȃ��l�Ԃɓ��݂ɂ����Ă��܂����I�́A
���̏ꏊ�ł̑������A�������肠����߂Ă��܂����悤���B�I�̗c���͋a�̐H���ɂȂ�A���ނ͔엿�ƂȂ�B
�Ă�搉̂��Ă����Z�~���A�W�W�W�Ɖ��𗧂Ă����ނ����܂ɗ�����ƁA�����������������W�܂��Ă��ď������Ă����B
�w偂̎q�������Ă���܂���������j��ƁA�u�w偂̎q���U�炷�悤�Ɂv�@�w偂̎q�������܂ǂ��B
�J�}�L���̎q���z�������̉���������Ȃ��B5�~���قǂ̊���U�肩�����ĈЊd���Ă���B
�R�I���M��L���M���X�͂܂��܂��������đ̒�1�Z���`�قǁB�@�Ő�������ƍ��E�ɒ��ˉ��B
�āB�@���̂������ӂ��B
�@�@ ���R�̕�炵401�@�@2018.8.14 �@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@  ���i��
���i��
����͑䕗13���ɔ����A�ߍ݂̈���ʎ��_�Ƃ̐l�B���A�^���ÂɂȂ�܂őΉ��ɒǂ��Ă��鉹���A�x���܂ŕ������Ă��Ă����B���̓w�͕͂��ꂽ�悤���B�䕗�͓��̊C�ւƈ��Ă������B
����ŊF����Ђƈ��S�������낤�ƁA�_�Əo�g�̎������l���Ȃ��狹�ʼn��낵�����������B
���̉����Ă���ƁA�q���̂���삪�×����A�䂪�Ƃ̓c��ڂ������������̉��Ƃ������Ȃ��v������݂������Ă���B
���ɕ����Ԉ�̕c���A���܂ɂ������ꂻ���ɂȂ�---�����ʔ������Ō��ɗ���₩������āA�q���S�ɂ���邹�Ȃ������������v���������B
���āA�ǂ����J�͂����܂����炵���B
���N�����āA�u���[�x���[�̎��n������Ƃ��悤�B
|
 |
�q�}�����@�������@
�@�i�w���́@Helianthus annuus�@�L�N��
�@�@�@�@Heli�v�Ƃ́u���z�́v�̈Ӗ��j
���O�̒ʂ�A�����l�����߂ĉ��A�����ƐM����l���������A���͉��Ȃ��B
�c�c�̎����ɂ́A���������Ȃ�ׂ��悤�Ɣw�L�т�����
���L�����肷�邪�A�炭�����ɂȂ�ƉԎ�́@
�@�@�@�i��قǕς��҂łȂ�����j
����Ԃ̌��𗁂т邽�߂������āA�K�����������B
�Ԍs�̏㕔�̗t�́A���z�ɐ������z�̓�����ǂ����Ƃ��炱�̌�������܂ꂽ�̂�������Ȃ��B
���������̖��H�ɓ����ĕ��p�ɖ�������A�Ԏ�̌������������A�Ǝv���o�����B |
|
 |
���ȂȂ�������ɂ��ł���B
�Ƃ����킯�ł��Ȃ��āA�킪�n���Ă�����A
��I��J������邽�߂�---�@���Ȃ����B
�����܂̏d�݂��ϓ��Ɏ邽�߁A�s���˂���Ȃ���B
���p�ɐ܂��ƁA�܂�ŃX�g���[��܂����悤�Ɍs���f�Ă��܂��B�����ŃX�g���[�̎֕������̂悤�ɔP��Ȃ��炤�Ȃ����B
�����I���̎p�������ƁA��������ߎ��V�W���E�J����J�����q���̍U�������킷���Ƃ��ł��� �悤���B��́A����ꂽ�ʐςɂȂ�ׂ������̎�����点�邽�߂ɁA�t�B�{�i�b�`���̂��̂̕��ѕ������Ă���B�݂��ƂȎ��R�̒m�b���B |
|
 �@�@�@ �@�@�@ �@ �@
�@�@���i�V�W���E�J���j�@�E�i�J�����q���j |
 ���̉Ẵu���[�x���[�̂���A���悢��s�[�N���߂����B ���̉Ẵu���[�x���[�̂���A���悢��s�[�N���߂����B
�����͕�������̔������z���̂ڂ�O�ɁA�u�b�V����ɂȂ����Ɏ����Ċ��𗬂����B
�������肷��ƁA�܂��n���Ă��Ȃ������܂ŗ��Ƃ��Ă��܂��̂ŁA�C��t���Ă͂���B����͂�|���|�����Ƃ��Ă��܂��B�������Ȃ��ȁB���������́A�E�T�M�ɂ����邱�Ƃɂ��悤�B�����̎��n�́A��R�L���ŁA����̗ʂƂ��Ă͍ő傾�����B�����ō��N�̎��n�ʂ͂R�R�L���ɂȂ����B
�Ⓚ�ɂ͖��t�B�q���M��H�ׂ��I�I�J�~�݂����Ƀp���p�����B
��������̎��n�͂���Ԃ����������ɂ��悤�B
���R�̕�炵400�@�@2018.8.9 �@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
 ���키���̂܂�
���키���̂܂�
�@
|
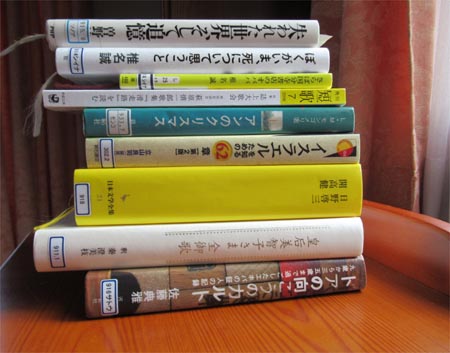 |
�Q���]�����āA
���������ƉE�ɉƁA
�T�C�h�e�[�u���ɒu���Ă���{��
�ڂɓ���悤�ɁA���ׂĒu���Ă����B
���ӂ��ӁB
���������Ċ������B
���A�������B
���쐫���ʂ߂܂��ǂ������������B
���ɉE���Ɏア���ˁB
|
�ߑO5�����Ɂi���܂��܂ȁj��ƊJ�n�B
���H�̂��Ƃ͗[���܂ŏ���C�܂܂Ȏ��Ԃł͂�����̂́A�Ǝ��ɂ͏I��肪�Ȃ��B
�ЂƂ肿�傱�܂��Ƒ�����B�@�����Ȃ��B
���H��A�������ɂ߂邽�߂Ƀx�b�h�ɂ����Ɖ��ɂȂ����A�����̂��Ƃ����ǁB
�J�[�e���͈����Ă��邵�N�����Ă��Ȃ���ˁB�@�����A�Ɋy�Ɋy�B
�c�����땃�����Q�̑O�ɁA
�u�Q����y�͂Ȃ��肯��B �����̔n���͋N���ē����v�ƁA����������Ȃ��炤���Ԃ��Ă����̂��v���o���B
�����́u�Ȃ����҂݂����ł��₾���v�Ǝv���Ă�������ǁA�����̕��̔N����Ƃ��ɉ߂��āA���̎v�����\��������قǗ����ł���悤�ɂȂ����B�@���̃Z���t�́@----�@
�������s�s�킾�����悤���B�@
�֑��F
�@�@ ���̓s�s��̂��Ƃ́u���݂̂₱�̂܂�܂ŁA�q���E�^�����������Łv�������B
�@�@ ���������ς�s�s�킩�A�@���邢�͒��Q�̑O�̎����������̂��B
�T�C�h�e�[�u���ɖ{��ςݏグ�āA���ڂŐς{�߂邱�Ƃɂ��悤�B�����ς������āA�K�����B
�H�����V�ǂޖ{���V�A�̉Ă̌ߌ�͂��ꂩ��B�₨��ǂꂩ����Ɏ���ēǂݎn�߂邪�A�ӂ������Ɩ��C�������Ă���B
�����ƑO���͕z�c�������̂��A�킽���B�@�z�c�ɂ���܂�Ă���ƁA�ӂ�ӂ킵���_�ɕ�����Ă���悤���B
��x�݂��Ă���x�b�h�ɍ������A�v���Ԃ�ɒŖ����̏��a�y���̂���g�����w������������X�̃I�o�o�x�ŃN�X�N�X���A�ŋߍ�́w�ڂ������܁A���ɂ��Ďv�����Ɓx�ŁA���낢��ȍ��̑����̌`�Ԃɂ��Ēm��@---�@
���V���ǂ��s�����́A���̍��̏@���⎩�R�̂��肩���@---�@�����ςŕς���Ă���B�l�X�̕�炵�̔w�i�𗝉����邱�Ƃ���Ȃ̂��낤�B
�Z�̂ɂ��Ă̎G�����p���p���B
���ōc�@���܂̌�̏W�ɖڂ�ʂ��B���A����Ȏp���œǂ�ł��Ă͂����Ȃ���������Ȃ��B�̂Ȃ�s�h�߂��ȁB
�@������݂Łw�C�X���G���x��ǂށB�@����m�炸���ė��j�𗝉����邱�Ƃ͓���B
���́w�h�A�̌����̃J���g�x�G�z�o�̏ؐl�ɐ��]���ꂽ�Ƒ��̕���B�ǂ�����Đ��]���甲���o�����A���̕��������������ڂ��������Ăق��������B
���M����Ƃ���܂ł͗����ł��邪�A�������甲���o���̂ɂ͂ǂ������w�͂��Ȃ��ꂽ�̂���m�肽���B
�@���������Ȃ���X�ɂ͗����ł��Ȃ����_�������B
�@�������Ƃ������Ƃ́A�l����L���ɐ����邱�ƂɌq����͂��Ȃ̂ɁB
�w����ꂽ���E�A�����Ēlj��x�@�@�]�숻�q�ƉƑ����A�}���ƃA�X�e�J�̈�Ղ𗷂��邨�b�B
�B�ӂ̕��͂Ɏ䂩���B
���L�V�R�ɂ�3���A���ɂ��̖{�ɏo�Ă����Ղւ͑��_���c���Ă̂ЂƂ藷����������A�������ЂƂ����B
�Ō�Ɏc�����̂́w�c���ǁx�B
�c��̐��オ�V���Ă䂭�B��ÁA���Ȃǂ̑��������Ă���{�B�ǂނ̂����낵���B
���k�J�ǂ��Č����Ă��A��������Ă͒�d�����ł��₵�Ȃ��B
�Ђ�����}���ق̖{��ǂ���8���̂͂��܂�B
�ڍՁi���������j�F
�ځi�J���E�\�j�ɂ͕߂炦�������݂ɕ��ׂ�K��������B���ꂪ�܂�ō��J���s���悤�Ɍ����邱�Ƃ���A�Q�l���������L�����炷���������炵���B
���łɁB���{�J���E�\�͐�ł����炵�����A���m�J���E�\�͊e�n�̐����قł��܂��܂Ȍ|�������Ă���Ă���B�ƂĂ������������B
�ڍՁF
���{���u�ڍՁv�̑����E��������А����́A���]�����������̖��O�ł�����B
�@�@�@�@< https://www.asahishuzo.ne.jp
>
����7���̐����{���J�ő傫�Ȕ�Q�������A���ݍċ��������炵���B
�@�@�@�@�@�@���R�̕�炵399�@�@2018.8.5�@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@�@�@
 �@ ���g���ȁH�@���a�̕������A�u�����ڑ��v
�@ ���g���ȁH�@���a�̕������A�u�����ڑ��v
����͂��̂��Ƃ������̂��낤�B
2�w�����n�܂��Ă�������������ǁA�n�Ǝ��ł͂Ȃ���������A�����炭9��2�T�ڂ̑S�Z�W��ł̍s���������悤�Ɏv���B
�搶�̍��}�����������ɁA�S�w�N����I�o���ꂽ�j��12�l�̑�\���d��ɃY�����ƕ���ł���B
�������ȁB�@�p���������B�@������䂢�B�@���ӂ��ȁB�@���܂舫���B��C�����B�@�����䂢�B�@�ǂ����ɓ����o�������B�������܂�Ȃ��B�@�Ƃꂭ����-----�B�@
���Ă��鎩�����g�A���̎q�����̎v����������邱�Ƃ��ł����̂��ǂ����A���ƂȂ��Ă͎v���o���Ȃ����A�u�Ȃ�ƂȂ��݂�ȁA�S���h��Ă���ȁv�Ƃ������Ƃ͕��������B
�����������v����āA�搶������������B
�u�����Ă݂�ȁB�w���������Ă����悤�B�v
��������}��12�l�̎q�������͌��������ĕ����܂���グ�A�傫���w����ق��ڂ��Ƃ����w����S�Z���k�ɂ��炷�B
���������������B
�ċx�݂̊Ԃɓ��Ă����A��ԍ����q�����D������B---�@���ꂪ�u�����ڑ��v�������B
�u���Ƃ���`���͌ߑO���ɁB�v
�u�h��͌v��𗧂ĂĂ��܂��傤�B�v
�u�ċx�݂͊O�Ō��C�ɗV�т܂��傤�B��������Ɠ~�ɕ��ׂ��Ђ��Ȃ���B�v
���̉����ɂ���̂��A�u�����ڑ��v�������B
�u���C�ɗV�ԁv����͂n�j�A����B�������u�u�h��͌v��I�Ɂv�Ȃ�āA��������������x�݂��I�Ƃ�����тɁA�ǂ����֔��ōs���Ă��܂��̂���N�̂��Ƃ������B
���ǂ��́A���Ă��~�߂�h�ꂾ�̐����⋋���悾�̂ƌ����邪�A�����́u�^������Ƃ��ɐ������ނ�Ȃ��v�ȂǂƁA���_�_��U�肩�����̈�n�搶�����āA��������ƂȂ��������Ă����q���������肾�����B
����Ɂu�����ځv�Ȃǂƌ��������t�́A���܂��B���ɂ���ƃo�b�V���O���������B���ʂ͐S����ɂ��ݏo����́A���t���獷�ʂ��n�܂�킯�ł͂Ȃ��̂ɁB
����͂��Ă����A��Ԏv���o�Ɏc���Ă���̂́A4�N���̂����ڑ������B
���̔N��ԂɂȂ��ĕ\�������������̂́A�e�ʋ̓d�C������̖��ŁA�����̎�����2�Ώ�B
���������B�@
�����قǍ��������I�@
�����܂��������B
�@�@�@�@�@�@ ���\�N���O�̏o�������v���o���̂́A�����̂��܂�]���Z���Ă��܂������炩�B ���\�N���O�̏o�������v���o���̂́A�����̂��܂�]���Z���Ă��܂������炩�B
����7���͍����A�ҏ��A�����A�����Ƃ��������t����ׂĕ\���������Ȃ�قǂ̋L�^�I�����������A����7��23���A�F�J�s�Ŏj��ō��l�̋C���A41.1�����L�^�����B
���{�̏W�����J�ɂ�鐼���{�L��ЊQ�̔�Q�̑傫���A�I�E���^�����̎��Y����13�l�A�������ɑS���̌Y�̎��s�����A���{�ɂ͍��܂Ōo���������Ƃ̂Ȃ��R�[�X�����ǂ�䕗12���̗��P�ƌ���Ȍ��������B
�����A����7���̊A���B�W���͂ǂ̂悤�Ȍ��ɂȂ邾�낤���B

�@�@�@
�S���E�J�T�u�����J�@�Ɓ@�t���b�N�X���炭����
������8������B�ߐ{�ł�8��1�������W����i���܂Ԃ��̂������j�ƌĂԁB
���̗R���͍�N�̓��L�ɁB
�@�@�@�@���R�̕�炵398�@�@2018.7.31�@�@
�@�@�@�@�@�@ �@ �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �E�e�̂��Ƃ��@---- ���ꂱ���E�e���@!
�E�e�̂��Ƃ��@---- ���ꂱ���E�e���@!
�����̋C�z���������킯�ł͂Ȃ����A�Q���̑�����ӂƗ���������낷�ƁA�ǂɉ����ē��{��E�T�M���A�ۂ�ۂ�ƒe�ނ悤�ɕ����Ă���̂������Ă��܂����B�炪�A�ɂ܂ɂ܂Ɗ����������������ǁA�C�̂������B
����͂������ォ�猩���Ă���Ƃ͋C�Â��Ă��Ȃ��B
��E�T�M�̌���������́A�Ƃ̊p���Ȃ��������ɂ���u�u���[�׃��[�̔��v�B
���Ƃ����Ă��A��������L���Ώn�������ڎ��邭�炢�̋����ɁA5�{�قǐA���Ă��邾���Ȃ̂����B
�J��������ɁA�������Ƃ������Ƒ��ɋ߂Â��A���Ⴊ�ݍ��ށB��������Ƃ����I
��E�T�M�������I
���ɗh���ė����������A�E���ĐH�ׂĂ���悤���B
�ʐ^���B�낤�Ƃ��āA���J�[�e����h�炵�Ă��܂����炵���B��E�T�M�́u�E�e�̂��Ƃ��v�f�b�L�̉�����蔲���A��ڎU�ɔ�ы����Ă��܂����B
�����c�O�������B
����ȋ߂��Ŗ�E�T�M��������Ȃ�āA�Ă̒��Ɏv�������Ȃ��y���݂��]���荞��ł����̂ɂȁB
���̏��Ă܂�Łu�s�[�^�[�E���r�b�g�v�̐��E����Ȃ��H
���͖�E�T�M���u���[�x���[��H�ׂ����āA�}�O���K�[����̂悤�ɁA�{�����肵�Ȃ����ǁB
��둫�ŗ����āA�O���Ńu���[�x���[���܂�ŐH�ׂĂ���----�Ƃ������z�I�Ȏp�ł͂Ȃ��������A�Ȃ��Ȃ��ʔ����B
���̖̉��́A��E�T�M���r�߂��̂��H�Ǝv���邭�炢��������Ƃ��Ă��āA�܂�ő|����������̂悤�ɁA�܂�����Ȓn�ʂ��L�����Ă����B
|
 |
���@�͍��̌�둫�B
�@�@�@���̎p���͂܂��ɃN���E�`���O�E�X�^�[�g���Ƃ���B
�������̑����Ƃ�����A�܂�ŏu�Ԉړ��B
�@�@�@�ؓ����̑̂������Ă�Ȃ��B
���@���������댯���@�m���邽�߂ɁA�������������Ă���B
�@�@�@�ڂ��Ԃ����ǂ����́A�킩��Ȃ������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�i�B�e�̓K���X�z���j |
���m�Ɍ������̃E�T�M�́A�s�[�^�[���r�b�g(Rabbit)�@�Ɠ����E�T�M�ł͂Ȃ��āA��E�T�M�i�gare)�B
�ĂȂ̂ő̖т͒����F�������B
��E�T�M�͌Q�����炸�P�ƂŐ�������悤���B���܂��������������A���̎��ɂ˂���Ƃ��Ă���ꏊ�𒆐S�ɔ��a400�����s���͈͂Ƃ��Ă���炵���B
��s���Ȃ̂ɂȂ��ߑO9���Ƃ������邢���Ԃɂ���Ă����̂��B��قǃu���[�x���[�̔��������Ɏ䂩�ꂽ�̂��B
�q����N�ɐ���Y�ݑ�����炵�����A�т̂Ȃ��ł��܂肻�̎p���������Ƃ͂Ȃ��B
�@�E�@���i���܁j�ӂӂ݉���o�ł��҂�����~�肻�����z�ɂނ����̊J���@�@�@
�@�@�@�@
�@���R�̕�炵397�@�@2018.7.26
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
 ���H�ׂ��
���H�ׂ��
������5�����N���B�������ܐ�����n�߂�6���ɂ͊O�Ɋ������B
���̂��ƋC�ɂȂ��Ă�������̃u���[�x���[�̎��n�Ɏ��|����B���łɋC���͏オ��n�ߎ��C�̑����Ƃ����܂��āA�Ƃɂ��������B���������ƂɁA�����܂łŎ��n�ʂ�18�L���ɂȂ����B�ڕW��25�L���I
�@
|

|

�R�S����1�{�̌s����A����Ȃɂ��@�@�@�@������炢���B |

�@�@�@
�@�@�@�}�b�^�[�z�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
����50�����H�ב����Ă����̂ɁA�Ⓚ�ɂɂ܂����N�̃u���[�x���[���A2�L���c���Ă���B
�����́A���N��7��10���Ɏ��n�������������B |
���������B���͗����܂܂ɂ܂����đ|�������A�K�v�ȉƎ��͂������ƍς܂��Ă��܂����A�ƍl����B���������Ƃ���͑��_���ꏏ�Ȃ̂ʼnƎ��͓����i�s�B�D������l���Ă��R�ɂ͓o��Ȃ��B
�Ӂ`�A�I������B�����̍Œ���̉Ǝ��͏I������B
���ꂩ�璩�H�A������7�����B�[���܂ł͎��R���ԂȂ�B�@�@���Ƃ��̂�т肵������̎n�܂�B
�^���p�N���Ɩ���Ƃ�܂������H��ۂ�Ȃ���A�u�ҏ��Ɍ����͖̂����ˁB�v�Ƙb���Ă��āA�ӂ��Ɏv���o�������Ƃ��������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�}�b�^�[�z�����̌����钬�A�c�F���}�b�g�ɘA�����Ă������̉ā@---�@2012�N��7���̂��Ƃ������B
������W��4000���[�g���n�_�߂��܂œo��A�C�^���A�̂��̂������݁A�}�b�^�[�z�����̐���������R�����]���A����������݂Ȃ���U�����āA�v��������
���Ă̂��Ȃ��̓~���o������1���B
���ʂĂăz�e���ɋA���Ă��āA���ė[�H���B�@�@����ǂ�����H�ׂ���---�B
�z�e���̃��X�g�����ŃA�e���h���Ă���邨�삳��ɁA
�u�O�̂��̖�o�[���A���C�����ɂ���2��H�ׂ����̂�B�v
�u���H����Ȃ��Ƃ�����g�̂ɗǂ��Ȃ��ł���B�������H�ׂĂ��������B�v
�u�����ĂˁA�������炸���ƃn�C�L���O���āA������ꂽ�݂����Ȃ́B��������2��ˁBTwice��B�v
����ȗ��݂��Ƃ����邨�q�͂ق��ɂ��Ȃ��̂�������Ȃ��B�ق����v�N�b�ƐԂ��ӂ���A�Ă����̃A���o�C�g�炵���n���̖�����́A�т����肵���ꂩ�班����������ʼn��Ɉ�������ōs�����B
������A�~�[�̐ӔC�҂Ȃ̂��낤���A���N�̏��������M��2�������ĉ�X�̃e�[�u���ɋ߂Â��A�j�R���J�i��ł����������B
�u���̏��������M�͑O�ؗp�ŁA�������̑傫���������C���f�B�b�V���p�̂��M�ł��B���̑傫������2�̖���ڂ�Ǝv���̂ł��ˁA����ł������H�v
�u�����A�T���L���[�A����Ō��\�ł��B�v
���͑傫�����M��t�ɖ�̂��ꂱ�������Ă��āA���_���O�{���C����H���������A�S�䂭�܂Ŕ�ꂽ�g�̂ɖ��⋋���邱�Ƃ��ł����B���������B
���S�͂����������ň��Ă����̂����B
�����ĂˁA���M�ɂĂ���ɂ�����̎R�̑̐ς��A�M�̔��a�����邮������̂̔����Ƃ���ƁA
���̔����̑̐ς́A
�u�R���̂S������i�p�C�E3.14�j�����锼�a�̂R��v�̔����ɂȂ�͂����Ȃ��B
���̏ꍇ�u���a��3��v���~�\�B�����Ŕ�r�ł���---�B
�O�ؗp�̂��M�ƃ��C���p�̂��M�̑傫���������Ɩڑ����Ă݂��B���i�v�L���ɂ��������ƌv�Z���Ă݂�ƁA�傫�����M�̕����A�������O�ؗp�̂��M��7�{�߂��̖���ڂ��邱�Ƃ��ł���̂��B�܂�A�O�̔�p2��7�̖��H�ׂ邱�Ƃ��ł���---�ƁB
���ӂ�ӂ�ƌv�Z���Ă��܂������A�����ł͂Ȃ������B
��ꂽ���ɂ͖���^�b�v���H�ׂ����A�Ƃ����]�݂����������̖�́A���p�����Ȃ��삳��̊���v���o���B
�u������܂���B���������X�������Ĕ��Ă���̂ł��B�v
�u����������������܂��ˁB�v
�u�ǂ����A������菢���オ��A�G���W���C�I�v�ƌ����Ă��ꂽ������̊���B
�@�@�@�@�@�@���R�̕�炵396�@�@2018.7.22
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
 �ҏ��Ȃ̂ŁA�T�ɂȂ낤
�ҏ��Ȃ̂ŁA�T�ɂȂ낤
�@�@
���̂Ƃ���A�C����34������R�T���̓��������A����B
���������炢���R�S�����A�����Ƃ����Ԃɐ����Ă��Ďc�O��7�����B
�����������Ƃ���ցA���_��������Ď����Ă��Ă��ꂽ�B
������A�M���������B
�����͑�D�������ǁA�M���A�����B
���̒����Z�������ɂȂ��Ă���̂ŁA���L�͂��̉摜�ł�����������Ƃɂ��܂���B
�ҏ��ł��B
�݂Ȃ���B
�������������B
�s���͂������B
�@�@�@�@�@�u��@���������������T��A�T�����---��v
������������V���L�����������B
�ł��A����5���N���A�C�͂�U��i���đ����ɐ��o��7�����B
�@�@
���R�̕�炵395�@�@2018.7.16
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
 �T�[�`���O�E�C���[�W�̌`��
�Ȃ����͂���Ȃɏ��Ȃ̂��@-----�@���э̂肪�B
�T�[�`���O�E�C���[�W�̌`��
�Ȃ����͂���Ȃɏ��Ȃ̂��@-----�@���э̂肪�B

�ŋ߂ƂĂ������[���{��ǂB
����́w�J���X���̑o�ዾ�x�@���s��w���w���m�@�����n���@�p��t����������
���҂͐����w�҂ŁA��ɃJ���X�̐��Ԃ��E�������Ă���u�s���h�v�����s���w�̊w�҂���B
�ޗǏo�g�̒��҂́A�v�l�̂����ނ�����\�����@�������ɂ����l�̂���ŁA�ǂ�ł��Ċ��Ɉꎞ�A�������悤�Ȋ��o�ɏP����B�����������ꂵ���B
�T�[�`���O�E�C���[�W�Ƃ́B
��O�ɂ���A��ꂩ�����Ă�����A�������ڎw���Ă�����̂�T���Ă������̌`��F�ɑf�����������邱�ƁA���邢�͂��̏�Ԃ��Ƃ������B
�K�v�Ƃ�����̂ɏœ_�āA�]�ނ��̂Ɏ�����Y���悤�ɒT���o���Ƃ������Ƃ炵���B
�W���ʐ^�̂Ȃ��̎����̎p���A���߂炢���Ȃ��T���o���B
����̒��̖��O�̗���A�悭�m���Ă������̐l���̂��̂�T���o���B
���������������u�T�[�`���O�E�C���[�W���`������Ă���v�Ƃ����炵���B
�Ⴆ�A�~�j���O�����ĂĂ���Ƃ���B
�厖�ȁA�ق��ɑウ�悤���Ȃ��l�W�����̒n�ʂɔ��ł��܂��āA�ǂ��T���Ă�������Ȃ��B
���������ꍇ�́A�T���Ă���l�W�Ɠ������̂����̒n�ʂɗ��Ƃ��A���������---�ƌ��Ĕ]�Ƀl�W�̐F��`���o��������B
��������Ɩ��������l�W���A�������������炪�Ă��̂悤�ɊȒP�Ɍ����邱�Ƃ��ł���B---�� ����Ȃӂ��ɍl�����B
��������ƁA���̔]�̒��ɂ́u�����r�v��u�G���v�̐F��������p����������L������Ă��āA�����Ƃ�����ʂɂ͎��R�Ɉ����o���Ďg���A�����r��G���Ɋ��Y�����Ƃ��ł���A�Ƃ������Ƃ��ȁB
�����r�͊���������ǁA�Ȃ��Y�����肪�G���Ȃ̂��@-----�@�Ƃ������G�ȋC���B
�l������낵�����Ƃ�������Ȃ��B
�����̐��_�Ɂu�Ȃɂ��Ɉ�����ꂽ���v�u�肢�����������v�u��������v�Ƃ������̂��������킹�Ă���ƁA�Ђ���Ƃ��č��\�A�@���Ȃǂɂ����炩����Y
���Ă��܂���������Ȃ�����B
�������A�������ړI�Ɍ������ēw�͂��肢�����Ă���ƁA�������̊肢�������A�Ƃ������Ƃ������ˁB
���ꂩ��A�v���[���e�[�V�����⋣�����Z�ȂǂŁA�\�ߐ�������C���[�W������Ă����B
�����̂��Ƃɂ��A�T�[�`���O�E�C���[�W�̌`�����菕�������Ă���Ǝv���邪�B�ǂ����낤���B
���R�̕�炵394�@�@2018.7.10
�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 ���́@-----�@���낢��ȉԂ��~�J������҂��Ă����̂��A��Ăɍ炢�Ă���
���́@-----�@���낢��ȉԂ��~�J������҂��Ă����̂��A��Ăɍ炢�Ă���
�@
|

�@�@�}�c���g�Z���m�E�@���{�剥
�@���߂Ĕ��Ԃ��炢���B
�@���͂̔Z���̂Ȃ��A�������������オ���Č�����B |

�@�n�C�u���b�h�E�����[�@�@�@�}���R�|�[��
�@�I���G���^�������[�ƍݗ��̎R���������G�����炵���A�@�ƂĂ��w�������Ȃ����B |
|

�@�@�n�C�u���b�h�E�����[�@�@�@�@�g���C�A���t
�@�I���G���^�������[�ƍݗ��̓S�C�����̌��G��B
�@�S�C�����̖ʉe������B |

�@�@�@���{�̍ݗ���@���}�����@�R�S��
�@���̎R�S���͍��S���̂��ƁB
�@���ꂩ��뒆�ɍ炫�����B
�@���̐�200�{���炢�B |
|

�@�@�@�j�b�R�E�L�X�Q�@�@�@�@��������
�@�W�����Ⴂ�䂪�Ƃ̒�ł́A����ȂɐF���Z����
�I�o������ۂ��Ԃ��炭�B�i�W��425���j
�@���͎��䑐�B |

�@�@�@�Ђ܂��@�@�@�������@
�@�쒹���H�c�����a��̎킩��A�뒆�ɉ���o����
�@���������Ԃ��炩�����B
�@�s���N�̓��V�g���i�f�V�R�i�������j�B |
�@
|
 |
�����̂悤�ɁA��̋����������Ă��āA���[����������炦���B
��`�����āB���ʂɊ肢���������Ă��Ȃ��̂�������܂��H
���̔N�܂ł����������C�ɐ����Ă����̂�����A����ȏ�̂��肢�́A----������ґ�Ƃ������́B�l���Ȃ�悤�ɂȂ�B�Ȃ�悤�ɂȂ������ɂ́A���܂��܂ȑI���������āA���̈��
�u������߂�v
�Ƃ������͂Ȏ肪����̂�����B
�@-----�@����@���S�@���~�@���O���z�@�������S
���דk�H�̂����B�@���A���|��H������I
�Z���ւ��܂����B�@�@�@�@
 �ߐ{������35�x�܂ŏオ��̂��B �ߐ{������35�x�܂ŏオ��̂��B
|
�@�@�@
�@�@�@�@�@�E�@�@���܂�₵�����������j���Ƃ����������Ⴋ���̂��
�@�O��̓���---�킽���Ȃ�ɁB
�@�@�@�E����ق̐搶�͓ȍ��q��B
�@�@�@�@�@�@�ȑ��̐搶�͂��炾�A�Ȏ��Y���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȑ���䕂���Ԃ��܂��Ȃ�A�ȑ��̐搶�̂��炪��Ԉ̂��B
���R�̕�炵393�@�@2018.7.6
�@�@�@�@�@�@�@ �@
�@
 �@��������@�����܂́@�������� �@��������@�����܂́@��������
|
 |
 |
|
�@�@�Ƃ����Ƃ߁@�ŋ߂͉Ăɂ��o��� |
�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�i���܂��j�@�Ȃ̎��@�������ɏn�� |
�Ȃ�ƁA6���̂����ɔ~�J���������ߐ{�ł��B
���݂̋C���͂R�S���B�����Ƃ������͂����Ɗό��ۂ̉A�d���I�ƌ��������Ȃ钩�B
����܂菋���̂ŁA�����̓N�C�Y�ł��B
�Ȗؖ��Y�́u�Ƃ����Ƃ߁v�̖��O����āF
�ȍ��q�傳�A����ח��S�S���d���_�l�ꔪ��h�J�h�ꂵ�āi�����ς���J�����̂ˁj
�u�Ƃ����Ƃ߁v����o�����B
�ȍ��q��̒�q�̓Ȏ��Y�����̋Z�p���p���A���ǂ��d�˂��B
�Ȏ��Y�̒�q�̓ȑ�������ɍH�v���d�˂��B
���āA����l�����������܂����B
�@�@�@�@�u�ȑ��̂������̂ق����A�Ȏ��Y�̂��������������������v�B
��������Ȏ��Y�A�v���C�h�������Ă����������Ƃ��B
�u�����Z-----�Z�Z�Z�Z�Z-----���������Z----�v
���́Z�Z�Z�Ŏn�܂镶�͂����������Ă��������B�i���Ȃ��Ȃ�Ɂj
���R�̕�炵392�@�@2018.7.2
�@�@�@�@�@�@�@ �@
�@
 �����̎�d��
�����̎�d��
�@
|
 |
6���P�O���̋L�^�ɂ���A�u���u���[�x��[�v���A�߂ł����n���Ă����B
���蓤�Ɠ����悤�ɁA��Ăɂ͏n�����A�u���ꂪ�n������A���x�͂���A�����Ă���v�Ƃ����悤�ɋK���������ʎ��l����S�����Ă���悤���B
��O�̎O�͍̂育��A�E�̎��F�͖����B�����Ďc��͂܂��܂����̓��ɁB�C�܂܂Ȃ킯�ł͂Ȃ��B����͎���c���Ƃ����ɐB���ɏ����������̂ŁA�������т���炵���B |
|
 |
�C���K�A�����Ȃ��I�A�����Ɠ����Ȃ���A�{�N���߂Ă̎��n�B
�܂���ԍ̂�����ׂ���ւ��������B
�u���������璷���������---�v�B
�Ǐn������B���̂��Ɛ����400�O�������p�b�N���Ⓚ�����B
�������B�Ⓚ�ɂ������ς��B
���̈�N�ԁA�����R�O���H�ב����Ă����̂ɁA
���N�̃u���[�x���[���܂��R�L�����c���Ă���---�B
|
|
 |
�킪�Ƃ̎R���̖͂܂��܂��Ⴂ�B
�Ԃ��炢�Ă����ɂȂ�Ȃ��B
�߂��̓��̉w�ŁA�����̏��ꂳ�甃�����߂��R���̎����A���ɒЂ���������������䥂ŁA�����_�炩���Ȃ����Ƃ����Ⓚ���Ă������B����߂�R���ɁA���ؗ����ɁB�����ł��s�����Ɛh���Ƃ͂܂��ɁB�G������ŁA��������ڂ����������肷���
�@�@�@�@�@---�����������I�Ƌ��ԉH�ڂɂ�������B
�u�Ƃ̒��ɂ��R���̎��݂����Ȃ̂������v�ƊO�삪�����B
�ǂ��ɁH
|
���R�̕�炵391�@�@2018.6.26
�@�@�@�@�@�@�@ �@
�@
 ����
�ԏҊ����@�Ԃ����� ����
�ԏҊ����@�Ԃ�����

�@�@�@�� �邩�����A�ߐ{�x��������тɏZ��
�@�@�@�� �������c�Ɍ��t�̌���́A�ꉹ�ŗh��Ă���
�@ �@�@ �� ���̐l���Ȃ����Ԃ��̂悤�ɔ����Ԃ��炫
�@�@�@�� �낱�тɈ�����X���������A���̘Z��
�@�@�@�� �q�i�����j��t����ƂȂ������
�@�@�@�[ ���̒�����������̂��@
*�@�������A
�@�@�@�@�@�@�@�@�� �� �����X�́@���̂܂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�� �ւ���������Ȃ�@-----�@�����������т�����Ȃ��B
�@�@�@�@�@ �����̂��q����
�����̂��q����
���R�̕�炵390�@�@2018.6.21
�@�@�@�@�@�@�@ �@
�@
 ���ꂪ�J�b�v���[�����̖��������I�@�@15�N�U�肾�I
���ꂪ�J�b�v���[�����̖��������I�@�@15�N�U�肾�I
�@
|
 |
�܂��A�����ǂ�����v
�u����ς�3���҂炵���v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@---�����Ƒ҂�---
�u����������Ȃ��́v
�u��������-----�ł́v�@�Ǝ��L���B
�u��—�ށA����Ȗ����������A�����Ԃ�Z���ȁv
�u���ɂ��A5�{�ł�������v
|
�R���r�j�Ŕ�������������A�������������ꂽ�B
�s�v�c�Ɠ��Ă�C�܂�܂�̓��ɂ͂͂���A�����݂����ɓX������Ɓu�ǂ���������Ȃ���ˁv�Ɩ��ʌ���@�������ɂ͓�����I
���������̂́u�g�������N�����̃J�b�v���[�����v�B������������t���Ă��āA���������B�����������X���̏ݖ����̂��g���A��Ȃǂ̓������ʏ`��U�肻�̂܂ܐH�ׂĂ��鐶���ɁA����Ȗ����ˑR��
���Ă����̂ň݂��т����肵�Ă���悤���B
�������A���������|�������ɂ͂��̖��͖�����������Ȃ�---�������Ȃ��ł������A�R���r�j����A���߂�ˁB
�Y�������ƍ����Ɩ��ƁB����3�_�Z�b�g��
���܂�ɖ��͓I������B���_��10�{�A����5�{�H�ׁA
�c��͐����݂y�����闠��̌��ɗ������B����p�g���[�����̂����̃J���X�A��������Ă����炵���A�}���ł���Ă��ăc�����c�����Ƌz������ł���B
�������C�͐t���ɗǂ��Ȃ���---�A�Ƌ���ł݂Ă��͂��Ȃ��B�J�b�v���[������H�ׂ��̂́A15�N�U�肾
�����B
���������A�R���r�j��X�[�p�[�Ŕ����Ă��邠�̃y�R�y�R�����܂ɓ����Ă���u�O�p���ɂ���v�Ƃ��́A���܂܂ň�x���H�ׂ����ƂȂ��B
�ς��Ȃ��B
��ɂ���ƁA�s��p�Ȏ��͊���Ȃ��āA�|�����Ɨ��Ƃ��Ă��܂��������B
*�@�����͕��̓��B���C���͔ȎY�̈����Ă����������[�[�������C���ƁA�Ԑg�̋��X�e�[�L��p�ӂ����B
�@�@�@�@�@�@�i�����Â��ȁA�܁A�������ɂ������낤�j
���R�̕�炵389�@�@2018.6.17
�@�@�@�@�@�@�@ �@
 �ڕ��@Kiss�@�@-----�@�N�����g
�ڕ��@Kiss�@�@-----�@�N�����g
|
�@ �@�@�@�@�@
�@�A�C�X�����h�|�s�[ |
 |
|
��N�̏H�Ɏ��d���A�O�����߂Đ��b�����ďt��������y���܂��Ă���Ă����|�s�[���A�v�����Ă��ׂĔ������Ƃɂ����B�����Ȃ̂ł��̑O�� �A�c�����ڂ݂����W�߂Ă݂��B
���̐��͖�200�{�B�Ԃт�Ɉ�ꂩ�����Ă���B�����ɉԂт���L����|�s�[���т�����B�@ ���C�����悤�ɂ����h��Ă���B
����������������B
���������
|
 |
�u�N�����g�݂������ˁv
�������B
�Ƃ�����낤���A�s��p�ŝR��I�ȉ�b�͂܂������Ēʂ�A���n����j�̑��_�������������B
�����͒����t������������A���̏ꍇ�̃N�����g�Ƃ͂��̍����ȍ�i���Ӗ����邱�Ƃ�
�A���̂��ƒm���̂������B
���͂ɗ֊s�����ۂÂ����ē�l�̐g�̂��������A�����z�ɂ͒����`�Ɖ~�`�̖͗l������������̂悤�ɕ`����A
���̒��ŕ��i�������j���̎p�́A���̐����甲���o�Ă��������ʂ���邩�̂悤�ɔ������B
�����ɂ͉Ԕ����L�����Ă���B
�����̕����z���炶�ジ�Ȃ��ɂȂ��ĉ��������ڂꗎ���Ă���B���F�A������A���F����B
�����͊R���Ղ��Ȃ̂�������Ȃ��B�Ђ��܂����Ă��鏗���̑���́A�g�̂��x�����ꂸ��
���ɂ����ꗎ���������B
�@�x�Ƒޔp�A����Ɠ����A���̌�ɗ�����͉̂����B
�A���o�����X�ɁA�s�����������Ă���B |
|
�E�B�[���ɍ����c��H�ʓd�Ԃ����p���A�x�����F�f�[���{�a�I�[�X�g���A�E�M�������[�֍s�����́A������ӂ�ӂ�Ɨ��������Ȃ��C���������B�{�a�̒������������Ɛi�ށB�ړ��Ă̕����ɋ߂Â��̂��y���݂Ȃ悤�ȁA���邢�͕|���悤�ȁB-----����������߂������ɗN���Ă���B�����Ɠ������Ă݂�ƁA����͐��_���k���Ă���̂�������Ȃ��A�Ǝv���Ă����B
���������悤�ɁA������悤�ɁA�l�X���Q��A�ЂƂ�ЂƂ肪�w�����Ă��銴��Ƌ��ɋ����Ă����̂������Ȃ���A
�G�̑O�ɗ����������̓��́A2012�N7��15���B���U�̓��ʂȓ��B
�w�jiss�x�u�ڕ��v�Œm���Ă���B
�@�@�@�@�O�X�^�t�E�N�����g�iGustav Klimt,�j��@���ʂ����������U��߂��Ă���B�@
�@�@�@�@�x�����F�f�[���{�a�I�[�X�g���A�G��فi�I�[�X�g���A�E�M�������[�j�����B
1907�N����1908�N���됧��
�@�@�@�@�@���R�̕�炵388�@�@2018.6.15
�@�@�@�@�@�@�@ �@
 �������́@�����Ȃ�����
�������́@�����Ȃ�����
�����͓������́B�ł͐A���͓����Ȃ��̂��B�s�����Ƃ������t�͖����̂��ȁB
���₢�₱��ȗ������悤���B
�@ ���@����@--- Blueberry�̏ꍇ�́B
���@����@--- Blueberry�̏ꍇ�́B
 �@�@�u���[�x���[ �@�@�u���[�x���[
�i���j
�c�c�W�Ȃ̐A���ɂӂ��킵�����A�Ԃ͂ۂۂƂ�����^�ŁA��Ԃ̑���I��h�����߂ɉ������ɍ炢�Ă���B
�}��҂̃}���n�i�o�`�ɂ́A��������܂��Ď~�܂�₷�������z���₷���B���̔��ʁA������Ζ����z�����Ƒ_���Ă���q���h���Ɏ���ẮA���ꂪ������
�s����B
�i�E�j
�������āA�����I
���̉Ԃ��x���Ă���Z���Ԍs�́A�z�����߂Ă����ނ�Ɏ}�̏㕔�ւƉ��Ȃ��瓮���Ă����B
����Ŋ����B����������������ďn���̂�҂��Ă���B
�@ �����@�������-----�@�X�N���b�g����̂��@--- �@Bluebell�@�̂ЂƂ茾�B
�����@�������-----�@�X�N���b�g����̂��@--- �@Bluebell�@�̂ЂƂ茾�B
�@ �X�p�j�b�V���E�u���[�x��
�X�p�j�b�V���E�u���[�x��
���������[��10�Z���`�Ƃ������z�I�ȏꏊ�ɐw����Ă���̂ɁA���̂Ƃ���J����B
�ق猩��B�y��������Ă��܂�������Ȃ����B���ꂽ�����ȂA���z�̔M�������ɓ`����Ă���B
�������Ȃ��B�V��������L���Ċ���Ȃ����L�^�����n�߂邩�B�X�N���b�g�A�X�N���b�g�B
�����A���������B��������ł������낤�B��H���x�ׂ͗̃��c�������Ă��ĕ��ƕ����Ԃ���n�����B
���x�͎߂Ɉړ����邵���Ȃ��ȁB �X�N���b�g�A�X�N���b�g�B
�摜�ɂ���Z���ׂ����́A���ʂ̍��B�y�̉h�{���z��������A�g�̂��x�����肵�Ă���B�E�ɒ����L�тĂ���̂��A�V���̌������i���k���j�B�s�荪���B
������g���ăX�N���b�g����B
���k�ɂ���Ăł������Ȃ�����---������ƌ����ɂ������B���̍����k�߂ċ�����y�̒��Ɉ������荞��---�ȒP�Ɍ@��N������Ȃ��悤�ɒn���[�����������B
�ق�ȁB�l�Q�����Ă݂�I���ɎȂ����{�������邾�낤�B�������������A�X�N���b�g���Ă���B
���Ⴍ�ɏ��̂́A�J�^�N���̃��c���B
�n�ʂɗ������킪�A����o���������k������40�b���̐[���܂Ő��荞�ނ��Ƃ�����B�l�Ԃ��܂Ō����Ȃ�A�n�ʂ�100���[�g��
���z�����[���܂Ŏ��͂Ő��邱�ƂɂȂ邩�B
�͂��炫�҂��I�@
�����Ƃ����̋����͂����Ԃ���������炵���A�����ł����Ȃ��ƌ@��N������Ă��܂�����ȁB














 �@�܂��@�܂��A�Ŏv���o�����B
�@�܂��@�܂��A�Ŏv���o�����B
���܂��ɋL���ɐ����c���Ă��鎖��������B
�c�Ȃ�����A�܂肢������҂̃K�L�E�`�r�̍��̂��Ƃ��B�m��6���炢�������Ǝv���B
���߂Ĉ�l�Łu�܉E�q�啗�C�v�ɓ���A���������܂����߂邱�Ƃ��ł����ɁA�M�ꂩ�������Ƃ�����̂��B
��|���肪�Ȃ��Ă��邷�銊��M���S�̕��C�̓��̒��ŁA���邮��g�̂���]���Ă�����-----���̐g���i����悤�ȋ��|���v���o���B
���邮��B���邮��B
���̖�A�ǂ�����đ̐��𗧂Ē������̂��A�v���o���Ȃ��B
������`�r�̎��͑̏d�����Ȃ��āA1���[�g�����炢�����w�䂪�Ȃ������͂�������B
�@�@�@�@�E �܉E�q�啗�C�̕�������ɂ�����Ă���Ђ炳�������Ė߂��
�@ ��Bluebell
�̖��_�̂��߂ɁB����Ȃɉ��炵���ԁB ��Bluebell
�̖��_�̂��߂ɁB����Ȃɉ��炵���ԁB
���R�̕�炵387�@�@2018.6.10
�@
�@�@�@�@�@�@�@ �@
�@
 �q�}�����̑����P�V�@�@�V��̗d���@���R�m�v�V�X�E�O�����f�B�X
�q�}�����̑����P�V�@�@�V��̗d���@���R�m�v�V�X�E�O�����f�B�X
�@
|
 |
������ɗ��āA���R�̒��ɍ炭�Ԃ̂��Ȃ₩���ɂ܂��܂��ڊo�߁A�G�߂��Ƃɉ�ɏo�����Ă���B
���R�̒��ɂ��鋭�������₩�Ȗ�̉ԁA�̉Ԃɖ����������X---�h�����Ƃ�߂������Ƃ��Ȃ��킯�ł͂Ȃ���----�����킹�Ȃ��Ƃ�
�B
�t�͂܂����m�ԁA�R���ɕ���A�Y�~�A���ẴV�����V�I�c�c�W�A�G�S�m�L�����Ă��́u�q�}�����̑����P�V�v�B
���̉Ԃ����Ȃ����Ƃɂ͉Ă��}�����Ȃ��B
�t�ƉĂ��Ȃ���A�Ђ���̕����ɍ炭�ԁB
�@�@����͋�̐F�A�q�}�����̋�̐F�B
�@�@���Ȃ���Ό����Ȃ��F�B
�q�}�����́A�W���R�O�O�O���ȏ�̍��n�ɍ炭
�u�q�}�����̑����P�V�v�B
�@�@��O�ː����A�����@�@�@�@�@ �@http://www.yamasyokubutu.co.jp/�@�@ |
���̐A�����ɂ́A���C�u�J������2��u����Ă��āA���Ȃ���ɂ��ĉԂ̍炫����m�F���邱�Ƃ��ł���B
����A����Ȃ��Ƃ��������B���C�u�J�����̑O�ɗ����A�F�ŃJ�����Ɍ������Ď��U��B
������X�}�z�Ŋm�F���A���т���j���̃O���[�v�����X�Ɍ���Ă����B
���Ⴀ���Ⴀ�B�킟�킟�B�u���E���̐l�����Ă邼�`�v
�݂ȁA�u����Ҋ����v�œ��������l�����Ȃ̂ɁA���ꂵ���Ɉ�ꂽ��́A�قƂ�ǐV�������̂���B
���A�����ƌ����Ă��A�����ł͂Ȃ��ėc�t�������ǂˁB
�ŁH�@�������̐^�������������āH�@
���͂͂��`�B�@�ł���܂��B
�@�@�@�@���R�̕�炵386�@�@2018.6.5
�@�@�@�@�@�@�@ �@
�@
 �����̉ԗV�с@�@
�����̉ԗV�с@�@
�@
|
 |
�����̉ԗV�т́B
�f���t�B�j���[���@�@�i���Ɛ��j
�j�Q���@�i����̓����S��������D���������ԁj�@�@�@�@�@�@
���[�X�t�����[
�N���}�`�X�@�i�����j
�V���[���[�|�s�[�@�@�@�i�ԁ@�s���N�j
�ē�
䉖�i��d���������j
�o���@�i�s�G�[���E�h�E�����T�[���j
���ׂ���ɒ������u�o�J���v�Ɋ����Ă݂��B
|
�u���͉R�����Ă���v�B
�E�u�������͉R�����Ă���v�̂Ȃ�u���͉R�����Ă���v���u�R�v�ɂȂ�A�{���̂��Ƃ������Ă��邱�ƂɂȂ�B
�E�u���͖{���̂��Ƃ������Ă���v�̂Ȃ�A�u���͉R�����Ă���v���{���ɂȂ�B
���̃p���h�b�N�X!
�ł̒��A�����ƍl���Ă���ƁA���ƂȂ��������r�̌Q�ꂪ�A���������B
�N���đ���H�ݎn�߂�E�E�E�B
�@�@
���R�̕�炵385�@�@2018.6.2
�@�@�@�@�@�@�@ �@
�@
 �����Ȃ��̊y����
�����Ȃ��̊y����
���N�̃z�g�g�M�X�́A�������Ă����̂������Ԃ�x�������B
���N�A�u���z�g�g�M�X�̐��v�̓������L�^���Ă��邪�A���N�قǂ��̓��₩�Ȑ����҂��������N�͂Ȃ������悤�ȋC������B���肵���A�����傫�����炢�̐g�̂Ɏ��Ă��܂��قǂ̒����H��w�����A����20���[�g���قǂ�
��̖̎������ꂷ��̒��𓌂��ւƔ�щ��B��ѕ��͂܂������T�}�ɂȂ��Ă��Ȃ��B�H�̑傫�����ז����Ă���̂��A�h�^�h�^�h�X�h�X�B���̖ʖڂ܂�Ԃ�B
���̉H�̑傫���́A�g�̂�傫�������������Њd���邽�߂̂��̂Ȃ̂�������Ȃ��B
���̐��̑傫���͒n���̂悤���B
�E�O�C�X�ɑ����z�g�g�M�X�̌����܂����s���́A�����炭�قƂ�ǂ����s���Ă���̂��낤�B
�����Ȃ��ƃE�O�C�X���S�ł��Ă��܂��Ă���͂��B�x�z�Ɣ�x�z�̂��̐▭�ȃo�����X�I
���H���̃E�O�C�X�̓꒣���苒���A�����̐��͔͈͂Ƃ��ĕۂɂ́A���̂悭�ʂ�傫�Ȑ����K�v�Ȃ悤���B
���܂����B
�܂����͈͂Â��܂܂Ȃ̂ɁA�ˑR�������Ă��鐺��
�����������@�����������@�@�i�������ƂR�������j�@�����Ő�����t�����z�g�g�M�X�A
�������������@�������������@�i���������@�Ƃ悤�₭�S���̐��Ɂj�i���t���C���j�@
�����Ŕ�ꂽ�z�g�g�M�X�A��������---��������----������----����---�ƌ�������
���̐����ǂ��u�����Ȃ��v���邩�ɂ́A���낢�날���āA
�u�Ă���@���������v�ƕ����������A
�u�����������ǁv�ƁA�������Ƃ��̂��̂̕����Ȃ�������l������炵���B
���ɂ͂Ă��������ƕ������Ă��邯�ǂȁB
�@�@---�����A
����4���Ƃ����̂ɁA�傫�Ȑ��Ŗڂ��o�܂����̂ɂ͕����邪�B
���������B�@�@����́u������v�Ƃ�����
�@�@ �@�@��̃I�g�M���\�E �@�@��̃I�g�M���\�E
���̒�ؑ��ɂ́A����Ȃ���ꂪ����B
|
�ނ����Z��̑鏠���A��̐菝�̎��Â̂��߂ɂ��̒�ؑ����g���Ă����B���܂�̖���ɖ�O�s�o---���Ԃ̑鏠�ɂ͂��̖���𖾂����Ă��Ȃ��B������A�킪���Ԃ̌��t�ɏ悹���āA��������̔閧�𖾂����Ă����܂����B�{���V���Ղ������B�Z�͒��{��̂��܂�A��E���Ă��܂����B
��̗��l�͈�̂ɋ���������A���̂܂܂��Ƃ�ǂ��������Ă��܂����B�{��ɂ܂����Ē���E�����Z�́A��ɕԂ��Č���ɐg�������Ȃ݁A���̂܂܃z�g�g�M�X�ɐg��ς��Ă��܂����Ƃ����B
�Z�͍�������A�u������A������A���Ƃ��Ƃ������v�Ɣ�щ���Ă���B�t���ς�ԂɌ����鍕���_�́A���̎��̒�̌�����юU�������̂��B |
�摜�́u�I�g�M���\�E�E��ؑ��v�B�@�I�g�M���\�E��
�I�g�M���\�E���@���N���@�~�ɁA���Ì��ʂ�����B
��R�Ɏ������A�Ƃ��Ė��ԗÖ@�ɗ��p����Ă������j�����B���ɐ菝�ɂ͖�����炽���B
�S�����A���R�[���x�̍������i�Ē��Ȃǁj�ɒЂ����ނƁA��Ɏh���ꂽ�ɂ݂₩��݂Ɍ��ʂ�����B
�����F�l�ɗ��܂�āA���Ɛ��̂���ݎ~�߂�����Ă����Ă��邭�炢���B
��ؑ��̉Ԍ��t�́u���݁v�u�閧�v�u���M�v�u�G�Ӂv�ȂǁB
�Ȃ�قǁA�閧�߂������̉Ԃɂ����ӂ��킵���B
����̂����ؑ��A���Č���f���s�@�A�A�����q�K�̃z�g�g�M�X�B
�����̗R����z���ƁA���ԃz�g�g�M�X�̐��ɕ��������Ă��܂��B
�@�@�@�E�ӂ��ɔ�іY�����Ƃ����������قƂƂ������^���̐Â���
*�@�v���t�������Ƃ�����B���̍b�������ɁA��͂�h�b�v���[���ʂ��ϑ������̂��낤���B
�@�@�����̓C�G�X�B
�@�@�߂Â����ɂ͑傫�ȍ������Ŗ��A���̏���щz���ĉ��̂��ɂ�A���������Ⴍ�Ȃ�A
�@�@���̃s�b�`���ɂ₩�ɊԐL�т��Ă����B
�@�@�Ȃ���قǁA�����̗����B�@�@
�@�@�����A�ʔ����z�g�g�M�X�̐�---���āA���Ȃ���ɐl���Ȃ��B
�@
���R�̕�炵384�@�@2018.5.30
�@�@�@�@�@�@�@ �@
�@�@�@ �@�C���J�@���@�c�o����
---�@���Ȃ��̖ʔ��� �@�C���J�@���@�c�o����
---�@���Ȃ��̖ʔ���
|
 |
�f���t�B�j���[���@Delphinium�@
�i�L���|�E�Q�ȃq�G���\�E���j
�@�@ ���Y�n�̓��[���b�p�e�n�̎R�n
�f���t�B�j���[���̖��O�̓h���t�B���idolphin�@�E
�@�C���J�j
��� �B
�ڂ݂��������Ɍ���ƁA�C���J����ђ��˂Ă���悤�Ɍ����邩��B
 �@�@���������C���J �@�@���������C���J
���{�ł̖��O�́A�I�I�q�G���\�E�i����j
�c��ڂɂ͐��������A�c����̕c�����ɂ��悢�ł���B
�c�o������ь������Ă̋�@---�@����ȃC���[�W���낤���A���F�̉Ԃ����ꂵ���B
���[���b�p�ł͂��̉Ԃ��C���J�Ƃ݂Ȃ��A���{�ł̓c�o�����Ƒz������B
�������������������_�炩�����͋C�������Ȃ�����A�������葶�݂��咣���Ă��邱�Ƃ���̔��z���B
���������Y���悤�ɗh��č炭�A���̉Ԃɂӂ��킵�����O���B���ԃ^�C�v�́A��̂ǂ��܂ŐL�т�̂��낤�A�ƐS�z���Ă��邤���Ɂu���������v�������A���⎄�̔w����z���āA2���[�g���߂��ɂ܂łɂȂ����B
�������ԂȂ̂ŁA�{���������Ύ����������@
�@�@�@�@�@---�@�F�l�̊Ԃ��ԊO���ɑ���������Ƃ��ƂƂ��B
���̃f���t�B�j���[���ɁA�炫�n�߂�䉖���K�N����荇�킹�A���[�X�t�����[�Ɩ��c��̃|�s�[��g�ݍ��킹�Ă݂�B
�u�܂��B�܂�ŃX�^�[�ɂȂ����C����v
���e�t����̗F�l���A�������Ă�������B�S�͂߂̂悤�ɋ���H
����ȉԑ����A���Ȃ����~�����H�@�@
�킽���A���������a�̂Ȃ̂��B�i�Ƒ��_�������j |
�@�@���R�̕�炵383�@�@2018.5.26
�@�@�@�@�@�@�@ �@
 �����܂��@�����܂��@�����܂�
�����܂��@�����܂��@�����܂�
�@����������L�����Ȃ��̂ɁA���R�ɐ����Ă�����̒��E�����܂��E�I�_�}�L�B
|

�@�@�@�@���m�I�_�}�L�@ |

�@���������m�I�_�}�L�̔� |

�@�@���m�I�_�}�L�̌��G�� |
|

�@�@���m�I�_�}�L�@ |

�@�@���m�I�_�}�L�@ |

�@�@����I�_�}�L�@ |
|

�@�[�R�I�_�}�L |

�@�@���m�I�_�}�L�@ |

�@���{�̎�����@�R�I�_�}�L |
�@�@�ȒP�Ɍ��G����炵���A�������Ƃ��Ȃ���ނ������Ă��Ă����܂����뒆�ɍ炢�Ă���B
�@�@�@�@�@ �@�������ăf�[�W�[�����J�ɁB �@�������ăf�[�W�[�����J�ɁB
�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������n�C�W�A�N�����A���[�[�t�@�@�i�`�����A���E�f�[�W�[�j
���R�̕�炵382�@�@2018.5.22
�@�@�@ �@
�@
 ���َq���Ƃ��������@�@�ᓜ���̕�炵
���َq���Ƃ��������@�@�ᓜ���̕�炵
���_�̕��e�����َq�D���������A�Ƃ����Ă��̂̓c�ɂ̂��Ƃ�����A���َq���]�T�ȂǂȂ�����̘b�����B
�Y����������ɐۂ�̂́A���сA���ǂ�A������\���A���c�q�A�݂Ȃǂ��������A���������َq����ɓ���Ƌ`����
�q���̂悤�ɑ厖�ɑ厖�ɂ��ĐH���Ă����炵���B
�@�@�@�@�@�i���������̘b�A�����p�Ɍ˒I�ɉB�������Ă����A�Ƃ�����b�������Ƃ����邭�炢�j
�@�@�@�@�@�i�����A�����������Ȃ܂Ȃ������̂�����A���َq�Ɏ�������C������������Ȃ����Ȃ����j
�@�@�@�@�@�i����ɂȂ�ƁA�����葁�������ŃJ�����[��⋋�������Ȃ�炵���B��ӂ�������̂��H�j
���ʁA�S���Ȃ�܂ŁA�������ɋꂵ�ނ悤�ɂȂ��Ă��܂����B
���N�O�̂��ƂɂȂ邪�A�`�Z����u�����l�������Ȃ��Ă����̂ł��َq��H�ׂȂ��v�Ɠd�b���������Ă����B
���������āu�����炩�玞�X�͂��ו��̒��ɂ��َq�����Ȃ��ŗ~�����v�Ƃ̂��Ƃ������B
�����^�ɎāA��x�܂������Â��������Ȃ��ו��𑗂�����A�`���̎o���@�i���A�������Ƃ��Ă����ǂ��ł��j
�u�v(���`�Z)���y���݂ɂ��Ă����̂ɁA���َq���Ȃ������ł���A������Ɖ������������E�E�E�v�ƁB
���`��A���ŗ~�������A�g�̂Ɉ������E�E�E�B�Y�ށB
���������A�u���َq��H�ׂȂ��v�錾���A����ɐS���ƂȂ������̂����ɂ��Ďv���o���B
�{�S�ƌ��ɏo�����Ƃ̈Ⴂ��z���ł��Ȃ������q�����ۂ��H�������H���v���m�炳�ꂽ�B
���āA���ꂩ�炪�{��Ȃ̂��B
�������َq������������ɁA���_���v�����Ă��������Ă݂��B
�u���������肪���������Ă��܂��B���͖�薳���̂ł����A�������猾���Ď��������̐ۂ�߂��ɋC��t���悤�Ǝv���܂��B���ẮA���َq�͂������������������E�E�E����ʂ�B�v
�`�Z�ɕ���Đ錾�����Ƃ������Ƃ��B
���_�ɂƂ��ẮA����͂����Ԃ�v���肪�K�v�������炵���B
���������́A�������D���Ȃ��َq�����f�肷��̂����邱�ƂȂ���A�Ȃɂ�葊��̋C��������������������Ȃ��̂�����B
������������l�̑Ή����ł��Ȃ��������̂��ƌ�����Ă���B
�������܂ߗF�l�m�l���g�̂̂ǂ����ɕϒ����o����N��ɂȂ��Ă����B
�������������Ă�A�_�X��������̂Ŗ��͍���A�̑��������̂ł����͉����������A�������ł���̂Ńo�i�i���O���[�v�t���[�c���H�ׂ��Ȃ��A�t����������ƂˁA�Ȃǂ��܂��܁B
����ɉ����Ă߂��߂��̍D���������l����ƁA�{���ɒN���ɉ������A���Ƃ��D�ӂ���Ƃ��Ă������グ��͓̂���B
|
 |
��������1���ԁA�\�h�K�₵�Ă����u�N�������v�B�����N�̗Y�L�����炩��ŋɂ܂�Ȃ��A���̂��������ς₢�B
�킪�Ƃւ̖K�₪�������ȁA�Ǝv���ƌ��݂ǂ�ɂȂ�r����������Ȃ������Ă���B
���̂����Łu�������v���ł��Ȃ��Ȃ����炵���B���O�r��܂肽���߂Ȃ��Ď߂ɍ����Ă���B
�������̔L���āA�Ȃ��Ȃ����͓I������ �̂ɁE�E�E�B |
�@�@�@�@ �@���R�̕�炵381�@�@2018.5.19�@
�@�@�@ �@
�@
 �@�w�N���m��Ȃ������ȍ��x
�������Ƃ钘�@�@�R���|�b�N���̉B��Z�ނ̂� �@�w�N���m��Ȃ������ȍ��x
�������Ƃ钘�@�@�R���|�b�N���̉B��Z�ނ̂�
���̖{�̑薼�����āA�u�����A�����ǂ��Ƃ�����v�Ǝv�������Ȃ��B
���L���Čq���܂���E�E�E�����N����Ă����A�����ƁB
|
�傫�ȐԂ��ւ̉Ԃ��炫�A�����₩�Ȑ킫�o�Ă��āA�����������鏬���ȎR�́A�̂��珬�l�`���̂���ꏊ�������B���������ɌC������Ă����B���̒��ɂ����̂͏����Ȑl�����B�ڂ��Ɍ������Ď��U���Ă����E�E�E���̎R�����̑�n�J���̔g�ɓۂݍ��܂ꂻ���ɂȂ�B���l���������Ȃ���I
�����Ŏ�l���̃Z�C�^�J����@�i�q���̍�������w���ł͂Ȃ����j�@�͈�v���߂��炷�E�E�E�B |
���w���̂�����A���̖{��10�ΔN���̎o����v���[���g���Ă���������́A
�{�̂Ȃ��́u����ɌC�����ꗈ�āA���̏�ŏ��l���������U���Ă���v�Ƃ����V�[���ɁA���܂��_�炩�������S������ł�����Ă��܂����B
���̏��l�́u�R���|�b�N���v�B
�A�C�k�̓`���ɓo�ꂷ�鏬�l�ŁA�u���̗t�̉��̐l�v�Ƃ����Ӗ��B���������₭���i���Ȃǂ�j�ɂ�����A���̗t���������ɏZ��ł����A�Ƃ���Ă���B�������̗t�����邽�сA���̎q���̂���̏Ռ����v���o���B�Ђ���Ƃ�����Ƃ����v���������āA�������n����Ƃ��́A�������A���J�ɐ���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ҍ������Ƃ邳���2017�N2��9���A�S�s�S�̂��߂��S���Ȃ�ɂȂ�܂����B�i�����j�@�@
�@�@�@*****�@�����r�̂��Ƃ̓t�L�@*****�@���̂��Ƃ͂����ƃE�h�ƃ~���E�K���ȁ@*****
�����炩�A�A�����L���͖����̂ɁA����̕Ћ��ɕ��������Ă���悤�ɂȂ����B
�V�t���J���̌s���L�т��������̎��������n�̎����B
�����́A�ʔ����Ƃ��ꂵ���ɁA���ӂ��ӏ��Ȃ�������Ă����B
��������䥂łĂ������������A��������o�������ϕ��������炦���B
������������ؒő���l�Q�A���g���ȂǂƐ������킹�A�ݖ��F�̉��������������̏o���オ��B
���Ō����u���̐�������E�ӂ��̂�������v�B
������Łu�ӂ��̂�������v�ƌ����Ă��ʂ��Ȃ��B
�u��������v���ĉ��H�u�^�C�^�����ēy���̉q������Ȃ��H�v�ƌ�����̂��I�`���B
�������������g�������܂�ł͂Ȃ��̂ŁA�u���̐�������v�̔����ȋ�����������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�u��������v�A�u�ϕ��ɂ���v�A�u�ς��߁v�E�E�E�����̈Ⴂ���ǂ��������Ȃ��B
���܂ꂽ�y�n���痬��A�͂邩�ȓ����ɂ��ǂ蒅�������̓f���V�l�B���������A�̋����������l�B
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@
|
 |
�l�i�V�O�T�@���������@�q���K�I��
�z�Ղŗ��݂��Ă���̂́A�u���[�x���[�̂Ђ����B
�܂����肵�A����������n�������ƓK���ȗ��݂���������A�������n�߂�B
���������Ă₨�獪��藎�Ƃ��A�������̐g�̈�{�Ől�������ɏo��B
���Ƃ͊�̉h�{���z�����āA�܂��܂��傫���Ȃ�B
���@�n��10�b���̏����獶���ɐL�тĂ� �� |
|
 |
���낻��Ԃ��炩���悤���B
�������N�`���B
�t�Αf�H����Ȃ��̎����Ȃ������ĕ��C�B
�h�{�͂��炦��������B
�t���ρH����Ȗ��ʂȂ��͕̂t���Ȃ��B�j�[�g�����āH
������������Ȃ����A�I���̓I���Ȃ�̍l���������Ă̂��ƁB
���̂܂܊�������ɗ��݂��߂��āA�͂炵�Ă��܂��Ă���肾����ȁB
���̂����ɂ��Y��ȉԂ��炩���Ă��铡�����Ă݂�B���݂��i�ߎE���Ă��܂�����̖��A�������ɂ���
�B�����邩�B
�����J�b�R�E�����������B
�����̗����Y�݉߂��đ���肪�����Ȃ��Ȃ��Ȃ������ς��낤�B
�@ |
* �@5��14���@���N���߂Ắu�z�g�g�M�X�v�̐������������B
�@�@�@�@�@�@�t��10�������������̂ɁA�z�g�g�M�X�̐���10���x�������B
�@���R�̕�炵380�@�@2018.5.15�@
�@�@�@ �@
�@
 �R�C(���j������Ȃ� ����
:�@�R�̂Ђ��肵����C�̂���
�R�C(���j������Ȃ� ����
:�@�R�̂Ђ��肵����C�̂���
�@
�A�x���͂Ȃ�₩��ƖZ���������B��̉ԂƐV�̍L�t���Ɉ͂܂�Ă��Ă��R�C������Ȃ��E�E�E�E�ǂ��ɂ����炸�߂��̎R�֏o�����Ă����B
�s����́u�����P���Ƃ݂����R�v�B��������W���P�P�O�O���O��ŁA�킪�Ƃ���͐��k�̕����ɂ���B
�݂����͂��Ȃ킿�������E�E�E�����́u���m��N�� �v�����߂�ꏊ�B
�@�@ �@�@ �@�@
�@�@�@�@�ߐ{�x���]�@�����̖����@�܂����@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�E�S�N�~�c�o�c�c�W�@�Y�ǂ�10�{�@
�@�@ �@�@ �@�@
�@�@�@�@�^�e���}�����h�E�@�Ԃ̐���30���܂� �@�@�@�@�@�]��ł������ł͋N���ʂ킽���B �P�j���̃����r
�Ԍs����������
�@�@�@�@�@�@�@�@
�͂Ă��āA�R�C�i���j�Ƃ����B
�R���C�Ȃ甄��قǂ���E�E�E���Ȃ��������ł���悤�ɁB
�ŋߕs�v�c�Ɓu����Ɓv����v���o���Ă��܂��悤�ɂȂ����B
�E�E�E�E�E����́u�R�C�i��܂��j���o���v�Ƃ������t�����ǁA���̈Ӗ��́u�R�t�v�ɋ߂��B
���܂��܂��܂��������Ƃɐl����������l�A���R�̐�������l�̂��Ƃ��낤�B
���Ȃ݂ɎR�t�Ƃ� �@�@
�@�@�E�z��������T���ĕ����A�z�̍̌@���s���l�B
�@�@�E�R�т��t����E�E�E���E�̕�����Ȃ��R�̎��X��������ɖق��Đ�|�����Ƃ����낤���B
�@�@�E���@�I�Ȏ��Ƃɑ���l�B
�@�@�E����ɂ́A���\�t�A���@�t�Ȃǂł�����炵���B
�@�@�@�@�@�@�@***�@������r���@***
�@�@�@�u�肪�����˂��v
�@�@�@�u�����ƈꏏ��v�@�u�����r����{�����Ď��L�������_�ŁA���̃����r��ڂŒT���̂��R�c�v
�@�@�@�u����A�����r�ڂ��Č�����v�Ǝ��B
�@�@�@�u�ł͐��l���ʂ�����͑��������ʂƂ����炵������A�����r�̎��n�͔C�����v�Ƒ��_�B
�������ƃ����r�������Ă���ƁA����Ƀn�C�ɂȂ��Ă��āA�o�b�O�̑��݂�Y��Ă��܂��������B
��Ȃ���Ȃ��A����ȎR�̒������ĉ����N���邩����Ȃ��B
���_�͕Ў�Ɏ��̃o�b�O������Ă��ɗ����A���킴���ςĂ���B
�R���C�̑����킽���ł��A���R�̐����Ȃǖ����Ă��Ȃ��B�P�j���̐��ʂ͕K�R�Ȃ̂��B
�@�����r�̂��������̕��@�́A
�@�@�@�ǂ��A�s�̍d���Ƃ���͐藎�Ƃ��B
�@�@�@�����r�̗ʂɂ���邪�A�P�j���̃����r�Ȃ̂ŁA����3���b�g�����炢�������B
�@�@�@�������蕦��������i�g���n�����^�������������邽�߁j
�@�@�@������������85�����炢�܂ŗ�܂��B
�@�@�@�O.�W���̏d�������A�ǂ������B�i3000���~0.8����24���j
�@�@�@�����r�����A�����W������B
�@�@�@���X�G���ď_�炩�����m���߂�B�i������2���Ԃŏo���オ��j
���Z���ɁA�����X�`�ɁB�c��͐�����ėⓀ�����B
�@
���R�̕�炵379�@�@2018.5.10�@
�@�@�@�@
�@
 �@
�l�����@�܂��܂��@���Ƃ��̎q�@ �@
�l�����@�܂��܂��@���Ƃ��̎q�@
�@�@�@�@�@�����̂��̎q�́@�܂ނ��j����B�@�������Ƃ��̎q�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�����X�W�F���_�[�̃X�[�p�[�X�^�[�@�@�}���V�O�T�@�T�g�C���ȃe���i���V���E��
|
 |
�}���V�H�@�����A���̃}���V�B
�摜�ɂ���悤�ɁA�����ƐL�т��s����ł��铛��̗t�₪�u�}���V�v�Ɏ��Ă��邱�Ƃ��炱�̖��O���t����ꂽ�炵���B
�܂��@���@���̌̂͂��̎����łȂ����A���������������i�ނƁA���S�������ԏ�
(�ɂ�����������E�����ԂԂ����钷�ׂ���)�𗧂��グ�A���̔w��ɂ͊}�ɂ悭��������䚂ƌĂ���^��䚂��A�Ԃ����悤�ɐL�т�����B
�T�g�C���ȂȂ̂Ő��m�Ԃ┒���J���[�̉ԂɎ��Ă���d�g�݂������Ă���
�ƌ����Ε�����₷�����낤���B
����ɐ����Ă���̂́A�}���V�O�T�̂����u�J���g�E�}���V�O�T�E�֓�坑��v�B
���F�̕���䚂������̂́u�����T�L�}���V�O�T�E��坑��v�ƌĂ�Ă��āA���̂��̐��ݕ����Ă���悤���B�܂��摜�ɂ͌����Ȃ����A���̕���䚂̖͗l�͂Ƃ��Ă��������I
�������̂���D�ΐF��������䚂́A����Ȃ̒����ɍ��킹��т̂悤���B�}���V�O�T�͎��Y�ي��B�ł��A�Ȃ����̎q�����N���̒j�q�ƕ����邩���āH�E�E�E�E�����́u�H�ɐԂ��ʎ������点�Ȃ�����v�B
������Y�A������܂��Ⴂ�Y�Ȃ̂��B
�}���V�O�T�̈ꐶ�F
��q���甭�肵�A�n���̈��Ɏ�����s������傫���ɂȂ�܂ł̉��N�Ԃ́A�t��������B���̌��s��������x�ɑ傫���Ȃ�ƁA�͂��߂ɗY�Ԃ�t����B�������ď\�ɉh�{����s�ɒ~����ƁA�₨�玓�Ԃ�
�炩����B
�������A���Ԃ͂��̂܂���
�̂܂܂ňꐶ���I���邩�Ƃ����ƁA�����ł��Ȃ��B�h�{��Ԃ������ƍĂїY���ɖ߂邱�Ƃ�����
�@�E�E�܂肱�̃}���V�O�T�́A���������Ƃɐ��]���A���炵���B�͂��ߒj�̎q�A��������ƈ�l�O�̏����ɁB���������ƍĂђj�̎q�ɂȂ��ĂЂ�����l����ς���B���̑I���̓}���V�O�T�̈ӎv�ɂ����̂ł͂Ȃ��炵���B |
�����A�j�ɂȂ����菗�ɂȂ�����B�߂܂��邵�����Ƃ��B
�Ƃ������A���n�����̂Ɉ�܂Ŏ��̐�����c���̂�҂A�Ƃ��������ȑI�������Ă���̂�������Ȃ��B
�킪�S�g��U��Ԃ�ɁA
�@�@�@�@�O�ʔ@��F���S�@�鍳
�@�@�@�@�O�ʔ@�鍳���S�@��F
�}���V�O�T�͂��̓�̊Ԃ�h�ꓮ���̂��E�E�E�B(�O�ʔ@��F���S�@��F�ɂȂ��āA�Ƃ��邳���O��j
�Ƃ��낪�A���l���Ă��邤���Ɂu�l�Ԃ̊�{�͏��ł���v���ƂɎv���������Ă��܂����B
�l�Ԃ̐��ʂ͈�`�q�ɂ���Č��܂�悤���B46������F�̂̍Ō�̓���u�w�w�@�v�ł���Ώ����ɁA�u�w�x�v���ƒj���ɂȂ�B
���̓�̐��F�̂��l�Ԃ̐������肷��B���Ƃ��Đ��܂�A�r������j�ɕϗe����炵���B
�Ȃɂ��u���͒j�̘]��������ꂽ�v�킯�ł͂Ȃ��B
������u���͑��݁A�j�͌��ہv�B�@�@�����̂��搶�������Ă����B
�ӂ��ށB������ւ�Ń`�����`�������Ă���O��́A����͒P�Ȃ錻�ۂȂ̂��B
�@�@�@*�@���݂ǂ�ɏt�̉J���Ȃ���ɂ��ނ�������E�̎�ŕ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T�g�C���ȂȂ̂ŁA�~�r�A���ɂȂ�邩�ƌ����A�Ȃ�Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V���E�_�J���V�E�����܂ނ̂ŁA�L�ŁB�@�@�@�@
�@�@�@���R�̕�炵379�@�@2018.5.5�@
�@�@�@ �@
�@
 �@���܂ɂ́@���肬�肷�� �Ȃ�܂����B
�@���܂ɂ́@���肬�肷�� �Ȃ�܂����B
�@�@�@�@�@����Ȃ� ��������̎��Ԃ��@��ɂ����Ă����̂�����
�@�@�@�@�@���܂ɂ� ���肬�肷�Ɂ@�Ȃ�܂��傤�B
�@�@�@�@�@������ �i�F���y���� �����ɂ��ł��B
�@�@�@�@ 
�@�@�@�@�@�@�@���������ɓ����
�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�p�[�S���̎���͍���
�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���x�~�Ɨь�̔�����
�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�Γ�ԂƖ쑺���݂��@�U�P���炢�Ă���
�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@���납��������� �@����͂����I���
�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ԃ��U�P�Ƃ����݂ǂ�̐V��Ɓ@�@�@��F�̎�荇�킹
�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��D���ȉ�顑��i��ނ葐�j �@�@�`���[���v�̖��O�́A�n�E�X�e���{�X

��O�̓u���[�x���[�@���N���L��炵��
�@�@�@�@�@�@�����̎ʐ^�̒�́A�S�̂̔����̍L���Ȃ̂ł��B
�@�@�@�@�@�@��̓z���Ԃ���A�����̓L���M���X�ɂȂ���B�E�E�E���j���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�������A�A������A���{�L���M���X�ւƃM�A���ւ���̂́A�z���g�ނ�������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�֏o��Ƃ����������Ă��܂��B�E�ƕa���j
�@�@
���R�̕�炵378�@�@2018.4.29�@
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �^�P�m�R�̂��̌�@�E�E�E�@�킪�����������Ɋy�A����ۂۂ̂悤�ɁB
�^�P�m�R�̂��̌�@�E�E�E�@�킪�����������Ɋy�A����ۂۂ̂悤�ɁB
�@�@�@�@
�����̂����ꂳ��B�^�P�m�R�����肢�������̏��ꂳ��B
���ЂƂ悵�ŁA�ł���������҂̏��ꂳ��������ĂԂ��Ƃɂ��悤�B
�u�����܂ŗ��Ă���邯�H�Z���́����Z�A�d�b�́����Z�B���H�����̋��H�Z���^�[��m���Ă��邯�H�@���̃Z���^�[����200���[�g���قǖk�̕����ŁA�ߐ{�̂��̏����瑖���Ă����ƁA���H�̍����Ɏ��̉Ƃ������v
�Ȃ�Ƃ����I�m�Ȑ������B�����Ă��܂��B
�u�͂��A���v�ł��B������܂��v�Ɠ�����ƁA
�u�������������B�v
���̕Ԏ��ŏ��ꂳ��̓��̒��ɃJ�[�i�r�A�܂��̓C���^�[�l�b�g�Œ��ׂ�ȁA�ƑM���Ă���̂���Ɏ��悤���B
���炵���A���̂��N�ŁI
9��15���ɂƖ��A�҂����肻�̎��Ԃɒ����ƁA���ꂳ��A����`��Ə������đ҂��Ă��Ă��ꂽ�B
��y�Y�ɂƐH�p������n���B
�@�@�@�i�c�ɂł̂��������ꍇ�A�傰���ɂȂ炸�A����ɂ��C�����킹�Ȃ���y�Y�́A�H�p���A�����A���ȂǁA
�@�@�@�@���邢�͑���ɂ���邪�h���ƈꏡ���B�@������ӂ̌��ˍ���������j
���k�Ȃ��������ꂳ��̊炪�A�����Ⴍ����ƏΊ�ɂȂ�A���ꂪ�܂��ƂĂ����炵���B
�����҂̂�����̍H�[�������Ă��������A���y�Y�ɂƝ������Ă̂��݂��������Ă����������B
�����������A�q���̂���̓c�ɂ̐������v���o���B��������A�������B
�u���̓y�n�ɂ��łɂ��ĂU�O�N���܂�ɂȂ�B���̍��͘m�����̉Ƃ������B���܂͑��q�v�w�Ɠ������Ă���B���q�H�y�؊W�̎d�������Ă���A�y�j���E���j���͔_�Ƃ�����Ă���Ă���B���ǂ�����ȏo�������ł����Ă���Ċ������B���ł���������q�����q�����B
���ł���H�w�Z�̐搶�Ȃ��B�����҂ŁA�������ŁE�E�E�E�B�v�Ƃ����ɘb�������Ă����B
���̒�̎ʐ^�����������A���݂��ɉԂ̏����������������B�N�͂����Ԉ���Ă��A�����������ނ������������Ȃ̂ŁA�ꏏ�ɍs�������_�������قLjӋC���������B�i����Ȃ���A���̎q�Ȃ���ˁj
���ŁA�ʂ˂��̘b�ɂȂ�B
�u���A�ǂ����炫�����H�v
�u���{�œ�Ԗڂɔ���������B�ʂ˂��̎Y�n����A�ߐ{�Ɉ����z�����Ă��܂����B���̐ԓy�Ǝ_���̋����ΎR�D�y�̂��̏ꏊ�ł́A�ł���ʂ˂��̖����Ⴂ�܂��B��ԁH�@����͒W�H���Y�ł��A�Â��̂ł���B�v
�u�������ׂ��B������ӂ̃y�[�n�[�͂T����Ƃ��ƁB�ʂ˂��Ɉ�ԗǂ��̂̓y�[�n�[�U����V���ׂ��v�u�ΊD����t����Ď_�x�������邳���v�Ə��ꂳ��B�i�@�y�[�[�n�[�Ƃ͂����̂��Ɓj
�܂��܂��������B
���܂蒷�X���ז�����̂��E�E�E���낻�뎸�炷�邩�E�E�E�Ɖ�X���v�����̂�����������̂�������Ȃ��B
�����̂����ꂳ��́A���c��ɂ��C�ɁA�ł����肰�Ȃ��A�������p���炤�����Ƃ��݂��ׂĂ���������������B
�u���N�̕��ɁA����������S�����������`�v�u��t����ė[�т�H�����C�֓������B���������C���Ⴏ��ǂ��A���̖�͂��Ƃɒ��������E�E�E���ɍs�����畗�C�̒��ł����ʖڂɂȂ��Ă����v
�u�E�E�E�v�u�E�E�E�v�@�@���t���Ȃ��B
�ŁA�^�P�m�R���B���h���B
�}���ŋA��A�F�l�ɕĂʂ���t���Ĕz���ĕ����B
�@�@�@�@�E�E�E�^�P�m�R�O���̒��������B�i�^�P�m�R���������ǁA�N����炵�́j
�@�@�@ ���R�̕�炵377�@�@2018.4.26�@
�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �@���Ƃ����t�Ȃ̂� �@���Ƃ����t�Ȃ̂�
�@
|
 |
�}�C�i�X10���̋C�����������������~��ς��� ��n���A
�@�t���������Ƃ����
�@�����I�ɖ����P�����Ă���B
�@�V���{���̃`���[���b�v���炫�A�P�}���\�E�����ނ�A
�@�|�s�[��T�N���\�E���Ԃт��h�炵�Ă���B
�@�C�̑����c�c�W���т�
�Ԃ�����ǂ�A�����̎R�����A
�@�ӂ����Ɖ������Ă��ɍ炫�n�߂��B
�@ ���̗z�ɂ���Ȃ�Ƃ��������p������
�@�[����w�Ɏ鎞�A
�@�ꖇ�����܂��̉Ԃт炪�A
�@�n�ʂɎU��~�����������Ă��邩�̂悤�ɓ����ɂȂ�
�@�P���𑝂��Ă���B
���N�̏t�̑����́A�S���ǂ��t���Ă����Ȃ��قǑ����B
�@�O�t��ԁB
�@
�@�@
�@
�@
�@
�@�@�E�͑��ɍ��̏t����ӂ邳�Ƃ͔���܂����琼�̂��̋�
�@ |
���R�̕�炵377�@�@2018.4.21�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@
 �w���t�W�x�œ�ԖڂɍD���ȉ�
�w���t�W�x�œ�ԖڂɍD���ȉ�
�@
�E�@�Ă���@���Ď����@�@������@�@�������@���̊x
�ɍؓE�܂��Z�@�ƕ����ȁ@���炳�� ����݂�a��
���� �����ȂׂĂ�ꂱ������ �����ȂׂĂ�ꂱ�������@���ɂ����͍���߁@�Ƃ���������
�@�i������@�݂������@�ӂ�������@�݂ق肭�������@���̂����Ɂ@�Ȃ��܂����Ɂ@���������ȁ@�̂炳�ˁ@
����݂@��܂Ƃ̂��ɂ́@�����ȂׂĂ�ꂱ������@�����Ȃׂā@��ꂱ�����܂��@���ɂ����͂̂�߁@
���������Ȃ����j�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Y���V�c�@�@�@�w���t�W�x���P�@000�P
|
���ߐ����~�����O�A�V�c�����v�z�����ׂ鎞��ɕҎ[���ꂽ�w���t�W�x�̊��P�ƂQ�̃g�b�v�ɂ��̉̂��u���ꂽ�Ƃ���ɁA�����̐����̂������������B
�̂̌`���͒��̂����A���͕̉̂ϑ��I�B
�R���A�S���A�T���A�V���Ɖ����q���ĐL�т����������Ǝv���ƁA�ӂ���4���ɏk�܂�B
�����ŋ����̂���u����݂v�i�����t�j���������u��a�̍��́v�ő���̒��ӂ��䂫�A�u�����Ȃׂāv�Ɓu�����Ȃׂāv��Δ䂳���Ō��9���A7���ƍL����₪�Ď��ʂ��Ă������̎��
�́A�������w�������u�́v�̋N�����v���N�������Ă����B
�܂�ŏ��j�}�B�Â��瓮�ցA�ɂ���}�֕ω����Ă����B
�����3�y�͐��̌����Ȃ��B�@�@�@�i* ���̂Ƃ́A�T�A�V�A�T�A�V�Ƒ����Ă����Ō�͂V�A�V���Ŏ~�߂�́j
���t�̎���A���O�͓��ʂȈӖ��������Ă����B���O�ɂ͂��̐l�̍�---�������h��A�����m���邱�Ƃ͑���ɂ��ׂĂ��������ƁA���邢�͋������邱�Ƃł��������B
���O�����\�\�\�Ԏ�������B����͋���������ӎv���Ӗ����Ă����B
���t�ɂ͍�������A���t�������ĐS�������Ƃ��ł���ƐM�����Ă������ゾ�����B
�t������ɒ����A��R�ɂ��܂��܂ȍ��萶���Ă��������̖�V�тŁA�V�c�ɋ������ꂽ�����́A�����炭���̒n���̍����̖����낤�B
���̓��͌Ñ�̉A��܌��ܓ��ɍs��ꂽ�u����v�̍s���̓��������̂�������Ȃ��B���z�͍����P���A��R���ɐ��܂�A�я�����������ߕ��������͂˕Ԃ��Ă���B
�u�āE���v�ɂ͉��������Ă����̂��z�����Ă݂�B�R����낤���B
���A��f�A����܂��A�n�A俁A�͂��ׁA�����肻���A���Ӎ��A�����Ĉߕ������M�ȐF�̎��ɐ��߂邽�߂Ɍ@�������A���܂��Ő��O�̓��{�����T�L�̍��������̂�������Ȃ��B
�@�@�@
�@�@�@*�@��ԍD���ȉ̂́A���̓����̎��ɂ���ĕς��B������2�Ԗڂ͂������̉́B�@
�@�@�@�@
 �^�`�c�{�X�~��
�^�`�c�{�X�~��
���R�̕�炵376�@�@2018.4.20�@
�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �^�P�m�R��T�����@
�^�P�m�R��T�����@
�t�̉J�����x���~��A���X�̉萁������N�ɂȂ��������N�B
�^�P�m�R�����������`�����Ă���̂��A�ߏ��̒|�тŌ������B�֓����[���̍��y�ɐ��炷��^�P�m�R�́A���̂��̃A�N�̖����_�炩�����̂Ƃ͈���Ă��d���A�A�N���������Ă݂Ă������������ɂ͒������B
�������^�P�m�R�̓^�P�m�R���I
�����ЂƂc�O�Ȃ��Ƃɓ��n�Y�̃^�P�m�R�́A���˔\�̎c���ʂ��K���l�����������Ă���̂ŏo�ׂ��K������Ă���B���R�A�Y���̓X��X�[�p�[�ɏo��邱�Ƃ͂Ȃ��B
�����A���X�̕��˔\�ȂNjC�ɂ��Ȃ����A�����������N�̃^�P�m�R�������Ȃ�炩�̐g�̓I�g���u�����N�������Ƃ��Ă��A�����͂��ꂾ�����A�Ȃ���Ď����G�r�f���X�Ȃǖ������낤�A�Ɗy�V�I�ɍl���Ă���B
�H�ׂĂ��H�ׂȂ��Ă������ꗈ��Ƃ��͗���̂����ˁB
��D���ȃ^�P�m�R�B�@�@�ł͏t�̖����ǂ�����Ċy���ނ̂��B�@�@�v�Ă̂��ǂ��낾�B
�����ŁA�}���ٍs�������ˁA���˔\�c���ʂ����Ȃ��A�̔���������Ă���͂��̑��܂Ńh���C�u���A����������铹�H�����̎Y���̓X�ɏo�����Ă����B
�u�^�P�m�R�A����܂��H�v�@�i�X�Ԃ̂�����A������߂āj
�u�ӂ��ށA���Ǝ��̊ԂȂ炠�邯��--�v
�@�@�@�i���肱�Ԃ��Ŏ����̋����������A���̂܂��̋����w���A�����낦��Łj
�u�N�ɂ�����Ȃ��A�Ƃ������ƂȂ�����Ă������v
�u�n�j�D����Ŏ��ł��܂��傤�I�v
�ڂ��������Ă݂�ƁA���N�͂��̑��̃^�P�m�R���K���l��������Ă��Ȃ��炵���B
���N�͍K���̔��������̂ŁA�����Ŏ�ɓ������̂����ǂȁB
������K���l���ꂷ�ꂾ�����̂ŁA
�u�ی������`�F�b�N�ɂ��Ȃ��A�y�j���Ɠ��j���Ȃ�^�P�m�R�����`�v
�ƓX�Ԃ̂�����́A����������ۂ���Ō��������̂������B�����B
����c��ڂŒ��������Ă��āA�オ��肵�Ă��瓹�H�����ɍ����|�����������A�����̐l�����̍������܂œ������肳��������B
������͏����Ȃ������������̂Ƃ������A�y�g���b�N���y�X�Ɖ^�]���Ă���B
�L�r�L�r�Ɠ��̉�]�������A���������ƃ^�P�m�R�낤�Ƃ��邨����B
�y�n�ɑ����Đ����Ă��邨����B����Ȃ�����D���I
�݂��ɓd�b�ԍ����������������B�^�P�m�R�̍Ő�����҂��Ƃɂ��悤�B
�����̐l�B�̍������̂ق��ɁA������@���Ă����Ԃ̔��������������ł���B
�u���̉Ԃ̖��O��������Ȃ����ǁA���m���Ă邩���H�v
�u�m���Ă܂��Ƃ��I�v
�u����Ƃ���Ƃ���́����A�Z�Z�A�Z�Z��v�ƃ������Ă������B
����ɍ��t���Ă����B���̐A���Ɋւ������t�ɉ������ȁE�E�E�Ɩʔ�������������B �@
|
 |
���ɂǂ����Ă����O��������Ȃ��Ԃ��������B
������ɂ͂���������ĂƗ��܂�Ă���B
�A��Ē����B�L�C���W���E���E�z�g�g�M�X�Ɏ��Ă��Ȃ����Ȃ����A�z�g�g�M�X�͏��H�̉ԁB�ꏏ�ɍ炢�Ă���̂��N�}�K�C�\�E�E�F�J���A�Ԋ���5���Ƃ������Ƃ���A�u�L�������v�Ɣ�������B
����50 �Z���`�̃L�������ȂǍ��܂Ō������Ƃ��Ȃ��B
������ɓd�b���āA�u�L�������A�����_����_�������_���̃L���E���ł���v�Ɠ`����B
�i�L�������A�ł͒ʂ��Ȃ��B�����̂��A����͂̂��A���̂��A�Ƃ������悤�ɘa���ʘb�\�̐^�������ē`���Ȃ���
�A�N�z�̑���͗������Â炢�炵���j
�����E�L������
�L�������i�����ACephalanthera falcata�j�����ȃL���������̑��N��
�n�������̈��@
�G�ؗт̒n���ɂ���ۗނƋ����W�ɂ���B |
�@�@�@�@�@�@���R�̕�炵375�@�@2018.4.16�@
�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
 ����Y��Ȃ��Ł@ Forget me Not!
����Y��Ȃ��Ł@ Forget me Not!
��ォ��ߐ{�ɈڏZ���Ă���16�N�O�̓~����t�ɂ����Ă̂��ƁB�J���g�@���̐M�҂ɂ����������������Ƃ����ߗ׃g���u���Ɋ������܂�Ă��܂����B�Ȃɂ���펯���قɂ��Ă���B�b���ʂ��鑊��ł͂Ȃ������B
���_�I�ɐh���v�������Ă��������ɁA����ƂȂ������Ă����������ߏ��̏��ꂳ�܂��A�������܂����\��ł�����̂�͂��Ă����������B
����́u�z����v�B�z���̃����[�t���B���̎q�̔��݂ɔ���̏㒅�i���Z�H�j���܂Ƃ��āA�̕���̌G���ɂ��������ς����Ă���B�ǂ����I�ƌ�������đ���A�E�܂������Ƃ��̂����Ȃ��B
���ꂳ�܂́A
�u�������N�łW�O�ɂȂ�̂���B�Z�Z�q����ɂ́A����܂ł��낢��Ƃ����b�ɂȂ�܂����B
���肪�Ƃ��ˁB����ȕ���������������Ă����H�v�B
�S����a�݁A�s�������Ă���̒��Ɨ����ɁE�E�E������B�����̂悤�ɗz�C�œ��₩�Ȕޏ����A�����̂悤�ɘN�炩�ɁA��������㵂̐F���ׂȂ���_���Ȋ�ł���
���������B
�܂����I�܂����I�P�Ȃ�L�O�i��ˁB�܂����I�`�������ł͖�����ˁB
����Ȃ��Ƃ����ɏo����킯���Ȃ����肪���������āA���Ԃ̂��C�ɓ���̏ꏊ�ɁA���ł�������悤�Ɋ|�����B
�ߐ{�̖�͏tࣖ��B
�������Ԃ��炫�A�����h��A�G�߂̕��݂��m���Ɋ�������4���B
����ݍs���̂́A�l���܂��B
�@
|
 |
���x�̜��ł��Ȃ��A���������ł��Ȃ��A�Ԃ��ۂ������̂ł��Ȃ��B
�z����E�E�E�B
���₩�Ȃ��Ƃ��D���Ȃ��̐l�炵���B
 �@�킷��Ȃ��� �@�킷��Ȃ��� |
�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@ ���R�̕�炵374�@�@2018.4.12�@
�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@�@ �������A���H�֍s�����@�E�E�E�E�E�i�q�����{�̂��m�点�ɂ���悤��
�������A���H�֍s�����@�E�E�E�E�E�i�q�����{�̂��m�点�ɂ���悤��
�@
�@�@�Ù��_�ގ� (�ՍϏ@���S���h�̎��@�B�{���͎߉ޖ��B)
�֓��n��������������Ȃ����A�����^�ގ��𗷂���g�i���S���̂b�q�i�i�q�����{�j�����f����Ă���B
������11��23���ɍg�t�����ɏo�����邪�A���N�͓߉ϐ�͔Ȃ̎}�������y���ނ��łɑ��������Ă݂��B
�V�ɂ͂܂������A���̗т��ނ��鉾���́A�����̂悤�ɐÂ��Ɍ}���Ă����B
�@ �E�ؑ�����͂�Ԃ炸�Ėؗ��@�i�m�ԁj
�����͉ԍՂ�B
�_�ގ��ł������ɍ�����Ò����������Ő��߁A�O���̕������F���Ă���̂��낤���B
�q���̂���A���e�̑㗝�ŕ�ɂ��Q�肵�A�����̂�����������������A�Ƃ��玝���Ă�������ʂɊÒ�������Ă�����ċA�����̂��v���o���B
���X�Ƃ��ė��e�ɕ��ĊÒ����Ƒ��ɔz��A�c����Ƃ̎��͂ɎT���Ă����̂́A�֏����̂��܂��Ȃ��������̂��B
�@
|
 |
�i���ׂ̂������܁B��ɔ~���炫�܂����B�j
(���A�ł��B
�ӂ����炵���Ԏp����A����͈ǂł��ˁj |
�@�@�@ ���R�̕�炵373�@�@2018.4.8�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
 ��ɏt���炫������
��ɏt���炫������
�@
|

�@ ���N�a�Ƌ����Ŏ�����A�n���ɖ��߂Ă�����b�オ����A70�{�܂łɑ������J�^�N���B
�@�@�@�@�t�̗z�ɁA����t��������Ԃ��āB |
|

�@������������݂̃X�M�i�B���ł���͍̂��̗t�B |
�@

�@�@��֍炢�Ă��A��֍炢�Ă��A�O�֍炢�Ă��A
�@�@�@�@�@����֑��� |
|

�@�@�@�L�̖ڑ��@�킪�L�̖ڂ̂悤���B |
�@

�@�@�R���Ӎ��@�X�v�����O�E�G�t�F�������̂ЂƂB
�u�t�d���v�Ƃ�
�~��n���ʼn߂����A���͂̎��X���t���o���O�A�����͂₭����o���Ԃ��炩���A�ʎ������点�鑐�Ԃ̑��́B�t�̂͂��Ȃ����́A�Z�����B |
�@�@�@�@�@�@�@�@���R�̕�炵372�@�@2018.4.5�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@ �@�ߐ{�̏t������ �@�ߐ{�̏t������
�����������������Ƃ��B
�e�ʂ�����Ă��邩��ƁA�F�l�����Y�́u�ߐ{�̏t�����ǁv��͂��Ă��ꂽ�B
�R�k�T�C�Y�ƌ����ΕЎ�ł͂��݂���Ȃ��قǂ̂̑������B
�������n�E�X�ő����͔|�������̂����A�t�̓�����ɂ��鍡�̋G�߂ɂ́A�ق�̂��݂������Ď������̗ǂ�
���̂��ǂ������ӂ��킵���B
�킪�Ƃ�2�{�c���A�c���4�{�͂��ߏ�����ւ��������B
�Ԃ̕c�����ǂɉ����A���ǂ����������T���_���ɕϐg���A���萻�̒Е��ɁA�����Ă����݂ɂȂ��ĕԂ��Ă���B
�����������݂̂͂�ȂŁI
����͓c�ɂ̃X���[�K���B
�@�@�@�@�@�@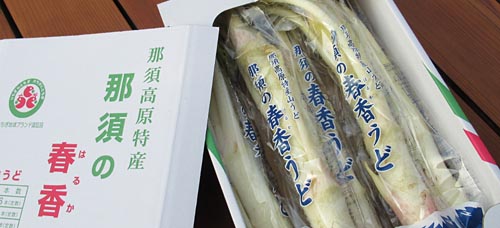
�@�@�E�@���Џo�łēߐ{�̏t���̖����������V�Ղ炫��҂�u��v�̕t�����Ƃ�
�@�@�@�@�@�@*�@��|���̂Ă�܂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�͂��߂���낿���Ȃ��ς��ρA�F���������̂ŊW������B
�@�@�@�@
(�ˑR�A�����̗F�l���P0�N�Ԃ�ɗV�тɗ��Ă��ꂽ�B���������ē����A���ڂ�������ł����j
�@�@�@�@ ���R�̕�炵371�@�@2018.3.31�@
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �����āA�t�̑�|�����@
�����āA�t�̑�|�����@
 �����C�ł��傤���A���ׂ̂����l�B����̒��10�{�炫�܂����B �����C�ł��傤���A���ׂ̂����l�B����̒��10�{�炫�܂����B
�@
�����������g�̂ɟ��݂��Ă�����́A����͎q���̂���̎v���o���낤�B
���̐��Ƃ͒����R�n�̐^�́A�܂��邢�~�n�̎R����ɂ���B
�Ƃ����̑�|���͈�N��2��A�t�ƏH�������B
�t�͂��傤�Ǎ�����A���x��̐��Ղ�̑O�ŁA�悤�₭�������a�炢�ł��āA�g�̂��y�ɓ�������悤�ɂȂ鎞�����B��q���J�������V������C�ɓ���ւ���
�̂��������āA�}�ɍ��~���L���������B
�߂����ɓ���Ȃ������~�̉�艏���猩��r�ɁA�Ԃ��������ł���̂�O�������߂Ă������̂������B�����͂܂��d�����Ȃ��B�~���̐������ق�̏���
�����B�H��11��3���ɁB�n��������i�����A����������O�ɏ���O�ɏo���A�݂��ɗ��Ă����Ě����B�����ɑ傫�ȓ���ɂ���
�A�H�̏��߂Ɏ��n�����哤���ςāA���X�Â�����n�߂Ă����B
�Ȃ����Ƃ̒����A�A�h���i�����̏o���ςȂ��Ƃ����ɂȂ�A���̂��̌\�p�̂���v�w�ł͂��������A��������g��������ŖZ��������
��������Ă����̂��v���o���B
���R�q�����������̋C�������`�����A�V�тɂ��s�����^����ꂽ�d�������Ȃ��Ă��� �B
�����̈���́A�ǂ����������B
�������Č������āA�L���ۂ��Ȃ��ĉ����ɖ���A�ɂ�Ƃ肪���V�т܂���Ă���B���܂��ɓ܂ňꏏ�������B
���N�̏t�͍��������炵���B
��������ς邱�ƂɑS�͂�s�������_�Ǝ��́A���߂����Ă�����d���̌v��𗧂āA���s����E�E�E���̎�����͋�����Ƃ����邷��Ɛi��ł����B�i�͂��j
�Еt���͑�D�������|���͌����Ȏ��E�E�E�E�����������ɂЂƕ����̗\��ő|��������\��𗧂Ă��B
���̂��Ɨ���̂́A���O���̓��X�B�ꏊ�ƕW����ς���قڈꂩ���͊y���߂�B
|
�@�@ |
|
�@�̓��������̂Łu�������v�ƌĂ�ł���L����������Ă��āA�f�b�L�Œ��Q����B
���܂ɔ��ɍ��荞��ł���̂����Ă���ƁA�͂����đ����ɂ���Ă���V�W���E�J����_���Ă���悤���B
�����`�[�Y�����Ă��Ă��A���a�̖��͂ɂ͏��ĂȂ��炵���B
���낿���A���h���т̉��`������ł���A���̎��݂��Ă�����B |
�@�@�@�@
���R�̕�炵370�@�@2018.3.26�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
 ���ԂƂ������� ���ԂƂ�������
���̂Ƃ���A�ӁH�@�Ƌ^��Ɋ����邱�Ƃ��������B
���́i�P�j
��s�̂`�s�l�ȂǂŁB
����ŏ��Ԃ�҂��悤�₭�p���ς܂����̂ɁA���̑��ōēx��̍Ō���ɕ��тȂ����l������B
���鎞�s�v�c�Ɏv���A���̐l�ɐu���Ă݂���A�i�����̂����ނ��܂܌��ɏo���Ƃ��낪�A���l�ۏo���B�j
�u�����āA�p������ς܂����̂ɁA���̂܂܋@�B���L����̂��Č��̐l�Ɉ�������Ȃ��H�v
�ƕԂ��Ă����B
���܂܂ŋL���Ɉ����o���ɂƁA�d�˂ėp�����ς܂��Ă������́A�����܂������������̂��E�E�E?
���́i�Q�j
���̉w�̃g�C���ŁB
��������������A���l��������ɕ���ł��邪�A�ق�̂P���҂ĂΎ����̔Ԃ�����ɂ���B�i�悭����b���j
�����։䖝���M���M���Ƃ������l�q�́A7���炢�̎q������F��ς��Ĕ�э���ł����B
�擪�̂��w�l��
�u�����A��ɓ���Ȃ����ȁv�Ƃ��̎q���ɏ��Ԃ������Ă�����B�����܂ł��ǂ�����b���B
�������A���ɕ���Ă����ʂ̏��̐l���i�h�̗��ɋC�t���Ăˁj�i�l�A�Ƃ͌h�̂����j
�u���A���̎q�ɏ����Ă��������A���̏��Ԃ��ЂƂx���Ȃ�������Ȃ��́B�������ɕ���ł��Ȃ��ŁA��Ԍ��ɕ��ёւ��Ȃ����v�Ƃ܂������Ă��B
�������B
���̐l�ɂƂ��Ďq���ɏ��Ԃ�����̂́A���ɐ������˂邱�ƂȂ̂�
�@�@�@�E�E�E�E�E����قǐ؉H�l�܂��Ă���悤�ɂ͌����Ȃ��̂ɁB
�v���o�����B
��錧�ɂق�̈�N�قǏZ��ł������Ƃ�����B���̊ԁA�Ԃő�������{���ɓ���̂ɁA�K���Ƃ����Ă����قǖ{���̎Ԃ������Ă���Ă����B
����܂ŋC�̒Z�����l�̃h���C�o�[�̊Ԃ�D���Ă��������Ɖ^�]���Ă������́A�S����������̂��B
�������ȁB
�����������Ƃ̐ςݏd�˂��A���̒n��A����̕��������グ�Ă������ƂɂȂ�̂��A�Ǝv���������Ȗł̐����B
�����ł̐������A����15�N�ɂȂ�B
|
 |
�������ƒ���ق�����Ԃ��Ă�����A���D�̎m���ׂɂ���Ă����B
�ق��2���[�g���̏��܂ŋ߂Â��ė��āA���̎茳��`�����ށB���������B�~�~�Y��T���Ă���̂����H
�I�P�������낻��o�Ă����ȁB���V�т��Ă���������ǁA���������A�����Ԃ̕c��H�ׂȂ��ł�����B
�@�@�@�@�L�W�@�i�L�W�ڃL�W�ȃL�W���j
�햼�ŕ�����悤�ɁA���̒��͓��{�̌ŗL��B
���܂��ɓ��{�̍����ł�����B
�����ǁA�u�H�p�v�ɂ���Ă���B
������H���鍑�Ȃ̂��A���{�́B
|
�@�@�@�@ ���R�̕�炵369�@�@2018.3.20�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �������B �������ō炩�Ȃ��ŁB�@�i���C���x���g�E�A�[���[�Z���Z�[�V�����j
�������B �������ō炩�Ȃ��ŁB�@�i���C���x���g�E�A�[���[�Z���Z�[�V�����j
�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@
�Ԋ��݂͂�ȓ������
2���̊����ŊJ�Ԃ��x��Ă������炫�̃��b�p���傪��Ăɍ炫�n�߂��B
�뒆�́A���F���Ԃ̂��̐������S����1000�{�I
���̂��ƃ}�E���g�t�b�g�A�A�C�X�t�H�[���X�Ƃ����������̐��傪���b�p���f���A�Ō�ɔӐ��̃L�������b�g���炭�̂�4�����{�B����3000�{���炢���B
�����炯�A�������炢�āA�ƋG�߂̕��݂Ɉ���J����O���B
�����������Q���Ă����Ȃ��B
���̌��̒��Ō��������́A�Ɋy�ɍ炭�Ԃ̂悤���B
�@
|
 |
�C��20���ƁA�v�������Ȃ��g���������������B
�~�����Ԃʼn߂����Ă����[���j���[�����O�ɏo���A�����ڂ��������Ă���B
�Ԃ̋ʂ����сB
�@ |
�@
���R�̕�炵368�@�@2018.3.15�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
 �@������
�������� �@������
��������
���r���L�тĂ悤�₭������T���_���ŕ�����悤�ɂȂ����B
������̍��y�����ɂႮ��ƒ��C�ɂ܂Ƃ����A���̕s�����Ȋ��G����悤�₭������ꂽ�B��������t����������������u�Ԃ��B���邠��B
�Ē��t�L�����Ă����ꏊ�ɁA���̃g�E�������t�L�m�g�E�����B�@�@
�������ꂵ���ȁA����͂����������I
�~�̊Ԑg�̂ɗ��܂����ŏ��������˂ăt�L�m�g�E�̓V�Ղ�I7����E�E�E�E�����4��3�ɕ�������E�E�E�E�E�v��4�A����3�B
�����ɂ���ƂP�]�鐔���͂��낢�날�邪�A�f���Ɋւ��Ă͂��ꂪ�����Ɠ��Ă͂܂�B
�t�L�m�g�E��9����5��4�ɕ������A11����6��5�ɁA13����7��6�ɁA17����9��8�Ɂ@�E�E�E�E��
������f����D���B
���܂�������e�L�ɓn���邩��B�@�@�i���̏ꍇ�̃e�L�́A�a�̎R�قŁh�e���Ȃ鑊��A�܂��͔ށE�ޏ�"�̂��Ɓj
�������A�u���O��l�v�̂�������v���o���Ă��܂����B
������������ȂǂƋC�Â��Ă����Ȃ��悤���B�߂ł����B
 �@���������Ⴂ����
������ �@���������Ⴂ����
������
��O�G�f���u�Q�v�́A�����ɂ���Ɨ]��Ȃ��B����͎₵���B
�@�@�@
�@�@�@ �@�@ �@�@�@ ���R�̕�炵367�@�@2018.3.12�@
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@ ��`�A�����傤�����B
��`�A�����傤�����B
����Ȑ������������悤�ȋC�������B
�u����A�����Ԃ����Ƃ��̕����ɋ����ȁ[�v�@�u�ق�܂�v�@�u�������납�v�@�u���N�̏H���炾������Ⴄ�H�v
�u�������������O�֏o������`�v�@�u�݂�Ȍ��Ă�A����Ȃɉԍ炩���Ă�����v�@�u��A�Ƃ������H�v�@�u������Ǝc���Ă��邯�ǁA�������v�݂�����v�@�u���`�o�����ł�����E�E�E�v
�@�u�ǂ���ȁv�@�u�ǂ�����Ȃ�����v�@
���������������B
���Ƃ��Ύw��ł܂ނ�50�����炢�t���Ă��邭�炢�E�E�E����������u�����ԁE�H�q���v�Ƃ͂悭���������̂��B
�|�b�g�ɔd���A�������Ő��������A�ǂ�����o�Ă�������Ԉ����A����傫���|�b�g�ɐA���ւ��A�z�[���Z���^�[�Ńr�j�[�����Ă��ĊȈՉ��������A���[�J���ĉ��x�߂��A�엿������āA����ɑ傫���|�b�g�ɐA���ւ��āE�E�E�E�Ƃ���
��Ƃ𑱂��Ă�������5�����Ƃ������́A��ɂ��̃A�C�X�����h�|�s�[�̕c�������痣��邱�Ƃ͂Ȃ������B������Ɣ�ꂽ�B
���̐S���|�s�[�������@���Ă��ꂽ�݂����B
�u��ꂽ�C�����v�Ɓu�o�����ł����v�Ƒ����|�s�[�̎v�f���A�p�`�b�ƋŌ�������3���̒��������B���낻��A�Ԓd�ɂ��ڂ肢�������āA�@�i�ڂ��͎̂������j
�L�X�����y�̒��ɂ����܂肢�����������B�u�݂�ȁI���ꂩ��O����I�v �@�E�E�E�E�E�u��`���v
�u�����q���ˁ[�v�@�E�E�E�E�E�u�����ˁ`�v
�u�O�͊�����`�v�@�E�E�E�E�E�E�u�ւ�������炾���B���O�����ăA�C�X�����h�E�|�s�[�Ȃ�v
�W���ʐ^���B�������Ƃ����A���Ă��ꂩ���Ƃ��B�@�@�@
|

|
�S����150�{�B
����ő���邩�ǂ����͐A���Ă݂Ȃ��ƕ�����Ȃ��B
���Ȃ݂ɁA�������H�K�[�f�i�[�Ɏ���ĉԕc�̍œK�Ȑ��Ȃǖ����B
�^���X�ɂ��܂��Ă���m���̂悤�ɁA������Α����قǗǂ��̂��B |
���@�A�C�X�����h�|�s�[�͎��Y�����A������L�B�ł�����Ȃ̎q���ۂ���ˁB
�@�@�@�@�@�@���R�̕�炵366�@�@2018.3.7�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
 �W�߂��@�E�E�E�E�@�t�N�W���\�E�̏ꍇ�́@
�W�߂��@�E�E�E�E�@�t�N�W���\�E�̏ꍇ�́@
 �@
�i�L���|�E�Q�ȃt�N�W���\�E���j �@
�i�L���|�E�Q�ȃt�N�W���\�E���j
�@���@����
��̂��������ɐႪ�����c���Ă���̂ɁA�C�̑����t�N�W���\�E���炫�n�߂��B
���������݂��������t�̋��w�i�ɁA���Ɖ��̃R���g���X�g���������B
�t��Ԃɍ炭�Ԃ́A�y���~�Y�L�A�����~�Y�L�A�}���T�N�A�T���V�����A�_���R�E�o�C�E�E�E����ɍ̉ԁB
�ǂ���G���n�߂����͂̔��ΐF�ɉf���ďt���������Ƃق��A������Ă���悤�ɂ�������B���t�ɉ��F�̉Ԃ������̂͂Ȃ����낤�H�K���Ӗ�������͂����B
�Ԃ͂Ȃɂ��l�Ԃ�����邽�߂ɍ炢�Ă���̂ł͂Ȃ��B
��(����j�����̐���Ɉ����p�����߁A�Ђ�����w�͂𑱂��Ă���̂��B
�����⒎�Ƃ������}��҂��Ăэ��ނ��߂ɁA���܂��܍������߂��炵�Ă���B���Ƃ��G
�E������U��܂�
�E�Ԃ̐F��ω�������
�E�Ԃ̌`��ς��A����̒��Ɏ��܂�����B�ȂǁB
�����u����Ԃ���A�Ђ����璎�Ɂi�}��ҁj�ɕ�d�A���邢�̓A�s�[��������̂���B
���̂Ђ�����Ȏv���⌒�C���ɁA�S��������邱�Ƃ�����B
���̎����A���������������n�߂鍩���́A�A�u��n�G�B
�����̒������́A�i�l�Ԃ̌���j���F�̒Z�g�������₷���B���F�ɕq���ȒP��ƌĂ��튯�������炾�B
���̃t�N�W���\�E�A��������閨�������Ă��Ȃ��B�������蒎�����Ɍ������₷�����F�ł킪�g���A����U���Ă���Ƃ����킯�B
�������A�ڂ̎��d�g�݂��قȂ�̂Ől�Ԃ̖ڂŌ��鉩�F�́A���̖ڂ�ʂ��Ɛ₤�����Ɍ�����炵���B
�Ⴆ�p���W�[�̉Ԃ�����ƁA
���ǂ𑱂��āA���܂�J���t���ȉԂ������Ă���p���W�[�́A�Ԃ̒��S�͂ǂ���u���F�v�B
����͍�������c�l�̋�J��Y��Ȃ��A�p���W�[�̐g�̂ɍ��荞�܂ꂽ�ɐB��킪�\�ɏo�Ă������́B
�@���@�����@�E�E�E�E�@�t�N�W���\�E�̉Ԃ̓p���{���A���e�i
�悭������p���{���A���e�i�����ĂĂ���łȂ����A�t�N�W���\�E�́B���̐́A�̂ނ����B�����Ɛ́B�����̎��ԂɏK�������Ƃ�����B
�E�������̕����I�Ȑ����ɁA
�u�œ_��������邢�͓d�g����ƁA�������ɔ��˂��Ă���͕��s�ɂȂ��ďo�Ă����v�Ƃ������ƂȂ��Ă͂킯�킩��Ȃ����̂��B�t���^�Ȃ�B
�u���s�ɓ����Ă�������d�g���A�������Ŕ��˂���ƁA�œ_�ɏW�܂�v���ƂɂȂ�B
���s�i�ߎ��l�I�j�Ɏ��z�̌����A�A���e�i�ʂŔ��˂����Ԑc�i�œ_�j�ɂ��̔M���W�߂�B
��������ƊO�C�����g�����Ȃ�A���������A�ɐ�������B�����l�����B
�₪�ăf�R�{�R���̎�܂ɐ�������A�Ƃ������ƂÂ��߁B
�z��������ƉԂ��J���A�Â��Ȃ�ƉԐc����낤�Ƃ��ĉԂт����A�a���`�̉Ԃт�ʂɂȂ�B
�܂�Ŏq��̂��`�ɂ����炱���Ȃ�A�Ƃ����悤�ɁB
�@�E�@�܂���Ȃ��t�ƂȂ肽�艩�̉Ԃ̂܂ق�ɊJ�����炩�ɕ�
* ����^�Ԃ̂́A�����̋a�B
��ɂ̓G���C�I�\�[��(Elaiosome�j���t���Ă��āA�����
�������Ɠ����Ă����a�ւ̂��ق��сA���ʒ��B
���̌��ɂ��ẮA�܂��̋@��ɁB�i�X�~���̃G���C�I�\�[���ɂ��Ă��������B�j
|
 |
��� �@�i�f�R�{�R���j�i�������݂����j
�܂��킪�n���Ă��Ȃ����̎����ɍ̂�d�����Ȃ��ƁA��̂������������������o���Ă�������Ȃ��ƂɂȂ�B
����͂���ŗǂ��̂����A��͂�Q��ɂȂ��č炭�Ɠ��₩�Ȃ̂ŁB
�@ |
�@�@�@�@�@�@�@���R�̕�炵365�@�@2018.3.3�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �ӂ����т݂����@�E�E�E�E�E�@���r���O�̃~�j�؉��ł͂��܁B �ӂ����т݂����@�E�E�E�E�E�@���r���O�̃~�j�؉��ł͂��܁B
���c�͔̍|���B�s�̂̂��̂���x�������Ďg���A�������𐅂ɐZ���čĂѓ�������̗ǂ��ꏊ�ɒu���Ă����ƁA�V�����肪�o�Ă��āA�u���������v�Ɖ����������邭�炢�f���ɐL�тĂ����B�ؓ��Ƒ������ǂ��A�ݖ�Ƃ��ĂƂĂ��֗��B
�@�@
�@�@�@����2�x�ځ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E��3�x�ځ@
�@�@�@�@�@�E�@�~�̔��Ət�̂����܂̌Ђ���̔@���̗z�̂�������͂炩�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@
���R�̕�炵364�@�@2018.2.27�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �@�F���{�[���y���E�E�E�E�@�Q���낪���ď�����{�[���y�����~������ �@�F���{�[���y���E�E�E�E�@�Q���낪���ď�����{�[���y�����~������
�����̎����ς���Ă����B����ɂ��ƈ꒼���ɒ���ڎw���Ă����Ⴂ���낪���������B
���▰��͘Z�ʂ̃T�C�R���B
�R�����ƈ�ʂ��ЂƖ��肵�A���̖ʂ͈Â������Ŗڂ���āA�悵�Ȃ����Ƃɓ����߂��炷���ԁB
�����Ă܂��V�����ʂɓ]�����E�g�E�g�Ɩ���B
�����Ē��̋C���́A����͂ǂ��]�Ԃ��قƂ�ǃ��V�A�����[���b�g�ɋ߂��B
��������B��������B��������B��������B���܂ɂ��������B���`�ށB����Ȓ��̌J��Ԃ��B���������N���Ă����̎��ԁA������ǂ����悤���B
���̒������܂��܂ȍl���ň�t�ɂȂ��ɁA�v���t�������Ƃ��}���Ń����ɂ��铹��~�����ȁA�Ƃ��˂Ďv���Ă����B�����ŁA�v�������͉̂F���{�[���y�����I
�@�F���{�[���y���G�@
�F���D�̂Ȃ��̖��d�͏�Ԃł̓{�[���y�����g���Ȃ��B�F���ɐl�Ԃ𑗂荞�m�`�r�`�͖c��Ȏ��ԂƔ�p�������āi����ɂ�10�N�̍Ό���120���h���Ƃ������Ă��邪�j���ł��ǂ��ł��A�F���ł����̒��ł��C�����}�C�i�X�ł�300���̍������ł��t���ɂȂ��Ă��A�ǂ�ȕ\�ʂł��������Ƃ̂ł���{�[���y�����J�������I�{�[���y���̒��ɒ��f�K�X���[�U���A���̃K�X�̈��͂ɂ���ăC���N���[�ɑ��肷�炷�珑����Ƃ����㕨�B���̈��͂�3000�w�N�g�p�X�J���A�܂�n���̑�C�̖�3�{��
�B�C���N���g�͔S���������̂ŁA��������100�N�ȏ���g�p�ł���炵���B
 ���ꂪ�F���{�[���y��
�i�������j�t�B�b�V���[�А� ���ꂪ�F���{�[���y��
�i�������j�t�B�b�V���[�А�
�@
���l�i��6��~���炢�B���������̂ɋ����ÁX�̎����A�������钆�̂��ꎖ���A100�ςŔ������m�[�g�ɏ����L�����߂�
6��~�����ʌ����ł��Ȃ���E�E�E�E�E�B
�l�������炵�����̂́A���Ǘ��������ǂ���́G
0.7�~���̃V���[�v�y���V���ŁA�a�̔Z���B
����ŕM�����キ�Ă��A�X���X���v���̂����������c�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B
���̘b�ɂ͌���k�������āA�u10�N�{120���h���v���₵���A�����J�ɑ��āA���V�A�̓��P�b�g�Ɂu���M�v�𓋍ڂ����炵���B�����I�ȑΉ�����̂������V�A�ƁA�Z�p�̐��������ĊJ���ɐg���ł����A�����J�ƁB����́A���n�l�ԂƂ����łȂ��l�Ԃ̍l�����Ɏ��Ă��Ȃ��H
�F���{�[���y���̊J����ʂ��āA�V�����Z�p�����̂ɂ���
�B����͈Ӗ������邱�Ƃ��B���̋Z�p���u���P�b�g���p�v�̘g���щz�������ʂɗ��p�����E�E�E�E�Ȋw�Z�p�̔��W�Ɋ�^����B�E�E�E�E�ŁA���̍s��������́H�Ȃ���U�����̍l�����Ɏ����ꂽ��A���̍l�������Ɉَ��Ȃ��͈̂ӎ����Ĕr������A���n�j�̂킪���_�Ɏ��Ă��Ȃ����Ȃ�
�Ɗ��������B
���R�̕�炵363�@�@2018.2.3
�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �@�@
�U�������܂��A�Ղ�Ղ�l���邱�� �@�@
�U�������܂��A�Ղ�Ղ�l���邱��
���̋C���}�C�i�X5���B��������ɂ�ċC�����オ���Ă����B
�A�Ɨz�A�e�Ɠ����̍�������ɍۗ����Ă��āA�t�̒����͂�����Ċp���o���A�܂䂢����̓�������Ⴊ�͂����Ԃ��Ă���B
�������̂Ȃ��Ղ�Ղ�B�l���Ă��邱�Ƃ��A�������������ςݏd�Ȃ��Ă����B
�E�@�������Ȃ��Ă��ǂ����ɂ́A����������ǂ��̂��낤�B
�E�@�������͖̂����E�E�E�E����͖����̂�����̂��B
�E�@���o�����^�C���W�����{�~�j�E�E�E�E�傫���̂��������̂��B
�E�@�l���L�������Ă���̂��A�L���l�������Ă���̂��B
�@�@ �������Ă��������Ă͂���Ȃ��A���C���h�L���b�g�����������A�ɗ����B
�E�@�ۂ��ۂ����p�k�ɏ���Ă��̂ЂƐ��߂����킯�ɂ͂����ʂ��L��B
�E�@�Ԃ̕c����Ă�̂́A�J���Ȃ̂��A�x���Ȃ̂��B
�E�@�S�����ɂ��炸�B�Ȃ�S�͂����ǂ��ɂ���̂��낤�B
�E�@�u���Ȃ����v�͔߂����A�������A�������B�����͂ǂ���g�������B
�E�@�F�m�ł��Ȃ��Ȃ�̂ɁA�Ȃ��F�m�ǂƌ����̂��낤�B
�E�@��N���o�̂�����ɑ����Ȃ�̂́A���̉�]���x���Ȃ�A���삪�̂낭�Ȃ邩�炾�B�V���ΐ����_�B
�E�@��s�����n�k���N����\���́H����30�N�Ԃ�70�`80���B�����ɍ��w���z������������̂͂Ȃ��H

�@�@�@�@���R�̕�炵361�@�@2018.2.14 �@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �Ȃ��A�߂̈ӎ����������̂��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�Ȃ��A�߂̈ӎ����������̂��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
|
 |
�[�d����̂�10���Ԃ�������B
�[�d�I���̂��m�点���Ȃ��B���������A�d�r���u�j�b�J�h�d�r�v�Ǝ���x��B�N���[�i�[�ł͂Ȃ��āA�|���b�V���[�Ƃ������O�����Ă���B
�i�v���X�`�b�N���ɂ܂Ȃ����H�j
�������B
�Ȃ����{�̉Ɠd���[�J�[�́u���C�@�v�Ȃ���̂����Ȃ��̂��B�ȂǂȂǁA���낢��l���Ă�������ǁA�v�����Ĕ����A���̂Ƃ���͐����������B
���C�����łȂ��āA���ʏ���䏊�̃V���N�̂��ݓ������������ꂢ�ɂł���B
���́A���̃j�b�J�h�d�r���ǂ��܂Ŏ����A���B |
�����C�̏���ǖʂ�|������̂ɗ~�����ȁE�E�E�ƍl���͂��߂ĉ��N�ɂ��Ȃ�B
�|���@�A�①�ɁA����@�E�E�E�ƉƓd�̂����b�ɂȂ閈�������A���́u���C�@�v�Ȃ���̂Ɏ��L���̂ɁA���N畏����Ă����̂͂Ȃ����낤�B��Ǝ�w�̎����u��B���g���Ă����C��|������v�ƍl���������ŁA�S�̒�ɂ���Âт���w�̐S���Ȃ���̂ɂ����Ǝx�z���ꑱ���A������Ȃ�ł�����Ȏ蔲���͂ł��Ȃ���ȁ`�ƁA���ꎩ���̓��X�𑗂��Ă����B�����ōl�����B�|�C���g����I�|�C���g�𗭂߂Ĕ����A���̂����₩�ȍ߂̈ӎ��Ȃǖ����ł����ȁI
�u�ۂ��ۂ��ۂۂv�Ɗy�V�ŗ��߁A�悤�₭����2���A�����ʂ�܂ŗ��܂����Ƃ���Ō��蔭�Ԃ����B
�Ȃɂ���A�ꌎ�͋N�������̕��ϋC�����}�C�i�X4�����������A���t�߂��Ă��܂��܂������������Ă���̂�����B
�@�@�@ ���R�̕�炵360�@�@2018.2.9
�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
 �c������̂͂ȂɁH�@�E�E�E�@�����炬�́A�⌾��������
�c������̂͂ȂɁH�@�E�E�E�@�����炬�́A�⌾��������
1���̌ߑO6�����̊O�C���̕��ς́A�X�_���S���B��ԉ����������}�C�i�X�P���B��Ԋ��������̂��X�_���P�Q�D�T���B
����ȂɊ����~���o���������Ƃ����������B
�����͏t�̐ߕ��B���낻��t�̒��������������Ƃ���B�����ɔ��Ă����E�E�E�B
2���͓�l�̒a�����Ȃ̂ŁA�⌾�������������B
���łɏ����Ă���⌾�����J�����A��N�O�̍l���ɕύX���Ȃ������m�F���A�܂��V���������ɂ��܂��ĕ������錎�B�����Ƃ���l�Ƃ��A�⌾�̓��e��
�u����ɂ��ׂĂ��c���v�Ȃ̂�����A������Ċm�F���邽�߂����ɕ�����j���āA�ӂ�ӂ�������̂������Ă���B�������A�v��B
�����̃v�����^�[��f�Ă��̔��A�a���̂��ꂱ��A��Ƃ��ĂׂȂ����g��ق�̏��������B
����Ȃ��̂��c����Ċ��������ȁB
�E�@�z�̍��̐�����ӎ��v�̖ڂ̕��m�̂��Ƃ���������т�
�@�@�@
�@�@�@�@�Ⴊ�Z�����ۂ��Ղ������킩��܂����B
�@�@ �@�@�@�x���ɋA��A��}���ŏt�����̋���u�߁A�M���t���C�p�����܂����Ղł����I
�@�@���R�̕�炵359�@�@2018.2.3 �@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �@
1,807�@�Z���`�������[�g���̕������� �w�X�J�[���b�g�x �@
1,807�@�Z���`�������[�g���̕������� �w�X�J�[���b�g�x
�@�@�@�@�@�@�@�@�@The Sequel to �wGone With The Wind�x
�A���N�T���h���E���v���[�@�Xꢎq�@��
|
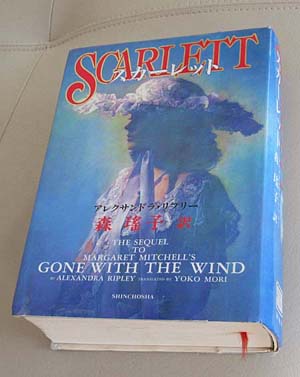 |
����͂������{�ŁA�c22�Z���`�A��15.5�Z���`�A����5.3�Z���`�̑傫���B�̐ς́F1807Cm�������[�g���B
�܂�傫���y�b�g�{�g����t���炢
���낤���B
�Ⴄ�̂́A�y�b�g�{�g���̒��ɓ���̂��A�R�[���₨���ł͂Ȃ��āu�����v�ł��邱��
�B���܂��Ƀy�[�W��1096��������B
�d����1.2�L���O�����łقƂ�ǒЕ��B�ƂĂ����Q���Ă�ǂ݁A�����Ȃ����牮���ɕ����A�Ȃǂǂ��������͂ł��Ȃ��㕨.�i�܂��܂��@�y�`���ɂȂ邶��Ȃ��j�Ў�ł͎��ĂȂ�
�قǏd���A���������^�тɂɂ͗�����g���Ă���B
���N�����ƂɁA�����̊O�o�ł��Ȃ�������I��ł��̖{�Ɏ��L���B
���́w���Ƌ��ɋ���ʁEGone With The
Wind�x�i�}�[�K���b�g�E�~�b�`�F����j�̑��҂Ƃ��ď����ꂽ�{���B
�@ |
��������߂ēǂ̂́A���w���̂��낾�����B�l�Ԃɑ��铴�@�͂������A���Ȕ��Ȃ��邱�Ƃ�m��Ȃ��P�Q�A�R�̂���̂��ƁB��k�푈�����̌�̃A�����J�̗��j�ɐ�߂��ʒu�ȂǁA
�����ł��Ȃ������c�������������A��l���̂܂������O�����߂Đ����Ă���p�ɁA�傢�ɉe�����ꂽ���̂������B
�Ȍ㌴���ǂ̂́E�E�E10�炢���낤���B
���̑��҂��Ȃ����̊����ɓǂ�ł���̂��A�ƍl���Ă݂�B
�����炭��l����������G�l���M�[�����A�ǂ�������Ɓu�T�v�̍��]���藎�������Ȋ����G�߂ɁA���̂����������グ�邽�߂Ȃ̂��Ȃ��A�Ƃ��݂��ݎv���B�����̌��C�ɂȂ��A���ꂪ���̖{�B
�������B�ǔj�Ɏ��Ԃ̂����邱�Ƃƌ�������Ȃ��I�Ǝ��̍��Ԃɓǂݐi�ނ̂ɂ���5�����������Ă���̂�����B
�悤�₭�X�J�[���b�g�����c�̒n�E�A�C�������h�ɗ����A�����œy�n�ւ̈���֖ڊo�߂��ʂ܂ł��ǂ蒅�����B���ꂩ��A�C�������h�Ɨ��^���Ɋ������܂��X�J�[���b�g�́A�g������̐��E���L����B
�A�C�������h�ɂ́A�Â��m�l���ό��K�C�h�����Ă��邱�Ƃ����E�E�E�����A�̓��A�C�������h�A�d���̏Z�ލ��A�C�������h�ցA�s���Ă݂����B�v���͕�����B
�@�@���R�̕�炵358�@�@2018.1.27 �@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �@�s�A�m���̂ق��ɁA������~��������
�@�s�A�m���̂ق��ɁA������~��������
�@�h �����X�A�|���i�^�C���B�@ �ނ����ނ����̃h�C�c�̂��b���ł��B
����Ƃ���ɁA�d���ĉ�������܂����B���e�͎O�l�̑��q�����q�ɂ��āA�ҋƂ��c��ł���܂����Ƃ��B
�w�͂̍b�゠��d���Ă̋Z��g�ɒ��������j���Ɨ�����ɂ�����A���e���S�ʂƂ��Ė��@�̃e�[�u����܂��B
�u�e�[�u����H���̗p�Ӂv�Ə���������ǂ���ɐH�������ԂƂ����D����́B�Ƃ��낪���̒��j�A���̓r���̂���h���ł��̕s�v�c�ȃe�[�u�������������Əh�̒���Ɍ����Ă��܂��A���܂�Ă��܂��܂��B���āA���j�ł��B
����i���Ȃ�j�ɂȂ�Ȃ���Ηǂ��̂ł����E�E�E�E�����悤�ɕ��e���瑡��ꂽ�u������������Ƌ��݂ރ��o�v���A�Z�Ɠ����h�̒���ɋU���Ƃ���ւ����Ă��܂��܂����B�Ō�͎O�j�ł��B
���j�Ǝ��j�́A�Ԃ������Ă���Ƃ͂����A���Ƃ̓^���e�Ɏ莆�Œm�点�܂����B�����ŕ��e�͎O�j�Ɍ�g�p�ɂƁu���@�œ�������_�v���������܂�܂����B��l�Ɠ����h�ɔ��܂����O�j���厖�ɕ�����܂����āA����͎O���т����v�������悤�Ɗ�݁A���̑܂�����ւ��悤�łɂ܂���Ă���Ă��܂��B
�҂����܂��Ă����O�j�́A�������Ƃ�������������A�܂̒��̂���_�ɂЂƓ��������܂��B
����_�́A�������₢�Ȃ�h���̎�l�ɉ���|����A���炵�߂܂����B
���Ȃ�����l�́A���j�Ǝ��j���瓐�u�e�[�u����H���̗p�Ӂv�Ɓu���݂ރ��o�v��Ԃ��܂��B
��������Ԃ����O�j�͌Z�B�ɂ��ꂼ���Ԃ��A���̂��Ƃ݂͂�ȍK���ɕ�炵�܂����Ƃ��B �h�@�O�������b���
�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@�@���@�@�@�@���@�@�@�@��
�h�u�O�C�̎q�E�E�E���̉ƁA�̉ƁA�����̉ƁB
���ꂼ��̍ޗ��ʼnƂ����Ă��q�����B
�I�I�J�~�ɏP���Ȃ������̂́A�����̉Ƃ����Ă������q�̎q����B�h�i�C�M���X���b�j
���̂��b�ɂ悭���Ă���̂́A�Ђ���Ƃ��āA���q�����̏K��������y�n�����炩�ȁH
�r�Z�̒��j�͂ڂ���A����ȉ��͂�����Ƃ𗣂��̂ł������肵�Ă���E�E�E���ƂɊW���邩�ȁH�i�Ό��j
���₢�▖�q�����Ȃ̂�������Ȃ��B���ώ������Z������́A�����q���Ռp���ɂȂ邱�Ƃ�����������B
������Ȃɂ��B
�H���̒��B�Ƃ��̌�̒�����ՕЂÂ��ɁA�����ԂԂ�������̂����퐶���B
�����A�h���̒��傪�~������͂�����A�c�ƃR�X�g���h���I�Ɖ�������́B
�u�e�[�u����H���̗p�Ӂv�Ȃ�e�[�u��������A�ǂ�Ȃɏ����邩�B
�����A10�̎��̂ނ�����B�w�O�������b�x��ǂ݂Ȃ���A������������ˁB
�u�ڂ��A�傫���Ȃ�����u�e�[�u����H���̗p�Ӂv���A���������A���������������Ă����邩��v�ƁB
���̖͂ǂ��Ȃ��������H�@
�����������ȁH
�@�@���R�̕�炵357�@�@2018.1.23 �@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@
 �~����̊�Ɉ��������
�~����̊�Ɉ��������
�@�@
�߂��̉H�c���ɔ����I�I�n�N�`���E
�Ă͌ߑO5�����ɋN���A���̋G�߂�6������6�����ɋN������B
�Ǝ��[���Ȃ��A���H��ۂ�ƂȂ��g�̂��V���L�b�Ƃ����A���̒���N�����U�����Ă���悤�ȁA�ڂ��肵����ԂɂȂ��Ă��܂��̂��c�O���B
�ڂ��蓪�͂��̂��Ǝg�����ɂȂ�Ȃ��ł͂Ȃ����B
�����ŁA�ߌ㔼���Ԃقlj��ɂȂ�A�����͂��ߍ����r���x�܂��邱�Ƃɂ��Ă���B
�����B
�����B
�����̑����x�b�h�ł��A�����ނ�ɂ��C�ɓ���̖{����Ɏ��B�E�E�E�����A�����̎��Ԃ��Ȃ��B������グ�Ė{�����ƁA�������Ɏ肪�₽���Ȃ��Ă��āA�r�����邭�Ȃ��Ă���B
�N���A�ǂ�ł���{���Ŏx���Ă���Ȃ��H
�������āA������ō��}����ƁA���Ƃ��Ώu��������ƃy�[�W���J���Ă���Ȃ��H���₢��B�ق��5��������Ǝ��͖��̒��ɂ���̂�����A�s�A�m���͕K�v�Ȃ����B
�@�@�i�Q�鎞�Ԃ͂ق��5������10���B���ꂪ�߂��ۂ������ڂ�����B�j
�@�@���R�̕�炵356�@�@2018.1.18 �@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �Ԃ����z�ɑΛ�����l���@�@�W���A���E�~����
�Ԃ����z�ɑΛ�����l���@�@�W���A���E�~����
|

�@ |
�~������3�T�Ԍo�����B
���̏t�ɂ͂܂��܂����邪�A���������������ɐL�тĂ����̂ŁA��D���ȃ~���̍�i���A�������̕ǂɎ��t�����B�G����������������悤�ɂƁB���̊G�̑�́u�Ԃ����z�ɑΛ�����l���v�B
�l���̖ڂ͎߂ɕ��сA�ǂ������Ă���̂��킩��Ȃ��B�Λ�����H�Ȃ��u�Λ��v�Ƃ������t���������̂��B�@
���̋��ɕt���Ă���̂̓��{�����H���H
����A���̐l���̉��炩�̈ӎv�ł͂Ȃ����ȁB�E���̉��F���ď������l���́A���̐l���̃h�b�y���Q���K�[�H����Ƃ��u���b�P���H����Ɏ��̂́A���ƑېF�́E�E�E���[��A�Ȃ낤���H����Ԃ̂́A�������S�\�̐_�[�E�X����𓐂v�����e�E�X���낤�B
������@�G�ł͂Ȃ��ȁB�~���́A�ʎ����ɂ߂����炱���A���̂悤�ȊG���`����̂��낤�B
��{�������ēW�J������A����͂����邱�ƂɌ����邱�ƁB
�@
|
|
�m�j�g���W�I�̑��ɍ��킹�Đg�̂����Ă���Ƃ��A���̊G�̐��ʂɗ����Ƃɂ��Ă���B
�҂��҂��B�ǂ��ǂ��B
��������ƃp�[�c�������яo���Ă���B
�܂�ŃL���[�r�Y���̊G�̂悤�ɁB����ɂ��Ă��A�����̋C���̓}�C�i�X8���B
�����銦�����I |
�@�@�@���R�̕�炵355�@�@2018.1.13 �@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
 �@��
���~�葱���@�@�@ �@��
���~�葱���@�@�@
�@�@
���̓~���x�ڂ��̐Ⴊ�[�邩��~��ς���A�ڊo�߂�Ɓ@���@�̏�ԂɁB
�N���ɍ~�����Ⴊ�悤�₭�Z���͂��߂��Ƃ���Ȃ̂ɁA����͍���ɂȂ肻�����B
���������ƁA��₭�ʂ��̎}�ɐς������Ⴊ��Ăɒ���삯�߂���B
�z���C�g�A�E�g�B���z���̌i�F����ʐ^�����ɂȂ�B
�f�b�L�̎���Ɏ��t�����t�F���X�ɂ́A���܂ɂ��]�����������ȐႪ�ڂ�A�낤���o�����X��ۂ��Ă���B
�@�@�i�����Ƃ��A���̎l�p�E���̘A�Ȃ�́A�Γ���̃`�F�b�N�Ɏg����̂��~�\�@�j
�H���悵�A�ǂޖ{�悵�A�����悵�A�K�\�����悵�B
���k�J�ǂ͊���Ȃ����A��ǂɂ͂ӂ��킵�������B
�@
���R�̕�炵353�@�@2018.1.3 �@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
 �@�މ�V�N
�@�މ�V�N

�@
�E�@���炵��Ɛ��܂��������̖����Ē��̂Ђ���ɒ��킽��䂭
�E�@���킽���ΐ��̔��̂����܂����V�����̍��ɂ��Z���
�E�@�������F���邲�Ƃ��~��ɂ�����������鉩���O�� ( �����ɂ݂��Ԃ��E�����˂݂ڂ�) �@�@�@�@�@�@�@�@�@

���R�̕�炵352�@�@2018.1.1. �@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@
�@
 ��������
��������
�ߌ�A������Z���Ȃ��܂܂̑����݂Ȃ��痠��ɏo��ƁA�Ȃɂ��]�N�]�N�Ɖ������C�z������ł͂Ȃ����B
�@�@�E�E�E�V�W���E�J�������������̎}�Ɏ~�܂�A�������Ă����B
10�N�ȏ�ɂȂ�쒹�ώ@����A�쒹�������Ƃ��͔�펖�Ԃ��N���������Ƃ��₷���z���ł���B���������������ɉ����������̂��낤
�B�p�g���[�����Ă݂Ă��v��������߂��Ȃ��B
���̂����u�o�^�o�^�v�u�����v�ƉH�������������Ă����B�q���[�q���[�Ƃ����߂����Ȃ����ꐺ���������Ă���B
���̎�͂��̒��B

��D���ȃA�C�X�����h�E�|�s�[��~�z�������邽�߁A�_�Ɨp�r�j�[�����g���Đݒu�����ȈՉ����̒��ɓ��荞�݁A�o���Ȃ��Ȃ����悤���B
�������Ȃ̂ŁA������͂���������Ă������̂ɁA�����疳����肱���J���ē���A�a�ł��T���Ă����̂��B
��������㩂��瓦��悤�Ƃ�����s�t�Ȃ̂͐l�����̂��́B�ǂ����o���������ڂɓ���Ȃ��悤���B
�������J���A�Ȃ�Ƃ����������Ƃ��Ă݂Ă��A����̓p�j�b�N���N�����ē����܂ǂ����肾�B
�Q�Ăӂ��߂��悤�₭��ї������̂�5����ŁA���̊Ԃ����ƃV�W���E�J���͎}�Ɏ~�܂����܂ܑ呛�����Ă����B
���̌��t��|��ƁF
�u���[���A�����̗��l�I���v���B�������肹���B�o���͂������������Ƃ��낾�[�B���������I�ǂ����͂�����I���̐l�Ԃ͉������Ȃ����[�A�a�������l��
�v�B�쒹�̎�ނ͈���Ă��Ă��A�������꒣��Ƃ��钇�Ԃ��Ǝv���Ă���̂��B�쒹�Ȃ�������̒��Ԉӎ��̋����ɋ����B�������������o���₢�Ȃ�A�V�W���E�J�������͈��S�����̂��A��Ăɔ�ї����Ă������B
���̒��͏ł��ĉ��x���r�j�[���ɓ����Ԃ����炵���B�������������Ă��锯�̖сi�H�сj������Ă��܂��Ă���B�������ł����邵���m�ȗl�q�ɏ��Ă�����B��ނ͂��܂��ɕ�����Ȃ��B�@���߂Č����ŁA���邢�́u�z�I�A�J�v��������Ȃ��B
�@�@�@�@���R�̕�炵351�@�@2017.12.25�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@�@ �`������̌����ɓ~��������
�`������̌����ɓ~��������
�@ �@122�@���ꂩ��Ԋ|�� �@122�@���ꂩ��Ԋ|��
���邭�邭��ƁA�a�`�̔�������Ă��邤���ɁA����ɋC�������g���Ă���̂́A�������Ȃ̂��B
���N���A�i���_�̍D���ȁA���͐H�ׂȂ��j�����`����̋G�߂ɂȂ����B�H�̒��J�ƁA�䕗�̉e���Œn���Y�̖I���`���s��炵���B���܂蓹�̉w�ɏo���Ȃ��܂�11�������̎����ɂȂ����̂ŁA���˂Ă̒m�荇���ɂ��肢���āA�u���n�`�v���Q�O�L�������ɓ��ꂽ�B---�u�Q�O�L������v�H
�����`�̍D���ȑ��_�̂��߂ɁA���N����3�{�̊`���ނ��Ă������A�悭�悭�l���Ă݂�ɁA�����̉�̊����`���ʂɍ��A���_��l�ŐH�����Ƃ͐g�̂ɗǂ��Ȃ��B
���������̘b�������́ior �����荇���j�̂��A���̗ʂɗ����������̂�����̂��Ƃ������B
��d���̑�D���Ȏ��B�H����̌ߌ�A�������Ɣ���A�`�����n�C���y���B
�`�̖��O�ɂ͂��ꂼ��̒n�搫���o�Ă��āA���ʂ����̉����y�����B
�̂Ȃ���̘m�����̉Ƃ�����A�킫�ɉ��{���̊`�̖������āA�H�̗z�ɋP���Ă���l�q��z�����Ă��܂��B
�S��̎��Ƃ̂悤�ɁB
�E�@�I���`�@�@�i�n���ƖI������Ă��邩��H�j
�E�@���n�`�@�@�i�ג����^�����Ɋ��������邩��j
�E�@��Ðg�m�s�`�@�@�i���肷���Ď}���܂��̂����܂킸�A����Ɏ�������B���킷�Ɣ����j
�E�@�x�m�`�@�@�@�i�x�m�̖��̒ʂ�A���̎p�͒[���j
�E�@�M�`�@�@�@�i�M�̂悤�ɂق�����Ɓj
�E�@�S��`�@�@�i�������ɑ傫���B�������喡�@�S���375���j
�E�@���Y�`�@�@�i���Y�`�͂���̂��H�j
�E�@�x�L�`�@�@�i�a�̎R���Y�̂��̊Ê`�j
�E�@���j���`�@�@�i�����́A�a�����p�̊`�j
����́u�����`�v���肪�����A�����Ƃ��̍��M�Ȗ����������B
�`�̖��ɂ�䕂̂��̉��炵�����O�Ƃ͈Ⴂ�A�ǂ�����Ƒ�n���琶�܂�Ă����悤�ȋ���������B
���N��11���B���N�̍����������Ă����̂��A�ߋ��̃y�[�W���߂����Ă݂���E�E�E�B
��͂�`���A�M�q�̃W����������ėⓀ���A�ڊ⑺�̖�O�s�o�̐Ԃ���������3���Ԃ����Ĕ������ߊÐ|�ɒЂ��A�Ԃ̕c��A�����݁A�����Ń|�s�[����ĂĂ���B
�l���̃x�N�g���͉������B���������N�Ɠ������Ƃ��ł���Ƃ����̂́A����͈��̐i���Ȃ̂ł͂Ȃ��̂��B
�ς��ʂ��Ƃ͗ǂ��ƁB
���R�̕�炵348�@�@2017.1111
�@�@ 
�@�@ �݂�ȉ����q�ǂ�����
�݂�ȉ����q�ǂ�����

��������炸�H�̎d���ɒǂ��Ă��閈���B
�����͗���ɊȈՉ�����ݒu�����B����ň��S���ē~���}������B�@�@�ق��I�@�Ђƈ��S�B
���łɗ��t�p�ɁA�`���[���b�v��120�A�r�I����130�{�A�����B
���Ƃ͂��́u�A�C�X�����h�|�s�[�v��~�z�������邾���B�@�i200�{����I�j
3�������Ă��̕c���Ԓd�ɐA���t����ƁE�E�E�ǂ��Ȃ邩�E�E�E�������I�tࣖ��̒�̏o���オ��I
�@
|
 |
��D���ȁA�A�C�X�����h�|�s�[�B
�ڐA�������̂ŁA�u�H�q���قǂ́v�ƌ`�e�����ׂ�������|�b�g�ɔd���A��ɏ]���Ĉ���傫�ȃ|�b�g�ɐA���ւ��Ă����B�������邱�ƂŁA������������|�b�g�ɉ��A��ւ̉Ԃ��t�̕��ɗh�����i���ł�������B
�K���̐F�͉��F�H
�|�s�[�̐F���A�����ƁB |
���R�̕�炵347�@�@2017.11.8�@�@
�@�@ 
�@
�@�@ �ǂ�҂Ⴊ�܂̃W�����Â����@�@�i�c�n�[�@�c�c�W�L�ȃX�m�L��
�ǂ�҂Ⴊ�܂̃W�����Â����@�@�i�c�n�[�@�c�c�W�L�ȃX�m�L��
�@
|
 |
�u�w�ǂ�҂Ⴊ�܁x�́A�ǂ�҂���Ăǂ������Ӗ��Ȃ̂ł����H�v
�������Ȃ肱���q�˂����ɁA
�u�ǂ�т�v�H�u�y�r�̂��Ƃ�v
�����Ȃ��������ォ�猩��Ɠy�r�̂悤�ŁA������݂�ƒ����̂悤�E�E�E����Ȃ��H�v
�߂��́A�����s���Y���̂��X�ŊŔ����Ă����N80�̂l����B
���A�ꍇ���Ƒ傫�Ȕ_�����o�c���A�ό��_�����J���Ă��q���y���܂��A�ł��ł��Ă��̂����A���Y�̎��ȊO�Q�����Ƃ������A�Ƃ������邭�Ă�����ׂ�D���Ȍ��C�ҁB
�u���N�ˁ`�A����҂̓C���t���G���U�̗\�h���˂��Ȃ����Ƃ���������ꂽ�̂ŁA�d���Ȃ����̂�A�͂��߂Ă�B
����̓��N�`���𔖂����Đg�̂ɂ����Ȃ��A80�N�ԃC���t���G���U�Ȃɜ�������Ƃ̂Ȃ��̂��т����肵�ĔM���o����������E�E�E���̓��ɂ̓P�����Ǝ���������ǂˁB�v�Ƒ������B
��ݍ��܂��悤�ȁA�������傫�ȏΊ炪�S�Ɏc��A����Ȃӂ��ɔN����肽���Ǝv�킹����̑傫����������B
�@ |
�ǂ�тႪ�܁A�ƃi�c�n�[���ĂԂ̂́A�Ȗ،������̂悤�ŁA���ł͕����Ȃ��B
�Ăɔ��i�n�[�E�͂��j�̂悤�ɗt���g�t���邱�Ƃ���A�i�c�n�[�ƌĂ�Ă��邪�A���́u�ǂ�тႪ�܁v�̂ق����������ӂ�A�e���݂�������̂́A�悤�₭�Ȗؐl�ɋ߂Â��Ă����؋���������Ȃ��B
���̂ǂ�тႪ�܁E�y�r�����̓u���[�x���[�̂���c�l�̂悤���B
��Ɉ�ĂĂ���2�{�̖̂����A�Е��͍��������n���ăi�c�n�[���Ɂi���A�ǂ�тႪ���̂��Ƃł��j�A����1�{�̂ق��̓W�����ɂ��Ă݂��B
��������щ��q���X�Y���o�`���x�����A�G��Ƃق�ق뗎��������W�߁A�J�̌ߌス�����Ɠ�������B
�����������ȂƎ��H���Ă݂�ƁA�������a�݂��c���Ă���悤���B
�u���E�E�E����͂����Ɣ�ɃN�Z������ȁv
�قƂ�ǃW������ɂȂ����h���h�����A��ƒ��g�ɕ�������Ɏύ��ނ���1���Ԃ��܂�A���b�^�������W�������o���オ���Ă����B�u���[�x���[��6�{���̃A���g�V�A�����܂ދM�d�ȃW�������B
�Ƃ��낪�I�@�a�݂͒��g�̂ق��Ɋ܂܂�Ă����炵���B�W�����ɂق�̂�a�ꂢ�����c���Ă����B����Ȃ��ƂȂ��Ԃ��������ɔ���̂܂܁u�v���U�[�u�^�C�v�v�̃W�����ɂ�������I�i��������̖��_�̂��߂ɁE�E�E���������A��l�̖����B�j
�i���܂��P�j�@�]��ł������ł͋N���Ȃ������l�̎��A�c��������W�߉ʓ��������ėⓀ���A���[�O���g�̏�ɍڂ��ĐH�ׂĂ݂��B�i���������j�i�|���t�F�m�[���̂����܂肾���̂ˁj
�i����ɂ����܂��Q�j�@�M�d�ȃW����������ɂ������������B�����A���������Ȃ��B���������ėn�����A�[���`�����ӂ₩������u�ǂ�тႪ�܁E�[���[�v�������炦���B
�g�b�s���O�Ƀn�[�Q���_�b�c�̃A�C�X�������B����܂����������B
�J�̌ߌ�́A�W�����V�тŕ��Ă����B
�@�@�@�@�@ ���R�̕�炵346�@�@2017.10.29�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 
�@
 賂̔��B���@�@�@�L�W�ڃL�W�ȁ@���{�̍����@�Ì��賎q�i�L�M�X�j
賂̔��B���@�@�@�L�W�ڃL�W�ȁ@���{�̍����@�Ì��賎q�i�L�M�X�j

�����������B
�����������B
����̊��q�q�o�̍����ŁA賂������т̐^���Œ����B
�������ɂ��̍s���ڌ���̂͒��������ƂȂ̂ŁA�����Ɗώ@���Ă�����A�����[�Ƃ�����ł�����s���ɂ�݂��Ă����B�i�悤�Ɍ������j�A�X�p���K�X�̕ʖ��́u賂̔��B���v�B��O�Ƀ~���g�����Ă��邪�A�A�X�p���K�X�Ȃǐ����Ă͂��Ȃ��B�܂������A��������ی�������B賂����B�@�@�i�摜�͗Y�j
�Y������Ȃ��B
����22�N�O�̂��ƂȂ̂ɁA�L���̒�ɂЂ����薰���Ă��āA���ɑN�₩�Ɏv���o���A�S���Ȃ����F�l�m�l���Â�ł͉��Ƃ��\���ł��Ȃ��v���ɂƂ���邱�Ƃ�����B
�l�Ԃ̐g�̂ł͊����邱�Ƃ��ł��Ȃ��n�k�̏����������A賂͊����邱�Ƃ��o����B
�]�k�������劦�̓��X�̂��Ƃ������B
賂����A��͂܂��ĉ����܂Ő��������B
賂����E�E�E�@�ꑧ�����Ԃ��Ȃ��A�]�k���P���Ă��Ă����B
�R����A賂̐�������ɂ܂����B
������ɗ��čĂьo�����������{��k�Ђ����A���̐_�˂̒n�k�̓ޗ��ɗ�����悤�ȋ��|�̂ق����A�͂邩�Ɏ����̑̂̉���ɐ[�����ݍ��܂�Ă���悤�ȋC������B
����͂Ȃ��H
�����͎������D�悷�閽������������B�����č��A���ׂ��͌Ȃ̑��݂̂݁B��������R�ƌ���Ό��������B
�@�@�E�@�l�ԂɌ��߂�����̂����痣�ꏬ���ƂȂ肽���������@�@�@�@
�@�@�@�@���R�̕�炵345�@�@2017.10.24
�@�@ 
�@
 �@�@������E�E�E�E�T�[�r�X�t������ҏZ�� �@�@������E�E�E�E�T�[�r�X�t������ҏZ��
�I�̐��Ƃ��ǂ��ɂ���̂��B�l���Ō�̑I������������Ō��݂̒n��I�сA�Ƃ����Ăĕ�炵�n�߂�15�N�B
�I���͌���Ă��Ȃ������A�Ǝv���������̂́A�̒��̕ω���v��ʕa�ɓ|��A��삪�K�v�ɂȂ邱�Ƃ��l���āA���̐��N���܂��܂Ȏ{�݂����w���ĉ���Ă���B����A�R�X���X���炫�����ߐ{�̎R�[���h���C�u���A
�@�@�E�@�T�[�r�X�t������Ҍ����Z�� �u�A�N�[�������y���v�@�����Ă����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�蕨����ŃI�[�v��������������B�e��ݔ��͍ŐV�ŁA�ٓ��̃X�^�b�t�����̏Ί���܂Ԃ����B
�{�݂ɗאڂ���A���R���̏h�ꂾ�������쉷�������X���p�ł���B
�������B�����ōl���Ă݂����̂��B���̎{�݂ɕ�炷�ƁA�}�a���삪�K�v�ɂȂ����ꍇ�̑Ή��ɂ͈��S�ł��邩������Ȃ����A�������Ă�����Ԃ��A�͂����āu����ҏZ��v
���K�v�Ȃ̂��낤���B
�������Ă���E�E�E���Ȃ킿�����ŕ�炵���x���邱�Ƃ��ł���Ԃ́A�킴�킴����ҏZ��Ɉڂ�Ȃ��Ƃ��A���̕�炵���H�v���Ȃ��瑱���Ă������Ƃ��o����悢�̂ł͂Ȃ����B�Ȃɂ���A�p�[�g�̒��ݗ��̉��{������l�i�����Ă���̂�����B���݂̉Ɓ��T�[�r�X�͎��O�̍���Ґ�p�Z��ł͂Ȃ��H
�����Ƃ������Ɍ݂��ɏ���������F�l�����Ƃ̃l�b�g���[�N�����A�����̐��_�������Ȃ��玞�̗���ɐl���ɏd�˂Ă��������B�����l����͈̂��Ղ����邾�낤���B
�ň��̎��ԂɑΉ����鏀���͂��Ă����B
�ł��A�]�����Ă�������v���Y�݂����邱�Ƃ́A�������Đ��_���k���܂��Ă��܂��悤�ȋC������B
������Ȃ��Ȃ��E�E�E�E�B�Ȃɂ���A�s�����͏��߂ĕ������B
����F�l�̌��t�F
�u���ꂱ��l���Ă��A�v�����悤�ɂȂ�Ȃ��̂��l���B�Ƃ肠�������������C�Ő����Ă���A�����Ə�肫����v�B
�ĊO���ꂪ�������˂��ӌ��Ȃ̂�������Ȃ��B
�@�@�@�@�@
���R�̕�炵345�@�@2017.10.16�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@
 �@�J�Y�I�E�C�V�O�����A�m�[�x�����w�܂���܂����E�E�E�@������
�@�J�Y�I�E�C�V�O�����A�m�[�x�����w�܂���܂����E�E�E�@������
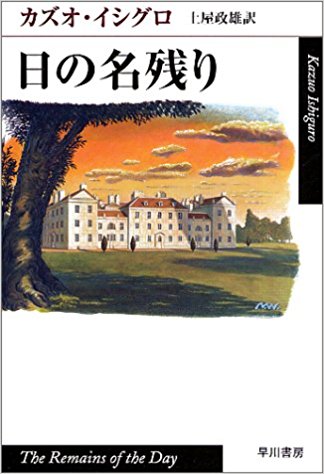 �@ �@
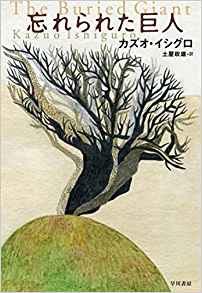 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��������|��ƁE�y�����Y�̎�ɂ���ē��{�ꉻ���ꂽ��i�j�@�@�@�i�摜�͔M�щJ�т���q�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��������|��ƁE�y�����Y�̎�ɂ���ē��{�ꉻ���ꂽ��i�j�@�@�@�i�摜�͔M�щJ�т���q�j
�w���̖��c��x�̂��납��̃t�@���Ƃ��āA���̎�܂͎v���Ă����Ȃ���т������B
�ڑO�ɂ������ƁA���L���Γ͂��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ̍��o���o����قǂ̋߂��Ɋ����錶�o�Ƃ̊Ԃɂ���ǂ��A�₷�₷�Ə��z������߂��Ă�����ł��镶�͂�������i�́A�|��ƁE�y�����Y�̑�z�������{��͂Ɏx�����Ă���B
����A�|��Ƃ����������e���|��Ƃ̐g�̂�ʂ��ĕ\�o���Ă������̂ŁA���������珑�����̂ł͂Ȃ����Ǝv����قǂ̓��{�ꂪ�A�Ȃ��Ă�����i��ǂނ̂́E�E�E�ƂĂ��Ȃ������I�W�X�Ƃ������t��ςݏd�ˁA���t���S�ɂ���s���������ɂ������ė���Ƃ��A�P�������ꕁ�Ր�����ɓ���邱�Ƃ��ł���B
����͋F��B��҂́A�l�Ԃ̑��݂ɑ���F��B
�J�Y�I�E�C�V�O���F
���茧�o�g�̓��n�C�M���X�l�����ƁB�i���e�͓��{�l�j
1989�N�ɒ��ҏ����w���̖��c��x�ŃC�M���X�ō��̕��w�܃u�b�J�[�܂��A�A�����2017�N�Ƀm�[�x�����w�܂���܂����B
*�@��N��܂̑O�]���̍����g������ki�̍�i�́A�ǂނ��тɎ����ƍ�i�̊ԂɁu�u�ǁv�������邱�Ƃ������B
�@�@���������Ă������ǂł��Ȃ��B
���R�̕�炵344�@�@2017.10.9�@�@
�@�@ 
�@
 �@�w�L�̉x���@�@�@�I�p�[���̋P���͎����₷��
�@�w�L�̉x���@�@�@�I�p�[���̋P���͎����₷��
�u�E�E�E�͂��߂��炨���܂��܂ł��ꂳ��͋����Ă��肨��܂����B�������r��g��ł����ƍl���Ă��܂������A�₪�ăz���C�̂��Ȃ���Â��ɂ������Č������܂����B
�@�u�����ȁB����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ɂ�����̂��B������悭�킩�������O�́A�������킢�Ȃ̂��B�ڂ͂����Ƃ܂��悭�Ȃ�B�������悭���Ă�邩��B�ȁB�����ȁv
�@���̊O�ł͖�������ė闖�̗t�͂����炫�����A�肪�˂����́A
�@�u�J���A�J���A�J���J�G�R�A�J���R�J���R�J���v�ƒ��̏��������炵�܂����B�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�L�̉x�@�@�{����
�쒆�́u�肪�˂����v�͏��H�ɍ炭�u�c���K�l�j���W���v�̂��ƁB
�{���̍�i�́A�ЂƂ�����ΎO�����ł��Ȃ��Ȃ�A�Ȃ�Ƃ��O�ǂ�������A����ɉ����܂ŋ^��_���A�Ȃ��Ă��āA�ǂ߂ǂ��ǂ߂ǂ�����A�ꐶ����A�܂藈���܂œǂݑ�����ƂЂ���Ƃ����D�ɗ����邩������Ȃ��A�Ƃ��������́B
 �c���K�l�j���W��
�c���K�l�j���W��
�@�@�@�@�@ ���R�̕�炵341�@�@2017.9.14�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@ 
 �g�C������������肵��
�g�C������������肵��
���̓��B�ق�̂R�O���O�ɂ͐���ɓ��삵�Ă����g�C���i�s���s�����A�g�p14�N�j���A�ˑR�A�X�g���C�L���N�����Ă��܂����B�t���b�V��������A�����Ȃ�^���N�ɐ��������悭���܂��Ă����̂ɁA�^���^�����т��тƁA�ׂ�����ɂȂ��ă^���N���ɗ��ꗎ���A�Ȃ��30�����������Ă���ƈ�t�ɂȂ�Ƃ����̂��炭�B����Ȏ��قǃl�b�g�̂��肪�����������邱�Ƃ͂Ȃ��B
�u�^���N�ɐ������܂�Ȃ��v�Ō�������ƁA�����Ƃ����Ԃɂ��̉�����������Ă��ꂽ�B
1.�@�X�g���[�i�[�̑|��
2.�@�_�C���t�����̌���
�����B
�^���N�ւ̋���������A�X�g���[�i�[�����O���A���ԑ|���p�̃~�j��������ő|�����Ă݂��B
����������ł͚��������Ȃ������B�^���N�̊W���J���A�`�F�b�N���Ă݂���A��͂�_�C���t��������ꂽ�炵���A�c�悪���ɎU����Ă���B����͌������邵���Ȃ��B
�͂��B�����܂ł̓����͗ǂ������E�E�E�E�B
�u�������������B�y�V�̃|�C���g�����܂��Ă��邽�B���������g���Ă��܂����v�ƍl�����̂���͂��������B
���̎��A�������ē͂��܂ł�4���Ԃ́A�o�P�c�Ő������݁A�����悭�����Ƃ����J��Ԃ��ɂȂ�Ƃ͎v��������Ȃ������B
�܂������z�[���Z���^�[�ڎw���Ă�����A���̓��̂����ɏC���ł��Ă����̂ɁB
������x���o�P�c�̐��𗬂��Ă���ƁA����ɃA���u�̍��ɂł��Z��ł���悤�ȋC���ɂȂ��Ă����B����ɂ���ɁB�ʔ������Ƃɂ��̐��̗���������ʓI�Ɏg���ׂ��H�v���Â炷�悤�ɂ��Ȃ��Ă���B�����ʒu�ƁA���ʂ߂��āA�g���l�[�h���N�����Ə����ɗ���邱�Ƃ����A��l�ʼnx�ɓ���B�y�����H�@��炵�������Ƃ����Ԃɉ߂��A�V�������t�����_�C���t���������������ƁA����ȋ�J�Ƃ������Ȃ���J�͂������ƖY�ꋎ���Ă����B
�_�C���t�����i�ciaphragm�j
���炩�̈��͂�A�t�̗̂��ʂ₻�̉t�ʂȂǂ��R���g���[�����钲���فE���������B
�g�C���̃^���N�̏ꍇ�A�����ƃ^���N�ɗ��܂������Ƃ̃o�����X��������������B�������I�[�g�X�g�b�v����̂͂��̃_�C���t�����̂������B
�M���ނ̉��u�����_�C���t�����ƌĂԂ̂́A���������B���u���͋ؓ��łł��Ă��āA���o�ƕ��o�̊Ԃɂ���u�ǂ������炵���B���������͉��u�����z���B��A�����ɂȂ��Ă�����������B
�@�@�@�@ �@���@���ꂪ�_�C���t���� �@���@���ꂪ�_�C���t����
�@�@
�@���R�̕�炵340�@�@2017.9.5�@�@
�@�@ 
�@
 ���N�̃u���[�׃��[
���N�̃u���[�׃��[
���z�I�ȍ͔|���́G
�������肪�ǂ��A�_���y�ŁA�\���Ȏ��ԋ�����ۂ��A�����ʂ�A�h�{�L�x�ȓy��ɐA���A�K���ə�����s�����ƁB
�����̏����̂����A�䂪�ƂŖ������Ă���̂́A�_���y�ł��邱�ƂƁA�엿��^���Ă��邱�Ƃ̂݁B
�őP�̊��Ƃ͂ƂĂ������Ȃ���̋��ŁA���肪�������Ƃɍ��N����������������Ă��ꂽ�B����ԒǏn�������ƁA�T�O�O���ɏ��������Ⓚ�ɂɂ�������l�ߍ���ł���B���̑܂̐���������45�ɂȂ����I�����������������܂߂�ƁA�����̎��_�Ŗ�24�L���O�����̎��n�����������ƂɂȂ�B
�W�����ɂ��ĕۑ�����Ə��ʂɂȂ邪�A�����\�[�X�����A���Ԃ��������c������ԂŃ��[�O���g�ɍڂ��Ă���̂�����̂��D���Ȃ̂ŁA��ނȂ��`�𗯂߂��܂ܗⓀ���Ă���B���������ėⓀ�ɂ͖��t�I
����ȏ�͂�������Ȃ��̂ɁA�܂��܂��召10�{�̖ɂ͍�����n�������Ԃ牺�����Ă���B
 No.45�̑�
No.45�̑�
��L���̎��n�ɗv���鎞�Ԃ�50���B
�����Ǝ�����т܂��I�ƃC���K�Ƃ̓����ł�����B
�R�[�q�[���̎��n�Ɠ������A���̕ω��ɓK�����邽�߁A���X�ɏn���Ă����u���[�x���[�E�E�E�[�S�̂������ɏn���̂ł͂Ȃ��̂ŁA�ЂƂЂƂ����n��������T���A���L���Ď��Ƃ����ʓ|�ȍ��
�����C�悭�����Ă����B
��������𗈔N�̉Ă܂ŐH�ׂ���A�Ƃ�����т̂�������B
�@
���R�̕�炵338�@�@2017.8.27�@�@
�@�@ 
 ��ԍD���ȃ����@�@�@���̎q�S��
��ԍD���ȃ����@�@�@���̎q�S��
�W���S�O�O���O��́A�������Ȃ��Ⴍ���Ȃ��A�ۂ������₩�ȎR���A�Ȃ钆���R�n�́A����������R���ɐ��Ƃ͂������B
�Ί_���ς܂ꍂ��ɂȂ��Ă���~�n�̂��������������ʂ��Ă��āA���H�̌������ɂׂ͍��삪����Ă����B
����̔_��Ƃ��I�������́A����ɑ���Z���Ȃ��������A���̓��̓�������������Ă��̂��킾�����B
���Ɛl�ƁB���͉���������炵�A���͎�����ƈ�̂ɂȂ�����тɁA�傫���ۂ��ڂ����܂��Ă���B
��݂ɂ͒|����A�Ăɂ����т₩�Ȍu�̃g���l���ƂȂ����B
���炾��Ɠ����H���オ��ƁA����40�N��Ɍ��Ă��A�����͒����������u��K�ƂŊ������v�̉Ƃ�����B
�I�̖̑��������c���ɑ���A�q���̂���ł������łɒz70�N���z���Ă������Ƃɂ́A��ʂɍL���������L�тĂ����B
���[�ɂ͍����Ղ��A�H�̏I���ɂ͓�Z�����낲�����ł����B
���̉�������荞�����ɏ��@����̕������T���Ă��āA��Ԃ̏��̊Ԃɂ͕�̐S�Â����̉Ԃ��������Ă���B
������̏�̎V�ɂ́A�W�ƈт̔\�ʂ������Ă����B
�c������A���̔����ʂ�ڂɂ���ƐS�������݁A�N�ɐ����Ȃ��������閧�߂��������ɓ��鎞�ɂ́A�|���������Ďv�킸���葫�ɂȂ��Ă����̂��v���o���B���̕������猩����̂́A�R����N���Ă��鐅���W�߂��r���ӂ��B
�ےr�Ɗp�r�̊Ԃ͓y�ǂ�ʂ��Đ����s�������A���̓�̒r��Ԃ�����݂ɉj���ł���̂�����̂́A�߂����ɂȂ��y���݂������B���̒r�̂قƂ�ɂ́A5���ɂ͉ԊC�����A���~�ɂ͎��̎q�S�����炢�Ă����B

���a30�N��́A���ƕ�ƌZ�Ǝo�Ƃ�7�l�̕�炵�B
�q���̂��댩���Ԃ́A�d�����̂�����قǂ̐g�̂̉���ɁA�Ȃ������L���Ƃ��Ďc���Ă���B
�@�@�E�@�Ђ��߂��č炯�ǂ��ЂƂ莭�̎q�S�����܂��炶��ƏH�̍��̂���
�@�@
�@���R�̕�炵337�@�@2017.8.21�@
�@�@ 
 �ڋߑ����@�E�E�E�@����Ȃ��s�v�c����
�ڋߑ����@�E�E�E�@����Ȃ��s�v�c����
�c�ɂɉz���Ă��ĂЂ������d���ɊJ�����Ă��邤���ɁA����ɓ��������Ă��Ă��鎄�B
���������l�Ƌ��ɋN���ē����A���ޓ��߂Ȃ���[�H��ۂ�A���߂ɖ���̐��ɂ͂���B
�V�����[�̂��Ƃ������萅������ŋx�ނ̂ŁA�^�钆�Ɂu���R�ɌĂ��v���Ƃ�����B
���`��ƐQ�Ԃ��ł��A�x�b�h����̂������͂����悤�ɋN���オ��A�Q�ڂ��܂Ȃ����ł����Ƃ���Ɍ�������
�����Ă����ƁA�Ȃ�ƃh�A�̑O�ɑ��_������ł͂Ȃ����B
��͂�Q�ڂ�����ŁA�ܐ悪�オ��Ȃ��������̂܂܁A�ʎ���������Ă��Ă����B
�����A�����Ƀh�b�y���Q���K�[�I
����Ȃ��Ƃ������ċN���Ă��܂����B
�L������Ԕ�s�@���A�ڋ߂���悤�Ȃ��̂�������Ȃ��B
�������Ԃ�7���Ԃ�8���Ԃ�����̂�����A�Ȃɂ��҂�����o���Ȃ��Ƃ��ǂ��̂ɁB
���̏ꍇ�A�ǂ��炪�D�悳��邩�́A�ً}�x�ɂ��B
�@�@�@----�̂ł͂Ȃ��B
�u�ǂ����v���ǂ��炪���ɂ��邩�B
����͂������B��͂莩�����A�ƌ������̂͒p���������Ƃ����C����������悤���B
�ʂ�㵒p�S�ȂǂƂ��������h�Ȃ��̂Ɉ�������ꂽ�킯�ł͂Ȃ����B
����͒������Ԃ������č��荞�܂ꂽ�����E�E�E�W�F���_�[�̐�������̂Ȃ̂�������Ȃ��B��������̏o��������A�傫�ȃC�x���g�Ɏ���܂ŁA��r�I�i�I�j�����̈ӌ���ʂ����Ƃ������̂ɁA���̖��ɂ��Ă͂Ђ����瑊��ɏ����Ă��鎩����������̂́A
�ʉf�䂢�B���������ƃx�b�h�ɖ߂�A�K�Q���肷�邱��5���ԁB�����ނ�ɋN���o���āA�̂��̂��ړI�n�ɂ����ނ��B
����낪�̂��̂��ɕς��A�x�b�h�ւ̋A��̑����̓p�L�p�L�B
�ڂ��Ⴆ�Ă��܂������̂��Ƃ̎��Ԃ̒����́A�H�̖�̂��Ƃ��B
 �S�S�������� �S�S��������
�E�@�����͋S���S���S���ܖ��邫���̗t�����E�͂�@
���R�̕�炵336�@�@2017.8.14�@�@
�@�@ 
�@
 ��䪉�
�i�ă~���E�K�Ȃ̂Ŋۂ��ĂӂƂ�����B����̍����ƌ�������Ȃ��B�j
��䪉�
�i�ă~���E�K�Ȃ̂Ŋۂ��ĂӂƂ�����B����̍����ƌ�������Ȃ��B�j
�J�̑����Ă̂��������A�~���E�K�������ɖ����ǂ�����o�Ă����B
�֎q�ƃ~���E�K�̐�Ђ��͗��z�I�B�|�̕��������ȁB
 �J�����Ƃ�Y��邩�A���������邩�B
�J�����Ƃ�Y��邩�A���������邩�B
���~�̌��̂����Ȃ̂�������Ȃ��B�����Ă���l�����A�S���Ȃ����l�̂��ꂱ����ÂсA�v���o�ɐZ�邱�Ƃ̑����ߌ�𑗂��Ă���B�Ⴍ���ĖS���Ȃ������l���̗F�l�B���ɕĎ��܂Ő������c����B
���a12�N�̂̂��A�c���q�����c�����O�̎����}�����p��̒B�l�������F�B
�����āA���̒��ɏo�Ă�������B
�@ �E�@�ʁi�����j��������L���ɂ����₩�Ŗ����Ă���肯�ӂ̂ܒ��ԁ@
�@�E�@���̐������₭�₤�ɂ��ڂꗎ���n���ƂȂ�ĕ��т�邩���@�@
����̈�Âł����Âł��Ȃ���a�ɐN����A15�ɂ��ĂقƂ�ǂ̎��͂�����������B
�Ŋ��͎o�̉ƂŌ}�����B�@
�@�@�E�@���V���Ă������������Ȃ�ɂ��薺�̑��ɂ�Ă����ɂ�����@
�@�@�E�@�����݂ɑςւĉ߂�������\�N(�����̂�)�̒Z��̕���ῂ��݂Č���
�@�@�E�@�����ʖڂ̌����Ђ��肠��[�����Ă��̂��͂ꂳ���͂��肫
�@�@�E�@�Γ�Ԃ̍炭�Ƃɕ��̂˂ނ��ē��̏Ƃ�ق��֕���������
�@�@�E�@�����̐S�����������\�N�̑ς֗������̔���������
�@�@�E�@�t���̖ڗ�(�܂���)�ɏh����N�o��v�Ђ𖾂邭�Ƃ点�@
�@�@�E�@�ڂ��Ђ炫�����Ƃ炦������ꐶ�ꂵ���Ȃ��K�F�̋�
�����āB�@
�@�@�E�@�Ɋy�̖�̔���T��قǂ̎��͂��c�����ł��ꂩ���@�@
�P�O�N�ȏ���̋��A���Ă��Ȃ��B�A��Ȃ��B
�@ �E�@����̂��܂��������ӂ邳�Ƃ̕��ւ����Ƃ͗���ɐ��܂�
�@�@
�@�@�E�@�����͂͂̂��͂����̑����Ƃ̂킪�\�܍̂͂邯������
�@�@�E�@���Ă��݂𗧂Ăđ��ӕ��l�̐��̒[�ɋ���l�݂Ȕ�����
�@�@�E�@�Ƒ��Ƃӂ݂������G�߉߂��ɂ������̂Ȃ��̂ɂ��肵�߂�Ł@
�@
���R�̕�炵335�@�@2017.8.8�@�@
�@ �@
�@
 �@�n���̊��̊W
�܂イ �@�n���̊��̊W
�܂イ
�����͔���B�Ȗ،��̓ߐ{�n���ɂ͂���ȕ��K���c��܂��B
���̒n���ł�8��1�������W����i���܂Ԃ��̂������j�ƌ�
�сA�n���̊��̊W���J���Ƃ������B����c�l���A�W�̊J�����������X�ɔ�яo���A����ƂȂ��Ă��̂��̂̉ƂɋA�낤�Ƃ�������ƌ������킳��Ă��܂��B
�n������̐��Ƃ܂ł̓��͗y���ɉ����A����i����j�ɏo�����Ȃ�����~�ɂ͊Ԃɍ����܂���B
�������Ȃ��A�Ђ����獰�̊҂�ꏊ��ڎw���ċ}������c�l�̔���������߂ɁA�p�ӂ���̂�����
�u�n���̊��̊W�\���v�@�i���N�n�ꂽ�������̔�ɒY�_�ƍ����������A���ɏ����Q���l�߂ď��������́j
�{���́A��������H�ׂ���悤�ɁA���~�܂ł�13���Ԃ̂Ԃ���\��������������悤�ł��B
�֎q����̔� �Ŏ��܂���ƁA����c�l�����݂�i�߂鉹����������ƁA�y�n�̌ØV�͌����܂��B
����c�l�͂��̂��\���̂ق��ɁA�֎q������������Â���闢�����@��o���Ă��H�ׂĂ���̂�������܂���B
 �������A�E�����_���\���@�@��������I
�������A�E�����_���\���@�@��������I
���~�͍�������n�܂��Ă���Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B
���̊W���J�������Ƃ���сA����̂��҂��҂����\�������������A�������������̊�т̂��������ɂ�������A�Ӗ��̂�����Ȃ̂ł��B�ł͂Ȃ��A����c�l�́u�n���v�ɂ���̂ł��傤���B���̏ꍇ�̒n���Ƃ͂��̐�
���Ӗ����܂����B�Ɋy�ł͂Ȃ��̂͂Ȃ��Ȃ̂ł��傤�B
���Ȃ�ɍl���Ă݂܂����B����͂���ȗ��R���炩������܂���B
�@�@�@�yWheel of Life�@�@�Z���։��}�@�z�@�i�܂��͘Z����䶗��j
�����ł́A�����̍s�ׂɂ���ė����̘Z��̐��E�ւ̍s���悪���܂�A�������J��Ԃ��Ƃ���Ă��āA����������̂��։�Z��ނ̐��E�̂��Ƃ�
�A�Z���։�v�z�ƌĂт܂����B
�P�@�n�����@�@�Q�@��S���@�@�R�@�{�����@�S�@�C�����@�i���C�����j�@�T�@�l���@�@�@�U�@�V���@�i�V�㓹�A�V�E���j
���ꂼ��̐��E�ɕ���u���A�ǂ̐��E�ɂ����Ă����ɂ��~�ς����邱�Ƃ�����Ă��܂��B
���́u�ǂ̐��E�ɂ����Ă����ɂ��~�ς�����v���Ƃ��A
���̂�̍߂��ӎ����Ă��錻���̐l�ԂɂƂ��đ�Ȃ��Ƃł��낤���Ǝv����̂ł��B�n���ɂ��Ă��~�ς͂���̂��ƐM�������B���Ƃ��n���ɗ����Ă������B������u�n���v�ł��̐����ے������̂ł͂Ȃ����ƁB
�ق��ɁB
�������Ȃ��̔��x�߂̂��߂ł���Ƃ��A�ċx�݂ɗՎ��o�Z����q�������ւ̂��J���ł���Ƃ��B
����Ȃ�����������܂��B
 �W�S�N�m�J�}�m�t�^�@
�ʖ��L�����\�E�@ �i�V�\�ȃL�����\�E���j �W�S�N�m�J�}�m�t�^�@
�ʖ��L�����\�E�@ �i�V�\�ȃL�����\�E���j
�捏�A�_�ސ쌧���͌��s�ɏZ�ޗF�l�i85�j�ɐq�˂Ă݂܂����B�F�l�̏Z�ޒn���ł́A�u���̊W�܂イ�v��8��16���ɍ���Ă���悤�ł��B���̒n��ł́u�n���̊��v�ɂ́A���������Ӗ�������܂����B
�N2��A�����Ƃ��~�̂P�U���O��ɂɕ���l���x�݂�������Đe���A����---�������M���肩�痈�Ă���----���[���c�ɂɋA�邱�Ƃ����M����B
�q���̔��N�Ԃ�̋A�ȂɁA���\��������đ҂��Ă����e�̊炪�����яオ���Ă���悤�ł��B
�n���̂悤�ȋߐ悩��ꎞ����邱��---�n���̊��̊W���J�����ƁB
�@
���R�̕�炵334�@�@2017.8.1�@�@�@
�@�@ 
�@
 �@�l��
�g������@ �i �����j �@�l��
�g������@ �i �����j
�����ōl�����̂ŁA���낢��|�J������̂ɋC���t�����B
�u���C�W���̓[���v�Ƃ������Ƃ́A���ƃJ���l�Y�~���������ɐQ�Ă���Ƃ���ƁA�ނ�l�Y�~���������C�𗘗p���đ���Ȃ��ł͂Ȃ����B���������c���c���A���������c���c���B�܂�Łu�g���ƃW�F���[�v�̐��E���B
�n���̏d�͂��W����͖̂������Ă��A�����͂������B
���@�l�Y�~�����ɂ́A���C�𗘗p�ł���ʂ̕���������������ĖႤ���A�̔ł��~���������������āA�ЂƓ�������
�@�@�@���炨���B
�E�E�E�E�E���āA�����܂ł��ĂȂ��A���̓l�Y�~�Ɉ��������Ă��炢�����̂��낤���B
�����͔���B�@
�@�@�@�E�@���܂����Ƃ�ŋ��̐S�n�悭�e���Â��ւĖ؉��ł䂭�@�@
�@�@�@
�@���R�̕�炵333�@�@2017.7.31�@�@�@
�@�@ 
�@
 �@�l��
�g������@ �@�l��
�g������@
�ߑO5�����N���B�������ɐ���@���͂��߁A�d�オ��܂Œ�����ǂ݂Ȃ���R�[�q�[�����ށB����̃��[�v�ɐ��͂ɏ��肽�Ă����ƁA���H�܂ł�30���͑O��̑����B
�@�@�����ł��łɊ������ɂȂ�B
8�����A���Ă��~�߂�h��^�I������Ɋ����A�N�[���[�{�b�N�X�Ɉ��ݕ������Ė{�i�I�ȑ����ɎQ�킷����A��͂�
�����������Ȃ�B
11���ɂ͋A��V�����[�𗁂т���A�J���������2�x�ڂ̊�����������B
�����A�����̎d���̃m���}�͏I���E�E�E�E�ƌߌ��Ԃɂ��傱���ƒ��Q�����Ă�����A�����S�n�̂Ȃ��A����Ȑ����������Ă����B
�u����ȂƂ���ŐQ�Ă���ƁA�l�ɉg������v�@�ƁB
�S���Ȃ���10�N���܂�ɂȂ镃�e�̐��������B
���������Ύq���̂���A�x���ɂ����荞��ŃE�g�E�g���Ă�����u�l�Y�~�ɁE�E�E�v�ƌ���ꂽ���̂������Ȃ��B���͂��Ƃ�ځB���Ƃ�ڂƂ͒��V�Œ�i�N��̉��j�̎q�B�܂薖���q���B
�͘F���̂Ƃ�ɓ����镃�̌Ӎ��̂Ȃ��ɂ����ۂ���荞��ł����̂��A�L���̒�ɂ���B
�c�ɉ��̎ŋ������̖،˂��˂�˂��ɕ�݂��܂�Ēʂ蔲���A�،˒�����������̂���������ƋL���ɂ���B�͂Ă˂��݁H
�ƃl�Y�~���A�h�u�l�Y�~�����Ȃ��̂ɁB����̂̓J���l�Y�~�����Ȃ̂ɁB���炤��ƍl�����B���̑̏d��50�L���B�J���l�Y�~�������W�܂��Ă��̂��̎��������A���̎������̑̂Ɍ��ѕt���A�������낤�Ƃ��鎞�A���������ǂ̂��炢�̐��̃l�Y�~���K�v�Ȃ낤���E�E�E�H���̌��i���Ă܂�Łw�K�����@�[���s�L�x�̒��̏��l���̃K�����@�[�ł͂Ȃ��H
�J���l�Y�~�����́A�ǂ̂��炢�͎����Ȃ̂��낤�H
�l�Y�~�����āA�����̑̏d���炢�̉ו�������������ˁB���̏ꍇ���C�W���̓[���ƍl���悤�B�܂�c���c���B
������������̂ɂ͉��C�K�v���낤���H
50�L���O������50000�O�����@500000�����i1�C�̑̏d10���j��5000�C���I�������I1�C�̃l�Y�~����߂�ʐς́A�������Ƃ��Ă�������8�Z���`�~3�Z���`��24�Z���`�������[�g���ƍl���悤���B�������5000�C����12�������[�g���Əo���B����܂��B���̕������l�Y�~�ň�t�ɂȂ邶��Ȃ��H
�J���l�Y�~�͌����łȂ����炢�����ǁE�E�E�B���̃l�Y�~�B�@�@�ǂ�����Ē��B����H
���R�A�u�˂��ݎZ�v�ő��₷�̂��������낤�ȁB
���������Ă�������l�ԃJ�[�����O�̎��́A���������ǂ��֘A��Ă������̂��Ȃ��B
�Ȃǂƚ����Ȃ����Ƃ��l���Ȃ���A���Q����o�߂��B���āA���ꂩ��ߌ�̎d�����B
�@�@�E�@�������ւ萶�܂ꂩ�͂�𗊂݂Ƃ��ꖳ���\�N�i�����Ƃ��j�������\�N�i�ƂƂ��j�@�i���j
�J���l�Y�~
�i���l�A���l�AMicromys minutus �j�́A�l�Y�~�ځiꖎ��ځj�l�Y�~�ȃJ���l�Y�~���ɑ����鏬�^�̃l�Y�~�B������ 54�`79mm�A����
47�`91mm�A�̏d 7�`14g�̓��{�ł͈�ԏ����ȃl�Y�~�̂��ƁB �iby Wikipedia)
 �J���l�Y�~�����邻�����B �J���l�Y�~�����邻�����B
�@�@�@�@�@���R�̕�炵332�@�@2017.7.30�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@ �@�щ���肻�̌� �@�щ���肻�̌�
 �@��{�̌s��50�̉ԁB�x���������Ɠ|��Ă��܂��B �@��{�̌s��50�̉ԁB�x���������Ɠ|��Ă��܂��B
���̂Ƃ���̃j���[�X�F
�@�Z�@�����̃u���[�x���[�̎��n�͏����ŁA����7�L���̍��ۂ������Ⓚ�ɂŏA�Q���B
�@�@9�����{�܂ŁA�̉��ɐ��荞�݊��������Ȃ���̎���ꂪ�����B�ڕW�͍X�ɍ����Ȃ�15�L���I �Z�@����̒��A�߂��Ƀc�L�m���O�}�����ꂽ�B
�@�@�@�Ƃ���ق�̏������ꂽ�ꏊ�ŁA�u�������v�ƌ��������u�����v�ɋ߂��B
�@�@�@�_�Ƃ̔��̃g�E�����R�V���n���Ă����̂ŁA�����ړ��Ăɂ���Ă����炵���B
�@�@�@���̎����̌F�́A�H���Ӓn�������Ă��邤���Ɏq�����Ȃ̂œ��ɋC���r���B
�@�@�@�������Ɩ邪��Ȃ��̂ŁA�C��t���悤�I�ƌ����Ă��ˁE�E�E�B
�@�@�E�@�J�����̊Ԃ̂ЂƂƂ������J���₤�Ɍ̐l�̒�ɂ䂤�����̍炭
�@�@�E�@�ꂵ�݂̈�u�Ȃ邪�Ȃ����߂��F�������Ă̂������Â���
�@�@�E�@�߂����������ߖ@�ɂČ��Ƃ����̂Â���Ȃ�t���̓��X
�@�@�E�@�g�ɂЂƂЂ��炵�̂�����藈�ĂЂ߂₩�ɂ����J���䂭�Ȃ�@�@
�@�@�@�@�@���R�̕�炵331�@�@2017.7.22�@�@�@
�@�@�@�@ 
�@
�@�@�@�@ �@�R�S�����ǂ�����炫�܂����I�@�@��200�{�I
�@�R�S�����ǂ�����炫�܂����I�@�@��200�{�I
�@�@�@
�@�@�@�E�@����Ɨ��̊k��剝���悤�� �߂��߂����͓y�Ɛe����
�@ �@�@�@�@���R�̕�炵330�@�@2017.7.16�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �{���̎��n�͂P.�TKg�@�E�E�E�u���[�x���[
�{���̎��n�͂P.�TKg�@�E�E�E�u���[�x���[



5��14���@�J�ԁ@�@�@�@�@�@�@�@�p���p���Ən���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���n�@7��11��
������60���ŏn�����@Blueberry�B�C�̑�����X�ɂ҂�����ׂ̂�[�E�E�{���̎��n1.5�L���Ȃ�B
����ō��v4.5�L���ɂȂ����B�Ⓚ�ɂ����t���B�����̎���������낻��I���ɋ߂��A���̒����̎��n�܂ŏ������Ԃ�����B���N�̖ڕW��12�L���B���N��16�L���A���̑O�̔N��23�L���I�������B
���R�̕�炵329�@�@2017.7.11�@
�@�@ �@�@
�@
�@�@�@�@ �}�C�u�[���̓S��������
�}�C�u�[���̓S��������
�^���s�����������Ȃ�����A������������̂͌����B
����Ȃ킪�܂܂������Ă�����A�g�̂��ǂ�ǂ�d���Ȃ�A�ܐ悪�オ��Ȃ��Ȃ��Ă����B�S�����߂āA���̑��Ƒ��̑��H�̂��Ƃ̓��ۂɂ��邱�Ƃɂ����B
�������A���̓�̑̑��𑱂��Ă���̂͂����ɂ��I�J�V�C�E�E�E�E���̑��ŃE�H�[�~���O�A�b�v���A�N�[���_�E�����B����ɑ��̑��ŃE�H�[�~���O�A�b�v���A�N�[���_�E�����B����������������Ă��邱�Ƃ��B
���̑��̍��߂͂��̂܂܂ŁA�����g�̋����ɓw�߂邱�Ƃɂ����B��ڎl����b����悤�X�N���b�g���A�̊���������ƕۂ��o�����X�������K������B
�Ō�ɁA�X�N���b�g�����`����
�i���Ȃ킿�ˋ�̈֎q�ɍ������`����A�܂��͂����o����̎l�҂̌`����j
������������邱�Ƃɂ������B���̂��܂�d���ɋ���10�����߂��B
�S�W���̊��D�Œ����ς炩�狏�Ԃ���������A���̊O���猩���l�͋������낤�ȁB
 �u���[�x���[�����n���ɁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �u���[�x���[�����n���ɁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@品i�Ђ��炵�j�����͂��߂��B�ߐ{�̉Ă�哂Ŏn�܂�A哂ŏI���B
���R�̕�炵328�@�@2017.7.7�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@ �A���̖��O�͂��̉Ԃ���
�A���̖��O�͂��̉Ԃ���
�~�J���Ő������}�������̂���B�x�炫�̃V���[���[�|�s�[���A����� �h��Ă���B
�w�Ԗт̃A���x�̍�҂k.�l.�����S�����́A��l���̖��O���l���Ă��鎞�A���̊O�Ɍ�����Ԃ��P�V�����Ė��O�̃q���g���炵���B�@��@�������̂����@�Ђ��Ȃ����́@�͂��Ȃ́`�@��@�i���@�R��H�v�j�@�̂ЂȂ���������B
�����āA�^�Ӗ쏻�q�B
�O�N�̏H�n�������v�E�S����ǂ��A�P�X�P�Q�N�̏t���{�𗧂��A�V�x���A�S���o�R�Ńt�����X�����������q���p���Ō����̂́A���̐Ԃ�㠈��i�R�N���R�j�B���[���b�p�ł͔���̏ے��B
�E�@�����H���������̖�͉̐F���N�̐�㠈�������㠈��@���q
�@�@ �@�@
��̃P�V�A����l���Ƃ�������B �@�@
��̃P�V�A����l���Ƃ�������B
�@�@�E�@�����肵�����̂��Ƃ����킪��ɃA���̖��O�̐Ԃ��ԍ炭
�@�@�E�@�n�ɕ����ĐL�т�����Ԃ������k�Ɍ��𗁂т����Ƃ��Ӂ@�@
�@(�����S�����̍�i�ɂ́A��l�����l���̖ړI�ɂ��Ėk�Ɍ��i�I�[�����j�ɐG������镔��������j
�@�@�E�@���낪�˂̉J�ӂ�Ȃ��̃R�N���R�̓��ސS���Ђ��߂ċ���ʁ@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�A���͐��U�A����������Ă��ꂽ�}�V���[�����Ă���j
�@�@�@�@
�@�@�@�@�@ ���R�̕�炵327�@�@2017.7.1�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@
 �L�Ƀ}�^�^�r�A�v�ɂ͔����i���܂����j�A���ɂ́H
�L�Ƀ}�^�^�r�A�v�ɂ͔����i���܂����j�A���ɂ́H
�@ �@ �@
�@�@�}�^�^�r�i�ؓV���@Actinidia
polygama �j�́A�}�^�^�r�ȃ}�^�^�r���̗��t�����ؖ{�B
�앗�i�͂��j���������̋G�߂ɁA�щ���R���ɔ�������߂��t�������鐫�ׂ̍��}�������ڗ��B
����̓}�^�^�r�B�i�}�^�^�r�́E�E�E�E�җ��H���A�����ł���H���痈�Ă���̂��ȁH�j�}�^�^�r�͎v���[���B�}��҂��ĂԂ��߂ɉԂ�t�����}�̐�[����̎ʐ^�̂悤�ɗt�𔒂��ω�������B�i�����j
�ǂ����������̖��Ȃ̂��A�A�����v�l�͂����Ƃ����l�����Ȃ��B
�����ɐB�̂��߂ɁA�����邽�߂ɁB���ɂ͗t�𔒂��ς��A�Â����𗭂߁A���ł₩�ȉԂ��炩����ԂƁA�Ԃ��i��A�����̂��̂̈ӎv�̋����������邱�Ƃ�����B�Ȃɂ��A�}�^�^�r�́u�L�Ƀ}�^�^�r�v�Œm���Ă��悤�B�}�^�^�r���L�̓����Ɏ䂩��A�l�R�Ȃ̓����͜����Ƃ���炵���B
�F�l�̔L�����i���m�ƃ~�~�j�̂��߁A�R���牽�{���̎}������Ă����B����A���̔L����̎�����Ɋ����������}��n���Ă���B�͂Ă��ĔL����͂ǂ̂悤�Ȕ����������̂��A�F�l�̕��y���݂��B
���C�I�����g�������̃}�^�}�r�ɐS��D����A�Ɩ{�ɂ��邪�A���̑傫�Ȑ}�̂ł��̉Ԃ̎��͂��̂�����̂��Ƒz������Ɩʔ����B
�E�@�Ђ邪����g�����炵�܂����т̑剹���ɒ����ĂԔ��@
���āA�p�\�R���V�т͂���܂ŁB�L����̎����傩�璸�����~�ŁA���܂���~�W�����������炦�܂��B
�@�@�@�@ �@���ꔒ�~ �@���ꔒ�~
���R�̕�炵326�@�@2017.6.26�@
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@�@ �@�G���p�i�[�_���̌�
�@�G���p�i�[�_���̌�
�L���Ƃ͕s�v�c�Ȃ��́B�g�̂̉��ӂ����A�C���̂悤�ɂ��䂽���Ă����v���o���A�G��̓����ɂ���߂Ƃ�ꂽ�̂��A����Ɍ`���Ȃ��Ȃ���A�����������Ă����B
���̃G���p�i�[�_�̂��X�̘Ȃ܂����v���o���Ă݂�ɁE�E�E�E���ɂ���{��̃L�b�`���ō��A���삳�O��ɂ��鉮��܂ő����Ă��āA�i������ׂĂ���
�悤�������B
�]���̃G���p�i�[�_�����߂ė���Ȃ����q�Ƃ̉�b���y���݁A���ɉԂ𓊂��iechar flor�E�E�E����������˂��E�E�E�Ƃ������������̌��t�𓊂��邱�Ɓj�A��k��
�A������I�W�T���́A���̓��_���l������ �̂��v���o�����B
�����������B���������_���l�ł���e�����F�l����A���̃I�W�T�����o���������Ȃ̂��Ƃ́A�������łɕ����y��ł����̂������B
���̍��̃��_���l�̃R�~���j�e�B�͂ƂĂ����������̂ŁA�݂��ɏ��������̂��ٍ��ł̕�炵�̍���ɂ��������炾�B
�N�̍��͂T�O����݁A���g�łӂ�����Ƃ����Ԃ��A�O������ނ��Ă���I�W�T���́A�i�`�X�̔��Q��Ă��̍��ɈڏZ���Ă��Ă����B��풆�ɂ͂����炭���w�����炢�̔N������낤�B
�����Ƀz���R�[�X�g��̌������̂��낤���B
���݂ɃX�y�C�����������Ă������A�{�����_�����̋��������̐��_�����ł����͂��B
�����̎��́A���ɖт����������炢�̔N��ŁA���_���l���w�����Ă�����j�𗝉�����ɂ͂قlj�����Ԃ������B
�{��f���Œm���Ă��������́A���_���l�̕��G�ȗ��j��i�`�X�ɂ�锗�Q���A�����ɂ��������ƂƂ͂ƂĂ��M�����Ȃ��E�E�E����ȗc���S�̎����傾�����B
���������\�N��A���_�����̐��n�E�G���T�����𗷂��A�I�����_�E�A���X�e���_���Ɏc��u�A���l�E�t�����N�̉Ɓv��K�₵�A�����̃��[���b�p�̗��j�Ɏv����y���邱�Ƃ��ł������ƁA���ЖK�₵�悤�ƍl��������
�B
����ɓߐ{�ɂ���A�E�V���r�b�c�L�O�ق����K�˂�o���Ɍ��т����̂́A���̎���A�A���f�X�̍���������̂��ƁA�I�W�T�������n�����ꂽ�G���p�i�[�_�ɂ��Ԃ���A
�ނ̃��_���l���L�̉��܂����ڂɏh������������炩������Ȃ��B�d���d�������̂��т��Ɏ����Ȃ�����A����ƕ�����ʂ悤�ɖ��邭��k�������Ă����I�W�T���́A�܂��G���p�i�[�_������Ă��邾�낤���B
 �@䉖�
�@�Ԑ��� �@䉖�
�@�Ԑ���
�@�@�E�@�u���͂�v�̂��Ƃ̌��t��T����č��i��ׁj�̌��܂̐��ׂ͂��炸���@�i���j
���R�̕�炵325�@�@2017.6.20�@�@
�@�@ �@�@�@ 
�@
 ����̓G���p�i�[�_
����̓G���p�i�[�_
�@�@ �@Las�@Empanadas �@Las�@Empanadas
�Ⴂ����Z��ł������Ƃ̂���A��Ă̍��̋��y�����A�G���p�i�[�_�B
�������������������t�̋����̃G���p�i�[�_�B
�G���i���ɁA�`����j�p���i�p���́j�i�_�i���̂悤�ɗ�������j���ꏏ�ɂȂ������t�G���p�i�[�_�B���������~�[�g�p�C�B�����~���`�Ɗe���ƁA�i���ꂪ�̐S�́j�Ɠ��̃n�[�u�����W�����ėg����E�E�E���̒P���ȗ������A�X�𗣂ꂽ�쌴�Ƀ|�c���Ƃ��鉮��Ŕ����H�������̂́A����͂����R�T�N�ȏ�̑O�̂��ƂɂȂ�B
����������Ă��邨�����A�o�̎���̃o�b�O����Ɏ�����
�u�Ȃ��A�����̂���B�ǂ����痈���H���{���炩���H���{�ւ̓o�X�łǂ̂��炢������H
�@���̃o�b�O�Ƃ��̃G���p�i�[�_�P�O�O�ƌ������Ȃ��H�v
�Ɩ{�C�ŕ����Ă����̂��v���o���B
�@�@�i���̂Ȃ��ɓ�����u�킳�сv����ꂽ�G���p�i�[�_������̂��B�����肩�͂��ꂩ�A�ǂ������낤�j
6��12���@���N�͂��߂āu�G�]�n���[�~�E�ڈΏt��v�̐������B��N�ɂȂ��x���B
�@�@
�@���R�̕�炵324�@�@2017.6.14�@�@
�@�@
�@
 �G�S�m�L�@�i�G�S�m�L�ȁj�@�Ԃт�̐��͑f�����D�݂̂悤��
�G�S�m�L�@�i�G�S�m�L�ȁj�@�Ԃт�̐��͑f�����D�݂̂悤��


�@�@�p�̖̑傫�ȗt��ʂ��Ƌ���Ő��F�ɐ��܂�B
�E�@���ɂ���݂苴���s���v�Ђ��Ĕ����ԍ炭��ɘȂށ@
�@�E�@���V�i����Ă�j�̗����Ȃ�ނƂ����̖̕��э炭���܂��ނ�̂��Ƃ����@
�@�E�@�L���̔��Ƃ��ӐF���͂܂�Ă��߂��͂��Ӊԓ��a�@
���R�̕�炵323�@�@2017.6.5�@�@
�@�@ 
�@
 �U��~���@
�U��~���@

�T�����{�̗������ŊJ�Ԃ��x�ꂽ�I�I�f�}���B
�悤�₭�炢�����Ǝv�����̂ɁA���̌�ɏP���Ă����ܔM�̂R���Ԃɑς���ꂸ�A�Z�������U�炵�Ă���B
�E�@�Ă܂�ȓy�ւƊ҂���̒��͂ЂƂ�ڂ����̂��܂��ЗV�ԁ@�@
���R�̕�炵322�@�@2017.5.30�@�@
�@�@ 
�@
�@ �@������Ɏ��������@�E�E�E�E�@�щ��̕s�v�c �@������Ɏ��������@�E�E�E�E�@�щ��̕s�v�c
�@�@ �@ �@
�@�@�@�@�@�@�@�R�S���̌s�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R���̎}�ƐV��
 �@�R�S���̓��̕���
�@�i���q���̂悤���j �@�R�S���̓��̕���
�@�i���q���̂悤���j
�ŋ߁A��Ō�������s�v�c�Ȍ��ۂ�����B
����͑щ��i�������j�B�ԉ��i�Ă����j�܂��͐Ή��i�������j�Ƃ��Ă��A�A���̂����̊�`�Ȃ̂��B
�s�̏㕔�ɂ��鐬���_�̕����g�D�Ɉُ킪�����A���̌s��t�⍪��ʎ���ԂȂǂ��L��������A�������Ȃ����肵�A�я�ɕ��ɂȂ邱�Ƃ������炵���B�i�����g�D�Ƃ́A�A���̖������ȍזE�̂��ƂŁA�זE������s���Ă���g�D�j�����͓ˑR�ψقɂ����̂��`�I�Ȍ������l������悤�����A�ۂ̊����⍩���A�_�j�Ȃǂɂ�鏝�Q�����̂��������ɂȂ�炵���B
�h�{�����ߏ�Ȏ����N����Ƃ��������A�����Č����āB���̒낪���̂悤�ȏ�Ԃɂ���Ƃ͍l���ɂ����E�E�E�i�����h�{���������₷���A���I�w�̏�ɂ��鑉�����y�n�̒�Ȃ̂ŁE�E�E�j�����ԂɎg����Ή����i�M��G�j�V�_�́A�Ϗܗp�ɒ��d����Ă��邪�A��̕S�������̏�ԂɂȂ������ɂ́A�������̋����̐����������߂邵���Ȃ����낤�B
���͂��g���ʂ����A������ƌ͂�Ă��܂��̂��I�`�Ȃ̂ŁB����͎��R�����Ƃ��l�����邪�A�Ȃɂ��я�ɂȂ��Ă܂ł������悤�Ƃ��Ȃ��Ă��悢�̂ɁB�@�@�@�@�@�@
�������z�g�g�M�X�E�E�E�͂��߂ăz�g�g�M�X�̖��������B
�܂��̂Ȃ��A�����тȂ����ы����čs���B�����炭��̑����T���Ă���̂��낤�B
�@�@�@���R�̕�炵321�@�@2017.5.25�@�@
�@ �@
�@
 �@
�`�S����(�t���S��) ���炢�Ă����@�i�����ȃ`�S�������j �@
�`�S����(�t���S��) ���炢�Ă����@�i�����ȃ`�S�������j
 �@
�@

�@�@�@�w�̍�����T�Z���`����P�O�Z���`�@�@�@�@�@�@�Z�̎��i���̎��̔w�̍����P���قǁB�`�r�ł����j
�������ɍ炭�A���������炵���Ԃ̎p����������u�`�S�����E�t���S���v�Ɩ��t����ꂽ�悤���B�`�S�����́A���̊O���ł͑z�����ł��Ȃ��قǂ̐����͂��������Ȃ̉ԁB
���X�n���s��L���A��̋��X�܂œ꒣����g������p�ɂ͈��|�����B�����Ă������Ă������Ă���h�N�_�~���݂̂�������҂Ȃ̂�����B
�t���Ƃ������A�c���̂���
���A����� ������
�q�Ƃ������t���k�炵���B
�t��Ԃ̉Ԃ��炫�I���������A���x��Ă��̎����ɉԌs��L���Ď��Ȏ咣����`�S�����E�E�E�������炢������B
�����N�̍l���Ă��邱�Ƃ͕�����������E�E�E�B��r�ɐB�������낤�H
�t���S���Ŏv���o���̂͘Z�̏H�A�����������{�̒ޏ��̊������j�����c�@�v�̒t���s��ɎQ���������Ƃ��B
�����炭�����̋L���̂Ȃ��ň�ԌÂ����̂��Ƃ��v����B
�����������ȗ��������t��������g�ɕt���A�V������z�Ɂu�ʐ��v�ƌĂ��Ԃ��ۂ��|�c���Ƃ����p�����ł��v���o�����炢��ۓI�ȏo�����������悤���B�_���ł́A�u�_�l�͗c����q���̎p���Ȃ��Č����v�ƐM�����Ă����炵���̂ŁA���̕����Ɖ��ς͐_�������B
�_�l�ɂ��d�����A�q��̖������q�E�����i���́j�ɂ͐_�̗삪���t���Ƃ������Ƃ��B
�Z�o�����͂��̍s���ɎQ�����Ă��Ȃ��B
�����{�̒ޏ��������j���Ƃ�����D�̃^�C�~���O�Ő��܂ꍇ�킹�����Ƃ́A�ƂĂ��K���Ȃ��Ƃ������Ǝv����B���ݎ茳�Ɏc��̂͏�̈ꖇ�̎ʐ^�ŁA�J����
���l�����̂������������ɁA���������N�����̎ʐ^���B�e�����̂��A�s�v�c���B
���t������Ƃ��č�ɎQ�����邱�Ƃ́A�q���̖��a���Ђ��F�闼�e�̊肢�����߂�ꂽ���̂ŁA���̎����͎l�\�߂��A��͎O�\���B���̎����������Ƃ����ƎႩ����
�B
���R�̕�炵318�@�@2017.5.12�@�@
�@�@  �@�@�@ �@
�@�@�@ �@
�@ �@  �@�g�̉ʂĂ�m�炸����䂭�l����č����ڂ�鉹�������Ȃ� �@�g�̉ʂĂ�m�炸����䂭�l����č����ڂ�鉹�������Ȃ�
��a�̂`�k�r�i�؈ޏk�������d���ǁj�ǂ��A�p�[�L���\���a�ƔF�m�ǂ���������
���l���A5�N�ɂ킽�莩��ʼn��𑱂��Ă����F�l���A�S�؍[�ǂœˑR�����Ă��܂����B
���ꂽ���Ǝv�����Ƃ���������Ǝv�������Ƃ��������͂��Ȃ̂ɁA�����ł��������낻���ɂ���悤�Ȃ��̂�̐S�̓���������A�Ȃ݂Ă킪�g�������ȂށB
����ȗF�l�������B
���̒��A���l�̌������ς܂���9�����낾�����炵���B
�S�̍[�ǂɏP��ꂽ�F�l�̋ꂵ�ގp���A�ʎ��ɐQ������ł���z��҂͌������낤���B���������낤���B�߂��݂�F�m���邱�Ƃ��ł����̂��낤���B
�������ꂽ�̂́A���삪�N���Ă���4���Ԍゾ�����B�F�l�́A�z��҂̐�]��ꂵ�݂Ɋ��Y���Đ����Ă�������5�N�Ԃ̔߂��݂ɂ��A���̍��ԂɌ����������Ȋ�тɂ��A���������������Ă����邱�Ƃ����ł��Ȃ������B
�펯�l�ŐM���ł��鐔���Ȃ��F�l�����������ɁA���������낽�������Ȃ̂��\����Ȃ����Ȃ��B
���̓������炫�A�������ɎU��䂭�C�z�������Ă����B
�F�l�͍��Ƌ��ɐ������B
�@���̂��̖��i����j���Ƃɗt�𐂂�ėh����Ȃ���������
�@�^����ꂵ������邩�̂悤�ɂق�ق낳����Ԃ̂��ڂ��
�@�̉Ԃ̂��ڂ�邳�܂ɕ�������
�@�Ԃ��ڂ�ފݍ��݂̂��͂Ђɂ�
���R�̕�炵318 �@2017.5.3
�@�@�@�@�@�@ 
�@
 �j��P�@���u���K�T�@�i�L�N�ȃ��u���K�T���̑��N���@�@�w���� Syneilesis palmat�j�@
�j��P�@���u���K�T�@�i�L�N�ȃ��u���K�T���̑��N���@�@�w���� Syneilesis palmat�j�@
�@
�@�@�@��O�̂���Ȃ肵�Ă���̗t�͎R�S����2�N���B�@�������E�̗t�͈�N���B
�@�@�@�@�@�@�N��Ⴄ�̂ł��B�Ԃ��炭�̂́A5�N��B
���̒��́A�S�[���f���E�E�B�[�N�Ə̂��ĕ�����n�߂Ă���̂ɁA���u���K�T�Ȃ�Či�C�̈������O�̐A����t����̂͂ǂ����ȁH���͂��̃��u���K�T�͐H�ׂ���悤���B�R�ؗ����̖{�ɂ��ƁA�u���Z���A�V�w���ɔ����v�Ƃ���B
�ɍ\���A����X�˂��悤�Ɍ�������̂́A�Ȃ̂Ȃ��f���ȏt�̖�������炵���B
�������A�����̒�ɐ����Ă������̂�H���̂́A�������Ɏv���Ď���o���Ȃ��ł���B
���̎����ɒ�ŐH�ׂ�����̂́G
���̃��u���K�T�A�E�h�A�O�t�A�~���E�K�A�R���A�������A�V�\�A�j���A�A�T�c�L�A�g�g�L�A�I�P���A���L�m�V�^�A�t�L�A�^���A�V���L��J���]�E�ȂǁB
�A�x�ɕʑ��ɂ����łɂȂ邲�Ƒ��Ƃ̍��e��H�E�E�E���������Β��Ԃ̈��݉��\�肵�Ă���̂ŁA�u�^���̉�ƃV���L�̓V�w�����������邱�Ƃɂ��悤�B
���R�̕�炵317 �@2017.4.28
�@�@�@�@�@�@
�@
 �@��������B �����N���������B�@
�@��������B �����N���������B�@
���傪�Ԑ���B���̐����悻3��{���B
�т̒��𗬂�镗�ɗh��A���̕����g�ł��Ă���̂�����̂́A���̋G�߂̈�Ԃ̊y���݁B
�u���̂悤�ɗh���v�Ɖ��O�̉Ԃ�\�������o�l���������A�������Ė����B
���傪�h��߂��h��Ă���̂����Ă��邤���A�s�v�c�Ȃ��Ƃɂ��̗h�ꂪ�u�������̂ӂɂ�ӂɂႵ�������v�ɏd�Ȃ��Ă��Ă��܂����B�Ȃ����낤���B
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�������@
�悶�o���Ă��� �@�������@
�悶�o���Ă���
�k�邱��3�N�B�^�q�`���̎�s�p�y�[�e�ł̗[�H��ł̂��Ƃ������B
�����̃_�C�j���O�e�[�u���ɍ����đO�Ɏ��t���Ă��鎞�A���ׂɍ������i�V�j�a�m���b�������Ă����B
�u�����̌ߌ�A���M�ɏ���ĎX��ʂ��߂���A�G�C�ƈꏏ�ɗV��ł��A�ق炱�̎ʐ^�����Ă��������B�v
�u�����Ȑ��ɎX��ʂ̐F���f���Ă��炵���ł��ˁB�G�C�͓Őj���ĉa�t�����Ă���̂ł��傤���H�v
�@�@�i�����I���̌����ȑ��_�͂��̓��̉����ɍs��������Ȃ������̂��B�c�O���Ȃ��j�i�S�̐��j
�u����H���̓������傫�ȃs�b�`���[�̊O�������Ă��������B���̏������Ăӂɂ�ӂɂ�Ƃ��Ă���̂́A����������Ȃ��ł��傤���B�v�u����Ȃ���K���ɏ�ɓo�낤�Ƃ��Ă��܂���B�v
�u����I�{���ł��ˁB������āE�E�E�E�������ł��傤�B�v�i���������Ƃ��ł͋����Ȃ����j
�u���������ĉƎ�B�Ƃ̎��_�ł���B���{�̃������ƈ���Ĕ������F�Ɣ��̐F�����Ă��܂��ˁv
�u����ɂ���Ȃɂق����肵�Ă��āI�v
�u�����ł���ˁB�̂̉Ƃ̌ˑ܂ɂ悭����ł��܂����ˁB�q�������������́u��������v�ƌĂ�ʼn������Ă������̂ł����B�܂��z�e���Ȃ̂Ƀ��������]���ďo�Ă���s�b�`���[�Ȃ�Ē��������ƁI�L�O�Ɏʐ^���B���Ă����܂��ˁB�v
�₨��J�����ɔ[�߂Ă̂��A�Y���������菵�����A�i�ق��̐l�ɂ�Ȃ��悤�ɏ����Łj
�u�ق�ˁB�����Ƀ������������ł��E�E�E�B�v�Y�������͎��͘T���B���낽���邱�Ƃ��낽���邱�ƁI
���܂��ɁA�������ɍ������s��l�Ȃ̂��낤�A��l�̂��w�l���A�����Ȑ��������̂ɂ�������A����[����[�����܂���B
�u�ǂ����悤�B���A���̐�����������B�����������那�����E�E�E�E�B�v�u���v�ł���B�͂��Ă��炸���ƃ��������������Ă����̂ŁA�N�����̐�������ł͂��܂�����āB�v
�ƂȂ��߂鎄�B�i���邳�����A�����ȁj�i�S�̐��j
���炫�̐���̎��ɉԂ�h�炵�Ă���̂́A�A�C�X�t�H�[���X�Ƃ������Ȗ��O�������Ă���A�������F�̉ԁB
�������͂��̉Ԃ̐F�����Ă����̂������B�����琅��̗h��邳�܁��������ƘA�z�����̂��낤�B
����������̂�����̂��v�������ׂ��������B
���{��������B�@�@�����~������o�߂������H
�@ ���R�̕�炵314 �@2017.4.8�@
�@�@�@�@�@�@�@

 �������Ƃ܂���
�������Ƃ܂���
�@�@�E�@�Ⴊ���͂܂��������Ȃ����� ���ӂ̓���̉������Ȃ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��Җ���(����)
���t�W ��14-3403
�@�@ �E�@�ƂɂĂ����䂽�Ӗ��g�̏�Ɏv�Ђ�����Ή����i�������j�m�炸���@
�@�@���t�W�@��17-3896�@
���܁A�w���t�W�x�̒��́A����ȉ̂��C�ɂȂ��Ă���B
�����̉̂ɂ���u�������v�Ƃ́u�����v�B���̕��A�ʂĂ̈Ӗ������Ɠ����ɁA�u�䂭��̂��ƁA�����ɂ́v�Ƃ̌�`���܂ށB���t����̐l�����́A���������Ԃ�����Ă��邱�ƂɁu���E�����v�������Ă����悤���B����͋����o�ɋ߂��̂�������Ȃ��B
���Ƃ��Ώt�ɂȂ�䂭���Ƃ��A�u�t���藈��v�E�E�E�E�R�̌���������t������Ă���A�ƕ\���A�����߂��䂭���܂��u�������s�����Ɓv�Ō�낤�Ƃ���B
�Ȃ�A�u���v���ǂ��\�����Ă������H
���݂́u�܂����v�B���́u�܁v�́u�ځv���B�ڂ̑O�ɂ��錻�����ڂ�ς��l�q���u�܂����E�ڂ����v�ƌ����\���A���Ԃ��̂��̂̓��������A����₠��s�����Ȃ���Ă��邱�Ƃ��d�����Ă���B���́u�����܂����v�̘A�Ȃ肪��������ɉߋ��ɂȂ��Ă䂭�B
�u�܂����v���h�~�m�|���̂悤�Ɍ��݂��т��A�����������ɋO�Ղ�`���Ȃ���B
�ߋ������݂��ЂƂȂ���̂��́A�Ƃ̊��o���V�N�Ɏv����B���̎��ɂ��関���́A�������Ă���ꏊ���牓���āA�ʂĂ��Ȃ��ꏊ�ɂ��邪�A�g�̊��o����߂��Ƃ�����
�Ă����̂�������Ȃ��B
�����āA������́u�܂����v�͐^�t�B
���̏ꍇ�́u�܁v�́u�^�v�ŁA�܂��ƁA�܂��߁A�^���A�{���A�����Ȃ�\���u�܁v�B����ɋt���܂Ȃ��Ƃ��N����---�܂����I
�ŋ߁A�܂����I�Ǝv���邱�Ƃɑ������A���݁i�܂����j�ɐ^�t�i�܂����I�j���d�Ȃ�o�������������B
������ǂ��l���邩�A�������l���Ă݂Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
�@�@�E�@�������ꂩ�g���M�ɂȂ��Ă킪�S���̋�֓����Ă͂���ʂ��B�@
���R�̕�炵312 �@2017.3.22
�@�@�@�@�@�@

�@  �����Ԃ���ɃX�C�b�`������ɂ́@---�@�^�C�}�[�ݒ�\���͂Ȃ�12���ԂȂ̂��B
�����Ԃ���ɃX�C�b�`������ɂ́@---�@�^�C�}�[�ݒ�\���͂Ȃ�12���ԂȂ̂��B
���@���̂P�@�@�i���ꂪ��ԑ������낤
�j
���̎������N�_�ɁA�w��܂�Ȃ��琔���Ă݂�B�ߌ�10������ߑO6���܂ŁE�E�E�B
11���A12���A1���A2���A�E�E�E�E6���B���A8���Ԃ��B����͂܂������P���ȕ��@�B
���@���̂Q
���@���̂P�ł͊��Ⴂ���邱�Ƃ�����B���ߌ�10���ŁA�����̒���6���ɃX�C�b�`������ɂ́A
�u6���v��18���ƕϊ����A�u�P�W�����P�O�v�ŁA8���ԂƓ������B
�Ȃ�قǁB�^�C�}�[�ݒ�̎��Ԃ̕\����12���Ԑ��ɂȂ��Ă��闝�R�͂������I
�����24���ԂŁA�N�_�̎��Ԃ͏�ɌߑO�����ƍl����Ƃ킩��₷���B
���@���̂R�@
�i�܂������댯�ȕ��@�������ȁj���_�ɕ����Ă݂���A�\�z�ʂ�B
�u���`��B�ȒP�B�ߌ�10������ߌ�12���܂ł�2���ԁB�ߌ�12������ߑO6���܂ł�6���ԁB���̓�̐����𑫂�������v�B�Ƃ����B
�������B���������������B�ʓ|����Ȃ��H
��ÂˁA�Ӂ`�H�Ɗ����邱�Ƃ������������A�e�L�̓��̒��͂����Ȃ��Ă���̂��B�Ƃ��݂��ݎ�������
�@�i�e�L�Ƃ͘a�̎R�قŁA���̐l�A���̐l�A�ށA�ޏ��̈Ӗ��j
���R�̕�炵310 �@2017.3.9
�@�@�@�@�@�@

�@�@ �@�����̂��̌� �@�����̂��̌�
�\�z�͂��Ă������̂̐U���������i�ɂȂ��āA���۔������N���Ă��܂����B
�����͒��~���ȁE�E�E�B
���̓~�܂ŋ˂̔��ɂ��܂��Ă����A��̋G�߂ɂȂ�����l���悤�A�ƈ�Ԋy�ȕ��@����邱�Ƃɂ����B�@
����摗�肵�������Ƃ����x������v���ɂƂ����B
�@
�@�@
���R�̕�炵313 �@2017.3.30
�@�@�@�@�@�@�@

�@  �@�킪���������̏I���
�@�킪���������̏I���
 �@ �@
�g�ӂ̐�����S�����Ă��邱�̓~�B�ȑO����S�ɏd���̂��������Ă����u�����̐����v�Ɏ��|���邱�Ƃɂ����B
�N���ɏ��邱�Ƃ͍l�����Ȃ����A����ƂČÕ����ɔ��蕥�����Ƃɂ���R������B��x�قǂ��ĕz�ɂ��āA���ꂩ��������z�̖���S����������@��T���Ă݂悤�B
���{���L���ɂȂ�n�߂����a30�N�ォ��40�N��́A��������ɓ������Ă��ꂾ���̒����𑵂��Ă����˂Ȃ�ʁA�Ƃ����������ϔO
�ɒǂ����Ă�ꂽ���ゾ�����B
���{���L���ɂȂ����A�����̖����ґ�ɂ�������g�ɒ����邱�Ƃ��ł���Ƃ�������ɐ��܂ꍇ�킹�Ă��܂����K���Ȃ̂��A�s�K���Ȃ̂��B
���������c�ޔ���ɂނ���w��������A�Ȃ��Ȃ��̒����ƑސE���ł��炦�������̂��ꂱ��B
�U���A�K�⒅�A�H�D�A���n�̖����̒����A�ē~�̑r���A�ہA�ܑсA�R�[�g�⏬���ȂǁB��������A�����n�߂Ă���B
��n�߂ɃR�[�g�ƉH�D���@---�@���荞��ň�ڂЂƖڂ�T���Ȃ���ꖇ�̕z�ɕς��Ă����B
�D�q����́A���̒����ɍ��߂����ԂƁA�Ⴍ�ĉ����m��Ȃ��܂܉߂����Ă��������̎��Ԃ��d�Ȃ�A�v��ʎ��Ԃ��߂������ƂɂȂ����B
�ꂩ���̋����ŁA���̒����ꖇ�����Ȃ������E�E�E�B�����Ⴓ���������������̎�����v���o���A�S���e�肢�������̔�ꂪ�c������B���āA���ꂩ��K�⒅�Ɏ��|����̂����A�͂����ĉ����肪�i��ł������ǂ����B
��Ɏ��Ƃ�������Ƃ����d�݂�����̂ɁA�w�̊Ԃ��炳�炳��Ɨ��ꗎ���Ă������̐G���ɖ��������B
���܂�ɂ��v�����l�ߍ��������ق����Ă������Ƃ��ł��邩�B
����͑����Ȃ�o��Ǝv���肪�K�v�Ȃ悤���B
���F�̐���̏��Ԃ��炢���B�@
�@�@�@�Z�@���ԍ炫�̉��߂����̂ЂƓ������@���͏t�̓��Ђ��@�@�@
���R�̕�炵309 �@2017.2.22
�@�@�@�@�@�@�@

 �@���O���̕�炵�͂��Ȃ����̂��@
�@���O���̕�炵�͂��Ȃ����̂��@


�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y���ˁi������Â��j
��ɗL�@�엿���������ނƕK������Ă������......�~�~�Y�ƃ~�~�Y��ǂ��ė��郂�O���B
���O���̃g���l���́A�l�ʔ��B�B���ꂼ�ꂪ��ڂ��������ȕ��������т��A���O����������ʔ����邩�̂悤�ɂ�����������o���肵�Ă���B
���������f�U�C�����ԕc��A�����݁A�����߂��Ԓd���Ђ�����Ԃ��Ă��܂��̂ŁA���N���Ă�������B���̂��܂�̘T�S�Ԃ�ɋƂ��ς₵�A�l�����邷�ׂĂ̑������Ă݂����̂́E�E�E�E�B
�E�@���U�߁@�i���ւ����j
�E�@�g���l���̒��ɌI�̃C�K�����Ă݂��B�i�ȂɁA�ق��Ƀg���l�����@��������ƁA�Ɩ��������j
�E�@���Ԃ�˂��h���ăg���l�����ǂ��ł݂��B�i�S�R�����ڂȂ��B���ɒʂ蓹����邾���̂��Ƃ�j
�Ȃ�ΏL���ōU�߂悤���B
�E�@�j���j�N�̗����g���l���̒��ɁB�i�҂��A�ƒn�ʂ̏�ɕ���o���Ă���B�t�ɂ͂�������肪�o�Ă����j
�E�@�i�t�^���������Ă݂��B�@�@�i�I�ăg���l�����@�����悤���B�뒆�Ɍ��ȏL�����������߂�j
�Ȃ�ƌ����Ă�����͐������Ȃ̂ŁA��܂��g���Ă܂ł̎E���͂������Ȃ��B
���O���͂ق̂��ɖ��邳����������̂́A�ڂ͑މ����ĂقƂ�nj����Ȃ��B�Â���炵���ꐶ�������O���B
���܂��ɐH�ב����Ă��Ȃ��Ǝ��͑҂����Ȃ��B
�摜�́E�E�E�\��t���Ă���������ǁA�ނ������`�ԂȂ̂ŁA�������Ă����ق����ǂ����낤�B
�����I�Ȃ̂͑O�������������Ă��邱�ƁB���j���̐��Ńg���l�����@��悤���B
�y���@�鑬�x���P���Ԃ�30�������炢�B�x�x�@��i�ނ̂Ŏ�����20���[�g���B�����̂��x���㖼���́u�����ނ�
�i����50���[�g���j�v�ɔ�r���Ă��x���B
����͂������B�摜�͎Ԃ����X��Ԃ���A�H�ӂ̌ł��y���@�����̂��̂Ȃ̂�����B
�摜�̍����A�A����オ�����y�́A�g���l�����@�����ۂɏo���y��O���ʼn����Ď̂Ă����́B
�E�̓��O�����ӂ����ѓy�̒��ɐ��荞�ՁB
���̓y�͕\�w�y���@��o���ꂽ���̂Ȃ̂ŁA�ӂ�����Ƃ��Ă��ĉh�{�ɕx�ށB
��������A�y���W�߂ĉԒd�ɖ߂��Ă��̂�����A�������Ƃ���łȂ��B
*�@�Ȃ�Ƃ����^�C�~���O�I
�������肢���Ă����c��Ђ���J�^���O���͂��A
�u�y�ɂ��������I���h���h�q�G�L�X�i�J�v�T�C�V���j�����O���E�l�Y�~�����ށI�v����u���O���X�e�B�b�N�@����_�v�̋L�����ڂ��Ă����B
15�Z���`�قǂ̖_��ł�����������ނ����B50�{��4217�~�Ɨ����B
�ł��A����͋߂��̓��̉w�Ŕ����Ă���A�u���h�������h�q�v���g���l���ɍ������߂͂�����������Ȃ��H
�͂āH�@��͂莸�s�͖ڂɌ����Ă���悤�ȋC������B
�@�@�@�@���R�̕�炵306
�@2017.1.28
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@ ���R�̕�炵 2016�N1������ 2016�N6���܂�
�@�@�@�@�@ |




 �T���^�����͎��̎���
�T���^�����͎��̎���










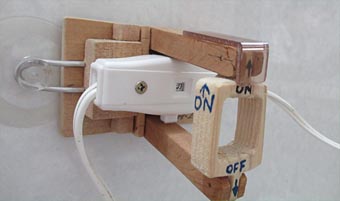



 �@
�@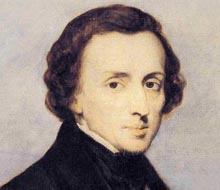
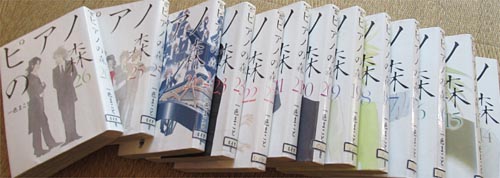


 �S�����
�S����� �@�@���ԃz�g�g�M�X
�@�@���ԃz�g�g�M�X







































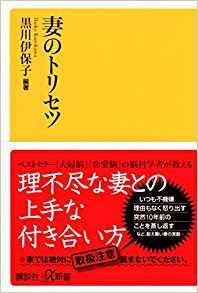

























































 ����
���� 
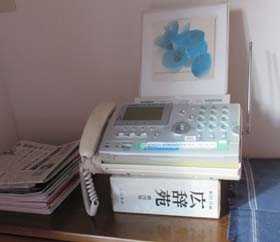











 �@
�@ �@�@
�@�@





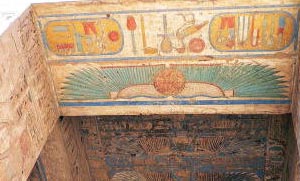

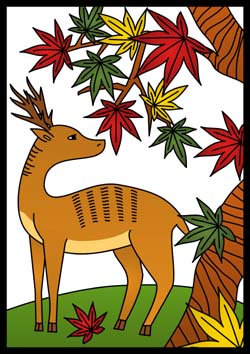



 �@
�@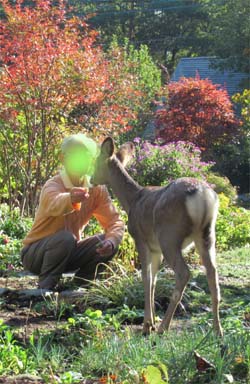









 �@�@�L�Œ��ӁI
�@�@�L�Œ��ӁI




 �o�q�̃N���~���������B
�o�q�̃N���~���������B






 �@�@
�@�@







 �@�@�@
�@�@�@ �@
�@ ���̉Ẵu���[�x���[�̂���A���悢��s�[�N���߂����B
���̉Ẵu���[�x���[�̂���A���悢��s�[�N���߂����B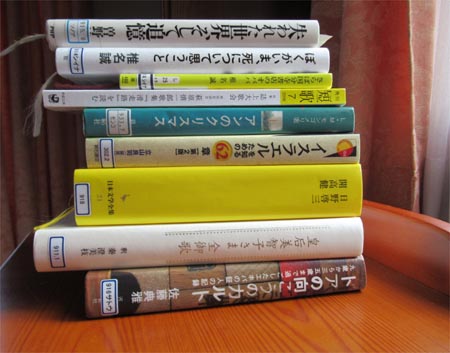














 �ߐ{������35�x�܂ŏオ��̂��B
�ߐ{������35�x�܂ŏオ��̂��B





 �����̂��q����
�����̂��q����


 �@�@�u���[�x���[
�@�@�u���[�x���[ �X�p�j�b�V���E�u���[�x��
�X�p�j�b�V���E�u���[�x�� ��Bluebell
�̖��_�̂��߂ɁB����Ȃɉ��炵���ԁB
��Bluebell
�̖��_�̂��߂ɁB����Ȃɉ��炵���ԁB

 �@�@��̃I�g�M���\�E
�@�@��̃I�g�M���\�E
 �@�@���������C���J
�@�@���������C���J








 �@�������ăf�[�W�[�����J�ɁB
�@�������ăf�[�W�[�����J�ɁB



 �@�@
�@�@
 �@�@
�@�@











 �^�`�c�{�X�~��
�^�`�c�{�X�~��

 �@�킷��Ȃ���
�@�킷��Ȃ���






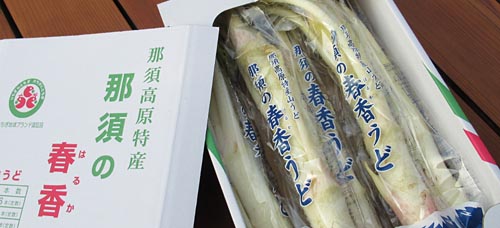
 �����C�ł��傤���A���ׂ̂����l�B����̒��10�{�炫�܂����B
�����C�ł��傤���A���ׂ̂����l�B����̒��10�{�炫�܂����B



 �@���������Ⴂ����
������
�@���������Ⴂ����
������
 �@
�i�L���|�E�Q�ȃt�N�W���\�E���j
�@
�i�L���|�E�Q�ȃt�N�W���\�E���j

 ���ꂪ�F���{�[���y��
�i�������j
���ꂪ�F���{�[���y��
�i�������j


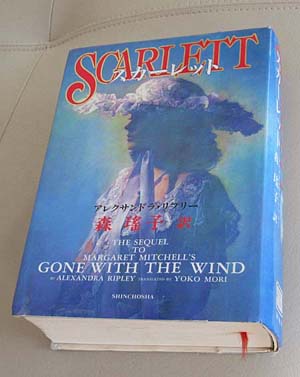






 �@122�@���ꂩ��Ԋ|��
�@122�@���ꂩ��Ԋ|��



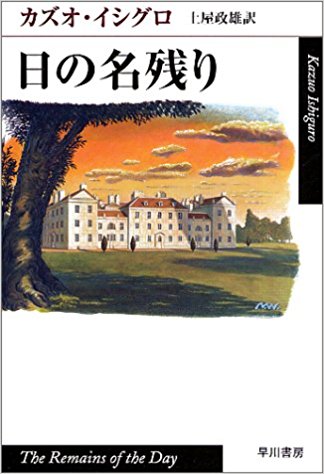 �@
�@
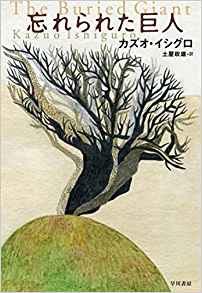 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��������|��ƁE�y�����Y�̎�ɂ���ē��{�ꉻ���ꂽ��i�j�@�@�@�i�摜�͔M�щJ�т���q�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��������|��ƁE�y�����Y�̎�ɂ���ē��{�ꉻ���ꂽ��i�j�@�@�@�i�摜�͔M�щJ�т���q�j �c���K�l�j���W��
�c���K�l�j���W�� �@���@���ꂪ�_�C���t����
�@���@���ꂪ�_�C���t���� No.45�̑�
No.45�̑�
 �S�S��������
�S�S�������� �J�����Ƃ�Y��邩�A���������邩�B
�J�����Ƃ�Y��邩�A���������邩�B �������A�E�����_���\���@�@��������I
�������A�E�����_���\���@�@��������I �W�S�N�m�J�}�m�t�^�@
�ʖ��L�����\�E�@ �i�V�\�ȃL�����\�E���j
�W�S�N�m�J�}�m�t�^�@
�ʖ��L�����\�E�@ �i�V�\�ȃL�����\�E���j �J���l�Y�~�����邻�����B
�J���l�Y�~�����邻�����B �@��{�̌s��50�̉ԁB�x���������Ɠ|��Ă��܂��B
�@��{�̌s��50�̉ԁB�x���������Ɠ|��Ă��܂��B



 �u���[�x���[�����n���ɁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�u���[�x���[�����n���ɁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@
��̃P�V�A����l���Ƃ�������B
�@�@
��̃P�V�A����l���Ƃ�������B �@
�@
 �@���ꔒ�~
�@���ꔒ�~ �@䉖�
�@�Ԑ���
�@䉖�
�@�Ԑ��� �@Las�@Empanadas
�@Las�@Empanadas


 �@
�@
 �@�R�S���̓��̕���
�@�i���q���̂悤���j
�@�R�S���̓��̕���
�@�i���q���̂悤���j �@
�@

 �@�������@
�悶�o���Ă���
�@�������@
�悶�o���Ă��� �@
�@