|
�@ �@ �@
�@6���̋C���@�|4�� (12/21)�@�|3�� (12/22)�@�|1�� (12/23)�@�|�T�� (12/24)�@�T���^������������낤�B
�@�@�@
�|1���i12/25�j�@�{1���i12/26,�����g�����j�@�{3���i12/27,�g�����ȁj �|5���i12/28�j
�@�@�@ �@�@�@ �{1���i12/29�j 0�� 12/30�j �|3���i12/31�j
�@




 �@�������āA�������Ȃ��Ƃ̐ςݏd�˂���N�ɂȂ�@-----�@�N���̕�炵 �@�������āA�������Ȃ��Ƃ̐ςݏd�˂���N�ɂȂ�@-----�@�N���̕�炵
�@  �@�������ꖼ�n�Ȃ�@�@���������� �@�������ꖼ�n�Ȃ�@�@����������
���N�������ŏI���B���܂̕�炵�ɕs���s�����Ȃ��킯�łȂ��B�ł��A���N��N�傫�ȉ�����Ȃ��A�a�C�ɓ|��邱�Ƃ��Ȃ��������Ƃ�f���Ɋ�
�ڂ��B
���ꂩ�犦���͖{�Ԃ��}����B�V�^�R���i��W�g�ł͍���҂��d�lj�����P�[�X�������炵���B�������s���Ă���C���t���G���U���S�z�ɂȂ�B
���N�A���X�̂��Ȃ���炵�̋L�^��ǂ�ł��������āA���肪�Ƃ��������܂����B
�F���܁A�̒��ɂ͏\���C��t���ĐV�����N�����}�����������B
 �@���ӂ� �@���ӂ�
�@���ӂ��@�i���t�\�L�ł́A���z�m�A���s�m�A���z�m�A���s�j�@�@�Z���_���@��h�@�i�Z���_���ȁj
�@*�@���������@���̉Ԃ͎U��ʂׂ� �@�䂪�����܂��܂����Ȃ��Ɂ@�@�w���t�W�x�@�R�㉯�ǁ@��5-798
�~�̋�ɂ��ӂ��i���݂̐�h�j�̎����Ԃ牺�����ėh��Ă���B�@�@
�i��ɕ{�̒����E�唺���l�̍Ȃ́A���l����B���C��܂��Ȃ��������܂����B�߂��݂ɕ��闷�l�ɂȂ肩���A���l�̍Ȃ̎��𓉂ݎR�㉯�ǂ͉r�݂܂��B�j
�@
�@�@ �@�܂����ڂꗎ�����@-----�@�t�^���������̑���
�@�܂����ڂꗎ�����@-----�@�t�^���������̑���
������C�̑�������A�͂��Ɛ����������ς܂��A䩑R�ƒ�߂Ă���B���̂��Ɖ����悤�H
���������A���ꂾ�Ǝv�����A�[���j���[���̙���Ɏ�肩����B
�d���̂����́u���������̂��߂̍����g�ȁu�����v�v��CD�B���荶�i�q�쎌�A��������ȁ@1961�N
�܂����y�́u�����^�́v�B�̎��͂���Ȃӂ��Ɏn�܂�B
��@���Ζ��Ă鑠�� �����@����܂̗т͍����Ԃ̎��@�͂邩�� �����A�R�͉����@�R�̏t�͍�����s���@
�����̎�t�h���
����n��R�̏t----��
�t�̏I��肩�珉�Ăɂ����Ă̑����̎R�̖��邳���A�̂����܂�Ă���B���邢�̂����R�B�j�����ł͂��܂�g�����ɓ]�����A���̂܂܂Ȃ��炩�ɑ��������Ǝv���ƁA�d�w�����̒����������(�����Ń]�N�]�N����j�A�̎R��ɔ����ȉA�e���{�����B�Ăуj�����ɖ߂�B�t�������A������������ꗎ����A�₽�����A���̒�����A�̂������猻��邳�܂��܂Ȗ��̌Q��B
��2�y�́u�����悤�ь���v ��������V�ȋ����B
�@��@�����悤 ��� �_�̏� �_���炱�ڂ�� ���̓��� �������� ��]�̂��� ���b�z�b�z
�@�����z�`�`�`�`��@
�����ĉĂ���H�ցA�~�̐�ցB�̂͑����Ă����B
��9�y�́u���t�v
�����̌��@�R�ɂ݂��@�_�͖��邭�@�����т���@���敗�킽��@���敗�킽��@�����R���@�����R���@���肩���₭
�}����}�ց@���͔�ь����@�t��t��@�R�̏t��
���̌���@�R�ɂ݂� �_�͖��邭�@�����т���@
����̂����炬�@����̂����炬 �@�����y���@�����y���@�J���s���R�ɂ����܂��� ���͂₳�����@��ь��킵�䂭�@
�����䂭�����Ɂ@��͂����₭�@ �]����t���@�]���摠���@ �����̎R�Ɂ@�t�͗������ʁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�����@�����@�����̎R�@ �����̎R��@ ------fff �ŏI���B
���y�͂̂͂��܂�u���v�̓t�H���e�B�b�V���ifff�j�Ŏn�܂�Afff�ŏI���B�@�T�^�I�ȍ����ȁw�����x�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���A�����������B�i���߂�ˁB�̎��͂��ׂĂ��܂����̒��ɂ��邩��B�j
���̋Ȃ���E���V���ɂ���u���t�F�X�e�B�o���z�[���v�̕���ɗ����A�̂������Ƃ��������B���̓����Y�Ɖ��y�ՂŗD�G�܂����������A���̎��������ė܂����ڂ���----�����č��A���\�N����ɗ܂����ڂ��B�܂ɂǂ̂悤�ȍ������邾�낤�B
�I�X�ƑO�Ɍ������ė���鎞�Ԃ����������̍��ƁA�����܂œ��B�����Ԃɔ�₵�����ԂƁA���ꂩ��̎��ԂƁB
����̂��̂ł��Ȃ������̎��Ԃ́A���̂Ȃ��̗܂ɁB
�u�����v���̂������̓�����35�N��A�����̒���ɗ����Ƃ��ł����B
����͏��a�̎��ゾ�����B���k�̎R�֓o�肽���Ǝv���Ă��Ă��A�]�݂͂Ȃ��Ȃ�������ꂻ���ɂȂ������B���̍��̎��ɂ��̌i�F�������Ă�肽���B
�@ �@�����̂����i�{�錧�ό���HP����j �@�����̂����i�{�錧�ό���HP����j
�u�����v�Ƃ����͂�֓��g�B
�@�@*�@�������ӂ��킯���܂���(����)�����܂ӑ����̎R�̉_�̒��ɗ���
�@�@*�@��������̂��ɑ����̑��z���͂����݂��肵��̉�
�@�@*�@�݂��̂����U���̎R�ɏ�(��)�̂������H�Ђ��蟎�݂Ƃق�܂�
�@
�@
 12��29���@�������L�̕�����
12��29���@�������L�̕�����
�@�@�@�@
�@�@�@�ȈՉ����̂Ȃ��ł��낮�u�X�|�b�g����Ȃ��N�v�������𗁂тĒg���������B�@�@�E�̃|�b�g�̓X�C�g�s�[�̕c�B
�@ �̔@�J�I�ɂ͐��𗭂߂Ă���B�ЂȂ����ɂ��邽�߁B��O�̖_�̓x���K���b�g�B
��6���̋C�����|5���B�������Ɋ����B
���v�ɔ����Ȃ������ɓ���ƁA�������Ď��Ԃ�����ĕ�炷�悤�ɂȂ�A�Ƃ͂��ꂪ�������̂��B�܂��������̒ʂ�B�N���Ȃ��Ă������̂ɋN���Ă��āu�����ł�����v�u���l�ł�����v�Ȃ�Č��t�����킵�Ă���B
�@�@�@----�u��������܂イ�@������ĂȂ��ȁv�u��������܂イ�@������ċ����ȁv----
�g�̂����Ƃ����ƒg�����Ȃ�B�����v���Đ���Ɏ��|����B�|���@�������Ă݂��肷��B
�������́u���Y���Ēg�����v�B
�ł́A�C�����̉������ɂ́u���Y���ė�����v�̂��H�H�H
�@
 12��28���@�g����j�ɕϐg
12��28���@�g����j�ɕϐg
��6���̋C�����{�R�����������B���ʏ��ɂ����Ă���Ζ��X�g�[�u���A�ق��10�������R�₵�Ă��Ȃ��̂ɓˑR�V���b�g�_�E�����邱�Ƃ��������B�u�v���X3�����Ă����������ˁB�Ă݂������v����Ȃ��n�����������̂��X�g�[�u�ɕ����ꂽ�̂�������Ȃ��B
�t�B���^�[�H�������|�������āA���C�ɂ��C��t���Ă���B�Ȃ̂ɓˑR�̃_�E�����ƂĂ��s�v�c�������B���̃X�g�[�u�́A�����Ԏg�p���郁�C���̋����r�C�X�g�[�u�ł͂Ȃ����A����̂����ق�̂P���Ԃقǂ����g
���Ă��Ȃ����炾�B�o�N���ȁH�Ȃǂƕ��������Ȍ��𗘂��킽���B
���ׂĂ݂��B�����������Ƃ́F
�u�R�Ė_�ɖ��������t�����A�_����Ɠd�C��R�l���ϓ����Ĉُ�R�Ă����v�Ɣ��f�����悤���B�N���H�������X�g�[�u�ɓ�������Ă���Z���T�[���B
�����ő��_�̏o�Ԃ��B
���͂��������d���������----���A�����ł͂Ȃ��āu�d���ɂ�����Ɓv�̂ق������m�ȕ\�������A���Ŏ����̃��O���Ă�C�����y����ł���B


�@�@�@���̓X�g�[�u�̑O�ʔł����O�����l�q�B�@�E�̓X�g�[�u�̔R�Ė_�B�@������|�������B
�@�@�@����ȏ�̏C���́A���������u������A�f�l�ɂ͓���B��ǂ��͌��ւ��B
���_�̎v�l�͏�ɂ܂������ŁA���̈ӎ��̌����͈͂͑S�ʂ�120�x���炢�B����180�x�̂������E��30�x�͂����ڂɓ����Ă��邾���B���ӂ������Č��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����ɓ�̂��Ƃ��ł��Ȃ��B�������������Ƃ͕�
�������̏��f�ʂ肳����B�ސ������ȑ��_�B���̎�����͒����B�g����j�ɕϐg����B
1���Ԍ�A����܂����ˁB�����ǂ��̃X�g�[�u�A�g�p���Ԃ͏��Ȃ������10�N�g�����̂�����A���낻�딃���ւ��̎������낤�B�C���̂��ƒ��֏o�����ĉƓd�i�X���q���A���ɔ����@���I�肵�Ă������B
���֏o�����łɁA���J���Ƃ��ĐV������ƃY�{���ƁA�����͍ɂ̖����ɏ��l�W�������Ă�����āA������Ɗ��������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�����傭���Ă���ł̓i���ł�����A�[�H�Ƀ��C���쉈���Y�́u���[�[�����C���E���v�ł˂��炤�B����ꂳ�܁B
�@
�@�@ �@12��27���@�����ɂ�������� �@12��27���@�����ɂ��������
�@�@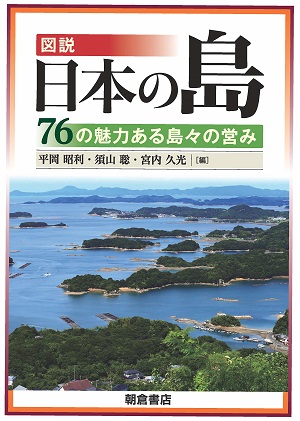 �@����Ȗ{����Ă��āA����őD�ɏ�
���Ă���B �@����Ȗ{����Ă��āA����őD�ɏ�
������B
�R���i�Ђ�4�N�ڂɓ������B���̊Ԃǂ��������ɂɏo���������ƌ�����----�������A�ǂ��ɂ��B
���ٓ��������ċߏ�Ńn�C�L���O�B���Ԍ��A���э̂�A�N���\���E�݁A�g�t���B����Ȃ����₩�Ȋy���݂�ƂɁA����3�N�Ԃ��߂����Ă����B
���̓~��������̓��𗷂��悤�ƍl���Ă����̂ɁA�R���i��8�g���Ă��āA���낭�����̊肢���������ōs�����B�������ɁA�s�����Ǝv���s����B�ł�----�Ƒ�����������̂͂���H �N�Ƌ���
����ɗp�S�[���Ȃ��Ă�����l�́A�Ȗ،��̘g���O���ďo������E�C���Ȃ��B
�ǂ����֍s�������B�����łȂ��ǂ���������Ƃ���֍s�������B�ł͂ǂ����邩�B�z���͂��g����������܂���B
�{�̃y�[�W���߂���Ƃ����͓����ւ̗U�f�Ŗ����Ă���B
�����͐l�Ԃ��Z�ޓ��̂Ȃ��ŁA�{�B�œ�[�ɂ���g�Ɗԓ��𗷂��邱�Ƃɂ��悤�B�������́A�����͑�p�I���C�݂̃}���S�[���������������B
Google
Map���N������B�h���[���ɂł��Ȃ����C���Ŕg�Ɗԓ��ɏƏ������킹�g�債�Ă����ƁA�����ɂ͂��̒n�ɏZ�ސl�����̕�炵���_�Ԍ����Ă���B���]�Ԃɏ�����C���ŃX�g���[�g�r���[
�̉^�]�Ȃɍ����ăh���C�u�B���͂͊C�B
���o�o�i�A�T�g�E�L�r�A�����̂��َq�B
���ꂩ��F���ցB
�@�EGoogle Earth
���u�L���[�|���ϑ����W���[���v�ō��ۉF���X�e�[�V�����iISS�j���猩���n���̎p�ƁA�����̗l�q��������B�i�Î~�悾���ǁj����َ͈����ɂ���悤�ȁA�����o�N�o�N��������ɖ����Ă���B
�ENASA
���ۉF���X�e�[�V����(ISS) ���C�u�J�����Ō���
1980�N�āA�܂��\�Z������ɂ����������NASA�����w�������Ƃ��������B�ԓ������ɂ����s�L�g�̍x�O�̊ϑ����ł́A�܂��R���s���[�^�[������قǓ�������Ă��炸�A�{�y�A�����J�Ƃ̘A���́u�e���^�C�v�v���g���Ă����B�̂Ă�ꂽ�^�C�v���̐�[�����肪�������������Ă��āA���{�ɑ��������Ƃ��������B���͂ނ����B
�@
�@�@ 12��26���@�������� 12��26���@��������
 �@ �@ �@�I�I�o�� �@�I�I�o��
��c���s�x�O�ɂ���H�c���ɁA�����̂悤�ɔ��������ɏo�����Ă����B
�k�C�����o�R���āA�V�x���A�������Ă����������A���̓~�����œ~���z���Ă���B��N�O�͖�200�H�������ƋL�����Ă��邪�A���N�͉��H����Ă����̂��낤�B�ȑO�́u����v�̐l�������a�������A�����J�E���g���Ă������A���R�ی�̗���i���͂ʼna��T����悤�Ɂj����A���݂͒��~����Ă���B
�قƂ�ǂ̔����͒������߂��̓c��ڂ̗����t�E���ɏo�����Ă���͂������A���̐e�q�͐��̔�ԗ͂��܂��ア�̂�������Ȃ��B���Ɏc�������萅�ʂ��j���ʼna��T���Ă���B
�Ƃ��낪�A�L���m���C��������J�����}���ɂ����������B�����̕������̉h�{�ɂȂ�̂ŁA����܂ł͔����}���Ă����c��ڂ̎�����
���A�{�{����߂����Ƃ����A�ԉ�g���Ēǂ������Ă���悤���ƁB
��B�Œ��C���t���G���U�����s���n�߂��̂��������ɂȂ����悤���B�@�ԉɂ��т��������͂ǂ��ʼna���̂��Ă���̂��낤�B
�E�̉摜�̓I�I�o���i�N�C�i�ȃI�I�o�����j�B���m�Ȃ��炢����O��ɗh�炵�Ȃ�������Ă���B�����ۂ��ۂ�----����Ȋ������ȁB
���邢�͂������H----�ڎ�蒎�̕������B���̓����Ŗڂ̈ʒu���n�\������̍����ɂȂ�悤�ɁA�������Ă���悤���B
�i�N�C�i�ȁ��u�N�C�i��@���v�̃q�N�C�i�̒��ԁj
���Y�A�I�I�T�M�A�`���E�T�M�A�S�C�T�M���������̋���_���Ă���B�݂�Ȃɉ�Ė����̓~�̓��B
���R�̕�炵699�@ 2022.12.30 �@�@  �@ �@
�@
 �T���^�N���[�X�̏Z�ޒ��� ---- 2012�N7��14��
�T���^�N���[�X�̏Z�ޒ��� ---- 2012�N7��14��
���̎��Ԃ͋Ïk����Ă��܂ł��S�Ɏc��̂͂Ȃ����낤�B2012�N7���A�֓���k�Ђ̎��̔N�ƌ����̂Ɏ��l�������A�k������I�[�X�g���A�A�X�C�X�ւ̗��ɏo���B
�w���V���L�����w�́A���[���b�p�̉w�̃V�X�e���Ɉ�킸�A�^�[�~�i���w�ɂӂ��킵�����ɍL�����āA���{���̃z�[��������ł���B���̈�ɐw���A�ߌ�8�������̗�Ԃ�҂��Ă��鎞�́A���g����C�����v���o���B2���Ԓx����Ȃ�̂��́B
�s����͖k�Ɍ��E���b�v�����h�̊X�����@�j�G�~�iRovaniemi�j�B
 |
�t�B�������h�̎�s�w���V���L����k�Ɉʒu���郉�b�v�����h�́A�k�Ɍ��̌����B
�I�[�����ϑ��n�Ƃ��Ēm���Ă���B
�Ȃ��ł������@�j�G�~�̓T���^�N���[�X�̌̋��Ƃ��Ă��L���ŁA
�x�O�Ɂu�T���^�N���[�X���v������A���܂��܂ȃN���X�}�X�C�x���g���y���߂�B�@
|

���S�ɂƂ��Ă͐����̓I�A�T���^�N���[�X�E�G�N�X�v���X�B�t�B�������h�̎�s�w���V���L�����s�d�Ԃ�12���ԁB
��X��������̂́A18�F30���̐Q��Ԍ�1���V�����[�t��(�f���b�N�X�R���p�[�g�����g)�B�ŏ㋉�̕����Ȃ̂�
�v�����������������B
�x�b�h�ɉ��ɂȂ�Ȃ���A�d�Ԃ�����ʉ߂��Ă��������A����ɔ����������锒���̑������̐�����Œǂ��Ă����B

�T���^�N���[�X���̓�����B����Ƃ����k�Ɍ������������܂������ƂɂȂ��B��������k�Ɍ��ɂ͂��艜�̊Ԃɍ����Ă���T���^�N���[�X�ɂ����A�����B���̂��ƊG�t���Ɛ؎�����߁A���{��J�i�_�̗F�l�̂��ꂩ��ɑ���B
���āA���o�j�G�~����w���V���L���߂�Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���ʂ͔�s�@���g���Ƃ��낾���A���S�̉���͓��R�S�H�ɂ�郋�[�g���S���j��ڎw�����B���H��I��Ő����B�����ԗ��̍őO��Ɍq�������u�����̎ԗ�24�l���v���̂��āA���X12���Ԃ́u�ǂ��܂ł��Â����H�v�̗���g�̂ɟ��ݍ��܂����B
�����т������B���̊ԂɌ����n���̉w�ō~���l�A���l���ώ@�����̐l�̔w�i��z�����Ă͖ʔ�����B�l�Ԃ��Ėʔ����B
�v���o�͏�Ɏ��̎�̒��ɂ���A���[�r�b�N�L���[�u���悤�ɁA������z���č��ɕ�����������y����������B
 �@���̎����Ɋp������̂́A�݂�Ȏ��̃g�i�J�C�B
��������T�Ԃ��B �@���̎����Ɋp������̂́A�݂�Ȏ��̃g�i�J�C�B
��������T�Ԃ��B
�@�@�@���R�̕�炵698�@ 2022.12.21�@�@
�@�@  �@ �@
�@
�@
 �F���낢��@----�����łǂ̂悤�ɕ\�����邩�@�@�@�@
�F���낢��@----�����łǂ̂悤�ɕ\�����邩�@�@�@�@ �@�@ �@�@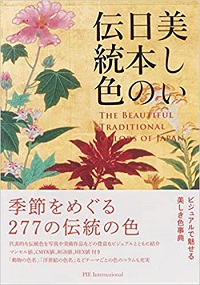
�@�@������@�������@���̐��t���߁@�n�C�r�X�J�X�̉Ԑ���
|
������ |
�A�J�l�̍����ς����Đ��߂��B�n�͗l�������オ���Č�����B |
| ���̐��t���� |
�{�������߂́A�^�f���y�����A���ʂ�����Đ��߂�B
���̗��̐��t���߂́A�Ă̏I���ɐ��̃^�f���𝆂݁A�F�f�𒊏o���Č��z����߂����́B |
| �n�C�r�X�J�X�̉Ԑ��� |
�G�W�v�g�̓�A�X�[�_���Ƃ̍����ɋ߂��A�u�V���x���̓y�Y���Ŏ�ɓ��ꂽ�u�n�C�r�X�J�X�̉ԁv�Ő��߂��B�{���͉Ԃ������ɂ��邪�A��}���̕��@�Ō��z����߂ăX�g�[���ɂ����B |
���܂ɐ��Ƃ̗F�l�ƈꏏ�ɑ��ؐ��߂����邱�Ƃ�����B�����͐A���R���Ȃ̂ŁA���̐��ߕ����u���ؐ��߁v�ƌĂԂ��Ƃ������B
������@�Œ��o�����F�f���A�}���ނ��g���Đ��n�ɒ蒅������B���������Ɖ��w�����Ő��F���鎞�Ɠ����悤�ɁA����̐F�ɐ��܂邩�ƌ��������ł��Ȃ��B
�Ⴆ�A�J�l���g���Đ��߂�ꍇ�ɂ��A�ޗ��̕i���A�C���A�}���ނ̗ʂ�蒅��������@�̂�����Ƃ����Ⴂ�ŏo���オ��̐F���ς���Ă���B�r�����炩�̕����i��F�S�Ȃǁj�ɐG��Ă��܂����ꍇ�ȂǁA���Ղ���������c���Ă��܂�����A���f
�ł��Ȃ��B
�����F����߂�B�F���Č�����B����͂ƂĂ�����B���N��NHK��̓h���}�́w��������x�炵���̂ŁA���܂��܂ȐF�ɐ��߂��������\��P���܂�
�����P���܂����̎p������̂��y���݂��B
�@�@*�@12��27���@���Ⴂ�������B�u�ǂ�����ƍN�v�i NHK �j�������B�ǂ����炱��ȏ����d���ꂽ�̂��H
* 2024�N��̓h���}�w����N�ցx �ė��N�������B�҂��������B
���{�ɂ́A�F��\�����錾�t����������B��ʉE�ɒu�����w���������{�̓`���F�x���J���Ă݂�ƁA�����ɂ͈�ࣂ���F�ʂ̐��E���L�����Ă���B�F���g�����������A���̐F��\�����Ă��錾�t�̔������ɂ́A
�������炭�炵�ĂƂ낯�Ă��܂��������B
�Ⴆ�A�t�̐F�Ƃ��ẮA���F�A�g�~�F�A�X���F�A�g��A�ٕ��F�A���O�F�A�g��----�ƍׂ����F�̈Ⴂ�����t�Ɍ��������Ă���B
���̝R����ǂ̂悤�ɐF�ɒu�������邩�H�Ðl�͂��܂��܂ȍH�v�����炵�Ă���B
���̖{�ł́A�F�̖��O���傫����ʂ�̕��@�Ŗ��t�����Ă���Ƃ������B
�@�E�ޗ��i���ށj�̖��O����----�A���R���ƍz�����痿�Ƃ���B���F�@���_�F�@
�@�E���R�ɂ��鎖�����璼�ڎ������----�S�F�@��F�@�I��F�̂悤�ɁB
|
�ł͐F���f�W�^���ɕ\������ɂ͂ǂ����邩�B���̖{�̐�����ǂ�ł悤�₭�������ł����B
�y�}���Z���E�J���[�E�V�X�e���z�Ƃ́B
���ׂĂ̐F�o�͐F���i�F�����j�A���x�i�F�̖��邳�j�A�ʓx�i�F�̑N�₩���j�̎O�̑����ɂ킯����B���̎O�̑����̑g�ݍ��킹�ł����̐F��\��----�Ƃ������Ƃ炵���B
�O�̃f�[�^����_�ɏW��A����͎O�����̕\�킵�����B
�m�F���n�F����\���B�ԁiR�j���iY�j�iG�j�iB�j���iP�j����{�̐F���Ƃ���B���̒��Ԃɉ��ԁiYR�j���iGY�j�iBG�j���iPB�j�Ԏ��iRP�j��u����10�̐F���ɕ�����B����ɂ��̂��̂̐F����10�ɕ�����100�̐F���ŕ\���B
����͍L���傫��Tree �\���Ƃ��v����B�}���Z���l�Ƃ��ĕ\�킷�B
�m���x�n�F�̖��邳�B���x�������Ɣ��ɋ߂Â��A�Ⴂ�ƍ��ɋ߂Â��B�F�������Ȃ����⍕�ʐF�ƌ����A���̖��ʐF����ɂ��Ė��x�͌��߂��Ă����B�ł����邢���𖾓x10�ɁA�ł��Â����𖾓x0�Ƃ��A���̒��Ԃ̐F�i�D�F�j��1�`9�̐����Ă͂߂ĕ\���B
�m�ʓx�n�F�̑N�₩���B�ʓx�������Ə��F�ɁA�Ⴂ�Ɩ��ʐF�̃O���[�ɋ߂Â��Ă����B���A�D�A���̖��ʐF���O�Ƃ��A�N�₩���������邽�тɐ������傫���Ȃ�B���L�ʐF�ɁB
�I�t�Z�b�g����Ȃǎ��}�̂Ɉ������ꍇ�A�t���Ȃǂ̉�ʂɕ\������ꍇ�Ȃǂŕ\���̕��@���Ⴄ�悤���B
�I�t�Z�b�g����Ȃǎ��}�̂Ɉ������ꍇ�́B
�@CMYK�l----�F������d�˂�ԓ_�ʐς��p�[�Z���g�ŕ\���Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�ԓ_���C���N�������ȓ_��Ɉ�����āA�Z�W��\�����邱�ƁB�������I�F�̓h�b�g�ŏo���Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�قȂ�F���d�ˍ��킹�邱�ƂŁA�����̐F�̊K�����Č��ł���B
�R���s���[�^�[�ŐF��\������ɂ�RGB�i��R�@��B�@��B�j�̒l�ŕ\������Ă���B
�Ⴆ�Ύ�F�͂����\�킹��B
�}���Z���l�i7.5R 6/16�jCMKY�l�iC0 M65 Y75 K0�jRGB�l�iR255 G88�@B65�jHEX�l�i�F��web�l��FF5841�j
�F��web�l�ɂ̓f�W�^���ԍ����^�����Ă��āA���̎�F�́�FF5841�Œ��ړ��͂ł���BHP�̔w�i�̐F��ԍ��Ŏw���ł���̂͂��̂������炵���B
HEX�l�Ƃ́B
��������Ȃ��Ƃ�����B�u���E�U��Web��ŐF���Č�����ꍇ�A���S�Ɍ��̐F���Č��ł���Ƃ͌���Ȃ��B
�ǂ̃u���E�U���g���Ă��A�Ⴄ�n�r�����ɂ����Ă��F���̈Ⴂ���N���Ȃ��F������A6�i�K��RGB�̑g�ݍ��킹�ɂ���Ăł���216�i6�~6�~6�j�F�̊�{�J���[�̑��̂̂��ƁB������E�G�u�Z�[�t�J���[�ƌĂ�ł���B
|
������Ɩʓ|�Ȃ��Ƃ������Ă��܂����B����͎����̐S�o���̂��߂ł����āA���̓��L�ɂ͑��������Ȃ���ˁB
�����Ɩ����ɂ͖Y��Ă��܂����낤�B�����Ɓ������炭�����Ԃ�B
���Ȃ݂ɁA��ʂɂ���O���̌��̕z���A��L�̖{�̐F�ɓ��Ă͂߂���A
�@�@�A�J�l���߂̕z----���O�F�@��D75455
�@�@���̐��t���߂̕z----�K���@��86A697�@�͂��߂͂����ƑN�₩�Ȑ��������A�F�����悤���B
�@�@�n�C�r�X�J�X�̉ԂŐ��߂��z----���[�^�X�E�s���N�@��DE82A7�@����ɂ͓��{���������B
����ȕ��ɓǂݎ�ꂽ�B
�A�J�l�Ő��߂��̂Ɉ��F�ɐ��܂��Ă��Ȃ��̂��A���S�҂̎��ɂƂ��ē���������[���B
��{�̃A�J�l�̐F����A���̎��̏����̈Ⴂ����F�ɂ��ꂪ�N���Ă���B�ƒ뗿���̖�����邽�є����ȈႢ������̂Ǝ��Ă��Ȃ����Ȃ��B�܂��܂����S�҂ɂ͖ʔ����B
�ł��A���߂��������F�͂��Đ��l�ɕ\�킷�����A���̐F�̊��G��N���オ���Ă���v���������̂��̂ɂ���ق����y�����Ȃ��H�܂��������R�Ɏ����̐g�̂Ɋg�U���Ă����F�ɑ��銴�G���A��u�A��u���Ƃɖ��킦�����̂ł͂Ȃ��H
�L�`�L�`�Ɛ����Ă����̂��~�߂悤�ˁA�킽���B
�Q�l�F
�w���������{�̓`���F�x�@������Ѓp�C�C���^�[�i�V���i���Њ��@2021.11.24�@���ő������s
���R�̕�炵697�@�@ 2022.12.17
 �@ �@
�@
�@
 �����̂͂��܂�
�����̂͂��܂�
 �@������@3�Z���`�@12��6�� �@������@3�Z���`�@12��6��
 �@�V�W���E�J���i���j
�@�V�W���E�J���i���j
��`���B�����`���ȁB����A��������̓��[�����H�@�u�R�`�ԓ��h�݂��E����C�v----�h�����ȂˁB
���݂���������Ղ����āA�{�̂��ڂ���g�b�s���O�ɂ��Ă��ꂽ���āH�@����͊��������낤�B���オ��̃L�~�͂��ڂ낪��D��������ˁB
����͔��Ɓi�{�{�j���c�q�̓炾�Ȃ�ē~�̏��߂̓V�����`�B���C�������ނ́H�����ȁB
���ꂳ��̓t�X�}�̃p���ɍ��������̗M�q�W����������ł���́H�����ȁB�t�X�}�p���ĕ��������Ƃ͂��邪�A�������������H�S�[���ƒ|�ւƏo�����Ⴑ��ώϕ��Ɏς��H�����l�������邵�J���V�E�����ۂ��ˁB
����̎c��̃I�f��������̂��B���̉w�̏��{����̑卪�͈�i�I�@�������Ăłӂ����炵�Ă���B
�f�U�[�g���L�D�C�Ɗ����`�����āB�܂��܂������ȁB
�f�b�L�̎肷��Ɏ~�܂��ăV�W���E�J�����`������ł����B�ߌ�͒�|���̗\��B
�~��O�ɍ��N�Ō�̑|���ɂ��������Ō�ɂł����炢���Ȃ��B
�V�W���E�J���́u��}�̐ߋG���炫�E�����̂��������炫�v�Ƃ����������������Ă��������B�@
�@�@���R�̕�炵696�@�@ 2022.12.10
 �@ �@
�@
�@�@ ����ł͏��Ȃ��@----�K�[�f�i�[�ɂƂ��Ă̍ɂ́A������Α����قǗǂ��B�K���ɂȂǂȂ��B
����ł͏��Ȃ��@----�K�[�f�i�[�ɂƂ��Ă̍ɂ́A������Α����قǗǂ��B�K���ɂȂǂȂ��B

�@�@�@�A�C�X�����h�|�s�[90�{�A�X�C�g�s�[12�{�B���������ꂾ���B
���̐��́A�Ő����i2008�N����2015�N�j�̂���̎l���̈�B���܂��܂Ȏ�ނ̉ԕc����Ăē~�z�������Ă������̍��̈ӋC�͂ǂ��֍s�����̂��B
�悤�₭����ɊȈՉ�����ݒu���āA�~�z���̏������ƂƂ̂����B���܂ɔL�����荞��Œ��Q�����Ă���B
����ŏo��ӋC���������F�l�Ƃ̌𗬂������A�ŋ߈��ۊm�F�����˂ĉו����s�����藈���肵�Ă���B
�킯���Ȃ�������
�B�@�@�����āA�݂��ɂ��܂��Ă���ł͂Ȃ��ł����B
�_�˂���́A����ꂽ���s�̘V�܂́u���̖��X�Ђ��v��
�����Ă����B�����̂��Ă��āA���Ƃ������Ȃ���i�Ȗ��������B�����炩��͓c�ɂ̃G�b�Z���X��----�����`��M�q�Ȃǂ��l�߂đ������B
�\�����킹�ė���ŗ��������A�������قɔ��܂��ė��̎v���o�Ő���オ������ʂ̗F�l�v�w�B
�͂�钷�����h���C�u�����ĖK�˂Ă��Ă��ꂽ��t�̂��v�w�B
�k�C�������̕ւ���Ă����F�l�B
���������Ɗ������ƁB�ǂ̗F�l�����܂Œm��Ȃ������V�������E�������Ă����B
������A�F�l�����Ɉ�������E����Ă���̂��낤���B
���Ԃ��������Ɛ���B�~�����z���ē����Ă��Ă悤�₭���蒅�������ɁA�ߐ{�̎R�͔����p�������Ă��ꂽ�B
���R�̕�炵695�@�@
2022.12.5
 �@ �@
�@
 �u�X�|�b�g�N�v�Ɓu�X�|�b�g����Ȃ��N�v�Ɓu�X�|�b�g����Ȃ��v�N
�u�X�|�b�g�N�v�Ɓu�X�|�b�g����Ȃ��N�v�Ɓu�X�|�b�g����Ȃ��v�N
 �@���c�X�|�b�g���� �@���c�X�|�b�g����
�E���ł������̂��킪�Ƃ̎��͂�p�j���Ă����L����B�V�тɗ���悤�ɂȂ��ĂR�N�ɂȂ�B
���Ƃ��Ǝ����L�������̂��A���ɐl�������L�������B�D��S�����ŁA���������̒��Ŏd�������Ă���ƁA���ۂ̖ɓo���Ă܂Ŏ������̂������݁A���Ă����I�[���𑗂��Ă���Ă����B���܂ɃK�[�{�̈֎q�̏�Œ��Q�����Ă������Ƃ��������̂ɁA���̂Ƃ��댩�����Ȃ��B
���̉��ɍ����_������̂ŁA�n��L�ɉa��^��������Ƃ��Ė��O��t���Ă����B�u�X�|�b�g�N�v�ƁB
�u�X�|�b�g�N�`�v�ƌĂт�����Ǝ����ς��ς��u�����Ă����`�v�B�Ȃ�Ƃ����炵���q���B�ł����̂Ƃ��댩�����Ȃ��B
 �@�X�|�b�g����Ȃ��N �@�X�|�b�g����Ȃ��N
���c�X�|�b�g�N������Ă��Ȃ��Ȃ�����A�킪�Ƃ̒�̓꒣���_���ĐV�����L���V�тɗ���悤�ɂȂ����B
�܂��܂��X�|�b�g�N�Ɏv�����c���Ă���B���̐V�Q�҂ɖ��O��t���ď�ڂ�̂����Ȃ̂ŁA�t�������O���u�X�|�b�g����Ȃ��N�v�B
������Ƃ��ꂾ�ˁA�ޖ{�l�ɂƂ��Ă͕��J�I�Ȗ��O���낤�ȁB������ID�͂ǂ��ɂ���H�@
�܁A�X�|�b�g�N�̒n�ʂɂ܂ŒB���Ă��Ȃ��̂�����d���Ȃ���A�u�X�|�b�g����Ȃ��N�v�B
 ���_�_�ƂɂƂ��ẮA�������ɐ�������l�Y�~�ގ��̂��߂Ɂu�L�͌����������Ƃ��Ȃ��v�͂����B
���_�_�ƂɂƂ��ẮA�������ɐ�������l�Y�~�ގ��̂��߂Ɂu�L�͌����������Ƃ��Ȃ��v�͂����B
�ŋߑ��Ȃ���ʂ��Ă���ƁA���́u�X�|�b�g����Ȃ��N�v�ɂ悭�����L��������������悤�ɂȂ����B�����Ɠ����e���琶�܂ꂽ�̂��낤�B
�ӂ�܂����g�̖̂͗l��������ʼn��ڂɂ͌��ԈႦ�邭�炢���炢���B
�܂��܂����̎q�����ɐV�������O��t���Ȃ��Ƃ����Ȃ���----�w�u�X�|�b�g����Ȃ��v�N�x�͂ǂ����낤�H
�u�X�|�b�g�N�v�Ɓu�X�|�b�g����Ȃ��N�v�Ɓw�u�X�|�b�g����Ȃ��v�N�x�B���̊W�͂������I�ނ���
�K�����u�W���v�̍l�����Ɏ��Ă��Ȃ��H�I�傫�ȗւ̒��̏������ւ��ӂ��B����ɔL�ƌ������ʍ�������B
���߂̓�͓���̔L���A�����āw�u�X�|�b�g����Ȃ��v�N�x�́A�����璆�́A���{���ɂ���A���E���̔L���w���Ă���ȁA�ƕςȂƂ���Ŕ[�������̂����ς�炸�̖钆�̃x�b�h�̒��������B
���\�N����ɂȂ��Ďv���o���Ƃ͖ʔ����B
 �E�g�E�g�������ƁA�܂��l���t�����̂́A
�E�g�E�g�������ƁA�܂��l���t�����̂́A
���������邱�Ƃ𗧏���͕̂��@�����킩��ΊȒP���i�z���g�H�j�B�������������������Ƃ��؋����Ă�̂͂Ƃ�ł��Ȃ�������Ƃ��ƁB
���Ƃ��A�Ƃ̒��ʼn�����T���Ă���Ƃ���ƁA�����邱�Ƃ͂ł���B���������Ƃ��Ɩ������̂�T�����Ƃ͂ł��Ȃ��B
�Ƃ��イ��O��I�ɒT���Ȃ��Ɓu�Ȃ��v�Ƃ͌����Ȃ��B�F���l�͑��݂��邩�ƕ����ꂽ�瓚���́u������Ȃ��v�ƌ��������Ȃ��B�F������T���Ă��̑��݂�ے肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����B
�����ęl�߂ɂ��āB�L�߂𗧏��邱�Ƃ͏؋�������Ή\�����A���߂��A�܂����Ă��Ȃ����Ƃ��؋����Ă�͓̂��----����܂��x�b�h
�̂Ȃ��ōl�������ƁB
�ł��ˍŌ�ɁB
���̎q�����Ђ���Ƃ��āu�N�v�łȂȂ��āu����v�Ȃ̂�������Ȃ��B�u�ɂ��Z�Z�v�������Ɗm���߂����Ƃ��Ȃ��̂ŁB
�@
���ς�炸�ۂ����̂������Ă���B�a�`�A�������������iafter��before�j
�������������́A������Ƃ�������Ɋ��ł��炦�邩��֗��B
���R�̕�炵694�@�@ 2022.12.1
 �@ �@
�@
�@
�@ �@��d�̓����@�@�_�u�����C���{
�[�Ɉ������� �@��d�̓����@�@�_�u�����C���{
�[�Ɉ�������

�@�i����ł͋��낵���قǂ̔��������������A�f�W�J���ł̎B�e�͂��ꂪ���x�������B�j�ߑO�X���A��Ղ̒��B
��Â��玞�J���ԂԂƔ��ł��Ă������B���̂悤�ɍׂ����J���~�肵����A���˂����ɂ������đ��ɂԂ���B
�~����---�Ƃǂ���Ƃ��Ȃ����t�ɂ��āA���ꂩ��̊������v������������B
�O�ɏo�āu����--�v�Ƃӂ��茾�t���Ȃ��B
�k�k���̋�Ɂu�_�u�����C���{�[�v������Ă����B���܂�̔������ɓ��R�Ƃ���B�S�������ނ�����B
���̃_�u�����C���{�[�͂ƂĂ����������ۂŁA����������l�͐l�����D�]����A�j������Ă���A�肢��������----����Ȍ����`��������悤���B���̂����ɂ́u���C�ŕ�炷���Ɓv����Ԃ̊肢���낤���B
�Z���Ă͂����肵����������A���̏�ɔ킳���Ă��锖�����������B�u����đ��z���������ł���Ȃ��A���J���~���Ă���v----�������������ɂ҂�����̓V��ɕ\����d�̓��������̂́A������ɗ��Ă���͊o���Ă�����肱��łR�x�ڂ��B���̂��炢�������B
����͉J���ɓ������������P�˂���āi42�x�̋��܁j�������̂ɑ��A�����͉J���̒���2�ˁi50�x�̋��܁j�����B���̂��߁A����͋���ԁE��E黃�E�E�E���E���̏��Ԃ����A����̏�ɂ������猩���镛���͐F�̏������ɂȂ�Ԃ��n�ʑ��ɂȂ��Ă���B
�k�k���ɖ��J���~���Ă��Ă��̉J���X�N���[���Ɏg���A��쓌����˂���������̓������o�����悤���B
����ƕ����̊Ԃ͂�┖�Â��B��̓������o�������̋��ܗ��ɈႪ����A����̓�����ƕ����̊O����Ɍ����W�܂邱�Ƃ���A�ώ@���Ă��鎄�ɂ͓�̓��̊Ԃ̋Â�������Ƃ������Ƃ炵���B�i�A���N�T���_�[�̈Ñсj
�@ �@�ł��ˁA�J���ɂ͂����������Ȃ�42�x��50�x�ɋ��܂���̂��B�Ȃ��Ȃ̂��A�����ł��Ă��Ȃ��̂ł��B�����w�エ���炭�[���Ȃ�^�����B����Ă���̂ł��傤�B�ł�������Ȃ����͕̂�����Ȃ��̂ł��B
��{�̍l�����Ȃ̂ŁA�C�ۂɊւ���{�ɂ���������������Ȃ��̂ł��B���䂢�w���Ɏ肪�͂��Ȃ��C���Ȃ̂ł��B �@�ł��ˁA�J���ɂ͂����������Ȃ�42�x��50�x�ɋ��܂���̂��B�Ȃ��Ȃ̂��A�����ł��Ă��Ȃ��̂ł��B�����w�エ���炭�[���Ȃ�^�����B����Ă���̂ł��傤�B�ł�������Ȃ����͕̂�����Ȃ��̂ł��B
��{�̍l�����Ȃ̂ŁA�C�ۂɊւ���{�ɂ���������������Ȃ��̂ł��B���䂢�w���Ɏ肪�͂��Ȃ��C���Ȃ̂ł��B
�m���̕\�ʂ��|�`���|�`���������ʼnj���ł��āA�Ղ�Ղ�V��ł���̂����̎��B�������悤�Ƃ���\�͂Ɍ����Ă���Ȃ��Ƃ��݂��݊��������ł����B
�@
�@ �@���ڂ̗M�q�W�������@�@�܂��Ⴂ�����g���� �@���ڂ̗M�q�W�������@�@�܂��Ⴂ�����g����
 �@�Ƃ肠����16�@��̏d����600�� �@�Ƃ肠����16�@��̏d����600��
��������ׂ����Đ��ɂ��炷���Ƃ����B�������ɒЂ��Ă����A�Ō��䥂ł��ڂ�����2��B
���g���������i��ōi��A�ʏ`�Ǝ�Ƃɕ�����B��͏W�߂Đ������������A�y�N�`������肾���B
䥂ł��ڂ�����ɉʏ`�Ǝ��o�����y�N�`���������A���Ƃ͂��邮��ςĂ��������B����d���ł͖�������ǁA�d���̗���ɋt�炦�Ȃ��̂ŁA�Ƃ��J�����Ȃ��B��Ԃ�����������B��N���̊y���݂̂��߂ɁA�����̌ߌ�͗M�q�O���B
�i���䥂ł��ڂ������̒��ɂ́A�I�����W�Ό��Ɠ������u�E�ʊ����܁v���܂܂�Ă���̂ŁA�䏊�̓V��V���N�ɂ������Ɨ����A�u���V�ŐB������Ƃ��ꂢ�ɂȂ�j
�i���̕��肪�r���j
���̗ʂň�N����3���Ȃ̂ŁA����2��̍�Ɓi���₢��y���݁j���c���Ă���B�����̗M�q�͂܂��g���Ⴂ�̂ŋ�݂������A���������ʓ��̕��ʂ𑝂₵���A�Ƃ����Ă�2����
���ǁB���Ƃ��̏H�̓����S�W�������̗\�肪2��B�@
�@�@�@���R�̕�炵693�@�@ 2022.11.27
 �@ �@
�@
�@
�@�@  �\�t�g��\���̒���
�\�t�g��\���̒���
�܂��N���Ă��܂����B�g���Ă���HP�쐬�\�t�g�͖�20�N�O�̂��́B����܂�Windows8����Windows10�Ƀo�[�W�����A�b�v����ۂɂ��قƂ�ǒv����ԂɊׂ������Ƃ��������B�s���͂����N���Ă���B
�s�K�͓ˑR����Ă���B����̗[���A�\�t�g���J���Ă݂���A�f�[�^���u�������Ⴉ�߂����Ⴉ�v�ɂȂ��Ă��܂��Ă��āA�ǂ��ɂ��n�������Ȃ���ԂȂ̂ɏo���킵���I�@���̎��̏Ռ��́u����Ŏ���HP�͕��邱�ƂɂȂ邩��----�v�Ƃ����������̂������B�@�܁A�~�߂�ɒ�����������Ȃ��Ƃ��v�������B
�x�b�h�̂Ȃ��ōl�����B�@�i�l����̂ɂ悢�ꏊ�F�O��i�n��A����A�̏�j�Ƃ������̂ˁj
�l�b�g�ɏグ�Ă���̂Ȃ�A�~�낵�Ă����������Ȃ��H���̃f�[�^���\�t�g�ɂ͂ߍ���ł݂悤�A�ƁB�ŁA���܌��݂��������Ă��܂��B�Ȃ�������C���̉����@���������Ȃ�B
�L����ɓ]���\�t�g���g���ăA�b�v���� ---- ����̗[�H�������������ǂ����͂��̌��ʂɂ������Ă���̂��B
 ��閾���ăp�\�R�����N�����A���邨����l�b�g�Ɍq���ł݂��B�����I
��閾���ăp�\�R�����N�����A���邨����l�b�g�Ɍq���ł݂��B�����I
�P���Ɋ������B
�������ɂȂ����B�����������@�Ńf�[�^���č\�z�ł���̂��I�@
 �Ȃ瓖���炵���\�t�g���g���ǂ��H ���̒ʂ�B
�Ȃ瓖���炵���\�t�g���g���ǂ��H ���̒ʂ�B
�������t�H���_40�A�y�[�W��400���߂��f�[�^��V�����\�t�g�ɓ���ւ��鎩�M���Ȃ��̂��{���B
���R�̕�炵692�@�@ 2022.11.23
 �@ �@
�@
 ��̂��낢��@----���܂ł��I���Ȃ��d�� ��̂��낢��@----���܂ł��I���Ȃ��d��
 |
�|�s�[�̎�͊H�q���̂悤�ȁA�ƌ�����قǏ������B
�H�ފ݂Ɏ���������A�C�X�����h�E�|�s�[������Ȃɑ傫���Ȃ��Ă����B
����Ȃ��������B
���ꂩ�����傫���|�b�g�ɐA���ւ��āA����ɊȈՉ���������A�R���܂ň�c����B
���Ȃ炻�̂܂ܘH�n�ő傫���Ȃ�̂ɁA�����ł͂���Ȏ�Ԃ������Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
�ł��u�|�s�[�̍炩�Ȃ���v�͍l�����Ȃ��̂ŁA�����B
�@ |
 |
�`���[���b�v�̐A�����݂ɂ͂����x�����A���܂ł��炭�ẲԂ̔�����肪�ł��Ȃ��āA����Ȏ����ɂȂ��Ă��܂����B
�F�ʂɕ����ĕۑ����Ă������A����ɂ��ꂪ�ʓ|�ɂȂ��Ă��āA���܂�܂������ɁB
�ǂ��łǂ̐F���炭�̂��́A�炢�Ă̂��y���݁B
�������邩�ȁB�����炭500���炢���B
�Ō�͖ʓ|���i�����āA��֎Ԃ��Ɓu�����`�v�ƂԂ��܂��āA���̏�ɕ��y������Ƃ��������̋ɂ݁B
�y���݂ƌ������A�`���ɂȂ��Ă��܂�����d���B |
 |
���c�f�i����̊w��: Fatsia
japonica�j�E�R�M�ȃ��c�f���̏�Β�B�ʖ��́u�e���O�m�n�E�`���E�V��̗t�c��v�̂ق��������Ɩʔ������O�����ǁB
���̎����Ɋۂ��������ƍ炭�����Ԃ��ڗ����n�߂�Ƃ��悢��~�̎n�܂肪�߂��B
�Ԃ̏��Ȃ��G�߂Ȃ̂ŁA���������̐l�C�ҁB�����ɂ������͉J�͗l�Ȃ̂ŁA���̎p�������Ȃ��B
��������̈����Ƃ���ł����炷��̂ŁA�킪�Ƃł͒�̋��̃c�o�L�̉e�ɂȂ�Ƃ���ɐA���Ă���B
 �@�@�@�V��@��{���̉��� �@�@�@�V��@��{���̉��� |
 |
���c�f�E����́A�t�ɐ[���ꍞ�݂����邱�Ƃ���B�ꍞ�݂̐��ɂ͕ω�������A�܂A�Z�A���A���Ƃ��̐��ɂ͌��܂肪�Ȃ��B�����c���t�A�������t�A���A�̗t�قǐꍞ�݂̐������Ȃ��悤���B
���A���L����̔��B���̔��ɂ́u���������v�Ƃ����Ӗ�������炵���B�����ւ��������B |
 �@����̊w�����h
Fatsia japonica�h�ł��邱�Ƃ���A���{�̌ŗL��ł��邱�Ƃ�������B �@����̊w�����h
Fatsia japonica�h�ł��邱�Ƃ���A���{�̌ŗL��ł��邱�Ƃ�������B
���݂́u��Łv�Ɣ������邪�A�w���\�L�ɂ���悤�uYa�v�ł͂Ȃ��āuFa�v�ƂȂ��Ă���̂ɂ́A���R������悤���B�w���́hFatsia�h�͌Ñ�̓��{��́u���v�i�ӂ����j���炫�Ă���Ƃ̂��ƁB
 �@�n�n�͐̂̓p�p�������B-----����͗L���Șb�B�u���v�i�ӂ����j�̔����ɊW���邩���ׂĂ݂悤�B �@�n�n�͐̂̓p�p�������B-----����͗L���Șb�B�u���v�i�ӂ����j�̔����ɊW���邩���ׂĂ݂悤�B
�ޗǎ���ȑO�̌Ñ���{��ł́A[h]����[p]���Ŕ�������Ă����B����[p]���͕��������[�U]���ɁA�]�ˎ���ɓ����Ă悤�₭[h]���ɕς���Ă��Ă���B�p�p----�t�@�t�@----�n�n�@�����ω����Ă����B
[p]���͗��O�j��----�͂������B[�U]���͗��O���C���B[h]���͌��W���C���ł��łɐO���g��Ȃ����ɂȂ�B
�����͊y�Ȃق��֊y�Ȃق��ւƕς���Ă����Ƃ������Ƃ炵���B���������X�y�C������t�����X���[h]�������Ȃ��̂ɋC�t�����B�p����������A[h]��������
���P��������ˁB
���R�̕�炵691�@�@ 2022.11.16
 �@�@ �@�@
 �[�Ă��ƒ��Ă��͂��Ȃ����̂� �[�Ă��ƒ��Ă��͂��Ȃ����̂�
���̋C��������Ɖ�����A�ꌅ�̏������ق��ɋ߂��Ȃ��Ă����B���ɑ����~��邱�Ƃ������āA���悢��H�̏I��������������X�������Ă���B
������������������A�����V�C���B���؉z���ɗ[�Ă��������A���Ă������X�̊Ԃ���܂���Ȍ��ƂȂ��ē͂��Ă���B
�v���o���̂́A�l�p�[���A�|�J���̃T�����R�b�g�̋u���猩���q�}�����̖���u�}�`���u�`�����i6993���j�̒��Ă��v�B���̋���݁A�������ޒn������͂������A�R���K�N�F�ɋP������ɔ����𑝂��Ă����A��̐F�ɕω����Ă�
�����B���̐��̂��̂Ȃ�ʔ��������L���������A���͉F���ɔ�т��݂����������B
�������Ƃ��[���ɂ��N�����B���Ԃ��t�ɉ�����悤�ȋC������B�Y��ȗ[�Ă��������B

�@�@�����̓}�i�X���A�������}�`���u�`����
�[�Ă��ƒ��Ă�----���̓�͓������́H�@�Ȃ��N����̂��낤�B������� �̂̋L������������o���Ă݂�B
�@�@�@�@�@�@�@�i������Ǝv���o���̂ł����āA������Ƃ̐̂ł͂Ȃ��B�����Ԃ�Ȑ́A�����\���Ⴉ��������̐́B�j
�܂����z����̌��ɕ����ׂĂ݂�ƁA����Ă���Β��Ԃ̋�͐��B�ڂɌ�������͉����ƌĂ�A������Ԃ܂ł̌��Ƃ��Č��邱�Ƃ��ł���B�����̌��͑��z����n���ɓ͂��Ƃ��ɁA��C����ʂ�B���͋�C�̕��q��`���ɓ������ĎU���B����Ȃǂ̔g�����Z�����قǂ��낢��ȕ����ɎU����Ă��鐫���������Ă���B�i���C���[�U���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�C���Z���l���\��銴���H�@�̂�т肳��͂܂������i�ށj
�ł͂Ȃ���́A�g���̒Z�����F�łȂ��H
���͂ƂĂ�������ŎU�����Ă��܂��̂ŁA��ɂ͎��ɔg���̒Z�����L���邱�ƂɂȂ�B
����[�́A���z�̍��x���Ⴍ�Ȃ�̂ŁA�n���ɓ͂�������C�̒���ʂ鎞�Ԃ������Ȃ�B���̕��ق��̉������U������Ă��܂��A���
�g���������U������ɂ����u�ԁv���c���Ď������̖ڂɌ�����B
���ꂪ���Ă��Ɨ[�Ă��̎d�g�݂炵���B
�u�ԁv�͔g���������B������M���@�́A�J�̓����܂�̓����A���[���Ȃ�ׂ������֓͂��悤�ɂƁu�Ԃ��v����A���ӂ𑣂��Ă���B
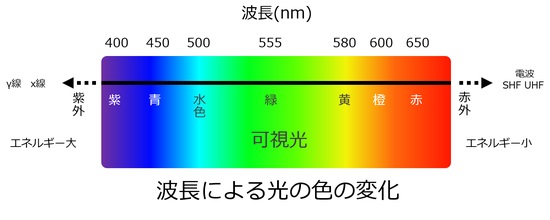 �o�T�FWikipedia�@������ �o�T�FWikipedia�@������
�ł�11���W���̖�Ɍ���ꂽ�F�����H�́A���̐Ԃ����́H�ǂ����痈���F�H
�i���������j�F�����H�́u���z�ƒn���A�����꒼���ɕ��сA�����n���̉e�ɓ���v���ƂŋN����B�������H�̊ԁA���͔����P�������ƒn���̈Â��e�̑Δ�������Ă����B���ꂪ�F�����H�̏�ԂɂȂ�ƁA���F
�Ƃ�����----�ԓ��F�ɋP���Č������B
���z���̐Ԃ����͔g���������ĎU������ɂ����A�n���̑�C��ʉ߂ł���B
���̌�����C�ŋ��܂��Ēn���̉e�ɓ��荞�ނ��߁A�����Ԃ��Ƃ炳�ꂽ�Ƃ����̂��^���炵���B
����͒n���̒��Ă��Ɨ[�Ă��Ɠ����悤�ɁA��C��ʂ����Ԃ��������ɔ��˂��ĐԂ�������Ƃ������Ƃ��B���Ƃ���ƁA���̐ԓ��F�Ɍ��錎�͌�
���[�Ă������Ɠ������ƁH�@������̂ƁA���˂��Ă��̐F��������̈Ⴂ���낤���B
�@   
���͐Ԃ����́A���팩�����邱�Ƃ������̂ɋC���t�����B
���Ă��Ɨ[�Ă����Ԃ��̂Ɠ������A�����Ⴂ�ʒu�ɂ���ƁA������̌��̍��x���������A�n���̑�C�̒��Ń��C���[�U�����āA�Ԃ̉����������c�邩�炾�B����Ɍ����Ⴂ�ʒu�ɂȂ��Ă��A�c��ڂŖ�Ă����āA������ɉ����Y���Ă���
�Ƃ��������ƌ��͐Ԃ�������A�s�C�����B����͋�C���ɉ���`�����Y���Ă��āA�ԈȊO�̐F�����C���[�U���������ʂ炵���B
�F�����H�Ō���ꂽ�Ԃ����́A�u�V���ɂ��������璿�����P�[�X���Ǝ�����v�Ƃ������Ƃ��B
�����ЂƂ��ɂ��Ă킩��Ȃ����ƁB����́u�F���x�v�B���̐��������x�����Ă��D�ɗ����Ă��Ȃ��B�P���r���l�A�g���ȂǂȂǂ��܂��܂Ȍ��t����ь����Ă��āA���̂Ȃ��͂��炪�����B
���ꂩ�����āB
����Ȃ���Ȃ��l���Ă��Ă��炻�낻��[���B����ƍ�����������́u���̖I���`�v���A�g���̒����Ԃ������ăI�����W�F�ɋP���Ă���B����͊`���[�Ă����Ă���̂��H
�@���ƂS�O���ŏo���オ��B
 �������܂Ŕ��������̂ɁB�[�z�����������B �������܂Ŕ��������̂ɁB�[�z�����������B
�@  �@�S�������čs�����Č����Ă��B �@�S�������čs�����Č����Ă��B
�I���`�̖A����60�N�߂��B���ߐ{�삪���ɓ��A�����F�l�̑c�����A�����ꐶ�܂�Ă��鑷�ɐH�ׂ��������ƐA�����B�����̑��͊����`�ɖڂ�����Ȃ��B�����ʼn���̏o�ԁB���͑��_�A�E�͋C�O�̂����F�l�B�s�̒��S�n�ɍL���y�n�����n�傳��B
 �����́u�[�Ă��v�́A��̒��Ԃ̒��q�K�C�h�������ꂽ�L���ɁA�S�������ꂽ���́B �����́u�[�Ă��v�́A��̒��Ԃ̒��q�K�C�h�������ꂽ�L���ɁA�S�������ꂽ���́B
�@�@�i�I�R�K�C�h�̃A�C�������h���L ���@http://naokoguide.com/�@���@2022.10.17�@
�@�@�@�n�C�W�̐�A�����āu�R���R���Ă�I�v�i�n�C�W�̕����K�˂ćB�j
�@�@�@�@���@http://naokoguide.com/blog-entry-4167.html�@���@�@
�@�@
���R�̕�炵690�@�@ 2022.11.11
 �@�@ �@�@
�@
 �@�ۂ����̂������������� �@�ۂ����̂�������������
 �@��T�ԑO���̂����a�`�i��Ðg�s�m�`----�g�̒���m�炸�A�}���܂��قǗ�Ȃ�Ɏ����Ȃ�j�̕����J���Ă݂��B������C�ɂ��炷�Ǝ��ɔ��������o���オ�����B���������B�T���g���[���C�����̌��ʂ͐�傾�B �@��T�ԑO���̂����a�`�i��Ðg�s�m�`----�g�̒���m�炸�A�}���܂��قǗ�Ȃ�Ɏ����Ȃ�j�̕����J���Ă݂��B������C�ɂ��炷�Ǝ��ɔ��������o���オ�����B���������B�T���g���[���C�����̌��ʂ͐�傾�B
�@�@ �@��̓�͗M�q �@��̓�͗M�q
 �@���Ă͐��E��h�����h�q������----�n�o�l�� �@���Ă͐��E��h�����h�q������----�n�o�l��
��������ɓ������̂ŁA�����͗Ⓚ�Ɏc��͊��������Ă���B��Ӎ�p�ɗD��Ă��Č������悭����悤���B�Ƃ�ł��Ȃ��h���B����҂炲�ڂ��ɂق�̏��������A�����̈ꂭ�炢����œ����Ƌ���̂��܂݂����������A�Â�������������悤�ɂȂ�B
�������A��舵���ɒ��ӂ�����B��������n�o�l����G�����w�Ŗڂ����������肷��ƁA���Ƃ͔����̔ߌ����҂��Ă���B���͂����ĔM�������炢�h���I�ȃn�o�l���B���܂ɂ͂���������B
�@�@
 �@�P��̊����`���� �@�P��̊����`����
�������݂ŖI���`75�A���n�`65�̔���Ċ������B�݂��ɂ������Ƃ��ꂢ�Ɋ���������Ȃ��̂ŁA����Ȏ���������
�`���������ɕ��ׂ�B���ŗp�ɗp�ӂ��Ă���25�x�̏Ē��ɐ����A���z�ɓ��Ă�B���炫��ƋP���I�����W�F�͂��ꂱ���`�F�B
�����͑��_�̂��߂ɁB�c��̔����͗F�l�m�l�ɁB�����Ă��鏊�������Ă��܂����אl�ɂ��������킯�B
�i���͐H�ׂȂ��̂ł��B���̃e�N�X�`���[���D���ł͂Ȃ��̂ƁA���_�̍D��������Ă͈�������B���̑��莄����ԍD���ȁu�C�`�W�N�v�ɂ͎���o���Ă��Ȃ��B�������B
�j
�{���͉��Ɉ��10�Ŋ������̂炵���B�u�O�E���ƃj�R�j�R�A���E�Ȃ��r�܂����v��2�{6�{2��10�B
�@�@

 �@�r�I���̒�A
�@�@�@5���Ԃ��������B�@ ���a�W�Z���`�̍��ۃ|�b�g��130�{�B �@�r�I���̒�A
�@�@�@5���Ԃ��������B�@ ���a�W�Z���`�̍��ۃ|�b�g��130�{�B
���H���ς܂��Ă����O�ɂł�B�r�I���i���|�햼�́A�r�I�� �\���xXP
YTT�j�B������F�Ƃ��Ƃ����Ȃ��F�B���͂ɉ��F�̃T�N���\�E���炭�̂ŁA��F�̐n��I�B���̂Ƃ���̐��V�ŁA��y�������Ă���B�܂������肩��͂��܂�B
�ȈՉ����̂Ȃ��ł͈�l�O�̊i�D�����Ă������A�n�ʂɂ��낷�Ƃ����ɂ�����Ȃ��A�c���q�����r���ɕ��Ă���悤�Ȏp�����Ă���B
�@�@�@ �@
�ԐF�͔�����ւƕς���Ă��� �@
�ԐF�͔�����ւƕς���Ă���
 �@���ׂ̕ʑ��ł̓L�m�R�͔̍|���Ȃ����Ă���B�����̓N���^�P���R�����������B����͂���`�B �@���ׂ̕ʑ��ł̓L�m�R�͔̍|���Ȃ����Ă���B�����̓N���^�P���R�����������B����͂���`�B
 �@�߂��̓��̉w�ɍs������A�X�������������Ðg�s�m�`�������������B�a�����@���������Ȃ��悤���B�����Ƃ������̓X���́A�Z�����Ă���Ȏ��Ԃ��Ȃ�
�Ǝv�����ǁB��������Ȃ�----���܂ɓX�ŏo��������q�����
�A��̈������₻�̂�����������ďグ�Ă��邩��B����{�����e�B�A�����B �@�߂��̓��̉w�ɍs������A�X�������������Ðg�s�m�`�������������B�a�����@���������Ȃ��悤���B�����Ƃ������̓X���́A�Z�����Ă���Ȏ��Ԃ��Ȃ�
�Ǝv�����ǁB��������Ȃ�----���܂ɓX�ŏo��������q�����
�A��̈������₻�̂�����������ďグ�Ă��邩��B����{�����e�B�A�����B
�@�@�@���R�̕�炵689�@�@ 2022.11.6
 �@�@ �@�@
�@
�@
 �@�ߐ{�삪�������َ�Ấu�J�G�����T�[�`�v�ɎQ���������ʂ����@�@ �@�ߐ{�삪�������َ�Ấu�J�G�����T�[�`�v�ɎQ���������ʂ����@�@
�@�@�@�@���T�[�`�̊��Ԃ́F2022�N�S���P������11��1���܂ł�7�P���ԁ@�������ꏊ�͎�Ɏ��̒�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ̏ꏊ�́F�W��425���@�ߐ{���P�x�̓쐼�ʂɍL������n�@���͍͂L�t���t���̗�
���炩���ߒ����ΏۂƂ��ꂽ�J�G���T��̂����A�A�Y�}�q�L�K�G���ɂ͏o���Ȃ������B
�������ԈȌ�ɂ��J�G���������邩������Ȃ����A�Ƃ肠�������N�̒����͏I���ɂ���B
|
�g�E�L���E�_���}�K�G�� |
34�� |
�����S��12�� |
�I��10��14�� |
|
�A�}�K�G���i���{�A�}�K�G���j |
10�� |
�����S���U�� |
�I��10��29�� |
|
�j�z���A�J�K�G�� |
�P�� |
10��3�� |
�@ |
|
���}�A�J�K�G�� |
�S�� |
����9��25�� |
�I��9��28�� |
���ꂾ���̏��ł͌X�������߂Ȃ��B�قƂ�ǂ̃J�G���Ƃ͒�ł̏o��������̂ŁA��ɏo��@����Ȃ����������āA�J�Ȃǂ̓V��ɍ��E���ꂽ�B
���������N�̃��T�[�`�ɎQ�����邱�Ƃɂ���āA�J�G���Ɋւ���m���������Đ��_���_�炩���Ȃ����悤�ȋC������B���������Ă�������ǃJ�G���ɂ��Ēm��Ȃ����Ƃ������A����ɃJ�G�����ɖڊo�߂��̂��������낢�B���̈ꉟ���́u�j�z��
�A�J�K�G���v�B����̂��锒���f�R���e���m�[�u���ȕ��͋C���܂Ƃ��Ă����B
�����قɂ͕ʓr�ڍׂȏ�����邱�Ƃɂ��悤�B���N�͂ǂ����u�ցv���Ώۂł���܂���悤�ɁB
�Q�l�ɂ����}���Ȃ�
�@�w���{�̃J�G��48�@�Έ��}�Ӂx�@����M�咘�@�͏o���[�V��
�@�w����`��J�G���x�Ȃ�ׂĂ݂��----�@�@���������ʐ^�@�������]���@�A���X��
�@�w���{�̃J�G���x�@�R�k�n���f�B�}��9�@�@���������ʐ^�@���R�����Y���@�R�ƌk�J��
�NjL
���a30�N�㒆���n���̎R�Ԃ̑��ł́A�I�I�T���V���E�E�I�i�̒�0.7�`1���[�g���j�������Ε߂����Ă����i�H�p�j
2001�N�A��ォ��ߐ{�ɈڏZ�B2013�N����܂ŗтŃV�}�w�r�A�A�I�_�C�V���E�A���}�J�K�V�������Ό���ꂽ�B
2010�N���炢�܂ŃG�]�n���[�~�̐����������Ă����B
2010�N���炢�܂ł́A��ɃA�Y�}�q�L�K�G�����������Ă����B
2022�N10��26���@�����R�N�̉Ƃ̉��̒r�ɁA�����A�I�K�G���������Ȃ������B
�@ �@�C���t���ΘJ���̓��X�@----�@�P�O���s �@�C���t���ΘJ���̓��X�@----�@�P�O���s
6���N���A�Ǝ���7�������Ȃ��A�ߑO3���Ԍߌ�2���Ԃ̒�d���i�Ē�̐����A��܂��A�|���A����Ȃǁj�B���_�̉Ǝ��S���͖�3���B���̐����͓��ɂ���ĈႤ���傫���ق��ɂ͓����Ȃ��B
���̍��Ԃɍg�t��肪5��i���ٓ���������----���ꂪ�܂�������Z�����j�����10���������B
 �@�����тł��ٓ� �@�����тł��ٓ�
�@ �@�̎������d���� �@�̎������d����
�ăn�[���A�K�}�Y�~���Ƃ��Ɏd�オ��͏����B�i���˂Ȃ̂ɁB�ӂӁA�ԉG�X�q���j���N�Q���̒a�����ɊԂɍ������H
�a�`�����킹��B25�x�̏Ē��ł͐S���ƂȂ��̂ŁA���_�ɖق��Ď���Ēu���̃T���g���[�E���C�����i40�x���炢���j��U�肩���A��Ï��Ɏd�������B����1�T�Ԃŏo���オ��i�͂��j�B
 �@���h�ӂ��₳�� �@���h�ӂ��₳��
�@ �@�Ԃ��Ԃ�Ђ��� �@�Ԃ��Ԃ�Ђ���
��Â̎R���A�ڊ⑺�֏o�����ē��Y�̐Ԃ��Ԃ����߂Ă����B�z100�N�ɂȂ낤�Ƃ���Ȃ��艮�ŁA���h���c�ނ��v�w�ƒm�荇���ɂȂ��āA��炵�̂��ꂱ������q�˂���̂́A�̂̓c�ɂ�m�����ɂ͂ƂĂ������[�����Ƃ������B���̉Ƃ��������20���ŁA���������̋���������ȂǁA�܂����������đA�܂�������B���2���[�g�����~�邯�ǁB
�@�@�@�@�@ �@�ڊ▼���Ԃ��� �@�ڊ▼���Ԃ���
�@ �@10��23���@���ᒎ �@10��23���@���ᒎ
���ᒎ���������B�ӂ�ӂ�B�Ƃ炦�ǂ��낪�Ȃ��B�w�ł������ĐG���Ă݂�B�v���o���͎̂q���̂���ǂw�����x�i�����̎��`�I�����j
�B
�`���̊W�������̂ɁA��������������Ȃ��قlj������Ă��ꂽ�c������̂ԁB�Ȃɂ���`���̑c��͎��̑c�ꂪ�����ɖS���Ȃ�����A�����ꍥ
�̂X�l�ڂŒn��̌㊘�Ɏ��܂�����J�l�B
�@ �@10���ɓǂ{�͖�2�O���{10�� �@10���ɓǂ{�͖�2�O���{10��
���݂��ݖ��킢�Ȃ���������ǂ̂́A
�w�{��֎q�̗��H�x�w�V�x���A�Ő[�I�s�x�w�v���A�ǓƂ͔������x�w�n�R���j�b�|���x�w���j�w�҂ƌ����a�x�w���̐��Ő����闝�R�x�w���ǁ@�Ԗт̃A���x�w���{�̒n��������Ȃ��x�w���炵���F���̐}�Ӂx
10���́A���ʂɓǔj----���������ē��e���S�g�ɔ����������Ă��Ă��Ȃ��B
10���͓��e���\�z�ƊO�ꂽ�̂ŁA���r�܂œǂ�ŕԋp�B�i��������j
�@ �@��������ʋ�~���Ă���̂� �@��������ʋ�~���Ă���̂�
�V�W���E�J���̐��A�L�c�c�L�̃h���~���O�A�K�r�`���E�i������j�̊y�����Ȑ��A���邭�Ȃ�ƃW���E�r�^�L���u�q�b�q�b�v�Ɠ꒣��錾������B�ׂ̉Ƃ̉����ŁA�����炭�����̍s���\���b�������Ă���̂��낤�A�J���X�̒���̂�����������B�J�P�X���ӂ�`��ӂ�`��Ɣg���s�ł���Ă����B���ԂɃ��Y���u�L�L�[�v�Ɩ��A�L�W����߂�ł����������Ă���B
 �@���悢��11���@�����`�̋G�� �@���悢��11���@�����`�̋G��
�`�Ƃ̏o��͋��R�ƕK�R�̂܂������B���̉w��Y���̓X�Ƃ悵�݂�ʂ��A�������ƒʂ��Ǝv��ʊ`�Ƃ̏o�������B�Z�������y�����d���̎n�܂�B�i���͐H�ׂȂ��̂ɁB���̍�Ƃ��D���Ȃ����B�ۂ����̂�����Ƃނ������Ȃ�B�j
�F�l�m�l����悭�Ȃ��m�点���͂��B�����ɂ��Ȃ�B
���������悤�ɂ��v���邪�A�C�Â��ΏI����Ă���10���������B�~�̏����܂ł��Ə�������B
�H�̌i�F��S�ɖ��ߍ���ł������B
�@�@
�P���L�@�N���@�R�i���@�C���n���~�W�@���}�U�N���@�J�c���@�u�i�@�u�i�̎��@�^�`�c�{�X�~���@�q�����u����
���R�̕�炵688�@�@ 2022.11.1
 �@�@ �@�@
�@
 ����Ȏd������D�� ����Ȏd������D��
�H�̗т̌b�݁A����͂��܂��܂Ȗ̎����n���Ă��邱�ƁB
�����͐}���ق֏o���������A�O��ɉ�����C�A��������x�����Ȃ�������Ă���̂ɂł��킵���B�����l�Ƃ̒�̊`�̎��⃀���T�L�V�L�u�̎��Ɏ䂩��ĎR���牺��Ă����̂��낤�B�ăn�[��K�}�Y�~�̎����_���Ă���ɈႢ�Ȃ��B�����͂Ȃ炶�Ɛ���z���A���n���Ė̎�����������B����Ȏd������D���B���˂Ȃ̂ɉ������o��������ߒ������Ă���̂���D���B�@
�@�@(�}���ق̑O��ɉ�������----�ǂꂾ���c�ɂȂ́H�@���₢�╁�ʂ̓c�ɂł��B�j
 |
 �i�c�n�[�� �i�c�n�[�� |
�i�c�n�[���Ԃ�Ԃ�B�c�c�W�ȃX�m�L���B�ߐ{�ł́u�ǂ�҂Ⴊ�܁v�ƌĂ�邱�Ƃ������B���̂�����́H�@�ʎ��������猩��Ɓu���r�v�Ɍ����邩��B�u���[�x���[�̒��ԂŁA�n���O�ɐH�ׂ�Ǝ_���ς��B�Ē�25�x�ɂ��Ĕ��N�҂B���y���邽�߂̉h�{���Ƃ��č�����������B
�V�R�y����������u�h�E���A�����������Ɣ��y�����i�ނ炵���B����̓����S���̔n��������鎞�Ɠ����B
���܂��ł���Ƃ܂�ŃJ�i���A�����E�}�f�����C���̖�������i���Ƃ�����j�B
 |
 �Ђ��n�� �Ђ��n�� |
�K�}�Y�~�̐Ԃ����B�����v�N�\�E�ȃK�}�Y�~���B�������ɓ�����O�Ɏ��n�����B�i�c�n�[�Ɠ������Ē��ɒЂ���B���͍��N���߂Ă̒���Ȃ̂ŁA���������ǂ̂悤�Ȃ������ł���̂��A�y���݂ł�����S�z�ł�����B
�K�}�Y�~�̕ʖ��Ɂu���c�h���E���E�h���v������A�ߐ{�ł̓��E�h���ƌĂ�邱�Ƃ������B
�Ƃ��낪�u�I�g�R���E�h���E�j���E�h���v�Ƃ����悭�����A��������B�ӂ�ӂ킵�������Ԃ��炫�A�H�ɂ͑^�X�Ƃ����Ԃ������n�����A��̃K�}�Y�~�̂悤�ɐH�p�ɂȂ�Ȃ��B�ʎ��͑����Ă��Ă܂�ɕt���B���ɗ����Ȃ����Ƃ���u�I�g�R�v�������āu�I�g�R���E�h���v�ƌĂ��悤�ɂȂ����Ƃ������������邪�������낢�B�H�ׂ��Ȃ�����j�H
�@�Ȃ�قǐH���Ȃ��j�Ȃ̂�������Ȃ��B���t�����̂͂����ƁA�������[������Ȃ��ڔz��ł��邵������҂̏��̐l���낤�B
�@�I�g�R���E�h���@���@ �@ �@
 �@��@�J�����J
�@�� �@�i���V�A��: �K�p�|�y�~�{�p�j�@���V�A�̈����́B �@��@�J�����J
�@�� �@�i���V�A��: �K�p�|�y�~�{�p�j�@���V�A�̈����́B
�r�ɒЂ����ފԃJ�����J�̉̂���������ł����B�J�����J�Ƃ́A�K�}�Y�~���̎����Ӗ����郍�V�A��u�J���[�i�v(�{�p�|�y�~�p)�̎w���`�B�����A�������ƌ������Ӗ���t�������铭��������悤���B���{��Ō����u�K�}�Y�~�����v�Ƃ������Ƃ��납�B�i�J���[�i�����m�J���{�N�j
�����ԃ��V�A���w���Ǝv���Ă������A���ׂĂ݂�ƃC�����E�y�g���[���B�`�E�����I�[�m�t�i��ȉƁE��ƁE���w�����ҁj��1860�N�ɍ쎌�E��Ȃ�����i���ƕ��������B
���́u�J�����J�J�����J�J�����J�}���v�ƌy���Ɏn�܂�C���g������ۓI�B
�K�}�Y�~�ƃG�]�C�`�S�̑g�ݍ��킹���A�Ⴂ�j�����ے�����ƍl����ƁA�����y�n���ւ̋������N���Ă���B
�@�@ (�C�Â������ƁF�K�}�Y�~���G�]�C�`�S���������딒���Ԃ��炫�A�Ԃ���������B�j
��K�}�Y�~��A�K�}�Y�~��A���̃K�}�Y�~��I
��ɂ͎��̃G�]�C�`�S���A�G�]�C�`�S�̎��������
----����----
�����I�������������A�Ⴂ���S��
�ǂ��������D���ɂȂ��Ă�����I
�A�C�E�����[���A�����[���A�A�C�E�����[���A�����[��
�ǂ��������D���ɂȂ��Ă�����I
�K�}�Y�~��A�K�}�Y�~��A���̃K�}�Y�~��I
��ɂ͎��̃G�]�C�`�S���A�G�]�C�`�S�̎��������@��
�@�@�@�@�@�i��� ���L�@���{�̃`�F���t�ҁA���y����ҁj |
2016�N�A���q���S����ǂ��ă��[���V�A�嗤�����f�����V�x���A�S���ɏ�肽���ƂЂƂ�ŗ��������āB
�u�����[�g���a���i�o�C�J���Γ쓌�ɂ��鋤�a���j
�ɁA�鐭���V�A����ɍ����ږ�������ꂽ�R�T�b�N�̎q�����Z��ł���B�I�̎��̑��������g���đ���ꂽ�A���j������������傫�ȏW�c�Z��̒��ŁA�N�������ߑ����܂Ƃ��Ă��̉̂��̂��Ă��ꂽ�B
�ق��8�N�قǂ̑O�̘b�Ȃ̂ɁA�����ɂ����ƌÂ��L�����S���Ă���B��������������ŁA��҂������ă��V�A���w���̂������a�̎��オ�������B���̋L���Ƀ��V�A��
�������u�J�����J�J�����J�J�����J�}���v�̉̂��d�Ȃ�B
�ŋߎv�����Ƃ������B----�ߋ��̊y���������o�������܁A�������t���ċA���Ă��Ă���悤�ȋC������̂��A����������ŁB
�@�@
�@�@�@���R�̕�炵687 �@�@
2022.10.25
 �@�@ �@�@
�@
�@ �@�����͐��E�ň�ԑ傫���؎肾�����@�@����p�����a100�N�L�O�؎� �@�����͐��E�ň�ԑ傫���؎肾�����@�@����p�����a100�N�L�O�؎�
 |
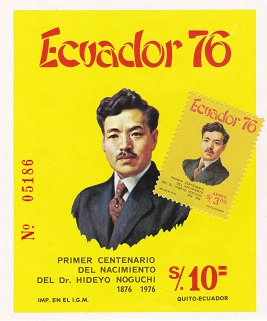 |
 �@�S���F�l�I���q���璸�����؎�u����p�����a100�N�L�O�؎�v���Ƃ��Ƃ���������B �@�S���F�l�I���q���璸�����؎�u����p�����a100�N�L�O�؎�v���Ƃ��Ƃ���������B
�c12�Z���`�A��8�Z���`�Ƃ����傫���́A�������E�ꂾ�����ƕ����Ă����B�ޏ��̎v���o�������Ȃ�͎̂₵�����Ƃ����A���̎茳�ɒu���Ă��������A�v�����Ċ�t����ق�����ԂƐM���āB
���
�@���v���c�@�l ����p���L�O��E����p���L�O��
���Ƃ����̂܂ܕۑ�����Ă��āA���ɂ͉p�������u�u����Ăэ��n�܂��v���c���Ă���B
����p��
1876�i����9�j�N11��9���� �������O�c�a���O�銃�i�����c�㒬�@���Ƃ��璖�c��܂�2�L���قǁj
�@1928�i���a3�j�N5��21���@���M�a�̌������A�p�̃S�[���h�E�R�[�X�g�i���݂̃K�[�i���a���j�̃A�N���Ŏ����@51��
��ɍۊw�̌����ɏ]�����A���M�a��~�ł̌����Œm���Ă���B�������`�L�Ȃǂœ`����Ă���悤�ɂP�̎��Ɉ͘F���ɗ����č���ɉΏ����A���肪�����Ȃ���
�����B���t���щh�̐s�͂Ŏ�p���A�s���R�Ȃ�������肪�g����悤�ɂȂ�B���̎����Ɋ��������p���i�����͐���j�͈�t��ڎw���悤�ɂ�
��A����חサ21�ň�t�Ƌ����擾�����B
���̌�A�����J�֓n�q�B�y���V���o�j�A��w��w���̏�����o�ă��b�N�t�F���[��w�������Ŏ�ɍی����ɋ��ށB
�������������A�d�q�������̑��݂��Ȃ�����ɁA���M�a�̃E�B���X�������Ǝv��������p���̔ߌ����v�������B
1918�N�A����p���͉��M�a�̕a���̂����A���N�`�����J������ׂ��A�������������Ă����G�N�A�h���֔h������Ă���B
�����̌��ʊJ�������Ƃ����u���M�a���N�`���v�͊ԈႢ���������A�����̃G�N�A�h�����{���犴�ӂ���A�G�N�A�h���R�̖��_�卲�ɔC������Ă���B
��s�L�g�s�ɂ͖���ʂ肪����A�x�O�ɂ�Colegio Noguchi�i��������w�Z�j������B
�G�N�A�h���؍ݎ��i1982�N�j�A���{�l�w�Z�ƃR���q�I�E�m�O�`�Ƃ̊Ԃɂ͌𗬂��������B
 �@����L�O�ق�K�₵���̂�21���I�ɂȂ��Ă����̂��낾�����B�Ռ������莆��W�����Ă������̂��v���o���B�ɂ߂��̕n���ƁA�^�~�ɌŃV�W�~���l���Ĕ��錵�����J���ƂʼnƑ����x���Ă�����V�J���A���q�p���ɑ������莆�������B���������Ȃ��ꂪ�A�C������`��������S�Ŋw�я����������莆���B �@����L�O�ق�K�₵���̂�21���I�ɂȂ��Ă����̂��낾�����B�Ռ������莆��W�����Ă������̂��v���o���B�ɂ߂��̕n���ƁA�^�~�ɌŃV�W�~���l���Ĕ��錵�����J���ƂʼnƑ����x���Ă�����V�J���A���q�p���ɑ������莆�������B���������Ȃ��ꂪ�A�C������`��������S�Ŋw�я����������莆���B
�莆�A���̉��[�����Ƃ炦�ǂ���̂Ȃ����́B�l�̎v���̔��I�ł������͂����A����Ɂu��^�v�Ƃ��ĕω����Ă����B�q�[--�h��̌��т�������A����̈��A����^���������̂���������B������w�ׂΑ���Ɏ���̂Ȃ��t�H�[�}���Ȏ莆��������A���ꂪ��V�Ƃ��ĔF�߂���悤�ɂȂ��Ă����B
���ʂ���ȏ�ʂ����������邱�Ƃ������Ȃ����B���t�������V�������`�������قǁA���e����a�ɂȂ菑�����l�̐��_���痣��Ă����悤�Ȉ�ۂ���̂��B
 �@�����ɕ�V�J�̎莆������B���M�ŏЉ�ł��Ȃ��̂��c�O�����A���߂Č����Ƃ��A���̓��e�̌������Ɣ��͂ɋ������B���q�ɑ��钼�B�Ȏv���A������Ǝv���e�S���܂������ɓ`����Ă���B �@�����ɕ�V�J�̎莆������B���M�ŏЉ�ł��Ȃ��̂��c�O�����A���߂Č����Ƃ��A���̓��e�̌������Ɣ��͂ɋ������B���q�ɑ��钼�B�Ȏv���A������Ǝv���e�S���܂������ɓ`����Ă���B
�^�������������Z�p���Ȃ����A�͂�����B�`���������e������B
���܃C�́B�����i�o���j�ɂ�B�݂Ȃ��܂��i���낫�j�܂����B�킽��������낱��ł���܂���B
�Ȃ����i���c�j�̂���̂܂ɁB���܂ɂ˂�i���N�j�B�悱����i��U��j���B�������܂����B
�ׂȂڂł��i�������炵�Ă��j�B���肩�Ȃ��B
���ڂ��B�ق�i�G�X�q���ߏ��̒n�� �ɂ́j���܂肨��܂����B
���܂����B�����Ȃ�B�����킯�i�\����j���Ă��܂���B
�͂�ɂȂ�g�B�݂Ȃق����h�i�k�C���j�ɁB���Ă��܂��܂��B�킽�����B������ڂ�������܂���B
�h���i�ǂ����j�͂₭�B���Ă�������B
���˂��B���낽�B���g����ɂ��������܂���B�������������g�݂Ȃ̂�āi���܂�āj�B���܂��܂��B
�͂₭���Ă�������B�͂₭���Ă�������͂₭���Ă�������B�͂₭���Ă�������B
������i�ꐶ�j�̂��݂̂āB����܂���B
�ɂ��i���j���ނ��Ă�B�����݁i�q�݁j�B�Ђ������ނ��Ă킨���݁B���Ă���܂��B
�����i�k�j���ނ��Ă͂����݂���܂��B�݂Ȃ݁i��j���ނ��Ă킨����Ă���܂���B
�������i����j�ɂ킵�������i���₿�j�����Ă���܂��B
����܁i�h���l���C�����̑m���̖��O�j�ɁB�������ɂ킨����Ă���Ă���܂���B
�Ȃɂ��킷��Ă��B����킷��܂���B
������i�ʐ^�j���݂�g�B���������Ă���܂���B�͂₭���Ă�������B������g�����āi�����āj��������B
����̂ւ��܂��āi�Ԏ���҂��āj����܂���B�˂Ă��˂ނ�܂���
�@ |
����p���Ɋւ���]�`�́A�n�ӏ~���̖���w���������x������B����́w���y���x�w���̗��Y�n�x�Ȃǂ͕��w�̈߂��܂Ƃ����|���m�Ɲ�������邪�A�����̈��
�����w�������x�w���e���x�w�����x�������[���B
�@�@�@�@���R�̕�炵686
2022.10.17�@
 �@�@ �@�@
�@
�@ ��^��ƒ� ��^��ƒ�

�r�I��200�{�A�f���t�B�j���[��30�{�A�A�C�X�����h�|�s�[120�{�A���̑���c���B�Ē�̐������܂������A�҂����Ȃ��̍�Ƃ��R�ρB
�����ς܂��čg�t�����ɍs���Ȃ��ẮB
�A�P�r���Ԃ牺�����Ă���̂����ڂɁA���������ꂩ���Ƃł��B
���R�̕�炵685
2022.10.12�@
 �@�@ �@�@
�@
 ������Ƃ������ ������Ƃ������
�����Ǝv����Ȃ��ł����B�t�̒�̈�Ԃ̉Ԃ́u�A�C�X�����h�|�s�[�v�B���̉Ԃ��炩����ɂ́A�����ߐ{�̓~�̊������e������̂ŁA
���i�K�̎菇��K�v�Ƃ���B
�@�@�C�������v����ď������|�b�g�Ɏ������----����͂P�T�Ԃ���10����------��������̗ǂ��ꏊ�ŊǗ�------
�@�@�o�t���o�Ă��������傫���|�b�g�ɐA���ւ���------�X�ɑ傫���Ȃ������ԑ傫���|�b�g�ɐA���ւ���----
�@�@���̃|�b�g�𗠒�ɕ��ׂ�------�ȈՉ���������ĕی삵�Ă��-----�R�����{�ɉԒd�ɒ�A����B
�~�̊Ǘ���
��ԑ�ρB�뉺�ɉ���������̒��A����ł�����������Ȃ���B���C�Ń��b�Z�����Ȃ��牷���܂ł��ǂ蒅���B�g�̂͂�������₦�Ĕ@�J�I�����肪�������ށB�i�����ł��ߑ��j���N�͂�����߂悤�A�����̊Ǘ��͕��S���傫������B
�������A�������͂�߂悤�Ǝv���������킽���A���ƍ̎�̎���������ق��̎�ނ������Ă݂悤�ƒ��������̂����́u�T�������v�B�͂�����܂����Ăт�����
�����B
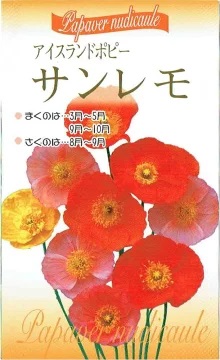 |
��܂̕\�ɂ����������B�@�����H�ԈႢ�����邼�B
�A�C�X�����h�|�s�[�@�T�������i�̔��p�̕i�햼�j
�@�@�܂��̂�----�R���`�T��
�@�@�@�@�@ �@�X���`10��
�@�@�����̂�----�W���`�X��
����ɗ��ɂ�
�u����l��(���т���)�Ƃ��Ă�A����l(�܂��͋�P)�Ƃ͐`��������ɂ������H�̈��l�ŁA�ޏ��̖��ɍ炢�����Ƃ��炱�̖��O������ꂽ�Ƃ����Ă��܂��B�|�s�[�Ƃ������̃A�C�X�����h�|�s�[�ŁA�������邱�Ƃ̂Ȃ��N�₩�ȉԐF�ƕ��ɗh��߂��p�������̏t��A�z�����܂��B���̋����Ƃ���ł͔̍|�͔����āA�g�����Ђ��܂�ɐA���Ă��������B
�v
�u�a���͂ЂȂ����v�B
�����H |
�ʔ̂Ŕ������̂ŁA�̔�����HP���畷�����킹��B
�E�A�C�X�����h�|�s�[�̎�͏H�Ɏ����A�~�z���������̂����̏t�̂R������T���ɊJ�Ԃ��邱�ƁB
�E��܂̕\���ɁA�u�炭�̂͂W������X���v�Ƃ���̂͂�قǂ̊���n�i�V�x���A�A�t�B�������h�̖k�̒n���Ȃǁj�B
�@���̏ꍇ�Ɏ����̂͂R���`�T���B
�E�a�����u�ЂȂ����v�́u�V�x���A�ЂȂ����v�̊ԈႢ�B
�E�ЂȂ����́u�V���[���[�|�s�[�v�̂��ƂŁA�w�������s�����Ă��̐�ɉԂ�����B
�@�Ԋ��̓A�C�X�����h�|�s�[���x���ĂT������U���I���ɂ����āB
�E����l���ƌĂ��̂͏�ɏ������V���[���[�|�s�[�B
 |
�����ĕ��匾���̃����X�^�[�Ɖ������̂ł����B
���������̓��A�̔�������L�`���ƕԎ����͂����B
�u���������ʂ�ł��B���N�̔��p����������܂��v�ƁB
�[�������������A���l���Ă��܂����B
����g�D�ɕ���������͈̂Ղ����B�ł����ꂪ�Όl��������ǂ����낤���B�Ȃ��Ȃ������͂����Ȃ����낤�B
���͓T�^�I�ȓ��{�l�炵���A�ڂ̑O�̐l�ɕ��������ɂ͗E�C������B�����Ɖ䖝�𑱂��āA���鎞���_�̌�����ꂽ�悤�ɔ��ꂵ�Ă��܂����Ƃ�����B�i�ؗE�B���܂�
�A10�N�Ɉ�炢���ȁj
9/24�̋L�^�ɂ���悤�Ɂu���Ȃ��ɂ͐ӔC�����Ȃ��̂ł����I�v�ȂǂƓ{���Ă��܂��B
�����̗����ʒu���l���A��ӂ��B���Ȃ���v���ʂ�ɑ�������قǂ̑�l�ɂȂ�̂͂��ɂȂ邾�낤�B
�Ȃ�Ȃ��˂����ƁB
�@ |
�@�@ �@10��7���@�U���̋C����10������������B�܂�ő��̓~�̒��̂悤���B�~�p�̈ߗނ��茳�ɏo���A �@10��7���@�U���̋C����10������������B�܂�ő��̓~�̒��̂悤���B�~�p�̈ߗނ��茳�ɏo���A
�@�@�@�@�d�C�J�[�y�b�g���R�Z�b�g�A���t�g����~�낵�Ă��ĕ~�����B
 �@
�n���̍g�ʃ����S���Y���̓X�ɏo�Ă����B12��500�~�B�W��������낤�A�A�b�v���p�C�������ȁB �@
�n���̍g�ʃ����S���Y���̓X�ɏo�Ă����B12��500�~�B�W��������낤�A�A�b�v���p�C�������ȁB
�@
���R�̕�炵684
2022.10.7�@�@
 �@�@ �@�@
�@
�@
 �@���{���R���@�j�z���A�J�K�G���@���}�A�J�K�G���@�ǂ����H �@���{���R���@�j�z���A�J�K�G���@���}�A�J�K�G���@�ǂ����H
����4������n�߂��ߐ{�삪�������َ�Ấu�Ȃ͂����T�[�`�J�G���v���A�Ă��߂��Ă��悢��I�Ղɋ߂Â��Ă����B�@�@�@
�@�ߐ{�삪�������ف@���@http://www2.city.nasushiobara.lg.jp/hakubutsukan/�@��
�@�Ȃ͂����T�[�`�J�G���@���@http://www2.city.nasushiobara.lg.jp/hakubutsukan/event/research.html�@��
�����W�̊��Ԃ́@2022.4.1�`11.1�܂ŁB
�P�j �j�z���A�}�K�G��
�Q�j �g�E�L���E�_���}�K�G���@�i�Ȗ،��ɂ̓g�m�T�}�K�G���͂��Ȃ��j
�R�j �A�Y�}�q�L�K�G��
�S�j �E�V�K�G���@
�}�ӂ���Ă��āA��ɏo�邽�ђn�ʂɖڂ��Â炵�A�т�����ƁA���͂̋C�z�Ɏ����Ƃ��炷�B
���܂܂Œm��Ȃ��������Ƃ��������Ă���̂́A�ڂ̑O�̐��E�̉𑜓x���オ���ĐS�������v�����B
 �@�j�z���A�}�K�G���A�g�E�L���E�_���}�K�G���A�E�V�K�G���̐���
���A�g�E�L���E�_���}�K�G������ђ��˂���ڂŒǂ��B���͂���ǂ��p�͌������B�܂�ŔE�҂̂悤�ȃJ�G�������B �@�j�z���A�}�K�G���A�g�E�L���E�_���}�K�G���A�E�V�K�G���̐���
���A�g�E�L���E�_���}�K�G������ђ��˂���ڂŒǂ��B���͂���ǂ��p�͌������B�܂�ŔE�҂̂悤�ȃJ�G�������B
���N�ԁA�J�G���J�G���J�G���ƔO���Ȃ����d��������̂́A�܂�ŃJ�G�����e�[�}��BGM���S�ɗ���Ă���悤���B
�Ȃɂ��둊��͓����̑f�������c�B������Ƃ���ĂĒǂ������A�_�Őg�̂��Ђ�����Ԃ��Ă݂�B�����͂Ȃ炶�ƃJ�G���͊撣��B���Ƃɖ߂낤�Ƃ���B���ː_�o���������܂��A�J�����Ō����u�u���s���v�����ă��c�̒��˂���\�z����B�h���̂��閈�����B
�Ƃ��낪�A���̂X���̖�����V��̃J�G������Ɍ����Ă����B���ꂪ���̎ʐ^�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�����قɂ��₢���킹�A�}�ӂōׂ��������������ʁA����́u�j�z���A�J�K�G���v�Ɣ��������B�w����������A�{���Ƃ��艡��̓m�[�u���A�{�ɂق�̏����̖͗l�������āA�Ȃɂ��{�̉������Ɣ����Ă��ꂢ���B�f�R���e���L���Ă�������A�������͔����I�����W�F�B�Ȃ��Ȃ����킢���B
�悭�������}�A�J�K�G���́A�}�ӂɂ���
�P�j�w���ɂ���2�{�̔畆�������A�ۖ��̌��ŊO���ɋȂ���B
�Q�j�w�Ƙe���̋��̋��ڂ̌��œ����ɋȂ���B�����猩��ƌۖ��̌��ʼn��ɋȂ���B
���̂悤�ɂ������B�j�z���A�J�K�G�������S�̂ɂ��肵�Ă����܂�����ۂ��A�u���}�v�Ɗ������킯�ɔ[���ł���B
(10/3 �ߌ�A���̃��}�A�J�K�G������ɂ͂��߂Č���ꂽ�B�Ȃ�قǃj�z���A�J�K�G���Ƃ͈Ⴄ�B����A�����j
�Q�l�F
�u�Òr��@�^��э��ށ@���̉��v�@�i�����m�ԁv�j
���̋�͔m�Ԉ��i�[��j�ʼnr�܂�Ă���A�����ɂ̓g�m�T�}�K�G�������Ȃ����Ƃ���A���́u����Áv�Ƃ̓g�E�L���E�_���}�K�G���Ƃ��������L�́B
���邢�̓c�`�K�G���i�C�{�K�G���j�Ƃ�����������B �c�`�K�G���͂��₾�ȁB
�ł͐��̃X�^�[�A���s�̖썂�R���̍���u���b�l���Y��v�̃J�G���́A
�@
�@�@����͊��ɐ�������g�m�T�}�K�G���B�����ɂ�����炵���B
������̐���ςȂ̂��낤�A���C�Ɍ����A��яo�Ă���ӂ��̖ڂł�����߂Ă���----��炵�����C�Â��Ă���钇�Ԃ��������B�����̖��m�ɋC�Â�����邱�Ƃ������Ă��@���Ȗ���
�������B
���������J�G���͏�ɑO�i����̂݁B��s�@��E�T�M�Ɠ����ŁA���������ł��Ȃ��B
�J�G�������Ă��ďo�Ă��铚���́u�i�߁I�v�B
���̃J�G�����T�[�`��11.1�܂ŁB�O�ɏo�邱�Ƃ������Ȃ鎞���Ȃ̂ŁA�J�G���̊ώ@������@������邾�낤�B�ώ@���L�ɒNjL����L�^���܂��܂��m���Ȃ��̂ɂȂ�܂��悤�ɁB
�Q�l�ɂ����̂́A
�w���{�̃J�G��48�@�Έ��}�Ӂx�@����M�咘�@�͏o���[�V��
�w����`��J�G���x�Ȃ�ׂĂ݂��----�@�@���������ʐ^�@�������]���@�A���X��
�w���{�̃J�G���x�@�R�k�n���f�B�}��9�@�@���������ʐ^�@���R�����Y���@�R�ƌk�J��
�ق��B
�@�@�@
�@�@�@���R�̕�炵683 2022.10.3�@�@
 �@�@ �@�@
�@
�@ �@���X�̂��܂��܂Ƃ������� �@���X�̂��܂��܂Ƃ�������
���R�̕�炵682
2022.9.28

�@�@�@�@�@�@�@ �@
�@
�@ �@���Ȃ��ɂ͐ӔC�����Ȃ��̂ł����I �@���Ȃ��ɂ͐ӔC�����Ȃ��̂ł����I
�@�@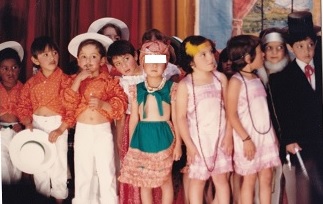 �@���e�����y����A�t���b�p�[����A�^�L�V�[�h���� �@���e�����y����A�t���b�p�[����A�^�L�V�[�h����
�̂�т�ƒx�����H��ۂ��Ă��鉀���̉Ƃɓd�b���������B�̂�肭���ƌ�������鉀���Ɏ��͓{�����A���l�ɐ����r�������ƂȂǂ���܂łȂ��������Ƃ��B
���������ƂɁA�����͎����̗�����ڂ݂āu���Ȃ���A�ӂ�v�C�������݂�����������킹�Ă��Ȃ��悤�������B
�b��40�N�O�ɂ����̂ڂ�B��ẴG�N�A�h���ɏZ��ŁA�����T�̖������n�̗c�t���ɒʂ킹�Ă�������̂��ƁB�T���̂��钩�A���̑��}�o�X�ɏ悹����o���������A���O�̋A��o�X�ɏ���Ă��Ȃ������̂��B����Ă��Ȃ������ǂ��납�A�o�X���̂��̂��A�p�[�g�܂ł���Ă��Ă��Ȃ��B
�ʉ����͂��߂Ăق�̂ӂ����قǂȂ̂ŁA���͂܂����R�ɃR�~���j�P�[�V���������Ȃ��B����������N���܂�̃X�y�C����̌�����Ȃ̂ŁA�v�������Ƃ����R�ɕ\���ł���킯�łȂ������B�ǂ�������A���͂Ȃ��B�v�͂������d���ɏo�����Ă��ė���Ȃ��B
�ƂڂƂڂƐS�����̂悤�ɏd���B������ƔR�������ɔM���B
�܂����ǂ��ǂ��������ɓd�b����B
�u���炟�A�����Ȃ�ł����B�^�]��ɘA��������Ă݂܂��ˁv�B
�d�b�̑O�ő҂��Ă��Ă��A�Ԏ����Ȃ��B�悤�₭1���Ԍ�ɁA
�u�^�]��̉Ƃ܂ŘA��Ă����ꂽ�悤�ł��B�o�X�̒��ł��삳��͖����Ă��āA�^�]��ɂ͌����Ȃ������悤�ł��v
�������Ȃ��^�]�肪�o�X�̉^�s���[�g��Y�ꂽ���H���̕Ԏ����Ȃ������B���S�z�����Đ\����Ȃ��A�̈ꌾ���Ȃ������B���{�Ƃ̎Љ�펯���Ⴄ�ƌ�������܂ł����A���n�ɂ͂���Ȃ�̊��K�Ƃ������̂�����̂��낤���A�����ɂ��̂�т肵���Ή��Ȃ̂ŁA�킽���͓{�����I
�������n�̐V���ɂ́u�s���s���ҁv�̗��������āA���O��N����炩�ɂ���Ă���q�������������������B�����Ύq���̗U���͂܂܂��邱�ƂŁA���܂Ȃ瑟��ړI�̗U�����Ƒ������Ƃ��낾�낤�B�q�������́u�J���͂Ƃ��Ĕ�����v�Ƃ������킳����ь����Ă����B
�O�o�ɂ͕K���ی�҂��t���Y���̂��펯�ŁA����͂���Ȃ�ɑ�ς��������A�O���l�͓��ɑ_���₷���Ƃ������Ă����̂łȂ�����C��t���Ă����̂ɁB
�ߌ�3���A�悤�₭�^�]��ɘA����ċA������ɕ�����������A
�u��������́A�Ƃł��т�H�ׂĂ�����B�o�X�̒��ő҂��Ă�����W���[�X�������Ă��Ă��ꂽ��v�u���̂��ƃo�X�ɏ���đ����Ă��ꂽ�B������ƐS�ׂ������ȁv�B
���������̂܂܂ɂ��Ă����Ȃ��B�̂��ɑ������{�l�̂��߂ɂ��A�����͂�����Ɛ\�����ꂵ�Ȃ��Ƃ����Ȃ��ƍl�������ǂ����B���s�s�Ȃ��Ƃ�����āA�R�c�ł��Ȃ��ł͑��l��������B���C�Ɉ���ĉ����ɓd�b�����Č������̂���L�̃Z���t�B
���̋@��ɉ��������ɗ��āA�������茾�����B
�u���Ȃ��͂����Ɖ��₩�ŁA���{�̂���l�Ɏv�����̂Ɂv�ƁB�ق��Ƃ��āI������O�ł��傤�B
�����A���Ă��Ȃ������ԁA�ꂵ�������B���̂��̂��̂낤�������A�ׂ��P����č��ɂ�������̂ł͂Ȃ����Ƒz�����ċꂵ�������B�����A�ǂ������������Ă��܂��悤�ɁA�����ł���܂��悤�ɁB�������l���Ă����B
�É����q�V���s�̔F�肱�ǂ����Œʉ��o�X�Ɏ��c���ꂽ3�̗c�����M�˕a�Ŏ��S�������̂�����Ă���B���e�͂ǂ�Ȏv���ł��̎������~�߂�
�̂��낤�B
���̏ꍇ�A�낤�����̖�����͓����Ă����B�������̗��e�ɂ͂��̖�����͏����Ă��܂��Ă���̂�����B
����̎����ł́A�c�t���̐l�o�s�����������悤�����A�������ł͂Ȃ��悤�Ɏv���B�؍��ł��łɓ�������Ă���悤�ɁA�l�Ԃ̑̉������m����Z���T�[������A�u�������\�h����V�X�e��������ƕ����Ă��邪�A�������ꂾ���ł͊�Ȃ��B
�Ⴂ����́u�n��q����v�̊������猾���邱�Ƃ́A�u��l�̖ڂ������������قǁA�q���ɑ���댯�͑����v���B
���ۂɁA�q������������������̉āA�����q����̃v�[���V�тłU�Ύ����ق��20�Z���`�̗c���p�v�[���œM�����鎖�����N���Ă���B���͂ɂ͉��l���̗��e���q���̈��S�����Ă����͂��Ȃ̂ɁB�吨������ƐӔC�����U���A���܂��ɒ��ӂ��U���ɂȂ�B
IT�ɂ��T�|�[�g���厖�����A��ԑ�Ȃ̂͐l�Ԃ̑z���͂ƍs������͂��낤�B�l�Ԃ̓E�b�J���~�X�����邱�Ƃ�O��ɍs�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B99.99���C��t���Ă��Ă��A���̌��Ԃ��炷����Ɣ��������Ď������N����B������i�߂�ɁA�b�ɂ���̂͐l�Ԃ��ɂ����Ƙ_���B���s������----�_���̏o���_�͏�B��̏�ɘ_����g�ݗ��Ă邱�Ƃ��厖���ƍl����B
�@�@ �@��������݂� �@��������݂�
�@�@�@�@���R�̕�炵681
2022.9.24
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@
�@
 ���ڂ�(���ۉF���X�e�[�V�����j��ǂ������� ���ڂ�(���ۉF���X�e�[�V�����j��ǂ�������
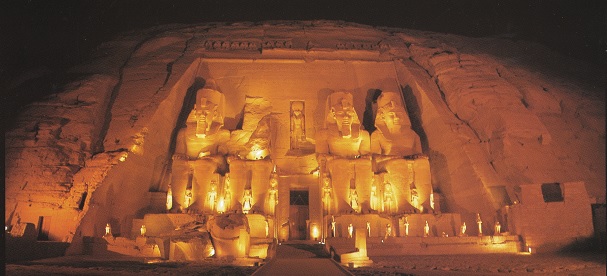 �A�u�V���x���_�a �A�u�V���x���_�a
������͐V���������19�����̉��E�����Z�X2���B��_�a�͑��z�_���[���A���_�a�͏��_�n�g�z�����Ր_�Ƃ��Ă���B
�@�@�u����A�l�H�q���ł��Ȃ��v
�@�@�u�l�H�q�������ł���---�v�u�l�H�q�����Ĕ�Ԃ́A����Ă���́H�v
�@�@�u�l�H�q�����A�ق�ق猩�āA���ɗ���Ă���----�v�u���ꂩ��----�v�u�������v
�G�W�v�g�ƃX�[�_���̍����ɋ߂���Ձu�A�u�V���x���_�a�v�̑O�ɔ�����ꂽ�������̃x���`�ɁA�܂�ʼn��̃}�O���̂悤�ɃS���S����������Ă��铯�s�̊F����B
�Â��Ȃ菉�߂�������߂Ȃ���A���ꂼ�ꂪ�v���v���ɉ����Ԃ₢�Ă���B
�A�u�V���x���_�a�̔w��̎R���猻��A�i�Z���̏���сA�������l�H�q���̋L�����~�߂悤�Ƃ��Ă����B
�����E�Ɍ�����ƁA�n���k�r�A�̐l�������������y�ɂ̂��ă_���X���I���Ă���Ă���B���{�l�̂������肩���A�ނ�Ǝ����荇���ėx�苶���Ă���B��������ƃi�Z���̐��ʂ��A�[�Ă��F��ттėh��Ă����B
��u���ςݏd�Ȃ���3���Ԃ��A����܂Ōo���������Ƃ��Ȃ��قǏd��������ꂽ�A���̖邾�����B
�@ �@�k�r�A�l�̗x��@ �@�k�r�A�l�̗x��@
�k�r�A�l�͎�悪��p�B�r�[�Y��l�`����悤�Ƃ��ċ߂Â��ė���B
�u����ɂ��́A���邾���`����Ȃ��`�v�ƌ����Ȃ���B����H�@����Ȍ��t��u���y�Y�ɂ����̂́H
 ���������A�F�l�ɋ����Ă������ �u���ڂ�(���ۉF���X�e�[�V�����j��s���[�g�v�̒ǂ����������Ă����B ���������A�F�l�ɋ����Ă������ �u���ڂ�(���ۉF���X�e�[�V�����j��s���[�g�v�̒ǂ����������Ă����B
�v���l�^���E���̂���Ȋw�فE�q�~�Ȋw�Z���^�[HP�@�ihttps://kurakagaku.jp/tokusyu/iss/index.html�j��
�Ȗ،��ł̊ϑ��\��ɂ��ƁA
�@�@ 9
�� 16 ���@ 9
�� 16 ���@
19 �� 3 �����됼�쐼�̒Ⴂ��Ō����n�߁C 19 �� 6 ������ �k���̒����炢�̍����̋�( 47.5 ��)�ł������Ȃ�A
19 �� 9 ������k���̒��֓��������Ȃ��Ȃ�B
�@�@ �@
9 �� 17 �� �@
9 �� 17 ��
18 �� 14 ������쐼�̒Ⴂ��Ō����n�߁C 18 �� 18 ������ �k���̓��̐^�゠����( 89.4 ��)�ł������Ȃ�A 18
�� 21 ������k���̒��֓��������Ȃ��Ȃ�B
�f�b�L�ɐw���F���X�e�[�V�����̋O�Ղ����悤�ƁA��ꂪ���̋�߂邱�Ɛ����B�т̖ɂ��������Č����Ȃ��B���܂��ɖ����N���Ă��Ă��܂����B
�v���o�̃V�[���Əd�˂Ă݂�B �i2013�N�U���@���_�𗯎�Ԃɒu���āA�G�W�v�g�֏o�������j
���R�̕�炵680
2022.9.19
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@
 �H���������̂Ȃ� �H���������̂Ȃ�
�v���Ԃ�Ɂu�ڂ��炤�낱�v���������B��������T���Ă�����ӂ𑖂��肽���C�����B
���܂܂Łu�H���������v�Ɋւ��Ă͂����肵���������`��T�������Ƃ��Ȃ��������A�u���40�����炢�v�ƋL�����Ă����悤�Ɏv���B������u�������K�v�Ƃ���H����40�����������Ő��Y�ł��Ȃ��ȁv�Ƃ����y�������ɏI����Ă����B�L���ɂ͍��������ƂɂȂ邪�A���̗L���͂܂����������Ă���Ԃ͋N���Ȃ����낤---�Ɛ��퉻�o�C�A�X�������āB
�����ȂȂ̂��B�����Ȃ�̃A���e�i�𗧂āA����Ɉ�������������������W���W���Ƌ������L���Ă����̂������̗�ŁA�A���e�i�Ɉ������������Č��ɂ���ẮA�{�_���痣�ꂽ�ꏊ�Ɏ�����A��Ă������Ƃ��������B
�Ƃ��낪���[���ł̗F�l�̏����ꂽ�L���ɂ������ɐG�����ꐄ�E���ꂽ�{��ǂB�����B
�@�@�x���o�������H�̖����������Ă����邾�����B
�@�@�@�@�w���{���Q����I�x�@���E�H�Ɗ�@�̐^���@�R����m���@���~�Ɋ�
�H���������Ƃ́F�i�J�����[�x�[�X�Łj
���ݍ����Ő��Y����Ă���H�����A�A���i���܂ߏ���Ă���H���Ŋ��������́v�Ƃ������Ƃ������B
�@�E���ꂪ�傫���ꍇ----���݂̂悤�ȗA���H�i�������O�H�̎���́A���̊����͉�����B
�@�E���ꂪ�������ꍇ----���Ƃ��Α���E����̋Q��̎���́A�C�O����H���������Ă��Ȃ��̂ŁA��������100���ɂȂ����B�i
�܂������̕s����ԁj
�@�E�L���ɃV�[���[�����j��ėA���ł����A�H�Ɗ�@���N�����ꍇ�́A�������Y�ʂƍ�������ʂ͓����Ȃ̂ŁA��������100���ɂȂ�B�i������
�܂������̕s����Ԃ͓���----�Q���ԂɂȂ�j
����H
��������100���Ƃ����̂́A�����S�����Q���邱�ƂȂ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ������悤���B�P�Ɏ�������������A�����̐H��������ɂ���킯�ł͂Ȃ��āA�w��ɂ���
���E���_�Ƃ̍\���A�A���̌����ɑ傢�ɉe�������Ƃ������Ƃ炵���B
�@�@�@�H�����S�ۏ၁�C�O����A���ł��Ȃ��Ȃ������ɁA�����ŐH���Y���āu�����̐����v��
�@�@�@�ێ��ł��邩�����ł���B
���͔_�Ƃ̐��܂�B���ɔ_�Ɛ���ɗx�炳�ꂽ���ゾ�B����̕ω��ƂƂ��Ɍ�������������āA���ݍ����̔_�n�ʐς́A�풆���600���w�N�^�[���ɑ���450���w�N�^�[���B�l����7200���l����A�P��2�疜�O��ɑ������Ƃ����̂ɁB
��H�ɂȂ鍒�����Y�p�̔_�n�����炷�悤�Ȑ�����{�s���Ă��鍑�͓��{�̂ق��ɂȂ��B�Ȃ�����Ȃ˂��ꂪ�N�����̂��A���ꂩ�炶������l���Ă�
�悤�B
�ڎ������ǂ��Ă݂�ƁA�H���Ƃ͉����A�f�Ղ��猩���鐢�E�̐H������A�^�����䂪�߂�ꂽ���{�̔_�ƁA�������̂܂₩���A�����\�ȓ��{�̐��c�_�ƁA�_���g���C�A���O��
�iJA�_���A�_�ё��c���A�_�ѐ��Y�ȁj�A�H�Ɗ�@���̕s�s���Ȑ^���A���{���Q����---�Ƒ����Ă���B
����JA�̌o�ϊ����Ɣ_������ɂ��ďڂ����B�L���ɂ������@��z�肵�ĂȂ��A���������ď������Ȃ���Ă��Ȃ��Ƃ̂��ƁB
�܂��������̒ʂ肾�B
���_�̐��Ƃ����̕����A������Ă��鐿���l�ɓc��ڂ̊Ǘ���C���Ă���Ȃ̂ŁA�����̓��e�ɂ������ɋ���������B�ǂݐi�ނ̂��y���݂����ǁA�|���B�m�邱�Ƃ͊��������Ƃ����m���Ă��܂����オ�|���B
�@���ꂩ�玕��҂ցB�@���ꂪ���̎��̗L���B
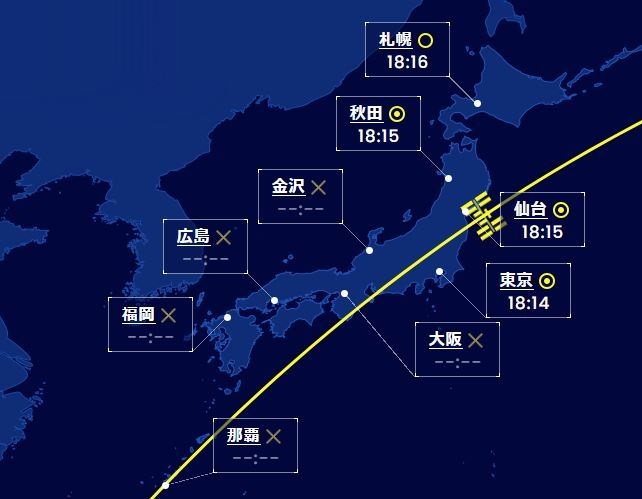
���ڂ�(���ۉF���X�e�[�V�����j��s���[�g
�P�U����17���Ƀ`�����X�������Ă���B�@����܂��悤�ɁB
���R�̕�炵679
2022.9.15
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@
�@
 �ŋߏZ��n�ŋN���Ă��邱�� �ŋߏZ��n�ŋN���Ă��邱��
������ɏZ�ݎn�߂�����A���͂͂��ꂼ��̊y���݂������ĕ�炷�O������҂��قƂ�ǂ������B�F�����ő��ˁA����҂̗��z�I���f���ƌ����邭�炢���C�����ς��������B
�Ȃ�������Ȑ����������Ƒ����Ǝv������ł����B
���ꂩ��20�N�߂��o�B����Ȃ�ɑ̗͂�C�͂�������N����}���A��X���ӂ��ߖ��������l��������悤�ɂȂ��Ă����B
��������ɂȂ�Ȃ��悤�Ԃ̉^�]�͕K�������A�F�m�@�\�����ɗ����Ă��܂��l���o�Ă����B�g�̂̂ǂ����ɏ�肪����@�\�I�ɉ^�]���ł��Ȃ��Ȃ����l������B
�E�F�l�v�w�����̂V���A�q���Ƒ��Ɠ�������ƒ��N�Z�ߐ{�𗣂�Ď�s���Ɉ����z�����Ă��܂����B����o�����ߗZ���͕��G�ȋC���Ɋׂ�B20�N
���̂���������ĕ�炵�Ă����̂ɁA����ɂȂ��Ă���̓��������܂������̂��B����ɂ��Ă����̎���ɐe���т��Ăъ鑧�q�v�w����
�邱�Ƃ���Ԃׂ��Ȃ̂��낤�B
�E����������邽�߂ɁA�v�����ŕ�炵�Ă������A�g�̕s�@�ӂɂȂ��ĕʋ����Ă����Ȃ̂Ƃ���A�����P�[�X�B
�E����������������邽�߂ɁA�Ȃ����ŕ�炵�Ă������A�a�ɓ|��ʋ������v�̂Ƃ���A�����P�[�X�B
����ɁA
�E��N���}���������A�v��S������l�ɂȂ�����e�Ɠ������n�߂��P�[�X�B
�E�N�V�������e�̐g�̏�ڂ̓�����ɂ��āA�}���呁���ސE���ē����ɓ��ݐ낤�Ƃ��Ă��鑧�q�B
���̓�̗�̎q���́A����������̔N��܂Ŗ����̂܂܉߂����Ă���B
�@�@�@�i�j��25.7���A����16.4���c���U�������@�@2021�N���q���Љ������)
�@�@�@�@�u���U�������v�͒��������_�ō���ꐶ�U�������Ȃ��ł��낤�l�̊����ŁA
�@�@�@�@�i���U��ʂ��Ė����ł���l�̊������������̂ł͂���܂���B
�@�@�@�@�@50�Ŗ����̐l�́A��������������\�肪�Ȃ��ƍl�����Ă���悤�ł��B�j
�e�̉ƂɏZ�݁A�ƌv�̂��镔���S���A�����I�ɂ͐e�̕s���Y�⓮�Y�𑊑�����B�e�̉��̓���ʂ�Ȃ��Ƃ����Ȃ����A�q�����g�̘V����͐摗�肵�Ă�����̂́A�o���ǂ��Ƃ����ɂ�������B
�������e�q�Ƃ͌���������Ƃ��N���邾�낤�B
�Ď��߂��e�ɂ��������т�q�ǂ�������B�M�����u���ɂ͂܂�q�ǂ��Ɏ���Ă��V�ꂪ���āA�q�ǂ����e���тƌ𗬂������Ȃ��P�[�X������B
�q�ǂ�����ɂƂ��Ă��A���̓��{�ŁA�����̕�炵�𗧂ĂĂ������Ƃ͓�����낤�B
�킪�g��U��Ԃ��Ă݂��B��������ɁA���e����ɂ�����ς���]�T�����������Ƃ����ƁA�����ł��Ȃ��B��Ƃ肪�������Ƃ��Ă��A�����̊y���݂�D�悵�Ă����L��������B
����Ȃɕ֗��ȎЉ�ɂȂ��āA�e�q���q�����i�͂������邪�A�p���ē���Ȃ����̂��낤���B�֗��ɂȂ����Љ����肠�����l�Ԃ��A���͈�Ԃ��֗̕��������ė]���Ă���悤�ȋC������B
�N����d�˂Ȃ��ƌ����Ȃ��i�F������B������l���̖��킢�Ɗ���肽�����A����ɂ��Ă������Z������B
�@�@�@* �@�q�̋���ĉ����߉��̖@�t����
�@�@ �@䪉ׁ@�Ă̗J����Y��悤 �@䪉ׁ@�Ă̗J����Y��悤
���R�̕�炵678
2022.9.9�@�d�z�̐ߋ�@���݂������������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@
�@
�@
 ����Ƌ��Ă�������@����H�ׂȂ��� ����Ƌ��Ă�������@����H�ׂȂ���
 �t�B�b�V�����[�X�^�[ �t�B�b�V�����[�X�^�[
���܂܂Ŏg���Ă����̂�IH�R�����t���̃O�����������B�ȕւŏꏊ�����Ȃ������Ǝn������ρB���̖��ɂ܂݂ꂽ�M���A�����ƈ����o���ăV���N�Ő�----���܂ɏ��ɂ��ڂ���A�V���N�̓M�g�M�g�ɂȂ�
��B�������B
�v�����Ĕ������̂����̃t�B�b�V�����[�X�^�[�B�M�ɐ�������Ƃ���܂ł͓��������A�g�������Ƃ̑|���̎�Ԃ��������ɏȂ���B
�w�̋����g�̂ɂ����͕̂������Ă��Ă���������B�����āu�^���A�����v���Ă��Ă݂��B�ϋ������܂�D���ł͂Ȃ����_���A���傤���`�������Ղ肩����
�Ă��A�W���u���������v�ƌ����ĐH�ׂ�悤�ɂȂ����B�ǂ��ƁB
�����̂����߂���Ă����̂͂��̑傫���B���낤���ăV���N���Ɏd�����邪�A���̕��傫��������p���g���[�̒I�Ɉ����z�������邱�ƂɂȂ����B���ɐ����g��Ȃ����Ȃ̂ŁA����ŋ��Ă����͉����B
���āA���͏H�����̏o�Ԃ��B�M�q�̎����o��邩�ȁB
�@ �܂��n��Ă��܂����@�����3�L�����炢�@-----�����֊}������������Ă���
�܂��n��Ă��܂����@�����3�L�����炢�@-----�����֊}������������Ă���
 
��������n�ꎞ�ԁB3�L�����炢���邩�B�����Ⓚ�ɂ͖��t�����A������l�ɂ͕����Ă��܂����B�ǂ����悤���B
�u�n��ɗ��āA�n���������S���グ�邩��v�ƌ����Ă��~�����l�͂������Ȃ��B
�����֒���
��F�l������Ă����B�Ȃ�Ƃ����^�C�~���O�I�@�傫�ȂԂǂ����R�[���y�Y�Ɏ����Ă��Ă��ꂽ�B���A�ꍇ���̗F�l�̔��Ŋn�ꂽ���̂炵���B�ߐ{�̎R�̎R�[������肮���Ǝ��n��������Ă���B�܂�Ń��[���b�g�B������Ŋ������B
�@�@�@�@�@�i���̉w�̂��Ղ肭���łȂ�Ɓu�u���[�x���[�v�������������Ƃ��������B
�@�@�@�@�@�@���l�̎��͂�������ƌ����āu�g�}�g�v�ɑւ��Ă�������B������ǂ��Ɓj
�����������̂Ԃǂ��́A�t�̎R��͂������炾�Ƃ̂��ƁB�t�̎R���H�̂Ԃǂ��ɉ������B�}�������̂悤���B
���܂��ɂ��̋��F�́A��̃u���[�x���[��S���������A��ɂȂ����B������ɂƂ��Ă�������ɂƂ��Ă��u�}�������v�ŁA�o���ɂ�܂�B
�@�@�@���R�̕�炵677 2022.9.4
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@
�@
�@
 ����ɐ�����ςȃ����@�@�����S���i�O����j�@�S�C�������� ����ɐ�����ςȃ����@�@�����S���i�O����j�@�S�C��������
 |
���O�͑�p���Ӗ�����Ì�̍���������B���{���Y�̓S�C�����ƈ���āA�摜�Ɍ�����悤�ɗt���ג����B
����Ă��̖��O���o���Ă����l�͏��Ȃ��āA
�u���̌������ŗw����@���₱�̉Y�M�ɔ��������ā�̍�����v�B
���������Ƒ�̕������Ă��炦��B
���̃����Ɠ��{�S�C�������������킹���̂��u�V�S�C�����v�B
�t�̂͂��߁A�ג����o�t���̂����������Ǝv���ƁA�~�J�̎����ƍ������Ȃ����z���A���~�߂����炱��ȂɉԂ��炩����قǐ����������B
�����炩�A�Ԃɂ��܂肠�肪���݂������āA
�u�ז��I�v�ƌ����Ȃ��������������邱�Ƃ�����B
�g�n���̃������A���k�암�܂Ŗk�i���ɐB���Ă���̂́A���g���̂������B���̂����k�C���ł������邩������Ȃ��B
����ǂ����낤���B�k�C���Ɩ{�B�̊Ԃɂ���Ìy�C�����A�M���ނⒹ�ޕ��z�̋��E���ɂȂ��Ă���i�u���L�X�g�����j����A�ĊO�X�~�܂肩������Ȃ��B�킟���A�ʔ����B
�����͔����V���E���C�M�N�B
����܂������č��N�͔����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B |
�Ƃ��낪���̃����ɂ���_�������āA�납�炠���Ƃ����ԂɎp���������Ƃ�����B�����́u�A���Q�v�ŁA�E�B���X�ɂ���邩��Ƃ����l������B
�뒆�ɍL����----���̎����̂��ł₩���͑f���炵��----�Ƃ��낪���ꂢ�����ς�A���@�̂ق����ş��������̂悤�ɁA���Ȃ��Ȃ�B
��̐��͈�̉ԂŐ������A���ꂪ���ɏ���Ĕ�юU���Ă����A�������ł��������܂Ɋ�����킹����悤�ȏꏊ�ɒ��n������A���̏�Ő��͂��L����B
�������A���̓y�n�ł̔ɐB���Ԃ�5�N�قǂƁA�ɐB------���ł̖������[�v���J��Ԃ��Ă���悤���B���̒�ł̔ɐB�́A�o���Ă�����荡�N�łR��ڂ��B
���R�̕�炵676
2022.8.30
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@
�@
 �X�|�b�g�N�����ڂŌ��Ȃ���
�@�Ȃ�ƑA�܂����A �L�͂����Ȃ��B �X�|�b�g�N�����ڂŌ��Ȃ���
�@�Ȃ�ƑA�܂����A �L�͂����Ȃ��B

�����̎d���́G
���t�A�W�T�C�̙���B����̑傫���Ȃ�߂������t�A�W�T�C�̔������ς܂����B��̒f�̗���i�߂�B�ׂ��}�͌���ŁA�J��������Ȃ��悤�����̒��ɒu���Ă����B�����ɂ��肢���Ă���{�E�̎d�����I�������A���̌�n���̃g���b�N�ɕ֏悵�čڂ��Ă��炤�\��B�t���ς͏W�߂ăS�~�܂ɓ���ĔR����S�~�ɏo���B���R�̂��̂����R�ɕԂ��Ȃ����ƂɎߑR�Ƃ��Ȃ����̂����邪�A�������Ȃ��B
���V���������̂ɁA��������ē��̓V�����[�̌�̂悤�Ɂu�������ԁv�ɂȂ��ĉ��𐁂������B�����Ȃ������т����z���������ڂɓ����Ă���ڂ���ڂ���B�܂��V�����[���B
�ʐ^�̍��[�ɂԂ牺�����Ă���̂́A�C�[�X�^�[���ɒ������Ƃ��A���}�̃��C�̑���Ɏ�ɂ����Ă�������L�̃l�b�N���X�B���̂��ƁA�^�q�`���̖��Y���^��̂��X�Łu3�疜�~�v�̍��^��l�b�N���X���������A����������肪�����B
�C�[�X�^�[���ւ̓�����}�^�x�����ۋ�`�́A��čŒ��̊����H�������Ă���B�X�y�[�X�V���g���ً̋}�����p��NASA�����������炵���ĂƂĂ��Ȃ������B
��`�ŌW���ƁA
�u�F��������Ȃɒx���������邩��A��X���[��J�����Ă����B�v
�u����͂��C�̓łɁB�ł���s�@���x����������Ȃ́B��납���s�@�������悩�������Ȃ��H�v
------�Ȃ�Ă��n���ȉ�b�����킵���̂��v���o���B�i2014�N�P���j
�@�@�v���o�����ς��̊L�̃l�b�N���X�Ȃ̂��B
�@ �@�X�|�b�g�N�ƒ��ǂ��Ȃ����������͂����ɁB �@�X�|�b�g�N�ƒ��ǂ��Ȃ����������͂����ɁB
�@�@ [���T�C�N��
���������ۂ�----�����Ȗ��O�̃{�����e�B�A]
���R�̕�炵582 2021.4.2
���R�̕�炵675
2022.8.25
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@
�@
 �@�p�̎��̂��肭����ĉ_�̕�@----���̉ē����_�����邱�Ƃ����Ȃ����� �@�p�̎��̂��肭����ĉ_�̕�@----���̉ē����_�����邱�Ƃ����Ȃ�����
�@ �@�p�̎��@ �@�p�̎��@
���a20�N����30�N��̂��ƁB���̖p�̖̑傫�ȗt���ςɁA�ɂ���߂��i���ɂ���ł͂Ȃ��j����ŁA�c��ڂœ������e�̂Ƃ���֓͂��Ă����B���e�́A���𗬂��ׂ���Ŏ��A�V�C�^�P�╙����g�����ύ�
�������ɁA����т���������Ă����ȁB�{�͎����Ă��Ȃ���������A���Ă��Ȃǂ�����������B���̍��̗��e�́A���̎����̔����قǂ̔N������Ȃ��B�͂�邱���܂ŗ������̂��B
���_���A�J�ɔG���傫�ȗt���ς����Ȃ���Ԃ₢�Ă���B
�p�t���X�Ɏg����悤�ɁA�p�̗t�ɂ͎E�ۍ�p������B�����R�n�ɂ�����Ƃɂ́A���̖p�̖͖��������̂ŁA���̖�����ڂ����m��Ȃ��B���ׂ�f���C�Ȃǂ̖�Ƃ��ė��p���ꂽ�Ƃ��������A�`��ɕ����Ă����悩�����B
�@�@�ʎ��͑܉ʁB��R�̑܂̏W�܂�B�܂̒��Ɏ�q�������Ă��āA���������H���i�ނƕ��ꗎ����B
�@ �@����̂͂��܂� �@����̂͂��܂�
���N�̏H�̒�̙���̗\�肪�X���X���ƁA��N�ɔ�ׂĂR�T�ԑO�|���ɂȂ�A���̕������B���S�������Ƃ𑁂��n�߂Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ����B��������
����5�N�قǂ́A�\������ł��鎞������3�T�Ԓx���̂�������O�������̂ŁA���N�́u�ł͂R�T�ԑ�������\�悤�v�Ɨ��ǂ݂������Ƃ���n�܂����~�X�B
������͂����v�����炵���B�u�����R�T�Ԓx��Ă��Đ\����Ȃ�����A���N�����˗������s�b�^���ɍ�Ƃ��Ă����悤�v�ƂˁB
�v�f�Ǝv�����d�Ȃ��Ă���Ȏ��ԂɊׂ����̂��B
����B�������������Ă���8-9���ɂ����Ē�̙���ȂǁA����B
�������u�ׂ�S����l�Ԃ́A�S���Ȃ��l�Ԃ���قǍK���Ȑl�Ԃ��v�ƍ���Ă{�ɂ������B�A���u�̊i���炵���B�����ɂ��݂ɂȂ�Ȃ��悤�A��������I���悢��{���̍�Ƃ̎n�܂�B
���R�̕�炵674
2022.8.20
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@
�@
 ���䒉�Y����̑�l�̏W�@�@ ���䒉�Y����̑�l�̏W�@�@
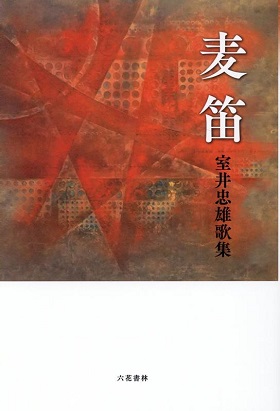 |
���肪�������Ƃɂ��钩�A�|�X�g�̒��Ɂu�ޒ�{�v�Ƃ��Ēu����Ă������B�F�l�̎��䒉�Y����l�̏W���㈲�Ȃ������̂��B
����܂ł̂悤�ɁA�\���G�͑��`���p�ƁE���������̍�i�B�@�@�@
�M�������[�́A[ �������n�E�@Art Works Ken]�@�����߂��ɂ���B
�܂������ɐڂ������Ƃ͂Ȃ����A��ނ͓y�⍻��n�Ȃǂƕ����Ă���BHP�ɂ́A�u���R�ɂ���s�v�c�ɐG�ꂽ�̂��n��̂��������v�Ƃ��������A���̎v����Ɠ��̕��@�ŕ\������Ă��āA���邽�тɂ��̐F��`�ɖ�������B
���̂̂��N���Ă���̂́A���y�␅��A����������Ă��ꂽ���܂��܂Ȏ��R�Ƃ̑Θb�ƁA�����̐��_�����������@���Ă݂悤�Ƃ��Ƃ����v���B
�Z�̈Ӗ�����͉̂����낤���B��䶗��}�H
�������͓�\��̂���A���R����̊G�t�E���J�쓙���̍���
�u���ѐ}�����v�ɖ�������A��Ƃ��u���ꂽ�Ƃ������B
�@�@�@�M�������[�̎��͂ɂ́A�ԏ��т��L�����Ă���B |
���䒉�Y����̂���܂ł̒���́A���̏W�w�V�g�̕����܂��x�A���̏W�w���̗��ʐM�x�A��O�̏W�w�N���オ�菬�@�t�x�B�����Ă��́w���J�x����l�̏W�B
���䂳��͂��̏H�̏��߂ɂ͌Ê���}������B
����邩�A���邢�͒����Ȃ����B�̂��ǂ��ω����Ă����̂��A�y���݂��B
�ޒ�{��������ɂ́A���炩�̊��z�������肵�Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�ǂނ̂͊y������Ƃ����A���z���܂Ƃ߂�̂͊y������Ƃł͂Ȃ��B
����Ⴕ�ď������莆���A����B���̏W�w���J�x��ǂ�� >
�@�@�@���������Ȃ��Ƃ��Ȃ��炠����ʂĂ�B�����Ɠ��̒����J�I�X�ȂB
���R�̕�炵673
2022.8.15
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �@ ������ō炢�Ă���̂� �@ ������ō炢�Ă���̂�
��4���B�z�g�g�M�X�����͂��߂�B�钆�����ς����Ă����̂ɁA�������܂����R�I���M�̐��������Ă���B�����ŃK�r�`���E�i�`�����j�����������B�L�W���ЂƐ��B�V�W���E�J���͍����͉��o�����炵���B�q���h���A���Ȃ��Ă�낵���B
�@
�@���@�J�b�R�A�U�~�@�@�@�E�@�n�i�X�x���q���@��������}����ő��₵���B�@��F�̎�荇�킹�͂ǂ��H
 �@�t�E�`���E�\�E�@�������@ �@�t�E�`���E�\�E�@�������@
�A�����J�t�E�`���E�\�E�Ƃ��Ă�Ă���Ƃ���A�O����B�Ƃ�ł��Ȃ������B�N�ɓG�ΐS�������Ă���̂��낤���A�s�̃C�K�C�K�����āB�݂邩��ɒɂ����B���{�̐A���́A�݂��ɕ��t�����Ȃ��琶�����Ă���B�����֊O���킪����Ă��Ă��܂��C��ɓK�������Ƃ��́A�ǂ��ɂ�����ł��Ȃ��قǂ̔ɐB�͂������邱�Ƃ������B���̃t�E�`���E�\�E�������B
 �@ �@
�u���[�x���[���̂�߂����B�F�l�m�l�ɔz���Ă������ł��Ȃ��قǂ��B�Ⓚ�ɂ͖��t�Ȃ̂ŁA�[���[������Ă݂����A������̂��\���݂����Ɏd�オ�����B�炲�Ǝg���A�h���Ȃ�Ă��Ƃ����Ă��Ȃ�����B��Ɉ�ԉh�{��������̂ˁB
�S�肪�����āA��C���������܂��ł��Ȃ������B���ɂ͕ς�肪�Ȃ��Ǝv�����Ƃɂ��悤�A
���R�̕�炵672
2022.8.10
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
 ������Z������\�ܓ��@�r�ݐl���� ������Z������\�ܓ��@�r�ݐl����
 ����͉��ł��傤�@�@��Ë��R���o�g�̂��ڂ���i���ڂ܂�j ����͉��ł��傤�@�@��Ë��R���o�g�̂��ڂ���i���ڂ܂�j
 |
QR�R�[�h�ł͂���܂���
�J�[�����O�X�g�[���ł�����܂���B
�w�\�V�ŐQ�Ă���L�ł͂���܂���B
UFO�ł�����܂���B����͂��ڂ���B
��Ö��Y�̂��ڂ���B
�n��U���̎菕������
�C���[�W�L�����N�^�[�ɂȂ��Ă��邩�ڂ���
�@�@�@----���O�́@���ڂ܂�B |
����ȂɑN�₩�ȃI�����W�F�̂��ڂ�����������Ƃ�����܂���B���ƂȂ����Ă���s�����̂ɂƂ�ł��Ȃ��͂�����܂����B�摜�ɂ���܂�Ȃ��̕����́u�w�\�v�B
���a15�Z���`�̑傫�ȃf�x�\�I
���R���͕������̉���Òn������S�ɂ���A��Òn���̐��Ɉʒu���A�V�����ƌ�����ڂ��鎩�R�L���Ȓ��B
��i�̔鋫�H���̑������́A2011�N�V���̐V���E�������J�ɂ���Ĕ�Q���s�ʂƂȂ������A���̏H10��1���S���J�ʂ������悤�ł��B
���S�A�B��S�̉���Ƃ��ẮA�����͂��Џo���������Ƃ���B�ʂ����ăR���i�̏H�͂ǂ̂悤�ȏH�ɂȂ�̂��B
�@�@
�@�@�ό����T�C�g�@�@ https://www.town.kaneyama.fukushima.jp/site/kanko/
�@�@���R���ό����Y����@http://kaneyama-kankou.ne.jp/�@
�����s���ɏZ�݁A�ق��10�L����������Ă��Ȃ��F�l�ƒ��ډ�܂���B�����������J�[�h�𑗂�����A�i�{�[���ɂ�������l�܂�����������Ă����̂ł��B
�g�E�����R�V�A�X�C�J�A�W���K�C���A�ʂ˂��A�����Ă��̂��ڂ���B�ޏ��̔��ł����܂ň炿�܂����B
���肪�������Ƃł��B
��ԑ傫��������o���Đ�A���ꂩ�炿�傱���Ɓu����������----���ڂ���O���v�ɏo�����܂��B
�ǂ������Řb�����݁A���傱���Ƃōς܂Ȃ��Ƃ��낪�~�\�����ǁB�������قŁu�H�����v�ƌĂԂ̂ł����B
�����������݂̂͂�ȂŐH�ׂ悤�I
 �@�����̎��n�@3.8�s �@�����̎��n�@3.8�s
���R�̕�炵671 2022.8.4
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@
�@ �W�J�o�`�̋t�P�@�@���䂢�ɂ� �W�J�o�`�̋t�P�@�@���䂢�ɂ�  �@ �@
�u�p�`�b�v�Ɖ��������B�E�������̔����ȕ������W�J�o�`���h�������������B
�������������B�V�����[�̌�́A�����ς�Ɗ��������ʃp�W���}�ɒ��ւ���B
����𒎂̒m�点�Ƃ����̂�������Ȃ��B�����͏㒅���璅�n�߂�̂ɁA�E��ɏ㒅���������܂܁A�����̓Y�{�����܂��������B
�ǂ�������荞�̂��낤�B����������ƃW�J�o�`���������Ɏ~�܂��āA���܂ɂ��h�����Ƃ��Ă���ł͂Ȃ����B
����������Ɏ����Ă����p�W���}�̏㒅�Łu�o�V�b�v�ƒ@���̂߂��B
�@�@�@�@�@�@�Z�~���{�H�I�� �� ���������I���Z--------�@������鑫������----�B
�����ς�����ď��ɓ]�������W�J�o�`�́A�g��k�킹�ĂЂ̏�Ԃ̂悤�Ɍ������B
�@�@����������Ƃ�������������āH�@
�@�@�@�@���₢��B���N �n�`�Ɏh�����̂͂���ŎO��ڂȂ̂�����I�i���ꂼ��ʂ̃n�`�����ǁj
���Ẵp�W���}�����ǐj���c���Ă��邩������Ȃ��B�����܂����B
���������ĒE�����p�W���}������ɓ���悤�Ƃ�����A�u�p�`�b�v�B
�m�������S�����t�P�҂����̌�ǂ��֍s�����̂��A����@�̉����̂����Ă݂Ă�����������Ȃ��B
�@ �@ �@
�@�@�@�@�R�I�j�����@�@ �ނ����������Ȃ�
�@ �@�����I�@�@�@�@�@�Q�l�@�w�E�\�����������̂����x�@�X�������@���c�_��ďC�@�Ώ��[�� �@�����I�@�@�@�@�@�Q�l�@�w�E�\�����������̂����x�@�X�������@���c�_��ďC�@�Ώ��[��
�T�D�U���̍Ő����ɔ�ׂď��Ȃ��Ȃ����Ƃ������̂́A�z�g�g�M�X�����Ȃ��獂������ь����Ă���B��ȑ����̃E�O�C�X�̐��́A�����ΎG�ؗт��畷�����Ă��Ă���̂ɁB���܂��ɑ�����������Ȃ��悤���B
����钹�̓J�b�R�E�Ȃ̒��Ԃ����ł͂Ȃ����A���S�̂ł͂P���ɉ߂��Ȃ��B�J�b�R�E�Ȃ̒��́A�S�O���������ƌ����Ă���B���������J�b�R�E
�Ȃ̒��Ɍ��т��̂��낤�B
�����͔������������B���˂đ���闝�R��m�肽���������A�V�����o�ꂵ���B
�u�J�b�R�E�Ȃ̒��̂킽��̋����͒����̂ŁA�����ɗ������Ƃ��ł���悤�A�����Ɓv�ƁB�������ɃJ�b�R�E�̓��[���V�A�嗤�ƃA�t���J�嗤�ɐ������A���{�ɂ�4������5���ɂ����Ă킽���Ă���B���[���b�p�ł����{�ł��t�������Ƃ��Ēm���Ă���B�H�ɂ͓�։����Ă����B
�^��P�@�������A�H�܂ŃJ�b�R�E�Ȃ̒��́A���{�ʼn������Ă���̂��낤�B������������������ł���̂��B
�@�@�@�@�]�T�������ē쉺���āA�z�~�n�ɂ��ǂ蒅�����Ƃ͂��̌�̔ɐB�ɗL���ɓ����̂��낤���B
�^��Q�@��̃^�C�~���O�́B
�h�傪���łɎY��ł��闑�����A���Ƃ���Y�ݕt����ꂽ�J�b�R�E�Ȃ̒��̗��̂ق����z������̂������B�Ȃ��Ȃ玓�̐g�̂̒��ŗ��͂��Y�ݕt��
���Ă������悤�ɁA���ߑ����Ă��邩��i�̓������Ƃ����炵���j�@�@
�@�@
���R�̕�炵670 2022.7.31
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
 �@�A���́q�m���r�������Ă���@ �@�A���́q�m���r�������Ă���@
�@�@�@�X�e�t�@���E�}���N�[�]�{�A���b�N�T���h���E���B�I���A�}�C�P���E�|�[���������@�v�ۍk�i��@NHK�o��
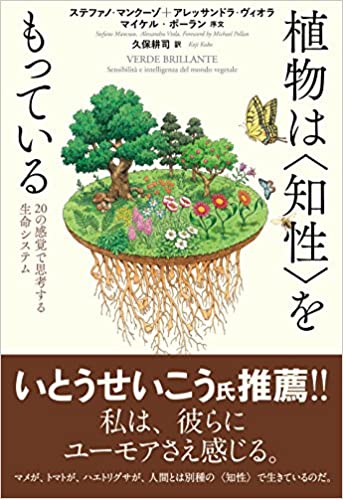 |
�u�悵�悵�A�悭������ˁv�u��������������_����v
�O����Ɏ������p���W�[�̎킪���肵���B�������߂đo�t��L���̂ŁA�s��180�x��]�����Ԍs���܂������ɒ����Ă��B����Ȏ��ɐ���������B
�u���ݍ����ċ����ɂȂ�������ׂɍ��i�������j��L���Ĉړ������ˁv�ƃu���[�x���̋����ɘb��������B
�q���̂��납�炸���Ƃ����������B
�ǂ���玄�́A���������Ă����悤���B�A���͒u���ꂽ������������藝�����Ă��āA�����b�������錾�t�������Ă���邾�낤�ƁB
�A���͈�̂ǂ��ōl���Ă���̂��낤�B�����̂悤�ɔ]����������V�X�e���������Ȃ����A�_�o�n�����菄�炳��Ă���킯�ł��Ȃ��B�P�Ȃ锽�˂Ȃ̂��낤���A���A���������ː_�o������̂�������Ȃ��B�����Ԃ���
���l�������B
�Ƃ��낪���̖{��ǂ݁A���N�̋^�₪��C�ɕX�������B
��������ča���щz�����悤�ȋC���ɂ����Ă����B
�@�y�A���͈ӎv������ ���� �m���������Ă���̂��B�z |
�͂��߂ɁA���҂͂��̖{�Łu�m���v�Ƃ͉������`���A���q���n�߂Ă���B
�u�m���v�Ƃ́u�����Ă��邠�����ɐ����邳�܂��܂Ȗ�����������\�́v�ŁA���̔\�͂������ʂɔ������ꐶ���c�邽�߂̒m�������炵�Ă���A���ꂪ�A���̐������p���ƁB
�u�Ȃ��v��₤�O�ɒ�`������B�ړI�n���߉�㈓I�ɍl����X�^�C�����D�����Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�i����������͎����̓����������؋������ǁj
�A���̓����Ƃ̑傫�ȈႢ�́A�i���̉ߒ����琶�܂�Ă������́B��O�͂��邪�ړ��ł��Ȃ�����Ɂu���W���[���\���v����ɓ��ꂽ�B�g�̂̈ꕔ�������Ă������Ȃ��炦�邱�Ƃ��ł���B���M��q�c�W���H�ׂĂ��A�������̐g�̂ɏC���ł���̂����̂����Ⴞ�낤�B�g�̂̈ꕔ�͕����\�Ő�ΓI�ɕs���Ȃ��̂ł͂Ȃ��āA�ق��̋@�\�ŕ�U�ł���Ƃ�������
�炵���B
�Ⴆ��A�W�����Z�^�̃X�[�p�[�R���s���[�^���̔]�Ƃ݂Ȃ��ƁA�A���͂܂�Ő������ƌ^�̃C���^�[�l�b�g�̃C���[�W��^���Ă����B�A���͕��U�^�̏���Z���^�[����
���Ă��āA�����̂悤�ɌX�̊튯�ɋ@�\���W���������A���U�����Ă���B�W���]�Ƃ��ē����Ă���悤���B
�A���͌������ŃG�l���M�[�������ł���----���R�E�ɂ���G�l���M�[�̑唼�͐A���R���̂��́B�ΒY��Ζ����������B�l�Ԃ��������A�������ł͐������Ȃ��̂ɁA�A���͂����ł͂Ȃ��B�����͐A���ւ̐�ΓI�Ȉˑ��W�ɂ���---�H���Ƃ��āA�G�l���M�[���Ƃ��āA�_�f�����A��̍ޗ��Ƃ��āB�����l����ƐA���͐H���A���̍ł��厖�ȓy��Ɉʒu���Ă���Ƃ����悤�B�A���͑��z�Ɠ����Ƃ̒���҂ł�����B
�����ʁi�o�C�I�}�X�j�i���d�ʁj�Ƃ��Ă݂�ƁA�A���͒n�����99.5���ȏ���߁A�����s���~�b�h�̍l�����ɂ��ƁA�ŏ�ӂɈʒu����i�ƍl�����Ă����j
�l�ԂƓ����Ƃ͂킸��0.5���ɂ����߂��Ȃ��B���ےn���͐A���̂��̂ŁA�V�����͐A���Ɋ����オ���Ă���A�ߋ������݂��A�����炭�������B
�ł͂Ȃ��l�Ԃ͐A���ɒm��������ƔF�߂悤�Ƃ��Ȃ������̂��낤���B�����Ȃ��i�悤�Ɍ�����j���炩�B�Ƃ��낪�A���́A�l�Ԃ̎��T�̊��o�i���o�A���o�A�G�o�A���o�A�k�o�j
�̂ق��A����ɐl�Ԃɂ͖������o
�������Ă���ƒ��҂͐����B���������Əd�́A��������m����A���x��������A���w�����̓y��ܗL�������͂ł���A�ȂǂȂǁB
���҂́A���̖{�̒��ŁA���̈��̍������グ�A������ʂ��Ď����Č����Ă��ꂽ�B�������낢�B
 �@�k�o�B�g�̑S�̂��g���ē�����������B�זE�̕\�ʂɎ�e�̂�������Ă���B �@�k�o�B�g�̑S�̂��g���ē�����������B�זE�̕\�ʂɎ�e�̂�������Ă���B
�@�@�@���w�������g���ĐM���𑗂�A���̐M���̘A��������邱�Ƃ��ł���B
�@�@�@����ɓ��������o�����Ƃ����s���B�i���w�����ŏ���������̂́A�l�Ԃ̔]�̓`�B���@�Ɠ������ȁj
 �@���o�B�h�{�f�Ƃ��Ďg���鉻�w��������荞�ގ�e�̂����B�y�̒��̔��ʂȉ��w���������m����\�͂����B �@���o�B�h�{�f�Ƃ��Ďg���鉻�w��������荞�ގ�e�̂����B�y�̒��̔��ʂȉ��w���������m����\�͂����B
 �@�G�o�B�G���ꂽ���Ƃ�
�m�o����B����������������o����B �@�G�o�B�G���ꂽ���Ƃ�
�m�o����B����������������o����B
 �@���o�B�U�������m���`����B �@���o�B�U�������m���`����B
 �@���x��d�͂����m����B�����������B�����������牓������B�C�E���g���Čċz���s���B�ȂǁB �@���x��d�͂����m����B�����������B�����������牓������B�C�E���g���Čċz���s���B�ȂǁB
 �@�e������������B
�����I�ɓ������Ƃ�����B �@�e������������B
�����I�ɓ������Ƃ�����B
 �@�ۂ�F�ɂ��Ă���B �@�ۂ�F�ɂ��Ă���B
 �@�L�p�Ȗ�����o����B���i�M�̗t����A�X�s�����A�L�i����L�j�[�l�̂悤�ɁB �@�L�p�Ȗ�����o����B���i�M�̗t����A�X�s�����A�L�i����L�j�[�l�̂悤�ɁB
   �@����ɑ��� �@����ɑ��� |
�A���������̔\�͂������Ƃ��A��̗�������Đ����������Ă���̂ŗ������₷���B�A���͗\�����A�w�сA���Ԃ⓮���Ə��������A
����͂��A����Ȃ�ɐB��ڎw���Đ����c��헪���l���Ă���̂��Ƃ���B
���ԂƁA���邢�͓����Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����\�͂������Ƃ���������Ă����B�����Ƃ͐������єɐB���邽�߂ɋ����W�ɂ���A�̎菕��������
�}��҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����ɂ��D��Ă���Ƃ̐����ɂ͂��ǂ낭����B
�ǂݏI���Ă����l�����B
�u�m���v�Ƃ́u�����Ă���Ԃɐ����邳�܂��܂Ȗ�����������\�́v�ƒ��҂͂����B�m���Ƃ͎��ʂ�������{��v�l�͂Ƃ������l�Ԃ̕\�w������\���Ă���C�����Ă�����������B��������\�͂Ƃ͐����Ă������߂̗͂��B���̐���ɖ����q���͂Ȃ̂��B
����܂ł��܂��܂ȏo�������������B���\�N���O�̂��Ƃ����A���̈Ӗ��������ł����B�l�����B���قǂ̏o���������������A����͐l���̖��A��햡�������̂�������Ȃ��B
�m�������͂��̃q�g�Ƃ��Ă̎��ƁA�m��������̐A�������ƍ����𖾓��Ɍq���ł������B
���R�̕�炵669
2022.7.25
�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �@�ւ���������߂��@�J���X�r�V���N�@�G���ہ@�T�g�C���ȃn���Q���@�ʖ����āi�͂j���Y���� �@�ւ���������߂��@�J���X�r�V���N�@�G���ہ@�T�g�C���ȃn���Q���@�ʖ����āi�͂j���Y����
�摜�̍����L�т��̂��ԁi����ԏ��j�ŁA��̗̂��͕̂���䚁B�����ł��B����䚂ɕ�܂ꂽ����ԏ��Ƃ�----���̐��m�ԂƓ������B�ΐF�ŏ�ɂ�����ƐL�тĂ���͕̂t���́B�S�̂̃o�����X�����Ă��āA
���̔������Ɍ��Ƃ�邱�Ƃ�����B
 �@ �@
���̕���䚂��J���X���g�����ۂɌ����Ă��悤�����A�Ȃ�قnj����̐�ɂ��̉Ԃƌs�������Ȃɂ����d���邩������Ȃ��B�J���X�����O�ɔ킳�����A���́A��̃p�b�Ƃ��Ȃ����̂������B�J���X�͂��Ȃ킿�𗧂����̂��邵�Ȃ̂��B�J���X�E���@�J���X�m�G���h�E�@�J���X�U���V���E�Ȃǂ��邪�A����Ȃ�ɗ��p���l������B�J���X�E���͑��Ă��̖�ŁA�ʏ`����ɂ��肱��ł������̂����ǁB
�����Ƃ����̂悤�ɘb����B
���̃J���X�r�V���N�̍����������������̂Ăƌ����A������Ƃ��ė��p����Ă���B���\�͊P�~�߁A��M�A�r�C�A�t�����ɂȂǁB
�E�摜�͑����炵���̂ʼnԒd���甲�������́B�Ȃ������炵���̂�?
�@���̐�̔����O�p�`�̂��̂͂ނ����B�J���X�r�V���N�͍��Ƃނ����ŔɐB���A���Ɂu�S���������v�ƌĂ�Ă���قNj쏜�A�r��������B�������u
���̂������`�͔������Ɗ����Ă��A������������������@��グ�Ď̂Ă邱�Ƃɂ��Ă���B
�ǂ��ցH������̒�łȂ��ǂ����ցB�ł��B
�ł͂Ȃ��ւ�����Ȃ̂��B����̂��鍪�s���@���Ė֎������ݏ��K�ɑւ��Ă���������Ƃ���B�ނ������`�Ɏ��Ă�
�ČI�̂悤�ł�����----�u�ւ�����v�B
����ȕ��ɍl�����B�_�Ƃ̂��ł��A�h���J���̊Ԃ�D���ăJ���X�r�V���N�̍����W�߁A���ɏo���܂ɂ����ɑւ��Ă��炤�B���Ƃ���ɒm���ʂ悤�ɂ�������ƁB
����͐^�����Ȃւ�����B
�������Ă���z�������Y�͕v�w���L�̂��́B�ł͂��̋��L���Y����u�����ߎ��H���܂��܂Ȏ���g���đ��₵�������`�̂ւ�����v��
������������̃��m���낤�B�L�`�ɂ͂�͂苤�L���Y�Ƃ��v���邪�B���₢�⎄�̐S�͋����B
�ւ�����̉B���ꏊ�����܂����_�͒m��Ȃ��B
 |
���_�����y�j������̌��n�����ɏo�������B
���ٓ��͂����̂���ׂ���i���g�͔~�����A�����̒ώρj
��Ԃ̃g���J���@�@�������܂ڂ�
�u���b�R���[�̂������Ӗ��a��
�֎q�̒��Ђ��{��D���Ȃ��傤��
�������D���Ȕ����̔����\��
�����S�{�X�����{��̃u���[�x���[
������N�[���{�b�N�X�ɓ���āB���������B
�@ |
|
�ǂ����e�L�́u�J�~���n���Ă��ꂽ�v�Ƃ܂��Ɍ��������炵���B�ʓ|�Ȃ̂Łu�R���r�j�ʼn��������A�ق��̐l�͂����ł���v�Ƃ����Ƃ������ɝX�˂��A�����ɏo�����鏬�w���݂����ɁB |
���Ȃ݂Ɂu�e�L�v�Ƃ́u�G�v�ł͂Ȃ��āA�a�̎R�قŁu���Ȃ��A���݁v�̂��ƁB���������āu���Ȃ������v���u�e�L���E�e�L���v�ƌ������炷�B�i���܂ɓG�ɂȂ邱�Ƃ����邩�炩�j
�@�@�@�@�@���R�̕�炵668
2022.7.19
�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@�@  Cebiche
de Camarón�@�@�Z�r�`�F�f�J�}���� Cebiche
de Camarón�@�@�Z�r�`�F�f�J�}����
����G�N�A�h���ɏ������������̂����������ɁA���̍����v���o���ăZ�r�`�F������Ă݂��B�Z�r�`�F�͓�Ă�L�V�R�́A�V�N�ȋ���ނ��l���n��̖����������B���k�ނ��g�����}���l�ƌ������炢����������Ȃ��B
���������̒n��ō̂��n�[�u���e�����̂ŁA�n��ɂ���Ĉ�������Ɏd�オ��B
�ޗ��́F����ށB�ʂ˂��A���ʂ˂��A�g�}�g�A�������A���C���A�V�����g���A�p�Z���A�I���K�m�A�����A���h�q�ȂǁB�I���[�u�I�C���������邱�Ƃ�����B�D�݂ɂ���ăp�N�`�[���ł�������ɎU�炷�Ƃ���炵�����ɂȂ�B���D�݂̂܂܂ɂƂ������Ƃ��B
�@�@�@
�y���[�ł̓����i�A�C�i���j��R���r�[�i�i�j�x�Ȃ̋��j�A�y�w���C�Ȃǂ̔��g�̋��A�G�r�A�^�R�A�C�J�A�z�^�e�A�n�}�O���Ȃǂ̊L�ނ��g����B���t�����_�����������������ς薡�Ɏd�グ�Ă������B���̐�g�����C���������邱�Ƃɂ���āA��������\�ʂ������Ȃ��Ă����̂����Ă��Ėʔ����B
���L�V�R�ł͐h�����h�q�������������A�s���b�Ƃ������Ɏd�グ�A�^�R�X�ɋ���ŐH�ׂĂ����̂��v���o���A
�hSe me hace la boca agua�g ------�����A�����������B
�����̓G�N�A�h�����Ȃ̂ŁA�ʂ˂��͔��ł͂Ȃ��Ď��F�̂��g���B�g�}�g�������Ăɂ��₩�ɁB����Ƀg�}�g�P�`���b�v�����������ƃG�N�A�h���炵�����o�Ă���B�����͓V�R�G�r�����Ɉ�x�̔��z�Z�[���̓��������̂�
�A������g�����B�p�N�`�[�͂Ȃ��Ȃ��B�①�ɂŐQ������B������������������������ɏo���オ�����B
Cebiche de Camarón�����Ȃ���A�ЂƂ�����b���e�B
42�N�O�̂��Ƃ��B�y���[�̖k�����ɂ��郏���X�̒��i�W��3052m�A���X�J�����ւ̓o�R��n�j�����s���}
�֖����A�҂��A����y���[�����̃��X�g�����Œ��H��ۂ��Ă���ƁA���X�̂���l���o�Ă��āA
�u�����l������A����̓T�[�r�X�ł��v
�ƌ����Ȃ��甒�g���̃Z�r�`�F���ǂ�����e�[�u���ɍڂ��Ă��ꂽ�̂��v���o�������炾�����B�����炭����l��
�ږ�2����3���������̂��B��c�͓��{�̂ǂ�����ږ����Ă����̂��낤�B���Ζʂ̎������ɂ���Ȃɐe�ɂ��Ă���������-----�ǂ����ǂ������肪�Ƃ��������܂�----���₢��ǂ�����----�B
��Ăɒ����ĂR���A�܂�����ׂ̍����\�����ł����ɁA����ꂽ�P��Œ��B�\�������ł��Ȃ��������낾�B���������b������ڏZ�̂������₲�Ƒ��̂��ƂȂǂ����q�˂ł����̂ɁB
�Ƒ��݂ȎႭ�c���A���̐�ɍL���鐢�E�����邱�Ƃ�M���Ă������̂�����v���ƁA���ܕʂȐ��E�ɏZ��ł���悤�ȍ��o�Ɋׂ邱�Ƃ�����B
 �@���̗[���A�Z�r�`�F��n�������̕Ԃ�����----���ĕ���n�T�~�Ɏ����ւ������������B�������Ⴂ�����̂������Ƃ������Ȃ��Ă����O�������藬�ɐ��Ă��܂����B �@���̗[���A�Z�r�`�F��n�������̕Ԃ�����----���ĕ���n�T�~�Ɏ����ւ������������B�������Ⴂ�����̂������Ƃ������Ȃ��Ă����O�������藬�ɐ��Ă��܂����B
���̌㋾�����ē��R�̂��Ƃ��ߖ��グ�邱�ƂɂȂ����I�u�肷�����I�v
�O�������ɕ��сA����ł͂܂�ŏ��a�̎q�����B���Ƃ���A���т܂�q����� �̂悤�ɁB
�u���̂����L�т邾�낤�v�A�u�N�����l�̑O���Ȃnj��Ă��Ȃ���v�ƈԂ߂Ă���邪�A���^�V�͍������L�тĂق����̂��I�@���قŌ����u�C���`�v�Ȃ̂��B�e���r�����Ȃ���O������������B�u�L�т�L�т�L�т�v�B
 �@���̒�5�����B�L�т������z�^���u�N���̌s����Ă�����A�w��Ɂu�o�`���v�Ƃ͂�����悤�ȉ��������B����̓A�V�i�K�o�`�i
�����I�j���W�K�o�`�i����I�j�Ɏh���ꂽ���B����ĂĉƂɓ��� �ʼnt���i��o���A�X�e���C�h�N���[����h��B�����ǖI�̐j
�ɂ́u�Ԃ��v�����Ă���̂ŁA�i�����Ƃ���ʼn����o�Ă��Ȃ��B�u�ɂ��Ƃ��䂢�v�̘A���Z���J��o���Ă���I�Ɉ��Ԃ������������B
���т܂�q������ԂȂ̂ɂ���͂܂��ǂ��������Ƃ��B�������ʂɖI���̂��́B �@���̒�5�����B�L�т������z�^���u�N���̌s����Ă�����A�w��Ɂu�o�`���v�Ƃ͂�����悤�ȉ��������B����̓A�V�i�K�o�`�i
�����I�j���W�K�o�`�i����I�j�Ɏh���ꂽ���B����ĂĉƂɓ��� �ʼnt���i��o���A�X�e���C�h�N���[����h��B�����ǖI�̐j
�ɂ́u�Ԃ��v�����Ă���̂ŁA�i�����Ƃ���ʼn����o�Ă��Ȃ��B�u�ɂ��Ƃ��䂢�v�̘A���Z���J��o���Ă���I�Ɉ��Ԃ������������B
���т܂�q������ԂȂ̂ɂ���͂܂��ǂ��������Ƃ��B�������ʂɖI���̂��́B
 �@�S���Ԍ�A�V�����I�Ɏh���ꂽ�B����łS��ڂ̃R���i���N�`���̒��˂������B
����قǐl�Ԃɉ��Ȃ���炵�����Ă�����Ȃ̂ŁA��@�ɏW�܂��Ă����u�q�g�v�ɋ����ÁX�B
���l�̔w�i��z�������҂����Ԃ̂P�T���������B�[���ɂ͐ڎ�ꏊ�����Ԃ��Ēɂ݂��o�Ă����B�������тɂ���肶���ƍ��r�ɒɂ݂�����B�Ƃ�����A����ŏI���B���S���Ă͂����Ȃ����B �@�S���Ԍ�A�V�����I�Ɏh���ꂽ�B����łS��ڂ̃R���i���N�`���̒��˂������B
����قǐl�Ԃɉ��Ȃ���炵�����Ă�����Ȃ̂ŁA��@�ɏW�܂��Ă����u�q�g�v�ɋ����ÁX�B
���l�̔w�i��z�������҂����Ԃ̂P�T���������B�[���ɂ͐ڎ�ꏊ�����Ԃ��Ēɂ݂��o�Ă����B�������тɂ���肶���ƍ��r�ɒɂ݂�����B�Ƃ�����A����ŏI���B���S���Ă͂����Ȃ����B
���R�̕�炵668 2022.7.14
�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �~���̉e�����g�߂� �~���̉e�����g�߂�
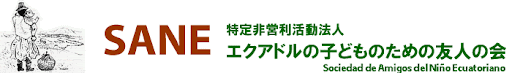
35�N�O����Q�����Ă���uSANE�����c�������@�l�G�N�A�h���̎q���̂��߂̗F�l�̉�v���炨�肢���͂����B
�@�@�@���@http://sanejapon.blogspot.com/�@��
SANE�͂S���Ɉ�x�G�N�A�h���֊��������𑗋����Ă��邪�A���̂Ƃ���̉~�����傫���e�����āA���̂܂܂��Ə��w���̐������炷�K�v���łĂ���I�ƁB
�~�������܂ő������\�z�ł��Ȃ����A���̉~���������Ɨ��N�x�̎��Ɠ��e�����������ƂɂȂ邩������Ȃ��B
�S�����̒������9500�h���𑗂�ꍇ�A
�@�@�P�h��110�~�O�ゾ�Ɓ@�@�@�����z�͂��悻105���~
�@�@�P�h��135�~�O�ゾ�Ɓ@�@�@�����z�͂��悻128���~�@�@���̍���23���~�B��N�Ԃł�100���~�߂��ɂȂ�B
�G�N�A�h���ł͌��݂قƂ�ǐV�^�R���i�E�B���X�ւ̊����҂͌����Ȃ��Ȃ������A�Љ���ւ̉e���͋����c���Ă��āA�������������Ƒ���d�����������l�������B
�Ȃɂ��ł��邩�B����������������������Ȃ��B
�@�@*�@�G�N�A�h���̌����h��������i�_���[���C�[�[�V�����j
�H�Ȃ��Ƃ����A�G�N�A�h�����{��2000�N�A�o�ϕs�U�Ǝ����ʉ݃X�N���̖\���ɑΏ����邽�߂ɁA�����ʉ݂�p�~���ăh����@��ʉ݂Ƃ���u�����̃h��������v�������B
���̌�ΊO�I�ɋ����h���Ƀ����N���邱�ƂŒ��N�ꂵ��ł����C���t���������������o�ς����肵�Ă����B
����������SANE�����������h���͂��̂܂܌��n�ʉ݂Ƃ��ė��ʂ���B�ēx�̈ב����̕K�v�͖����B
�����h��������ɂ���ėA�o�����i�����肷�锽�ʁA�h���́��A�����J�̌i�C�ɍ��E����A�G�N�A�h�����{�̋��Z���ǂ͈ב։�����邱�Ƃ��Ȃ炸�A�����g�ɂ����Z����A�R���g���[�������o���Ȃ��Ȃ�B
�@*�@�R���i�Ђ̂���6���A�G�N�A�h���ł́A�G�N�A�h����Z���A���iCONAIE)�ɂ��R�����i�͂��ߕ��������Ȃǂɑ���R�c�f�������������B����3���Ƒ����̂����l���o���B���x�~�����i���h�����l�����肵������̂��ƂŁA��펖�Ԑ錾���o�����܂ł������B�W��̎��R�������A�Ƃ���ɂ���Ă͊O�o�֎~�߂����߂���Ă����B
6��30���A�R�c�����͋���̍��ӂ������Ď��������͗l�B
 �T���p�u���E���R���̃E���x���g�E�t�B�G���Z
�T���p�u���E���R���̃E���x���g�E�t�B�G���Z
�@�q�������̕����i
�@�@�i��ȗA�o�i�́A�Ζ��A�o�i�i�A�R�[�q�[�A�J�J�I�A���ԁA�܂���A���тȂǁj
�@�@�i��ȗA���i�́A�Ζ����i�A�����ԁA�ԗ����i�A�S�|�Ȃǁ@�@-----2022�N�@�O���Ȋ�b�f�[�^���j
���R�̕�炵668
2022.7.11
�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@
 �Ȃ������E�N���C�i���@�@�V�F�t�`�F���R���W�@�w�R�u�U�[���x��� �Ȃ������E�N���C�i���@�@�V�F�t�`�F���R���W�@�w�R�u�U�[���x���
|
�@�@�u�⌾�v�@�^���X�E�V�F�t�`�F���R�@
�@�@�@�@�킽��������B
�@�@�Ȃ������E�N���C�i��
�@�@�Ђ�т�Ƃ��������i�X�e�b�v�j�ɂ������ꂽ
�@�@�����ˁi���q���j�̏�ɁA�����Ăق����B
�@�@�ʂĂ��Ȃ���̘A�Ȃ��
�@�@�h�j�G�v���A�藧�R��
�@�@���n����悤�ɁA
�@�@�K�肽�Ƃǂ낫����������悤�ɁB
�@�@�h�j�G�v���̗��ꂪ
�@�@�E�N���C�i����G�̌���
�@�@���C�ւƗ�����������A
�@�@���̂Ƃ������A����R��----
�@�@���ׂĂ����Ă悤�B
�@�@�_�̐g�����Ă��̂ڂ�A
�@�@�F����������悤----��������܂ł�
�@�@�킽���͐_��m��Ȃ��B
�@�@�킽���𑒂�A�����������Ăق����B
�@�@����f����A
�@�@�����ȓG�̌�����
�@�@����̎��R�ɐ���������Ăق����B
�@�@�����āA�f���炵���Ƒ��A
�@�@���R�ŐV�����Ƒ��Ɉ͂܂�Ă��A
�@�@�킽����Y�ꂸ�A�v���o���Ăق����A
�@�@������̂��������Â��Ȃ��ƂŁB�@1845�N12��25���@�y�����X���E�ɂ�
�@�V�F�t�`�F���R���W�@�w�R�u�U�[���x�@����x�q�Җ�@
�@�@�@
�@�Q���Њ��@2018�N10��17�����ő����@P179��� |
����V���L�������������ɁA�E�N���C�i�̎��l�u�^���X�E�V�F�t�`�F���R�i1814-1861�j
�v�̎��W���������ǂ�ł���B�@�@*�u���̊X�L�[�E�v2022�N�S��30���@���Y��s�q(�̐l�j�@���{�o�ϐV��������
���t���N���Ă��Ă���B������₷�����t�������Ȃ�����A���̔w��ɂ���u���̂�̓��𗝉����Ăق����A�`�������v���ЂƂЂƂ̃t���[�Y���ۗ������Ă���B
�ǂނƔM����̂悤�Ȃ��̂��A���̉����点�肠�����Ă���̂�������B
��́u�⌾�v�͎�e�W�w�O�N�x�̍Ō�̍�i�ŁA����o�ł��ꂽ�w�R�u�U�[���x�ɁA�`���̔��s�������u�⌾�v�̑�Ōf�ڂ��ꂽ�B����Ȍ�
���̎��́u�⌾�v�̖��ōL�܂�A�V�F�t�`�F���R�̍�i�̒��ł����Ƃ��m���Ă��āA�E�N���C�i�ł́u���̍��́v�̈������Ă���悤���B
�@�@�@�@���W�̖��O�́u�R�u�U�[���v�̓E�N���C�i�̖����y��R�u�U��t�ł��V���l�̂��ƁB
�@�@�@�@�`�����p�����j���p����蕔�ɂȂ�Ƃ̌��ӂ��������閼�O���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(youtube�Łu�⌾�@�V�F�t�`�F���R�v�ŒT���Ă��������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����y��R�u�T�̉��͓��{�̔��i�̉��F�Ɏ��Ă��܂��B�j�@
�@�@
��҃V�F�t�`�F���R�͋ߑ�E�N���C�i�ꕶ�w�̎n�c�B�鐭���V�A����̃E�N���C�i�Ŕ_�z�Ƃ��Đ��܂�
�����A�G�̍˔\��ɂ��l�X�̋��͂ɂ���Ă��̗��ꂩ�������ꂽ�B�_���̌��t�Ƃ������܂�Ă����E�N���C�i���ꂩ��p�����ɏ������A�E�N���C�i������`�̏ے��ƌ��Ȃ���Ă��鎍�l�V�F�t�`�F���R�B
�s������߂��݂�ꂵ�݂�{��ɓ]���������r�ށB���V�A�c��ւ̔��t�҂Ƃ���10�N�ԗ��Y�ɂȂ��Ă���B�ƒ�������Ƃ����Ȃ킸�Ⴍ���ĖS���Ȃ����B���������݂܂ł��̎��͓ǂp����u�����̕��v��
�݂Ȃ��ꐸ�_�I�x���Ƃ��Ă̖������͂����Ă���B
�E�N���C�i�͉ߋ��A���ӂ̑卑�̐N�U�������ė������j�����B�鐭���V�A�ɂ��
�����x�z�������]���̗��j�̂Ȃ��ɂ������B�\�A����œƗ���������������̂́A���̌ネ�V�A�ɃN���~�A�������̂��ꂽ�B
�����Č��݂́B----�퉺�ɂ���B
|
�u�킽���𑒂�A�����������Ăق����B�^����f����A�^�����ȓG�̌����Ł^����̎��R�ɐ���������Ăق����B�v�i����x�q��j
�@�@���l�͐l�X�������ە�����B |
�u�����ȓG�̌����Łv�������n�ɃE�N���C�i�l�̌�����������B
��R���l�̔߂��݂Ɠ{�肪�A���l�X�̓���ɉ������B
�u�\���ꂽ����v
*�@�Â����ɂ݂������E�@������ӂ邳��/�킽���̃E�N���C�i��B/���A���Ȃ��͂Ȃ�
�j��A�łт䂭�̂��B/���܂����A���z�̏���ʂ�����/�_�ɋF�������Ȃ������̂��B
�v�����ʂ̂Ȃ��q�ǂ�������/-----�ȉ����@�@�@����x�q��@�������V�F�t�`�F���R���W�@�w�R�u�U�[���x���B |
�߂��݂��ڂ̑O�ɍ����o�����B���l�̓{��̂����܂����A�߂��݂̑傫���[���A���������ɐÂ��Ȍ��t�������̂Ȃ����_��\�����Ă���B
�l�Ԃ̑����Ƃ͂Ȃɂ��B�R�T�b�N���y��{���V�`�Œm���� ���V�A�����̔��˂̒n�ł���Ȃ���A�卑���V�A�Ɏx�z���ꑱ���Ă����E�N���C�i�B
���V�A�ᔻ�͓��R�̂��ƁA���l�̓{��̓E�N���C�i�ɂ�������
�@�@�@----���V�A�̎x�z�̕Ж_��S�����E���ꂵ�߂�n�傽���ɂ��B
�܂����l�͂������r�ށB
*�@�킽���̌��̂Ă�ꂽ�n���������k���A/���Ƃ̎�q�i���ˁj�������Ă���B���̓���/�L���Ȏ���������炵�Ă���邾�낤---------���߂����R�̎�q��������Ă���I------����A���Ƃ̎�q�ł͂Ȃ��A/�����̎�q��������Ă���I----�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����x�q��@�������V�F�t�`�F���R���W�@�w�R�u�U�[���x���B
*�@�܂�����/�S�������̌�������n�߂܂����A/�����������Y���s�l�������A�ӂ�����/�Q������nj��̂悤�ɁA�������߂đ����Ă��܂��B�@�@�@�@����x�q��@�������V�F�t�`�F���R���W�@�w�R�u�U�[���x���B
�������B
----�����Ăӂ����сA������̂����������炩�Ȃ��Ƃ�/���Ȃ����]������̂�/�Â��ɉ̂��͂��߂�ł��傤�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����x�q��@�������V�F�t�`�F���R���W�@�w�R�u�U�[���x���B |
�u���Ȃ����]������́v�����܃E�N���C�i�̐l�X�̎��ɓ͂��Ă��邾�낤���B
�V�F�t�`�F���R�́A�V�q�V�c�A�V���V�c�ɐ_�̈˂��Ƃ��Ďd�������t����̊z�c�����A���邢�͉̂����ƂŌÑ�V�c�����x�����`�{�l���C���B�u�N���ɂ��܂ӂ��ƂȂ���v�Ɖr�^�Ӗ쏻�q���B�펞��������ꂽ�������V�c�ɒ����𐾂��āu�C�䂩�v�Ɖr��F�Ǝ����B
���t�̗͂͑z���͂ƂƂ��ɋ삯����B
 �@�}���R�|�[���@���炫�̃��� �@�}���R�|�[���@���炫�̃���
���R�̕�炵667 2022.7.7
�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �p�W���}�𗠕Ԃ��ɒ����� �p�W���}�𗠕Ԃ��ɒ�����
���̉ėp�ɂƏ������Ă����V�����p�W���}�����낵�Ă����B���ςȂ�ʋC���ς̉��F���p�W���}�B���ʖ͗l�����炵���Ċ������B�L�����R���n�ɂȂ�炩�̉��H���Ă���炵���A���Ă�ᰂɂȂ�ɂ��A�r����������肵�Ē��₷���B�����ǁA������̕s���́u�t���Ă���^�O�ƖD���ڂ����ɐG�邱�Ƃ�����v�������B
�l����------����𗠕Ԃ��Ē�����ǂ��Ȃ邾�낤��----�Ȃ�قNJy�������B�f���ɗD�����B
���̓��܂��l����-----����𒅂ċ~�}�Ԃɏ��悤�Ȃ��Ƃ�����A�����炭�������q�g���Ǝv���邾�낤�ƁB
���̓��A���̕��ʂ̒����ɖ߂��ĂȂ�ƂȂ����S����B
�ڂɌ����Ȃ�����������ɉۂ��B�펯�ɂ�����߂ɂȂ��Ă���B���ʂłȂ����Ƃ�����E�C���Ȃ��B���̐S�̋����Ƃ������������B���{�͑��_���ł̈�_���ł������u���ԋ��v���Ƃ̘_�����邪�A�܂��������̒ʂ�B���l�̖ڂ��C�ɂ��đ吨�Ɍ}���H�����x�b�h�̑O�̎������ʔ����B�@�@�����������B�^�O�͐�������̂��B
�@ �@������
���� �@������
����
�u�������₷�Ƃ��́A���̃��o�[�𐅂̈ʒu�ɖ߂��Ă���₽�����𗬂��ĂˁB�v
�u�����A�������肵�Ă��I�����̈ʒu�Ő����i�������j�����Ă��܂����̂��I�v
�u�������肵�Ȃ��Ă����������肷��̂����炤�����肷��Ƃ܂��܂��������肷�邩��v
�@��������̑�ՐU�镑���B
���̂Ȃ���ˑR����͂��߂��́B�Ȃ����H
�@�@�@��u�E�b�J������̉�����A�͂��͂�����ɂ��́B�`���b�J������̉�����A�͂��͂�����ɂ��́v��
���ŋ`���o�i84�j�Ƃ��̂��ׂ���i85�j�̊|���������˂̂悤�ȕ�炵�����ɕ�����ł����B�Ⴂ���납�璇�ǂ����Ȃ��狣�����Ă�������l����͂��܁A����Ȃ��Ƃ��ׂ������Ă���悤���B
�u�����̕������̐���������v
�u���̕������������Ȃ���A�ق�܂��O���[������ˁv
�y�E�b�J���v�l�ƃ`���b�J���v�l�z�@����H�y�`���b�J���v�l�ƃE�b�J���v�l�z���������ȁB
1950�N�ォ��60�N��ɂ����ă��W�I�����i���݂�TBS�j�ŕ������ꂽ�h���}�B�̂��ɉ��f�扻����Ă���B�����v�ȂƉF���v�Ȃ���l���ŁA���t�̊|���������ʔ��������L��������B�i�m���Ă���l�͒m���Ă���h���}�j

�@�@����Ńj�b�R�E�L�X�Q���炢�Ă����B�W�����Ⴂ�̂ł���Ȃɑ傫�ȉԂɂȂ�B
���R�̕�炵666
2022.7.4
�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@
 �����Ղ�ƉĂ��V�T���� �@�i�ߌ�2���A36���ɂ܂ŏオ�����j �����Ղ�ƉĂ��V�T���� �@�i�ߌ�2���A36���ɂ܂ŏオ�����j
10�������݂̋C����33���B���͂����ň͂܂�Ă���̂ŁA���C�������ď��������B�ߐ{�����Ɩ��t�����͎̂s�̊ό��ۂ̉A�d�ł͂Ȃ����Ǝv����B�Ă��܂��V�T��������A�ƍl���邾���ŐS���ӂ�����B
�����A���_�Ɓu���̉Ă̍��𗧂Ă悤�v�Ƙb���������B�Ƃ����𐮂��H�܂ŐS�g�Ƃ��Ɍ��C�ɕ�炷�ɂ͂ǂ������炢����-----���𐘂��Ă����낤�B���ׂ����ƂƂ��Ȃ��Ă������Ƃƕ����悤�ƁB
�@�S�̂Ȃ��ł́i���S����A�d���͂ˁj�i�����Ăɏ�邩�A���邩�j�i�����������͂ǂ����j�i�r�[�����ȁj
5���N���B�����J�������|���@������������ς܂����������Ȃ������Ɋ����B���̌�͑S�������̎��Ԃ��B�������R���i��孋����鐶�����R�N�ڂɂȂ�ƁA�͂����肵���֊s������
�肢��������Ȃ��Ȃ��Ă����B���C�ʼn߂������Ƃ͍l���邪��̓I�ɂ����������A�����֍s�������ƌ����C���[�W��������ł��Ȃ��B
�������A������ґ�������Ă͔���������B�������ǂ�Ŋy���߂�{��T�����A�Ǝv�����đI�̂����̖{
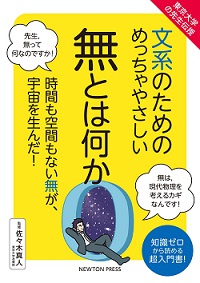 |
�����҂��u�߂�����₳�����v�ƌ����Ă��A�����Ƃ�N�G�̓��������n�Łu�����猻�㕨�����l����v�Ȃ�ĕ����ƁA�������킴�킷��B
��͈�́A�������ǂ�ł������B
�܂��A�����ĉ��H�_�C�i�~�b�N�ŃG�L�T�C�e�B���O�B
���̐��[��----���R�E�Ɍ����[���B
���̋�ԁA�^��B
�Ƃ������肩��Ӗ��[���Ȍ��t�̘A�����B
�y���߂邩�ǂ����B����͂ЂƂ��Ɏ��̓��̏o���ɂ��悤���B
����͔F�m�ǖh�~���Ǝv���������ǁB |
�@
�@ �@�@�����̎�d���@ �@�@�����̎�d���@
 �@���̃W���������
�@�i�T�L���j �@���̃W���������
�@�i�T�L���j
�M��������Ƃ��Ƃ��Ƃ̊Ö����\�ɏo�Ă���̂ŁA�����i�ʓ����g�����ǁj�̊�����15�����x�ŏ\���B
 �@ �@
���H�ɁF���[�O���g�A�����S�A�u���[�x���[�\�[�X�A�̂肽�Ẵu���[�x���[�ƃ��C���h�X�g���x���[
�@�@�@�@���C���h�X�g���x���[�͂��낻��I���B
���R�̕�炵665
2022.6.29
�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �@���悢��͂��܂� �@���悢��͂��܂�
�~�J��̉��A�����A�����A�Ӑ��Ƃ��낦�ĐA���Ă���u���[�x���[�̂����A�������n���n�߂��B�R�[�q�[���Ɠ����悤�Ƀ����_���ɏn��Ă���̂Ŏ��n�Ɏ�Ԏ��B
������C���K�i�Ƃ�ł��Ȃ��Q���B�h�����Ɣߖ��グ��قǒɂ��B��̑�l���������Ƃ����邭�炢�j�����������Ă��邱�Ƃ�����A���L���ɂ����鋰��B���S�h����Y�ꂽ���Ɂu�Y�h�b�v�Ǝh�����̂́A����������S�m�F�����Ȃ������Ƃ��̌�ʎ��̂Ɏ��Ă���B�i�u�Y�h�b�v�������ːj�Ŏh����邩�̂悤�Ɂj
�悵�悵�A�ۂ��đ������̂���̂낤�B������Ƃ݂�Ȉꏏ�ɏn���Ƃ������͏��������----�u�h�E�����Ă݂Ȃ����B���s�V�悭�Ԃ牺�����Ă����ˁB�܁A�����܂ł悭������B
�Ƃ��낪�������Ƃ��ꂪ�u���`�A�h�ҁE�����܂��ł������Ă��āA����h�炵�ė��Ƃ��ďW�߂����v�Ǝv���قlj����x�I�ɏn���Ă���B
�������Ǝ��n����B�W�b�v���b�N�ɂ��̂܂ܓ���Ĕԍ������A�Ⓚ�ɂɕ��ׂĂ���B�ł����̗Ⓚ�ɂɂ́A���N���n�����u���[�x���[�̃p�b�N��20�܂��炢�c�����܂܁B10�L���ȏ゠��B�����R�O�������[�O���g�ƈꏏ�ɐH�ׂĂ��ǂ����Ȃ��B���̕��ł͍��N�̎��n����H���̂�10���ɂȂ肻�����B������o���Ȃ̂�����B
�u���[�x���[���n�Ɋ��𗬂��Ă̎n�܂�B

�Z��n�̌f���ɂ����������B�u�F�ɒ��Ӂv�B�u���[�x���[�̋G�߂͌F�̋G�߂ł�����B �ŋߏZ��n�̂Ȃ����F��������Ă���炵���B�䂪�Ƃ̃u���[�x���[�𓐂�ɗ��邩������Ȃ��B
*�@�ẴJ�i�_�A�v�����X�G�h���[�h���ŊJ�Â����u�����S�����w��v�Ō����̐��ʂ\�Ȃ���ԏ����q�����Ɍ���̃��[���𑗂�����A������ԐM���������B���͊������炢�̓V�C�炵���B
�������̂��C���^�[�l�b�g�B�����������ɒn���̗������烁�[�����͂��Ɗ��������̂��B
�@�@�ԏ����q�����i�m�[�g���_�����S���q��w ���w�� �p��p���w�ȋ����j
�@�@�@�ߒ��� �w�Ԗт̃A�����獕���̃G�~���[�ց\�\L�EM�E�����S�����̏�����ǂށx 2022/03/25���s
�@�@ �n�ǂ����t�������B�@�����̐����[��
*�@�}���قցB���Ă�p�̖{����Ă����B
*�@�Q�c�@�c�������O���[���ς܂����B
���҂͌o�ϑ�Ȃǂ̖ڐ�̐�����������Ă�B������R�ς̂��̎����ɒ����I�Ȏ��_�Ŏv����[�ߍs���ł�����҂͂��Ȃ����̂��B
�Q�c�@�͎Q�c����@�ցB�����ɗ͂������Ȃ��̂�������Ȃ��B�o�ϐ�����D�悵���������ʁA�l�Ԃ����������̂��傫�����Ƃ��v���m�炳���B
�������A���{�̌o�ϐ����ƂƂ��ɐ����A���v�������N��̎��������A�̂��̐��Ƀ��m�\�����Ƃ͂ł������ɂȂ��B
�@ ���R�̕�炵664
2022.6.25
�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �@�V��̕P���S���@�q���T�����@�����ȃ����� �@�V��̕P���S���@�q���T�����@�����ȃ�����
���ꂾ���ł��������u���v�Ɂu�Ђ߁v���킳����̂́u���v�����Ă���A����ȁu�P���S���̗��v����Â̎R�Ԃɂ���B�@
�@�@�@�@�@���@https://www.kanko-aizu.com/information/29468/�@��
���N�܂ł��������@
�i�q���T�����͋{�錧�암�ƐV�����A�������A�іL�A��A��ȎR�A���x���ӂɎ���������{���L�̃����Ȃ̐A���B�j
�Ԃ̐���̂��̎����A�������玩���n�ɏo������̂��킪�ƍP��̍s���ŁA���N�������ɉʂ������Ƃ��ł����B
�悵�A�n�}���ǂ߂�A�^�]�����v�������A���V�C�͉ԓ��a�B�u*�m�́A�̗͎��̉^�v�����������Ƃ��m�F���邽�߁A����������낵�Ȃ��炱�������������B
�u���N�������܂ŗ���ꂽ�ˁA���N�͂ǂ����Ȃ��B���N�͈ꔑ���Ȃ��Ƃ����Ȃ���������Ȃ��ˁv�B
�Ȃɂ��뉝��200�L���̎R���ŎԂłS���Ԕ�������B�������B���_������ɉ^�]�����S�ɂȂ��Ă����悤���B
���̉Ԃ͎�ő����Ă����B�܂��n���ɏ��������������A�悤�₭�R�N�ڂɒZ���Зt������A�U�N�ڂɂ��Ă悤�₭��ւ̉Ԃ�����B���̌�͋������傫���Ȃ�ɂ�A���̉Ԑ��������Ă���----���̏́u�J�^�N���v�Ɠ����B���������������ĉԂ���Ă邻�̋�J���ꏏ�B
�J�^�N���ƈႤ�̂́A�W���������Ă̋C����œ~�͐�ŕ����ĕێ������y�n�łȂ��ƈ炽�Ȃ����ƁB���n�ɉ��낷�Ƃǂ�����Ă��A�ǂ�ȍH�v���Â炵�Ă��炽�Ȃ��B�������Ύ����n�ɑ����^�Ԃ����Ȃ��B
�t�ɎR�Ă������ĊQ����ގ����엿�ɂȂ�D�𗎂Ƃ��B�����r��A�͂����������邱�ƂŃ����̋�����ی삷��B���͂ɂ̓C�m�V�V�����̓d�C������点�Ă���B�Ǘ��͑�ςȍ�Ƃ��낤�B�Ȃɂ���X�L�[��S�̂̑�������̂�����B
�@�@*�u�m�́A�̗́A���̉^�v�B����̓A�����J���f�E���g���N�C�Y�i1977-1992�j�ł̎i��҂̗Y�����сB
�@�@�@�@���̔ԑg�Ɏq�������Əo���������B�N�����45�܂ł������B

�@���ꂪ���P�l�B�킩��10�N���炢�o���Ă���͂��B
�Ԃ͓���������č炭���Ƃ������B
 �@ �@
�A�}�r�G�̊G���B�������x���炵�āA��Â̎R�ɋ��������B
�j�b�R�E�L�X�Q���Ԑ���B���Ȃ݂ɕʖ��̑T��Ԃ̖��O�́A�j�b�R�E�L�X�Q���������Ă����ꃖ�����A���T���̒�Ɍ����Ă����ƂɗR������炵���B
�X�X�L�Ɏ��Ă���̂͐��F�Ɏg����J�����X�B�J�����X������ՁB���`�ʂ�A���̂܂܁B

�^�j�E�c�M�@�X�C�J�Y���ȃ^�j�E�c�M���@�@�ʖ��@�g�E�c�M�@�c�A����
�W��1000���[�g���ɍ炭�^�j�E�c�M�B�̂��ӂ�钆�ɓ��F�̉Ԃ��A�܂�ł�������x�z���邩�̂悤�ȑ��݊�������Ă���B����̓s���N�ł͂Ȃ��ē��F�ƌĂт����F���B

�R�Ԃǂ��̂܂������B�H�ɂȂ肱�̎����n���Ă���̂ɏo�������A����͂Ƃ�ł��Ȃ��F��A��ՁB�_���Ă���̂͌F�A�T���A�l�ԁB���ߑ����̂��������B����������u�h�E�ɂ��Ă݂����Ɗ���Ă���B�������A������낤���N���B
 �@ �@
�@�@�@�t���ς̐悪�҂��Ɣ�яo���āA�T�̍b���Ɏ��Ă���B
���u�}�I�@�iBoehmeria
japonica�A�M�����j�C���N�T�ڃC���N�T�Ȃ̑��N���A���B�J�����V�Ƌ߉��B���u�}�I���M�ɐ�����}�I�Ƃ����Ӗ��ŁA�}�I�͓����C���N�T�Ȃ̃J�����V�̂��ƁB�a���̓}�I���M�����������́B�؍���ɗR������悤���B���Ă̓J�����V�Ɠ��l�Ɍs�̐A���@�ۂ��玅��a���ŕz��D�����B
�J�����V�@����悭�g��ꂽ��A���p���l���傫�����t�قǁA���̒n���Ɠ��̖��O�����B�J�����V�͌Â�����A���@�ۂ��Ƃ邽�߂ɍ͔|���ꂽ�̂ŁA�I�i���j�A�����i����܁j�A���i�������j�A�R�I�i��܂��j�A�^���i�܂��j�A�����i�܂��j�Ȃǂ��܂��܂���B�s�̔炩��̂��x��@�ۂ͖��Ɠ����悤�ɔ��ɏ�v�ŁA�a���Ŏ��ɁA�b���ĕR���ɁA�Ԃ⋙�ԂɁA�@���ĕz�ɂ���Έߗނ⎆�Ƃ��Ă����L�����p����Ă����B��������Òn���̏��a�����B��̎Y�n�ŁA���̏d�v���`�������Ɏw�肳��Ă���u����J�k�E�z���z�v�̌����Ƃ���Ă���B
�@���@https://showakanko.or.jp/see/hakubutsukan/�@
�����a���@����ނ��H�|������
�ꕶ�̎��ォ��l�X�ɗ��p����Ă����A���@�ہu����ނ��v�u���v�͔̍|�Ɋւ�����j������Y����A�l�X�ȐD���Ȃǂ�W���������Ă���B
���̔����قŎ����́u����J�k�E�z���z�v�ŐD��d���Ă�ꂽ�������������A�قƂ�ǓV���̕��߂̂悤�Ɍy���A�������B
���R�̕�炵663�@ 2022.6.20
�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �@�ق��闈�悵��Ƃ�̒n�̍�̕ӂ� �@�@ �@�ق��闈�悵��Ƃ�̒n�̍�̕ӂ� �@�@
�@�@*�w�Î��L�x�ɘ`�����i��܂Ƃ�����݂̂��Ɓj�̍����A���q�̔��q���i�����j�̎p�ƂȂ�A�V���Ă��l�Ɍ������Ĕ��ōs�����Ƃ���B
�ȑO���ɏZ��ł����y�n�ɂ́u����v�̖����킳���Ă����B�u���q�̔��q���v�� ���̒n�ŋr���x�߂Ĕ�ы������Ƃ̌����`�����c���Ă���B
�܂�ŕ����Ȃ��B����ȂU���̖�͑��߂ɗ[�H���ς܂��A�܂������邢��ɖʂ��������ɏꏊ�����d�C�������B�ڂ������ɂ�Ď���Ɍ����Ă���̂́u�ق���v�������B�P�ق��邪�삩��オ���Ă��Ă����̂��B
�P�ق���͌����ڂ���ɔ�ׂđ̂��������A�������ɕ����͂�≩�F����ттĂ��āA�_�ł���s�b�`���Z���B�ӂ�ӂ�ӂ�ƒ���щ��A�ꎞ�Ԃقǖڂ��y���܂��Ă��ꂽ��A�ǂ��Ƃ��Ȃ������Ă����B
�߂��͂��̃h�A����L�́u�ۂ������v������Ă��āA�ƂȂ�ɔ�����肷��B�ǂ����炩��������ł����V�����L�����ǁA�L�炵���l�I�e�j�[���ȂǍ̂�Ȃ��B�����ƍ���A�ӂƗ���������ǂ����֍s���A�߂��Ă���B�a���ق��̔L�Ɏ���Ă����ւ���
�A����邪�܂܁B�C���������Ƃ��́i�߂����ɂȂ����Ƃ����j�Â��Ă���B�������ߓN�w�҂̕��͋C���܂Ƃ��Ă���L�������B
�ۂ����Ƃ��Ă��邩��u�ۂ������v�Ɩ��t�������A�Ƃɋ������̐��i��m���Ă݂�ƁA����͂ڂ��肵�Ă���̂ł͂Ȃ��āA�S�ɓƎ��̒��z���������������Ă���L��
�Ƃ������Ƃ��������Ă����B���́u�ۂ������v�ƈꏏ�Ɍu���݂�B
���ꂪ���N�U���̕������������B�Ƃ͊��V��`�������Ɍ����W�H����]�ލ���ɂ���A100���[�g���قǍ���������J�����ɏ��삪����Ă����B�I�B�Ɛ�B�̍����ɂ܂�����I��A���v�X���痬�ꉺ��_�Ƃɗ��p�����삾�B���
�C�܂ł̋�����40�L�����[�g���ɖ����Ȃ����炢�Z���B���̂������������͌u���Z�߂��悤���B
�@�@�E������݂Ɏw���Ğ������ق��邩��
�߉ϐ�͓ߐ{�̂킪�Ƃ���Ԃ�15���قǂ̋����ɂ���B���̌�������ق���̊ӏ܉�Â����ƕ����Ă���B
�ł����ɍs���Ȃ��Ă������B
���̂���̎v���o���L���̒ꂩ��d�������A�L�ƈꏏ�Ɍu�����Ă����U���������������̂�����B
�@
�@�@�s�G�[���E�h�E�����T�[���@�iPieere de Ronsard�j
�@�@�@�@*�@�����͂�������~�J��B�F�l���v�Ȃ��k���𗷂��Ă���B�ǂ����G��܂���悤�ɁB
�@�@�@�@�@���R�̕�炵662�@ 2022.6.15
�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@
 ���������ɂ債���������ڂ��@----�����܂ł͊o���Ă��� ���������ɂ債���������ڂ��@----�����܂ł͊o���Ă���
 �@��܂��
�F���w�Z�ɓ���O�A�����ς�̂��Ȃ���܂��t���ėV��ł����B �@��܂��
�F���w�Z�ɓ���O�A�����ς�̂��Ȃ���܂��t���ėV��ł����B
�@�@���ԉ�(��������)�@�l�Q(�ɂ�)�@�@�R��(����)�Ɂ@�ő�(��������) �@����(���ڂ�)�Ɂ@
�@�@�����q(�ނ��낶��) �@����(�ȂȂ���)�@����(�͂���)�@�ӉZ(���イ��)�Ɂ@�~�Z(�Ƃ�����)
�ljH���̉��̍������͂ނ��낶��B10�ΔN���̎o�����̂Ă���Ɍ����J���A�{�̉H���ނ����Č��̒��ɉ������ݒǂ��H��������Ă��ꂽ�B�H�����T���ɐL�т��ɕ��Ă��܂����ɂ��Ȃ��������ǁB���������������ɐႪ�Ȃ��ĊO�ŗV�ׂ�u�s��v�̑��݂�z�����ł��Ȃ�����----�����Ȑ��E�����m��Ȃ��������̎q������B�~�Z��
�����̂͂����Ԃ��Ƃ̂��ƁB
 �@�ق��ɂ���ȉ̂��B �@�ق��ɂ���ȉ̂��B
�@�@�����̔L�͍��L�ł����낢���čg����
�@�@�l�Ɍ����Ă�����ƉB���@�@�@�@�@�u�B���v�ł�����Ɖ���ċ�����B���̎��X�J�[�g���ז��������B
 �@��������߂̂�������A�Ƃ����̂��������B�܂�������ɗׂ̎q�ɓn���V�сB �@��������߂̂�������A�Ƃ����̂��������B�܂�������ɗׂ̎q�ɓn���V�сB
�@�@�����߂́@��������@�@�@�����̎����@���炢��
�@�@�ꖜ����S�@��l�@��l�@��l�܂�
�@�@������ɂ����߂ā@�����߂ɂ킽�����@�@�@�@�����𑝂₵�Ă�������ǁA���5���炢�Ŏ��s����B
 �@����ɁA�Â��̂� �@����ɁA�Â��̂�
�@�����ς�j�ā@���I�푈�͂��܂����@
�@�������Ɠ�����̓��V�A�̕��@����ł��s�����͓��{�̕�
�@-------�@�����@���e�������Ă���ȏ㏑���̂͋C��������B
���I�푈�̏�������������̂��̂��Ȃ���A�{�����q���B��㑊���o���Ă���̂ɁA���̓��e�Ƃ́I
�c��̉e���Ƃ��Ă��z������ɃV���[���B���C�H�ȐS�ɑ��l�̌��t�͂���Ȃ�����Ă����悤���B�|���ȁB
 �@�R���̎���������O���̂�1���Ԕ��A������łĔ���ނ��B���ꂪ�����̎�d���B����܂�ދ��Ȃ̂ŁA�̂̂Ă܂�̂��v���o���āA������
���Ă����B�R����G�����w�����r�߂Ă��܂�����A�[���܂ŐO�����т���ςȂ��B �@�R���̎���������O���̂�1���Ԕ��A������łĔ���ނ��B���ꂪ�����̎�d���B����܂�ދ��Ȃ̂ŁA�̂̂Ă܂�̂��v���o���āA������
���Ă����B�R����G�����w�����r�߂Ă��܂�����A�[���܂ŐO�����т���ςȂ��B
�@�@�����̎�d��

�@�@���ː��̋K���������Č��V�C�^�P����ɓ���ɂ����B�����͒��������V�C�^�P�B�}�ɂȂɂ��l�߂ďĂ������B
�@�@���X�}���A�h�q�}���A�{���ˁA�~���`���������������B
���R�̕�炵661
2022.6.11
�@�@�@�@�@�@�@
 ���킢���ȂȂ̂����@�@�V�W���E�J���̕����@���N�R�x�ځB ���킢���ȂȂ̂����@�@�V�W���E�J���̕����@���N�R�x�ځB
���܂ꂽ���_�Œj�̎q�����̎q���͕�����Ȃ��A�傫���Ȃ��ċ��̃l�N�^�C���͂����肷��܂ł͂ˁB�l�����i������man�ő�\�����悤�j�݂�Ȑ��܂ꂽ����B���̖т͂ق�ق�A�^�����Ŗڂƌ��������傫���B
�u���͂�����v�Ɨ��e�ɃA�s�[�����邽�߂���A����Ȃɉ��F�������ڗ����ĉ��ɑ傫���̂́B
������ƕꂳ�W�߂Ă����x�b�h�͒g������B�ޗ��̓R�P�A�߂��̋��ɂ������Ă���������̍����тƔ����сi�Ȃ����āA������͔���
�͗l�̃z���X�^�C���킾����ˁj��̖̉ԕ�A���̂������s�B�J�����荞�܂Ȃ��悤�ɓ������牓���ꏊ�ɕ~���l�߂āA�ꂳ���������Y��ł��ꂽ�B
������ƕꂳ���ɂʼn��߂Ă��ꂽ����A�l�������̊k�������Đ��܂ꂽ�B����܂����̂܂܂̌Z�킪�c���Ă���B��Ȃ̂����Ȃ̂��B�ǂ����ɂ��Ă�����������
�B�O�ɏo�����Ȃ�����A�k�𒆂���c�R�c�@���̂���B��������ƕ����ꂳ�O������A������ƍ��}�����Ă����͂��B�����I
���Ɨ[�A�J�̓��͕�����ƕꂳ�A���c�q�ɂȂ����l�����̏�ɔ킳���ĉ��߂Ă����B�ӂ���ƒg�����āA��������������B���̓����Ƙb�������Ă���鐺���悭�o���Ă������B������o���炱�̐��𗊂�ɁA�͂��߂̐��������т����ˁB�����Ăǂ�����Ē���߂܂����炢���̂��A������Ȃ�----�B
������ƕꂳ��́A������[�܂ŗт̒����щ���Đ��Ȃ̉a��T���Ă��Ă����B�l�������̐���H�ׂ����āu�s�[�s�[�v���Ă����ނ��ǁA�^��ł����͈̂�x�Ɉ�C�����Ȃ̂ŁA���܂��a�ɂ�����Ȃ�����6�H�͂�������B�ł����v�A�����ɐV���������^��ŗ��Ă���邩��B�ǂ���������ƕꂳ��́A�ǂ̎q���ǂ̏��ŐH�ׂ�������������o���Ă���݂������B�������ɑ��������ł���悤�ɁA�݂�ȓ����悤�ɑ傫���Ȃ��čs������ˁB
�����̓����ɂ͒��a2.5�Z���`�̌����J���Ă���B������傫������ƃX�Y����������ɂ���Ă���B�ł��������V�W���E�J��������A�������X�Y�������邩��A�v���悤�ɂȂ�Ȃ��āA���̑���������Ă��ꂽ���̉Ƃ́u����������v���X�Y���ɖ��N���𗧂ĂĂ���悤���B�ł����N�͐����I�l�����łR��ڂ̕����̗l�q�߂Ă͊��������Ă���炵���B�ł��ˁA�ߏ��̐l���Ă�ł��āA�����̊W���J���Č���
�т炩���̂���߂Ă���Ȃ����Ȃ��B �������͗�����B
 �@2022.6.1�@�z�� �@2022.6.1�@�z��
���R�̕�炵660
2022.6.5�@
�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �w�E�C�O���l�ɉ����N���Ă���̂��x�@�������Q�̋N���ƌ��݁@�������D���@PHP�V�� �w�E�C�O���l�ɉ����N���Ă���̂��x�@�������Q�̋N���ƌ��݁@�������D���@PHP�V��
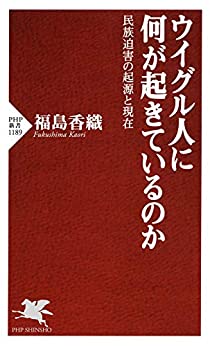 |
�~�J�̑���ׂ̍����J�������邱�̐����A�V�d�E�C�O��������Ɋւ���{��ǂ�ł����B
���ɁA�E�C�O��������ł̋������e��100���Ƃ������A�W�F�m�T�C�h�Ƃ��Ă�錻����----�������{�ɂ��e�����Z�����ꂵ�߁A����ɍݓ��E�C�O���l�ɂ��{������̒T���A���肪�y��ł���Ƃ������B
�E�C�O���l���ċ���Ə̂��ĝf�v����A�ƍߎ҂Ƃ��Ĉ����Ă���B�����Ə̂��Đ��]���A�������Q���s���Ă��邱�̌�����m��Ȃ������B�m�낤�Ƃ����Ȃ������̂�����܂��A
�����f���C�X��������`�������̌p����f�B����͕ʎ��ɏ������w�A���ƌ������̏��������āx�̓��e�ɏd����������܂ނ��낤�B
���ې����͋��҂̗ϗ��œ����B�Ē��̐V���\���Ƀ��V�A�̃E�N���C�i�N�U�������A��������{���푈�Ɋ������܂��
�̂ł͂Ȃ����Ƃ̋��|���������B�͂��߂Ă̂��Ƃ��B
�i�\���摜�̓A�}�]�����炨�肵�܂����B�j |
�E�C�O��������ɂ�2019�N�T���ɖK�₵�����A���n�Łu�������Ă��Ȃ������I�v�Ƃ����v���ɂƂ���Ă���B�����́A���ɃE�C�O��������͊Ď��Љ�
���A����͒Ɋ����� ����ǂ��B
�ǂ��ɍs���Ă��Ď��J�����̖ڂ������Ă���B�J�����ƃJ�����̋����͂ق��5���[�g���قǁB���������̎��_�ł��������{���E�B�O���i�����g���L�X�^���j�̌���A�����A�K���A�@����D�������ɏo�Ă������Ƃ�
�قƂ�NjC�Â��Ȃ������B�����̂��̂������ɂ͋����قǁB
���{�̎x�z�̖ړI�͎������A�j������Ƃ��č����n�т𗘗p���邽�߂��B�P�Ɏx�z��ڎw���̂��B�C�X�������̏K�����A���ꂱ�̒ʂ��ɂ��Ă��܂���A�Ƃ����f�B�X�v���C�͌������A���̗��ɂ���قǂ̔��Q���B����Ă����Ƃ́A�C�Â��Ȃ������B
�`�x�b�g��̏W�����K�ꂽ���A���̗��j�̔w���[���l���邱�ƂȂ��\�ʂ��������Ă����̂�������Ă���B�����Ƃ������茩�Ă����悩����----�B���������ւ͍s���Ȃ����낤
����B
�����͂����[���m��Ȃ��Ɛ^���������Ă��Ȃ��B���R���B���Ă������Ȃ��B����͎��̕s���̂Ȃ���킴�B
�������Ƀc�A�[�K�C�h�i���{�l�j�Ƃ���ȉ�b�����킵���̂��o���Ă���B
�@�@�@�u�^�N���}�J�������Ő��{�͊j�������s���Ă���ƕ����Ă��܂����A
�@�@�@�@���n�ݏZ�̐l�����A��ɃE�C�O���l�͂��̂��Ƃ�m���Ă���̂ł��傤���B�v
�@�@�@�u����`�B���������̂��Ƃ����ɏo���̂́A�댯��������܂���B�v
�@�@�@�u��������Ɏh�����Ȃ��ق����ǂ�����---�v
���ɒ������ڎw���̂́A��p�����߂����Ƃ��낤�B���͐�t�����Ɖ����_���B������R���i�U�ōs�����ǂ����B
�m�lK���̈ӌ��́A
�u��������������Ă��鍑�ɂ͐N�U���Ă��Ȃ��ł��傤�v�u���Ȃ������҂��܂��ˁB�v�������A���������҂Ƃ������@�����������B
�ƍN�����ȁB�������������ɂ����҂��Ԃ��c����Ă��邩�H���d��ɏo��\���͔ے�ł��Ȃ����낤�B
�k���S���͂��܂�Ƀ��V�A�̉����Ă��܂����B���̂����k�C����������ɑg�ݓ������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������|�����ۂ̂��̂ɂȂ�܂���悤�ɁB
���h��卑�A�����J�Ɉˑ����Ă���B���̎��_�ł��łɓ��{�͓��Ȃ̂�������Ȃ��B����������Ƃ͌����A�o�ϗ͂͂���Ǝv����������ǁA���̂Ƃ���̉~���́A���E�����{
���y�͂��߂������Ȃ̂�������Ȃ�-----���{�̎��Ԃ͎����ɖR�����ア���Ȃ̂��Ǝv���m�炳�ꂽ�B����A�v���m�炳�����B
���{�l�́A�y�V�I�ō��̕��a���N����邱�Ƃ͂Ȃ��ƐM����P�����H�͂ǂ����痈���̂��B�O������O��I�����W����邱�Ƃ��Ȃ��������Ƃ��傫�����Ƃ��l����B
�ߋ��̔e�����L���̒�ɂ��钆�����{���A�����Ɂu���v�������Ă���̂ł́H�����l���邱�Ƃ�����B���邢�͐��E���e�̖����̂Ă���Ȃ����B���̂����ň�̈�H�\�z��ł������A���؎v�z���������悤�Ƃ��Ă���̂��B
�悭���悤�A�l���悤�B�������B
��L��K�����炱����������ꂽ�B
�u�u�l�ނ���ՂƂ��������͑��݂��Ȃ��v�i�����͌����A����̒n��E�W�c��O��Ƃ��āA���̒n��E�W�c�ɑ���R�Ɠ����̉\�������Ă���Ƃ���ɐ��藧�B���Ȃ킿�A�P�ʎЉ�̓��ꐫ�iparticularism�j�������s���̊�Ղ��Ȃ��B�ێR���j�u�`�^��S������j�v
������Ă��܂��܂ȋ^�₪�������悤�ȋC������B
�@
�F�l�ɂ��͂��B�f���t�B�j���[���A���[�X�t�����[�A�V���N���N�A�~�j�J�[�l�[�V����
������ꂽ����Ȃǖ����̂ŁA�����S�~�܂ɕ�݁APP���[�v�Ō���ł���A�������̂��́B
�@�@�@�@���R�̕�炵660 2022.6.2�@
�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@
 �@�N��300���ő������ �@�N��300���ő������
�J�̊Ԃ�D���ă`���[���b�v�̋����̖x��グ�̒��B�������͂����A�����Ă��Ǝv���قǂ̊��������B�f�g�b�N�X�Ǝv���悢���A�Ȃ��Ȃ������������Ȃ��B
�H�ɋ����͔�����������炩�A�����Ă݂�Ǝv���̂ق�����������Ă���B���ł͂��̏t�ɉԂ��炩����̂��������ς��ŁA�����Ă���T���̏����ɁA�@��グ�������͂₹�ق������܂܂������B�����Ƃ��Ắu�����̎d���͍ς܂����v�Ƃ������Ƃ��B���̐���̂��ƂȂǂƂĂ��l�����Ȃ��قǂ̒����Ԃ�������Ă����̂ɁB
�ߐ{�ɗ��āA�����������Ă����ɂ͋������B���̉��F�̃`���[���b�v�ȂǁA1������R�����q�������ł��Ă���B
�����͐���Ċ������A�l�b�g�̑܂ɓ���ă~�j���O�̏����ɒ݂艺���ĉĂ��z������B�n�ʂɒu���ƃl�Y�~������Ă��āA�a�ɂ��Ă��܂�����B
�ǎ��ȒY�������̃`���[���b�v�̋����B��������Ă��ƁA����̍����Ă��`���[���b�v���ł��������B
�@�@�@�@ 1----3----9----27----81----243----��
1----3----9----27----81----243----��
�@�@�@�S���ł�������H700���炢�H 
 �����������ȓ����ҁ@�V����PC �����������ȓ����ҁ@�V����PC
�V�����p�\�R���iNEC LAVIE
�f�X�N�g�b�v�^�j�͏����ɓ����̂Ŗʔ����B�����������Ȃ��m�点�͑������̂́A���p�\�R���́u�d�������Ă���R�[�q�[�ꂽ�v������v���N���͊����I�ɑ����B------�ł��J�����ƃ}�C�N�̃f�r���[�͂܂��B���ԂɊ���N���ȂǍl���������Ŋ炪�Ԃ��Ȃ肻���B�����͕����܂܂��낤�B
�t���̉�ʂ��c�����ƌ����Ă���B20�N�O�܂Ŏg���Ă����u���E���ǃf�B�X�v���C�́A�����������̂���\������Ă������B���Ƃ�����HP�̃o�b�N�Ɏg���Ă��锖�̔w�i�́A�{��������Ƃ���
�A
���z���v�킹�銴�G�������Ă����B�f�W�^���J�����ƃt�C�����J�����̎ʐ^�̏o���オ��Ɏ��Ă��邾�낤���B���͂��̏ۂ̕@�̂悤�Ȓ����u���E���ǂ����������B
�u���E���ǂŎv���o�����B���̎O���F���r�[���œ��e���ĕ\�����Ă����u�ۂ̕@�v�́A�Ă��t����h�����߂Ɂu�X�N���[���Z�[�o�[�v�Ȃ���̂��A��ʂɗ����Ă������Ƃ��B
1980�N��̏I��肩��90�N�ɂ����āA�������̃o�u���̎���ł��B���[�v������p�\�R���ւƈ�C�ɗ��ꂪ�ς�������낾�����B
�c�ɂ̒��ɂ��g�������Ă��āA��X�܂���X�[�p�[�̈�p�ɁA�p�\�R�������ł����̂��B�Ⴆ���̃X�[�p�[�̖��O���u�C�Y�~���v�Ɓu�I�[�^�j�v�Ƃ���ƁA�o�������ăp�\�R�������
���āA�������̓X�ɂ́u�x������Ȃ����v�Ƃ����ӋC���݂������Ă����B
�����ł킽���A��������S�����N���N�ƗN���Ă����B�u�C�Y�~���v�ɓW�����Ă���p�\�R���̃X�N���[���Z�[�o�[�Ɂu���������̓I�[�^�j�Łv�B�u�I�[�^�j�v�̔����̃p�\�R���ɂ́A�u�������グ���肪�Ƃ��������܂��B�C�Y�~���v�Ɛݒ肵�ē����A���Ă����̂�------�B
�ق�ق�A�����̍s������{�C�ɂ���邶��Ȃ����B�i�ƐS�̐��j
�{���̓C�Y�~���ł́u�C�Y�~���ł����������y����ł��������v�ƁA�I�[�^�j�ł́u�{���͂��肪�Ƃ��������܂��B�I�[�^�j�v�Ɨ��������������ǂˁB
���R�̕�炵659
2022.5.29
�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@
�@ �ӂ����т�����B�����Ԃ����\�t�g�@�w��ǂ�ڂ��z�b�c�F���v���b�c�ӂ����т�����
�x�̋C�����B �ӂ����т�����B�����Ԃ����\�t�g�@�w��ǂ�ڂ��z�b�c�F���v���b�c�ӂ����т�����
�x�̋C�����B
�V�p�\�R���ɁA20�N���̃\�t�g���C���X�g�[�����ׂ������R�T�ԁB�����̂��Ƃ��ꌩ���X�^�C���̂܂ܕ�����������HP�B
���̂��тɕς���Ă����F�̐ݒ�i��15��ށA�Z�L�����e�B�����łɂȂ���W-10�ł��j��������������z���A���r�܂ŃC���X�g�[���ł��邪�A
�u�f�[�^�\�[�X�̐ݒ�Ɏ��s�A���W�X�g���ŃR���|�[�l���g��������܂���B�v
�u�K�v�t�@�C�����_�E�����[�h���Ă��������v�Əo�Ă���B�i�K�v�t�@�C�����ĉ���������Ȃ��j�\�t�g���g�����܂ŃC���X�g�[�������t�@�C���������I�ɍ폜���Ă��܂��B�i�߂Ȃ��B����----�B
���鎞�i������Ō�ɂ��Ă�����߂悤�j�ƁA�v�����āu�����v���N���b�N���Ă݂���A�Ȃ�Ɓu�������܂����v�ƕ\�����ꂽ�B
�ߑR�Ƃ��Ȃ��B�������ꂽOS�͂ǂ�ȋC�����ł���̂��B�u�����v�ʼn������������Ă������������A����������肾�����̂��B�Ƃ�����A�����ɂ͕ς�肪�Ȃ��B32�r�b�g��64�r�b�g���W�Ȃ������B
�l���Ă݂��CPU���������ʂ������邾���������B
�����A����̌��ʂɔ��q�������Ă��܂����B�T�[�o�[�Ƃ̌_��͑����Ă���̂ŁA���̍ېV�����\�t�g����ɓ���āA���e���̂��̂�V�������悤�ƈӋC����ł����̂ɁB�U��グ�����Ԃ��̂����čs���ꂪ�Ȃ��B
�����A���Ƃ̓t�@�C����]������ffftp���ŐV�ɂ��āA�n�b�J�[������Ȃ��ẮB
�O�͂T���̋L�����Ă���B�f���t�B�j���[�������J�B�[���u���[�̃~�i���b�g�𗧂ĂĂ���B
�@
�@�@�@
�@�@�@�@�@ ���R�̕�炵658 2022.5.26
�@�@�@�@�@�@�@
�@
 ���N�̏t�̂��������͂����ׂ� ���N�̏t�̂��������͂����ׂ�
�����A5��ڂ̃p�\�R��������Ă��邱�ƂɂȂ�܂����B�J�����ƃ}�C�N�A�X�s�[�J�[�t���Ȃ̂ŁA���܂܂ł̂悤�ɃJ�������}�C�N���Ȃ��A�萻�̃X�s�[�J�[���g����
��Zoom��c�Q���Ƃ������g�̋����v�������Ȃ��Ă��ǂ��Ȃ�̂ł��B
�@�i�p�\�R�����g����40�N�B��䂪����10�N�̎����������Ǝv���ƂȂ����݂��݂��܂��ˁj
����2003�N�ł�HP�쐬�\�t�g����肭�C���X�g�[���ł��邩�ł��B�Ȃɂ���64bit�@�ɓ����̂͏��߂āB���܂܂ł����܂��ܖ����N�����Ă���\�t�g�Ȃ̂ŁA���邢��
�uOS�{64bit�v�ƌ��܂����邩������܂���B�����������̂͏d�X���m�Ȃ̂ł��B�Ȃɂ���Â��I�i��ʌ݊���������v
�Ƃ͍l���ɂ����̂ł��j
�A�x�����܂Łu���R�̕�炵�v���X�V����Ȃ�������A�����ł��������Ă���F����A����HP��657�Ԃ������ďI�������Ƃ��l�����������B
�����Ԃ̂����ǂɊ��ӂ������܂��B
���ʁA64bit�ł̓���͕s�\�ł����B�i4��24��)
�V�K�܂�������}�邩�A���̂܂ܒ��߂邩�B�v�Ē��B�i���p�\�R����Վ��Ɍq���ŃA�b�v���܂����B�j
�ߌ�A���͂����肵�Ă��āA�R�����n���Ă��܂����B�n���M���A�V���L�A�^���m���A�E�h�A�����̃Z���ȂǁB����͂��������V�w���ɂ��܂��B���ꂱ���c�ɕ�炵�̑�햡�ł��傤�ˁB
 �@�V���L�ƃ^���m�� �@�V���L�ƃ^���m�� 
�P�ь�̉ԂƂڂ݁B�����ׂɂ��낪���炵�� 
���̒�͉Ԃ�����
����̎O�{�̂�܂�����@----�����ł��B
���R�̕�炵657
2022.4.24
�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@  Anne
with an �gE�h �@�@ �w�A���ƌ������̏����x���ς� Anne
with an �gE�h �@�@ �w�A���ƌ������̏����x���ς�
L�EM�E�����S�����̏����w�Ԗт̃A���x�i1908�N�j�����ĂƂ����e���r�h���}�V���[�Y�B
2017�N�J�i�_CBC��Netflix�ɂ�苤�����삳��ANHK��2021�N9������2022�N3���܂ŃV�[�Y��1����3�܂ł̑S27���f���ꂽ�B���̌㐧�삻�̂��̂����~����Ă���B
�V�[�Y��3�Ő���𒆎~�������R�́uCBC���̔��f�ŁA�����ڂŃJ�i�_�̎Y�Ƃ̊Q�ɂȂ�Netflix�Ƃ̋�������͂�߂�v�炵�����ڍׂ͕s���B�����S�����̍�i�Q��ᔻ���邱�Ƃ��������炵���B�ŋߐ���ĊJ���肤�����オ���Ă���悤���B
*2022.4.24���@���{�o�ϐV�������L�����
�u�l�b�g�t���b�N�X�̍��������]�@���}���Ă���B�R���i���������������������A����҂̑I�������L����A��������������Ă���B�R�X�g�͍X�ɍL����B���E�I�ȃC���t���̉e���ȂǁA�o�c�����������Ă���v
�J�i�_CBC�͂������ɂ����̂��H���ꂱ��l����Ƌ����[���B
�����ꂾ�����B�^�悵�Ă�����27���S���ɂȂ��Ă悤�₭���I���邱�Ƃ��ł����B
�Y��Ȃ������Ɉ�ۂ������c���Ă������B
�@ �@NHK��HP���炨�肵�܂����B
���肪�Ƃ��������܂��B �@NHK��HP���炨�肵�܂����B
���肪�Ƃ��������܂��B
���낢��ƍl���Ă��邤���ɁA�������͂ɂȂ��Ă��܂����̂ŁA�ʃy�[�W��p�ӂ��܂����B
�@
���R�̕�炵657
2022.4.17
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
 ��̂ڂ肪�앗�ɕ��� ��̂ڂ肪�앗�ɕ���

�����͓ߐ{�A�R�����˂܂ŗ��ꉺ��߉ϐ�i�S��150�q�j�̌����̖̖���̗���B����̖����u������v�̋߂��𗬂��A�Ăɂ͉͎��^�����������B
�t�A����҂��ė��݂ɓn���ꂽ���[�v�Ɍ�̂ڂ肪�݂邳���B�����͂��Ԍ����Ă猩���ɏo�����Ă����B
�܂��Е��̐�݂ɗ��Ă�ꂽ�|�[���ɁA�����Ē������C���[���[�v�����t������B�|�[���̊�b�̓R���N���[�g�Ōł߂��Ă���̂͂�����B�Ί݂܂ł�60���̒n�ʂ�----���̏ꍇ���ʂ��܂܂�邪�A���C���[���[�v��ʂ���
�����B
���̎��_�ł̓��[�v�͂���܂܁B��̗���̒������[�v����������Ă���B���̃��[�v�Ƀt�b�N�������A���Ɍ�̂ڂ�������Ă����̂��菇�炵���菇�ł͂��邪�B
���[�v�͐��̒��ɂ���B���܂ł���h�����𒅂���ƈ����A����ɋt�炤�悤�Ɍ�̂ڂ���ЂƂ��|���Ă����B
�P���Ȃ悤�����Ȃ��Ȃ�����B���̒�R�͈ꎞ�̂��̂����A�����̂ڂ肪���C�̈��͂��l���āA�o�����X�ǂ��݂邳�Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
�Ί݂ɓn���ꂽ���[�v���A�N���[���ň�������A�K���Ȃ���݂��܂�̂ڂ肪���o���Ă����B
���𗧂ĂȂ��畗�������A��̂ڂ�͋���j���ł���B
���̋G�߂̕������B������̂ڂ�̂����ۂ�����t�łĂ���B
�@*
����̒��F�������͋���������BB�̃����o�[T����ƈꏏ�ɋ������܂Ŋy���̂́A�����S�N���O�̂��ƁB
�@* �͎��^�@----���ʂ̓J�W�J�ƌĂ�邱�Ƃ������B�����͎��Ɏ��Ă���B�����̉̕P�B
���R�̕�炵656
2022.4.14
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@
 ���N�̓J�G���ł� ���N�̓J�G���ł�
�n�b�J�N�������A�}�K�G�����Ǝv���Ă��܂������̓��A���N�̓ߐ{�삪�������ق̎��R�����̃e�[�}�́A���N�̃Z�~�����ɑ����āu�J�G���E�^�v�Ƃ̂��m�点���������B�Ȃ����̋������ɋ����Ă��܂��B
�悵�悵�B���N�̊y���݂���������B���͂ɖڔz�肵�ċL�^����Ȃ�āA�h���̖��������Ƀs�b�^���̃e�[�}�ł͂Ȃ��H�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�ւ�
2022.4.1�`11.1.�@�܂ŁB
��ɏ����W���Ă���J�G���͂���B
|
�@�j�z���A�}�K�G���@�i���{�J�^�j |
�悭���邠�̏������^�B�����������Ȋ�����Ă�������q�B |
�@�g�E�L���E�_���}�K�G���i�����B���^�j |
�g�m�T�}�K�G���ɂ悭���Ă���Ƃ������B���܂܂Œm��Ȃ��������A�Ȗ،��ɂ̓g�m�T�}�K�G�������Ȃ��炵���B�w�ɋz�Ղ���
�����āA���̎�ނ͂ǂ�����Ėؓo�������̂��낤�B���܂��Ɂu������@��v�������I���Ƃ̂��ƁB�J�b�R�����@���āA�N���Ɏ��Ă��Ȃ��H |
|
�@�A�Y�}�q�L�K�G���i��寊^�j |
���̃q�L�K�G���B���ł́u�q�L�v�ƌĂ�ł����B�ł����̂ŋC��t���悤�B���邾����B |
|
�@�E�V�K�G���@�i���^�j |
���邳�����c�B�S�[�S�[�钆�ɑ������c�B
����O�������Ɏw�肳��Ă���̂ŁA�{���͕ߊl�̑ΏۂȂ̂����A�ǂ�����ăA�C�c�����܂���H
�@�K�r�`���E����������O�������̈��B |
�@�@�@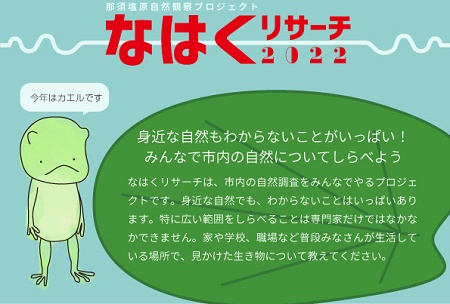
�@�@�@�@�@�ߐ{�삪�������ف@�@<http://www2.city.nasushiobara.lg.jp/hakubutsukan/>
�@
�@  �@�A�}�K�G�����������Ă���̂��@---�@������P�̃n�b�J�N���� �@�A�}�K�G�����������Ă���̂��@---�@������P�̃n�b�J�N����
�@�@�@�@�@���p�@�@�@���M�ȃ~���I�\�E��
���ꂠ��B���炟�B��̋��ɃA�}�K�G�����^�L�V�[�h���Đ������Ă���悤�ȐV�肪�̂����ċ������B�������A�����������тăs�J�s�J�����Ă���B���ꂩ��ԂɂȂ�͂��̊ۂ��삳���o������Ă����B
�u�������e���g���Ă���݂������v
�u�e���g���ĉ�������H�v
�u�R���|�b�N�����T�[�J�X������݂����v�Ƃ��قȉ�b�����킷�B
�̗t�����d�ɂ��d�˂āA��ɂڂ݂����C�������Ă���B���̗̉������ƂƂ��ɂ������قǂ��Ă����B
����͔��p�@�B���ꂩ�炮��t���L���A�Ԏ��̉Ԃ��炩�������ƁA�ۂ��傫�ȉʎ������点��͂��B�����ʼn�M�܂Ƃ��ė��p�����悤���B�t���L�������̑��݊��͔��[�ł͂Ȃ��B
�u���Ƃ͑������Ӗ�����̂ŁA�t�͎��ɂT�p��������9�p��������A���݂ɕω����Ă����B
�@�@
�@�@�@���R�̕�炵655 2022.4.8
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@�@ �@��c�m�C���S���Ȃ����@�@----�@���
�Ђ� ���R�̂Ђ� �@��c�m�C���S���Ȃ����@�@----�@���
�Ђ� ���R�̂Ђ�
�@��c�m�C�i1938.1.2�`2022.3.27�j���{�̃J�k�[�C�X�g�A��ƁA�G�b�Z�C�X�g�B
���{�̃��o�[�J���b�N�c�[�����O�̐��҂ŁA���{���n�߃��[���b�p�A�k�A�����J�A�I�[�X�g�����A�A�j���[�W�[�����h�Ȃǐ��E�e�n�̐���J�k�[�ŗ�����B�G���̋L�҂��o�č�ƂƂȂ�A��E�J�k�[�E�����Ɋւ��钘���𑽐����\�B���ǐ��g���͌������Ή^���ɂ��Q�����Ă���B�ȉ����@Wikipedia���
�w���{�̐�𗷂���x1982�N��9����{�m���t�B�N�V�����܂���܂������납��̈��ǎ҂������B���ɎG���wBE-PAL�x����ɓ���Ɩ����r�߂�悤�ɂ��Ă��̓Ɠ��̕��̂�ǂ������̂������B
�m���Ă���̂͒Ŗ����Ƃ̐[���e���ŁA�Ŗ����͖�c�m�C���J�k�[�̎t�Ƃ��ċ��A��c����̃J�k�[���K�N��ʂ��Ă̌𗬂͐��X�̒����f��ɂ���ďڂ����B
������Ɨ₽�������Ă݂͂����A���̓V���b�N���Ă���B1980�N�ォ�璘���ǂ݁A�G�b�Z�C�𖡂킢�A���̌y���Ȍ����⎩�݂Ȑ������Ɏ䂩�ꑱ���Ă��Ă������炾�B
�����̍�i�œ��Ɉ�ۂɎc���Ă���̂́A
�w���{�̐�𗷂���x�A
�w�厩�R�𗷂��� �J�i�_�E�i�V���i���p�[�N�E�L�����s���O�@1984�N
�w�̂�т�s�������x1986�N
�w�k�ɊC�ցx1987�N
�����̖{��ǂႢ������30�N��̏H�̏��߁A�A���J���b�W�o�R�ŃA���X�J�ɂ͂���A�悤�₭���[�R����̐�݂ɗ����Ƃ��ł����B
�����ʂ��Ė�c���[���h�ւ̎v�����������������ɁA�����ڂɂ����Ƃ��͂��������ɗ��������ނ��Ƃ����ł��Ȃ������B��c����̐��_�̈�[�����L�����悤�Ȏv���ŋ�����t�ɂȂ����B
����Ă������[�R���́A���₩�ȋu�̂Ȃ���̍��Ԃ�앝�L���ɂ₩�ɁA���邢�͌������������ꂭ����A����̕��������݂ɌJ���Ă��邩�̂悤
�ȕ\��L���Ȑ삾�����B
�@�@�w��������ēs��̒��ցx1988�N
�@�@�w�����ƃ��[�R���x1989�N
�@�@�w����l����x1992�N�@����O�Ƃ̋���
�@�@�w��ւӂ����с@��c�m�C�J�k�[�E�G�b�Z�C�E�x�X�g�x1993�N
�@�@�w�k�̐삩��x1994�N
�@�@�w�_�߂闷 �A���X�J�̐�ӂ���x1996�N
�@�@�w�J�k�[���E�K�N�x1997�N
�@�@�w���[�R���Y���x1998�N
�@�@�w���N�L�x1999�N
�@�@�w���E�̐�𗷂���x2001�N
�@�@�w���[�R����ʼn���x2016
��c�����R�ی�̂��߂ɒ��ǐ��g���͌������Ή^���ɎQ�����Ă������Ǝv���o���Ă���B�������Ή^���ɎQ�������J�k�[���y���ޗF�l�ɂ��Ɓu��c���J�k�[�ɍ����Ă��邾���ŁA�I�[�����������߂Ă����v�B�炵���B
�@�@�w�_���͂���Ȃ�! �V�E���{�̐�𗷂���x2010�N
���́u�I�[������v���o�ɂ��ẮA���̖`���ƁE�A�����Ȃ���Ɠ����R�x��ɏ������Ă����F�l���������Ƃ������Ă����B�u���������ǁA���������ɂ��邾���Ō�������Ă���悤�������v�ƁB���͐��_�̋����̕\��Ȃ̂��B
�������_�Ɛ��E�ɉH�������_�Ƃ��������A�������݂�ꏊ�Ɛ�������[�����đI�т����Ƃ����ӎv�����������Ă����l�������B
�R�c�R�c�Ɠ��X�n���ɓ����A���ɑ吨�ɓK�����邱�Ƃ�I�сA�q���̎����ɐS���������Ă������̓���̑��݂������B���Ԏ�������Ă���悤�Ȑ��E�ɐ�����l�������B�����������Ă��錻�݂̏ꏊ�����яo���āA�V�������E���o�����邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ��Ɗ�]���������Ă��ꂽ�M�d�ȑ��݂������B
�Ō�̍�i�́w�i�C����������Ă݂Ȃ����x�B
�����̓y�����ꂱ��ő͐ς�����A�J�^���N�g�ƌĂ�闄�݂����z���A�i�c�����V�т̍L����v�����e�[�V�����߂Ȃ���A���[�[���悹��ꂽ��肩���̂悤�ɗ���Ă݂����B
�傫�ȃN���[�Y�D�ł͖��킦�Ȃ��A�g�߂ȏ����Ȍo�������̓��ɂ��܂��Ă��������B�@�����A���̋C�����͗ǂ�������܂��B

�@�@�J�^�N�����ԕق点�Ȃ���炫�͂��߂��B�킩���ĂĖ�7�N�B�������͂ڂ� �B

�@�@�p�\�R���̑O�̂����̈֎q���炱��Ȍi�F��������B
�@�@�@�@�@�@�@���R�̕�炵654
2022.4.3
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@ �@���Ɍ�������Ă��܂��@�@�@----�s�v�i���������悤�@ �@���Ɍ�������Ă��܂��@�@�@----�s�v�i���������悤�@
�u�����ł����B�r���Œ��v���Ȃ����ƁB������ߋ������������Ă������ɓM��Ă��܂��ƁA��Ƃ��i�݂܂����v�Ƃ������̒��̕ʂ̎����A�����g�Ɍ�����������B
�u�����ł��v���C��ɉ����鎄�B
�n�߂Ă݂����A��͂�Ƃ������\�z�ʂ���Ă��܂����B
�t�̑�|���̎n�܂�͂܂����[�ꏊ���炷�ׂĂ̂��̂���������o�����Ƃ���n�܂�B�S���u���m�v�Ɋ��������Ȃ��悤�L���L��������āA�v��Ȃ����̂ʂ��Ă����B������
���܂��o���オ���Ă����̂ŁA���킸�K���[�W�ɒu���Ă����A���̃S�~�̓��܂ŖڂɐG��Ȃ��悤�ɂ���̂��R�c�A�Ɖߋ��̂���������w��ł���̂����B
�a���̉����牽����������������Ă��āA���̏�̊o���̂���M�Ղɋ������B
�u�s�p�i�A�p���̂��Ɓv�����܂ł͗ǂ�����----���̉��ɏ������u�����炭�̂Ă��Ȃ����낤����A����܂ŕۑ����Ă������v�Ƃ������B���A����ǂ��m���Ă���----�B
���āA�����炭�܂łɑ�|�����ς܂���ɂ́A���������ǂ�����ĐS�̂����߂�t�����炢���̂��낤�B�v���̂����������m�ɑ��鎷���͂ǂ�����Ď̂Ă��炢���̂��낤�B����炷�̂ɕK�v�Ȃ��͓̂��R�c���Ƃ��Ă��A���N�Ԏg���Ă��Ȃ����̂͏������ׂ����낤���B
�����������ɓ��ɒg�����Ȃ邱�̎����ɁA�����̂悤�ɖ������B�����ς�Ƃ������͂ǂ��ɂ���̂��B
���Ȃ��̂���A�����ƁB�@�@�@�i���x����B�ǂ�����Ă���ȂɊ���肪�ł����̂ł����B�j
�@
 �C�`�����\�E�A�j�����\�E�A�T�������\�E�@�@�T�������\�E�͒����� �C�`�����\�E�A�j�����\�E�A�T�������\�E�@�@�T�������\�E�͒�����

����̓L�N�U�L�C�`�����\�E�i�e�炫��֑��j �C�`�����\�E�̓C�`�Q�i���)�Ƃ��ĂтȂ�킷�B
�@�@�����Ȃ��t�ƉԌs���������Ă����̂ŁA���O������g����邽�߂ɁA�Ԃ݁i�A���g�V�A���j���������Ă����B
�@�@�@�@����ɗΐF�̗t�ɕω����Ă��Ă���B
��̂�����������C�`�����\�E���Ԃ��J���Ă����B�L�N�U�L�C�`�����\�E�A�C�`�����\�E�A�A�Y�}�C�`�����\�E�A�����ăj�����\�E�����B�݂�Ȃ悭���Ă���B�t���ς̈Ⴂ�Ō������邪�A�炭���ԂŌ�������̂���̕��@�B
�݂�ȉ����t�̐敺�B�@�X�v�����O�E�G�t�F�������iSpring ephemeral�j�̒��Ԃ����B
�@
 
�@�@�@���́@�C�`�����\�E�@�@�E�̓j�����\�E�@ �ەق̉Ԃ͂悭���Ă��邪�A�t�̌`�ɈႢ������B
 ���ꂪ [�o�^�[�J�b�v�X] �̕c�@�뒆�ɑ����č��������Ƃ��B
���ꂪ [�o�^�[�J�b�v�X] �̕c�@�뒆�ɑ����č��������Ƃ��B
���R�̕�炵653 2022.3.30
�@�@�@�@�@�@�@
 �S�Q�N�ڂ̂����� �S�Q�N�ڂ̂�����
���߂ăJ�i�_�̒n�̂́A���܂���42�N�O��7���̂��Ƃ��B���X�A���[���X�o�R�Ńo���N�[�o�[�ɔ�сA�嗤���f�S���ɏ���ăW���X�p�[�ցB�����ŎԂ���ăG�h�����g������o���t�ւƃh���C�u�����B�������J�i�f�B�A�����b�L�[�̎R�����邱�ƂƁA�S���ɏ�邱�Ƃ���Ԃ̖ړI�������͓̂��R�����ǁB
�@�@�i���X�̋�`�ŁA�o���N�[�o�[�s���̃`�P�b�g���_�u���u�b�L���O���Ă����̂����������I
�@�@�@�@�J�E���^�[�̂��o����̋@�]�Ŏ��̕ւ��m�ۂ��Ă��炢�A
�@�@�@�@�@�u���Ȃ��͓V�g�ˁv�Ƃ���������B�i���T���[���X Los Angeles�@�V�g�����̒��j
���̐܂ɔ������G�͂��������̂S�Q�N�Ԃ����Ɩ{�̂�����Ƃ��Ďg���Ă���B
�[�͖щH�����A���Ȃ��ȂƗ͂Ȃ��{�̊Ԃɋ��܂��Ă��邵����B�{���炷�����͂ݏo���悤�ɂ���āA�T�C�h�e�[�u���̏�ɒu���Ă����B�������薰��邨�܂��Ȃ��̂悤�ɂ��C�ɓ���̖{�𐔃y�[�W�ǂ�ŁA���ꂩ�烍�b�L�[�̎ʐ^�ߗ��̎v���o��䍂��Ă���d�C�������B�������Ɓu���܂Ƀ��b�L�[�̖��v�����邱�Ƃ������āA���̒��͂����킹�B
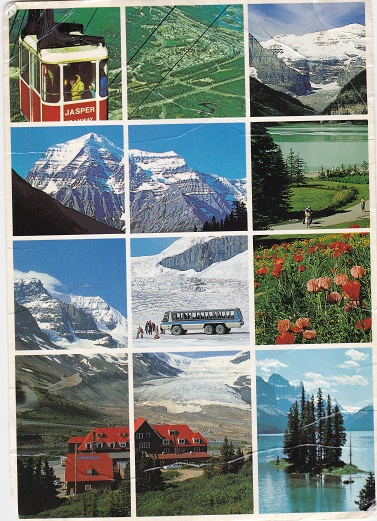 |
1980�N�̉Ă͂܂��܂��ό��q�͏��Ȃ��āA�u����v�̊Ŕ�ړ��ĂɁA�����̔�э��݂Ń��[�e������ꂽ�B�S�l���̑傫�ȕ�����30�h������50�J�i�_�h���ƈ����B
�W���X�p�[�̃X�J�C�g�����œo��������ɂ́A�V���^�C���x�b�N���Q��Ă��āA�Ȃ�Ȃꂵ���߂Â��Ă����B
���C�N���C�[�Y�ƎU�����A�I�j�Q�V�B�J�i�f�B�A���J�k�[�𑆂������A���܂�i�܂Ȃ��B���邮��ӂ������Ă���B
�}�E���g���u�\���̃g���C����������B�X�͂���̃V���g���܂��͏W�܂��ė��ꂭ����B���܂�̋}���Ȃ̂ŁA�����ƌ��Ă���Ɛ��������ɂȂ�B䕂̎����������B
�R�����r�A�E�A�C�X�t�B�[���h�͕X�͂��h�̂����߂��܂ŗ��Ă����B���͐��S���[�g������ނ��Ă���炵�����B
(���Ɣ�э��݂ŕX�͂������镔������ꂽ�I�j
�}���[���̂Ȃ��̃X�s���b�g�A�C�����h�ɂ́A�w�Ԗт̃A���x�̍�҂���ԍD�����Ƃ��������l�\�E���n�ʂɂт����萶���Ă����B�ӂӊ������ȁB |
 �A�T���̊L�k���Ԓd�� �A�T���̊L�k���Ԓd��
�g���J�`�łƂ�Ƃ�Ԃ��Ĕ엿�ɂ���B�j���g��������Ί�Ԃ̂ɁA�������̎����j���g���������Ȃ��B
�@�@ �i�L�k��H�ׂ�����ƁA���̊k���������肷��̂ł��j
���̌����́A�u���̏Ƃ�Ă��A�A�T���̂��z�����A�V�R�ڂ̂��Z���A���˂��ƃJ�j�J�}�̂ʂ��B����Ɍ��t�T���T���[���B
����ł͒��F�̐H��Ȃ̂ŁA�J�{�`���𔖐�ɂ��ďĂ������ƁA�A���~���ɕ��Ńg�}�g�\�[�X�����������A�`�[�Y���悹�ăg�[�X�^�[�ɁB�i����͖��ςɁj�����ăf�U�[�g�̓I�����W�B���˂���8�{��130�~�Ƒ��ł͍l�����Ȃ��قLj����B�������ƐH�ׂ�B

�������̗̓��C���h�X�g���x���[�B�n���Ɣ��������B
���R�̕�炵652 2022.3.26
�@�@�@�@�@�@�@
 �@�����݂�
---- �����݂�E�N���C�i�̐F�炩���߂� �@�����݂�
---- �����݂�E�N���C�i�̐F�炩���߂�
�@�@�@
�R�X�~���@��俁@�@�@�t�̐F�A�ԐF�ɕψق������ĔY�܂����X�~���B
���������ƂɊw���́@V.japonica �@ �Ԃ̐F�⑤�ي�̌`�Ȃǂɂ���āA����ɍׂ������ނ����B
�����5�`10�Z���`�B���̒�ł͏t��Ԃɍ炭�X�~���B�����̒����炢�̊Ԃɂ��Ԍs��L���Ă����B�����͖k���������āA�֓��k���ł͐�̗\�o���Ƃ����̂ɁA�����ۂ܂������Ԃ��J�����B
�Ί_�C�`�S�Ɠ����悤�ɁA���̂Ȃ��ɍ������낵���������A�n�����オ�����悤���B
������A�~���O���炫�B���ꂩ������A�����炪�炭�B

�����Đ�̒��B ����͂��Ȃ���Ă���L�N�U�L�C�`�����\�E�B�@�@�@�@
�@�@�@�@�@���R�̕�炵652 2022.3.22�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@ �n�肪�����@�@�@�@�@2022�N3��16���@�ߌ�11��36���@�@�킪�Ƃł͐k�x5�}�C�i�X �n�肪�����@�@�@�@�@2022�N3��16���@�ߌ�11��36���@�@�킪�Ƃł͐k�x5�}�C�i�X
�������u�������v���ƒn�̒ꂩ�畷�����Ă���悤�ȉ������āA������̎R��������ɂȂт��Ă���悤�ȋ�C�̗�����@�m�����Ƃ���A�n�k���N�����B���̊��o�́A��_�W�H��k�ЂⓌ�k��k�Ђ̎��Ɠ������B����͖钆�Ȃ̂ŁA�h��ɕq����賂����Ȃ������B
�@�E11��36��50�b����55�b�@�n�肪�����B
�@�E�@ �@�@�@55�b����37��20�b�܂œ����̗h��
�@�E11��38��40�b����80�b�ԁ@�㉺����������
�@�E���t���ς��A12��55������30�b�ԁ@���k���������B
��ыN���ăe���r��t�����B�k���̃}�b�v��������A�Ôg�������̃e���b�v�������B�k���͗��n�ɋ߂��悤���B
�A�i�E���T�[�̐������Ԃ��āA�Q�Ă邳�܂����Ď���B�u���������Ă��������v�ƃe���r�ɉf��A�i�E���T�[�ɐ������������ǁA����͖��ɗ����Ă��Ȃ��B��N2���̒n�k�ƈ���āA��d�������Ă����킢���B
�킪�Ƃ͓ߐ{�R�[�ɂ���B���n�̍��I�w�̏�ɉΎR�D�y���~��ς������y�n�Ȃ̂ŁA���I�����R�̖ƐU���u���̂��̂̋@�\���ʂ����Ă���B���������Ēn�k�ɂ͂߂��ۂ������B
��l��炵�̂��ׂ���ɂ́A�邪�����Ă���d�b���悤�B�����Ē��A��̒��ɏZ��ł��鎄�ɂ́A���͍͂���ƑS���ω����Ȃ�
�悤�Ɍ����邪�A����o��ƍL�����E�͔�Q���傫�������悤���B
�@�@
�@�@�k���n�͕��������@���������̓�쓌60km�t�߁@�ő�k�x6���@�}�O�j�`���[�h7.3�@�k���̐[��60km

�t�̐Ⴊ�@�@�ފ݂̓���Ɋ����̂͂�����܂��@�@3.18
�@
���R�̕�炵651
2022.3.17�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@
�@
 K����ւ̎莆�@�w���̖��c��x�ƃJ�Y�I�E�C�V�O����i�ɂ��� K����ւ̎莆�@�w���̖��c��x�ƃJ�Y�I�E�C�V�O����i�ɂ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�iK����͐A���T���̂����ԁB���N150�ʂ̃��[�������������j
�J�Y�I�E�C�V�O�����A�w���̖��c��x�����ǂ݂ɂȂ��Ă̊��z�����܂����Bk����Ǝ��̎��_�����邱�Ƃ��v���m��A��ϋ����[���q�ǂ������܂����B
����A����ɑ��鎄�̈�ۂ������肷���₢�Ȃ�A�������܂��Ԏ����Ԃ��Ă��܂����B�ԐM�܂ł̎��Ԃ̒Z������AK����̎����ł��C�̑��������i�����߂Ċ���������ł��B
���肪�Ƃ��������܂����B�i���Ƌ����j���������̃��[���̉����́u�R�r����X�ցv�̂悤�ł��ˁi�X�ɏ��j
�m���ɁA�����w���̖��c��x�Ɋւ��āA
�u���ċ��ɓ������L�\�ȏ������P���g������莆��������X�e�B�[�u���X�B�����Ă����~�X�E�P���g�������o�X��������Ȃ���A���邶�ɒ����߂��Ă��̂�̐l��������Ă��܂����Ɩ��̂Ȃ������B�j�̐l�������V�[���ł���Ȃɔ߂����\�����������Ƃ�����܂���B�v
���������܂������A���́u���v�Ƃ����\���͒t�ق������Ǝv���Ԃ��Ă��܂��B�����X�e�B�[�u���X�͉ߋ��̐l���ɂ����āA�ق��ɑI�ԓ�����������������Ȃ��̂ɁA�Ɖ�ڂ��Ă���̂ł��傤
���B�����ɂ��������̌������������������܂���B���������Ƃ��ߋ��ɕԂ邱�Ƃ��ł����Ƃ��Ă��A
��͂�^����ꂽ�������ʂ������Ƃ��āA�����Ƃ����l�p�Ȕ��̒��ɕK���⎩�g����ꍞ�݁A��������I�Ԃ��낤�Ǝv�킹�Ă���܂��B
�j���͂���������ʂł͎�����ے肵�����Ȃ����䂦���A���̂�̗�����������������̂Ƃ����K����Y��Ă���܂����B
���̃C�M���X�Љ�ŁA�����Ƃ��Ă̖����e���狳�����܂�A����������̌��Ƃ��Ă����̂ɁA���オ�ڂ�A�����J�l�̎�l�ɂ͂��̍l�����𗝉����Ă��炦�Ȃ��B���̊������~�X�E�P���g���Ƃ̕ʂ�ɕ����o���Ă������̂ł͂Ȃ����B�ƍ��͍l���Ă��܂��B����������B���ĉ߂����Ă����ߋ����v���o�����̂�������܂���B
�Ō�́u�A�����J�l����ԃW���[�N���l���悤�v�Ƃ����l���̌��t���A�����E�C�M���X�ł̎����Ƃ���������A�߂����������ے����Ă��܂��ˁB
�J�Y�I�E�C�V�O���Ɏ���Ă��́w���̖��c��x�Ɓw���𗣂��Ȃ��Łx�����݂܂ł̑�\�삾�Ǝv���܂��B��������y�����Y��ŁA�܂�Œ��҂��߈˂������̖ɂ́A����͂܂��悤�Ȋ��o�������܂����B
�ŋ߃t�@���^�W�[��i�����������\���Ă��܂��B�J�Y�I�E�C�V�O�����ڎw�����̂͂ȂɂȂ̂��H�@��������܂��ˁB
���č����̖{��ł��B
���N���O�u�m�[�x���܍��
�J�Y�I�E�C�V�O���̕��w���M�����v��NHK�̔ԑg�Ō��܂����B�u�Ȃ��J�Y�I�E�C�V�O���͖{�������̂��v�B�{�l�̘_����K����̂��������u�����Ɛ^���Ƃ͈Ⴄ�B�����͎����ł͂Ȃ��B�����������ɂ͂����̐^��������B�v�������̂��v���o���܂����B����ɐl�ԂƂ��Ă̊���i�S�̂�����j��ǎ҂ƕ�����������������Ƃ������̂��B
���̂��Ƃ������̍�i�Q��ǂ��납�炸���ƍl���Ă��܂����B�u�����͐^���Ɋ܂܂��v�ƁB���̎������̂��̂��牽���������āA�����̑̓��Ɏ�荞�ށB���ɕω���^����B�����č�i��ǂނ��Ƃɂ���Ď����̊�����A���l�̂���Ƌ��L���A�������������Ƃ��ł���
�B�v
�l�Ԃɂ͐g�̐����K�v�Ȃ̂ł��傤�B�܂葼�҂Ƃ̌𗬂ł��B�����ɕ��w��ǂޑ�햡������̂ł͂Ȃ����Ƃ������܂��B
����ɔ]�̓����̂Ȃ��ɁA�u�ߋ��̋L��������������A�s������v�����邱�ƂɎv��������܂����B�]�͂ǂ̎����⋕�\������^�������ݎ�邱�Ƃ��ł���Ƃ������ʂ�������ł��B
���w�A�P���ɂ����Ə�����ǂނ̂͂Ȃ��Ȃ̂��B����͕��w��ʂ��đ��҂�m��A�������甽�f���Ă�����̂�ʂ��Ă��̂��m��A�V�������E��m�邱�Ƃ��ł��邩��B�l�Ԃ̕s������m��A�|�p�̍���𗘂��A�����čs����̋^�₪�����Ė�������A��O�ɐV�����i�F���L���鎞�AEureka�I�Ƌ��Ԃ߂����ɖ�����т邽�߂Ɏ��͖{��ǂ�ł���̂��ƁB
�m�邱�Ƃ͊�тł��B�Ȋw���n�����w�ۓI�ɍL������e�̖{���A���Ƃ����B�ł��钸�����Ⴍ�Ȃ��炩�ł����Ă��A���̒�����ڎw���Ƃ��͒��o����A�W�O�U�O������A��蓹����Ȃ̂ł��ˁB���Ƃ������ڎw���Ȃ��Ă�����Ŏ��R�Ƃ���ނ��̂��ǂ����ȁB�@---�K����臒l�͒Ⴂ�����A�K�����������₷���ł��傤����B
�ȉ��AK����̌��t�����p�����Ă��������܂��B
�����܂Łu����͎����ł͂Ȃ��v�Ə����̖����_����w�E���ď����ȂǂƂ���Ӗ��ŕ��u���Ă��������̔����ɉ������o���������ЂƎ��������B
���̕���q�ǂ��Ă悤�₭�����ł��܂����B�킪�A�ꍇ���Ɠ����ł��B�Ȃ������镶�w��i��ǂނ��ƂɋC���i�܂Ȃ��̂�----�ނ̒���K����Ɠ������o�����Â��Ă���̂ɋC�t���܂����B�V�N�Ȏv���ł��܂��B�C�Â���^���Ă��������āA���肪�Ƃ��������܂����B
�[孂��P�O�����܂�߂��Ă悤�₭�t�̉J���~��܂����B
���炫�X�C�Z���u���C���x���g�E�A�[���[�Z���Z�[�V�����v���T���炫�ł��B���F�����ɗh��Ă��܂��B
���ꂩ��A�C�X�t�H�[���X�A�}�E���g�t�b�h�Ƒ����A�Ō�̒x�炫�L�������b�g�Ő���͑ł��~�߂ɂȂ�܂��B
����3��{�B3��{�ȏ�̐��傪�g�ł��܂͐S�����i�ł�����A�N�Ɉ�x�̉䂪�Ƃ����̐���ՂɁA���䂩�牺��Ăǂ������o�������������B���ꂽ���ɁB

�@�@����݂͂�ȓ��������Ă���B�@�@ ���C���x���g�E�A�[���[�Z���Z�[�V����
���R�̕�炵650
2022.3.16�@
�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �@�ߐH�҂͔L���H �@�ߐH�҂͔L���H
�Ԍ{�i�A�g���j�̉H��������ɗ����Ă����B�U�炩����Ďc�����H���������B�A�g�����]���ɂȂ����悤���B
�����������Ƃ͕Е�����̂ݍl���Ă͂����Ȃ��B�����邽�߂ɐH���B����͐����̏h���Ȃ̂�����B
 �@ �@
�����͂��̂������쒹�����܂����Ă��Ȃ��B�x������Ă���悤���B�@�@�A�g���@�i�X�Y���ڃA�g���ȁj
�@ �@�g�b�v�M�A�ő���Ȃ��� �@�g�b�v�M�A�ő���Ȃ���
���Ē�̓����i�K�[�{�j�̉����̐��R��̏C���Ƃ����t�̑�d�����n�܂����B���ܐݒu���Ă������͂����A�����p�̎d�g�݂����O���ĉ����T���_�[�ō��A�y���L��h��B���̂��ƐV����������t����\�肾�B����́i���_����D���ȁj�z�[���Z���^�[�֍s���čޗ��B���Ă����B�ނ�O�Ɋ������Đ��_�����g���A�������Ȃ������炵���A�����̑O�̏��w���̂悤�ɁB
���������ƊȒP�Ɍ����邪�A������ԕ�����ԏt�̋�����グ�č�Ƃ���͔̂���B�r�������āA�Ԃɑ�������ɓn���A���̏�ō�Ƃ�����̂����A�S�[�O�������Ă��邹���������ē��삪�ɖ��ɂȂ�B���������ڂ��Ȃ��B
���Ɏ����̑��_�̐��i�́A�����Đ��܂�Ắu���˖Ґi�v�^�B���肢������g�b�v�M�A�ő���Ȃ��ŁB�������A�R�����܂ŁA�����炭�܂łł�������d����i�߂āB
 �@��␅�����ށ@���S�m�� �@��␅�����ށ@���S�m��
�@
 �h���O��3����o�����@----�@���ꂪ10�����܂ő��� �h���O��3����o�����@----�@���ꂪ10�����܂ő���
����̓R�i���̃h���O���B�h���O���Ƃ͎�Ƀu�i�Ȃ́A���ɃJ�V�A�i���A�J�V���Ȃǂ̂悤�Ɋk�l�ɕ����Ă��錘���ʎ��̂��ƁB
���̋C�����}�C�i�X�T���ɉ����钩�������Ă��Ă��A��������ĂɌ����Ă̏������i��ł���B�܂��Ԃ݂�тт��卪���o���đ̂��Œ肵�A�����ނ�ɑo�t���L����B���Ƃ͂Ђ����瑾�z�Ɛ���҂��Đ������邾���B
����͂R������̉ʎ��B�Ƃ��낪��̂��������ɎU����Ă���h���O���́A���ɂ��̍���ڊo�߂����Ĕ���̎�����҂����헪���̂��Ă���B�܂�A�S�����A�T����---10�����̂悤�ɁB���͂̊��̕ω��ɑΉ����킪�������т�悤�Ɏ�����t���Ĕ��肵�Ă����B���ꂪ10���܂ő����B
��U�������đo�t���L�����h���O���������������ɂ͂Ƃ�ł��Ȃ��͂��v��B�u�傫�Ȃ��ԁv�̂悤�ɁA���̐l�̎���肽�����炢�Ȃ̂��B�����炱�̔���r���̃h���O������������A���������������Ƃɂ��Ă���B���������d���Ȃ��B
�@�@�@�@�@��@�ǂ�@���낱��@�ǂ�Ԃ肱�@�������ɂ͂܂��ā@���������ւ�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�ǂ��傤���łĂ��ā@����ɂ��́@�ڂ������@��������Ɂ@�����т܂��傤�@��@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���F�ؑ��`�A��ȁF���c��@�吳����̓��w�j
���̓��w���u�ǂ�@���낱��@�ǂ肱---�v�Ƃ����Ɖ̂��Ă����B�������́u�ǂ�Ԃ肱�v�Ȃ̂ł��B
�F����́H����Ȋ��Ⴂ�����܂���ˁB
 �@�͐��� �@�͐���
���R�̕�炵649
2022.3.11�@�@�����{��k�Ђ̓�
�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@
 ������ۂ̂��Ȃ��́A�����ڊo�߂��@18���[�H--6���N���{���߂��O�̎d��--7�������H�@13���Ԕ��̋@ ������ۂ̂��Ȃ��́A�����ڊo�߂��@18���[�H--6���N���{���߂��O�̎d��--7�������H�@13���Ԕ��̋@
�ԕ������ł��邪�A�v������9������2���Ԕ��A��̑ۂƂ�i�A���ɕ������Ԃ����Ă���ۂ���菜���j�Ƒ����B����̉肪�傫���L�тĂڂ݂�t���Ă���B���߂Ȃ��悤�ɋC��t���Ȃ���̎d���Ȃ̂ŁA��Ԃ�������B�n�ʂ͂܂��������܂܂Ȃ̂�
�A��������₦�Ȃ��悤�ɃE�[���̌����C�����Q�d�ɗ����A���_�̑傫�Ȓ��C�ō��
�������B�����͗\�肵�Ă��������n�J���s�����B�B������������B�����́A��{�D�����B
�v���悤�ɂȂ�Ȃ���炵�̂Ȃ��ŁA��Ƃ̌��ʂ��ڂ̑O�Ɍ����ƋC�������������肷��B
�@ �@�������Ƃɒu���Ă������Ƃ� �@�������Ƃɒu���Ă������Ƃ�
�u�D�_�������Ă��A����Ă����̂͑��o�����v�Ə������قljƂ̒��Ɍ�����u���Ȃ������𑱂��Ă��Ă���B������1995�N�P���̍�_�W�H��k�ЁA2011�N3���̓����{��k�ЁA����ɐk�x�͏��������̂́A���т��ыN����n�k
��䕗���o�����Ă��邤���ɁA �������͈ȑO���p�S�[���Ȃ��Ă����悤���B
����Ɋ��f�w��50�L�����[�g���̏��ɑ��݂��邱�Ƃ�m���Ă���͂悯���ɁA������₵���s���������悤�ɂȂ����B
�ŋ��̎x������ƌv�ɂ������p�́A�قƂ�Nj�s�U�ւɂ��A�H���Ȃǂ̓��p�i�w���͂͗��������̃N���W�b�g�J�[�h���g���Ă���B�ȕւ������|�[�g���ƌv��̑���ɂȂ邩�炾�B�����畁�i�̕�炵�Ō������o�Ă����̂́A�Y���⓹�̉w�̖�����ŁA�����͂ق�̐����~���茳�ɒu���Ă��邾���B
�Ƃ��낪�A���̓~�l�����B�����s���̎���----���ρA�n�����X�N�A��s�����n�k�A���A��C�g���t�n�n�k�ƌ��������{����芪�������傫���ω�������ǂ��Ȃ邩�B���d���N��ATM�������Ȃ��A�N���W�b�g�@�\���g���Ȃ��Ƃ����Ɋׂ�����ǂ��Ȃ邩�ƁB
���̎����������̂̓A�i���O�̌����Ɛ��������̌������낤�B
�@�@�@�i�A�i���O�̐l�ԊW�ŏ��������Ƃ������@������A����͑厖���j
�s�ւȂƂ���ɏZ��ł��邹���������āA���̓~�j�}���X�g�ł͂Ȃ��B�����܂⎆���i�Ȃǂ͔��N���A
��{�I�ȐH�Ƃ͂Ђƌ������炢����~���Ă���B�K�\�����̓^���N�̔����܂Ŏg������A��[����ƌ��߂Ă���B�R���i�Ђł��̏K�������ɗ��������Ƃ��������B
�v�����Đ�����3�����������ʼnƒ�p���ɂɂ��܂��Ă������B����� �������S�B
���S�����̂����̊ԁA���̓��̐V���Ɂu���V�A�A�E�N���C�i�ɐN�U�v�̋L�����ڂ����B���̒��Ƃ͗\�������������̂��B
�ɂ킩�ɂ͐M�����Ȃ��B����E���Ȍ�́A���[���b�p�ł̐푈�ɔ��W����\���Ɍ��y���鎯�҂����āA���f�B�A������ɒǐ����Ă���B
�����S�O�N���O�ɂȂ�B�G�N�A�h���ɑ؍݂��Ă���1983�N�t����Ăւ����āA�t�H�[�N�����h�����iFalklands
War�j�A�X�y�C����ł́u�}���r�i�X�푈�v�iGuerra de las
Malvinas�j���u�������B���{�̓A���[���`���֗F�R�Ƃ��ăG�N�A�h������h�����A�����̗F�l�m�l�̂��A�ꍇ�����A���l�����W�ɉ������̂��L�����Ă���B�S���̓����҂ł͂Ȃ��������̂́A�ٔ�����������o�������B
���̃��V�A�̃E�N���C�i�N�U�ɔ����邽�߂ɁA���͉����ł��邩�A����͉������Ȃ��ق��������̂����l���悤�B
�@
�@  �k�A�s�̑O�Ɂ@�@2��26���@�������� �k�A�s�̑O�Ɂ@�@2��26���@��������
���܂�V�C�������̂ŁA��d���͋x�݁B��c���s�̉H�c���ɁA���������ɏo�������B
�����͈�U�����ɂȂ�ƁA�ꐶ�A��Y���B�i���̓_�A�I�V�h���Ƃ͑�Ⴂ�I�j
���̉Ƒ��͒������A����3�H�A��Ă���B�������ƕꂿ���撣��Ȃ���B���̓I�i�K�K���ƃz�V�n�W���B
 �I�I�n�N�`���E�@
�I�I�n�N�`���E�@
�����͒n��ł͎��U��U��̂��̂������B�ƂĂ��l�������āA���̐e�q�͏�����オ����
��������������H�ׂĂ���̂ɋ߂Â��Ă����B���ٓ��̒��g�ɋ����ÁX�̂悤�ŁA���ɒ������L���Ĕ`���Ă����B䕂ł������Ă��悩�������ȁB
�Ăʂ��̃R�u�n�N�`���E���Ɗ���Ă��āA���ٓ��𓐂�ł������A���̏��ɂ͂��Ȃ�������S�B
�i�R�u�n�N�`���E�́A�����Ȃ�����Ă��Ă��������|�P�b�g�ɓ˂�����ł݂���A�o�b�O�̒��g���������肷��B
�@�@�Ê��݂��Ă��āA���̒��͏_�炩�����̂悤���B�����\�ɂ��B�j
 �@�}�K�� �J���ڃJ����
�@�}�K�� �J���ڃJ����
�@�@�}�K���̗Y�@�@���̐F�́u�\���F�v
���̂�̔�������m���Ă��m�炸���A�����̑���Ƌ��ɂ����Ƃ������܂�A���A���̎������R�̒��Ő����Ă���B
�R���ɂȂ�ƒ������̓_�C�G�b�g���n�߂�B�g�y�ɂȂ��ĉ������V�A��ڎw�����߂��B�e���͖k�A�s�ɔ����Đ��ɉH������������B���������k�ւ̒������ɑς����邩�B3���̗͑́A�ؗ͑�������----���̏��ɔ�������������̂��ƂЂƌ��B
�}�K���̓��́A���̉摜�ł͐H���B����������������p�x�ɂ���Ă��̐F�ʂ��ω����Č�����B���鎞�͍��F�ɁA���A�ł͍��ɁA����������ƋP���悤�Ȑ�
�ɂƁB
���̌������̐F�̕ω��̓}�K���̉H�����{���̐F�f�̕ω��ł͂Ȃ��āA����g���̌�������������̐F�݂̂˂��邱�Ƃł����錻��
�炵���B�F�f�͓���̐F�ȊO���z������̂ɑ��A�\���F�͓���̐F�˂��邱�ƂŐF�����Č�����B
�ق��A���̍\���F�̓R���p�N�g�f�B�X�N��V���{���ʁA�J���Z�~�A�^�}���V�Ȃǂł�������B
���ꂢ���B�i�������A����͂��̃}�K�����{���̍ޗ��ŁA�s�̂���Ă���̂̓A�q���A�܂��͍����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�����A�����Ȃ���悩�������j
���R�̕�炵648
2022.3.3�@�ЂȂ܂�
�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �@�ӂ邳�ƁA��̂Ȃ� �@�ӂ邳�ƁA��̂Ȃ�
�N��������͂��Ƃɖk����̊��C�̗������������āA���{�C������k�C���ɂ����ĐႪ�~�葱���Ă���B�C�������Ȃ����E�Ȗ،����A��ÎR��
�Ŋu�Ă��Ă���Ƃ͂������̗̂�O�ł͂Ȃ��B�W��425���� �킪�Ƃ̏�ɂ͂��܁A��������A����̐�----�����ߐႪ�~���Ă���B
�����o�������Ƃ��C���������葱���Ă��邹�����낤�B
���܂�ɏ������āA��������܂ŎĂ݂Ă����̘Z�Ԃ̌����͌����Ȃ��B�����痎���Ă����A�Ƃ������邵�����Ď��邾���B
���������A�Ⴊ�������B�ڂ̑O������F�ɂȂ�A�L���锒����̒�����ڂ���ƁA�ፑ�ɏZ�ދ`���Z�v�w�ւ̎v�����c���ł����B
���Ԃ����v����ēd�b���Ă݂āA�܂��q�˂�̂́A�u�d�b���͊����Ȃ��ł����v�B
���邢�����Ԃ��Ă��Ĉ��S�����B
�u40�Z���`���炢���ȁB���A80�Ή߂��ď���@���^�]���Ă����v�B�Ƌ`�o�B���c���a�肳�����������B��炵�����ݍ���ł��錾�t���Ԃ��Ă���B�����ۂ�Ɛ�ɕ���ꂽ�Ƃ̒��́A�z��������g�����悤���B����ɋL���ɂ��邠�̍��قǐႪ�~���Ă͂��Ȃ��炵���B
���̍�------�������ď��߂Ă̓~�̂��Ƃ������B�u���АV���̐�����������v�Əo�������v�̐��Ƃŏo�������̂͐�B�䂫�A��ʂ̐�B
�����͐�˂��Ė��邢���̂́A���Ԃ̑�����͌�����̂͊O�̌i�F�ł͂Ȃ��A�����ςݏオ������̕ǂ����������B���̎��͐ϐ�R���[�g�����炢���������B���Ɛ�̕ǂ̌��Ԃ���A�߂Ɍ��グ��ƁA�悤�₭������
�B��͂�͂��ɕ����悤�ȋ�F�������B
�v���q���̂���́A�낪��ɕ�����Ă��܂��A���ւ��瑱����̊K�i����艺�肵���炵���B��̊K�i�ǂ��납�A��K����o���肵�����Ƃ��������̂�����
�A��̂ǂ̂��炢�̐Ⴊ�~�����̂��낤���B
�q�����������H��ۂ��Ă���ԂɁA���e���{�ʂ�܂ł̂P�L���̓��C�œ��ł߁A�w�Z�w�̓����m�ۂ��Ă����炵���B
�@�@�i�v�ɂ悭�����炩�����̋`�����A�������ɔw���ۂ߂Đ�ł߂Ă����l�q�A
�@�@�@�@���܂ł����̓����A�Ƃ�X�q�̖h�Ђ����Ԃ��Ċw�Z�ɒʂ����Z�킽�����v���ƁA
�@�@���������ŁA�Ȃɂ�炠���ł��Ƃ������A�������ߕt������v��������B
�@�@�@�@�@�@�܂�ŏ��얢���̓��b�̐��E�̂悤�����A���X�̂̕�炵�𑗂�̂���ςȊ��������j
���̎��̌Z�킪�Ê���߂��A�P�����߂��ĘV���̓�������Ă���B
�ǂ����Ă��܂����̂��낤�A����ȂɌ���U��Ԃ��Ă��肢��̂́B���̗���ɔw�������A�ߋ���ڂ̑O�ɂ��A���Ƃ����肵�Ȃ��疢���Ɍ����ĕ����Ă���悤�ł͂Ȃ����B
�R���i�Ђ���������A���̐��N�Ԃ��₩�ȑr���������Ă���B�ߋ����v���o���A����Ɠ����������A�����đ��������������������Ă���Ǝv�������̂�������Ȃ��B
�悵�A���̋��邭�Ȃ��Ă����B���̐�����낻��~���ނ��낤�B
  �� �h�Ё@���������g���Ă���
�� �h�Ё@���������g���Ă���
�@�@�@����@
�@�摜�́A������Ѓ����}�[��HP���炨�肵�܂����B
�@�����}�[�H�@�݂�Ȓm���Ă�V�C�\��́u�����V�j���V�v�̃����}�[�ł��B
�@�@�@���R�̕�炵647 2022.2.25
�@�@�@�@�@�@�@
�@
 ����@���Ɣ]�݂��������@�@------�q���̂��낱������ꂽ ����@���Ɣ]�݂��������@�@------�q���̂��낱������ꂽ
���ɒ����Ԃ����M���������Ă����A�u�]�זE�́A���X����ł����v�ƁB
�Ȃ�قǁA���̂Ƃ��낤������~�X���p�����A������T���ɍs���āA����T���ɂ����̂���Y��邱�Ƃ������Ȃ����B���̖��O���o�Ă��Ȃ��Ȃ��Ă���B����͂����̂���
�Ŏd���Ȃ��A�]�זE�͎��ɂ���̂�����ƁA���������܂����Ă��Ă����B
���̃R���i�Ă�̒��ŁA�͂܂��Ă��܂������Ƃ�����B�u���قȃA�^�}��Ȃ��v�Ɠ��X�����Ă���̂ŁA�ǂ����ɂ��̂��ق̐i�s���~�߂��������邩
�A�ƒH���Ă��������ɁA�]�Ȋw�ɍs���������̂��B
�������炱�����A�]�Ɋւ���{��ǂޓ~���߂����Ă���B
�w�����m�\�Ɛl�H�m�\�x�i�����G�F���@�u�k�Њ��B
���ꂱ���]�ɐ��݂킽��悤�ɖʔ��������B
��������͓���B�ēǁA�čēǂ̕K�v�����肻���B�������A���˂čl���Ă��Ă�������----�u�l�Ԃ̔]�͍��x�ȃV�X�e�����Ȃ��A�ߋ����L����������\������B�K���Ɍ��݂���
���߂ɔ]�͍œK�������߂Ă���̂��낤�B���������ĉȊw�̐��ʂ�Nj����A�_��n�����邱�Ƃ͂��̖ړI�ɍ��v������̂ŁA�]�̓����������炫�Ă���̂ł͂Ȃ����B���̃I�E���^������M�������n�̐l�����������ł������悤�ɁB�v����Ɠ����悤�ȓ��e���L����Ă��ċ������䂩�ꂽ�B�������v�l�̃��x�����Ⴂ�����邯��ǂ��B
�ǂ{�̂Ȃ��œ��ɐV�������_���J���ꂽ�̂��A�_�o�Ȋw�Ɩw����Ƃ���r�J�T���������ꂽ���܂��܂Ȗ{�B�����͂܂����Ⴂ�B���������𑱂��Ȃ���{���������Ƃ�������Ƃ̎�����̂悤���B
���������ƁA
�w�i�����������]�x�i�����o�ŎЁj
�w�]�͂Ȃɂ��ƌ�����x�i�˓`�Ёj
�w�P���Ȕ]�A���G�ȁu���v�x�i�����o�ŎЁj
�w�]�ɂ͖��ȃN�Z������x�i�}�K�Ёj
�w�]�͂Ȃɂ��ɕs�����x�w�]�͂����Ԃ���y��`�x�w�ł��Ȃ��]�قǎ��M�ߏ�x(�p�e�J�g���̖��]��)�x�����V���o��,
�w�C�n�@�]�͔��Ȃ��x����d�������i�����o�ŎЁj
�w�p�p�͔]�����ҁ@�q�ǂ�����Ă�]�Ȋw�x�i�}�K�АV���j
�]�͍��x�ȏ��V�X�e���B�]�̓����₻�̕ȁA�����������Ȃǂ�������A������Ă���̂ŁA���g�����o���ēǂ�ł��܂����B�Ō�́w�p�p�͔]�����ҁ@�q�ǂ�����Ă�]�Ȋw�x��ǂނɎ����ẮA�u�����������̂��A���̎q��Ă̎��s
�H�̌����͎����g�̐��i�ɂ������̂��v�Ǝv�킹�Ă������e�ŁA���u������x���߂���q��Ă����Ă݂����B�����Ə��ɂł��邩������Ȃ��v�Ɗ����Ă��܂������炢���B������---�B
���āA���e�ɂ͂��܂��܁B�]�̃��J�j�Y���͑@�ׂŔ������A�������]�͂���������噓�������A���܂����킻���Ƃ��A���܂������Ƃ�����A���̂��܂����͐l�Ԃ��y�ɐ����Ă��邽�߂̕���̂悤�Ɏv����B
�L���Ƃ͉����낤�B�L���͎�����ID�ƂȂ莩��̑������̂��́B�����ɑ��鏀���Ȃ̂��B�ߋ���m��A���݂ɑΉ������A�����Č��݂��邱�Ƃ��ł���B
�]�̂��Ƃ�]���g���ċ^��������A���Ƃ́H�Ǝ��̐S���g���čl����B���邮���肾�B�ċA�A�����ARecursion.
�]�̂��Ƃ�]���g���čl����Ƃ�����q�\���ɂȂ��Ă���]�Ȋw�̌����́A���̊��S�Ȗ������͂��肦�Ȃ��Ƃ������Ƃ��B
�킟���Ƌ��т����ɂȂ�B
���ʁA�������{��ǂ����M���ׂ�����---�����L�^���Ă��������̂́A����B
�u�]�̐_�o�זE�́A���܂ꗎ��������100���Ƃ���ƁA�Ȍ㖈�������������A3�Ύ��_��30���Ɍ����Ă��܂��B�܂�3�N�Ԃ�70���̔]�זE�����ł��Ă��܂��B�����Ďc���ꂽ30���̔]�זE�̐��ɂ͕ω��������A���N�ł���Ȃ��100���z���Ă��ێ�������Ƃ��������v�B�����I�Ƌ����܂���ˁB
�@�@�@�@�@�@�i���N�ł���Ȃ�A�Ƃ����������t�����j
�ǂ�������͐l�Ԃ̐����헪�̂悤�Ɏv����B�َ��͐��܂��܂łǂ̂悤�Ȋ��ň�̂�
�����ł͑S���\�z�ł��Ȃ��B�Ȃ�A��������ɒu����Ă��������������邽�߂ɁA���ʂɌ�����قǂ̐_�o�זE�������Đ��܂�Ă���̂��낤
�B
���܂�Ă̂��́A���ɍ��킹�Đ_�o�̉�H�����グ�A
�]�̉�H���ĕҐ�����---�v��Ȃ��זE���̂ĂĂ��܂��Ă���----�_�o�זE���œK�����Ă���̂��]�̃��J�j�Y�����Ƃ������ƁB
��l�ɂȂ��Ă����X�]�זE�����ł��Ă���̂ł͂Ȃ��B�����m���������Ŗ{��ǂb�オ�������Ƃ������̂��B
���S�����B���̎��̔]�זE�͐��܂ꂽ����30���̂܂܂ŁA������g���č��܂Ő����Ă����Ƃ������ƂɂȂ낤���B����ȏ㖳�����Ȃ��悤�ɂ��悤�A�e�Ɍ���ꂽ�悤��
�A�Ԉ���Ă���Ƃ��Ă�����@���Ȃ��悤�ɂ��悤�B
�₨��낸�̐_�l�A�ǂ���30���c���Ă���Ǝv���������ƁA�������𑝂��Ă������_�̔]�זE������肭�������B
�@ �y���܂��z
�w�]�͂Ȃɂ��ɕs�����x�̂Ȃ��ɂ���Ȗ�肪�������B
�u���iA��B�̓�̋��z�̍��v��110�~�ŁAA��B���100�~�����BB�͉��~���H�v
-----100�~��10�~�Ɠ������l�A�f���ŋ^�����Ƃ�m��Ȃ��l�B�@���ɂ͂܂邱�Ƃ�����A�Ƃ������B
�@ -----���A���A��u�u100�~��10�~�v�Ǝv���Ă��܂���----�@A��105�~��B�͂T�~����ˁB----
�r�J�T���Fby Wikipedia
���{�̖�t�A��w�ҁA�]�����ғ�����w��w�@��w�n�����ȋ����B
�_�o�Ȋw����іw����Ƃ��A�C�n���]�玿�̉Y������������B�]�Ȋw�̒m�����Љ���ʌ����̒�������M���Ă���B
 �@�������@�Ԃт�͕�������`���Ă���B �@�������@�Ԃт�͕�������`���Ă���B
���R�̕�炵646
2022.2.20
�@�@�@�@�@�@�@
�@
 ���ԂȂ� ----Youtube�ł����Ό��Ă���`�����l�� ���ԂȂ� ----Youtube�ł����Ό��Ă���`�����l��
�V�����Ԃ��͂���20���ɂȂ�B���܂܂ł̌y�����Ԃɔ�ׂāA���܂��܂ȋ@�\���lj���������Ă���̂ŁA���S�ƌ����Έ��S�����A�����I�Ƃ������ɑ����ɑΉ��ł���悤�ɁA���������̃��o�[��G���Ă݂���A���S���u���m���߂Ă݂��肵�Ă���B
�Ƌ��X�V�̂��߂̍u�K�ŁA�u�t�Ɂu�F�����Ό��^�]�𑱂��āA�����̋Z�p�ɖ��S���Ă��邩������܂���B�����@��ł�����A���Ђ������̍��܂ł̉^�]�Ȃ��āA��Ȃ��_�����߂�悤�ɂ��������v�ƒ��ӂ��ꂽ�B
�v������ӂ������������肻�����B
���ŋ߁A�ߏ��ŃZ���^�[���C���I�[�o�[�̎ԓ��m�̏Փˎ��̂����������肾�B
�Ȃ̂ō����A���_�Ƃ�����Ƌ�����b�i���܂Ƃ������邩�j�������B
���_���u�E�ɑ傫���J�[�u���铹�H�v�ŁA��ɃZ���^�[���C���Ɋ�肷���邱�Ƃ����ɂ������炾�B
���ߖ@�ŁA�E�J�[�u�̏ꍇ�͍������[�����L���������邤���ɁA���_�͉E�����Ȃ̂ŁA���E��ɗ͂�����߂��Ă���悤�Ɍ�����B�����������̑��_�͂������ق���----�����I�ȏ���^�]���Ă������_�̃v���C�h�ɏ�����炵���B���_�͂��Ă��Ȃ���
�A�i���������B�@�@�@�����Ń��^�V�A�������Ə��Ղ��邩�炷�������t�H���[����B�u�����ɑ�D���Ȋ����`��H�ׂ�H�v�ƁB
�@�@�@�@����ƕs�@���ȃJ���X�ɏ����߂��Ă���̂��i�ʔ����j�B
�ŋߌ��Ă���̂��AYoutube�ɃA�b�v����Ă����ʎ��̂̎��̂���S�^�]�ւ̒��ӂ��B
�@�E�������H���E�܍��܂��鎞�̒���----���i�Ԃ̃X�s�[�h�́A�z��������������Ƒ����B
�@�E���f������n�낤�Ƃ��Ă�����s�҂́A�ŗD�悷��B
�@�E���]�Ԃ̋}�Ȕ��i�ƒ�~�A���f�ɒ��ӂ���B���]���̂�����B
�@�E�J�̓��Ɩ�Ԃ͉^�]���Ȃ��ł������B����͑��v�B
�@�E�m�F����A�˂Ɋm�F����B
���l�̐U�茩�ĉ䂪�U�蒼���A���R�̐Ƃ��ׂ��B�i�����g�ɐ��݂�B�C��t���悤�B
�@ �@�悤�₭2020�N�Y�̂̃u���[�x���[��H�I����� �@�悤�₭2020�N�Y�̂̃u���[�x���[��H�I�����
���H�̃��[�O���g�̒��ɓ���ĐH�ב����Ă����u���[�x���[�i2020�N�Y�A���n��38�L���j�������H�I������B���������B�����̒������2021�N�Y�̌���邱�ƂɂȂ�B�ǂ���ɂ��Ă��Ⓚ�ɂ͂������₩��Ŗ��t���B���N�͓��ɗM�q�̃W�����̗ʂ������B
�@�@�@�@�ߐ{�A�R�̓����B�����ɉ�Â̔����R��������B

2020�����I�����s�b�N�L�O�̐؎�V�[�g������B���܂���g���̂͊Ԕ����Ɏv���Ă���B�ǂ����悤���B
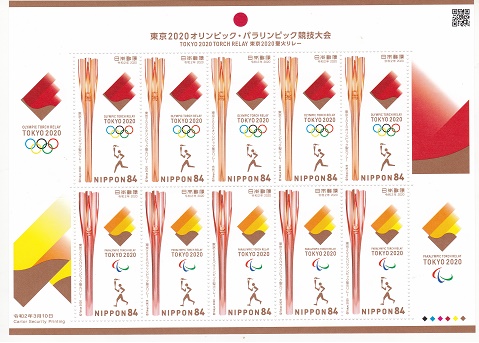
���R�̕�炵645 2022.2.16
�@�@�@�@�@�@�@
�@
 ���̓��@�@------�@���Ȉ����̂��̓��L ���̓��@�@------�@���Ȉ����̂��̓��L
��Ǝ�w�Ȃ̂�����ƁA���\�N���Ƒ��̂��߂ɖŎ��_�@�����Ă��Ă����B�����Ŏ�����t���A�ƒ�̂��܂��܂Ȗ������ɓ�����̂������̋`���ƂƂ炦�Ă��Ă����B
���낻��ו������낻���A��l�ŗ��ɏo�Ă݂悤�A�ƍl�����̂��A12�N�O��2���̂��Ƃ������B�s����̓��L�V�R�B
���L�V�R�암�̃��J�^�������ɂ���}�������̈�Ղ�K�˂闷�̓r���̂��Ƃ������B�`�F�`�F���E�C�b�c�A�̈�Ղɋ߂��A�V�G���_�ɏh�����A�����Ղ�K�˕��������̓��̗[�H���X�g�����ɂ́A������Ƃ����������đ��߂ɏo�����邱�Ƃɂ����B�����������ƌ����Ă��A�����̃W�[�p���ł͂Ȃ��āA������l���Ď��Q����30�N�O�̃����s�[�X�𒅂āA�p�[���̃l�b�N���X��t�������������ǁB�i�p�[���͂������ɂ���
�A����������j
�[�H�̑O�͂�������̎U����������A��t����Ƙb��������ƋC�y�ɉ߂������̂�����A���̓��X�̂Ȃ��ł���ȏ������肵�ĉ�����ɖ��������͖�
�������B
�E�F�C�^�[����Ƃ́A�u���̃X�[�v�̍ޗ��͂ȂɁH��H�J�{�`���̉ԂȂ̂ˁB�����ʼn��F���킯����v�ƌ������b�����������ɂ��āA�O����̃R�[�X���n�܂����B���X�g�����̓����͂��q�ň�ꂩ��������B���e���̐l�X�̗z�C�Șb�����Ɗ��t���d�˂���₩�ȕ��͋C�Ɉ��|���ꂻ�����B
���C�����n�܂邱��A�ˑR�A�e�[�u���̑O�Ƀ}���A�b�`�̊y�c�����ꂽ�B�E�F�X�^���f��Ō���悤�ȑ�j�������A�ނ��A�����͂�����悤�ɂ��ĉ��t���n�߂��̂������B
�@�@ 
�g�����y�b�g�̍������������V��ɂ͂˕Ԃ�B�o�C�I������傫�ȃM�^�����A�M�^�[��r�E�G���������̎������A�}���A�b�`�̉��t���n�܂����̂��B���������̐Ȃ̖ڂ̑O�ŁB
�\�����̂��j���̐������ł₩�ŁA�����̂���M�^�����������炵�Ȃ���A���ݖ炵�A�̂��x���Ă����B
�܂�Cielito Lindo���A����Paloma�B
Desperado�Ƒ����Ō�̋Ȃ͉��ƁuCumpleaños feliz�v�i���a�������߂łƂ��I�j�̉̂������B
�@Cumpleaños feliz
�@ Cumpleaños feliz
�@ Te deseamos todos
�@ Cumpleaños feliz
���a�������߂łƂ��@���a�������߂łƂ��A�݂�ȂŌN�ɂ��߂łƂ��@���a�������߂łƂ�
���̉̂��J��Ԃ��A�Ō�͂��߂łƂ��Z�Z�q�����I�ŏI������̂������B
�E�F�C�^�[�����M�ɍڂ��������ȃP�[�L���^��ł��āA���̏�ɉԉ����{���}���A�����Ă����B�͂�����ԉ������ȉ��𗧂Ă�B�������ē��Ɍ�����������́A�Ă�����X�C���Ɗ��Ⴂ���āA�ꐶ�����������Ƃ���B���x���Ȃ�ǂ��������Ƃ��邪-------������킯���Ȃ��B���̂����ɉԉ̒����猩����}���A�b�`�R�c�̎p���ڂ₯�Č�����悤�ɂȂ����B����H���^�V�A�������Ă���H�@�܂����Ƃ��炠�Ƃ���N���o�Ă���B
�������̃E�F�C�^�[����A���C�~�قǂ̃i�v�L���������o���āu���l�A����Ő@���Ă��������v�ƃ��e���̒j���̂₳�����������Ă��ꂽ�B�u���肪�Ɓv�ƂȂ�Ƃ��Ί��������ꂽ�B�����苃������
�A�Z�����B
�Ō�ɗ��s�Ђ���n���ꂽ�v���[���g�́A�u�����̖v�������ǂ������L�V�R�E�V���o�[�̃y���_���g�B
�@
���������v���o��䍂��邱�Ƃ̑����A�R���i�Ђ̓~���B���̓��͂������N������ȓV�C�͖��������ƁA�J���N���̐l���������X�Ɍ����u�₩
�Ő��ꂽ���������B
���̎��̗��́A���ƓV�C�Ɠ��s�҂Ɍb�܂ꂽ���Ƃ��낤�B
�����A2��11���B�Â��͋I���߁A���̌����L�O�̓��B�����Ď��̒a����
���܂��܂Ȃ�����������āA�s�����s�o�����������ߋ������ǁA���낻��d�グ�̔N��ɍ����|�����Ă���̂�����A���܂܂ŕ����Ă����܂̒��g���v�����Ď̂Ă悤�B
��������V������N���n�܂�B�Đ��ɂ͐����̖����ӂ��킵���B
���Ĕ]�֓͂��悤�ɃA�N�Z����������蓥�����B�ǂ���ڎw�������B���N�͐A���ٕ̕ʂ������Əo���܂��悤�ɂ��낤���B
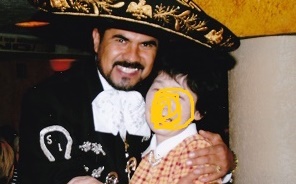 |
���e���̐l�����̈��A---�ق��ɃL�X���ăn�O����----�ɂ͋����Ȃ����A�����܂Ő����̂���n�O�͏��߂Ă̂��ƁB
���������B
���̎ʐ^���ڂ���̂ɁA�����Ԃ����������B
�v�����������͌Õ��ȂƂ��낪����悤���B����͒P�Ȃ�n�O�Ȃ̂ɁA�N�����Ƃ��v��Ȃ��̂ɁB
�����Ă��܂��A����Ƒ��M���N���b�N�ł����B
�ł�����ȋL���������ĂƂĂ��������B |
���R�̕�炵644.
2022.2.11
�@�@�@�@�@�@�@
 ���̏t
���̏t
 �A�C�X�����h�|�s�[
�A�C�X�����h�|�s�[
�t�͎R���z���Ă���Ă���B
�����Ƃɗz�̓��肪�x���Ȃ��āA�C�Â��Γ��k�ɋ߂����̒n�E�ߐ{�ł����A�ߌ�5�����ɂȂ��Ă��O�͖��邢�܂܂��B
�V����܂X�̎}�Ɍ���������Ԃ����˂��Ă���B��������荞�ތ��������̉��܂ŏƂ炵�A���Ƀv���Y�����͂��悤�ɗh��Ă���B
�g�����B
��N�X��22���Ɏ�܂������A�C�X�����h�|�s�[�̏��Ԃ��A�������炢�Ă��āA���̂����肾���ق�̂薾�邢�B
�[���A���𗁂тċP���悤�ɉԕق�U�肽�Ă�B���̓��ɐႪ�ς����Ă��Ȃ���A��A�܂ŁA���ƂR�O�����܂�B
�@ �@�n�Y�n�����Ȃ���F�Y�F�� �@�n�Y�n�����Ȃ���F�Y�F��
���̓~�o���Ō�̗M�q�ɂȂ�͂��B25��300�~�̗M�q���Ă��ėM�q�W���������A�Ă̒�ō̂����V�\�̎��̏ݖ��Ђ��ƈꏏ�ɗF�l��ɓ͂��ɍs�����B���ƉƂ̒��Ƃœ{��Ȃ��炵��ׂ�A�}�X�N���ז������NJ����������Ȃ̂Ŏd�����Ȃ��B
�F�l����́A���A�W���R���ɂ��낵�Ă݂��ݖ��ɒЂ��A�����ɎN�����u�A�W�݂̂���v�������������B
������u�F�Y�F���v�ƌĂԂ̂ł��B
���R�̕�炵643.
2022.2.4
�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �S�捡�N�͖����ɂȂ��� �S�捡�N�͖����ɂȂ���
 �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@  �ӂ��̂Ƃ�
�ӂ��̂Ƃ�
�@�@�@�ߕ��̂������Ƃ��Ă��邨�ʁB�@�@�@�@�@�@�@
���̋S�̖ʂ́A���\�N�������f�U�C���������悤�ȋC������B
���́A�n�[�g�`�̐Ԃ��̂́A�u��v�A�u�S�̃}�t���[�v�̂ǂ���ł��傤�B
���ɏZ��ł�������Ɏ����Ă������i�����Ă����̂��E���Ă����A�G��j�̖��O���ȂȂ����i�������j�ŁA
���̖������������i�S�����j�������B
���̋S�̖ʂ�����
�u�|����A���킢��v�u�ق�ق�v�Ƌ������ėV���̂������B
�ȂȂ������A�������������𐂂�ĕ|����A���ǂ��ǁB�B���ꏊ��T���Ē�����낤�낵�A���_�̊Ԃɓ���˂����݁A����������Ȃ��悤�ɂ��Ă����B
�ȂȂ����i�������j�Ɩ��̂��������i�S�����j�B�낭�i�Z�j�łȂ��̂ł��B
�@
 �����������----�J�𐁂��Ȃ� �����������----�J�𐁂��Ȃ�
�q���̂��납�炸���Ƃ����Ɠ���Ă������ƁA����͐e�w�Ɛl�����w���ۂ߂ĐO�ɓ��āA�w�J��炷���Ƃ��B
�w�A���v�X�̏����n�C�W�x�̂Ȃ��ŁA�y�[�^�[�₨�������A�n�C�W���ĂԂ̂Ɂu�s���`�C�A�s�[�v�ƌ��J�𐁂��Ă����̂��o���Ă���B
�����������A���v�X�̎R�ɂ����܂��āA�R����������̂�Č��Ă����B
�^�̈Ӗ������߂āu�s�[�v�Ɛ����B���̎w�J�ɓ���Ă����B
�x�b�h�ɓ����Ă�����Ɨ��K���Ă݂�B�o�Ă���̂́u�Ӂ[�Ӂ[�v�Ƃ��������ꂽ�������B���܂��Ɋ̐S�̌��J�������Ȃ��Ȃ����B���̎��͂̋ؓ����������̂��낤�B
�c�O�����ǁA���̂Ԃ�ł͈ꐶ���������ɂȂ��B�ł����ӏ����������K���Ă݂�B
�@�i��Ɍ��J�𐁂��ƋS������A�Ǝq���̂��닳�����Ă����̂ɕ��������̖����q���B�j
�@ ���� ����
�@�@ �@�Q��1�� �@�Q��1��
3�w���̎n�Ǝ��Ɋ����̈�قŁA�Z���搶�����������܂����B
�u�P���͂��ʁA�Q���͓�����A�R���͋���v---����ʂ�ƁB�q���̂���A�ǂ����Đ搶�͖��N�������Ƃ������̂��A�s�v�c�Ŏd���Ȃ������B
�����Ƃō���Ɠ������𑗂��Ă���ƁA���̂P���������������悤�ȁA���������悤�ȁB
----�ǂ���Ƃ����Ȃ��C���ł���B
�܂��R���i�����̖����A���A�g���K�Ôg�A���ς�炸�̖k���N�̃~�T�C�����ˁA�����剫�n�k������A�ߐ{�ł͎�������g���ɏP��ꂽ�A��t���e�Ō����ꎀ�S�A�ٔ�����E�N���C�i��Ǝ����⎖�̂��ƂĂ����������B
�]���̗ǂ��搶�������̂ɁA�N���j�b�N���ΎE�l���A�y�ΕY�������ԕ��Ύ������A����͍͂�N�̎��Ȃ̂��B
�@�@�@�@ ���R�̕�炵642. 2022.2.1
�@�@�@�@�@�@�@
 �悤�₭ �悤�₭

16�N��葱�������́uKei�v�B���s�����͂R���U��L�����[�g���B�܂��܂������łƂĂ����C�Ȃ̂Ɏ�������B�ւ�����Ŕ������̂ŁA���́uKei�v�ɑ���v���͐[���B�̔��X�ɒu������ɂ��鎞�ɋ����l�܂�v���������B�K����ԂƂ��ė��p���Ă��炦��悤�Ȃ̂ŁA�㐶�͈��ׂ��B
��N11�����A�R���i���������������Ă��������ɁA�v�����đ��_�̕��ʎԂ���������B�V�����w������Ԃ̔[�Ԃ�12�����{�ƕ����A�X�m�[�^�C���ւ̗����ւ��̃^�C�~���O���v�������ʂ����Ȃ����̂��B�Ƃ��낪�A�����̕s������[�Ԃ��x��ɒx��āA�悤�₭����̌ߌ��邱�Ƃ��ł����B
�����B75���҂�����A���ƂȂ��C�����Ă������_������ň���S�B���̎Ԃ͓�l�ŏ��ԂƂ��Ă͍Ō�ɂȂ邾�낤�B�����v���ƐV�N�Ȏv���őΉ��ł���B
�A�蓹�A�Ԃ̂ǂ��ɉB��Ă����̂��u�X�s�[�h�ɋC��t���Ă��������v�Ƃ��������̐�������B
�����A60�L���o�������B
�u����������Ă��������v�Ƃ�����̏��������Ԃ��Ƃ��������B�ʔ����B
�V�����Ԃɂ͏Փ˖h�~�Z���T�[�i�L�Ђ��j���O�㍶�E��4�J�����t���Ă���A���̑��̈��S�^�]�T�|�[�g�@�\���[�����Ă���̂ŁA�ˑ����߂��͗ǂ��Ȃ����A���S�ł��镔�����傫���B
�@
 �Ƃ�ł��Ȃ�������------�s�������҂������I�ɑ������@ �Ƃ�ł��Ȃ�������------�s�������҂������I�ɑ������@
1�����ɂȂ�A�l��11��5��l�ɑ��āA�A��20�l����30�l�̊����҂��o�Ă���Ȃ̂��|���B���N�`����3��ڂ̃u�[�X�^�[�ڎ�̓�����2������3���ɂ����Ĕ�є�т̓��ɕ���ł��ĕs�����B�x���ڎ킵������҂́A���̂܂܂�����3���ɒlj��ڎ���邱�ƂɂȂ邩������Ȃ��B
�s�����ύX�ɕύX���d�ˁA4��ڂ̕ύX�ł悤�₭�ڎ�ɂ�������������̗\��̕��@�͂Ȃ��Ȃ��悭�ł��Ă���B�N��Ɓu�ڎ킵��2��ڂ̓��t�v�ōׂ����O���[�v�����A�����ɂ͂ߍ��ނƂ����Z���̗p���Ă���B���ς�炸Web�\���S�ɂȂ��Ă�����̂́A�d�b���𑝂₵�đΉ����Ă���B�����ŁA��r�I����҂ɂ��\������₷���B
�@�@�@�i�����ɖ���������B���߂̗\����@�������������Ƃ�����A����̕��@���������Ƃ����悤�B�j
�@�@�@�i�������͂Q���U���A�t�@�C�U�[�ڎ�̏������\��ł����B�j
�ψق����I�~�N�������́A�����͂͋������̂́A�a��͔�r�I���ƂȂ����A�Ⴂ����ɂ͏Ǐ���Ȃ��l������悤���B�܂蕁�ʂ̕��ׂɂȂ����ƍl������̂��A�f�l�ɂ͂悭������Ȃ��B���ʂ̕��ׂɋ߂��Ȃ����̂Ȃ疠���h�~�ւ̓w�͂��s���Ȃ���A�Љ�E�o�ϐ������ĊJ������@�ɂ��������Ȃ��̂��B�����ɘa�ւ̓���T��ACovid�Ƌ��ɐ����Ă�����Љ��ڎw�����B���邢�͊��S�Ȃ�}������----�[���R���i�������������߂�̂��B�s�̎i�ߓ��͒N�Ȃ̂��A���̎v�l���ǂ������Ă��Ȃ��B
�w�N���̊w�Z�������A�s���ɃR���i�|�Y�������Ə��������Ă����B�Љ�ɕ��f���N���Ă���C������B�����ɑ��ĕq���ɔ�������l�ƁA�S�������m��Ȃ��q���̂悤�Ȑl�ƁB������������炵�ɒ�������l�ƁA�����łȂ��l�ƁB���邢�͍��������Ή����Ă���l�����A�m�l�F�l�ł���A�܂������̑��l�ł���A�E�B���X�����҂ł͂Ȃ����Ƃ����^�S�ËS�ɂ�������----�W�����f����鋰�ꂪ�A���ꂱ���������Ă���B
孋����āA���܂ɂ͑P���s�����ƌ������������̌ߌゾ�B���������ߕ��A�S��ގ����Ă���B
* �̐S�Ȃ��Ƃ������Y��Ă����B�Ⴂ�l�ւ̐ڎ�𑁂��i�߂ė~�����B
���{���x�����҂�厖�ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
���R�̕�炵641.
2022.1.28
�@�@�@�@�@�@�@
�@
 ���Ă��ˁ@ ���Ă��ˁ@
�@  
�@�@���́u�̂ǂʁ`��v�@�E�̓w�A�I�C���@�@
��10���B�Ȃ̂ɐQ�Ȃ��C�ɂȂ��ĂX���ɔ���n�߂Ă��܂����B
�u�X�����ɂ͉Ƃ��o�Ȃ���v�ƋC���}���B
�オ�������ɁA�u���̐낪�������ꕨ��---����v���X�v���[���悤�ƁA�ڂɓ���������@���Ȃ���r��L���A�������t����B
��T��Ŏ���āA�V���V�� �B���ɓ���܂����B
����A�ȂK�T�K�T����B
�Q�Ăĕt�����̂́A�u�̂ǃX�v���[�v�������I
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ��҂��
�@
���R�̕�炵640.
2022.1.23
�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �܂ڂ낵�̉i����
----- ���������̒��Ō������� �܂ڂ낵�̉i����
----- ���������̒��Ō�������
�R������̏h���o�āA���Ƃӂ����������͑�{�R�i�����B�i�����͐��Ƃő�X�M�̑ΏۂƂ��Ă����u�����@�v�̑��{�R���B
�o�X�ׂ̗ɍ��镃�́A���������Ă���ӂ����������̂́A���S�͗x������̊������ł��ӂ�A���҂ŋ����C���Ȃ̂����Ď���B
�������Ȃ��B�����߂��܂ŁA������c�Ɋ��ӂ��A�Ƒ��̈��ׂ�����ēnjo�𑱂��Ă������ɂƂ��āA�u���{�R�v�֎Q�w���邱�Ƃ́A�ӔN�ɂȂ��Ă���̍ő�̖]�݂������̂�����B�C�X�������M�҂ɂƂ��Ẵ��b�J�Q��̂悤�Ȃ��̂��낤�B
|
�k�i�����́A�����T�t�ɂ���ĊJ���ꂽ���T�C�s�̓���ŁA�����@�̑�{�R�B1244�N�i����2�N�j�����T�t45�̎��ɎP�����啧���Ƃ��Č�������A����2�N���1246�i����4�N�j�ɋg�ˎR�i�����Ɖ��߂��Ă���B770�N�ȏ�o�������݂��i�����̏C�s�͑T�@�̒��ōł��������ƌ����A��160���̉_���i�����j�ƌĂ��C�s�m���C�s�����𑗂��Ă���l |
�Ⴂ���납��㎋���������́A�ӔN�͂��̎��͂��Ƃ݂ɐ����Ă����B���������ڂ��Ȃ��B�Βi��o��̂ɓ�a���Ă���悤���B�����̂悤�ɘr���������般���Ďx���A�u����3�i�ł����͏I����v�u�i�������邩��C��t���āv�u�ق�A������v�Ɛ��������Ȃ���o���Ă����B
�X��������Q���͑ۂނ��Ă��āA����������B
���āA�萅�ɂŎ�𐴂߂����ƁA�K���ɂ�����18���ɍs����]�Ǒ�ʎ�F���Ɩ@�v�̗l�q�ɏo����Ƃ��ł����B�����̂��܂肩�A���͌o���ɏ��a����悤�ɐO�����A�g���났�����Ȃ��B
�i�����͍L���~�n�Ɏ����������������т����7�̌�������L�Ō���Ă���B
��L�������������������ēo��B���̎��Ԃ��ʂ悤�ɁA�������������ƁB
�V��ɕ`���ꂽ���{�悪�������P���t�ŁA���̔����������ɂ��A�w�����Ă����̖ڂɂ͓͂��Ȃ��B���������Ⴂ����Ȃ�A���邢�͂��̔��𖡂키���Ƃ��ł�����������Ȃ��̂ɁB
�C���������߂Ă��{���ɂ��Q�肷��B�@���͎��������̍ł������Ƃ���Ɉʒu���Ă��āA�{��d�ƌĂ��d�̒����ɂ͂��{���A�߉ޖ��������A�������i����ӕ��A�ߋ����i�鈢��ɕ����J���Ă���B
�q�炵�A�傫�Ȃ��ߑ����������B���̎������v�����̂��낤�B
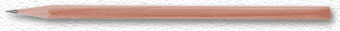
�����A�����Ƃ����̂ɁA���������Ėڂ��o�߂��B���Ɖi�����ɂ��Q�肷�閲�������B���܂�ɑN���ŁA����͖{���ɋN�������Ƃ������̂�������Ȃ��A�Ǝv�����B���������B��͂薲�������B
��_�W�H��k�Ђ��v�������A���̎��S���Ȃ������̐l���̐l���v���Ԃ��Ă������Ƃ̖���͐A�����C�ɂ������Ă������Ƃ��ʂ��G�̂悤�ɔ]���ɓ��e���ꂽ�悤���B
���͂Ȃ��A���������ꂾ���̂��Ƃ����Ȃ������̂��낤�B���̒����Ԃ̖]�݂Ȃǒm���Ă����͂��Ȃ̂ɁB
�Ȃ��i�����֘A��čs���Ă����Ȃ������̂��낤�B�e�F�s�Ȃǂł���Ƃ��ɂ���Ă����Ȃ��ƁA�������
�Ƃ͕������Ă����̂ɁB���Ԃ͂��̍��ƌq�����Ă���̂ɁA���͂������Ȃ��B�]�݂�����Ȃ��܂܂̕����A���Ȃ��Ă��܂����B
�@
���R�̕�炵639. 2022.1.20
�@�@�@�@�@�@�@
�@
 ���X����낿���
���{���X�܂��͖{�y���X (ꖎ��ڃ��X�ȃ��X��) ���X����낿���
���{���X�܂��͖{�y���X (ꖎ��ڃ��X�ȃ��X��)
��N���̓��L�i632
����݂̂����Ɓ@2021.12.18�j�ɂ���悤�ɁA�c���̒����ӓ��̎����E���ɍs�����w�͂��������B�~�̊ԁA�V�W���E�J�������̉a�ɂƍl���Ă������A�Ȃ�ƁI�{�Ɩ{���̃��X�i
���{���X�j���a�����߂Ē�ɂ���Ă��Ă��ꂽ�̂��B
�N������R�T�Ԃ�������ɑj�܂�āA�a��������Ȃ��炵���B�Q���Ă���̂��A�O��̋L�������₹�Č�����B
���H�̓r�����������A���𓊂��̂ĂăJ�����������B�����瑋�փ��X�̌��ǂ��ĕ����A�B�����ʐ^������B
�����Ǝv��������A�������T���܂�������B���E�O��ɓ������B����͒��̔�ѕ��Ɠ����ŁA�����牺�E�̉a��T���Ă���ߐH�҂̖ڂ�����܂����߂̂悤���B�u���s�������ĎB�e���悤�ɂ��A���̒n�_�ɂ͂Ȃ��Ȃ����Ă���Ȃ��B
 |
���X���Ăъ邽�߂ɁA�q�}�����̉Ԏ�𗠕Ԃ��A�N���~��u���Ă������B
���ނ�Ō����u�܂����v���B
���X�͂������������Ă��Ԃ���B
���̐^���Ȗڂ����Ă��������B
���̎����X�͂ǂ��l�������낤�B�킭�킭����B
----���߂��B�G�T���B
���X�͂��̂��ƁA�N���~������č��̖̑������ɓo���čs�����B
�J���X�����ǂ����A���X�̏������g�̂��̎}�̊Ԃɕ��ꍞ�ނƁA�傫�ȉH���ז����Ă�����o�����ł��Ȃ��B
�̒���16
����22�����B���̒�����13����17�����B�̏d300���B������̐�[�̖т͔��B�ċG�͔w�ʂ��Ԋ��F�i�Ėсj�A�~�G�ɂ͔w�����D���F�ɂȂ�A���̐���ۂ̖т��L�т�B�����������̌̂̎����₯�ɒ����B�~�͊�̎��͂ɂ킸���ɔ����̖т�������B |

�@�@����ȉ����q�����Ă��ꂽ�̂ŁA�����̎d���͌�܂킵�B
�����A�G���Ă݂����A�����Ă݂����B���F�̖тɕ�܂�Ăӂ�ӂ킵�Ă��邪�A�ׂ����i�ŏo���Ă���̂��낤�B
���̂��������Ȃ��̂�B�u�����������݂̂͂Ȃ������v�B
*
�l�b���ʊ����ǂɋC��t���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
�V�^�R���i�����ǂ��A�l���玭�Ɋ����������Ⴊ����Ă���B�i�w���{�o�ϐV���x�@2022.1.16 )
���R�̕�炵638. 2022.1.14
�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �������Ƃ͂������Ƃ� �������Ƃ͂������Ƃ�
���̗��R����p�����ɏo������Ƃ��́A�u���֍s���Ă���v�Ƃ����������B�i�}�`�A������A�ǂ����̋C���Łj
���܂ł�15�L���A�s�����̒��S�n�ɂ́A������l���ɂ��Ă͑������鐔�̃X�[�p�[��z�[���Z���^�[����������ł����p������B���̒��Ŗڗ��̂̓h���b�O�X�g�A���B���a500���̉~�̒��ɂ́A�`�F�[���X�ÎQ�̂g�ЁA�㔭�̂l�ЁA���x���
�h���b�N�X�g�A�ő��̂v�ЁA�㔭�̂`�Ђ�
�V�K�J�X�������Ă����B�Ō�ɂ��̏ꏊ�ɉ��荞�݂��������͓̂��k����ՂƂ���H���A��Ȃǂ̈�����h���b�O�X�g�A�b�ЁB�����������I�ƌ���n�ɑł��ďo�����̂b�Ђ́u���������Ń|�C���g�t�^�����v�ƁA�ЂƐ̂��ӂ��̂��O�́A���������ɂ��ׂĂ���������̔����@���̗p���Ă���B
������������Â����͋C�͂Ȃ��B����ǂ��납�]�ƈ����炪�s���͂��Ă��āA�F�����V�������ċC�������Ă���B��������⍂���悤���B
�������X�̐��ʂɓX�܂��J���Ƃ����q���ɏo���̂����������̂��A��ɓ�����Ă���B�R�X�g�_�E���ɓO���Ă��āA�����Ŕ����Ă���i���͊m���Ɉ����B�����ƌ����Ă��������̂����������Ă���̂ł͂Ȃ��āA���̃X�[�p�[��h���b�O�X�g�A�ɔ�r���Ĉꗬ�H�i���[�J�[�Ȃǂ�
��ԕi������2�A3���������̂��B
�����ŐV�����헪�ɏo���̂��A�������X���B���ʈ����荇�킪�n�܂��āA����҂Ƃ��Ă͂ƂĂ����肪�����Ȃ̂����B
C�X�ɍs�����т����A����ł����̂��낤���A�ƍl����B
�������`�F�[���X������A�g�[�^���Ōo�c���l����ׂ��ŁA���{�o�ϐV�����̑��ɂ��ƁA����5�ЂƂ����v���m�肳���Ă��邪�B
�������l���ɑ���p�C�͌����Ă���B���̌���ꂽ�p�C���e�X�ŒD�������Ɖ����N���邩�B
�n���ɌÂ����炠���ǂ����Â��ɓ|�Y�A���邢�͑�^�X�ɋz������Ă���̂����B���̃��[�v�Ɋׂ邱�ƂɂȂ�B
�������Ƃ����Ǝ�ɂ��N�����B����ɃR���i�Ђʼn������̎��Ə����|�Y�� ������������B�n��S�̂̌i�C���x���Ă���̂͒n���̒�����ƂȂ̂ɁB
���{�̍��̒������������Ɗ����邱�Ƃ������Ȃ����B���{�l�̋����͂Ȃ�����30�N�ԏオ���Ă��Ȃ��̂��B����2000�N�ɂ͈�l�������GDP�́A���E��2�ʂ������B���ꂪ2020�N�ɂ͐��E��23�ʂɗ������݁A����GDP��28�ʂŁA���܂���̊؍��������Ɉʒu���Ă���B�����GDP�������Ɏ����Ă�100�ʈȉ��ɂȂ��Ă��܂��Ă���B
���̋@�Ŕ�������ݕ���1�h���ȉ��ŁA�����R�C������Β��H���ۂ��A��i���ł���ȍ��͏��Ȃ��A�������A�܂���{��2�����̒��ԓ��������
�̂��낤�B
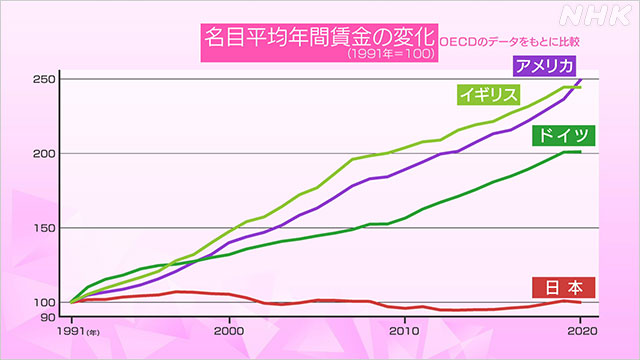 NHK���炨�肵�܂����B NHK���炨�肵�܂����B
(�������A���̍��̐����̌`�ԁA�Y�Ƃ̂�����A�����A���N�ی��̗L���A�ŋ��A���ɏ���łȂnjX�̏�����������傫�����E���邾�낤�B)
���Ԋ�Ƃœ����l��2020�N�̕��ϋ��^��433���~���܂�B����30�N�ԂƂ������̓��{�̋����͂قډ����Ő��ڂ��Ă���B
���҂̈ӌ��͂����������B
�@�E�o�u�������̕s�Ǎ�����������Ă��Ȃ��B
�@�E���������Ⴂ----���ʂ����s�m���Ȃ̂ŁA�v�����Ē������グ�Ă��Ȃ��B
�@�E���������ĕ������オ�炸�A���������������Ƃ���Ɏ~�܂��Ă���B
�@�E�������グ�Ȃ�����ɉ��ق��Ȃ��Ƃ����I�������Ă����B
�E���Y�����Ⴂ-----�i�����N���Ȃ��B
�@�E�C�O�Z�p�ړ]����ƂƂ��ɐ�������܂ňڂ������ƂŁA���{�̂Ȃ��ɂۂ�����ƌ����J���Ă��܂����B
�@�E�f�W�^�������i��ł��Ȃ��B
�@�i������A���̔N��́A�����Ď��������オ�A���܂����{�̐������Əd�Ȃ����b�܂ꂽ�N�ゾ�����ƌ����邩�B
�@�@���ȓI���Ȃ��A���̍l���́j
�������A��N���A�l�オ��̐��������������畷�����Ă���悤�ɂȂ����B�����̕s���A�l��s���ɃR���i�Ђ��ǂ��ł��������Ă���B�K�\�����ⓔ�������A�d�C��A�g�߂ȂƂ���ł͓ؓ��Ȃǂ̐����K���i�̒l�i���A���킶��Əオ���Ă��Ă���̂�������B
�N���͕����ɃX���C�h����̂ŁA���̐��N�Ԃ̓f�t���ɍ��킹�ĔN���z���������Ă��Ă����B���ی������l�オ�肵�A����z�������Ă��Ă���̂��B
���܂ł͕������オ��Ȃ�����ǂ��Ƃ��ׂ��A�ƍl���Ă������A�Ȃ��s�����̃C���t���i�X�^�O�t���[�V�����j���N�������ȋC�z��������---�傰�����낤���B
�@ 
�@��N4���{�̒�B���{���A���|�����̂ŁA���N�̏t�͂�����₵���Ȃ邾�낤�B
�@����ȏt�܂ł���100���B
���R�̕�炵637.
2022.1.10
�@�@�@�@�@�@�@
�@
 ������� �������
搔���Ă͓����A搔���Ă͓����B�N���X�}�X�ɍ~������ɔN�����g�̐Ⴊ�����A�N�������Ă��~�葱���Ă���B������Ԃ��Ȃ��~��̂ŁA�����H�̐�͍~�������̗[���܂łɎ�菜���Ȃ��ƁA��̂����ɓ����Ă��܂��A�̂��̂��Ƃ�ł��Ȃ���J���邱�ƂɂȂ�B
���^�X�R�b�v�ŃK���K������搔���ďW�ߓ�����A��������x������Ē�����̍�Ƃ͂���ƏI������B
�ǂ��ւ��s�����A�N�������B��ʂɔ������߂��Ă���H���ƁA�}���ق̖{�Ƃ����ׂɓ����߂����A�����͂��������T�����B
�U���Ԃ��l�Ԃ̊�����Ă��Ȃ��B���ǂ����闏�_�_�Ƃ̔L�Ƃ����̖쒹����----�V�W���E�J���A���}�K���A�L�W�A�q���h��---�̎p�������Ă��Ȃ��B
���̂Q�N�Ԃ̃R���i�Ђł̕s�@�ӂƁA�N������Ⴒ����ł��݂��݂Ɛg�ɟ��݂��B�l�Ɛl�Ƃ��o��A������āA����@���A���`���������Ƃ����������ď��A�����������̂������������Ęb�����Ƃ��A�ǂ�Ȃɑ�Ȃ��Ƃ��������B�o�����̐G�ꍇ���������ɐl�Ԃ̐��_�̈���ɂƂ��ĕK�v�Ȃ��ƂȂ̂��ƁB
80�Ό㔼�̗F�l�v�w���ߏ��ɕ�炵�Ă���B�ߌ�ɂ͓d�b���āA���킢�̂Ȃ��b�ł����Ă݂悤�B�@
�@ 
���R�̕�炵636. 2022.1.5
�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �@�@�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��@�@ �@�@�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��@�@

��A���ɑ����B����͍P��̂��Ƃ������͔��c��������̃s�A�m�܂Ŗ��키���Ƃ��ł����B�V���p���̋Ȃ����Ȃ����t����A�I��́u�}�Y���J�v�������B���̓y�n�ɏZ�ސl���������ł������Y�����A�Ȃ̒ꂩ�猻��Ă���B�|�[�����h�̖������x����̂肢�ꂽ���Y���ɗh���Ԃ��Ė���A�C�����悭�ڊo�߂����U�́A��ʂ̐�i�F�Ŏn�܂����B
���X�̎}�ɐς������Ⴊ�A�����������ѕ����~��Ă��ẮA�����オ���Ă����B�n���Ⴊ�Ƃ̎��͂������Ă������B
��N�̎n�܂�̓����B�z�C�ɂӂ�܂��~���炸���̂�����������ƂȂ��߂������B
�@
�@�@�@���R�̕�炵635. 2022.1.1 �@
�@�@�@�@�@�@�@�@
���R�̕�炵 2021�N1������ 2021�N�P�Q���܂�
�@ |
 �@
�@ �@���ӂ�
�@���ӂ� �@�����̂����i�{�錧�ό���HP����j
�@�����̂����i�{�錧�ό���HP����j


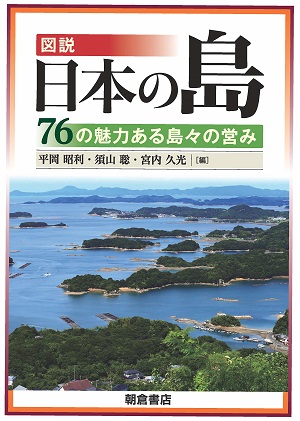 �@����Ȗ{����Ă��āA����őD�ɏ�
������B
�@����Ȗ{����Ă��āA����őD�ɏ�
������B �@
�@ �@�I�I�o��
�@�I�I�o��


 �@���̎����Ɋp������̂́A�݂�Ȏ��̃g�i�J�C�B
��������T�Ԃ��B
�@���̎����Ɋp������̂́A�݂�Ȏ��̃g�i�J�C�B
��������T�Ԃ��B �@�@
�@�@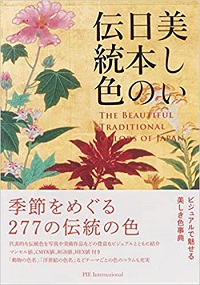
 �@������@3�Z���`�@12��6��
�@������@3�Z���`�@12��6�� �@�V�W���E�J���i���j
�@�V�W���E�J���i���j
 �@���c�X�|�b�g����
�@���c�X�|�b�g���� �@�X�|�b�g����Ȃ��N
�@�X�|�b�g����Ȃ��N

 �@�Ƃ肠����16�@��̏d����600��
�@�Ƃ肠����16�@��̏d����600��





 �@�@�@�V��@��{���̉���
�@�@�@�V��@��{���̉���

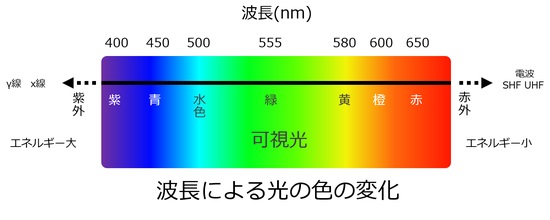 �o�T�FWikipedia�@������
�o�T�FWikipedia�@������


 �������܂Ŕ��������̂ɁB�[�z�����������B
�������܂Ŕ��������̂ɁB�[�z�����������B �@�S�������čs�����Č����Ă��B
�@�S�������čs�����Č����Ă��B �@��̓�͗M�q
�@��̓�͗M�q

 �@
�ԐF�͔�����ւƕς���Ă���
�@
�ԐF�͔�����ւƕς���Ă��� �@�����тł��ٓ�
�@�����тł��ٓ� �@���h�ӂ��₳��
�@���h�ӂ��₳�� �@�ڊ▼���Ԃ���
�@�ڊ▼���Ԃ���

 �i�c�n�[��
�i�c�n�[��
 �Ђ��n��
�Ђ��n�� �@
�@
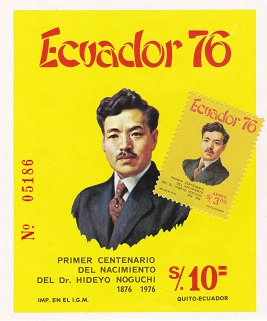

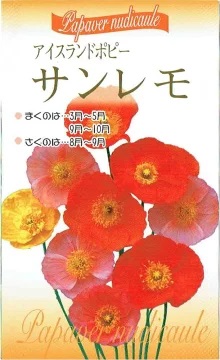










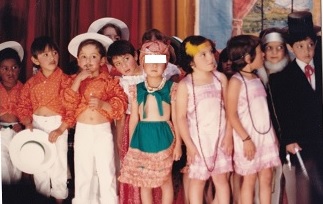 �@���e�����y����A�t���b�p�[����A�^�L�V�[�h����
�@���e�����y����A�t���b�p�[����A�^�L�V�[�h���� �@��������݂�
�@��������݂�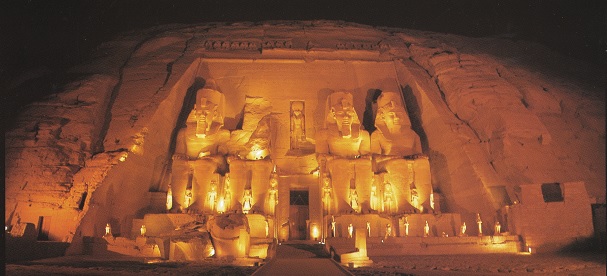 �A�u�V���x���_�a
�A�u�V���x���_�a �@�k�r�A�l�̗x��@
�@�k�r�A�l�̗x��@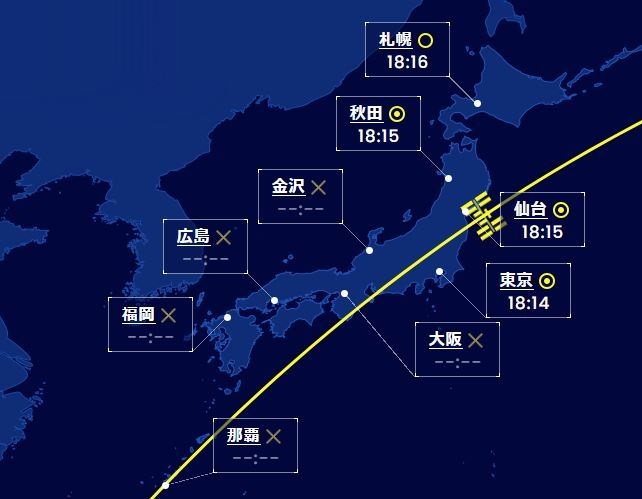
 �@䪉ׁ@�Ă̗J����Y��悤
�@䪉ׁ@�Ă̗J����Y��悤 �t�B�b�V�����[�X�^�[
�t�B�b�V�����[�X�^�[



 �@�p�̎��@
�@�p�̎��@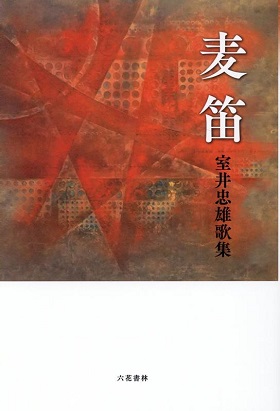

 �@�t�E�`���E�\�E�@�������@
�@�t�E�`���E�\�E�@�������@ �@
�@
 �@�����̎��n�@3.8�s
�@�����̎��n�@3.8�s �@
�@ �@
�@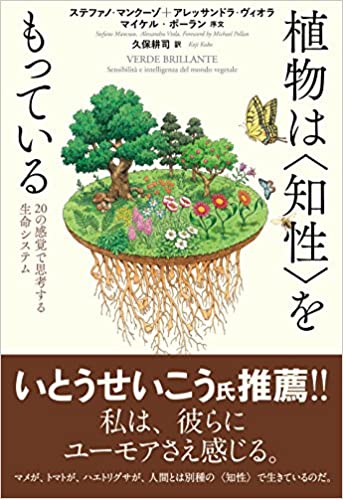
 �@
�@


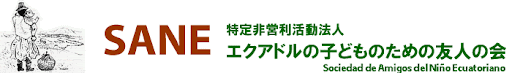
 �T���p�u���E���R���̃E���x���g�E�t�B�G���Z
�T���p�u���E���R���̃E���x���g�E�t�B�G���Z �@�}���R�|�[���@���炫�̃���
�@�}���R�|�[���@���炫�̃���
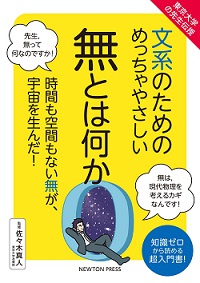
 �@���̃W���������
�@�i�T�L���j
�@���̃W���������
�@�i�T�L���j �@
�@

 �@
�@


 �@
�@

 �@2022.6.1�@�z��
�@2022.6.1�@�z��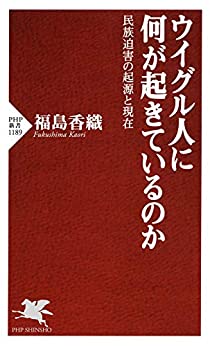

 1----3----9----27----81----243----��
1----3----9----27----81----243----��

 �@�V���L�ƃ^���m��
�@�V���L�ƃ^���m��



 �@NHK��HP���炨�肵�܂����B
���肪�Ƃ��������܂��B
�@NHK��HP���炨�肵�܂����B
���肪�Ƃ��������܂��B
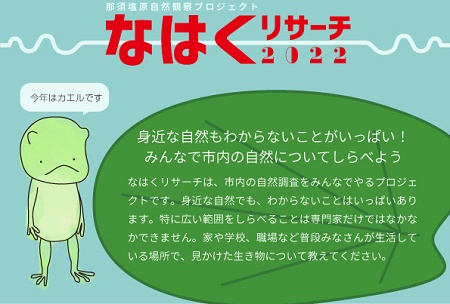






 ���ꂪ [�o�^�[�J�b�v�X] �̕c�@�뒆�ɑ����č��������Ƃ��B
���ꂪ [�o�^�[�J�b�v�X] �̕c�@�뒆�ɑ����č��������Ƃ��B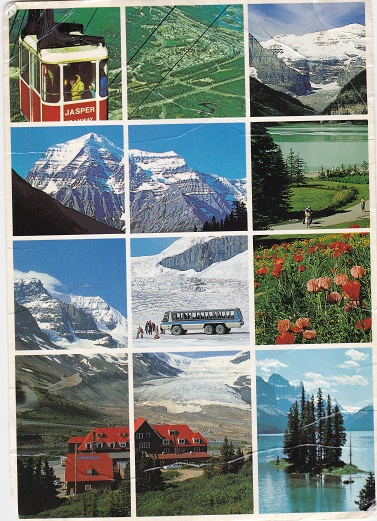






 �@
�@
 �@��␅�����ށ@���S�m��
�@��␅�����ށ@���S�m�� �@�͐���
�@�͐���  �I�I�n�N�`���E�@
�I�I�n�N�`���E�@ �@�}�K�� �J���ڃJ����
�@�}�K�� �J���ڃJ����
 �� �h�Ё@���������g���Ă���
�� �h�Ё@���������g���Ă��� �@�������@�Ԃт�͕�������`���Ă���B
�@�������@�Ԃт�͕�������`���Ă���B
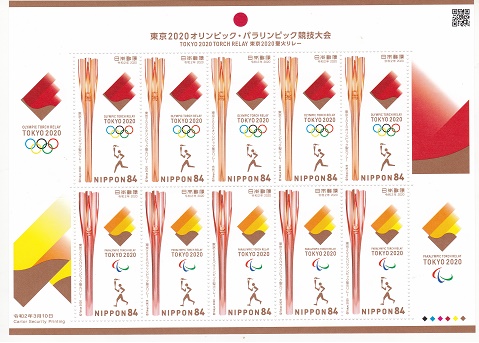

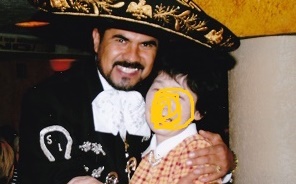
 �A�C�X�����h�|�s�[
�A�C�X�����h�|�s�[ �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@  �ӂ��̂Ƃ�
�ӂ��̂Ƃ� ����
���� 




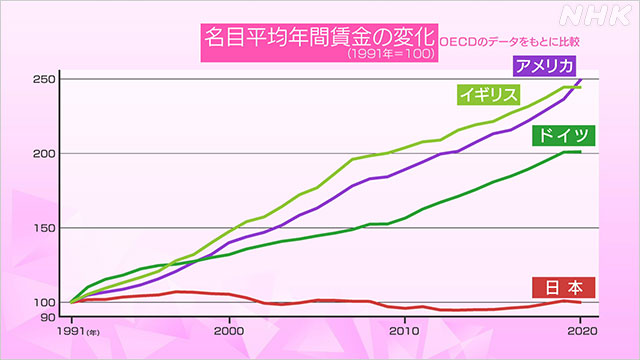 NHK���炨�肵�܂����B
NHK���炨�肵�܂����B

