|
 12��31��
�������
12��31��
�������
35�N�O����Q�����Ă���SANE�iNPO�@�l�G�N�A�h���̎q�ǂ��̂��߂̗F�l�̉�j����N���N�n�̂����A�����˂āA��͂����B
����́A�����ɂ����郏�N�`���ڎ�̏ƁA�X������̐V�N�x���}���A�q���������ǂ̂悤�Ɋw��ł��邩�̕ƁAJICA���̍����ƂɊ�Â��h�{�u�K��̗l�q�Ȃǂ��f�ڂ���Ă�
���B
�@�@�@�@�iJICA���Ɨ��s���@�l���ۋ��͋@�\�B���{�̐��{�J�������iODA�j���ꌳ�I�ɍs�����{�@�ցj
����ɐV�N�x���}���A��̒n�悩��I�ꂽ���ꂼ��13�l�ƂS�l�̐V���w���̏Љ�Ȃ���Ă����B
�I�l�ߒ��𒊏ۓI�ɕ\�������A�����ɑ����������̂ق����������Ă��������邩�ƍl���A���l���̉ƒ���Љ�Ă݂����B
�G�N�A�h�������{�̗��
����悤�ɁA�L���ȉƒ�ƕn�����ƒ�̊Ԃ̋���i�����傫���Ȃ��Ă���B�m�ɒʂ���q���AIT�@���^�����ĕ��ł���q���ƁA�Ƃ̎d������`���Ȃ���悤�₭�w�Z�֒ʂ���q���Ƃ̂��̑傫�ȍ��͖��߂悤���Ȃ��B���������n���I���R�������Ċw�Z�֒ʂ��Ȃ��q������������
�B
��������ď��w���Ƃ��đI���ƁA�����̐E�Ƃ̑I�����������ƍL���邾�낤���A���͋@���^�����Ȃ������q���������B�w�ԋ@���^����ꂸ�A�Z�\��g�ɕt���邱�ƂȂ��Љ�ɏo�Ă������N�Ə���----�D��ꑱ����l����I�Ԃ����Ȃ��命���̂̎�҂��������̌��ɂ���B
|
�@�r���� |
�T�b�J�[�D���ȗz�C�Ȑ��i�B�V�X�e���G���W�j�A�ɂȂ閾�m�ȖڕW������B���e�͓������Ă��炸�o�ϓI�Ȏx���������B��e�͍Œ�����̎����̂݁B |
|
�@F���� |
�E�ϋ������i�ŁA�����D���B���e���S���Ȃ��Ă���A��������̕�e�̎����͕s����B��100�h�����z���邱�Ƃ͂Ȃ��B |
|
�@�r���� |
���e���R�����O�ɖS���Ȃ�B�h���̂Ȃ��ł��ǂ����т��ێ����Ă���B���w�≻�w���D���B���͈�҂ɂȂ邱�ƁB |
|
�@�j���� |
�I�����C���ŕ��ł�����ɖ������A�D�G�Ȑ��т����߂��B�Ƒ������������e�����Ȃ��B��e�̎����͍Œ�����ɖ����Ȃ��B |
|
�@H���� |
�x�l�Y�G�����܂�B���͏b��œw�͉ƁB��Ɩ��̂R�l��炵�Ŏ����͌�50�h���i���{�~��6000�~���炸�j |
�ڂ������̂̓x�l�Y�G������̈ږ��Ƒ������l�̏��w�����I�ꂽ���Ƃ��B
�x�l�Y�G���͂��ē���ꍑ�Ƃ��Ēm���Ă������A����������n�C�p�[�C���t���Ƃ������o�Ϗ�̂��ƁA����s����ɂȂ�A���������܂⍑�𗣂������߂č��O�֒E�o�A���o���Ă���̂�����̂悤���B
1981�N�̔N���A���傤�Ǎ�����x�l�Y�G����K�₵�����A�X�͊��C�ɂ��ӂ�AOPEC(�Ζ��A�o���@�\)�̎�v���Ƃ��ĉh���Ă����̂��L�����Ă���B
���[�}���V���b�N�ɂ�錴���̒l������A�ʉ݉��l�̉����A���{�̊C�O�����A�����ɂ��X�Ȃ�ʉ݂̉����������Ă���B----�v���ł��Ȃ��قǂ̃C���t�����~�܂�Ȃ��i�n�C�p�[�C���t���j�ʉ݂͂قڎ���ɂȂ��Ă��܂����B�ǂ��ł���������R���i�ЁB���݃x�l�Y�G�������̂R���ȏオ���O�E�o���Ă���ƌ����Ă���B
�G�N�A�h���͊m���ɕn�����B�x�l�Y�G���͂���ɕn�R�ȍ��ɒ������Ă��܂����B�����X�y�C�����b���������A�ږ��i�قƂ�Ǔ�ɋ߂����j�Ƃ��đ����Ő�������ɂ͑z�������Ȃ��قǂ̋�J�����邾�낤�ɁB���̂��Ƃɂ��C�W��������炵���B�������������̊�t����������35�N�B�u�w��L���Ă��̐悪�G�ꂽ�ꏊ�ɐS���悤�v�ƍl����35�N�B
�����͐V�����N���n�܂�B

�@�@�@�@�@�@2021.6 ���i��̓��̏o�@�@�摜��T�����炨�肵�܂����B
�@
 12��30�� �������
12��30�� �������
�u������́A�ǂ��Ȃ����B�N�_�l�Ɋ肢���͂��Ȃ��B�v�u����ɁA�N���̗\�肪���Ă��Ȃ������҂��Ǝv���邾�낤�B�v
���������������B���̎��̕���40���������߂������납�B
�@�@�u�Ӂ`��v
�@�@���������͉̖T��ɂ��Ⴊ�݂���Ō��Ă����A�����炭�T�A�U���炢���������낤�B
�͘F���̂��ɓ���𑵂��A���̏H�Ɏ��n�����V�Ă̘m�𑩂ˁA�Ȃ���ؒƂłƂ�Ƃ�@���Ă����B��������Ƙm���͂���Ȃ肵�čH�����₷���Ȃ�B���̕����ő����w����A�����ዾ�̌`�ɐ����������肪����ɂł�������̂����Ă���͖̂ʔ����B���N�̎�����F���āA��̗���t������������{���}���Ă����A�^�����Ȏl��𗼕��ɐ��炵�A���̏�ɂ���߂�����Ō�ɂ݂����----�R���Ȃ̂ŁA��Ȃǎ�ɓ���悤���Ȃ�---���ѕt���Đ������肪�o���オ�����B
�܂����ւɁA�����đ��ɁA���ň�˕��ɁA�؏����A�Е������A�������Ǝ��t���ĔN�_�l�����}�����鏀�����������B
�傫�Ȉ͘F���ł́A���̏t�A�������҂����˂Ď����R�����o���ė����d���R���Ă���B�h��߂��Ԃ��Ɨ��d�����݂��ɂ��Ȃ��������Ă���悤�������B
�`�̏a��h�����a���̒��ɁA�݂ۖ�����������ł���B�_�I�ɂ͐V���������l�肪�Ђ�߂��A��̎}���s���Ɛ���Ă���B�������}����e�S���Ƃ��イ�ɖ����Ă������\�N���O��12��30��
�B
��������A���Ǝ��̉�b�͂��ׂāu�����v�łȂ���Ă���B���̂܂܂ł͗������Ă��炦�Ȃ��̂ŕW������ǂ��ɏ��������Ă��邪�A����ł͎�Â���ɂȂ闇�d���̈Â���A���a50�Z���`�͂��낤���Ƃ����I�̖̗���z�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�͂���̉��������������Ȃ��B���t�ƌ��t�����ɂ���u����Ȃ��ł����v����
���������Ȃ��B
���t�Ŏx�����Ă��镶���́A��������ĕω����Ă����̂��B���̂���̓��X�̕�炵�̒��ɂ������l�Ɛl�Ƃ̌q����Ɖ��������A�悻�s���̌��t�ł�
�v���o���Ȃ��̂��������₵���B
 |
�@
���R����ԏ��̎}�ƕO�t���A��悩���V�̎����W�߂Ă��āA����������������---����͌��ւɁB |
�ߌ�R���B���̂����͏�V�C�ŁA������Ԃ����ߐ{�R���ǂ��������̂ɁA�����獕���_�������Ă��ĐႪ�~��o�����B���悢�搳�����g������Ă����悤���B
 12��29��
��𓊂���@6���̋C���}�C�i�X�W���@���̓~�Œ�̉��x�@�ǂ����������������Ă���
12��29��
��𓊂���@6���̋C���}�C�i�X�W���@���̓~�Œ�̉��x�@�ǂ����������������Ă���
�킠���Ɗ����������B�f�b�L�̏�⓱���H�̐��Ⴉ���X�R�b�v�ł��������A�����ł͂Ȃ��u�ǂ����ցv��������A�Ƃ����d�����ς܂������炾�B���ʂ͈ȉ��̒ʂ�B�����Ղ�Ⴊ�ς݂������āA����Łu���܂���v����ꂻ�����B
������ɗ������́A��E�T�M�₩�܂��������ėV���̂����A�ŋ߂͂�������������肵���S�������Ȃ��Ă����̂��A�����Ђ������𓊂��邾���B
�����ł��B�Ⴉ���ł͂Ȃ��Đᓊ���Ȃ̂ł��B��������������ł́A��̍s���ꂪ�����ɂȂ��Ȃ�B�����珉�߂���A������ꏊ�̐S�Â�������Ďd���ɂ�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
���C�œ��ނƁA���カ�カ����ƁA��������B���Y�����̂��鉹���B
 ������܂ł̓��b�Z���Ԃ����Ă����
������܂ł̓��b�Z���Ԃ����Ă����
�ς�����������Ȃ���A�q���̂���̍ی��Ȃ��V�ѐS���v���o���Ă����B�~�̈�Ԃ̊y���݂́A�u�|�X�L�[�v�B�����̒��̍⓹������X�L�[�Ŋ���~��邱�Ƃ������B
�u�|�X�L�[�v���͓~�̏��߁A�Ⴊ�~��O�ɗ��R�̐^�|��50�Z���`�قǐ�o�����Ƃ���n�܂�A���e�̖ڂ𓐂�Ŏ����o������Ŕ����ɂ��A���A���C�̕����Ŕ��炵�A�X��h���Ď���̒|�X�L�[�����B����ŕ����̎q�ǂ��Ƃ��Ĉ�l�O�B
�Ⴊ�ς���Ǝq�ǂ������i���K�L�j���W�܂��ď���������Y�܂�-----�ǂ��̍��Վ��̃X�L�[��ɂ��邩---���̍�̏�̏�������̓R���C�A�������͑��v���낤----�{��ꂽ��Ƃ肠���������o����---�Ȃǂƍ��𗧂Ă�B
���n�W���B�F�ʼn����тɂȂ��Đᓹ�ł�3�����������Ȃ��X�L�[�ꂪ�o���オ��B
���̂��Ƃ́A�������グ�Ȃ��犊��~��A�X�L�[�������ďo���_�ɖ߂�A����̖������[�v�������B
�@
 12��28���@�S�Ԃ� ----�������@�肽�{��S���Ԃ����B
�ϐ�25�p�@�~�葱��
12��28���@�S�Ԃ� ----�������@�肽�{��S���Ԃ����B
�ϐ�25�p�@�~�葱��
�ߑO�ɏo�����Đ}���ق̖{��S�Ԃ������B�[���K�G�V���B�������B
��������2�T�ԂɈ�x�o�����đ݂��o�����x�������ς��̖{����Ă���B�������͂��ނ̂ŁA�ݏo���ԉ����������A����͐�悭�S���Ԃ��āA�V������Ă����B
�v���t���Ĉ�N�Ԃɂǂ̂��炢�肽�̂��L�^������Ă݂��B
���̈�N�ԂɎ肽�{�̐��͂Ȃ��300���ȏ�ɂȂ����B���̒��ł�������ǂ̂́A200�����炢���B�n�E�c�[�{�̏ꍇ�́A���߂���邽�߂ɃX�L�������Ȃ���ǂނ��Ƃ������B���܂ɗ\�z���O��đS�������������Ȃ��{�����邪�A����͂���ō���Ȃ������Ƃ������Ƃ��낤
�������A����ȓc�ɕ�炵�œǏ�������Ƃ������Ƃ́A
�@ �Ǝ������낻���ɂ��邩�A
�Ǝ������낻���ɂ��邩�A
�@ ���̎d���A���ɒ�d���ɖڂ��ނ邩�̂ǂ��炩���B�J�߂�ꂽ���Ƃł͂Ȃ��B
���̎d���A���ɒ�d���ɖڂ��ނ邩�̂ǂ��炩���B�J�߂�ꂽ���Ƃł͂Ȃ��B
�ʔ��������̂́A
| ���̖��c�� |
���ȐӔC�Ƃ����\�� |
�O���[�o���Y�������E��łڂ� |
�����`�Ƃ����s�v�c |
|
�J�Y�I�E�C�V�O���ǖ{�@ |
�I�v�̎��𗷂��� |
�y���M���̑��͂Ȃ�����Ȃ��� |
���삨���̍ד��@�@ |
| ���R���̃X�X�� |
�����ꗘ�̏��a�j |
�����Y�̋o�c�q�͌o��ŗ����邩�@ |
�f���[�~�̓�@ |
|
�G�N�A�h����m��60�� |
�����@�㉺�@ |
�c�Ӑ��q18�̓��̋L�^ |
���b�Y��̂��ׂā@ |
| �쐣�b����i�W |
�����͂Ȃ����ʂ̂��@ |
�X�p�C�X�J���[�V��@�@ |
�������{ |
| ���q�����@ |
�NJ��ɏo������ |
���������̂��������� |
����m�q�̍��� |
|
�P��̍� |
�l�ԂɂƂ��Đ��n�Ƃ� |
�{���̖|��̘b�����悤 |
��ɕ� |
| �q�����r�N���l |
���I�Ɖ��� |
�����̉̂���q�g�̌��t�� |
�C�̌����闝���X |
| �����m�푈�ւ̓� |
���̃X�C�X |
���܂�Ă����ȏ�͐����˂Ȃ�� |
�u�Ȃ���v�̐i�������w |
| �l�V���́u���{�_�v |
������I�������� |
�������͂Ȃ�����Ȃɕn�����Ȃ����̂� |
�V���N���[�h�I�s |
�ǂނ��Ƃł��܂��܂Ȍo�����ł���A����ɂ͉��l���邪�A�ǂ{�𗅗�̂�----����͈���̋ɂ݂��낤�B���̒����J���Č����邱�ƂɂȂ�̂�����B�{��ǂނ��Ƃʼn������ς��A���̍s���Ɉڂ���̂ł͂Ȃ�����A�Ǐ��͑s��Ȏ��Ԃ̖��ʌ����ɂȂ邩������Ȃ��A�Ƃ����̂��N���ɕ��������S���B
�@
�@  12��27��
�u�Q���j�J�v���ς��i�c3.5���[�g���A��7.8���[�g���j
12��27��
�u�Q���j�J�v���ς��i�c3.5���[�g���A��7.8���[�g���j
���U���̋C���̓}�C�i�X�S���B10�����݂̐ϐ�15�Z���`�A������͐^�����ŁA���c������d���̂��ꂱ�ꂪ�B��Ă��܂��Ă���B�悵����ł����A���N�̎d���̂�����͌��Ȃ����Ƃɂ��悤�B
���H�̂��Ɠ؏`�����A�Q�����Ă������B���̂��Ƃ́A�V���N�i�Q��n���Ȃǂ̐�~�낵�Ƃ��������d�����҂��Ă���B�|ⴂŐς��������@���ƁA�ʔ����悤�ɐ�ʂ��]���藎���Ă���B
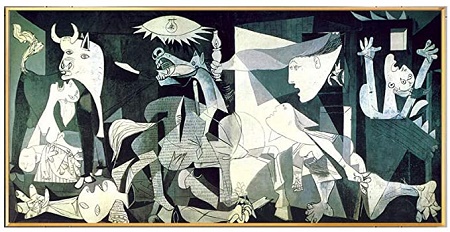 �@
�@ �@
�@
�@�@�@�@�@�摜�̓A�}�]�����炨�肵�܂����B
 ���i26���j��NHK���j���p�ق̃e�[�}�́u�Q���j�J�v�������B��O�s�o�̌����NHK��8K�B�e���Ď����A��A���{�ŋ��僂�j�^�[�ɉf���o���A���̊G�ɐڂ��������Ƃ�
��Ƃ��ǂ̂悤�Ȉ�ۂ���������������A�Q���j�J���`���ꂽ�������Ȃǂ̉�����Ȃ��ꂽ�B
�i�X�y�C���̉�ƃp�u���E�s�J�\��j�i�o���ҁF��������Y�@����[��Y�@������������j ���i26���j��NHK���j���p�ق̃e�[�}�́u�Q���j�J�v�������B��O�s�o�̌����NHK��8K�B�e���Ď����A��A���{�ŋ��僂�j�^�[�ɉf���o���A���̊G�ɐڂ��������Ƃ�
��Ƃ��ǂ̂悤�Ȉ�ۂ���������������A�Q���j�J���`���ꂽ�������Ȃǂ̉�����Ȃ��ꂽ�B
�i�X�y�C���̉�ƃp�u���E�s�J�\��j�i�o���ҁF��������Y�@����[��Y�@������������j
�Q���j�J���ς��̂͂��܂���12�N�O�̂��Ƃ��B���̊G����������Ă���X�y�C���̃\�t�B�A���܌|�p�Z���^�[�́A�O�ςɃK���X�𑽗p�������邢�����������ƋL�����Ă���B
�����ǂɋ��܂ꂽ�L����i�ނƁA�����傫���ŃQ���j�J������Ă����B�G�̓��m�N���[���Ƃ��܂��܂��~���̃O���[�ŕ\������Ă��āA���̑傫���Ɉ��|�����B
�u�L���[�r�Y���I�\���v�ƌĂԂ炵���B�ЂƂЂƂ̊G�̉A���̂��̎咣���Ȃ�����S�̂Ƃ��Ă̓��ꂪ���Ă���B����ɂ��̊G����F�������オ���Ă����B�G����������肩���Ă���B����͂�ŗh���Ԃ���
�B�s�J�\�����̊G���ے��I�ɕ`�������ƂŁA�̂��̐��Ɂu���푈�v�̃V���{���Ƃ��Ď����ꂽ�悤���B
��Q�����E���O��A�h�C�c��R�̓X�y�C���E�o�X�N�n���̌Ós�Q���j�J�ɖ����ʔ������s�����B�Q���j�J�̒j���͂قƂ�ǐ�n�ɂ������̂ŁA1600�l�̎��҂̂قƂ�ǂ͏����Ǝq���������B������G�ɂ͏����Ǝq���A�X�y�C���l�Ɏ���Đ����̏ے��̋��Ɣn���`����Ă���B
�i������1937�N4��26���j
�Q���j�J�ւ̔����ɓ{�����s�J�\�́A�����ɋ}�����Ă���悤�ɂ������Ђƌ��ŋ���ȁu�Q���j�J�v��`���グ���̂��B
���������p�ЂƉ������߂��݂̊X�u�Q���j�J�v����l�ŖK�ꂽ�̂́A�{�����ς�3�N��̂��Ƃ������B�X�̒��S�Ɂu�Q���j�J�v�̑�Ŕ��f�����Ă͂�����̂́A�������ꂽ�X�̎p����́A���Ă̎c�s�ȍs�ׂ̎c��͌����Ȃ��B�����A�Q���j�J���a�����قœW���i�����w���A�̉������������S�̂��h���Ƃ����펞�̌����������Ƃ������L���Ƃ��Ďc���Ă���B�푈�̋L����������Ɏc�����Ƃ͓���B
�o���Z���i�̃s�J�\���p�ق�K�₵���̂́A����ɂ��̂R�N��B
�s�J�\�̎Ⴂ������̍�i���A���n��ɓW������Ă���B�O���͂����ς�K�삪���т�����s�J�\��i�����܂茩���Ȃ��B�s�J�\���p�ق̌��ǂ���̓x���X�P�X�́u���������i���X�E���j�[�i�X�ELas
Meninas�j�v���s�J�\���A�����W������i�Q�������ƋL�����Ă���B�����ň�ԂɊ��������Ƃ́A�u��{�̃f�b�T���v���������Ƃ������ƁB������ɂ������ʂ�ɔ��p�ق������āA�悤�₭�^�N�V�[�ł��ǂ蒅�����B�A��ɃK�E�f�B�̃T�O���_�E�t�@�~���A�։��݂������̂������v���o���B
 �W���K�C���̃K���b�g�i�W���K�C���A�n���A�L�m�R�A�x�[�R���A�`�[�Y�j����������A���`�[�Y�̑܂Ɖʓ��̑܂��ԈႦ�Ă��܂����B����Ăĉʓ����d���o�������A�����c���Ă��܂����B�܁A�Ö�������K���b�g���Ǝv���������B �W���K�C���̃K���b�g�i�W���K�C���A�n���A�L�m�R�A�x�[�R���A�`�[�Y�j����������A���`�[�Y�̑܂Ɖʓ��̑܂��ԈႦ�Ă��܂����B����Ăĉʓ����d���o�������A�����c���Ă��܂����B�܁A�Ö�������K���b�g���Ǝv���������B
 �ߐ{�삪�������ق́u�o�b�N���[�h���w�c�A�\�v�ɐ\�����B�撅��10���Ȃ̂Ńt���C���O�C���̎��Ԃ��������A�Ȃ�Ƃ���l���̐Ȃ��m�ۂł����B�i2022.3.20�̗\��j �ߐ{�삪�������ق́u�o�b�N���[�h���w�c�A�\�v�ɐ\�����B�撅��10���Ȃ̂Ńt���C���O�C���̎��Ԃ��������A�Ȃ�Ƃ���l���̐Ȃ��m�ۂł����B�i2022.3.20�̗\��j
�d�b�̂�����́A�ẴZ�~�ώ@�L�^�S���҂������̂Łu�₠�₠�v�ȂǂƘb���B

�@
 �@12��26���@�@�����͗ʂȂ̂��@----�Ⴊ�~�肵���� �@12��26���@�@�����͗ʂȂ̂��@----�Ⴊ�~�肵����
�\�z�ʂ�A�锼�̋����������܂����ߑO4�����炢����Ⴊ�~��n�߂��B�N�����͂ق��2�Z���`�قǂ������̂ɁA���Ԃ��o�ɘA��Ď���ɂЂǂ��Ȃ��Ă����B
����6���̊O�C���̓}�C�i�X3���B4���Ԍ�̍��̊O�C������͂�}�C�i�X3���B�����Ƃ��g�����Ȃ��ė��Ȃ��B�ϐ��7�Z���`�ŁA���������ďd�����ɂ��Ă���B�ߌ�ɂ͐�~�낵���v�邩������Ȃ��B����͊����d�����Ȃ�----�B
�u���܉��x�H�v�ƌ����Ȃ���N���Ă��鎄�����B�C�����v���X30������}�C�i�X4���܂ł͂���Ȃ�Ɓu�Z�Z�x�v�ƕ\������̂ɁA�v���X30���ȏ�ƃ}�C�i�X5���ȉ��̏ꍇ�́A�u35��������I�v�A�u�}�C�i�X7��������I�v�Ƌ�������\�����g���̂͂Ȃ����낤���B���ʂłȂ������Ɗ����́A�ʂƂ��đ����A�d�����Ƃ��Ċ����Ă���炵���B
�����̒����Ɏs����́u�V�^�R���i���N�`���lj��ڎ�i3��ځj�v�̂��m�点�����ݍ��܂�Ă����B
1�T�ԑO�܂ł̎s�̂g�o�ɂ́A3��ڂ̐ڎ�\��́A�u2��ڐڎ킩�炿�傤�ǂW�P����̓����ꏊ�œ����ꏊ�v�Ƃ������B�O��̐ڎ�����̃f�[�^�����̂܂ܗ��p�i���c�J�����j���������I�����A����҂��\������̂ɂ����ӂ����Ȃ��čςށB�O��\���
��s�����F�l����������ň��S���Ɗ��ł����̂ɁA�Q�T�Ԃ̐ڎ�O�|�����e�������̂��A�傫�ȕύX���Ȃ���Ă��܂����B
�O��ƈႢ�A�ʐڎ�i���������ł̐ڎ�j�͍s��Ȃ�����ɁA�s����5�����̈�Ë@�ւ�ڎ���Ƃ��Ďw�肵�A�N��ȂǂŃO���[�v�������ė\����t����炵���B�l�b�g�ŃA�N�Z�X�ł��Ȃ�����҂��������A�\��p�̓d�b�����啝�ɑ��₵���Ƃ��邪�A�F�l
�̈�l���g���Ă���d�b��͐̂Ȃ���̃A�i���O��d�b��Ȃ̂ŁA�ƂĂ��Ԃɍ��������ɂȂ��B
���l���̗F�l�̕����\�Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ŁA�����͂͂��ƃA�h���i�������o���B
�悵�A���̓��̒��͂�������W�����悤�ƁB
 �@�A�C�X�����h�|�s�[�̕c�i�d���90���j �@�A�C�X�����h�|�s�[�̕c�i�d���90���j
 12��25���@----�͔�T������
12��25���@----�͔�T������
12�����{�͖����̓V��̕ω����傫�������B�������̓�������A���t���a�ɂ������g�������Ɍb�܂�邱�Ƃ��������B�z�B���ꂽ2�g���͔̑���A�،͂炵�̍��Ԃ�D���A�蕪�����ĉԒd�ɎT���I������B���N�͑��߂ɐ���̉肪�o�Ă���̂ŁA���������ăX�R�b�v��U��̂�����B
��֎Ԃ�76�t�Ƃ͑����ȗʂ������B��������ƂɁA���ɂɂ͉����Ȃ����^�V�B�s�@�ӂ����������Ȃ̂ŁA���܂ɂ͂����Ƃ���̈���������
���̌������~���z�������ɂȂ��B
�ߌ�R���ɂȂ�Ƌ}���ɋC�����������Ă���B���������̗\��B�����ӂ�Ȃ������̒������ς܂��A�K�\�����^���ɂ��Ă����B�K�\�����X�^���h��߂��̓��̉w�ɁA�ό��q�̎Ԃ����Ă���B�X�L�[��ɂ͂����Ⴊ�ς����Ă���悤���B
�@�@���R�̕�炵634. 2021.12.25�`12.31�@�@ �@
�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �̎����E���ĐX�ւ��ǂ�
�̎����E���ĐX�ւ��ǂ�

�����ʂ��ăG�N�A�h���̎q�ǂ��x������NGO�i���ۋ��͖��Ԓc�́jSANE�ɎQ������36�N�ɂȂ�B
�G�N�A�h���̎q�ǂ��̂��߂̗F�̉�iSANE) <
http://sanejapon.blogspot.com/ >
�H�̏I��A������炨�m�点���������B
�u�J�����x�̏��w���̃_�r�b�h�N��瀂������ɑ����A���̓����ӎ��͂��������̂́A�Иr�ƕБ������䂵���B�����Ɏ�p���I���A���n�r�����邱�ƂɂȂ������A�̂��قƂ�Ǔ����Ȃ����߁A���ナ�n�r���ɒʂ��K�v������A���̂��߂̔�p��������B����͉Ƒ��ɂ͑傫�ȕ��S�ɂȂ�v�ƁB
��Ô�͕ی��Ŏx�����邪�A���n�r���̔�p����A��ʔ�Ȃǂɖ�1000�h�������邻�����B�Ƒ��̕��S�̑傫���͌����܂ł��Ȃ��B���܂܂ŋً}���ɃT�|�[�g����̐��������Ă��Ȃ���������ǂ��A�u�_�r�b�g�N���x�������t�����肢�v�Ƃ��������������������B�W�܂��������̓_�r�b�h�N�̉Ƒ��̕K�v�ɉ����Ďx�������B�]������o���ꍇ�́A����ً̋}���Ԃɔ�����ׂ��Ǘ������B
�@�i2020�N�̈�l�������GDP�́A��5,600USD )
�@�i����������͕��ς��ꂽ�����ŁA�����̌o�ϊi���͂ƂĂ��傫���B�H���������ɐۂ�Ȃ��n�����ƒ낪�����B)
 �N���X�}�X���������B �N���X�}�X���������B
�@�@�@�n�҂̈ꓔ���ǂ������Ƃ炵�Ă����悤�ɁA������t�����B
�@�@�@�����Ƃ��̊y���݂����A�_�r�b�g�N�̐g�̂̉ɕ�����̂ɁA�ӂ��킵���G�߂��B
�@�@�@�ق�̂ЂƂ������B
�G�N�A�h���̐�Z���ɓ`��閯�b�@---�@�n�`�h���̂ЂƂ������@�i�Čf�j
Había una vez un incendio en el bosque.
Todos los animales, insectos y pájaros en el bosque corrieron
por sus vidas.
Pero había un colibrí que se llamaba KURIKINDI iba y venía
botando una gota de agua en su pico al fuego.
Cuando los animales lo vieron, comenzaron a reir, �g¿Para que
sirve?�h
Y KURIKINDI respondío,
�gYo estoy haciendo lo que puedo.�h
�X���R���Ă��܂���
�X�ɂ��ޓ����⒎�Ⓓ�����͈�ڎU�ɓ����Ă����܂���
�ł��A�N���L���f�B�Ƃ������̃n�`�h��������
�������ɐ��̂���������H���^��ł�
�X�̉̏�ɗ��Ƃ��Ă����܂�
���������͂��������
�u����Ȃ��Ƃ����ĂȂɂ����ɗ��̂��H�v�ƌ����ď��܂��B
�N���L���f�B�͓����܂�
�u�o���邱�Ƃ����Ă��邾������v �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ٖ�j
�G�N�A�h���̖��b�Ȃ̂ŁA�{���A���ăC���J��������������Z���̌��t�i�P�`���A��@Quechua�j�ŏ�����Ă���͂��B�V���v���ŗ͋������t���A�l�̐��_�ɋ����Ă���B

�`���{���\�R�i6268m)�ƃn�`�h��
�`���{���\�Ƃ͌��n��Łu����v�B���O�̒ʂ�X�̗͂߂��u���[�Ɍ���
���R�̕�炵633. 2021.12.21�@ �@ �@
�@�@�@�@�@�@
 ����݂̂�����
----���܂���
����݂̂�����
----���܂���
�k����݂̂ЂƂ育�Ɓl
�������厖�Ȃ̂́A�q�����c�����ƁB���̏t�Ԃ��炩�������Ɏ𗊂݁A�Ă̏����ɑς��ĉʎ��i�j�ʁj���悤�₭���点���B�H�̕��ɏ���Ēn�ʂɗ����悤�Ƃ����A�܂��ɂ��̎��A���̉��ɑ҂��Ă���l�Ԃ����悤�Ƃ͎v�������Ȃ������B�~�̊Ԃɒ�ɗ���쒹�̉a�ɂ���炵���B�f�v����ĉ�ɕԂ肠��������ƁA��������̒��Ԃ��߂���̐g�ɂȂ��Ă���ł͂Ȃ����B
�k��Έ�̑Ή��l
�߂��̗��_�_�Ƃ��番���Ă����������u�����͔�Q�g���v���A�{�i�I�ȓ~������O�ɒ�ɎT���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���̓~��Ԃ̊��g������Ă���Ƃ����j���[�X�ɁA���̐����A�ł��Ă����B
�͔���~�낵���ꏊ�����֎ԁi�Ȃ����l�R�E�L�ƌĂ�Ă���B�L�̎���肽���H�j�ʼn^�Ԃ̂����A�������肷��Ɖ^��ł��邤���ɁA���t�ڂ������̂���������Ȃ��Ȃ�B�܂�ŗ���̎������B���v�����Ƃ��������A���ꂩ��̎d���̗\������ނ��߂ɐ������~�����B
���_���l�������Ƃ͂������B�X���ɏW�߂Ă����u�I�j�O���~�E�S�ӓ��v�ƒi�{�[���̏�����p�ӂ��āA���I��邲�Ƃɂ��̃N���~�̒��ɓ���Ă����Ƃ������@�B
������������A�v�킸�u����͂́v�Ə��Ă��܂����B����͗��R�ɏZ�ރl�C�e�B�u���{�l�̂悤�ł͂Ȃ��H���邢�̓v���~�e�B�u���{�l�ƌĂ���������������Ȃ��B�u��Έ�̑Ή��v������Ȍ`�ł͂����Ƃ́B
����̗[���ƌߑO�̎d����37�͔̑���Ԓd�ɉ^�ѓ��ꂽ�B����̉�ɂ����Ȃ��悤�ɒ��ӂ��ă��[�L���g���čL���Ă������B---����͌��\���ƌ��ɂ���B�����Čߌ�A���������̗\��ɂ킪�g���܂��Ďc��͔̑���^�т��ށB���̉�25��B
�����č����͐�B��̉��ɂ���͔�͐�����⋋����ė��z�I�ȏ�Ԃɂ��邾�낤�B�\��ʂ�Ɏd�����i�ނ��Ƃ͂߂����ɂȂ��̂ŁA����ȂɊ��������Ƃ͂Ȃ��B

�k���w�̂�����������l
�Q��O�̈Ԃ߂ɂƁA���̂Ƃ���u���̕���W�v�����ǂ݂��Ă���B
��23��19�b�ɔ�b�R�����ɏZ�ގ����m�s�̘b���������B
�u����ɋɂ��͗L��l�ɂėL����B----�m�s�A���Q�����肯��ɁA�Ⴋ��q���A�t�̗͗L��R�āA���ނ��ׂɁA�ӓ�����Ď����āA�m�s�̑��̎w�\�����Ɍӓ������݂��肯��A�m�s�͋��Q�������肯��A�ŔC���Ě�܂�Č�A�Q�����ׂ�l�ɑł��ނ߂đ����݂���A���̌ӓ��A��x�ɂ͂�͂�ƍӂɂ���B�v
�����A�ǂ�ȗ͎����Ȃ낤���I�I�j�O���~�͋��Â����g��Ȃ��Ɗ���Ȃ��̂ɁA���̎w�ŋ��݊���Ƃ́I-----�����Ă݂����A�����܂ł��Ȃ����̑��w�ł͊���Ȃ��B���X�h����B
�@�@
 �@�͔���T���Ă�����A�~�~�Y�����Ȃ����ƃL�W������Ă����B �@�͔���T���Ă�����A�~�~�Y�����Ȃ����ƃL�W������Ă����B
�@�k�������ɐH�ׂĂ��������l----�@�̐g���{����N���~�̎�
���ɏW�߂��I�j�O���~�̐���1021�B���Â����g���ƁA�]�̌`�Ɋ���Ă���B���̎����W�߂ăN���~�a���ɂ���ƁA�܂��Ƃɔ��������̂����ǂ��A����͒�ɗ���쒹�̂��߂ɏW�߂��̂�����A�l�Ԃ���O�𝛂˂�킯�ɂ͂����Ȃ��B12���ɓ������̂ŁA����ɂV�̊����Œ������ɔz���Ă���Ă���B���������̎��b�������Ղ�̃N���~�ɑ��т��Ă��钹�����B������ςĂ�������͂ق̂ڂ́B



���R�̕�炵632. 2021.12.18�@�@ �@ �@
�@�@�@�@�@�@�@
 ���������
���������

�ق��ق��Ə��C���オ���Ă���̂́A���_�_�Ƃ́A�����͔�����郉�C�����璼�ڃz�C�[�����[�_�[�ɍڂ��ē͂���
�u��������́v�B�K���S���Ƒ傫�ȉ��𗧂ĂȂ���A����ԂɏZ��n�̒���ʂ��Ă���Ă����B
�u�����{���������{���݊k�v�y���������̂ŁA pH�l(�y�[�n�[)�͂ǂ̂��炢���H4����S.�T���炢�H
�������炱�͔̑���Ԓd�ɏ������݁A��̍����ɕ~���Ă��B��y�ΊD���K�v���B
���N�Ō�̒��ƂɂȂ�B�ǂ������_�̍����Ō�܂Ŏ����܂��悤�ɁB�i���A������Ƃ̔����������܂���j
 �Ⴂ���� Wheellroader �̓C�P�����B���N�ɂȂ����p�͏a���ĂȂ��Ȃ��̂��́B�@
�Ⴂ���� Wheellroader �̓C�P�����B���N�ɂȂ����p�͏a���ĂȂ��Ȃ��̂��́B�@
�@
�@�@ ���R�̕�炵631.
2021.12.15�@�@ �@ �@
�@�@�@�@�@�@�@
�@
 �����̂��s�����Ă���@----���ꂪ�g�߂ɔ����Ă���
�����̂��s�����Ă���@----���ꂪ�g�߂ɔ����Ă���
���_�̕��ʎԁi�SWD�j�Ǝ��̌y�����ԁi�QWD�j�p���āA���S���u�������T�|�[�g�J�[�i���̃T�|�J�[�j�ɏ�芷���邱�ƂɌ��߂��̂͂���11���������B
�@�@�i�T�|�J�[�F�Փ˔�Q�y���u���[�L�i�Ε��s�ҁj�A�y�_�����݊ԈႢ�}���i�}�����u�A�Ԑ���E�x��A
�@�@�@�@�@�@�@�@��i���C�g�i�����ؑ^�O�Ɠ��j�Ȃǂ̋@�\�����ԁj
���������T�|�[�g�J�[�̔[���͂P�Q�����{�ƕ�������Ă����̂ŁA���������Ȃ����A�X�m�[�^�C���ɗ����ւ���O�ɔ��p�葱����i�߁A���X��11�����{�ɕ��ʎԂ�������Ă��܂����B
�Ƃ��낪���E�I�Ȕ����̕s�����e�����āA�u�[�Ԃ͗��N�P�����ɂȂ肻�����v�Ƃ̘A���������Ă����B�Ȃ�A���݂̌y�����ԁi�QWD�j�łP�����܂ł��̂������Ȃ��B�X�m�[�^�C���𗚂������ƌ����Ă����ʎԁi�SWD�j�قǐᓹ�ɋ����Ȃ����낤�B
�[�Ԃ̒x��̌����́A�����̕s���ƃR���i�Ђ̉e���Ŏ����Ԑ��Y���̂��̂���������ł��邱�Ƃɂ���炵���B���̂����ŎЉ�S�̂ɑ傫�ȉe�����o�Ă���悤���B����Ƀ}���[�V�A
�Y�̃S�����s�s�⍑�������̉e�����Đ��Y�ʂ�����A���E�I�S�����v�ɒǂ��t���Ă��Ȃ��B�����ԓ����p�̌������s�����Ă���炵���B
�@�@�@�i���|�p�̎g���̂ăS����܂̒l�グ���ɂ��B�R���i�O�̖�R�{�ɂȂ����B�j
���݂̒��ÎԎs�ꂪ���~�܂肵�Ă���̂��A����ȂƂ���ɗ��R�����߂���悤���B���{�̒��ÎԂ𓌓�A�W�A�ɗA�o���Č��n�ōĎg�p����炵���B���_���������T�Ђ̕��ʎԂ́A�A�W�A�̂ǂ����łQ�x�ڂ̐l���𑗂邱�ƂɂȂ�̂��B����͂���ŒN���̖��ɗ��̂�����[���ł���B
��������V�[�g�̉��ɁA�莆�ł��B���Ă����悩�����B
�T�|�[�g�J�[�̔[�Ԃ�҂��āA孋��̓~�ɂȂ肻�����B
�@
 �����̂Ƃ͂ȂɁH
�����̂Ƃ͂ȂɁH
���E�̌o�ς����E����قǂ̏d�݂����u�����́v�Ƃ͈�̉��Ȃ̂��B���t�����͒m���Ă��Ă��A����͒P�ɒm���ł����Ȃ����A���������m�����̂��̂��������킹�Ă��Ȃ��B���Ɏ���Ĉ�ԃC���[�W���₷�̂́A�u�p�\�R���̃n�[�h�f�B�X�N���J����ƁA��Ղɍ������̂�����Ă���B��������s���s���b�ƂЂ��������Ă���v��Ԃ��낤���B�����̂̋�̓I�Ȏp�Ƃ��ĖڂɌ�����̂����̍������́B
�����������Ă݂悤�A�Ǝ�Ă����̂��A���̖{�B
�@�@�@�w�u�����́v�̂��Ƃ�����ł܂邲�Ƃ킩�� �x
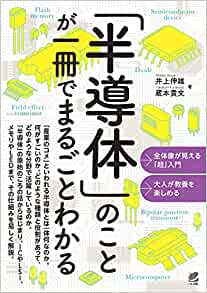 ��� �L�Y �A ���{ �M�� (��) �@�x���o�Ł@2021.11.25��
��� �L�Y �A ���{ �M�� (��) �@�x���o�Ł@2021.11.25��
�����̂Ƃ́F
��f�̖{�ɂ�����ɁA�����͓̂�̖����ɕ�������Ƃ������B
�������̂P.�@�d����d���𐧌䂷��i�A�i���O�����́j
�@�@�@�@�@�@�@�X�C�b�`----�d���𗬂�����~�߂��肷������B���䂷��B
�@�@�@�@�@�@�@�ϊ�----�d�g�M����d�q�@��̂Ȃ��ň�����悤�ɐM����d�g�ɕς��铭��
�@�@�@�@�@�@�@����----�Z���T�[�������������ȏ���d�C�M���ɑ�������B
��������2.�@�l����@�\��S���@�i�f�W�^�������́j
�@�@�@�@�@�@�@�v�Z����---�v���Z�b�T
�@�@�@�@�@�@�@�L������---������
�����܂ł͕�I�Șb�Ȃ̂ŁA�����ł���B�����͓̂��̂Ɛ≏�̂̒��ԂɈʒu���Ă���Ƃ��B
���������̌オ��肾�����B�����̂̌��n����n�܂�A���{�̒ʐM�Z�p���t�����̘b��AIC��LSI�A��������LED�܂ňՂ���������Ă���---�͂��Ȃ̂ɁA��܂��ɂƂ炦�邱�Ƃ����ł��Ȃ��B���̏o�����̏ڍׂ𐔎�����ʼn������Ă��邪�A���w�{�d�C���s�̎��ɂ͂��ށB���������Ƃ�
�\�ʂ��Ȃ��邾���ŏI���\���������邱�Ƃ��o���Ȃ��̂��B
�u�Ȋw�I�ɂ₳����������Ă����āA�����̊J���̍őO���ɗ����Ă������҂����炱����������e�ŁA�Z�p�j�v�f���܂݁A��[�Z�p�܂ł�������Ƃ炦�Ď���ɗ�����Ȃ����发�v�Ȃ̂ɁB
���̂��̂̐��i�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��A�z���͂ł��邪��������グ��H���⌳�ɂȂ鐔���������Ɠ��ɓ����Ă��Ȃ��B
�J�̌ߌ㔼�������ēǂݒʂ������A
�ʓ|�Ȃ��Ƃ͂�������A�Ƃ��������̐��i���łĂ��āA�O���͂Ƃ������A�㔼�̐����͐[�������ł��Ȃ������B
���Ď���̂́u���ɂ��Ȃ����l vs
���ɂ��Ȃ��Ă��Ȃ��U���Ȏ��v�̑Η��B�\�ʂ������Ɵ����ĕ������Ă������ɂȂ邪�A���̉��ɍL���鍪�����̊̐S�ȕ����ɖڂ��s���͂��Ă��Ȃ��B
�����A�c�O�B�����ŃC�x���g�͂����܂��B����ł͎O���V��ɂ����Ȃ�Ȃ��B
�@�@*�@�̖��ŁA�u���p�`�̒��_��ABCD----�Ə��ɔԍ���łƂ���v�B
�@�@�@���̔ԍ��̈ʒu��ς�����A��������番����Ȃ��Ȃ�N������̋C���ɂȂ����B�i������l�ɂ͕�����b�j
���R�̕�炵630. 2021.12.10�@�@ �@ �@
�@�@�@�@�@�@�@
 �@���蕨�̓�� �@���蕨�̓��
�����ւ����V�����X�m�[�^�C���̒��q������̂����˂āA�����炨�Ε��葱���ɏo�����Ă����B������͂���������W�ɂ�����B�����ƁA����������d�Ȃ����I�ԂƂ́A���Ȃ��炿������肵�Ă���B
�������ĔY�ނقǂ̂��Ƃ��Ȃ��I��ŏI������B����ŔN���̎d������I��B�`�F�b�N�������ڂ���������Ă�����Ƃ��I���Ɛ���������A�Ƃ����i��肾�B
���Ε�Ƃ������B����ɂ͂���v���o������B���_�������̂���A�G�߂ɂȂ�Ƒ�}�ւ�����Ă��ē͂��Ă����i�����A���X�Ɂu��苑�ہv���Ă�������
�Ȃ̂��B
�h���C�o�[���u��������ۂł����H�v�Ɩ���̑O�ŕ����Ă���B�u�͂��v�Ǝ��B�`�[�̗��Ƀn���R�������ċ��ۏI���B�u�[�Ɖ��𗧂Ăăg���b�N�������Ă���---�u����̓J�j�A���̑O�̓r�[���B���̑O�͔����������珤�i�����낤�ȁv�Ɩ������܂����v�����肵�Ă����B�����͉�Ђ̎�����肾������A�l�c�Ƃ̕���������B
���鎞�ȂǁA�����i�l���Ǝ�j�̉��l����
�u�Ȃ�����Ă��������Ȃ������̂ł��傤���v�Ƃ̓d�b�������Ƃ��������B
���_�̈ӌ����Ă̎��̕Ԏ��́A
�u���܂��d���̗��ꂪ�Ⴄ�Ƃ���ɂ��邾���ŁA����܂Ǝ��ǂ��͋������Ďd�������Ă��钇�Ԃł��B����Ε����Ȃ̂ł��B�����������\���グ�Ă���̂ł�����A�����Ă��C�����̖����悤�ɂ��肢���܂��B�v�Ɠ������B�Ȃ����u�����h�ȕ��Ȃ̂ł��ˁv�Ƃ̕Ԏ����������̂��o���Ă���B���h�H����͂��������A�䏊��a�����w�Ƃ��ẮA�������c��B
�������ȁA�������̑��蕨����邱�ƂŁA�d���ɉe���������Ă͂����Ȃ��A�Ǝv�������B
�傰�������A�u�����m�푈��̐H�Ɠ�̎���ɁA�ŕĂ����ۂ��ĐH�ƊǗ��@�ɉ������z���H�Ƃ݂̂�H�ב����A�h�{�����ʼn쎀���������v�̋C�������ق�̂����������ł���B�����̐M���邱�Ƃ��т��邩�B�n���ē݂��Ȃ��悤�ɁA�ƐS�����������B�ł��������A���B
�����A���V�A�v���C�h�������B���_�ɂ��̍s���ɋ�藧�Ă�̂͂��̂ǂꂾ�낤���B�ӌŒn�Ȃ̂�������Ȃ�---�������t���v�������B����́u�������悢�v���B
������_�̌Z�v�w�ɂ��Ε�������肵���B�`�o�ɂ̓T�C�Y���m���߂č��̃J�[�f�B�K���A�`�Z�ɂ͓��{�O���\���́u�������\��3��v�A�萻�̊����`��M�q���R�A�J���V�E���⋋�̂��߂̃E�F�n�[�X�̋l�ߍ��킹�A�C�ۂȂǁB
���ł�����������̂�T���ĂЂƌ��̊ԁA������������땂�����v���������B
���̓��A�`�o�Ɠd�b�łP���Ԃ���ׂ�ʂ��A�Ƃ���͂����̂��ƁB���ł��������Ċ������B�Ȃɂ���`���e�̍Ŋ����Ŏ���Ă�������������l�Ȃ̂�����B
�@
�@�X�C�X�A�O�����f�������g�̌i�F�i2021.12.1�j�@�i�z�e���E�_�[�r�[��3�K�A�H�������������j
����Ɍ�����̂��A�C�K�[�k�ǁB�A�C�K�[�r���[�̕����ɂS�A�����ăn�C�L���O�����̂͂����W�N�O�ɂȂ�B�E��̓C���^�[���[�P���ɍ~���d�ԁB����̂P�Ԑ�����́A�A�C�K�[�������ă����O�t���E�������d�Ԃ��o��B
�i�ʐ^�͓��{��ό��ē���HP����j
�@
�@�@�@�@�@�@���R�̕�炵629. 2021.12.5�@�@�@
�@ �@
�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@ �@����
�Ă̎����ԋ��K�� �@����
�Ă̎����ԋ��K��
�H�̏��߂��炸���ƋC�ɂȂ��Ă����Ƌ��؍X�V�̂��߂̋��K�ɁA�v�����ďo�����Ă����B������S�O�N�O�ɓ�ĂŎ擾�����Ƌ������̂܂ܓ��{�Ɏ����A��A�Z�\���`�F�b�N����邱�Ƃ��Ȃ���ւ����̂�����A���̉^�]�̘r�̓w�^�̋ɂ݁B
�S�O�N�O�̓�ĂłقƂ�ǃe�X�g�炵���e�X�g���Ȃ��A������Ɖ�薼�O�������Ă����܂��A�Ƃ��������ɍ��i��������ƌ����ċZ�p���g�ɂ��Ă���킯�ł��Ȃ��B
�A�����ĉ^�]���n�߂��̂͂���15�N��B�Ԃ����{�ԂŁi���̂��́j���H�ɏo�ė��K���āA���̂܂܍��Ɏ����Ă���B���K���̃R�[�X���m��Ȃ����A���ȗ��̉^�]�Z�p�����g�ɂ��Ă��Ȃ��B�Ȍ�5�N���ƂɖƋ����X�V
�ł������̂́A����e�X�g����ƍl���������ŕs���͂����ς��������B���K���̃R�[�X�𑖂�ƍl���邾���ŁA�g���k�ށB�����A��������ׂɏ悹�A�u���A���������̎�������ċ��K���Ȃ���̂ɗ����̂͏��߂Ăł��B���ʎԂɏ����̏��߂ĂȂ̂ł��B�v�ƌ����܂��������ƁA
�������̊炪������A����Ȃ̃T�u�u���[�L�ɏ悹�����ɗ͂��������悤�ȋC�������B�u���̎Ԃ��Ԃ��Ȃ��ł��������ˁB�ُ����Ă��炢�܂���i���j�v�B
���������������Ƃ�youtube�ŗ\�߃C���[�W���Ă������炩�A�r���J�[�u���N�����N����Ȃ��ʂ�߂��āA�ꌏ�����B����Œa�����O�ɍX�V�葱��������ΐV�����Ƌ�����ɓ��邱�ƂɂȂ����B
�������A�����o���������B���̋��K�����������ɁA��ʖ@�K�������炢���A���ɍ���҂��Ƃ��₷���ԈႢ�ɒ@�������Ƃ͈�Ԃ̎��n�������B
�ߐM����ȁA���s�җD�悾�A�댯�Ɨׂ荇�킹�ɂ��邱�Ƃ�Y���ȁB�ƁB
 �@���̂Ƃ���̎�d�� �@���̂Ƃ���̎�d��
���R�̕�炵628. 2021.12.1�@�@�@ �@
�@
�@�@�@�@�@�@�@
 �������I���
�������I���
11���̖Z�����Ƃ�����---�u��Ԃ悤�ɉ߂�����X�v�������B
�ĉԒd�̐����Ɨ��t�ւ̏����A�c�̐A�����݁A�e�����@��グ�Ĕz���ĕ����B�`���R�������B�����F�l�ɂ�������������B
��2��������ɏo�����߂̒i���ƁA�Ǝ҂ւ̎�z�B���l���̔������Ǝ҂�����Ă���B�V�����Ԃ̑I��ƒl�������A���t�@�C�o�[�~�݂ւ̎�z�B�i�悤�₭�Ȃ̂ł��B�������x���n�悾�����̂ƁA�R���i�łQ�N����̂����Ă����j�����̕s���œ��������[�Ԃ��x���̂ɁA���X�ƈ��͔����Ă��܂����B�~�^�C������z���Ȃ��Ƃ����Ȃ��BZoom�u�����ă��|�[�g�𑗂�����A�����͌��H���ώ@���Ă�����B�g�t���ɂ��T��قǏo�������B�ɂ߂��͎��̎����ԖƋ��̏��������葱��������͂��B
�������̂悤�ɁA�V�����Ƌ�����ɓ����ɂ́A����ҍu�K���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���̑O�i�K�̔F�m�@�\���������\��₱�����āA���̐����o����̂ɓw�͂��Ă����B���A�L���͂̌��ނ͗}���悤���Ȃ��B
�Ƃ��낪�A�v��ʂ��Ƃ��N�����B���K���ɘA������ƁA�u���Ȃ��̔N��ƔF�m�@�\�����͕K�v����܂���B���͂⎋��̌����Ǝ��ԃe�X�g�����ł���v�Ƃ̕Ԏ����������̂��B�������Ɩ����Ɂu���v�������A�˂����قǂ̋����I�ȂB����Ȃ������̂��B���ς�炸�̂���Ď҂��B���_����----�p�̏�h��Ƃ͂��̂��ƁB
�F�m�@�\�e�X�g�ւ̑������Ă����̂��A���������������Ŏv���������K�v�Ȃ��Ȃ����B���njy�����Ԃ�����������Ƃ��������������A���_�̕��ʎԂ���ĎԌɓ���̗��K��������A��ʖ@�K���m�F���������ŏI��肻�����B

9���ɑ}���肵���[���j���[�����A�Ԃ�t����悤�ɂȂ����B
�S���S���I������15�{������}����̍s���悪�����B���̂܂܍��|�b�g�̒��œ~���z�������Ȃ����B���ꂩ�v��Ȃ����ȁB
���R�̕�炵627. 2021.11.24
�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@
�@
 �@���������W�߂Ĕ����Ԃ��
�@���������W�߂Ĕ����Ԃ��
���U���ɋN�����B�O�͂܂����Â��B�т̒����璩�����̂����A���𗁂тĔ�������B
�E�R�M�Ȃ̒��ԂȂ̂ŁA�^����E�h�̉ԂɎ��Ă���B�ʖ��̓e���O�m�n�E�`���i�V��̉H�c��j�B
 |
�t�͖{�����ɐꍞ���9���ɗĂ�����̂������͂����A��̃��c�f��3������6���ɐꍞ��ł��邾���B
�������܂�ʂ�Ȃ��̂ŁA�ꍞ�݂����ĕ��̗�������߂����K�v���������炩�B���ɂ͎O�ł�������B
�u����v�̔��͐��������Ƃ����Ӗ��炵���B
�Ȃ�قǁB�����Ԕ����ցi���}�^�m�I���`�j�҂ƐM���Ă��āA����Ȃ瓪��9�ł͂Ȃ����H�ƍl���Ă���
���オ�������B�������B
�@ |
 |
�L�N�C���E�e���v�����n���Ĕz���ĕ������B�O����@�L�N�ȃq�}������
�����ރC�k�������܂ݐH���@�ۂ��L���B���̌`������Ƃ��邪��ނƈقȂ�A�f���v�����قƂ�NJ܂܂Ȃ��B
�����l��R���X�e���[�����������p������B�Ɨǂ����Ƃ��炯�B
�@ |
 |
���_�����y�j�u����Â̌��n�����i�����j�ɏo�������̂ŁA����ЂƂ肾�I�E���V!
���ٓ��̒��g�́A�~���`�J�c�A�t�����A�V���E�}�C�A�ڊ�̐Ԃ��ԒЂ��A�����̊ÎρA����ׂ���A�u���b�R���[�A�����S�A���n�̓��{�C�`�W�N�A���{�O�储�\���̂ЂƂ����������\���i�����j�B
�Â₩�������H��l���Ɏ�������߂������ǁA���s�ҁi���w�l�������j������̂ł���͎��̌��h�B |
���R�̕�炵626.
2021.11.14
�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@
 �@�莆 �@�莆
�@K�l
����̂��ւ�ɂ������L�d�́u����̉J�v���~�钩�ł��B�J�����ɕ\�������G�́A�L�d�ɂ���ď��߂ĕ`���ꂽ�Ƃ��������܂����B���ꂩ��O���ʉ߂Ƌ��ɏH�̗��������r�ꂻ���ł��B���z���ɂ��̕ω������Ă���̂���������̂ł��B
�߉ϐ쒬�n���L�d���p�قɂ͂�������łɂȂ�܂����ˁB�@
�@<http://www.hiroshige.bato.tochigi.jp/>
���z�ƁE�G���ᎁ�f�U�C���́A���a�����c�Ɏg�����ǂ̘A���������������ł��B�|�т̕��̂��悬�������Ȃ�������ƁA�V�䂩��������~�蒍����捂ȋ�Ԃɑ����čL�d�̊G���W������Ă��܂��B
���������x���K�₵�A�L�d��i�ɏڂ����w�|������ɂ��܂��܂ȍ�i�ӏܕ��@��R�����Ă��������܂����B�J�̕\���ɂ�������������邱�ƂŁA�܂������������ۂɓ������Ƃ����M�d�Ȍo�������܂����B
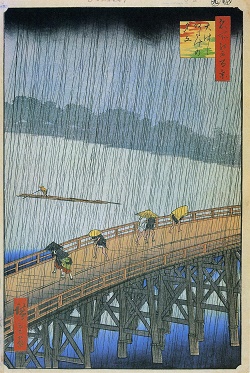 �@�̐�L�d�̖����]�˕S�i���́u��͂��������̗[���v �@�̐�L�d�̖����]�˕S�i���́u��͂��������̗[���v
���a�̍L�d�Ƃ��Ă�镂���G�t�B�ʼn�Ƃ̐쐣�b�����`�����u�����v��
�@�u���������˘H�v �]�˓��������� ���� 1918�N�i�吳7�N�j
�@�u�������ق��܁v �]�˓��������ُ��� 1918�N�i�吳7�N�j
�@�u����������v �]�˓��������ُ��� 1918�N�i�吳7�N�j
�����̍�i�������}���قɌf������Ă���̂����čL�d�̍\�}�Ƃ̋��ʓ_�������Ă��܂��B�ق��b���́u�����X���v�̐������d�ʊ��������Č���������܂��B
���ւ�̒���
���ߐ{�ɗ��ċ�����g���Z��̕悪���邱�Ƃ��B
�S�������u�k�t�̐����u������g���v�����W�I�ŕ����Ă��܂������A�q���̂���ł����牽�������T�b�p��������܂���B���v���ɁA������b���Ă����悩����----������邱��ɂ͐e�͖����B
�����g���Ƃ́u��������̓`���I�l���B���B�̍����Ƌ��s�̕��i�Ƃ̌��Ղ��s�������O���̏��l�v�u���`�o�����B������
�𗊂��ĉ��B����ɉ���̂��菕�������Ƃ����B�v�̂ł��ˁB�iby Wikipedia�j
 �@�H�F�̔��͂̊ց@���E�̍������������낢 �@�H�F�̔��͂̊ց@���E�̍������������낢
���ւ�ɂ���܂����B
�����������A�����ɋ����Y�����Ƃ����āA������V�c�̘b���v���o�����B�����͋��̍����������炱���������؊J�����̂��B
�����͋��̍��A�������ɁB
���{�͂��ĎY�����������̂��A���厛Ḏɓߕ����c�ɔ�₵�A����ɖ����A�����̕s�����ȋ�������̂����ł�����������ƕ����Ă��܂��B
�Ƃ���ōL�d���p�ق�ߐ{�̕��ʂɏ����o�����Ƃ���ɁA�u�����E���������v�̒n��������̂��������ł��傤�BNPO�@�l�u���{�ōł����������v�ɑI�ꂽ�A�I�c�̂��鑺���ł��B�]�ˎ��ォ�瑱���Ă����̗��B��������Â��͋����Y�o���A�ޗǂ̑啧�l�i���厛Ḏɓߕ����j�̑��c�Ɏg�p���ꂽ�Ƃ��������`��������܂��B�Ȃ��߂��̌����ɂ͌Ë��̗��̐Δ���������Ă��܂��B
 �@ �@
�@�����̒I�c�@�@�߉ϐ쒬HP���炨�肵�܂����B�@�@�@�@�@
�Q�l�ɂȂ�܂����B�w�C�s���x�i���݂䂩�ɂ��āj�B
�C�s���@����(�݂�)���r(����)
�R�s���@����(��)���r
��N(��������)�́@��(��)�ɂ������Ȃ�
���ւ茩�͂����@�i����(�̂�)�ɂ͎��Ȃ��j
�@�@�w���t�W�x��18�u�ꗤ�����o���ُ��́v4119�ԁB�i�唺�Ǝ���j�̒��̂���̉́B
���������F
�������ɋ����o���ُ����ꂷ�̈��A�ĒZ�́i�唺�Ǝ��j
�����́@����̍����@�V����@�m�炵��������@�c�c���߂낫�́@�_�̖��݂��Ƃ́@���d�ˁ@�V�̓��k�Ђ��Ɓ@�m�炵����@�N�̌����@�~���܂���-------�@�C�s���@���Ђ��r�@�R�s���@�������r�@��N�́@�ӂɂ������Ȃ߁@���ւ茩�́@�����ƌ������Ƃ��Ăā@��v��-------�����
�[�̎��Ɂ@��N�́@���̎��@���������ā@�l�͂��炶�Ɓ@���◧�ā@�v�Ђ�������@��N�́@�䌾�݂��Ƃ̂����̕����M��
�Ñォ�琭�̕ێ��̖���S���A�R�𗦂��Č��͂��֎����Ă����唺�A�����̗������A���ߐ��x���ƂƂ̂��������Z������ɘA��A���̐��͂������Ă����܂����B����K�v�Ƃ���Ȃ��Ȃ����̂ł��傤�B�@�Ŏx�z���鐢���n�܂����̂ł��B�R��I�Ō����繫���鐸�_�\�������唺�Ǝ����A�唺���̓����Ƃ��đ啧�����肵�������V�c�ւ̒����𐾂����u�ꗤ�����o���ُ��́v�B�K���Ȏv�����`����Ă��܂��B�����V�c��_�ߎ]����h���肤�ɁA�킪�g���Ȃ߂ĕ\������͕̂��ʂ̂��Ƃł����B�i�������������͈̂��̍˔\�̂悤�ł��j
���́w�C�s���x���푈���ە����邽�ߌR�̂Ƃ��đ���E��풆�ɗ��p���ꂽ�̂��ǂ��l����ׂ��Ȃ̂��A���܂��ɓ����͏o�܂���B
�̒n���瓌�������Ɛ��n�Ƃ��ꂽ�g��ɍs�������܂��B�����𗬂��g���ɒO���Ɩ��t����ꂽ�n�����c��܂��B������Y����Ƃ����Ӗ��ł��ˁB�����̍��ŎY�������ƁA�O���ŎY���鐅��Ƃ��A�}���K�������ɂ��A�������ꂽ�啧�l�ɋ����b�L���s���A�Y��ς�ŔR�₵��������������܂����B���̎��Ɏg��ꂽ����430�s�ȏ�A�����2.5t�B
�i���₪��������Ɛ��⒆�łɂ�����---�����a�ł�---���̂����œޗǂɂ͊�ȕa�C�����s����----�����c�@��������ߓc�@�A�{��@�͂��̕a�ɑΉ�������̂������Ƃ̐����j
���A���炵�܂����B����Șb���n�߂�Ɩʔ����Ă������߂��܂����B
���b���̂Ȃ��́A
���O�c�@�I���A�}�X�R�~�̗\�z�O��ɋ����B
���{�o�ϐV��11��7���t�������ɓ��[�s�����͂��ڂ�܂����B���O�\�z�����鎩���}�ւ̎x�����W�܂����̂͂Ȃ����B�j���A�N��A�K�w�ʂɑI���������ꍇ�̋c�Ȑ��𐄒肷���---�Ȃǂ̓��e�ł����B
�J�ɂ��������悤�ɁA���X�̗t�����ꗎ���Ă����܂��B
���̋G�߂���������鎼�������A�����������A�~���A���邢�͔N����d�˂�H���u�v���v�Ƌ����Ă���Ă��܂��B
���~���߂��܂����B���ꂩ�琁�����́u�،͂炵�v�ƌĂ��悤�ɂȂ�̂ł��傤�B
�@�@�@�@�@11��9���@
�@
�@�@���R�̕�炵625. 2021.11.9
�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@
�@�@ �@���邮����G�߂� �@���邮����G�߂�
�`���������B���̂Ƃ���70�B���ꂩ��܂��܂�������B
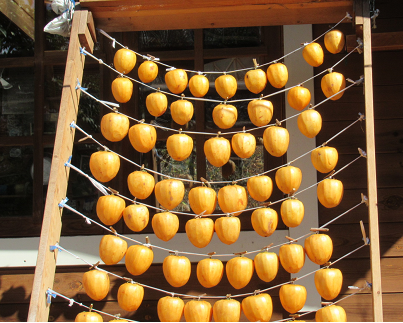 �@�I���`�@�E�B�X�L�[�ŏa���Ă����������B �@�I���`�@�E�B�X�L�[�ŏa���Ă����������B
�v��������Ă���ԁi1800cc�j�Ǝ��̌y�����Ԃ�葱���������B���ꂩ��͓�l�ň�䂾�B
�V�����Ԃ��葱�����ς܂����B�[�Ԃ�12���B
�r�I��200�{�`���[���b�v300�{���̑���A�����B���ꂩ�琔�������邩������Ȃ��B
�g�t���ɍs�����B�������܂��g�t���̗\��B
�ȂǁA�H�͂ƂĂ��Z�����B�p�\�R���Ɍ������]�T���Ȃ��̂ł��B
�@�@�@���R�̕�炵624 2021.11.5
�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@
�@
 ��A�܂ł���2�T��
��A�܂ł���2�T��

�X���W���Ɏ�܂������r�I�������̌�ǂ��Ȃ������BBefore��After�����̎ʐ^�B
���������Ă����g���[����A������c�p�̃|�b�g�ɐA���ւ���50���ɂȂ�B�{�i�I�ȓ~������O�ɒ�A���Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���ɒ��̋C����3���ɉ����邱�Ƃ�����̂ŁA���͓��ɓ��ĂďT�Ɉ��t�̔엿��^���A��Ԃ͊ȈՉ����ɓ����----������P��50���������B
��A��11��10���܂łɍς܂��\�肾�B�~�̊Ԃɂ͒n�㕔�قƂ�ǐ������Ȃ��A�Ƃ������������ŏk���܂��Ă��܂����A�n�ʂ̉��ł͊ۂ��傫�ȍ������{�[��������Ă��āA�t�ɂȂ�̂�҂��Ă���
 �@�g���[�Ɏ�܂�����ƁA�����^�яo���ĕ֗��B �@�g���[�Ɏ�܂�����ƁA�����^�яo���ĕ֗��B
�@�@�@
���R�̕�炵623 2021.10.29
�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@
�@
�@ �悤�₭�R�̓V�ӂɗ����@
�悤�₭�R�̓V�ӂɗ����@
��5��45���N���B�Ǝ����ς܂��Ē�ɏo��̂��W�����B�ẲԂ��đ͔�u����ɉ^�сA�������A�Ԓd�ɐΊD����������Œ��a���A�P�T�Ԓu���Ă���u�����͔삽������{�{�������{���y�����{�L�@�����엿�����v�������čk���B�ߑO�̕��A�ߌ�̕��ƖZ�����B�܂��炢�Ă���ẲԂ�ɂ��݂Ȃ��甲���A��ĂĂ���ԕc�̐��������Ȃ����A�̎�����T��B
����ȍ�Ƃ����[�[�[�Ƒ����Ă��Ă悤�₭�H��Ƃ̎R�̃e�b�y���ɓo���Ă����悤�ȋC�������B�����͏H����B�ق��Ƃ���B��Ƃ̓W�J��������Ƃ��C�������o�Ă����悤���B
��������́A�ΊD���������Ԓd�ɑ͔삻�̑�������B��������Ȃ���������Ȃ��B�ЂƂ����蒲�B���Ă��邩�B
�������܂��������c�i�r�I���A�f���t�B�j���[���A�l���t�B���A���X���i�O�T�Ȃǁj��`���[���b�v�̐A�����݂��҂��Ă���B����A�����̍�Ƃƍl���悤�B
��Ƃ����Ă���ƒ���s�Ŗڂ̑O������J���X������B�����̃��c�B��@�ɗ����炵���B���Ԃ��Ăъĉ����ɂ��ނ낵�đ��������B�J���X�����͂���ׂ�Ȃ���㉺�ɂ͂˂�̂ŁA�ĊO�傫�ȉ����������Ă���B�K�r�`���E���W�܂��Ė���߂��A�q���h�����P�O�H�قLj�{�̖ɏW�����Ă�����܂��₩�܂������������Ă���B�����W�܂�ƃI�o�T��������悤���B
�Ƃ����킯�ŁA�{�i�I�ȍg�t���̑O�ɍς܂��ׂ����q���v�H�̓�����10���������I���ɋ߂Â����B�I���͂Ƃ����ɍς܂����̂ŁA���Ƃ͍��݂̌������B

�H�ӂ̃����^���@�}���V�O�T�̉t�ʁB�т̒��łۂ��`���Ƃ����������邢�B
���R�̕�炵622
2021.10.24
�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@
�@
 �u���邳���I�v�Ƌ��Ȃ��������-------�Z�~�ƃJ�b�R�E�̐�������
�u���邳���I�v�Ƌ��Ȃ��������-------�Z�~�ƃJ�b�R�E�̐�������
�ߐ{�삪�������ق̐䒲���@�Ȃ͂����T�[�`�@
http://www2.city.nasushiobara.lg.jp/hakubutsukan/event/research.html
���T�[�`�̒������ԁF�ߘa3�i2021�j�N5��1���i�y�j�`10��15���i���j
�����������ɎQ�����n�߂��̂͒x��č��N��7���W���������B
�c�O����5���ƂU���̋L�^�͎���Ă��Ȃ��B
10��15���Œ������I������̂ňȉ��܂Ƃ߂Ă��������B
�Ȃ��A�����͎��̒�ł̌��ʂł����āA�����܂ł���ŕ������^�C�~���O���L�^�������́B���l�̑̌��ł����Ȃ��B
�@�@�@�@�@�i ����̏ꏊ�͓ߐ{�A�R�̓쐼�A�W��425���̎G�ؗт̒��B�j�@�@�@�@
�������A�O���ŕ������ꍇ�͂��̎|�L�ڂ��Ă���B
| �@�� |
�����i�����j |
�I���i�I���j |
�@�@���l |
| �@�J�b�R�E |
�@7��14�� |
�@7��17�� |
�k�k���̍�������ѓn��̂�7/14�C7/16�A7/17��3�����B�����̔N�̃J�b�R�E�̏����͂T���A�x�������炢�����A��L�̂悤�ɒ������ӎ����n�߂��̂�7���Ȃ̂ŁA���N�͒��������˂��̂�������Ȃ��B���邢�͌̐������Ȃ������̂��H�@
�@ |
| �@�z�g�g�M�X |
�@7��15�� |
�@8��16�� |
7/15�A7/18�A7/20�A7/28�@7/30�A7/31�A8/6�@���ꂼ��1�H�����������B���������Ԃɔ�щ�邱�Ƃ����������B
�@ |
�@
| �@�� |
�����i�����j |
�I���i�I���j |
�@�@���l |
| �@
�@�q�O���V |
�@
�@7��8�� |
�@
�@8��23�� |
����Â��A���邳�������Ƃ��Ė��悤���B������������n�߂��̂ɂ͋������B���������ȋ��������鐺���B
���Ƃ��@7/8�@���q�O���V���i3��������30���ԁj
�@�@�@�@�@8/11�@�q�O���V�����i4��35������20���ԁj�B
�[���͂���Â��ɂȂ�ƁA���n�߂�悤���B���������Đ��V�̗[��6���ɖ��A�܂�̓���4���ɖ��Ƃ������ۂ��N�����B
�Ő�����7������1�T�ԁB�W�c�Ŗ��A���̏W�c�������������ė֏����Ă���悤�ɕ��������B�����t���[�Y��7�b�Ƃ���������茳�C�Ȍ̂̏W�܂�̂悤�������B
�Ƃ��낪8/12����͗�N�ɂȂ��������ŁA�����Ɨ[���̖������������Ă��Ȃ��B�I��8/23�B���̂���͗������P�T�Ԃ������B
�@ |
�@
�@�c�N�c�N�z�E�V |
�@
�@7��25�� |
�@
10��4�� |
������7/25�B�Ȍ�8�������ς��́A��L�̗������P�T�Ԃ�����������[���܂Ŗ�������B������Ώ����قǏW�c�Ō��C�ɖ������B��Ԃ̌��C���́B
10��11���@�ߐ{�삪�������Ńc�N�c�N�z�E�V�̐����R�x�������B
�@ |
�@
�@�j�C�j�C�[�~ |
�@
�@7��15���@ |
�@
�@9��13���@ |
�~�J�̍Œ���7/15�����B�W�c�Ő������Ă���悤�ŁA�W�����{�܂Ō��C�����ς��ɖ��B�����������͒n���ŁA���Ƀc�N�c�N�z�E�V�̐��ɂ����������悤�������B
���̌�������P�T�Ԃ��͂��݁A�I����9/13�܂ŋC���̍����Ȃ����ߌ�Ȃǂɖ����Ƃ��������B
�@ |
�@�~���~���[�~ |
�@8��11�� |
�@8��31�� |
��ł̏�����8/11�B�Ȍ�8/31�܂Ŗ������A���̓��̓V��ɂ���Ė��̐����ω�����B������������D���Ȃ悤���B���������̐��͏��Ȃ��B����G�ň͂܂�Ă��āA�D�݂ɍ���Ȃ��̂��H
�T2�x�s���߂��̓��̉w�u�����̐X����v�ł�7�����{����8�����{�܂ő升�����Ă����B�J���ē������肪�ǂ��A���̂����h�C�c���뉀���Ȃ̂Ŏ��t�̏o��J�G�f�ނ������A�����Ă��邩�炩�B�n�ʂɂ̓Z�~�������o���������������ɂ݂���B
7��27���@�����}���ف@����ɖ��Ă����B��������͂�J���ē������肪�ǂ��B�������J�G�f�ނ̎��͏��Ȃ��̂����B
��L�̓�̏ꏊ�ł́A�X���ɓ���ƃp�^���Ɩ������~�܂����B���鎞���ɏW�����Ēn�ʂ��甇���o�āA�ɐB��ڎw�����炵���B----�Ȃɂ��낻�̌̐��̑�������o�����������̂ł͂Ȃ����B
�@ |
| �@�A�u���[�~ |
�@7��30�� |
�@8��26�� |
����ĉĂ炵���V�C�̒��Ԃɖ����Ƃ������A�������P�̂Ŗ��Ă����B
�������J�͗l�̓��������āA���̉Ăɕ�������10��ɓ͂��Ȃ��B
�@ |
| �@�`�b�`�[�~ |
�@9��24���H |
�@ |
YouTube�Ŗ�����T���ĕ����Ă݂����A��ł̐����`�b�`�[�~�̐��Ȃ̂��ǂ����A�m�M�����ĂȂ�
�@ |
 �q�O���V��
����------���̂ɉ��x�A�Ɠx���傫���e������炵���B�ߐ{�ł�7������8���ɖ��A��n�ł�8������9���ɂ����Ė��B�ԂƂ�ڂ��H�ɂȂ�ƎR���牺��Ă���悤�ɁA�q�O���V�͕W���Ȃǂ�
���R��I��Ő�������̂�������Ȃ��B �q�O���V��
����------���̂ɉ��x�A�Ɠx���傫���e������炵���B�ߐ{�ł�7������8���ɖ��A��n�ł�8������9���ɂ����Ė��B�ԂƂ�ڂ��H�ɂȂ�ƎR���牺��Ă���悤�ɁA�q�O���V�͕W���Ȃǂ�
���R��I��Ő�������̂�������Ȃ��B
 �u��͂V�N�Ԓn���ɐ������A�H�����Ēn��ɏo��ƂV���Ԑ�����B�v �u��͂V�N�Ԓn���ɐ������A�H�����Ēn��ɏo��ƂV���Ԑ�����B�v
���ꂪ������Ƃ���Ă������A�@���ۂ͏������������Œ��Ђƌ��߂��̎��������ƒm�����B�V�N�ȋ������B
�l�Ԃ��͂��ߊO�G��ߐH�҂��������߁A�����Ԑ�����̂̓Z�~�ɂƂ��ē�����A���܂��܂ȉ^�Ɍb�܂��ƒ������ł���炵���B
 �v���t���Ē����ɎQ���������̉ẮA������グ���܂����Ă������B �v���t���Ē����ɎQ���������̉ẮA������グ���܂����Ă������B
�V�����C�Â������������Ƃ��A�P���Ɋ������B
 �ǂ�ł����������F����B��ɐ��܂��Ƃ�����ǂ̐��I�т܂����B�@���̓c�N�c�N�z�E�V
���ȁB �ǂ�ł����������F����B��ɐ��܂��Ƃ�����ǂ̐��I�т܂����B�@���̓c�N�c�N�z�E�V
���ȁB
�����̃����t���[�Y�̏I��̉������������Ə����Ă����̂��u����ꂽ�v�悤�ɕ������Ėʔ�������B�������C�Ő���t�V�q���̂�����v���o������B
�Ȃɂ������Y�����y�����B�՚��q�̂悤���B
 �@���̓u���[�x���[�A�E�̓I�I�f�}���@��̖��g�t���Ă����B �@���̓u���[�x���[�A�E�̓I�I�f�}���@��̖��g�t���Ă����B
�@
���R�̕�炵621
2021.10.17
�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@
 �Ԓd�̐������v���[���g
�Ԓd�̐������v���[���g
�u�����͌����L�O�����ˁv�u�͂͂������B�Y��Ă����v�u�����v���[���g���Ȃ��Ȃ��A�����ˁv�u���₢��v
���N�͂����ƖY��Ă����������A���_���₯�Ɍ����ȕ��������������������B
���X�g�����ŐH���H�@�Â��Ȃ��o�������Ȃ������܂���10�L���ȏ゠��B�A�肪�R���C�B
������ꂽ�������v���[���g------�_�C�������h�ł��v��Ȃ���B

�u���̍�������������A�����̉Ԓd�̉Ԃ̐����������Ȃ̂Ɂv�Ƃ��ڂ��Ă������t���ǂ����o���Ă����炵���B
���N���O�ɐ�|�������̖̍������������܂�łɎc���Ă���Ԓd�������č����Ă����B
���_�A�^����̂悤�ɔ����������Ă��̉Ԓd�ɍ��肱�݁A�X�R�b�v�Ŏ��͂̓y�������A�o�[���ō����ق�����o���\�ʂɌ��ꂽ���i���a10�Z���`�j����Ă����B���݂���
�ɂȂ�B
�܂�A���́u���@��v���v���[���g�ɂȂ�炵���B�����������Ċi�����邱��3���ԁA�悤�₭���������@��o�����Ƃɐ��������B
�ߋ����v�킸�i�ق�����o���Ɖ��₩��o�Ă���j�������l�����A�����V���[���ȁu���܁v���Ă�������B
 |
��O�̓}���[�S�[���h
�s���N�̓I�L�U���X�E�{�[�E�B�i�n�i�J�^�o�~�j
���̓������|�W���[��
�ق�̂莇�F�̓N���}�`�X�i�����j
���H���ʂ�G�߂̉Ԃ����B |
10��9���A���Ԓ�����Ђ̃u�����h�����������i�����s�`��j�����������u�s���{�����͓x�����L���O�v�̌��ʂ����\����A�Ȗ،��͍�N�̍ʼn��ʂ���41�ʂɖ��i�H�����B
��N��10��14���A����͌����ɂƂ��ċ����ׂ��o�������N�����B��L�̒����Łu�ʼn��ʂ͓Ȗ،��v���Ɣ��\���ꂽ�̂�����I
�V�����̂������B
����܂ł͈�錧���A��7�N�Ԃ��ʼn��ʂ������̂ŁA�u�[�r�[�Ƃ������ʂ�ʔ�����]�T���������̂�������Ȃ��B
�����������͂Ȃ炶�ƌ��m�����A���\��Ɍ��̃u�����h������������K��Ē��k���B
�u84�̒������ڂ̈�ł���u���͓x�v���u�����I�ȕ]���Ƃ̌���������Ă���v�Ǝw�E���A�u�ό��ӗ~�x�v��u���Z�ӗ~�x�v�Ȃǂ��������������I�ȕ]�����ڂ�݂���悤���߁A�������@�ɂ��Ă��A��600�l�������Ґ��𑝂₷���Ƃ�v�]�����B�v
��ӂ���̏o���́A�ʼn��ʂ��t��Ɏ�邱�Ƃ���n�܂����B���͐V�������͔��M�v���W�F�N�g�u47�i�����j����n�܂�Ȗ،��v�\���A�C�x���g���������A�Ƃ����a����C�`�S�́u�Ƃ����Ƃ߁v���g�p�����V���i���J�����A�����{�A�Ƃ�킯�����ł̒m���x�̒Ⴓ�ɍL���v�����[�V�����ɑł��ďo���B���ʂ�41��
���B����Ŗ������ׂ����H
���������v�̐����ȂǁA�������ɂ���Ă͂ǂ��ɂł��Ȃ�B�҂̔N��A�n��Ȃ̂̂�����肪���邩������Ȃ��B�����600�l�Ƃ������Ȃ����ŌX����_�����邾�낤���B |
 |
���R�̕�炵620 2021.10.11
�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@
 �܂����ɏo�����@
�܂����ɏo�����@
�u�L�ɖؓV���v�Œm����}�^�^�r�B���˂ĉʎ����ЂƖڌ������Ɗ���Ă����犐�����I�@�v����������̂��I
�A���Ɋւ��ĐV�����������ڂ̑O�Ɍ����ƁA��������邭�Ȃ�B
 |
�@ |
�т̒��ɂԂ��Ԃ��B���܂��ܖK�ꂽ�����̎R�̉��̏����ȋn�ł��ٓ���H�ׂĂ�����A���̏�ɂԂ��Ԃ��B����͂��ٓ��ǂ���ł͂Ȃ��B
���߂�ὂ߂A����������݂Ďʐ^���B��A�S�̂̎p���݂Ă͋L�^�Ɏc���A�Ō�͔�яオ���Ė�����������悤�₭������ɓ��ꂽ�B�ς�����`���B�ג����Đ���ۂ�����Ă���B�傫���͒����Q�Z���`���a1.5�Z���`�B |
�V�����m����������ƒP���Ɋ������B
�}�^�^�r�͉Ԋ��ɉԂ���芪���t�������ς��B����͎}��҂��Ăъ��킾�낤�ƌ����Ă���B����ȏ�͂悭������Ȃ��B�B
�H�̏I��ɂ͌��̐F�ɖ߂�炵�����A�����ɗ��t�̋G�߂����邾�낤�ɁB
�@ |
 |
�L�C�E�B�̌���ɋ߂��̂ŁA�ʎ��������Ă݂����̔z�u�����̂܂܃L�C�E�B�������B
�s�v�c�Ȃ��Ƃɂ��̎�����܂�ꖂ��Ă݂���u�h���v�B���̓��h�q�̐h���Ɠ����������B
�ߐH�҂ւ̖ڂ���܂����A�g�ɕt�����m�b�Ȃ̂��B
���̂܂n���ƊÂ��Ȃ�悤���B�����ɒЂ���ƃ}�^�^�r�����ł���B
�@ |
�悭�����A���ɃT���i�V������B��������}�^�^�r�Ɠ����}�^�^�r�ȃ}�^�^�r�������A
�}�^�^�r�ƈႢ�ʎ��̌`���L�C�E�B�ɂ�������ȕU�^���B�k�C���ł͂��̃T���i�V���u�R�N���v�ƌĂ�ł���B
�����ł��I�@���̃h���J���̉̂ɂ���A�i�h���J����DREAMS COME TRUE�j
��@���ꂽ�炢���ˁ@�R�֍s�������̓��j��---�ꏏ�ɍs������@������̎��܂��̂��Ă�--��@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�쎍�F�g�c���a�@��ȁF�g�c���a�@�ҋȁF�������l
���̋Ȃɏo�Ă���u�R�N���̎��v���āA�u�T���i�V�v�̂��ƁB����̃L�B�E�B�B�L�[�E�B���y���ɏ��������ł���Ȃ���A�\���ɏn���A�܂��ɂ��̖��̓L�[�E�B���̂��́I
����ɂ͂��܂������ɏo�����Ă��Ȃ��B�n�������ɂ́A�Y���̂��X�ɏo�Ă������Ƃ����������B
�������B----�h���J���̂��̉̂��]�����s�[�g���n�߂��B �]���Ɏ����]���ŁA����ɉ���肪���������Ȃ��Ă���B
���āA�}�^�^�r�ɖ߂낤�B
���܂𗚂������l�������̃}�^�^�r�������ĐH�ׁA���C�ɂȂ��āu�܂���������v�B�������̖{�ɏ����Ă���B�m���ɓ�����ێ悵�Č��C�����߂����Ƃ͂��肻�����B
�܂����ɏo�����������Ă��邾�낤���B
 �s����̂��m�点������A���s�̃��N�`���ڎ�͏����ɐi��ł���Ƃ̂��ƁB �s����̂��m�点������A���s�̃��N�`���ڎ�͏����ɐi��ł���Ƃ̂��ƁB
9��30�����݁A�P��ڐڎ튮��83.3���A2��ڐڎ튮��60.8���B
�����̖ڕW�������u�X������12�Έȏ�̐ڎ��]�҂̂W�����ڎ튮�����A�U�����Q��ڂ̐ڎ���I����v��B�����邱�Ƃ��ł��܂����B
���̐����͌����̎s�ł͍ł������Ȃ��Ă��܂�---�Ƃ܂��ƂɊ�����m�点�������B
��ÊW�҂�s���̒S���҂̊F����̂��w�͂̐��ʂ��\�ꂽ�̂��낤�B�H�̗z�����Ƃ���܂Ԃ������������B
���R�̕�炵619
2021.10.6
�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@
�@
�@ ���Ƌ��ɋx�ށ@
���Ƌ��ɋx�ށ@
10��1���A�锼����䕗�P���̉J�B��̙��肪8�������I��A�����͐g�̂��x�߂�����B
����3�T�ԂƂ������̐S�g�Ƃ��ɔ�J���Ă��܂��ē��������Ă����̂��A�悤�₭�l�Ԃɖ߂���Ƃɂ������B
�s�̃V���o�[�l�ރZ���^�[�Ɉ˗����Ă�����̙���̍�Ɠ��́A�{��10�����{�ɗ\�肵�Ă������Ђƌ����L�тĂ��܂����B�Z���^�[�ɓo�^���Ă��郁���o�[������Ō���A�X�ɉJ�̑������Ăɗ\�肪�������炵���B���t���͏H�̏I��̙���ł����v�����A��̃��u�c�o�L��C���O���b�V���E�z�[���[�͒x���ɐn��������ƌ͂ꂪ����S�z������B
�c�ɂ̐����́u�����w�́v�B
�����ŏo���镔����O�����Ă��A�v���ɂ��肢���陒��̗ʂ����Ȃ����Ĕ�p��ߖ悤�ƍl���Ă����B�Ƃ��낪�����̒m�点�Ɍ˘f��----�����������֑��_�̂ЂƐ��������āu���N�͎��������ł��ׂĂ�낤��v�ƁB
���ߑ������Ă݂Ă��n�܂�Ȃ��B�Ȍ�ē����H���̐����n�߂������A�A���������Ɗi�����Ă����B
�悤�₭8�������I������Ƃ���ɑ䕗�P���̒m�点������A�}���ŃN���[���Z���^�[�ւ̎������݂������˗������Ƃ���A�s�b�^���̃^�C�~���O�Ŕ������ł����B
�{����3�T�Ԃ��I������B�߁X�̒ɂ݂�������̖̂������ɐZ��J�̓��B���Ă��ꂩ��H�̗\��𗧂Ă悤�B
�����ǁA�v���̎d���͌��Ă��Ĕ������B��l�̑����s�b�^���d�Ȃ��āA���t�ɏo���Ȃ��Ă��d�����i��ł����B

���ԂɏH�̎�����Ă���B�O�t�A�P�r�������J���āB�쒹�Ƌ������B�ʐ^���B�������Ƃ̓��W���Ƀv���[���g����B��O�̊ۂ��̂́A���u�c�o�L�̎��B���ꂩ��֖����̂��炵���B���L�c�o�L�̗t�́A��̏d�݂ɑς�����悤�ɁA�����Ƃ���Ȃ肵�ď_�炩���B
 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���R�̕�炵619 2021.10.1
�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@
�@
 ��Z���̒�����--��肠�����摜��\��t��---�����͌��
�i���ǖZ�������Č���̐����͂ł��Ȃ������j
��Z���̒�����--��肠�����摜��\��t��---�����͌��
�i���ǖZ�������Č���̐����͂ł��Ȃ������j
�@�@ �@ �@
�r�I���@���x���_�[�E�s�R�e�B�@�@�@�A���ւ��Ăƕc���������B�{�t���o�Ă����̂Ń|�b�g�グ�B���藦90���B
�����̃s���N�A���F�̃v�������ɍ��킹��Ƃ��̐F�̑I���͓��R�̂��ƁB�������|�b�g�A���傫���|�b�g�Ə��Ƀ|�b�g�グ���A11�����{�ɂ͒�A����B�~�̊ԂɊ��͑傫���Ȃ�Ȃ����A�n�ʂ̂Ȃ��ł͍������葱���đ傫�ȃ{�[����ɂȂ�B

�j�̖̉��t���n�܂����B�J�c���ȃJ�c�����@�ۂ��ėc���ȗt���B���t�������ė����t���U��~���ƁA�J�������̂悤�ȊÂ����肪����B�@�@�ڂ������Ƃ́@http://kemanso.sakura.ne.jp/katura.htm�@

�߂��̓��̉w�ɗאڂ��āA�����̌��M�؎����̕ʓ@���ۑ�����Ă���B�L��ɍ炭�̂́A���ԃR�X���X����R�X���X�B
���R�̕�炵618 2021.9.26
�@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@
�@
�@
 �Ђ����������̂͏H�̓��̊y���݂̂��߁@--- �d����������Ă���V�ڂ�
�Ђ����������̂͏H�̓��̊y���݂̂��߁@--- �d����������Ă���V�ڂ�
 |
�`�Ӗ��̎����n���Ă����̂ŁA���n���O�ʂ��Ɗ��������Ă���B��͐A�������܂ނ̂ł������܂ɂ͓��Ă��Ȃ��B
���̂��ƗⓀ�ɂŕۑ����A�C�����������Ɂu�o�`���������̍��z�i������̑O�̂ق���������������ǁv�j�ƈꏏ�ɂ��Ēώςɂ���B�I���K�R���b�_���܂ނ̂ł����Ƒ̂ɂ������낤��
�l���Ė��N���d�����A�n���ɍ���قǔ��肷��̂ŊԈ������Ƃ������B
��Âł́u���イ�˂�v�ƌĂ�u�H�ׂ�Ə\�N�������ł���v�Ƃ������ꂪ����炵���B
���̒n�։��o���ĐH�ׂ邶�イ�˂�݂̔����������ƁI
���������H�ɂȂ邾�낤���B
�@ |
 |
�Ԃ�Ԃ炵�Ă���̂́A�ʎ����ɂ���i�c�n�[�̍������B���N��̓͂������Ɏ����Ȃ�悤�ə��肵�Ă��Ă��āA���N�����܂��������B
���n�̓K���͂��Ȃ̂��A��������B�n���ė�����A�쒹�ɐH�ׂ���A�͂��C����---�����̊Ԃ�D���Ď��n����B
�����͏Ē��ɒЂ��邯�ǁA���N�͕������ăE�B�X�L�[�ɒЂ��Ă݂悤���Ǝv�Ē��B
�i���͈�؈��܂Ȃ��̂ł��j
�i�����������Ƃ�����̂��D���Ȃ����j |
 |
���̌i�F���q���̂���̎����Ɍ����Ă�肽���B���̍��͂����т����������������----�B
�ׂ̋��E�ɂ��Ԃ����Ă���G�S�m�L�ɁA���̊Ԃɂ��~�c�o�A�P�r������t���ėh��Ă���B
���W���̌Q�ꂪ����Ă��ď�����������ׂĖ������߂��A���₩�ɐH�ׂĂ���B
�킪�܂܂ȃq���h���́A��H�Ŕ��ł��Ă�����������ق������Ă���B
�����������ŐH�ׂĂ���̂�����̂́A�������ĐS���ӂ��肷��������B |
 |
�悤�₭�O���̈�܂ōςB10��1�T�ɂ͎s�̃V���o�[�l�ރZ���^�[�ɒ�̙�������肢���Ă���̂ŁA����܂łɎ��������łł��镔����Еt���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�S���ۓ����Ƃ������@�����邪�A�����͐ߖ�̂݁B
�m�R�M���Ŏ}�t���A���������甲���A��֎ԂŏW�߂Ė和�̂Ƃ���܂ʼn^�ѐςݏグ��B
������l�ł�����T�Ԃ������Ă���B���݂̌ċz�ŁA�ƌ��������Ƃ��낾���A�ǂ�����u�����̕������������Ă���v�ƍl���Ă���炵���B���Ȗ����ɂł��Z��Ȃ��Ƃ���Ă����Ȃ��d���̗ʂȂ̂��B |
 �@9��17�����݁A���s�̃R���i�����҂̐��͂̂�377�l�A
��300�l�ɂЂƂ肪�����������ƂɂȂ�B �@9��17�����݁A���s�̃R���i�����҂̐��͂̂�377�l�A
��300�l�ɂЂƂ肪�����������ƂɂȂ�B
�Ƃ��Ƃ���������ɂ��Ď��E�����l�̃j���[�X���������Ă����B�g�̓I�ȋꂵ�݂���ł͂Ȃ��炵���B�Â����K�̎c��y�n�́A�n��̓������͂ɑς�����Ȃ������̂�������Ȃ��B�X�ɂ���@���c�̂̍����ʒu�ɂ���l�������炵���A
����Ȓc�̂����炱���̎��͂���̎����𗁂ю�����ӂ߂Ă��܂����̂��B
�s��HP�ɂ́u�R���i�����͂��̐l�̐ӔC�ł͂���܂���B���͂��ӂ߂Ȃ��悤�Ɂv�Ƃ����f�����Ȃ��ꂽ�����������āA���l�����
�A����͕s�K�ȏo����������������̂悤���B
���ǂ������邽�߂̏@���Ȃ̂�
�M�҂̃X�g���X�̖���ɂȂ����̂��A�S���I�ɕ��S�������̂��B��l�ŔY�ݎ���I�l�̐S������z������ƁA�l�Ԃ̐S�̐U�蕝�̑傫���ɋ����A���Ɍ������Ă��܂������_�̈��ꂳ�ɍ������邵���Ȃ��B
�@�@�@�@�@���R�̕�炵617
2021.9.19
�@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@
�@
 ��R�̃q�}�������ǂ��������ƌ�����
��R�̃q�}�������ǂ��������ƌ�����
 |
�Ђ�����E���i����͂����j�����B�������ă^�[�v�ɍL���Ċ���������B
�q���̂�����n�������������ɍL���Ċ��������̂��v���o���B���������B
����͓V�C�Ƒ��k�Ȃ̂ł����������炪�ł��Ȃ��B
�A�X�t�@���g�ɏƂ�t���鑾�z�M�𗘗p���čL����̂���ԁB |
 |
��O�Ƃ��Ċۂ̂܂܊����Ă݂��B���O�̌���łԂ�Ԃ炵�Ă���̂�����B
���̂����ڂ��Ƃ��V�W���E�J�����A���ڂ��݂ɂ���Ă���B
������ǂ����ȁB
�����͉ē����Ԃ��Ă����B10�����{�ɗ\�肵�Ă���v���̒�̙���̑O�ɁA�o���邾�����������ł�낤�ƁA�������l�ő啱���B
�v�����Đ�A���肷��B���܂��܁B
�N����炵������A�����w�͂�ӂ�Ȃ��B
�C�͂��I�@�ƌە�����A��������ꂽ�B�����B
�ł��d���͎n�܂�������B

��D���ȃr�[�c�̒��́A����Ȃɂ��邮��B |
���R�̕�炵616 2021.9.13
�@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@
 �r�I���̎�܂��@
�r�I���̎�܂��@
6���A�͂�鋞�s����r�I���̎킪�͂����B��͔��藦��90-95���Ɨ\�����Ă��Ē������Ă��������ǁA���N�O�����܂̒l�i�͕ς��Ȃ����A�����Ă����̐��������Ə��Ȃ��Ȃ����B��������2�{���炢�Ɏ����l�オ�肵���Ǝv���B
�x���Ŕj���邽�߂ɂ��̉āA��܂͗①�ɂ̈�ԉ��x�̍������ɂ��܂��Ă������B
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�r�I���@���x���_�[�E�s�R�e�B�@ �@�r�I���@���x���_�[�E�s�R�e�B�@
���N��܂��̓���9��1���̌ߌ�ƌ��߂Ă���B��N�ɉ�����������ƂȂ̂ŁA�ْ�����B
9��4���A�d���3���B�����Ȏ킪�����z���Ėc��݁A�������Ă���B�{�t���o��܂ŏ����ɐ������A���̌�̈ڐA���e�ՂȂ悤�ɕ��U����������ł��A���ʂ����ł��Ȃ������悤���B�����ۂɍ��������t�����킪�A�������������đ��z��������悤�Ƃ��Ă���̂Łi���̌������j�݂��ɗ��ꂽ�ꏊ�ɍ���L����悤
�A�ܗk�}�œy���������A�����ƈړ����Ă��B
�悵�悵�A�����q�������B
�X���U���@�o�t���o�Ă����B�k�����ē��ȕc�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA���̎��_�œ��ɓ��ĂȂ��Ƃ����Ȃ��B�܂������������Ă��Ȃ�������邪�A�����͎v���邱�Ƃɂ��悤�B���C�����^���Ă���A���̂������肵�Ă���̂͊m���Ȃ̂�����B
�i�Ȃ��A�����ɍ�������̂��H����͔ɐB���炵���B���X�Ɏ��͂̊������Ȃ��琶���̑��x�����Ă���B���炩�̊��̕ω��ɑΉ����邽�߂ɁB
�R�[�q�[�����u���[�x���[�����̍����̂����Ă���B
��̖̃h���O���ȂǁA����̎����͂T������P�O���܂ł̔��N�ԁB�����c���킾�B�j
���������C��������������A�D��������̂�Y�ꂸ�l���t�B���̎��d�����B
 �@�H�i�g���[���d�˂āB�����^�ъȒP�B �@�H�i�g���[���d�˂āB�����^�ъȒP�B
 �g�߂ȐA�������Ă��āA�u����͏��߂Č����I�v�Ƃ�����тɂ�����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ����B �g�߂ȐA�������Ă��āA�u����͏��߂Č����I�v�Ƃ�����тɂ�����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ����B
�v���Ԃ�ɏo����������̐A���u�R�P�I�g�M���E�ے�v
�B
�@�@�@�@�@�I�g�M���\�E�ȃI�g�M���\�E���@�w�̍���20�Z���`�قǁB�{���̃I�g�M���\�E�ɂ悭���Ă���B
�@�@�@�@ �R�P�I�g�M�� �@�Ԍa1�Z���`
�R�P�I�g�M�� �@�Ԍa1�Z���`
 �@�q�}�����̉Ԏ�@245�� �@�q�}�����̉Ԏ�@245��
 ���ꂩ�����O���i�E�����āj���������A�~�̊Ԃ̖쒹�̉a�ɂ���B
���������ƊȒP�Ȃ悤�Ɏv���邪�A�Ȃ�̂Ȃ�́B�����ƍ����Ă���J�����̂��́B�������́A���ɃV�W���E�J�������̊�Ԋ���v�������ׂȂ��ƁA�Ƃ��Ă�����Ă����Ȃ��d���B�܁A�����ł͂Ȃ����ǁB ���ꂩ�����O���i�E�����āj���������A�~�̊Ԃ̖쒹�̉a�ɂ���B
���������ƊȒP�Ȃ悤�Ɏv���邪�A�Ȃ�̂Ȃ�́B�����ƍ����Ă���J�����̂��́B�������́A���ɃV�W���E�J�������̊�Ԋ���v�������ׂȂ��ƁA�Ƃ��Ă�����Ă����Ȃ��d���B�܁A�����ł͂Ȃ����ǁB
���R�̕�炵615
2021.9.8
�@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@
�@
 �p���p���@�@�@��ԍD���ȗь�̘b
�p���p���@�@�@��ԍD���ȗь�̘b
�҂��ɑ҂����u���ь�v�����̉w�ɏo�Ă����B�Ԃ��Ă��B������ƁA����ȏ�Ȃ��قǂ̗ь�̊�����Ă���B�o���̂͂��̎�����2�T�ԂقǂȂ̂Łu�����炷�����ܔ����v�B�o��������̂��ь�B
�j���[�W�[�����h�쓌���֗����ă}�E���g�N�b�N�s���̃c�A�[�ɎQ���������Ƃ�����B�h���C�o�[����̐Ȃ̑��ۂɏ��Ԃ�̗ь炪�����ƕ���ł��āu�����R�ɂǂ����v�Ə����Ă������B�������ь�D���̎��́A���R�ɂ���Ɍ��܂��Ă������ǁB
�ߐ{�ɗ��Ă��̂��ь�ɏo��������A���̎��̃j���[�W�[�����h�̃o�X�ɕ���ł����ь�ɂ�������A�Ƌ��������A���R�������B���ь�̓j���[�W�[�����h�́u�K����v�ƁA���{�́u�����ˁv�����G�����č�o���ꂽ�i�킾����
�̂�����B
�����߂ʼnʔ�̐Ԃ݂������A�������u�����ˁv�̌��������Ă���B�u�K���v����͂�Ԃ��ʔ�������Ă���悤���B
�ʓ��͌ł߁A�Ö��Ǝ_�������a���Ď��ꂪ�����B
�p���p���B��������Ċ��������𗧂Ă�J�̒��B
�ً}���Ԑ錾�Ŏn�܂���2021�N�̉Ă��I���ɋ߂Â����B���̐��������̌�������8�������o�����Ƃ͂ƂĂ��M�����Ȃ��B�u���Ԃɂ��v����B����8�����͂܂�Ŏ��̒��ɑ��݂��Ȃ������悤�ɁA�����炢�����ȋ�C�̂悤�ɗ��ꋎ���Ă��܂����B���̏H
�̎��Ԃ͂ǂ̂悤�ȐF�����Ă��邾�낤���B
���������ƂɁA100�N�O�̃X�y�C�����ז����̎��ɂ��A�u�}�X�N��t����v�͋����ł͂Ȃ��āA���݂Ɠ������u���l�v�ɂƂǂ܂��Ă����炵���B���݂̂����͗v������A���l�����߂���-----�����Ȃ�̎���I�Ȕ��f�ɍs�����܂�����Ă���B���Ԃ̖ڂ⋤���̂���̓������͂ɂ���ē��X�U�镑���Ă���悤���B����͂������{���L�̕����ƍl���邵���Ȃ��B
�@
 �@�ЂƂ�60�~
�@�ЂƂ�60�~
*�u���v�ƌ������O�͊�茧�����s��8���ɍs���邨�Ղ�u�������x��v�ɗR������炵���B�ː����ォ�琷���s�ߍx�e�n�ōs���Ă������܂��܂Ȍ`�Ԃ́u���x��v�������̂����݂́u�������x��v�B
�@
�@�@*�{�錧���w�́u�����J�v�Ɗւ肪���邩������Ȃ��B�j���̂Ȃ̂ł��̗ь�ɏd�˂Ă݂�B
�@�@�@�@------���̉ƍ��~�͖ڏo�x�����~�@�߂ƋT�Ƃ������V��
�@�@�@�@�@�@�@�@�V���E�K�C�i�@�n�@�@���f�^�C�@���f�^�C-------
 |
 |
|
�@�^�J�T�S�����E�����S�����Ԃ������B���̉Ԑ�32�I |
�@���h�Ɖ`�Ӗ����킳�킳�B������ǂ��g�������B |
���R�̕�炵614 2021.9.4
�@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@
�@
 �Z�~�Ɗs���̐�������
�Z�~�Ɗs���̐�������
�ߐ{�삪�������ق̐䒲���@�Ȃ͂����T�[�`�@
http://www2.city.nasushiobara.lg.jp/hakubutsukan/event/research.html
���̃��T�[�`�ɎQ�����n�߂��͍̂��N��7���W���������B������10��15���܂ő����̂ł��傤�ǒ������_��8�����܂ł̌��ʂ��L�^���Ă��������B�i�����͒�ł̌��ʁB�O���ŕ������ꍇ�͂��̎|�L�ڂ��Ă���B�j
�@ ���X�̋L�^�͂����ɁFhttp://kemanso.sakura.ne.jp/birds.htm
�@�@�i�폜���܂����B�j
 �@�J�b�R�E�@�s�� �@�J�b�R�E�@�s��
�s���̐������̂́A7/14�C7/16�A7/17��3��B����ѓn���Ă������B�����̔N�̃J�b�R�E�̏����͂T���A�x�������炢�����A���N�͕����������悤���B���邢�͌̐������Ȃ������̂��H�I�X���ɐB�Ɠ꒣�葈���̂��߂ɖ��Ă���悤�����A����钹���ƒm���ĕ�����
�A�����܂������F�ɂ��v����B�Ñ�̌ď̂͌Ďq��(��Ԃ��ǂ�)�B
 �z�g�g�M�X�E�m�C�E�s�@�A�E���� �z�g�g�M�X�E�m�C�E�s�@�A�E����
7/15�A7/18�A7/20�A7/28�@7/30�A7/31�A8/6�@���ꂼ��1�H�����������B�������������߂��g�̂̊��ɉH���傫��
�A��ѕ������X�����ĕs��p�Ɍ�����B
��ؑ��`���ŁA�������Z���z�g�g�M�X�ɕϐg�����Ƃ��������`�����v���o���B�Z�͌�����Ĕ�щ��u������A���Ƃ��Ɛ����v�B
.gif) �Z�~�ɂ��� �Z�~�ɂ���
1�j �q�O���V�@
�ߐ{�ɗ���܂ŁA�q�O���V�͉Ă̏I��̂W������X���ɂ����āA�[�����Â��Ȃ邱��A�₵�������������鐺�Ŗ����̂��Ǝv���Ă����B������
������ɗ��āA�[���͖ܘ_�����A�Ă̏��߂̑����A�܂����Â�����Ƀq�O���V�����̂ɋC�Â����B
�ǂ���炠�閾�邳�ɂȂ�Ɩ��n�߂�悤�ŁA���Ƃ��A
7/8�@�@���q�O���V���i3��������30���ԁj
8/11�@ �q�O���V�����i4��35������20���ԁj�B
7/8����8/30��52���Ԃ̋L�^������ƁA�����ɖ��n�߂鎞�����������ɂ���Ȃ���P���Ԓ��x�x���Ȃ��Ă���B���邢�͓��̏o�̎����ƊW����̂�������Ȃ��B�F�s�{�C�ۑ�̋L�^��T���Ă��A�C�ے��ł͓��̏o���̓���̎����\���Ă��Ȃ��悤���B�����Ƃ�������������ꏊ�̈ܓx�o�x����A���̏o���̓��肪�v�Z�ł���炵�����A�Z�����s�̃��^�V�A��̑��ށB
�[���͂���Â��ɂȂ�ƁA�����n�߂�悤���B���������Đ��V�̗[��6���ɖ��A�܂�̓���4���ɖ��Ƃ������ۂ��N�����B�Ő�����7������1�T�ԁB�W�c�Ŗ��A���̏W�c�������������ė֏����Ă���悤�������B�����t���[�Y��7�b�Ƃ���������茳�C�Ȍ̂̏W�܂�̂悤���B
8/12����͗�N�ɂȂ��������ŁA�����̃q�O���V�̐��͕������Ă��Ȃ��B�Ȍ�8/30�܂ŗ[�������͒x�������ɖ��������邪�A�̐������Ȃ��悤���B
  �q�O���V�ɕt���Ă̎v���� �q�O���V�ɕt���Ă̎v���� 
���̂ɉ��x�A�Ɠx���傫���e������炵���B�ߐ{�ł�7������8���ɖ��A��n�ł�8������9���ɂ����Ė��B�ԂƂ�ڂ��H�ɂȂ�ƎR���牺��Ă���悤�ɁA�q�O���V�͕W���Ȃǂ̐����n�̏�Ԃ�I��Ő�������̂�������Ȃ��B
�@
2�j �c�N�c�N�z�E�V
������7/25�B�Ȍ�ꌎ��̍����܂ŁA������[���܂Ŗ�������B������Ώ����قǏW�c�Ō��C�ɖ������B��Ԃ̌��C���́B
3�j �j�C�j�C�[�~
������7/16�@�Ȍ㍡���܂Ŗ������������������Ă����B�W�c�ł���悤���B�����͒n���B���₩�ȃc�N�c�N�z�E�V��BGM�ɓO���Ă���悤�Ɏv����B
4�j �~���~���[�~�@
�߂��̓��̉w�≖���}���قł�7�����{���琷��ɖ��Ă���B�J���ē������肪�ǂ��A���Ɏ��t���z����J�G�f��~�W�̖������ꏊ���D�݂̂悤���B�ؓ��̉w�̒n�ʂ̓Z�~�������o���������������ɂ݂���B
��ł̏�����8/11�B�Ȍ㖈�������A���̓��̓V��ɂ���Ė��̐����ω�����B������������D���Ȃ悤���B
5�j �A�u���[�~
��ł̏�����7/30�B����ĉĂ炵���V�C�̒��Ԃɖ����Ƃ������B�J�͗l�̓��������č��N�͂��܂���Ȃ��B
���܂܂łɕ�������10��ɓ͂��Ȃ��B�P�̂Ŗ��B
�@�w���t�W�x�ɂ̓Z�~���r�̂�10��B
�@�@�E�Ђ��炵�̖��ʂ鎞�͂��݂Ȃւ��炫�����ӂ��s�����ׂ��@�唺�h�I�Ǝ��@�@��17-3951�@
�@�@�E���̉ԍ炫�����ӂɂЂ��炵�̖��Ȃ�ȂւɏH�̕������@�@�@�@��ҕs�ځ@�@�@�@��10-2231
�@*�W���R�P���͏h��̓��@
�@�@�킪�����j��������������B
 �@�A�����J�V�I���@�L�N�� �@�A�����J�V�I���@�L�N��
�@�@�@�@�@���R�̕�炵613 2021.8.30
�@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@
�@
 ���̓���ԁA���������Ȃ���������Ă����̂�
���̓���ԁA���������Ȃ���������Ă����̂�
�I�C���^���N�̐��R��C���A�ƂȂ�Ƃ��������̎d���������B�����͊���n�Ȃ̂ŁA�������������Ŕ����Ă����Ȃ��B�����̃I�C���^���N�i200�k����j���Ƃ̗����ɐݒu���A�������珰���ɔz�ǂ�L�����Ԃ̃X�g�[�u�i�����r�C�A�t�˔M���p�j�Ɍq���Ă���20�N�߂��g���Ă���B
����Ђ���ƌ���Ɓi���Ȃ���悩�����B�m��ʂ����Ȃ̂Ɂj�I�C���^���N�̉��Ɏ��t���Ă��鐅�����p�̃v���X�e�B�b�N�L���b�v�Ƀq�r�������Ă���̂��A���ɐ��H�����������Ă���̂�
�C�t���Ă��܂����B


�I�C���^���N�͊O�C���Ƃ̉��x���Ō��I���A������H2O�����܂��Ă���B
�t�B���^�[��ʂ��Ă��̐����A���N�Ɉ�x�͐����������Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
�^���N�͂��������d�g�݂ɂȂ��Ă���B����͐��ł͂Ȃ��ē������R��Ă���悤���B���ꂪ��肾�B
���������l�b�g�̒���T���ĕ����A�V�����I�C���L���v�������Ē������A�����A����Ɛ_�˂���͂����B
�C������ɂ͂܂��A�^���N���Ɏc���Ă��铔����Ԃ��|���^���N�Ɉړ������Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�������O�ɂ��ڂ�Ă��܂����B�����͋�C�����d���̂ŁA���ɗ��܂�B�p����Ⴍ����ƏL������Ȃ��B
�Â��L���b�v���O���A�X�g���[�i�[�i�h����j�ƃI�[�����O�i�ۂ����p�V�[���j��|�����čēx���t�����B
���������ΊȒP�����A�����A���ʼn����A����������̎O�d��̂Ȃ��悤�₭�C�������B
�Ԃ��|���^���N2�t���̓������Ăу^���N�̒��ɓ���߂�---���̕��@�́B
�܂��r���������Ă��āA�I�Ɍ����Œ肷��B���̌��̏�ɓ����^���N���ڂ��A���፷�𗘗p���ē��������C���^���N�ɓ����B�d���B��Ɏc�����͎̂蓮�œ����A���ꂪ����B
���S���Ȃ̂ŁA�\�߂��ׂĂ̋@�ނ����[�v�ʼn����Ɍ��ѕt���ČŒ肵���B���ꂪ���\���Ԃ�������B��Ȃ��d���͈�l����ԑ����A�Ƒ��_�����������ʂ�A��l�ł��Ƃ�����Ƃ����^�C�~���O�̂��ꂪ�����āA�C���c�N���Ƃ��������B�����̑��_�ƘZ���̎��A�u��������������O�ɁA���ꂩ��Z�Z�����A�ƌ����ĂˁB�łȂ��ƃT�|�[�g�ł��Ȃ����Ƃ����邩��v�B�O�����ē`���Ă��Ă��A�������Ǝd�������������_�ɂ͓͂��Ȃ��B
�����A�C�������B���ӂ̂��ق��т��т͂Ȃ낤�A�ƌ����Ă����͎̂��B
�i���j�����|���^���N�̐F
�֓��͐ԁA���͗B�Ȃ����낤���B�K�\�����͐ԃ^���N�ցA����͒�Ԃ̂͂��B���݂̓|���^���N�ɃK�\������ۑ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ�
�B�������������Ȃ��̂��낤���B�֓��l�͗�Ò����Ȃ̂��H
�i���j�c�ɂ̕�炵�́F
�o���邱�Ƃ͎����ł���̂����R�����A�S��肵���̂����σ��x���ȏ�̎d���́A�Ȃ�Ƃ��O���������Ǝv�����Ƃ�����B�����������������̖������ɂ͑ウ���Ȃ�
�B
���R�̕�炵612 2021.8.25
�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
�@ �@���������Ɏd�オ�����@�@ �@���������Ɏd�オ�����@�@
�H�C�������낻��Ԃ��炩�������B
�J�����������������S���̎����f���ɑ傫���Ȃ��āA���������݂艺���Ă���B
�������F�Â��Ă���̂����炵���B�q���̂���̗V�т��v���o���āA����čH�����Ă݂悤���Ȃǂƍl����B
���N���߂ĐA�����x�S�j�A�̉Ԃ�������}���Ă��āA�s���N----��----�s���N�̍s���ł₩�B

�@���R�̕�炵611 2021.8.20
��x�ڂ̔~�J�������� �䂵����@�@ �ԂƂ�ڂ��R���牺��Ă���
�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
�@ �w偂̎q�͂��낻��U���Ă������@
�w偂̎q�͂��낻��U���Ă������@
�~�j���O�̃f�b�L�ɃN���}�`�X�E�����^�i�����߂Ă���B�������J�̂Ȃ��A�t�̉A�ɒw偂̗��X���B����Ă���̂������Ă��܂����B
���X�̂܂��������̒w偂̎����o���A���`����Ă���B���傤�ǃI�����s�b�N�ō̗p���ꂽ�o�u�������̂悤�ɂ����ۂ�ƁB���邢�͐̂̉ᒠ�̂悤�ɁB
�o���A�̑傫����10�p�~10�p���炢���낤���B���X�𒆐S�ɂ��Ēw偂̎q�����݂͌��Ɉ��̋����i2-3�~���j��ۂ��Ȃ���A�g�̂����ɌŒ肵�Ă���B�o���A�̏���ׂ����J�����藎���Ă��������͔G��Ă��Ȃ��悤���B
�悭����ƁA�������̂͂��łɈ�l�O�ɒw偂̌`�����Ă����B�g�̂������݂ɐk�킹�Ă���B�O�C�����낤���B�k�킷���Ƃő̂ɔM�������Ă���̂�������Ȃ��B

�Ƃ��낪�J�������߂Â��Ă݂�Ǝq�w偂����̓������s�^���Ǝ~�܂����B�܂�ŒN�����u�t���[�Y�v�̍��}�𑗂������̂悤���B���܂ꂽ�ĂȂ�����A���w偂����͊Ⴊ������炵���B�߂Â��Ă����͕̂ߐH�҂Ƃł��v�����̂�
�B
�J�������������Ă݂�B���w偂̎������͂��Ȃ��Ȃ����̂��A50�Z���`�܂ŗ����Ə��w偂����͂ӂ����я����݂ɑ̂�k�������͂��߂��B
�V�W���E�J���̃q�i�́A�����O�ɑ����̒��ʼnH�����̗��K�����邪�A�w偂̎q����ԗ��K�����Ă���悤�ɂ�������B
�w偂͏H�ɂȂ�Ɨ��X�����藑���Y�݁A���̔N�̏t�ɛz������͂������A�G�߂̏�ł͂��łɒx���B�J���������������Ȃ̂��ǂ���������Ȃ�
���̉摜�̗��X�ɂ͂����q���������Ă����̂�----�����炭���S���琔��C�����A���̒��Ŗ����ɐ����ɂȂ��̂́A���̒���1���ɂ������Ȃ����낤�B
�w偂̎q������B���X�����肵�Ă���w偂̎q������B���U���Ă����B�����͉J������Z�������o���đ��̂悤�ɔ��ł����ɂ͑��������Ȃ������ȁB����������������҂��Ă���B�����R���i�Ă肵�Ă����B����1�N���ɂȂ��B�N�����̂悤�ɔ�яo���������A�����̐g�͎����Ŏ�邵���Ȃ��ȁB�����瑊�ς�炸�Ă��Ă����B�H�����ǂޖ{�������B
�N�������O�r����ȁB�����c���̂͂ق��1�C��2�C���낤����B
�y���X�@egg
capsule�@���͂��܂��܂ȕ����ŕ�܂�邪�A���̂Ȃ��ł�������Ă�����̂������B���̕ی�Ɛ����ێ��C�����◑���m�̕t���C�̐����Ȃǂɖ𗧂B�z
�y�w偂̎��@�N���̎��͋����ď_��B���������Ŕ�ׂ�ƁA�S�̎��̂S�`�T�{�A�i�C�����̎��̂Q�{�̋����z
�y�w偂̑��̌o���Ɖ����z�w偂͎����̑��ɂЂ�������Ȃ��̂�
���̉����ɂ͂˂˂����S���������t���Ă���B�c���ɂ͂��ꂪ�Ȃ��炵���B�w偂͌o���̏���Ă���悤���B�ł�����Ď҂̒w偂����邾�낤�ɁB���ׂ�ƒw偂̐g�̂�r�͖����������܂�ł��ĉ����Ɉ����������Ă��A������Ɠ�������悤���z
 �������G�ꂿ������B �J�ɔG�ꂽ賂��H�U�������Ă���B
�������G�ꂿ������B �J�ɔG�ꂽ賂��H�U�������Ă���B
�@�@�@���R�̕�炵610
2021.8.15 �����͔s��L�O���@6���̋C����16.5��������
�@�@�@�@�@ �@ �@
 �@K���Ƃ̐A���T��
�@-----�قƂ�Ǔ������̋C���� �@K���Ƃ̐A���T��
�@-----�قƂ�Ǔ������̋C����
K�����炱��ȃ��[�����͂����̂͂��̏t�̏��߁A3���̂��Ƃ������B
�u�t�ɂȂ�̂��猩�Ă��铹���̉Ԃ̖��O��m�肽���ēY�t���܂����̂ł���������������K���ł��B����Ȃ��肢�ŋ��k�ł��B�v�������ƒ��J�Ȍ��t�����Ȃ̂��B
��������̂Ȃ��A���T�����n�߂�K���A�H�ӂŌ������Ԃ̖��O���m�肽���Ē����𑱂��Ă����Ƃ���A���R�ɂ�����HP�́u�ߐ{�ɍ炭�ԁv�̃y�[�W�ɍs�������ꂽ�悤���B�v�����Ē��ڎ�������悤�ƘA�������������̂��A��̃��[���B
�X�ɋ��R���d�Ȃ�A����K���́A���_���ߐ{���V�j�A�J���b�W�̍u������u���Ă������̓��������Ƃ������Ƃ����������B
���Z�܂��͎��̉Ƃ���10�L�����炢�̂Ƃ���ɂ���B�W���͉䂪�Ƃ���100���قǍ������B�A���������Ⴄ�悤���B
�Ȍ�AK������قƂ�ǖ����̂悤�ɉ摜��Y�t�������[�����͂��悤�ɂȂ����B
�i���������ł��߉�Ȏ��́j�������܂��̃��[���Ɂu�A���̖��O�Ƃ��̕��ށv��Y�t���A�������M���ĕԐM���Ă����B�A���̎�ނ͂ǂ̂��炢
�̐��ɂȂ邾�낤���B���ł�100��ނɓ͂��Ă��邩������Ȃ��B
�A���ɋ����������n�߂��l���A�ǂ̂悤�Ȏv�l�o�H�����ǂ��ĒT�����L���Ă����̂��A����ɂƂĂ��������������B�Ȃ�قǁA���������ӂ��Ɏ��_���L����̂��B�A���������Ă��鎞�ƕ����r���ĉ�������Ă��鎞�ł́A�S���ʂȐA���Ɍ�����̂�----�ȂǂƂ��̐��_�̂����ނ��悪�����Ă��āA����Ɏ����ꏏ�ɎU�����Ă���悤�ȋC�ɂȂ��Ă����B
����A�u�n�߂ĂT�P���ɂȂ�܂��B���߂ƍ��Ƃł͂����g�̒T���̑ԓx�ɕω�������܂����H�v�ƕ����Ă݂��B
��͂肹��������K���A�������ܕԎ�������A�����������B
���܂�ɑf���ȕ��͂Ȃ̂Ŋ�������B�i�]�ڂ͂��{�l���������Ă��������܂����B�j
�u�A���T�������T�����I
�����ƌ����Ԃł����B�T���ԓx���ς�����Ƃ�����薼�O���������������Ƃɂ��Ԃ�T�������ƂƂ��ɁA���̈炿�Ԃ���ώ@����U�����y�����Ȃ�A�����A�������y��������ƂȂ�܂����B
���x���w�Z�̐搶�������̐��k�̖��O�Ɗ炪��v���A����ɂ��̐��k�̐����Ԃ肪�킩��悤�Ȋy���݂ł��B���w�Z�̐搶�̌o���͂���܂��A���̂悤�Ȋy���݂����邩�炱�����k��������Ƃ�����J���y���݂ɕς���ł��傤�ˁB���͂����낭���Ă��Đ��k�̖��O��Y��Ă��܂����Ƃł����B
���N�A�����ꏊ�ł܂����Ǝv���Ƃ���܂ŋL���͂��ێ����Ă������Ƃ����C�����ł����ς��ł��B�L���������܂����B�v
���Ƃ���K���́A���{�̗��j�╶�w�ɑ��w���[���A�A���̔w�i�ɕ��w�𗍂܂��ĉ������ƁA�f���炵���m���ł��Ԏ�����������B���Ƃ��Ό������Ƒҏ����̉�ɂ́A
�u�x�m�ɂ́A���������悭�����ӁB�v�i���Ɏ��j��ǂ�ł킴�킴�x�m�R�ɏo�����Ă��܂����A�ȂǂƂ������b�����Ă�������B
�i�����ɉ����F�̉ԂƂ��邩��ɂ́A���ɂ������͔̂����������łȂ��ĉ��F���ҏ������낤�j
����߂��N����K�������A�S������������Ȃ��B
�ǂ��A���F�B�Ƃ��������o�Ō݂��ɔ����ł���̂��y�����B
�@���̉w�ɉ��������Z���o�Ă����B�@�ҏ����̉Ԃ̐F�Ɏ��Ă���B

�u�Z�H�߂Ύq�ǂ��v�ق�I�H�߂܂��ĎÂ͂� ���Â���藈�肵���̂��ڌ��ɂ��ƂȂ�����Ĉ������Ȃ��ʁv�@
�@�@�@�@�R�㉯�ljr�@�@�@�r�܂ꂽ�̂͂��̉Z�Ɏ��Ă���B�q���̂��납�炠��Z�B
�@�@�@���R�̕�炵609 2021.8.10
�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 You might think but today's hot fish.
You might think but today's hot fish.
�䂤�܂��Ƃ������ǂ����傤�̂�������
�p����K���n�߂����w���̂���A����ȋY���������ď��Ă����̂����������B�������������g�Ɋ����邱�ƂȂ��A�ڑO�ɂ���u���Ɗy���݁v�ɐ��_���X���Ă������̎Ⴗ������X��B
�ߐ{����---����͗������đA�܂����B�ƊF��������邪�A�����Č����Ă���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�Œ�C���ƍō��C���́A�������ɑ�㎞������Ⴂ���A���͂�тɈ͂܂�Ă���킪�Ƃ́A�u�����ʂ�Ȃ��v�B���C�Ƒ��܂��Ă�͂菋���B�N�X������������Z���T�[���s�q�ɂȂ��Ă���悤�ȋC������B
�ߐ{�����Ƃ������O�́A����͎s�̊ό��ۂ̉A�d���Ǝv���B���܂��ɓȖ،��ɂ͊C�������B
�W���R���@���Ȉ���f��
�������̃��N�`���\�ƁA���s�̉��ɂ��鎕�C�̑|���B�킴�킴�L������o�����Ă������鎕��҂���ɁA�u�L���ق����������B���͉��R�o�g�Ȃ̂ŁA���̃A�N�Z���g���ƐS�����킴�킵�܂��v�Ȃ�Ď��Â̍��Ԃɂ���ׂ�
---�������͖��������ƌ̋����a����Ƃ��͕ʂȂ̂��B�i��H�����H�ނ���������H�j
�搶�ɕt���Y���̂������\�͂̂���e�Ȏ��ȉq���m����Ȃ̂ŁA���S���S�i�N���̎����݂������B�ςȌ��t���j�B
8���Q���@�ׂ̕ʑ��ɁA�ǂ����Ă��������Ă��邨������܂�����������B���N�Ԃ肾�낤���B
�u�Â��ŕ����Ȗ����ŁA���͍K���v�Ƃ��������B����Ƃ��X�R�ɂ��Ȃ肾�B�����Ă����Ό��̃G�b�Z���X�����肽�����g�̂���Z�݂����Ă���悤�������B���͂�������܂̂悤�ɔN����d�˂邱�Ƃ��ł��邾�낤���B
�@
�A�����̗��������Ԃɑ���������B
�����������đ����Ƃ�A�������������đ������B���ɂ������������Ƃ��łɑ����ڂ��ڂ��Ɖ��𗧂ĂĐ����Ă���B
�s��F�́A�n�k�Œ�d����������Z���B
���č������Z�~�ƃJ�b�R�E�̒����𑱂��悤�B
�ۂ̉Ԃ��炢�Ă����B��㎞��̂��ׂ��炨�S�ʂɑ}����������̂��A5���[�g���̍����܂ň�����B
�@�@http://kemanso.sakura.ne.jp/asagaho.htm�@�@�w���t�W�v�ɂ͂�������B
�@�@
���R�̕�炵608 2021.8.4
�@�@�@�@�@ �@ �@
 ��Ɏ��܂��ā@�@�Z�~�ƃJ�b�R�E�̐��Ԓ����@�@�@�@�@�@�@�@
��Ɏ��܂��ā@�@�Z�~�ƃJ�b�R�E�̐��Ԓ����@�@�@�@�@�@�@�@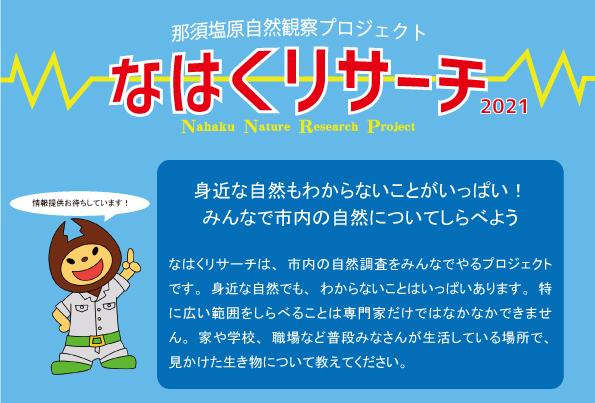
�@�ߐ{�삪�������ق̐䒲���@�Ȃ͂����T�[�`�@
�@http://www2.city.nasushiobara.lg.jp/hakubutsukan/event/research.html
�����������m�点������ƁA���������Q������̂����^�V����䂦��B
�͂��߂ăJ�b�R�E�̖��������B
�e��̐䂪���n�߂��A����͂��A�ǂ��ŁH
����Ȃ��Ƃœ�����t�ɂ��Ă��āA�������͋�ƗтɌ����Ă���B
���X�̒����͂�����F�@http://kemanso.sakura.ne.jp/birds.htm
�����͂P�O���܂ő����̂ŁA������܂Ƃ߂Ă݂���肾�B���Ă���Ȃ��Ȃ��ʔ����B
 |
������グ����A�т̒��ɖڂ���������B�n�ʂ́A�Z�~�����܂�o������T������B����Ȃ��Ƃ��肵�Ă����B�����ӂƌ����
�A��䪉ׂ��ǂ����蓪���������Ă����B
�i�ӂƌ��Ȃ���ǂ������B���肪�ǂ�ǂ�ɂȂ�A���т������ɂȂ��Ă��܂����j
����ē����������ɂ��Ċ������Ă����B
����H�ǂ�����ĐH�ׂ悤���B�����X�`���������A�|�̕��ɂ��悤���B�֎q�ƈꏏ�ɒЂ��悤���B
����䪉ׂ̍������́A�S�O�N�O�A���_�̎��Ƃ̗��R����@��グ�A���̉Ƃň�āA�����č��̏ꏊ�ɘA��Ă���
��ȍ������B���j�̂��鍪�����B
�H�߂��ĖY����̂����Ȃ��悤�ɁB�C��t���悤�B
�@ |
���R�̕�炵607 2021.7.29�@�@
�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �@���݂Ȃ肳�܂̓����� �@���݂Ȃ肳�܂̓�����
���_�̎��Ƃ�1970�N�ォ��̂��悻30�N�ԁA���L���̌��V�C�^�P���Y�҂Ƃ��Ēm���Ă����B���͋`�Z�v�w��������ďd���ɖ��^�ׂȂ��Ȃ�A�͔|�͎~�߂Ă���B
�߂����ɂȂ��A�Ȃ̂���ɋ`�Z���u���̑����N�́A�V�C�^�P���L��ɂȂ�B����͕Ă��ꏏ���B���̂��̃W�O�U�O�̌�����ȁi����̍ȁv�ƌĂԂ��낤�v�Ƙb���Ă����̂��A�ǂ����ɋL�����Ă��āA�Ȃ����낤�ƋC�ɂȂ��Ă������A�ŋ߂���Ɨ��ƃV�C�^�P�A���ƕĂ̊W���������Ă����B����܂ŃI�]�����W���Ă���̂��ƍl���Ă������A�܂���������Ă����B
���͓d�q�z���邾���łȂ��āA�}���Ȃ̐A���̓����Ɠ��������f�Œ�ɖ��ɗ����Ă���悤���B���f�͐����̐����ێ��Ɏ���đ�ȗv�f���B��C��8���߂����߂Ă���̂ɂ�����炸�A�������A�������f�����̂܂ܐg�̂Ɏ�荞�ނ��Ƃ��ł��Ȃ��B
�y���̃G�l���M�[�Œ��f���q�����q�ɕ�������A���̌��q���_�f�ƌ������Ē��f�_�����ƂȂ�B���̒��f�_�����͐��ɗn����̂ŁA�J�Ƌ��ɒn���ɓ��荞�ށA�܂��̓V�C�^�P�̞ɖɋz�������B�����̗ƂƂȂ�Ƃ����킯�B
�z
�ł͂ǂ̂��炢�̊����Ŏ��R�E�Œ��f�Œ������̂�----��10���炵���B���R�c���90���͍ۂ̗͂���Ă���Ƃ������Ƃ��B
�����Ɋւ��ċC�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����B���n�Z��n�S�̂ŊǗ����A�킪�Ƃł��g���Ă����ː��ɂ��̒��f�_�������Z�݂���ł��āA�����̐��������̂��т�
�������o����邩�炾�B
���̗͂��_�ƂŎ��炳��Ă��鋍�A���ɓ����̔r�����̒��ɁA�ߏ�ȏɎ_�����f���܂܂�Ă���̂����̌����炵���B
�Ɏ_�����f�y�ш��Ɏ_�����f�����v������ܗL�ʂ�10mg�^L
�ȉ��B���݂̐��l��1mg�O��Ȃ̂ł܂����S�����A�Ɏ_�����f��Ő��̍������Ɏ_�����f�ւƊҌ����Ă��܂���ނ̋ۂ�����炵���B����ɓc�����痬��o�����Ɏ_�Ԓ��f�́A����o������̕x�h�{���������N�����B
�z���Ă������ɂ́A�u��ː������߂�v�Ɗ��ł������A����ȑ��ʂ��������Ȃ�Ēm��Ȃ������B��{�̋����ꏊ�ɋt�Z�������g������ߑ��u�����t���Ă�
��A�킪�Ƃ̑䏊�ɂ��킪�ݒu����Ă���B���S�ƌ����Έ��S�����A�ߐ{���Y��Ȑ������҂��Ă������炱���A���G�ȋC�����B
�E7��23���@�I�����s�b�N�J��B
�V�c�É��̂����t�ɁA�u�j���v�ł͂Ȃ��āu�L�O�v�Ƃ������B
���Ȃ��ݑI�肪���̍ŏI�_�Ύ҂ɂȂ����̂��f���炵�����Ƃ��B�l�ނ̑��l���̋�҂�����B
�E�V���Q�P��
�O��ڂ̕����ƈ琗�ɐ������A�����ɂT�H�̃V�W���E�J�������������B
�����͒�������Ĕ�сA�e���ɉa�̎�����������Ă���悤���B���������������炵���B�u���A���A��--�v�B
�܂������������т����F���B
 �@���E�͂ǂ�ȂɍL���̂��낤�B
�@���E�͂ǂ�ȂɍL���̂��낤�B
���R�̕�炵606 2021.7.25�@�@
�@�@�@�@�@ �@ �@
 �w�ӂ肳������x
�w�ӂ肳������x
7���Q�R������A�w���{�o�ϐV���x�����������̘A�ڏ����ɁA���������Y�́u�ӂ肳������v���f�ڂ���邱�ƂɂȂ����B
���݂̘A�ڏ����A�ɏW�@�Î��́u�~�`�N�T�搶�v�͒��f�����������̂́A��Ƃ̉Ėڟ�����l���ɂ��Ă��āA�����A�吳���������Ƃ��̎���𑽖ʓI�ɕ\�����A�������鎞���`���ēǂ݉������������B���܂Œm��Ȃ����������߂���l�Ԗ͗l��`�����ƂŁA���̃p�Y��
�̃s�[�X�̒��S�l�����オ�点��----���̍�ƂƂ��Ă̔\�͂Ƃ��̗͗ʂɈ��|���ꂽ���X�������B
���̍�i�̌�������p���ɑ���������Ƃ͑����Ȃ�����łȂ��ƁA�ǎ҂��[�����Ȃ����낤�Ɨ\�z���Ă������A�\�z�����킸���j�����Ƃ̑�ƂƂ��Ēm������������Y�̓o��ƂȂ����B
���������Y�́A2011�N1���`12�N5���ɓ��{�o�ϐV�������ɘA�ڂ��ꂽ�w�����x�Œ��؏܂���܂����̂��L���ɐV�����B
��l���͓ޗǎ���A�����g�Ƃ��ē��ɓn�������{�����C�B���̍��Ǝ����ł���ȋ��ɍ��i�A���̍c�錺�@�Ɏ�藧�Ă�ꍑ�ېl�Ƃ��Ċ������{�����C�̋�Y��
�A����ɖ|�M���ꂽ���U���W�J���Ă����B�����������g�Ƃ��ē��ɑ؍݂��A�A���̌㐹���V�c�̑��߂Ƃ��ė͂��ӂ�����ɋg���^�����{�ڂ̎��Ƃ���
�A�Ƃ��Ƃ�������j���W�J���Ă����B
���̉Ă̒��͂��́w�ӂ肳������x���y���݂ɐV�����J����B
��҈��������Y���̌��t
�u--�����Ƃ̊W���ɂ��ẮA���{�̗��j�╶���͕�����Ȃ��B�O�\�N�قǑO�ɒ����𗷂������A�����Ɋ������B�����́A������������������������������Ǝv�������A�����ł��Ȃ��܂ܖY�p���Ă����B
�Ƃ��낪2013�N�ɍĂђ����𗷂��A�Y��Ă����h���ˑR�v���o�����B�����Č����g�̕�����������̉ۑ���N���A�ł���ƁA�傫�Ȏ艞�����������B���{�����C�Ƌg���^������l���Ƃ��镨��Ɏ��g�ޗR���ł���B�v�u���M�ɂ������ĉ͐����L����V�R��H�ւƂÂ��V���N���[�h����ނ��Ă����B�����C���������̓����A�A���r����[�}�Ƃ����Ղ��Ă������E�鍑���������Ƃ�������������������ł���B�v |
�S�ꓯ�������A�Ƃ����̂͂������܂������A2019�N5���A�Z���Ԃ��������A��C�o�R�V���N���[�h�k�H�𗷂����B���̗��̊Ԓ��A�S�ɖ苿�����̂��������̂��v���o�����B����͗}���������g�̂̉��ɂ����߂������̗��j�╶���ւ̓���B�������������v�����B�����̌`�ԁA�����A�����������̉e���������Ă������{�l�̈�l�Ƃ��āA�����̂Ȃ��ɂ��铲�ۂ��m�F���闷����������B
http://kemanso.sakura.ne.jp/silkroad.htm
�@�@�@ �@�@
�@�@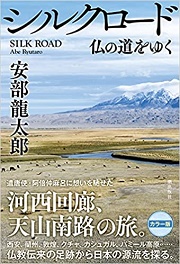
���F�������ꂽ�����g�D�̖͌^�B�����̐�[�I�ȋZ�p��p���đ��D���ꂽ�B�E�F���҂̋ߒ�
�@�@�摜�͋�B����������HP���炨�肵�܂����B���肪�Ƃ��������܂��B

���߂̔~�J�����ɁA���������炫�n�߂��R�S�����A�����ɂ��Ȃ���Ă���B
���R�̕�炵605
2021.7.18�@�@
�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �O��ڂ̕����@����͗]�T��
�O��ڂ̕����@����͗]�T��

���F���̂�����A�Ƃ͂�����V�B���̎��_�ł͗Y�������͕�����Ȃ��B
����͛z�����ĂR���ڂ��炢�̉摜�B�V�W���E�J���͕���10�ȏ�̗����Y�ނ̂ɁA�U���̕����ɐ������ċC��ǂ������e�����A�Ă�O�ɂ����ЂƓ��肵�����ʂ����̐������B
�ł��������̂R�H�Ə��Ȃ��B
���̂������A�e������������������p�����܂茩�����Ȃ��B����͂������낤�B12�H�̐������ɉa��^����w�͂ƁA�R�H����ďグ��J�͔͂�r����܂ł��Ȃ�����
���B
�S�Ȃ����A�e����������肵�Ĕ~�J�̏I��̓��X���y����ł���悤�Ɍ�����B
���̍ޗ��́A�ߏ��̗��_�_�Ƃ̋��ɂ��瓐��ł��������̖сB
���̒n��ł͎�ɔ����͗l�̃z���X�^�C����̋�
�������Ă���B���͌̎��ʂ���̂ŁA�߂Â��ƈЊd���邱�Ƃ�����B���Ɋ����ƊÂ��Ă����̂ŁA����͂���łƂĂ������B
�V�W���E�J���́A�����Ă��鋍�̔w������т��ނ��������̂��B����Ƃ������Ă���т��E���Ă����̂��B
�������͗z���Ă��鎞�A�����ꏊ�̕��������ꏊ�����M���z�����Ēg�����̂��B�ł̓V�}�E�}�͂ǂ��Ȃ낤�B
�~�J�������Ȃ�������Ȃ���l����B
 �@�z���X�^�C����̋� �@�z���X�^�C����̋�
���R�̕�炵604 2021.7.14�@�@
�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �Ђ����炩���@-----�@�ǂ̃W�����Â���
�Ђ����炩���@-----�@�ǂ̃W�����Â���
���A�N����Ɠ����ɑ����J����B�T�b�V�̘g�Ɏ��t���đ̂��x���A��߂ȃu���[�x���[�̖ɍ����L���A�ЂƂ�ƌ��ɓ����B�u�₩�Ȏ_���ς����N�������̐g�̂Ɏh���I�B
���č����̎n�܂肾�B
�����J�̍��Ԃ�D���Ď��n���Ă���u���[�x���[���A����������łP�O�L���ɓ͂����B

�T���̊����ƂU���̉J�ŁA�ǂ̎�Y�n�̒��쌧�Y���s��̂悤���B���܂ł��X���ɏo�Ă��Ȃ��̂ŁA���蔭�Ԃ����B
�X���Y�̈ǂ��U�L���w���B
�Ђ������������B�~�̗M�q�̎킩����o�����u�y�N�`���v�𑫂��ăW�����ɁB�������F�l�ɂ��������������Ƃ͗Ⓚ�ɂɕۑ�����B
�Ⓚ����ƊÖ���15���ɂƁA���Ȃ��ł���̂ň��S���B

�����������Ă���ƁA�f�b�L�ɒw偂������Ă���̂��������B���̒w偂��Ђ����瑃���ɗ�̂��낤�B�J�������Č��Ԃ�͏��Ȃ��悤�����B
�ߏ��̂��X�Ɂu�n���Y�̉��ꔒ�~�P�L��124�~�v���o�Ă����B����Ŕ~�W���������ׂ����ǂ����A�Y�ނƂ��낾�B�ǃW�����ŔM���ǂɂȂ肩���Ă�������Ă���͂��Ȃ̂ɁA�ۂ����̂�����ƃW�����ɂ������Ă��܂�Ȃ��B����H�ۂ����̂͂����C���ƌ������̂́B�R���i��������������̊�ł����Ă��Ȃ����B
���R�̕�炵603
2021.7.9�@�@
�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �����@���̂Q�@-----
�|�b�Q���h���t����
�����@���̂Q�@-----
�|�b�Q���h���t����
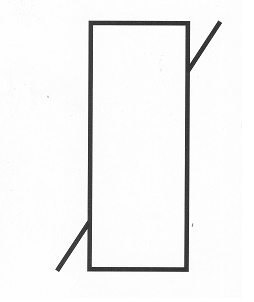 |
�@
�O�q�̖{�ɂ��ƁA�u�|�b�Q���h���t�����v�Ƃ́B
�����`��������͂��̒����`�̍��ƉE�ŁA�꒼���łȂ��㉺�ɂ���Ă���悤�Ɍ�����B
���������ۂɂ͂���Ă͂��Ȃ��B
�]�������ƌ����p�x��傫�����ς����Ă��܂��ƍl�����Ă���v�Ƃ̂��ƁB
�������ɁB |
 |
�摜�̓��[�x���X�̑�\��w�L���X�g�~�ˁx�iDescent from the Cross�j
�A���g���[�v�吹�� (����吹���̖��O�Œm����j
�A���g���[�v�i�x���M�[�j�@2015.7.15�@�@
�@�@�@(���E�̃p�l���̎��F�����́u����}���A�̃G���U�x�g�K��v�A�E���́u�_�a�ւ̕v�j |
2015�N7��15���B
�t�B�������h�̃w���V���L���N�_�ɁA���̖����N���X�}�X�E�G�N�X�v���X�i��s��ԁj�Ŗk�Ɍ��ɑ���L���A�D�ƓS���Ŗk���R�����o�R���āA�f���}�[�N�A�I�����_�A�x���M�[�A�h�C�c�A�X�C�X�A�C�^���A��
������B----���d�ɂ��������������𗧂ĂĎ��s�Ɉڂ��A�����̂��傤�ǔ����܂ŗ����Ă̓��̂��Ƃ������B
�u�����b�Z�����������A���E��������ƌ�����w�E�A���g���[�v�w�֍~�藧�����B���������Ƃɉw�ɂ͏㉺�ɏd�Ȃ���H���ʂ�A�S���̃h�[���^�̉��������Ԃ����Ă���B�Z�p�҂̑��_�͂��̍\�z���@�ɋ����ÁX�B���j������������K�i����͂̑����Ɉ��|�����B�ڎw���̓A���g���[�v�吹���i����吹���j���B�C�������g���Ă��������A�Ђ�����吹����ڎw���ĕ����B�r���Ŏ蕗�Ղ�t�ł邨������Ɉ�ȃ��N�G�X�g���A�傫�ȃn�O�������B
���̑吹���ł悤�₭�o����w�L���X�g�~�ˁx�B�C�G�X�E�L���X�g�̖S�[���~�낷�l���̗͋������̕\���Ɉ��|���ꂽ�L�������܂������Ȃ��B�ْ������ӂ�邱�̊G�̑O�ŁA�ǂ̂��炢�Ȃ��Ƃ��B
�ق��ƈႤ���Ԃ�����Ă���悤�������B
�C�M���X�̏����ƃE�B�[�_�ɂ��w�t�����_�[�X�̌��x�̍ŏI�́A�l�߂�������l���̏��N�l�����Ƃ�ǂ��A�N���X�}�X�C�u�̖�A�����i�J�����j�p�g���b�V���ƂƂ��ɐ�̍~�肵����Ȃ��A���g���[�v�吹����ڎw���A���Ɂw�L���X�g���ˁx�Ɓw�L���X�g�~�ˁx��ڂɂ��đ��₦��B���̖{�ɂ���̂��A���̃��[�x���X�̊G�B
�i�w�t�����_�[�X�̌��x�̃A�j�������i�{����1975�N�A�ĕ���2008�N�j�T���āA�ŏI���ɂ͗܂őO�������Ȃ��قǂ������B�F����́H�j
���̊G�̒��ɍ����𗘗p��������������ƕ����āA�U�N�O�̗��̋L�^�����o���Ă݂��B
�O�A�Ւd��̂��������p�l���́u�L���X�g�̏\���ˍ~�ˁv�����ƂȂ��Ă���B���̊G�̉E���A�C�G�X�E�L���X�g�̈�[�����낷���߂ɗp�ӂ��ꂽ��q�̂Q�{�̑������̂܂܍���ɐL���ƁA�G�̈ʒu�Ƃ��ꂪ�ł��Ă���B��҃��[�x���X�͂��̍������N���邱�Ƃ�\�ߒm���Ă��Ă��̂悤�ɕ`�����̂��B���邢�͓V�˓I�Ȋ��o�ɏ]���Ă��̍\�}����肢�ꂽ�̂��B
�G���c����Ă��邱�ƁA���̓l���̎���̂悤�ɒ��̒��ɉB�����̂ł͂Ȃ��A�K��҂̒N�������������ɂ��邱�Ƃ��ł��邱�ƁB����͖{���ɂ�낱�������Ƃ��B���̎v���o�����邱�Ƃ��A�f���Ɋ�т����B
�@
���R�̕�炵602
2021.7.4�@�@
�@�@�@�@�@ �@ �@
 �@�s�J�s�J����̂͂Ȃ����낤 �@�s�J�s�J����̂͂Ȃ����낤
���Ԃ���O�ւƒ��ڍL����f�b�L�̐�Ɏ��t���Ă���t�F���X�́A�ؕ��������ŕ��H���邱�Ƃ͂܂��Ȃ��B���l�p�`�ł͂Ȃ�����ǁA���̎ʐ^�̂悤�Ɋi�q���ɂȂ��Ă���̂ŁA���̖͗l�𗘗p���Ă��̉��N���͌��Ɉ��Γ���̃e�X�g����葱���Ă���B����ɗ���͂Ȃ����A�Ȃ����Ă��Ȃ����Ȃǂ��m�F���钩�́A
�����ْ����邱�Ƃ�����B
�Ƃ��낪���x�����̃e�X�g���J��Ԃ����сA�ʔ������ƂɋC���t�����B
�Жڂ��������t�F���X�ɓ�����ƁA���S�Z���`�̎������d�Ȃ镔���ɁA�Ƃ��D�F�Ƃ����Ȃ������F������Ă���̂��B�Ђ�Ђ�Ƃ��̐F������A�����Ԃ��Ƃ�����B�������œ_�����킹��i�q�̏d�Ȃ镔�������ɂ͂��̐F������Ȃ��B
������������͉��ȂA�ǂ����Ă��낤�B���邢�͎��̖ڂɉ����ُ̈킪�N�����̂��B------�N�ɂ����킸�S�Ђ����ɈĂ��Ă������A���̐S�z�������Ƃǂ߂���X�������Ă����B����͐��퉻�o�C�A�X���̂��̂��낤�B�����������瓦����̂͗ǂ��Ȃ��ȁB
�Ƃ��낪�����Ă����{
�w�Ȃ�����������H�ǂ����Ă���������H�����̂Ђ݂ɂ��܂�{�x
�@�@�@�@�i�V��m�V�ďC�@���ǂ�����ԕҁj�̒��ɂ��̓������������B
����́y�w���}���i�q�����z�ƌĂԖڂ̍��o�i�����j�������̂��B�@
�����̊i�q�����n�[�}���O���b�h�i��:Hermann-Gitter�A�p:Hermann
Grid�j�ƌĂԁB���̊i�q���Ɏ����Ă�ƁA���������������̕������D�F�Ɍ����A�����������ɂꂻ�̊D�F������Ȃ��瓮���Ă����B�u�F�̖��x�Δ�ɂ�鎋�o���ۂ�
�ЂƂv�炵���B
�@�@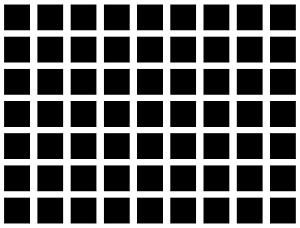 �@ �@
�@���̉摜�����Ȃ��炻�̎��������Ă��������B�ق�I�@�@�@��▾�x�Δ䂪�������B�܂肾���炩�B
Eureka�I
�]������ɔ��f���w�߂��o��---���̎����ł͗}�����Ȃ����ۂ��n�[�}���O���b�h���ʁi�n�[�}���O���b�h���ہj�ƌĂсA�����҂ɂ��Ȃ�Ńw���}���i�q�����ƌ����邱�Ƃ�����Ƃ������Ƃ������B
�m��ʂ͈ꎞ�̒p�ł͂Ȃ����A�s�v�c�Ɏv���Ă��邱�Ƃ̗��R����������Ǝq���̂���̂悤�ɐS�������B
����Ŏ��̖ڂɈُ�͂Ȃ����Ƃ������������ł���������Ƃ��B���S���ėΓ���`�F�b�N�ɗ�ނ��Ƃɂ���B
�U���Q�W���@���N���߂Ē�̃j�b�R�E�L�X�Q���J�����B�����̐�ꃖ���͂��������Ŗ��J�炵���B
�@�@�@ �@���̃j�b�R�E�L�X�Q�͂�⑾�߁B �@���̃j�b�R�E�L�X�Q�͂�⑾�߁B
�U���Q�V��
�R�[�q�[���[�J�[�̎����肪�ۂ���Ɛ܂ꂽ�B�����������_���C������B�Ƃ̒��ɏC�����Ďg���Ă��铹����ꂱ�ꂠ���āA��������邽�сu�������ĐV�������i���g��������--�v�Ǝv�����A�������������Ȃ��B
���R�̕�炵601
2021.6.29�@
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �J�̂��킢�ɍ炭�Ԃ�
�J�̂��킢�ɍ炭�Ԃ�
 |
 |
| �ԏҊ��̉Ԃ̖����z���� |
�N���}�`�X�@����
�@�A����18�N�ɂȂ� |
 |
 |
|
�Z���m�E |
�X�g�P�V�A�̏��ԁ@���͏h���r�I���i���j |
 |
 |
|
�g���e���C�A �@������ |
�@�@���x���_�[�@�����ꎞ��������
�@�@�E�̓}�c���V�\�E |
 |
 |
| �@�}�c���g�Z���m�E�@���������� |
�@�@�����T�L�c���N�T
�@�@���˔\�ɉ��������ƗY�ǂ��s���N�ɕς��@�@�@�@ |
 |
| �@���N�̃u���[�x���[�̎��n�i�R��ځj�T���̖���̉J�Ŏ�������̉Ԃ����X�ɗ����āA���N�͕s��̗\�z�B |
22���ߌ�A�Q��ڂ̃��N�`���ڎ�I���B�ڎ�ꏊ�����d�������邭�炢�Ŏ�藧�Ăĕ������͖��������B
���コ��Ɂu�҂������������ł��B��ƌ��߂�����ɂ͑������������̂Łv�Ƙb���A
�s�����̐l�ɂ�
�u���̎��̏ؖ������A�ʐ^�ɎB�点�Ă��������B�ꐶ�Ɉ��̂��Ƃł��傤����v
�u���̃��N�`�������ŁA�s�����̐E�������A��ς������ł��傤�v
�E������͓��������ނ���Ȃ���
�@�@----�u����͂���͑�ςł����B���ꂩ�����ς������܂��v
����ȉ�b�����ċA����B������ӂ������ɂ����l���Ɖ�Ȃ���v���B
�Q�R���B�ߑO���͑����B�ڎ킵�����ƂłȂ������퉻�o�C�A�X�������A�u����Ŝ��Ȃ��ȁv�Ȃǂƍ����Ȃ��M���Ă��܂����̂��s�v�c���B
�ߌ㐨���Â��ăJ�b�g�ɏo���������B�v���Ԃ�Ȃ̂ŁA���̂����ς芴���y���݂Ȃ���A���r���A���X�i�{�y���X�j���ˑR���ɔ�яo���Ă����B�v�킸瀂������ɂȂ���---�B�O�[�[���ƃu���[�L�ށB�����ĎԂ��~�ߋ��鋰��O�ɏo����A�����悩�����B瀂��Ă��Ȃ������B
���X�́H���[�̉Ƃ̒�ł���낿���҂��҂���ђ��˂Ă���ł͂Ȃ����B
�����������ɃJ�����������Ă��Ȃ��A�c�O�B
���̃��X�u����݁v����ɗ��Ă���Ȃ����ȁB�i����ɖ��O��t���Ă���j
�@���R�̕�炵600 2021.6.24�@
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �@���փh�A�̌��܂ꎖ��
�@���փh�A�̌��܂ꎖ��
�F�l�����@���A�Â�����̒m�荇��������������B�~�J���肵�������ŁA���Â���߂Ȃ���̒��H�����������C�Ȃ��B���F�l�̘b�ɂȂ�A�u�������Ƃ��Ă߂����ɋN���Ȃ����ǁA�������Ƃ͂����A������ˑR�ɂ���Ă����ˁv�u�{�����B��l�Ƃ����������N��Ȃ���A�C��t���悤�v�u�������ˁv�B
�O�o�̗\��̂��钩�������B���_�͈ꑫ��ɎԂ��o���ɍs���A���͏����x��Č��ւ̃h�A�Ɍ��������悤�Ƃ��Ă������̎��B�u�s�`�b�v�Ə���
�����������B�����������̂��悭�����ł��Ȃ��B���݂����Ă݂�ƁA���փh�A�̌����́A��̂����̈�ɐ܂ꂽ�����l�܂���-----�h�������܂܂ƌ���������----�ɂ������������������Ȃ��B����Ăē���
���܂������Ȃ��B
�Ƃ�������̌����̓��b�N����Ă�����̂́A���̌����ɂ͔��[�Ȍ��̐���ۂ��l�܂��Ă���A�Ƃ������Ƃ��悤�₭�[���ł����B�s�K���̍K���������B�����A�L�[���ă��b�N���Ă��鎞�ɐ܂�Ă�����A�ǂ�����Ă����ւ��J���邱�Ƃ͕s�\�������̂�����B���̏ꍇ�͂܂�������������ɒ��s�������B
��肠�����Ƃ��̂��̂́A���b�N����Ă���̂ŁA���̂܂܊O�o�������A�A���܂ʼn������@��T��ׂ��A�Ԃ̂Ȃ��ō�����炷�A�ƌ����Ă����n�l�Ԃ̃��^�V����̈Ă��o���邩�ǂ����B
1�j�c�������̔����ɐڒ��܂�t���A�����̒��ɕ����߂�ꂽ���ɂ����t���Ĉꏏ�Ɉ����o���B
�@�@�i�����͂Ƃ��Ă����G�ŁA�w�^����ƒ��ɉ�������łǂ����悤���Ȃ����ʂɂȂ肻���j
�Q�j���₳����ĂԁB
�@�@�i����̓G���W�j�A�̃v���C�h�������Ȃ��B�C������Ƃ����y���݂��ǂ����đ��l�ɓn���悤���B�j
�R�j�����Œ��ׂďC������B���ꂪ��Ԉ��オ��B����ł������B
���͒��ڂ̐ӔC�҂ł͂Ȃ��̂ŁA�C�y�Ȃ��̂��B�u�����������������A���Ԃ������Ղ肠�邱�̎����ɋN���ėǂ���������Ȃ��B�����ƕ�炵�̍ו��ɐ_�o�����点
��Ƃ����_�l�̐e�S��A�Ȃǂƒ��X������B�i�_�l�͌����ł͂��邪�A�����Đe�ł͂Ȃ��Ǝv���j
�܂��l�b�g�Œ��ׂ�B�����������̂ɂ͂��܂��܂ȃP�[�X�ƌ��������邱�Ƃ����������B���������̑�胁�[�J�[��HP�����Ă݂�ƁA
����ނ̌��V�X�e�������݂���悤���B���{�̉Ƃ̐�������������ƌ����Ă��������B
���ɉ䂪�Ƃ̌��͌��z���[�J�[�p�̓����炵���B�����[�J�[�́u�{���Ȃ炻�̌��z���[�J�[��ʂ��Ė₢���킹���K�v�ł����A---������ł��傤����Q�l�ɂȂ�g�o�����Љ�܂��傤�v�ƗՋ@���ς̓������Ԃ��Ă����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����܂ŕ��n�l�Ԃ����ɗ������B�j
���_�A�w�͂���ЂƁBHP�����Ă����ƕ��@��T��B��\�I�ȏ��O�V�X�e���̂̕�����@�ɂ��Ċw�Ԃׂ��A�摜�Ɠ���Ŋ�{�I�m�����Ƃ���œ�����ꂽ�B���Ƃ͎��H����̂݁B
��������̒��A�܂��T���^�[���������J�����B
 |
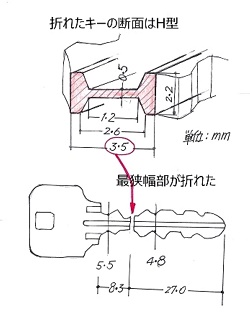 |
H�^�|�ƌ����̂́A���̌`���獶�E�㉺�ւ̑ϐ��������B
�����ǂ��ł�������������������6.5�~���Ƃ����̂͂����ɂ���サ��������B���Ɏォ�����킯���B
�ォ�����A�ƌ����Ă�20�N�߂��g�������Ă��������A������������g�����̂��B
�����ƌv�Z���Ă݂���Ȃ��7�炩��8���Əo���B
����ł͋�����J���d�Ȃ��Đ܂��̂�������O���B |
|
�����J����Ƃ������z�͖��������B�Ȃ�قǂ��̎肪�������B |
 �@ �@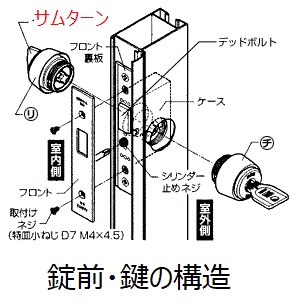
�@�T���^�[�����O��āA����ŕ���p�̃l�W���\�ʂɌ�����悤�ɂȂ����B
 �@�@ �@�@
����Ƃ���܂ł���Ă݂悤�B�O����O����l�W�����ׂĊO���A�V�����_�[�𗇂ɂ����B�r������C�^�o�l�����O�������ĕ��G�������炵���i�����͗ǂ������ł��Ȃ��j�B�����ԂقǑϐU�����͕K�v�Ȃ��̂��A�o�l�e���͋����Ȃ����������Ƃ̂��ƁB�Â��ɐÂ��ɁA�אS�̒��ӂ������ĕ������Ă����B�i�������߂Ȃ�v���̎�ɔC���悤�A�ƍl�������ǂ����j
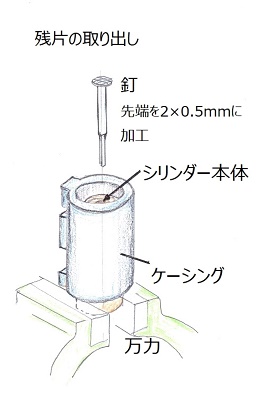 |
�@�@ �@
�@
�@
�@ �@ �@ |
�����͗��������āB
���̓����Ă���P�[�V���O�͂ŋ���Ŏ~�߁A�ォ��ׂ����H�����B���A�����ɉB��Ă���L�[�Ɍ����ď������ł�����ł����B
��������ق�̏����A�Q�~���قnj��̒f�Ђ������Ă����Ƃ�������������s���`�Ŏ��o�����B |
�@�͂��ߍl�����u�ڒ��܃v�����v�͂ƂĂ��������ƕ��������B
�@�����ɂ͏����ȒI�̂悤�Ȏd�肪����B
�@�L�[�����������_�ł�������H�����ގd�g�݂ɂȂ����Ă���B
�@���ꉟ������A�v���̎����Ȃ��Ɖ����ł��Ȃ�����
�@�͂����B |
�ߌ�̔����ƌߑO���̂Q���Ԃ��g���āA�悤�₭������������̌������B�v���ɗ��ނƔ�p��������B����莩���ʼn��������Ƃ����������邱�Ƃ��ł��Ȃ��������낤�B�v�Ă����炵�����̖�́A�����Ɩ��̒��Ńl�W���Ă������낤�ȁA���_�́B
���J���́A���̓��Ɂu�ߐ{���X�e�[�L�ƃ��C���̓��[�[�����C���̔��v��p�ӂ��悤�B���C���͂��łɗ₦�Ă���B
���������I���āB
���V�X�e���͂P�O�N����P�T�N�ŋ�������Ȃ邱�Ƃ������B
�����g���Ă���L�[�́A�P�O�N���炢�ŗi������J�j���Ă����̂ŁA�����ړr�ɐV������蒼���ق��������B
���ւ̃L�[����ւ����A����̏ꍇ�ɔ����āA�X�y�A�L�[������ꏊ�ɉB���Ă������B
�������Ԃ̃L�[�́A�Ԃ̊O���ɋ��͎��ł��g���Ē���t���ĂĒu���ƈ��S�B�g�����N���J����̂ɁA�Ȃ�ׂ��Ԃ̓������瑀�삵�悤�B����Ȃ��Ƃ�b���������B |
�@�@ ���R�̕�炵599
2021.6.19�@
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@�@�V�s���ƒ|�̏H
���B�X���̏h�w�Ƃ��ĉh�����̂��A�Ȗ،��k���̓ߐ{������B���̂͂���ɂ���̂��̖��̒n�u�V�s���v�B�i�䂬�傤��Ȃ��j���̖��O�́A����ɂ���V�s���̗��̏Z�E���Q�w�ɖK�ꂽ���ƂɗR�����Ă���B
���̒n�ɂ́u��������Ɏ��@19�㑸����l�i�V�s��l�j��������K�ꂽ�܂�A���̐��̘V����O���Ő����������v�Ƃ����@����̓`�����c���Ă���B
��O���̎��ɂ͑a���b�����A���̘b�͔\�y��w�Ȃ̑�ނɎg���Ă��ĕ����l�̊Ԃł͒m���Ă���悤���B�w�Ȃ́u�V�s���v�͐��s�̉r�̂��e�[�}�ɂ��Ă���炵���B
�@�@�E���ׂ̂ɐ�������T�����������ƂĂ��������ǂ܂��@�@�@�@���s�@(�w�V�Í��W�A�R�ƏW�x
�@�@�@
��O�̓��������₩�ȏ��쉈���ɕ����B�Q�{�̖������ɗh��Ă���̂��ڂɗ��܂�B���̖��͉���ɂ��킽���ĐA���p����Ă��Ă��邪�A�ŋ߂̌������Ă̂��������݂��������B���̖��A�����Ă���B�Ԃ̎�����
���Ƃɖ��̐V��̔��Ƃ̃R���g���X�g���������ꏊ���B
�Ȃɂ��A�����͌��\�̂��돼���m�Ԃ��K��āw���̍ד��x�ɋL�^���c�������Ƃ��琢�ɒm����悤�ɂȂ����B
�@�@�@�w���̍ד��x�i�V�s���@���\2�N4��20���j
�k���A�����Ȃ���T�̖��́A�b��̗��ɂ���āA�c�̔ȂɎc��B�����̌S��˕��^�́A�u�����݂���v�ȂǁA�܂���ɂ̋��Е������ӂ��A���Â��̂قǂɂ�Ǝv�Ђ����A���������̂����ɂ�������莘��
�l
�@�@�@�E�c�ꖇ�A�ė����������
���s�́u�����v�A�m�Ԃ́u�c���ꖇ�A����قǁv�̎��̗���������Ŗ�������B���s�ɌX�|���Ă����m�Ԃ̐S�͂������肩�B���Ŕm�ԂƑ]�ǂ͌Ó���k�Ɏ�蔒�͂̌Êւ�ڎw���Ă���B
����̂̂т₩�ȒJ�𗬂��ޗǐ�̉E�݁A�k���Ɉʒu���Ă���V�s���̔w�ɂ́A�Џ@�|�̗т��L�����Ă���B�|�H�̗��͋߂��B�����̒|�͂悤�₭���F���Ȃ�n�߂��悤���B�|�̏H���B
 �@���N���ԏҊ����炢���@ �@���N���ԏҊ����炢���@
���ʼnԏҊ������͂��߂Ă����P�T�N�ɂ��Ȃ�̂ɁA���܂��Ɍ@��Ԃ��Ĕ엿������A�y��⿂��ĎG���i��ɃJ���X�r�V���N�j����菜�����Ƃ��ł��Ă��Ȃ��B�����ɂ��Ă��Ă��Ă��A�G�߂̏���ɗ��V�ȉԏҊ����Ԃ�t���Ă��ꂽ�B
���̋G�߂ɍ炫�ւ邳�܂��܂ȉԂ͊m���ɔ������B�������A�N����d�˂Ă����������A���̉ԏҊ��̑u�₩�Ŏ��Ȏ咣�̏��Ȃ��Ɏ䂩���悤�ɂȂ����B
�R�쑐�̐Â��ȑ��݊����g�̓��ɟ��ݍ���ł���ɂ́A���Ԃ̐ςݏd�˂��K�v�Ȃ̂��낤���B
�@�@�@
�@�@�@���R�̕�炵598 2021.6.13�@
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 ���킢���ȂȂ̎q��
���킢���ȂȂ̎q��
20�N�߂��̌o�����番���������Ƃ����A�V�W���E�J���͂P��̕�����9����11�̗����Y�ނ��Ƃ������B���N�̂��̑�����w������e���́A�V�Ƃ�⏭�Ȃ߂̗����Y�悤���B
�䏊���猩����ꏊ�ɂ��鑃���ɐe�����o���肵�A�u�s���s���v���V�W���E�J���̐��̏����Ȑ����������Ă��悤�ɂȂ����B
�`��������ˁA�������˂Ɠ�l�́i�������j�ӌ�����v���A������������J���Ă݂���A�V�̉��F�������B��Ă����B
���̂������͑傫���ĉ��F���B�u�{�����F���v�͖̂��n�҂̗Ⴆ�����A���̏ꍇ�͐e�̎x���������Ɛ����Ă����Ȃ��Ƃ����Ӗ����낤�B���F���̂͐e���Ɍ��̈ʒu���A�s�[�����邽�߁B���̐��𐔂���̂ɂ��̉��F�����������ڗ����Đ����₷���B


���̂�����
�X�Y���������点���Ă���A����������ŁB
���܂ꂽ�Ă̐��́A�S�g�����F�����ƕ����܂܂̖ڂ��̂��̂ŁA�Ђ�����e�����a����a��҂��Ă���B�ڂ������̂͛z����T�����炢�ŁA���̌㎟��ɉH�������Ă���B
���̎��_�ő������J����Ɛ������͂����Ɗۂ܂��Ėڂ���u���ӂ�v������B
�Ƃ��낪���̉摜�ɂ���悤�ɂP�O�����o�ƁA�g�߂ɔ����Ă������z�G�������ƌ�������悤�ɂȂ�B��������܂イ��Ԃ����A��H����
���̒��̌E�݂���O�ɔ�яo���Ă��āA�g�̂��傫���悤���B
���ƂP�T�Ԃ�����V�H�̐������͑������낤�B
�Ƃ��낪�A���́u�O�ɔ�яo���Ă��Đg�̂��傫�����v���A�������̂��Ə����ȃV�W���E�J���l���𑗂�邩�ƌ��������ł��Ȃ��B
�p�g���[�����Ă���̂��낤�B������ɓV�G�̃n�V�u�g�K���X�������Ă��āA���̑��������������܂��Ƒ҂����˂Ă���B����s�����đ������Ď@���Ēʂ�߂��A�ق��̃J���X�Ə��������Ă���悤���B�����ɐg�̂̑傫�����P������яo������ǂ����B�����Ƃ����Ԃɉa�H�ɂȂ��Ă��܂��B����̏����Ȃ���A�������A���������A�Z��ɉ�����Ĕ�яo���Ă���----����������2���␗�U�����V���̕����������т�m�����������Ƃ�����B������̔��̏��N���邾�낤�B
�݂Ȍ��C�ŗ����ĂƂ����̂͊ȒP�����A���ҕK�ł̐��E���҂��Ă���B
�V�W���E�J���́A�ق�̐��L���l����꒣��Ƃ��Ă���B���ώ����͂Q�N�܂œ͂��Ȃ��B���ʂ͏t�ɂQ��������s���A������15�H�ȏ�̐�����ĂĂ���B�V�G�̔�Q�ɑ����A���̂Ŏ��S����A�����������Ƃ�
�l�����Ă���̂��Ȃ�ׂ������̐�����Ă悤�Ƃ��Ă���悤���B�������A�����꒣��Ɍ̂̐�����������̂���肾�낤�B�ǂ����P��ڂQ��ڂ̕�������肭�����Ȃ������N�����́A�R��ڂ̕������s���Ă���悤���B���܂܂łň�Ԓx�������̂́A�\���N�O�̂W��20���̑������������B�����̑I�������Ă���̂�������Ȃ��B
���邢�͏������Љ�ۏ�V�X�e�����B
�ǂ���ɂ���A��Ŕ�щ���Ă���̂́A����20�N�߂��̊Ԃɒ�̑����śz�����������̎q�����B
�@�y�݂�Ȃ݂�ȁA�����̂������Ȃ̂ł��B�z
�ώ@�𑱂��Ă��邤���Ɏ���ɃV�W���E�J���͖����ŃR�~���j�P�[�V����������Ă��邱�Ƃ��������Ă����B�����Ȃ�ɕ��͂��Ă݂��B
|
�u�W���[�W���[�v�@�@�ւ����邼�B�叫�������P�������̐��Ƃ�����A�Y����Ȃ��B |
|
�u�s�[�c�s�v�@�@�@�@��Ȃ����@�x���x��@�����ɋ߂Â��Ƃ��̐��ŋ����Ă���B |
�u�a�a�a�a�v�@�@�@�@�݂�ȏW�܂�@
�J���ށi���}�K���A�R�K���A�q�K�������j�͂��ꂼ��̖����ɈႢ��������̂́A�������g���Ŗ��Ă���炵���A�݂��ɈӖ��𗝉�����炵���B���̐����ƏW�܂��Ă���B |
 6��8���@���\���炪��
6��8���@���\���炪��
�}���ł��鎞�ɃG�v�����̕\�������炪�邱�Ƃ�����B�u�E���v�ƃ}�W�b�N�ŏ������ꂽ�B�悭������悤�ɂȂ����B
�Ƃ��낪�A�p�W���}�̃Y�{���̑O���Ɂu�}�G�v�Ə������B������茩�����Ƃ���͌�둤�������B�O�����Ɣ]���ϊ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
�����č����A�u�������q����A�G�v������������v�B�E���Ə����Ă��Ă��A���̂܂ܒ��Ă��܂����悤���B

���R�̕�炵597
2021.6.9�@
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
 ���傤�E�݁@6��2��
���傤�E�݁@6��2��
�U���͎R���̎��̎�肢�ꎞ�B�R���̖͉s��
�ΐ��̃g�Q�������Ă���̂Ŏ��n���̂��̂��|����Ƃ��B�����ŁA�唻�̎P��̉��ɍL������𗧂Ă��B
�Ă���܂Ŕw���͂��Ȃ��̂ŁA�����͑��_�ɗ��ނ��Ƃɂ���B
�Ў���g���Ď}��}���Ȃ���A��������̎�Ńp�`�p�`�Ɛ��Ă����B�}�̂͂˕Ԃ肪���킢�B���ʂ͉����̗e��Ɏ邪�A���N�̓I���[�u���n�̂܂ˎ������Ă݂���A���ꂪ�吳���B�����A�ɂ��Ȃ��A
�P�Ŏ���ƁA�v��ʏ����ɓ�l�łɂ�܂�B
�������Đ��ɎN���Ă������ƂP���ԁB��������������䥂łĂ����B���X�w��ł܂�ł݂ēK���ȏ_�炩���ɂȂ�������o���A���ɒЂ���B����ɂ����A���C����ėⓀ����B����ň�N���̎R������߂�̍ޗ����������B
 |

�ق�̏����W�߂�̂ɂ��A������J�����B
�@ |
 �@6���R�����B
�@�V�K�\�� �@6���R�����B
�@�V�K�\��
�T���U���ɍs��ꂽ���s�̈��ڂ̃��N�`���ڎ�\��̃V�X�e���\�z�ɁA�������W�܂����炵���B�撅���Ŏ���A������d�b�ƃl�b�g���ɗ��p���āB���̌��ʂ͍l����܂ł������l�b�g���p�҂̏����ɏI������B
���������A������Ȃ��֎q���A����҂R�l�ɑ��킹��ȂǁA�����Ȃ��Ƃ��낤�B���I���A�N��A�������ȂǍl��������@�͂��������낤�ɁA�s���͂����܂ł����������������č���҂̕s�����ĂыN�����Ă��܂����悤���B
�Ώێ҂���u���ǂ��Ŏ����v�����A�N��A��b��������ƌ������D��x���l�����Ē��I�ł��Ȃ������̂��B
���邢�́A�N��ɗ\������蓖�Ă�Εs�������������Ȃ����̂ł͂Ȃ����B���S���������A�O�i�K���������Ƃ���A����͐ڎ�҂ɂ��[����������������Ȃ��B
�U���R���@�V���Ȏd�g�݂̂��Ɛڎ�\�n�܂����̂ŁA���߉�ɂ�����̗F�l�O�l���̗\����s�����B
�N��̊��蓖�ĂŁA������75�Έȏ�̊�]�҂��t����B���������i�܂��͋ߏ��̈�Ë@�ցj��I�Ԃ��A���x��̏W�c�ڎ��I�Ԃ��B������X�����傤�ǂɊJ�n���ꂽ�\��V�X�e���Ƀf�[�^�𓊂�����Ă����B���v�w�̕��͊�]�ʂ��
�@�ւƓ�����������S�������A������l�̕��́A�f�[�^�O��ڂ̓��͂ɂȂ�̂ŁA���Ԃ���₸���]�������x�����������Ȃ������B�����A�c�O�������B���̎��̂��̏u���̔��f�~�X�����̌��ʂɌ��т��Ă��܂����B�\����Ȃ��B
�̊��I�ɂ́A����̃l�b�g�Q���҂͑O��̂R�{���炢�̂悤�ȋC�������B�O��̌��ʂ����Ă݂Ȋw�K�����̂��낤�B�e���F�l�W�߂ăA�N�Z�X���Ă���悤�Ɏv�����B
���̂P�T�Ԃ�70�Έȏ�A65�Έȏ�Ǝ�t�������Ă������A��Ë@�֑��͂��炩���ߒ���ɂR��ނ̘g������Ă���̂��ǂ���������Ȃ��B
������������
����Ȍ�̊�]�҂͂��ׂāA�W�c�ڎ�Ɏw�肳���̂�������Ȃ��B��Ԓx���W�c�ڎ�̓��ɓ������Ă��܂�����A�V�����ɂ悤�₭�Ԃɂ������炢���B
����������---�d�b�͑S���ƌ����Ă����قǒʂ��Ȃ��̂ɁA�l�b�g���p���ɂȂ�����҂ւ̃T�|�[�g�����Ȃ��B���������N���̎菕�����Ȃ��Ɨ\��������Ȃ��Ƃ����̂́A�V�X�e�����̂��̂�
�Ȃ�炩�̕s��������̂ł͂Ȃ����B
�i�\���s�́A�S�C�̋ʂ�a�����ēG�ɓˌ����Ă����C���������B�܂�Ń��V�A�����[���b�g�B�ǂ��ƃA�h���i�������o��-----���������Ζʔ��������B��������������̂ɁB�j
�l�������͂Ȃ����A�قƂ�ǂ̍����ɐڎ킷��̂́A��ɐ�������邾�낤���A�s��Ȑl�̎����Ƃ������邾�낤�B�������Ĕ�镛�����ƕ���p�ƁA�Ȃ����X�N��V���ɂ������---��ƌ��f���邵���Ȃ��B
���������l������B
����҂̖������A�Ⴂ�l�����̖���厖�ɂ��Ȃ��ƁA���{���łт邩������Ȃ�
�B���邢�͍���҂��d���镶�������グ�Ȃ��ƁA��҂����ĔN����d�˂邱�Ƃ��ł��Ȃ���������Ȃ��B�ȂǂƂ��������Ƃ��B
 |
����͂U���P���̏W�c�ڎ���̓����B
�^��w�̑̈�ق��g�p�����̂ŁA���Ă̂Ƃ��肷�����炩��B
���͂ɂ̓��}�{�E�V�̖̉Ԃ��炢�Ă��ĕ������������Ă����B��҂ƊŌ�t�����ꂼ��R�l���āA�T�ɂ͋~�}�Ԃ��ҋ@���Ă���B���ɂȂ�Ȃ�����
�Ɉ��S���B
���������ς�������ƂɎ�������l�A�����������҂͂����Ă����������ƌĂׂ��Ë@�ւ������Ȃ��B
��l�Ƃ���Ô���g��Ȃ��D�Ǎ����ł͂Ȃ��H
�Ȃ̂ɗD������邱�ƂȂǂ܂��Ȃ��B
�Ƃ��o�ċA���܂�40������������Ȃ������B
�@ |
���R�̕�炵596
2021.6.4�@
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �������Ă݂��B�@�A�����ǂ̂��炢�D���Ȃ̂��B
�������Ă݂��B�@�A�����ǂ̂��炢�D���Ȃ̂��B
�J�^�N���͍l�����B���̋����ꏊ��100�{�߂��̉Ԃ��炩���ĂP�O�N�ȏ�ɂȂ�B���낻��꒣����ڂ��Ȃ��ƁA���̂܂܂ł͖��ɂȂ��Ă��܂��B���U���ďn�������U���
���Ă݂Ă��A���������T�O�Z���`����������Ȃ��B�ǂ��������֍s�������B
�A���Ɏ�`���Ă��炨���B�v���[���g�ƌĂׂΕ������͗ǂ����A�����́u���܂����Ƃ���v���B
�@
 �@ �@ �@�@�@�����Ƃ����Ԃɋa���W�܂��Ă����@�@�@�@�@�@�@�G���C�I�\�[���Ɋ��ݕt���ĉ^�ڂ��Ƃ��Ă���a���� �@�@�@�����Ƃ����Ԃɋa���W�܂��Ă����@�@�@�@�@�@�@�G���C�I�\�[���Ɋ��ݕt���ĉ^�ڂ��Ƃ��Ă���a����
�J�^�N�����炢����ɑ傫�Ȏ�܂��ł��Ă����B���ɗh���Ăӂ�ӂ炵�Ă���B��܂������Ă݂�ƁA�\�z�ʂ�햍�i���タ��E�G���C�I�\�[��
Elaiosome)�ƌĂ�镨���������t���Ă����B ��̐�ɂ��Ă���c�u�����ꂾ�B
�A���ɂ͑������͓I�ȐH���Ȃ̂��낤�B�킪�e���Ēn�ʂɗ�����̂�҂����ˁA�Ԍs���悶�o���Ď�܂ɓ��荞��ł���a�������B
�G���C�I�\�[���͓�������������܂މh�{�ɕx�����B����͂��܂����B�A���ւ̃v���[���g���B�A���̔ɐB���̂ЂƂ��B
�a�͂��̉h�{���_�̃G���C�I�\�[������D���B�킪�e���Ēn�ʂɗ�����ƁA�ӂ�ӂ�ƗU�����ꂽ�a�����́A���́u��{�G���C�I�\�[���Z�b�g�v�𑃂Ɏ����A��A�G���C�I�\�[����H�ׁA�c������͑��̊O�ɓ����̂Ă�A�ƌ����Ă��A���͎Љ�I�����Ȃ̂ł����炭����V�X�e���ɑ����Ă��̉h�{�L�x�ȃG���C�I�\�[���͗��p�����̂��낤�B
�����A�����H�ׂ�@����邩�ǂ����^��ł͂��邪�B
�A���̂��̏K���𗘗p����A�����u�A���U�z�A���v�ƌĂсA�J�^�N�����̂ق��ɃP�}�����A�X�~�����A�I�h���R�\�E���Ȃǂ̍L�����ތQ�ɘj���Ă���B
�Ȃ�قǁA����ł��I��Őm�`��������荇���ł���̂́B�A���𖡕��ɂ���Ƃ́A�G��������́B
�i���ʐ^�j�@�����̗e��ɃJ�^�N���̎�܂�����A�W�߂Ă������B
�u�����͉̂Ƃ̒��́A���i�A���Ȃǐ���Ȃ��ꏊ�B�䂪�Ƃ͍��C�����f�M�̉ƂȂ̂ŁA�A�������荞�ނ��Ƃ͂܂��l�����Ȃ��B�������A���������R�O�����o���Ȃ������ɁA�a�������ǂ����炩����Ă��āA����^�яo�����Ƃ��Ă���B���������ǂ�����B�����ĉƂ̒��ɂ���J�^�N���̎�ɂ��Ă���G���C�I�\�[���̓�����
�K���X�z���ɂǂ�����Ċ��m�����̂��B���d�s�v�c�B
�i�E�ʐ^�j�Ⴆ���������A�D�_��������蔲���ĉƂɓ��荞�݁A�����̂�w�ɕ����Ă��ē����悤�Ƃ�����A�ו����ז��Œʂ蔲�����Ȃ��B����Ɠ������B�A���͐g�̂Ɠ������炢�̎�������Ă͑����瓦�����Ȃ�
�B���낤��B�A���̔������錄�͂������炵�� ���A�����o�錄�͖��������炵���B���߉�ȃ��^�V�A���ɋd���ďW�ߊO�ɏo���Ă�������ǁB
�@.gif) �@�V�W���E�J���̈��̑� �@�V�W���E�J���̈��̑�
�@ �@ �@
�Y�̃V�W���E�J�����A�A�ꍇ���̎��ɐ����v���[���g���Ă����B���̑����͑䏊�̐^���ʂɂ���A�������Ȃ���ώ@�ł���B���̂Ƃ���A�Y�����Ȃ̂��������Ȃ̂��͊m�F�ł��Ȃ��B�������J����Ƒ����������ꍇ������̂ŁA���ӂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
�����A����ȃV�[�������������B�i�K���X�z���A���w�Y�[��2�T�{���炢�j�܂��A�Y����������ċ߂��Ɏ~�܂�A���͂ɓG�����Ȃ����m�F�����Ă����B���̊ԃI�i�J�y�R�y�R�̎��͑����̓�����������o���čÑ����Ă���B�����ނ�ɗY�͎��̏��ɍs���ĐH�����v���[���g�����B���̎������̗͑͂��g���̂Ń^���p�N����K�v�Ƃ��Ă���B�����Ă���̂͐��ŁA�����Ėт��E��琶���Ă���Œ��������Ă���킯�ł͂Ȃ��B
�@*�i�w�͂�������ނ��x�̍�҂��S���Ȃ����B�A�����J�̊G�{��ƁA�G���b�N�E�J�[�������N�X�P�j
���R�̕�炵595 2021.5.30�@
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �����̉Ԃ��炢���@�@�G�S�m�L�̌Ö��@�G�S�m�L��
�����̉Ԃ��炢���@�@�G�S�m�L�̌Ö��@�G�S�m�L��
����Ԃ�D���ďt�̒�̐��������A�ĉԒd�ւ̏����ɖZ�������Ă������B���̏�ɔ����Ԃ��Q��炢�Ă���̂ɂ���ƋC�Â����B�V�Ɍ������ĐL�т��́A�}��ʂɔ����Ԃ��������ɕt����l�q�́A���Ă̗т��ʂ�ɂӂ��킵���A���N���̉Ԃɏo�����Ɛ���₩�ȋC�����ɂȂ�B�Ԃ̌�ɑȉ~��̉ʎ�����������t���A�Ԃ牺����l�q���܂����炵���y�������̂��B
�@�@�@ �@ �@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@
�ʎ��͖쒹�̃��}�K���̑�D���B�ʎ��́u���������v�����邱�Ƃ��炦���������������G�S�m�L�ƕω������Ƃ����B��ϕ�����Ղ��ω����B
�����p�Ɏ����킸�A�ʔ�͗L�łȃT�|�j�����܂ށB���̃G�S�T�|�j���ɂ͋��Ő������邱�Ƃ���A�ʎ�������Ԃ��Đ�ɗ����A�����Ă��鋛���Ɏg���Ă����ƕ����Ă���B
�܂��E�ʊ�����p�����邱�Ƃ���A�Ⴂ�ʔ�����Ƃ��ė��p�����炵���B�T�C�J�`�Ɏ��Ă���B
�w���t�W�x�ɂ�
------�����̉ԍ炯�鐷��ɂ͂����悵���̍Ȃ̎q�ƒ��[�ɏ݂ݏ܂��������Q��------�i���́j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�唺�Ǝ��@��18-4106
�z�����̍��i�Ƃ��ĕ��C�����唺�Ǝ��́A���̉̂̍��R�O�ΑO�ォ�B�Ñ�̂R�O�͂��łɒ��N�̎����A���f�͂��\����������N��낤�B
����͕����̎j�����������i�����傤�����̂����Ёj���V�s���w�i������߁A���y�X�œ��������j�ɐS��D���āA�A��Y�����Ȃ��Ȃ�������ɂ��Ă���̂�@�����̂Ȃ̂��B
�����^�ʖڂŎ����A�}���ȉƎ��A�����܋��|�ǂȂ̂��A�ׂ����L�^����鐫���͕ς��悤���Ȃ��B�����̍s���𐳂����Ƃ��Ă���A���̉̂����L�^�ɂƂǂ߂Ă���̂������B
�u�_��̂��납�畃��эȂ�q���݂�Ή����Ă��܂�Ȃ�----�����̉Ԃ̐���̎����ɁA���Ƃ��������v���ȂƎq���ƁA���ɗ[�ɏ�����A�܂��Q���Č�荇�����肵�����̂���---�����V�n�̐_�̂������ŁA���̏t�̉Ԃ̂悤�ɉh����Ƃ������邾�낤---���̎������Ă���̂ł��A���B�v��
�����ɉr��������B
����́A�u�a�߂鎞���A���₩�Ȃ鎞���A�x�߂鎞���A�n���������A�ȂƂ��Ĉ����A�h���A�����ގ��𐾂��܂����H�v���̐����̌��t�́A�Ñ��i�o�[�W�����̂悤���B
�ƒ������������̉~���ȗl�q���v���o�����悤�Ƃ��Ă��邪�A�ǂ����ȁB�͂����Đ������邱�Ƃ��ł����̂��B���l�̈ӌ��ȂǕ����Ȃ��̂��A�Ñ�������j�Ȃ�B���̕����Ȃ�j���������������S�����ǂ����B�Ђ�������������d�ː��`��������ƁA�������Ĕ����������Ȃ�̂��l��ł͂Ȃ����B
�����ɂ͔\�͂�����B�u�ւ��Ȃ���v���鎄�͂����v���̂ł��B �i��----���ݐi�s�`���H�j


���̃u���u���̌������B [���ҒŐA��]�@�ƌĂт����B
���}�K����������
�@
���R�̕�炵594
2021.5.26�@
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 ���Ȃ�ǂ�قǂ悩�����ł��傤
���Ȃ�ǂ�قǂ悩�����ł��傤
�@�@�@�@�@�y�� Lemon���@�쎍�E��ȁ@�ĒÌ��t
�v�������Ȃ����Ƃ��N�������A�����Ɏ��s���ė������ގ��A���Ԃ��̂��Ȃ��o�������I��ɂȂ������A���́�Lemon��̂������̃t���[�Y�����Ƃɂ��Ă���B
���Ȃ�---�m���ɂ����Ȃ̂��B���ꂪ���ł�������A�Ǝv�����Ƃ�����B�����������͌����̒��ɂ���̂݁B
���ƌ������������킹�A�ォ��I�I�f�}���̎}�����邮��ƉƁA���̂��듇���łĂ��Ȃ����B
�������邱�ƂŌ����Ă�����̂�����ɈႢ�Ȃ��B���Ȃ͂��Ă�����͂��Ȃ��ł������B
��������ƉJ���~��~�܂Ȃ��B

�@��ʂł͂Ȃ�����ǁA�I�I�f�}���̉Ԃт炪�U���Ă܂�Œn��̉Ԕ��B
���R�̕�炵593 2021.5.22�@
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �ǂ������炩�A�Ăъt�F���������N���Ă��Ȃ�����
�ǂ������炩�A�Ăъt�F���������N���Ă��Ȃ�����
�ߏ��Ɉ�l��炵�̂��N��肪�Z��ł���B�N��͂��łɎP���߂��悤���B���̒j���A�����炭�u�L�⌢���Ăъ�t�F�������v��g�̂�����o�����Ă���̂��낤�B�U�����鎔������nj����킸�A���̐l�̎p����������Ɛg���������Ă������Ă����A�������̂��܂�A�悾��𐂂炳�����B���ł���Ɛ��𗠕Ԃ��ăq�[�q�[���ł���B���[�h����������́A�����̗���͂ǂ����Ă���悤�Ɯ�R�Ƃ���ЂƁA�ꏏ�ɂȂ��Ċ�Ԑl�Ƃ��܂��܁B
�C�����̔L�����ē������B���ۏo���̖��̎p���ł��邮��Â��A���̖��͂ɂЂꕚ�������B�ǂ�������Ƃ��̐l�̉Ƃ̑O�ɍ��肱��ŁA�Ǝ傪�G���Ă����̂�҂��Ă��邱�Ƃ�����A�����������[���܂ł����ƁB
���V���A��ɂ����̂悤�ɌՔL������Ă���B10���ɂ͐^�����ȔL��----���Ă�����B�����̂��J���X�����ނ��Ǝv���Ă���邩����S����B�ł��[�����ƈÂ��ɕ���Ă��̍����p���ڗ����Ȃ���ł͂Ȃ��H�������A�L�ɂ̓q�G�����L�[�������āA�����̓꒣��łȂ��ꏊ��������ɂ́A���Ԃ�I�Ԃ̂��B�ߑO���ɗ���̂͌N�ɂƂ��ẴX�e�C�^�X�Ȃ̂��B
�ߌ㔒���L������Ă����B�Ă�ł��Ă�ł��m���炵�āA�L�p���`��������Ă���Ȃ��B���������ɂ͎O�т��ӂ�ӂ�������Ă���B�݂�Ȃ̂��ړ��Ă͖k���̊p�Ɍ@���Ă��鐶���݂��̂Ă錊�̂悤���B
�i�����h�v�l�ł͂Ȃ�����ǁA�u�̂Ă�ׂ����̂����̂ĂĂ��Ȃ�����A���L���H�ׂ���̂Ȃǂ߂����ɂȂ��v�j�B
���̂������܂��ė���L�����A���܂Ƀf�b�L�ɏオ���Ă��Ē��Q��������A�����璆���̂������肷�邪�A��{�G�点�Ă���Ȃ��B�߂����B�Ȃ���ł���A����ȂɍD���Ȃ̂ɁB�u�`�[�Y�グ�邩�炨���Łv�ƗU���Ă݂Ă������������Ă���Ȃ��B
�������ǂ̌��������ƌ����Ă��A����ȂɈ��z��U��܂��Ă���̂ɁB
��͂�u�Ăъt�F�������v������Ȃ��悤���A�������ǂ��Œ��B�ł���̂��낤���B�D���A�����ł͉����ł��Ȃ��s�v�c�ȉ��������݂���悤�ȋC������B
�ߌ�Q���B�J�͗l�̋L�����Ă���B�����������Â��ɖ��A���ԂɃV�W���E�J�������̉̂��̂��Ă���B�A�J�Q�����R�c�R�c����@���A�W���[�}���A�C���X���Ԃ�t���n�߂��B�q�o������������������p�͌����Ȃ��B�Â����B
 |
 |
���}�炫�A�N���}�`�X�E�����^�i�E���[�x���X�����ʏ��̑��ɗ��݂��Ă���B
�����猩��ƊO�̐��E���s���N�̊ۖ͗l�ɂȂ�B |
����I�_�}�L�@�����닗�������B�������肵�Đ��^�B�����B |
���R�̕�炵592 2021.5.18�@
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �x���A��������
�x���A��������
�������A���l�����������Ď���������Ă��邱�ƂƂ�����B���S�x��������̂�������Ă��̂��Ƃ��B
���ɏZ��ł��鑊�_�̗F�l���A���T�R���i���N�`���̏W�c�ڎ�ɐ\�����ނƂ����A�����������B
���s�͎s���̓w�͂������Ă���r�I�����A����5��23������ڎ킪�n�܂�B�K���ɂ����́A�������������̂�5���ɂ͗\������Ȃ��������A�w�肵��6��1���ɓ�l���̗\��ꂽ�B
���_�A�u�ނɐ\�����݂���肭�����悤�A�����A�h���@�C�X�����Ă����H�v�B
�����炠���鎖�Ԃ��l���āA���ꂱ��ׂ��������Ďd�グ���͂������A����ɋC�����ǂ���Ƃ��Ă����B
���l�����������ŁA�����������v�����������A���̍l���̋ɒv����ˁB������āB
�������\��ł������ƂŁA���˂��Ă��܂���������̕��ɐ\����Ȃ��B�N�����]���ɂȂ邵���Ȃ��������߂����B
�F��ɂ͑ウ���Ȃ����B���ꂾ��������Ȃ����A�\��ł��Ȃ������l�ɐ\����Ȃ��B
����ɂ��Ă��A���N�`���̐\�����݂̃V�X�e���ɕs�������邱�ƁI
����҂ɑ����ҏ�������点�Ăǂ�����I�@�l�b�g���g���Ȃ�����҂Ƃ́A���̃f�W�^���f�o�C�h���ǂ��l���邩�B
�����̔ԍ��Ŏd������B�n��Ŋ��蓖�Ă�B�N��ŕ�����B
����Ȃ��Ƃ��l�����Ȃ������̂��B---���ɉ���肩���ɁA�s�������B

����̍��Ɖ�Â̍����ɂ���哻���������Ɍ�����B�������Ⴊ�c���Ă���B
�W��1300���ɍ炭�~�l�U�N���E�����B�������������ꏊ�Ȃ̂ŁA�Ԃ݂͂Ȃ��Ȃ���č炭�B���͗₽���B
���R�̕�炵591 2021.5.15�@
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 ����܂̐V��
����܂̐V��

�u���珼�̂������ȉ���W�߁A�킽�����̓��b�������肽���v
�@�@�@�@�@�{�����@���W�w�t�ƏC���x���w�����_��x
�����́A���珼�̉��ʐ��i�N���\�v���[�X�j�ƕ\�����Ă���B
���t���́A�ς��Ǝ�̂Ђ�z�Ɍ������悤�Ȍ`�ɐV����L����B���̌`���������Ė��N���̎����ɓߐ{�̎R�ɓo���Ă��� �B
�����͓ߐ{�A�R�̖k�����A�W��1000��������B�܂�܂�Ƃ����h��������A���t���т��L�����Ă���B�Â����B�}�s�ȊR�ɐA�т���Ă̂��A�Ԕ��A�}�ł��Ȃǂ̎���������Ă��Ȃ��̂ō��ݍ����Ĉ炿�A����40�`50�N�̎��̊��̑��}�͂��łɌ͂�Ă��܂��Ă���̂��ɁX�����B
�Ȃ����̏ꏊ�ɗ��t���̗т������Ă���̂��B
����E���ɂ���ē��{�̎R�͍͂r�p�����B�X�т����̗�ɂ���Ȃ��B���͖؍ނB���邾���łȂ��A�J���ʂ����͐�A�Ђ��Ă͊C�ւ̗{���⋋�̖ړI�ŐA�т𐄏������B�i1957�N�A���L�ѐ��Y�͑����v��j
���炪�����Ď���ꂪ�ȒP�Ȑ������̑�\�ŁA�܂��������{�e�n�ɐA�т��ꂽ�B
���̂����Ō��݃X�M�ԕ��ǂ��������Ă���̂����ǁA�����͂��̕a��͒m���Ă��Ȃ������炵���B�u�����̏t���ׁv�ƌĂꂽ�悤�ɁA�ǒn�I�ȕa��Ɏ~�܂��Ă�����
�A���܂⍑���a�ɐ��肠�����Ă��܂����B
��c���e�ՁA���t���������A�����������Ƃ��������R�����茧�A�R�����A���쌧�A�k�C���Ȃǂɂ͗��t�����A�т��ꂽ�B�ߐ{�ɂ͂��̎����ɗ��t��
���A�т���A��錧�Ƃ̌����̔��a�R�n�ɂ͐����A�����Ă���B
�Ƃ��낪�A�O�ނ̗A�����i�݁A1970�N�ォ��n�܂����V�������z�p�@�̕ω��ɂ���č��Y�ނ͉��i��������A����ыƂ��Y�ƂƂ��Đ��藧������̂�����ɂȂ��Ă�����ƕ����Ă���B�v�̎��Ƃ̎R�тɂ́A�����̂Ă�ꂽ���т��L�����Ă���B
�u�X�͊C�̗��l�v�Ȃ̂ɁB
 �@�W���������Ȃ�ɂ�A���z���܂Ԃ����Ȃ�B�T�C�h�~���[��
���悯�^�I�����Ԃ牺���ăh���C�u�𑱂��Ă������̂��ƁB�������葋���J������A�����Ƃ����܂Ƀ^�I�������ōs���Ă��܂����A�V�}�b�^�B����ĂĎԂ����э~��A100���[�g�����ɗ����Ă���^�I���ڂ����đ����Ă�������30�b�B�i100����30�b�����������I�R���i�ő����Ă��܂����B�����ɂ��V�}�b�^������j
�i���₢��T�o�ǂ�ł͂����Ȃ��B30�b�ǂ��납�A�����Ƃ��������͂����j �@�W���������Ȃ�ɂ�A���z���܂Ԃ����Ȃ�B�T�C�h�~���[��
���悯�^�I�����Ԃ牺���ăh���C�u�𑱂��Ă������̂��ƁB�������葋���J������A�����Ƃ����܂Ƀ^�I�������ōs���Ă��܂����A�V�}�b�^�B����ĂĎԂ����э~��A100���[�g�����ɗ����Ă���^�I���ڂ����đ����Ă�������30�b�B�i100����30�b�����������I�R���i�ő����Ă��܂����B�����ɂ��V�}�b�^������j
�i���₢��T�o�ǂ�ł͂����Ȃ��B30�b�ǂ��납�A�����Ƃ��������͂����j
��q�����łɂ����A�Ԃ��肻���������B���}�h���������B�߂Â����ɋC�t���Ȃ��̂��A�^�I�������߂�ὂ߂��Ă���B
�@�@�E�����т��� �R���̔��� ��������� �Ȃ��Ȃ������ �ЂƂ肩���Q�ށ@ �`�{�l���C
�������ɔ��͒��������B�l�ԂƂԂ��肻���ɂȂ��ċ��������}�h���́u���܂����v�Ƃł����������̂��A�������Ŗ������A�}���ŗтɏ����Ă������B
�������܌��ɗ���Ƃ���ȂǁA�J���X���݂ɍD��S�������悤���B
 �t�����h�E �@�����͂P�O�Z���`�ق�
�t�����h�E �@�����͂P�O�Z���`�ق�
���̌̂͒������劔�Ɉ���Ă��邪�A�t�����h�E�͕��ʁA�Ԍs���Q�{����R�{�̂܂��₩�ȉԁB
�Ԍs�݂͂ȁA��쓌�������Ă���B�쒆�̈ʒu���班�������---��15�x���炢���B�t�̂��̋G�߂́A�����ɂ��ĂP�P�������炢�̑��z�������č炢�Ă���̂��s�v�c
���B������A�쑤��������Ă����ƒn�ʂɎ��F�̐����U����Ă���悤�Ɍ�����B
�t�̂��̎��������̏����Ȑ������B
���R�̕�炵590 2021.5.9�@
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 ���̂ڂ�G�Ђ݂����Ȃ͉̂��H�@�@�@�@�@�@�z�I�m�L�@���N�����ȃ��N������
���̂ڂ�G�Ђ݂����Ȃ͉̂��H�@�@�@�@�@�@�z�I�m�L�@���N�����ȃ��N������
�J�̑O�̗[���A�����肪���Â��Ȃ��Ă����������Ă������ׂ̐l�������������B
�Ȃ�قǁA���ڂɂ͎G�Ђ��Ԃ牺���Ă���悤�ɂ������邪�A����͖p�̖��V����L���Ă���Ƃ���B
�i����N�k�M�A�T�N���Ȃǂ͂Ƃ��ɔ��̗t���L���A���Ă̌��ɋP���Ă���̂ɁA���̖p�̖̗I�X����x���B���X������̂��B
 |
�ؑS�̂߂�ƁA�k���ɂ͑��}���o������𒆐S�ɓ��Ɛ��Ɋ�����}��L���Ă���B���̐�ɂ��Ă���V��̈ʒu���Ԃ��������悤�ɂ܂炾�B
*����͖p�̖̍�킾�낤�B�������Ɩp�̖���ɂ������A����Ȃ��Ƃ��l�������͍̂��N�����߂Ă��B
���Ƃ��Γ�ʂ���ʐ^���B��ƁA�S�̂ɂ��̐V��̈ʒu�����ɍL�����Ă���̂����Ď��A�h���[�����g���Ė̓V�ӂ���
�܂����������B��ƁA��͂�k���̌��������~�ɁA����@���������ĐV�肪�L�����Ă���̂������邾�낤
�B�̍������琂���ɏ���B���Ă��V�ӂ��������̂Ɠ����ɂȂ邾�낤�B��͂���̕��z�����ǂˁB
*�p�̖̍�킾---�����i���_���猾������͊ԈႢ�B�������A�ɂ��ӎv������Ƃǂ����Ă��l���Ă��܂��B |
�V��S�̂̃o���c�L���O�����̃f�[�^�Ƃ��Ď��Ƃ͂�����u���}�Ƃ��̐�ɕt����V��̈ʒu�v���K�����������Ă���̂ɋC�Â��̂ł͂Ȃ����B
�ʔ������낤�Ȃ��B���������A3�������[�U�[�X�L���i�[���~�����Ȃǂ�����ґ�͌����܂���B�i���߂ĉ�ꂩ�����|���@��V�����������j
�݂��Ɏז��ɂȂ�Ȃ��悤�A���ς��đ��z�𗁂т���悤�ɁA�t���傫���Ȃ��������C���[�W���ď㉺���E�ɊԊu�����A�������t���L����B
�U���̔����Ԃ��v���`���č����L����悤�ɂ������葾�z����B
����͐V��̃\�[�V�����E�f�B�X�^���X�A����h���X�e�B�b�N�E�f�B�X�^���X���B
�����g�A�p�̖ɂ͂͂��܂�v���o�������Ȃ��B�Ƃ��낪������ɉz���Ă��ď��߂ẲāA���_�������������������Ƃ�����Ɍ����������B�c�A������Ȃǂ̔_��Ƃ̔ɖZ���ɁA��������̂���傫�ȗt��E�݁A�c��ڂ̔ȂŐۂ钋�H�ɎM�Ƃ��Ďg�����炵���B������ɐ����Ă�����̎}��܂��Ĕ��ɂ��A�H���̌�͂��̂܂܍a�ɗ����Ă��܂�---�V�R�̐H����@�t���̔_��Ƃ������A�Ɗy�������ɘb
���������B
����Ă̓��B
�u�{�N��肽���v�u�����v�u�t���ςɍڂ��Ă�����H�ׂ����v�u�ł������̂����̓J���[��v�u���������肽���v
���M�ɂ͂ݏo��قǑ傫�ȗt���悹�A���̏�ɔM���J���[���C�X�������܂����B�����Ƃ����ԂɔM�ŗt���Ƃ��āA�M�̏�́u�t�{�J���[�{���͂�v��
�O�b�̑����B�����Ⴎ����̃J�I�X��ԂɂȂ��Ă��܂����̂ł����B
 �@��
�@��
�t�̕t��������P�O�Z���`�قǗ����Ď}���A�ׂ��Ē���̉����ɁA���Ƃ��R�O�Z���`�قǂ̎|�ɂɓ���A�M���b�ƈ����đ���ƕ��ԂɂȂ����B�J���J�����������B
�ނ������ǂ��� ���������܂����B
�@�@�@�@�@ ���R�̕�炵589 2021.5.4 �@�@
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 ���̔��̎�����͗D�������@�n���g���m�I
�i�t�Ղ̔��j
���̔��̎�����͗D�������@�n���g���m�I
�i�t�Ղ̔��j
 �n���g���m�I �i�t�Ղ̔��j
�n���g���m�I �i�t�Ղ̔��j
�^�f�ȃ^�f���̒��Ԃŏt�ɍ炭��ނ͒������B�Ԃт�̂悤�Ɍ�����̂��ӕЁB��яo���Ă���̂͂����ׁB
�E�͂�Ƃ�̂��ܔ����Ԃ̕�ɂ��łĂ������낫���Ȓ}�g�R�̓��@�@���a�V�c�䐻
�͂邩�Ɋ֓�������݂͂邩���}�g�R�̌�K�P���ɁA���̌�̂̔肪����B
�}�g�R�͈�錧���Ύs�ɂ���o����B�W��877m�̏��̎R�ƕW��871m�̒j�̎R�ŁA�ł��Ⴂ���{�S���R�Ƃ��Ēm���Ă���B�j�̎R�̐_�͈ɜQ�����i�����Ȃ��݂̂��Ɓj�A���̎R�̐_�͈ɜQ�����i�����Ȃ݂݂̂��Ɓj�B
�[���猩�グ��D���Ȏp�́u���̕x�m ���̒}�g�v�Ə̂����قǂŁA�w���t�W�x�ɂ͂�������B
�@�@ �E
�}�g��ɐႩ���~��邢�Ȃ������������q�낪�z�����邩���@�i��14�@3351�j����
�����{�R�́u�^��p�U���v�𖽂���B��́u�j�C�^�J���}�m�{���i�V���R�o��j�v�B�u�c�N�o���}�n���i�}�g�R����j�v���u�����ɋA������v��\���B�ꂾ�������Ƃ͈ӊO�ɒm���Ă��Ȃ��B
�E ��������̒@�������邠���܂����������Ă��т����肵�Ȃ�ށ@�@���a�V�c�䐻
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w���ق��Ȃ�x�i���a63�N�j�u�k�Дŏ��a�V�c�䐻�W�@�@�@�@�@�@�@
�Q���Ƃ̓L�c�c�L�̒��Ԃ������B�Ԃ��L�c�c�L---���O�̂Ƃ���Y�̌㓪���͐Ԃ��B
�邪��������Ȃ������܂����B���o���Ⴆ�킽��A��������̊���@��������������B�ӂƂ��̉��������������B�ʂ̖ɔ�шڂ����̂�---�B
�@�@�@�������Ă��т����肵�Ȃ�ށ@�@
��������͔�т������B���Ƃɂ͏��H�̒��̔�����̂Ȃ��A�����̐��E���L����B
���a�V�c�́A���a63�N7������ߐ{�ɂ��×{�ɂ������������B8���܂ő؍݂Ȃ������Ƃ���ƁA�����Ɂu�H�̒�v�Ƃ���悤�ɁA�W���̍����ꏊ�ɂ����p�@�i700���O�ォ�j�͂��łɏH�F���Z���Y���Ă������낤�B
�A���̂̂���9��19���A����䏊�ő�ʓf���A���a���ɕ����ꂽ�B
�����I�Ȃ̂́A�V�c�̍Ō�̍�i�Ƃ���邱�̉̂̏���͒��o���A�����ĂT��͔�ы������̂�������S���r�܂�A���т������̂��Ă��邱�ƁB���̂S�傩��T��ւ̑f���łȂ��炩�Ȓ��ׂɓV�c�̕��i��������B
���o���A��������̉���T�������Ă���S�̓��ւƎ��ʂ��Ă����A���̓������A���������---��e�ւƂȂ����Ă������B�������͕̂s���Ȃ��Ƃ��낤���B
����O�ɐl�Ԃ͒��o���Ō�܂Ŏc��ƌ�����B�₵������₵���Ɖ̂��A
�߂�������߂����ƕ\������A����������������ƌ��t��a���B�̂��r�ނ̂ɔ�����x�����ڕ\����V�c�����炱��������A�����
�l���o���̕��G���A���w�������_���炠���ꂽ���̂��B�����̎v�������߂Ď₵���Ɖr��ꂽ�V�c-----�����͏��a�̓��B
 |
���_���Ζ����Ă�����Ђۗ̕{�����A�ߐ{��p�@�̂�����ɂ������B����q���H����ۂ��Ă���ƁA�U���
���o�ɂȂ������a�V�c�̂��p���܂܂������������ƕ����Ă���B
�F�Ŏ��U��ƁA�C�����Ɏ��U���ĕԂ��ĉ�����A
���낤���Ƃɐ��q��
�u�V����`��v�Ƃ��Ăт��Ă��A��͂���U��Ԃ��ĉ��������炵���B
�@���ꂪ�A�J�Q���B
���̌�낪�Ԃ��̂ŁA���e�B
��̖Ɍ����J���āA���Â��肵�Ă���l�q���A���_���P�q���̖Œ�������i�B |
���R�̕�炵588 2021.4.29�@���a�̓�
�@�@���N�����J���~��
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@ �@ �@
�@
 ��N�ł��������������
��N�ł��������������

�킪�Ƃ̎����͗���ɐ����Ă���O�{�̎R������B�����悤�Ɍ����邪�����ɉԂ̐F���Ⴂ�A�炭���ɂ�����قǂ̂��ꂪ����B��̖������Ȃ̂��A���a200���[�g��
�ɂ͂悭�����ԐF�̍�������ł���B�����Ă��̌������̗тɂ́A���t�ŐԂ݂��������Ԃ��炩����R�������{������B
���U���A�N����Ɠ����ɑ����J����B�P���i�F���L�����Ă���B����ɂ͎���15���̓�̖��A�E�ɂ͖p�̖��L���t���̂������悤�Ƃ��Ă���B
�����̉Ƃ̂˂�����ԉ����悤�ɁA���̒�̎R������Ԃ��ꂢ���B
���R�̕�炵587
2021.4.23
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@ �@ �@
�@
 �₩�ɑ����͉̂��̂��߁@-----�@�������Ē�����������Ă���炵���H
�₩�ɑ����͉̂��̂��߁@-----�@�������Ē�����������Ă���炵���H
����̂��Ƃ������B�u�x�m�R�����߂ĕ�炵�Ă���v�K���ȕ����烁�[���������āA
�u��̃`���[���b�v����̒����ړ�����̂ł��A�Ȃ��ł��傤�B�v�Ƃ������₢���킹���������B
�������낢�B�`���[���b�v�͈ړ�����̂��H �����̓C�G�X�B�����`���[���b�v�����݂���̂ł��B
����Șb���ƁA���R�������ĐA�����s�����A���̖ړI�͉����ƍl���Ă��܂��������B���̕s�v�c���������l���Ă݂悤�B
�ŋ߁A�m�g�j�ł���ȓ��e�̕������Ȃ��ꂽ�B�@�A���Ɋw�Ԑ����헪�iE�e���j
�u�o���Ȃ̉ʎ��̉ԂŁi�~�A�ǁA���Ȃǁj�߂��ׂ������B�̂܂I��邱�Ƃ�����B����͎����̂��̂̔ɐB��킾�B�߂��ׂ̖����Ԃ��R�炩���A�₩�Ɍ����邱�ƂŁA�}��҂��ĂъA�q���i�ʎ��j���c�����Ƃ��Ă���B�߂��ׂ����Ȃ����ƂŁA�G�l���M�[���������A�����̂��߂̃R�X�g�������Ă���B�܂�A�Ӑ}�I�ɂ߂��ׂ����Ȃ��Ƃ��������̂��Ă���B�v
�@�iPrunus���̒��ɂ́A�����ׂ����B���Ȃ��Y�̉Ԃ�A�Y���ׂ��s�S�Ȏ��̉Ԃ��������ނ�����炵���B�j
�����ł������ɋ^���������B�Ӑ}���Ă��̍����̂�ƌ����̂́A�����̐i���Ɋւ��Đ��m�ȉ��߂ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�u�i�����ہv��l�Ԃ̍s���ɂȂ��炦����A�ړI��O�ʂɉ����o�������́A�ꌩ������Ղ��������₷���B���̍l�����������ƂȂ�ƁA�ړI����������̂�z�肵�Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ�B�i�������w�̂�������ꗂ����������ƂɂȂ肻���B
�i���_----���ݑ��݂��鐶���́A�����Ԃ����Ċɂ₩�ɕω����Ă����B���̉ߒ��̒��Ő��܂�Ă����Ƃ��������◝�_�������B�����̎p�������A�`���͌����ĕs�ς̂��̂ł͂Ȃ��B
�u�i���v�̎��ʂ�����u�i���v�Ǝ�肪�������A�P���ɂ��̏ꍇ�̐i���́u�ω��v���Ӗ����邾���ŁA�i���͂��Ȃ킿�ǂ��ق��ɕς�邱�Ƃ��Ӗ����Ă��Ȃ��B
 |
�@�ԓ�
���t�����Ԃɂ͂߂��ׂ�����B
�摜�ł͕�����ɂ������A
����ȊO�̉Ԃɂ͂߂��ׂ���������� ���B |
���̓��̉Ԃ̂߂��ׂ̘b�����A���R�ɁA���܂��܋N�����o�������ƍl���Ă݂�ƁB
�c���ړI�ɍ͔|����Ă���i��́A�����������Ȃ��Ă��A�傫���ė��h�ȉʎ����Ȃ�ق����͔|�������ǂ��B
�i�����̂��̂̑I���𑱂��Ă��邤���ɁA���R�߂��ׂ̂ł��Ȃ��Ԃ��炭�悤�ɂȂ����̂�������Ȃ��B
�@�@�@---����A�������̕�����R�Ȃ����B�傫�����B�Ȃ玟��---�B �i������A���łɈӎv�����荞��ł���j
���̋��R���d�Ȃ肻�̌��ʁA���ׂẲԂɂ߂��ׂ��ł���ꍇ�Ɣ�ׂāA���Ȃ��Ƃ��ɐB�ɕs���ɂȂ�Ȃ��A���邢�͂��L���ɂȂ����̂ŁA�u���܂��܁v���̐������`�����Ă����Ƃ��l������B
�i���_�͕ω��̘A�Ȃ�A�ψفA�ω����Œ肳������p����Ă������Ƃ��Ɨ������Ă����B�������A�A���w�̑f�l�Ƃ��ẮA�A���ɂ��ӎv������ƍl���������A���e���݂����Ă�̂����ǁB�Ƃ������A�ӎv�����ƍl��������A�[���ł��錻�ۂ����܂�ɂ���������B�������A�A���͐_�o�n�������Ȃ��A�ł͂ǂ��ŁH
�i���̉ߒ��̒��̂����u�ɑ������Ă���B����͂ƂĂ���������ł����Ƃ��B
�ȏ�A�ƒf�ƕΌ��ł����B��蓹���ł́A�����ł��Ȃ����Ƃ��������܂��B
��
�C���P����I�Ȃ��́B���̎��͒����������g�ː}�ĂŁA�j�����ɂ��铍�\���͂������炫�Ă���B
�����Y�͓��̎��̒��ɉB��Đ�𗬂ꉺ�������A���������w�Î��L�x�̂Ȃ��ɂ���Șb���������B�C�U�i�M�m�~�R�g���A���Ă̍Ȃ̃C�U�i�~�m�~�R�g
�ɒǂ��A����̍����瓦���A��Ƃ��ɓ��̎��𓊂��ď��������B��q�̓��j�́u���j�j�v�ƌĂꌌ�s�����P�����Ƃ��āA�ڂ݂́u�����ԁi�͂��Ƃ����j�v
�̖��O�ŗ��A��A�֔��Ɏg����B
 |
���N�h���̗��@�X�Y���ڃ��N�h���ȁ@�@
�u���v�Ə��������B
���_�̒��ɖ����̗����������B���̍����ČQ���
�M���[�M���[���₩�܂����z��B |
�@ ���R�̕�炵586
2021.4.21
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@ �@ �@
�@
 ���a500���[�g���̃X�~��
���a500���[�g���̃X�~��

.gif) �q���̂���A�^�`�c�{�X�~���́u���v���m���Ђ������ėV��ł����B���݂�̂��������B �q���̂���A�^�`�c�{�X�~���́u���v���m���Ђ������ėV��ł����B���݂�̂��������B
(
�����@�Ԃ̌��̉Ԋ����˂��o�Ă��́B�������߂�ꏊ�B���͉��܂ł����肱��Ŏ�������B)
�ЂƂ����肷�݂�̂������ŗV��́A�n�ʂɍ�����Ԃ̑��̂Ȃ��ɃX�~���̉Ԃ����܂��Ă������B
���̂����͂����B
���a�Q�O�Z���`�A�[���P�O�Z���`���炢�̌����@��A�X�~���̉Ԃ�L���|�E�Q�̉Ԃ��Ȃ��ɏ���B�n�ʂւ̂������݂����ɁB���̏�ɓ����ȃK���X��u���l����y�ŕ����ČŒ肵�A�ォ�猩�Ċ�ԁA�ƒP���Ȏd�g�݂�
�B
����Ȃ��Ƃ����ėV���Ƃ̂���l���܂����H ���葋�̂��݂�H (����ǂ����݂ꂾ---�j
�@.gif) ���{�Ɏ�������X�~���ȃX�~�����͖�60��ނ���B�������A���G��∟��A�ώ�A�O����A�V���ɍ�o���ꂽ���|�p�i������肻�̐��͊m��ł��Ȃ��B200�킭�炢���낤���H ���{�Ɏ�������X�~���ȃX�~�����͖�60��ނ���B�������A���G��∟��A�ώ�A�O����A�V���ɍ�o���ꂽ���|�p�i������肻�̐��͊m��ł��Ȃ��B200�킭�炢���낤���H
�X�~���ٕ̕ʂ́A���i�\���C���V�m�j�̊J�Ԏ�������ɍs���Ƃ����炵���B�O��Q�T�Ԃ��ٕʂł�����ԂȂ̂ɁA�S���i�܂Ȃ��B���낻������U��n�߂��B
�ł�A���N�܂ő҂Ă邾�낤���B���̉J���オ������A�J�����������ďo�����悤�B�ǂ����Ђ�߂��܂��悤�ɁB
|
 |
 |
 |
 |
|
�@�@�A�J�l�X�~�� |
�@�@�A�P�{�m�X�~�� |
�@�@�A�I�C�X�~�� |
�@�@�A���A�P�X�~�� |
|
 |
 |
 |
 |
|
�@�@�t���g�X�~�� |
�@�@�q�i�X�~�� |
�@�@�G�C�U���X�~�� |
�@�@�q�J�Q�X�~�� |
|
 |
 |
 |
 |
|
�@�@�}���o�X�~�� |
�@�@�R�X�~�� |
�@�@ �X�~�� |
�@�@�i�K�n�V�X�~�� |
|
 |
 |
 |
 |
|
�@�j�I�C�^�`�c�{�X�~�� |
�@�@�m�W�X�~�� |
�@�@�X�~�� |
�@�@�T�N���X�~�� |
|
 |
 |
 |
 |
|
�@�@�^�`�c�{�X�~�� |
�@�@�X�~�� |
�@�@�c�{�X�~�� |
�@�@�E�X�o�X�~�� |
���R�̕�炵584
2021.4.16
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 ���N�����������邩�B
���N�����������邩�B
���_�͂�����Ƃ����C�U���̃h���C�u�̂��Ƃ��A�ӂ����āu���ρv�ƌĂ肷��B
�@�@�i�ł͕��ʂ̕�炵�͖��C�Ȃ��́H�@----- �����ᎉ�b�̂����̖�����B�j
�Ƃ��o�Ă���A����܂ŒN�ɂ����Ȃ��Ƃ����h���C�u���A�������ďo����̂��c�ɕ�炵�̂����Ƃ���B
�ߐ{�̎R�̖k���ɁA��Âւƍ~��čs����������B�r���ɃJ�^�N����C�`�����\�E�̎����n������A����Ǝ��R�̋�����������n�悾�B
�����疡�σh���C�u�ɏo�����Ă����B�[�ɂ��閐�̗{�B��ɒ������̂͒��x�����B���Ă��ٓ����L���悤�ƍ��̖̉��Ƀe�[�u���ƈ֎q����ׂĂ���ƁA�ɂ₩�ɓ���������ΖʂɃI�I�}�c���C�O�T�̃��[�b�g���ڂɓ������B
���ٓ��͂��Ƃɂ��悤�B
�@
�傫���n�ʂɐL�т��t���A�~�̊��������̂����߂̎����������F����t�̗ւƕω����悤�Ƃ��Ă����B�������ƍ��E�Ƀ��[�b�g�t���L���ĉ������p�ɕ�����ł����v�����������B�ǂ��łǂ��X�C�b�`���������̂��A�u���̃I�I�}�c���C�O�T�̃��[�b�g�A�I�t�B�[���A�݂����v�Ɗ����Ă��܂����̂��B
���₢��B�Ȃ��n�����b�g�̈��ʂ������߂������̂��낤�B���A�w���{�o�ϐV���x�ɈɏW�@�Â̘A�ڏ����w�݂������搶�x���f�ڂ���Ă���B���̓����h�����w����ɁA�T�X�Ƃ���C�����Ԃ߂邽�߁A���̃I�t�B�[���A�����ɏo�����Ă����炵���B���ꂪ���ɂ������悤���B
�b�x��B�w�݂������搶�x��ǂ�ł��邩���蓹���Ă��܂����B�U����蓹�����܂̃��^�V�B
�u���[�b�g�v�Ƃ��K�N�ERose���炫�����t�ŁA�������̉Ԃт炪�d�Ȃ荇���Ă���l�q���ʂ����t���B�������̉摜�̂悤�ɕ���ɂȂ����\�������ˏ�ɁA���邢�͗�����ɕ���ł����Ԃ��u���[�b�g��v�ƌ������킵�Ă���B
���̃��[�b�g��̗t�œ~���z���A���͑����B�t�ɂȂ�ƒ�������s��L���w�������Ȃ�A����������ƉԂ�t����B
���̃I�I�}�c���C�O�T�́A���傤�ǂ��̃��[�b�g�t�Ɍ����Č��������s���ĐA���̂ɉh�{���A���S����s�t��L�����Ƃ��Ă��鎞���̂悤���B
�������B���̂̂т₩�œ��X����p�ɂ͋C�i����������B
�t�����[�b�g��ɔz��ړI�ɂ͑傫��������āA
�P�j �w�̍������̐A���Ƌ�������ƕ����Ă��܂��B��������A�����������Ă��Ȃ��ꏊ�ŁA�ɐB����B
�@�@�@----�I�I�o�R�A�^���|�|�ȂǁE
�Q�j
�~�̊Ԃ������[�b�g��̗t��t����B�����ɑς�����悤�ɒn�\�ɒ���t���ėt��L���A�n���𗘗p���Ȃ��炷�ׂĂ̗t�����z�̌�������悤�ɂ���������ɗt��L���B-----�摜�̃I�I�}�c���C�O�T���������B
�ق��ɐA���������邽�߂Ɏ��헪�́A���Ƃ��B
�E�������������A�㉺���E�Ɉړ�����@------�@�u���[�x���Ȃ�
�E��𐅂̗���ɗ��Ƃ��A�����ɏ���Ĉړ�����@------�@�T���O���~�@�V�̎���
�E����Ԏ�����炷�@-----�@�^���|�|�@���~�W�̉ʎ��@�Ȃ�
�E�A���ɉ^��ł��炦��悤���܂�������@-----�@�X�~���@�P�}���\�E�@�Ȃ�
�E����̎��������炷�@------�@�h���O���@����
������ƍl���������ł�����Ȃɂ���B�܂��܂�����B�l�X�Ɛ�������ɖ�������Ă���A���́A���̐������̖ʔ����ɁA���܂�
�Ɏ䂩�ꑱ���Ă���B
�u�ٓ��H�ׂ悤��v�B�u���܍s������v�B
���Ƀt�L�m�g�E���ǂ����蓪���������Ă���ł͂Ȃ����B��������������ς��ċG�߂̌b�݂������������Ƃɂ��悤�B�������܂��������B
����̌����́@�@�R�ł̏d���ٓ��̌�Ȃ̂ŁA�����ς�B
�@�@�������ɕ����X�@�i�R�̕��j
�@�@�����݂̂��Z���i�F�l�̒�ō̂����j
�@�@�ڂ̌Ӗ��a��
�@�@�Ⓚ�����M�q�ʏ`����ꂽ�M�q�卪�i�����卪�j
�@�@�V�ʂ˂����ɂ��A��������Ă��Č{���~���`�̂���
�@�@����@�@�ł��B
�@
���u���K�T�@�L�N�ȁ@�@��o���̂��남�Z���ɂ��ĐH�ׂ�Ƃ��������B
�@�@
�@�@�E�˂����Q�l���A�]�˂̗��X�ŎP����̓��E�����Ă���A����Ȃӂ��Ɍ����܂��B
���R�̕�炵584 2021.4.11
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �����������B�@�J�^�N���͂ǂ��ցB
�����������B�@�J�^�N���͂ǂ��ցB
�J�^�N�����t�̗z�𗁂тĐg�点�ċP���Ă���B�w�i�ɂ̓��b�p���傪�炫�ւ��Ă���
�@�@�@-----�S���ǂ���i�����A�t�̗z��O�ɍ��A�킯�̕�����Ȃ�������������Ă���B
���N��100�{�̑��܂ł��Ə������Ɗ�сA�c�c����R�o�Ă����̂ɁA���N�͂����Ɛ�����60�{�����炢�Ă��Ȃ��B�������̏��Ȃ��~�Œn�ʂ͊����C���������Ƃ͂����A�Ԃ̐����̂��̂����邱�Ƃ͂܂��l�����Ȃ��̂����ǁB
��͂肱��̓l�Y�~�̎d�Ƃ��낤�B���H�A�L�@�엿���ɏ������������A�~����t�ɂ����Ẵ��O���̊���Ԃ�́A����10�N�ԂȂ��������炢���������炾�B
���O���ƃl�Y�~�͊W����̂��H�ł����B�@�������ł��B
�L�@�엿���������ނƃ~�~�Y��������B�a�ɂȂ�~�~�Y��������ƃ��O��������Ă���B���O�����~�~�Y��T���ďc���Ƀg���l�����@��i�ށB���̃g���l���𗘗p���ăl�Y�~��舕�����B
�Ƃ��������킯�ł��B
�l�Y�~�͕ЌI�̋�����`���[���b�v�̋�������D���B�����������I�����������N�̃`���[���b�v�������������悤�ȋC������B����C�̂������A������C�̂����ł͂Ȃ��悤���B
�J�^�N�����Ԃ�t����ɂ́A7�N����9�N������ƌ����Ă���B��͎��b���Ɠ������܂ނ̂ŁA�����_���ċa������Ă���B�J�^�N���͂��̋a�̍s����ǂݎ�̎U�z����`���Ă�����Ă���B�i�A���U�z�A���j
�a�ɓ��܂�Ȃ��悤�ɑ��߂ɍ̂�A�n�ʂ�1�Z���`�قnj@���Ď�ߍ���ŗ��t�̔����҂B�i������̂�d���ƌ����܂��j���̍�Ƃ�15�N�ԑ����Ă������ʂ�100�{�߂��̉Ԃ����ɂȂ����̂�����A�v��������ЂƂ����Ȃ̂��B
�J�^�N���͏t�d���A���̈�Ō�������������Ԃ��Z���B�����琶�����x���B�܂ǂ�����������҂����Ȃ��A�Ƃ����Ό����d�˂Ă��Ă���Ƃ����܂ŗ����B������ߑR�Ƃ��Ȃ��B
�Ȃ����������A�Njy�̎���ɂ߂�ׂ��ł͂Ȃ����낤�i�j�B��͂�l�Y�~���낤���H
�l�Y�~��ގ�����ɂ́A���O����ǂ��o���Ȃ��Ƃ����Ȃ��A���Ďv�Ă̂��ǂ��낾�B

�@�J�^�N���@�L�N�U�L�C�`�����\�E�@���b�p����R��@���F���r�I���@�~���}�I�_�}�L�@False
Oxlip �@�@
�n���̌ØV�ɕ����ƁA���͕̐̂ЌI�Ȃǂ����璆�ɂ���A�Ԃ����Z���ɂ��ĐH�����Ƃ̂��ƁB
�������Ɍ@��W�߂ĕЌI���͎��Ȃ��������ǁA�Ƃ̂��Ƃ������B�@
���R�̕�炵583
2021.4.6
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
 ���T�C�N�����������ۂ�----�����Ȗ��O�̃{�����e�B�A
���T�C�N�����������ۂ�----�����Ȗ��O�̃{�����e�B�A
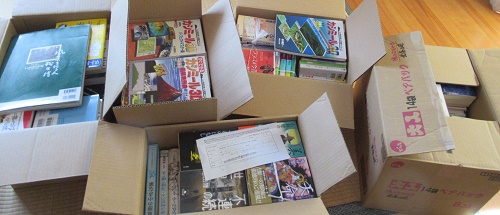
�~�̊Ԃ͂����Ƙa���ɒu���Ă����A�܂ݓǂ݂��Ă����������̖{�����i�ƂĂ��Ȃ������j�Ǝ莝���̖{�����킹�Ĕ��l�߂ɂ��A�悤�₭���邱�Ƃ��ł����B���Đ�́u���T�C�N�����������ۂ�v�B
�{�ACD�ADVD�A�Q�[���\�t�g�A��������A�p�\�R���Ȃǂ̓d�C���i���u���T�C�N�����������ۂ�v�Ɋ�t���A���̕��i���A�u�b�N�I�t�R�[�|���[�V����������Ђ��������A�������z�S�z�����ۋ��͊����ւ̊�t�Ƃ�����́B
���̏ꍇ�͔������z�S�z���ASANE(�G�N�A�h���̎q�ǂ��̂��߂̗F�l�̉�)�Ɋ�t����Ɠo�^���Ă��邩��A���̂����A�������邾�낤�B������ɂȂ邩�y���݁B���̂ق��A��Z�ւ̊�t�A�w�肵���{�݂ȂNJ�t���I�Ԃ��Ƃ��ł���B
�@�@ �@<http://kishapon.com/>�@���T�C�N�����������ۂ� �@<http://kishapon.com/>�@���T�C�N�����������ۂ�
 |
���ĉב���Ɏ�肩���낤�B�a���ɍ��肱�݃_���{�[�����ɋl�ߎn�߂Ă��炭����������A�|���������̉��ɁA���X��Ō��������ǔL��������グ�Ă���̂ɋC���t�����B
���ۂɈڂ��ăR�c�R�c�A�Ƒ���@���Ă݂��B
���H �s�v�c�Ȋ�Ō��Ԃ��Ă���B
�@�@���̉E���̃X�|�b�g�������ˁB
�@�@�����Η��Ă����Ɗ���������---�B
�@�@�����ԂȂɂ����Ă��H
�b��������ƁA�Ȃ������Ă��ꂽ�悤�ȋC�������B
�����̓X�|�b�g�N�Ɩ��t���悤�B
�d���ɖ߂�B�������Ǝ�����Ă�����A����ɉ����������Ă���̂�������ꂽ�B�X�|�b�g�N�������B
�X�|�b�g�N���A�Y���Y���Y���Ƒ��ۂ̖ɓo���Ă���ł͂Ȃ����B
�ǂ������́H
�D��S�����Ȃ��̔L����A���������ł��������������Ă���̂��낤�B���������m�肽����S�ōׂ��}�Ɏ��t���ēo���Ă����̂��B
�@ |
10���قǂ��������A�s����Ȏp���̂܂ܑ��z���ɕ����̒����̂��������Ă����B�ڂ��������тɐ��������Ă��Ɗ��������ɂ�������B
�X�|�b�g�N�ɂ��Ȃ�ő�D���ȃ��L�V�R���w�u�V�G���g�E�����h�iCielito Lindo�j�v�̃t���[�Y
�@�@��Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la
boca ��
���x���̂��Ă�����A���̂����]���Ŏ����I�Ƀ��t���C������悤�ɂȂ����B
�P����ƂȂ̂ŁA�ދ����̂��ɑ��قŘb�������Ă݂�B
�@�u�������Ȃɂ��Ă݂Ă͂�v�u����˂�v�B
�X�|�b�g�N�A���̂����[�������̂��~��悤�Ƃ��邪�A�L�͉��ɍ~���̂��s���ӁB���̂܂܍ׂ��}�Ɍׂ��Ă��邤���ɑ̂̏d�݂ɑς����˂��}���܂�Ă��܂��A���̂܂ܒn�ʂɂ��낪�藎���Ă��܂����B�h�W�ȗl�q�ɑ���B
�u���܂����v�u���͖̂����������Ƃɂ��悤�v�Ƃł��v�����̂��A�Ƃꂭ�������Ȋ�����A������t���t����h�̋������ɋA���Ă������B
�c���ꂽ�̂͂T�̒i�{�[�����Ƃ�������G�������B |
���R�̕�炵582 2021.4.2
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
 ����ɉe�𑗂낤�@�@�@�u����������v�̗V��
����ɉe�𑗂낤�@�@�@�u����������v�̗V��
�u���b�P�����ۂ�̌����悤�A�����̉e�Ɏʂ���낤�ƌ��߂���B�܂��܂��s�v�c�Ȃ��Ƃ��v�����Ă��܂����B�B�l�����Ƃ����Ȃ��牽���������ƌ��߂Ă��ĂӂƖڂ���炷�ƁA�����ɐ�قǂ܂Ō��Ă������̂̎c��������Ă���B����Ȍo��������܂��B����͎c�����ʁB
�ڂɌ�����Ƃ����̂́A�����Ă��镨���甽�˂������̎h����Ԗ��̍זE�����m���A���Ƃ��Ĕ]�ɑ���ꏈ������邱�Ƃ������B���̌��̎h�����A�ڂ̑O�ɂ��̕��������Ȃ�������i�ڂ���点������j�Ԗ���]�Ɏc���Ă��邱�Ƃ���c�����ʂ��N����炵���B
���i�F�j��������A�����F���c�����Ă݂�ꍇ----�z���c���B����͕�����Ղ��B
���i�F�j��������A���̔��̐F���c���Ƃ��Č�����----�A���c���B
 |
�Ȃ��A���c�����N����̂��B
�_�o�͔��ΐF�̕����Ō݂��Ɍ�������悤�ɓ����Ă���B
�Е��̐F��������Ƃ���܂ŗ}�����Ă������ΐF������Ă���Ƃ����s�v�c�Ȏd�g�݂̂悤���B
�@ |
���̉A���c�����ʂ��g���āA�Ƒ��̌��т���\����������G�{������B
 �w���������̂���������x�@���܂݂���@���I�q�G�@�����ˑn��G�{ �w���������̂���������x�@���܂݂���@���I�q�G�@�����ˑn��G�{ |
[��l���́u���������v�́A���e�ƌZ�Ƃ̂S�l�ŕ�炵�Ă��܂��B������������邱�ƂɂȂ�A�o������O���A�Ƒ��Ő�c�̕�Q��֍s���܂����B�����ʂ�悤�Ȑ�������グ�����́A�u�e���肪�ł��������v�Ƃ����Ċ�юq�������ɗV�ѕ��������܂��B�S�l����ł����Ɖe�����߁A���̖ڂ���ɓ]����Ƃ�����4�l�̔����e������Ă��܂����B�܂�ʼnƑ��ʐ^�̂悤�ɁB
���Ă̂����A��P�x��Ђт��A3�l�͊O�ւƂт����܂����B������r���ł��������͉Ƒ��Ƃ͂���Ă��܂����̂ł��B�����ƋQ���ɋꂵ�ނ��������́A��ɕ����ԉƑ��S�l�̔����e�����܂����B���������͏��Ȃ���Ԃ����̒��𑖂��Ă���-----���̒����������͋�֏����Ă��܂��܂����B] |
�@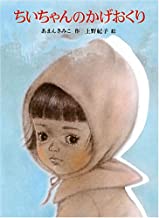 |
�݂��������t�A�ӂ���ތ��t�A���炩�����t�A����ɓY����ꂽ�G�ŁA�Ƒ����Ɛ푈�̋������A�ߎS����\�����Ă���B�����Ɖe�����߁A��ɂ��̉e���ʂ����B���̍s���̔߂��݂Ƒ����͋��t�ɍL����B
�u�e�v�͂��̂��̂̎��̂�\�����Ƃ�����B�u�\������Ήe�v�u�e��炢�āi�Éꐭ�j���j�v�u�������܂ŗV��ł����q�������̉e�������Ȃ��v�̂悤�ɁB
�e����ɑ���-----���݂���ɑ��邱�Ƃ́A���ł����Ӗ����邩����͂���͂ƂĂ��|�����t���B��Ẳߑa�̑��ŁA�ʐ^���B����ƍ����z�������ƐM���Ă���l�����ɉ�������Ƃ�����B�����̖ڂɌ����鐢�E���A�M�����邷�ׂĂƍl���Ă���l�����ɁB |
 �i���Ӂ@��������I�^�N�j�i�ŋ߃I�^�N���Ԃ��ǂ�ł��������Ă���ƒm��A���S���ď�����悤�ɂȂ����j �i���Ӂ@��������I�^�N�j�i�ŋ߃I�^�N���Ԃ��ǂ�ł��������Ă���ƒm��A���S���ď�����悤�ɂȂ����j
�@�@�i�����̂Ȃ����̓p�X���Ă��������j
�w�A���V���[�Y�x�̍�҃����S�����C�ɂ́A�A���Ɣ�r�ł��鏭���̐������ꂪ����B�w�G�~���[�V���[�Y�x�̎O���삪���ꂾ�B��Ɏ������g�ł��낤�Ɠw�͂���G�~���[�̕���́A�w�A���x�����D�����B���̂Ȃ��ɁA����ȏ�ʂ�����B
�u�G�~���[��---�ڂ̋ؓ����Ȃ�ƂȂ����������ƁA�ڂ̑O�̋�ԂŁA�ǎ��̖͗l���ʂ��Č��邱�Ƃ��ł���̂��B----���ɕ����ׂ��܂܁A�D���Ȃ���----�����āA���R���݂ɂ���������B�����Ƌ߂Â����肸���Ɖ����ւ͂Ȃ����肷�邱�Ƃ��A�傫�������菬������������ł����B�v
�����S������@�_�����v��@��U�́@�j���[�E���[���@�Е��ɂ��
�������ɂ���͗z���c���̌��ۂƎv����B
�����ǎ��̖͗l���ق�̐��b�ԁA�����ǂȂǂɎʂ����Ƃ͂ł��邪�A�����܂Ŏ��݂ɔ]�̋L���𑀂邱�Ƃ��ł��Ȃ��B����̓G�~���\�Ɏ�����ꂽ���ʂȔ\�͂ƍl���邵���Ȃ����낤�B�ׂ����f�[�^���E���W�ߔ]�̒��ʼn摜�������s���A�_�o�M���������̐_�o�n�Ɏʂ����L����Î~��ɂ��ĕۑ��ł���A����������ԁB
��҃����S�����������悤�Ȕ\�͂������Ă����̂�������Ȃ��B���邢�͍�Ƃ����o������ƓI�^���Ȃ̂��B�����͐s���Ȃ��B�z���͂��`��ς��ďo�Ă������̂�������Ȃ��B |
���R�̕�炵581
2021.3.29�@�@
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �d���T���̂͂��܂�
�d���T���̂͂��܂�
��Ԃ̓앗���Â܂�J�̏オ���������̂��Ƃ������B�V���b�^�[���J����ƁA��͈�ʔZ�����ɕ����Ă����B�萁���̖ւƎp��ς��悤�Ƃ��Ă����₭�ʂ��̎��́A���������ڂ���p�������Ă��邾�����B15���[�g���̍����ɂ������50�N�̎��X�̖ؖ��͖��ɕ���Ă��Č����Ȃ��B
�ˑR������ł����l�����������B�������I�@���N�͂��Ѓu���b�P�����ۂ��L�^���悤�A��������̒�ŁA�ƁB
|
���̌��w�I���ۂ̓h�C�c�����̃u���b�P���R�ł����Ό����邱�Ƃ���A�u���b�P�����ۂƂ��u���b�P���̗d���ƌĂ�Ă����炵���B�@�@�u���b�P�����ہiBrocken
spectre�j |
�z�����Ă݂�B��ɕY���Z�����̒��ɗ������z���w�ォ��Ƃ炷�u�Ԃ�҂ƁA���̒��Ɏ����̉e��������ł���B�e�̑�----���͂ɂ��閶�̗��ɑ��z�����U������A���Ɏ������̗ւ��ł���͂����B
Glory, Glory, Glory�@�c�cGloria, in excelsis Deo!�@
�������炵���A�̂������Ȃ�A�l���邾���ŐS�c��ށB
���̌��ւ��u���b�P���̗d���ƌĂԂƂ��������A�u���̉e�v���u�d���v�ւƏo������A����Ȑl�������낭���ʔ����B
�Ⴂ����A�V�c���Y�̎R�x�����ɖ������ꂽ�������������B
�w�����x�J�R�x
�́u�C�s�m�d�������܂܂ŒN���o�������Ƃ̂Ȃ������x�̒���ɂ��ǂ蒅�������ɂ��̌��ۂ��N�����A�m�d���͌��ւ̒��ɔ@���������v�Ƃ�����ʂ���ۓI�������B
���{�ł͂߂ł����H���ƂɁA���̌��ۂŌ��ꂽ�e�́u����ɔ@���v���ƐM�����Ă���悤���B
���Ɍ����Ɩ��̊Ԃ������炤���A�����̓��A���X�g�ɂȂ낤�B
�z�̌����w���ɓ�����Ƃ������Ƃ́A���ˊp�������Ԃ���
�Ƃ������Ƃ��B�����Ȃ�ƋG�߂͏H����t�̏��߂܂ŁA�~�����͂��R���ԂقǂɂȂ�B��C�͊������Ă���̂ŁA�p���ʂ荞�ނقǂ̔Z�������o�Ă��邱�Ƃ͍l���ɂ����B
�������ʂ�Γ������������݁A�������ʂ�Ζ������������ށB
�u���b�P�����ۂ����ۂɎ��̒�ŋN���邱�Ƃ͊�Ղɋ߂��H�@���₢�₻���v�����炨���܂����B
�@�i���F��������I�^�N�j�i������l�ɂ͕�����b�j
�w�A���V���[�Y�x�̒��ɏo�Ă���t�̏ے��́u�T���U�V�v�i�����Ԏq��ɂ��j�͖{��Trailing
arbutus�ƌĂ�陳�����̐A��Epigaearepens�i�c�c�W�ȃC���i�V���j�Ȃ̂��B���{�ɂ͓����̐A���������Ă���́u�C���i�V�v�ƌĂтȂ�킳��Ă���B
20�N�߂��O�̂�����A���͌��S�����B�K�����̖ڂł��̉Ԃ�����A�B�e����ƁB���̊肢���������̂́A���̓�����W�N���
��Â̎����̂Ȃ��������B
�@�@�@���@http://kemanso.sakura.ne.jp/anne-sanzasi.htm�@��
�����炱�̃u���b�P�����ۂ��ώ@�ł�������K���◈��ɈႢ�Ȃ��B����͂T�N�ォ10�N�ォ�B���̍����͉������Ă��邾�낤�B���邢�͉F�����猩���낵�Ă��邩������Ȃ��B
 �h�C�c�A�u���b�P���R�C�ۊϑ��W�]�䂩��̒���(
wikipedia����q���܂����j
�h�C�c�A�u���b�P���R�C�ۊϑ��W�]�䂩��̒���(
wikipedia����q���܂����j
���R�̕�炵580 2021.3.25�@�@
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �����炭�܂ł�
�����炭�܂ł�
�t�̒�d�����I��点�悤�ƁA���̂Q�O���Ԃ͂قƂ�ǒ�ɏo�Ă����B
�}�X�N�A��S�̂��ȖX�q�A�ȒP�ɒE�����ł���t���[�X�A�n�T�~�A�����̑��B�����͌����ł͂Ȃ��B����������
��Ƃ𑱂��Ȃ��炢�낢��l���Ă��邪�A���̂����ɓ��̒��͂����������ۂɂȂ��Ă��܂��B����͉����B
 |
 |
�@�h�����r�I��
�������Ԃ������o���č炢�Ă����B�t�����F�Ȃ̂́A��������g����邽�߁B
����́A�{�t���o�Ă�������̕c���A���̂������������邾�낤�B |
�@�@�Ǎ��̃L�W�o�g
����������H�ł���Ă��āA���邳���قǒ��ǂ��Ԃ����������L�W�o�g�B�����ɂȂ������͈�l�̂悤���B����ɂ��Ԃꂽ�Y�Ȃ̂�������Ȃ��B
�R���̖̎}�Ɏ~�܂��Ĉꎞ�Ԃ������Ƃ��Ă����B�Ԃ��ڂ��X�˂Ă���悤�ɂ�������B
���_���Ă���̂��A���ɂ��Ă���̂��B
���`���A�ǂ������B |
�@�@
���R�̕�炵579 2021.3.20�@�@
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �@SANE������ �@SANE������
��T�R���U���̂��Ƃ��B�uNPO�@�l�G�N�A�h���̎q�ǂ��̂��߂̗F�l�̉�iSANE)�v�̊�����J���ꂽ�B�悤�₭Zoom���g����悤�ɂȂ��ď��߂Ă̕�Ȃ̂ŋ����ÁX�B30�N�������𑱂��Ă��Ă��A�F����ɋ߂��Ŋ�����킹�����Ƃ͖�����������B�@�@��http://sanejapon.blogspot.com/��
��̌�A������ɍڂ��邩�犴�z�����Е������Ăق����ƘA���������B��u�C�̖��������������A�����œ����Ă͏����X�^���I
������������Ȃ����ǁA�ł����500���ƌ�����1000�������̂́A�����̂�����ׂ�̂������낤�B
�ySANE�������q�����āz�@�@�@�@�@2021.3.6
�u���Ƃ͐l�Ȃ�v�B���߂ĎQ������SANE�������Zoom��ʂɉf��F����̂����q�����Ă��������܂����B�R���i�ЂƂ�����O�̐��E�I�Г�̂��ƂŁA���{�ƃG�N�A�h���ł̎��Ƃ��r�₦�邱�ƂȂ��p������Ă����A���̊��͂̌��͊F����̐��_�̒��ɂ���Ƃ̔F�������������̂ł��B
���̃L�g�ݏZ���Ԃ�1979�N����1982�N�܂ŁB���n��ƂƓ��{��ƊԂɐݗ����ꂽ�Z�Z�������ى�ЂŁA�H�ꌚ�݂��琻���܂ł̋Z�p�w�����s���ׂ����C�����v�ɒx��A���w���Ɨc�t�����̓�l�̎q����A��ăG�N�A�h���ɓn��܂����B
�R�o�肪�D���ȉƑ��ł��B�A���f�X�̔��������₩�ȕ�ɂ͖�������܂����B�Ƃ��낪�L�g�ł̐����ɓ���ނɂ�A���₩�Ɍ����鐶���̒�𗬂��Â��������ڂ̑O�Ɍ���Ă����̂ł��B�����́A�����炭���݂��H�x���݂��A���n���ォ�瑱���K���Љ�ɗ��߂Ƃ��A�����̊Ԃō��ʈӎ��������Љ���f����Ă��܂����B
�G�N�A�h���̐l�����̕n���䂦�̐��_�̍r�p�����ɕ\�ʂɌ���܂������A���J�𐁂��Ղ�ɗx�苶���A���X�̕�炵�Ɋ�т������������m���ɂ���܂����B�w�ԋ@���D���A�c�����ē����n�߂�q�ǂ����������[�ɂ��ӂ�Ă��܂��B�������\���ȐH�����ۂ�Ȃ��ł��Ƒ����ɂ������������Ƃ���痂������������܂����B�߂��݂���т������Ȍ`�ō݂���----�l�Ԃ̌��^�����݂��Ă����Ƃ�������
���B�����炱��40�N�o���Ă������̋L���͔��ꂸ�A�G�N�A�h���Ɏ䂩�ꑱ���Ă���̂ł��傤�B
�u�l�ԎЉ�̔߂��݂ɏo����A���̂��ׂĂɎ�������L�ׂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B��������E�ɍL�����̎w�̐�ɐG�ꂽ�ꏊ�Ɛl�Ɋւ�낤�B�v�����������l����悤�ɂȂ����̂̓G�N�A�h������A���������납��ł����B����I�ȉ����ł͂Ȃ��A���ɐ����邱�Ƃ���тɊ�����悤�ȁu�����v��T���Ă������ASANE�ɏo������̂ł��B
SANE�̒n���Ɏ������W�߁A���������̐��_�����ɐV�������J�����Ƃ���p���ɋ������܂����B�����炩�片�����邾���ł͂Ȃ��A�������s�������u�������g�����������ǂ�������v�菕�������Ă����̂��A�G�N�A�h���̐l�����Ȃ̂ł��B�����̐l���̎x���ɂȂ荡�����Ă��邱�Ƃ��m��ł��銈��-----����͑o�����̉����Ȃ̂ł��傤�B
���̔N��܂Ő�������ė������ӂ����߂āA�G�N�A�h���̎��̐���̂��߂ɂ��ꂩ����������Ă������A���ł��邱�Ƃ�ςݏd�˂Ă������ƍl���Ă��܂��B
�L����A�q����A������B-----���̑f���炵���͉����ɂ��ウ���܂���B
�摜�Ɖ����̗͂͑傫���A�����ɂ�����SANE�����͐g�߂Ȃ��̂��Ɗ��������Ă��ꂽ��ł����B
���܂܂Ŋ������x���Ă��������Ă������ׂĂ̕��Ɋ��ӂ������܂��B
�@ |
�@�@ |
���炫�̐��傪���J�ɂȂ��Ă����B���F���g���h��Ă���t�B
�����ƒ�d���ŖZ�����̂ŁA�悤�₭�̉J�̒��}���ق֏o�������B�قƂ�ǐl�����Ȃ��������ɕ@����������P������l�������B�u�߂��ɗ���ȁv�Ɓh�O�h�𑗂�Ȃ���15����Ă����B�A��̓��̉w�ŃL�B�E�B15��300�~�Ȃ�B���ꂵ�B
�����ł��A�[�H�̎x�x�̎��Ԃ������Ă��鎞�̐V�����{���āA�ǂ����Ă���Ȃɖʔ����낤�I |
���R�̕�炵578
2021.3.13�@�@
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
�@
 �����炳���炳���炳���疜�̎����@�@
���S�n�r�@
�����炳���炳���炳���疜�̎����@�@
���S�n�r�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@ ��҂͊�茧��D�n�s�ݏZ�@�����{��k�Ђ��r�ݑ����Ă���
 �O�����݂̖����O�����@�@�̐X�s�Y�r�@�@�@�{�錧�Ί��s�ݏZ
�O�����݂̖����O�����@�@�̐X�s�Y�r�@�@�@�{�錧�Ί��s�ݏZ
�����̋�Ƃ��Ă���ȏ�̂��̂͂Ȃ����낤�B
3.11�ɋN�������S�̎��B
�R���i�Ђɝ˂ꂽ8419�l�̎��B(2021.3.11)
�ނ�̍����߂̂��߂ɂ��A����́A���͐����˂Ȃ�ʁB
���͉����Ǝv���鎞������܂ŁA������˂Ȃ�ʁB
���R�̕�炵577 2021.3.11 �@�@
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �@�L�Ђ������@
�����ɂ̓A�}�j�I�C���A�I���[�u�I�C���A�`�Ӗ��I�C���̂ǂꂪ�������B
�@�L�Ђ������@
�����ɂ̓A�}�j�I�C���A�I���[�u�I�C���A�`�Ӗ��I�C���̂ǂꂪ�������B
�ߐ{�삪�������َ�Ấu����̍��̗��j�U���u���v��A�������j�ۑ���J���Ă���u�n��̗��j��T�K����u���v���A�R���i�̉e���ň�U���~�ɂȂ����̂����傤�Lj�N�O�̂��Ƃ������B�Q���҂̂قƂ�ǂ�����҂Ƃ������Ƃ������āA�͂��Ƒ̂�ꂽ�悤���B���܂��ɍĊJ�̖ړr�͗����Ă��Ȃ��B���j�U���̍u���́A�m�Ԃ����������H�ɂ��Ă̍u���ƌ��n�������ς�ł����̂��K������������ǁB�s�v�ł͂Ȃ����s�}�ł͂���̂��c�O���B
�C�y�ɉƂ�K�ˁA�Ȃ�ł��Ȃ���b���y����ł����F�l�m�l�Ƃ�����A���R�ǂȂ�������������Ȃ����X���������ƈ�N�B���炵���Ƃ��Ă����������}�X�N�z���ɓ{��悤�ɘb�����Ƃɂ�����Ɋ���Ă����B
��������Ɖ����N�������B���_���������ɂȂ��Ă��܂����B���Ƃ���ΊJ���Ă�������Ĉ�{�̖_�ɂȂ����悤�ɁB
���������̊��o�Ȃ̂�������Ȃ��B���̓��̍��E�ɂ̓A���e�i���t���Ă��āA������Z���T�[�Ƃ��ē��������X�����Ă����悤�ȋC������B���傤�ǖj�̍��E�ɒ����q�Q�����L�̂悤�ɁB�l�Ɖ�A�l�Ƙb���B���Ƃ������ȃe�[�}�ł������Ƃ��Ă��A���̒��ɂЂƂ�A�҂����ƌ�����̂�����A���ꂪ�����̐��_�ƌĉ�����Ƃ����h���I�Ȃ��Ƃ��d�˂Ă��Ă����B
�������W�O�\�[�p�Y���̃s�[�X���ƍl���Ă݂�ƁA���̎�����\������ɂ͂ǂ���������̂��낤�B���͂̃s�[�X����ׂĒ���t���݂�ƁA���̊Ԃɂ����Ԃ��������g�ɂȂ�B�܂��̃s�[�X�͓Ǐ���������A�l�X�Ȍo���������葼�l�̒g�����v���������肷��B���l�Ƃ̊ւ肪���������Ă���Ă���̂ɋC�t�����B�����Ɏ����̐S��L���ɂ��A���肳���Ă����̂����A���������Ԃ��������܁A��芴����B
���o���Ă��邱�Ƃ����ǁA�����ɂ͌\�p������B���l�Ƙb���ƁA���̐l���p���Ȃ��炩�ɂ��Ă����-------���l�Ƃ̐ڐG�������ɑ厖�Ȃ��̂��B����g�݂����A�r��G�肽���A�ۂ�ۂ���@���āu��������v�ƌ��������B
���āA�ɂ����ĔL�Ђ����Ă������A���̂��Ɨ��鐢�E�̂��߂ɁB
 |
�@ |
�s�v�c�ȗM�q�̎�
���ʂ̗M�q�͂����������������炢�܂ł����o���Ȃ��̂ɁA���̎�Ȃ��M�q�͂R���ɓ����Ă������������Ă���B�������Ȃ邭�炢�ʏ`�͂����Ղ�B
�����͉ʏ`���i�����ėⓀ������A�c��̔���g���ăW�����������炦���B
�Ƃ��イ�A�Ȃ�Ƃ������Ȃ��ǂ����肪�Y���āA���@���Ȉ���ɂȂ����B
�@ |
�@�[���j���[��������������āB
�@�R���T���@�[�
�@�ȈՉ����ň�ĂĂ����A�C�X�����h�|�s�[�̕c�W�O�{��
�@��A�����B��N�̔����ȉ��̐����Ȃ̂ŁA�낪�₵���B
�@ |
�@�@�@�@���R�̕�炵576
2021.3.5 �@�@�[�
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �ނ�������@-----�����Ă����q�� Dana Dana
�ނ�������@-----�����Ă����q�� Dana Dana
���鐰�ꂽ��������@�����֑�����
�הn�Ԃ��S�g�S�g�@�q�����悹�Ă䂭
���킢���q���@�����čs����
�߂������ȂЂƂ݂Ł@���Ă����
�h�i�@�h�i�@�h�i�@�h�i�@�q�����@�悹��
�h�i�@�h�i�@�h�i�@�h�i�@�הn�Ԃ��@����
���悮���@�߂���т���
�הn�Ԃ������ց@�q�����悹�čs��
�����������@�������Ȃ��
�y�����q��Ɂ@�A�����̂�
�h�i�@�h�i�@�h�i�@�h�i�@�q�����@�悹��
�h�i�@�h�i�@�h�i�@�h�i�@�הn�Ԃ��@����
�쎌:���䂩����
|
���a�R�O�N��̐��Ƃł͏t�k����c�A���܂ł̓ԁA�����ɖ����Ƃ��ē������A�q������邽�߂ɋ��������Ă����B�����͈���A��A�쌴�ɐ����鑐�ȂǁB�암�̋Ȃ��艮�قǂł͂Ȃ�����ǁA�����|���������������Ƃ��ėp�ӂ��A�ꉮ����o�Ē��ڋ��̐��b���ł���悤�ɂȂ��Ă����B
���ɓ������͕��ɂƂ��Ă킪�q�Ɠ����������悤���B��̈��������閾���O�Ɨ[��
���Â��Ȃ��Ă��瑐������A�V�N�ȉa���������Ă���Ă����B
��N�Ɉ�x���܂��q���́A���N�Ԉ�Ăď����́u�_�ˋ��v�ɂȂ�ׂ��o�ׂ����B
�q���͐e���Ƃ̕ʂ�R�������Ė\��A�e���͂킪�q�̍s���悪�\���ł���̂��A�X�苩��Œn�c����ł����B
���̍��܂��������������p�̑�^�g���b�N��
�A���₪��q�����������ǂ����Ă���̂����āA�e���Ɨ��e���Ȃ�Ƃ������Ȃ��߂���������Ă����̂��v���o���B |
 ������u���n��������v�Ƃ����̂�----�����Ȃ�|�����Ƃ��ڂꂽ�܂��ʂ����Ȃ���v�킸���Ă��܂��� ������u���n��������v�Ƃ����̂�----�����Ȃ�|�����Ƃ��ڂꂽ�܂��ʂ����Ȃ���v�킸���Ă��܂���
25�N�䏊�ő傫�Ȑ}�̂��͂т��点�Ă����N�㕨�̗①�ɂ������ɏo���A�V�����①�ɂ��͂������߂��̂��Ƃ������B�܂��g����̂ɖܑ̂Ȃ��Ƃ͎v�����A���J���̗①��̍ɂ͏��Ȃ��B�ĂɓˑR���邱�Ƃ��l���ɓ���A���ꂩ��̍Ό��V�����①�ɂ��g�����������A�Ɣ��f�������炾�����B
�����̒��A�������o���|�������Ă��邤���ɁA����25�N�ԂɋN�������Ƃ̂���₱���----��a�C�A���_�̊C�O�P�g���C�A�₵���Ȃ������l�Őe�̐ӔC���ʂ������ƌ��C�ɁH�����Ă������X����݂������Ă���
�B
��S���̉����Ă����①�ɂ�A���肪�Ƃ��ˁB
 �Ȃ����J���X��������낽�B �Ȃ����J���X��������낽�B
�Ƃ��낪�A�V�����①�ɂ��ݒu�����ƁA������邭�炢���₭�����ł��܂����B500�k�̗①�ɂ̍�����180�Z���`�B��ԏ�̒i
�̉��ɕ������܂��ɂ͈֎q������B��Ȃ��������l�q�ň֎q�ɓo���ďォ�猩��ƁA���܂܂łƂ͈�����i�F�������� ����B
���邢�A�Â����A�Ƃ�Ƃ�ƒ@���ƃh�A���J���B�ӂ����āu�J�����܁v�ƌ����Ă݂��������B�����30�����̃u���[�x���[���A�ԉG�X�q----�Ⓚ�����`���]�T�ŕۑ��ł���B�Ȃ�قǁu�①�ɂ͐V�����ق����悢�v
�̂��B
�����炬������B�����̋C���̓}�C�i�X8���A���N��Ԗڂ̊����B
���R�̕�炵575 2021.2.28
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 ������ �@�@�@���C���x���g�E�A�[���[�Z���Z�[�V����
������ �@�@�@���C���x���g�E�A�[���[�Z���Z�[�V����
�@�@�@�@

���N�A���N�Ɠ������ɉԂ��J�����B�ڂ݂��c��ݎn�߂�ƁA�Ԍs�������L������t�z�̌��𗁂т悤�Ƃ��Ă���B�������邩�̂悤�ɑ��̏ꏊ��������F���Ԃ���ɕ����オ���Ă����B�t�͉��F�Ɏn�܂�B
�Q��O�̂��܂��Ȃ��ɁA���́w�L�т��x���ɒu���Ă���B
���炵���L�̎ʐ^�����Ȃ���A�q���̂��납�玔�������Ă����L�̎d���̂���₱�����l���Ă���ƁA�̂��g�����Ȃ��Ă悭�����B
������ɗ��ĕ�炵�ɔL���s�����Ă��邪�A���̎q�̍Ō�܂ŐӔC�����Ȃ����炢�܂���L�������Ȃ��B
�ŁA�l�������Ƃ�---�B
�ߏ��̎�v�w�Ɂu�L�����āB���s�֍s���Ȃ�����H�@�_���H�@���̎��͎��������b���邩��A���肢�v�Ɣ���̂͂ǂ����Ȃ��H
�u���ɂ�A���Ɏ����Ƃ�����E�̎q�������H���̔����q�������H�v�Ƒ��_�Ƙb���A�L�̂����炵��z�����Ă��钩�B�O�͉�Â�����ł����Ⴊ������Ă���B |
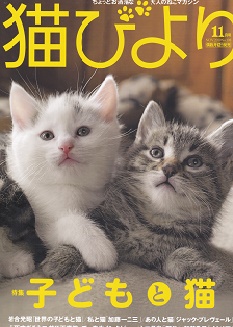 |
���R�̕�炵574 2021.2.24
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
�@
 �͂邩�ȓ��A������ Allá
lejos y hace tiempo.
�͂邩�ȓ��A������ Allá
lejos y hace tiempo.
 |
����Ԃ������������I�ȁu���H���炵�̊فv�́A��������150�N�O�Ɍ��Ă�ꂽ�_�Ƃ��ڒz�ۑ����A�_��ƂɎg���Ă����������p��W������Ă���L�O�فB�����̏Z���Ɛ����l���̈ڂ�ς������邱�Ƃ��ł���B�G�߂��獡�͐����肪�W������Ă���
�@
���~�̕Ћ��ɒu���Ă��������̒��F���|���v���������Ƃ���ɁA���̉�����N���オ���Ă���������B
���ꂪ���̂Ȃ����̂��Ă���B
���̎K�т��|���v��ʂ��āA�����ߋ��̖����̏K�����������Ƃ��v���o�������炾�B |
���Ƃ͒����R�n�̎R�����́A�쐼�ɍL����J�������낷�ꏊ�ɂ������B���Ɍb�܂ꂸ�Ƃ���20���قǗ��ꂽ�~�n�̋��Ɉ�˂��@��A��������Ɖ��ɐ��������Ă����B
��˂Ɏ蓮�̗g���E�����\�ȃ|���v�����t���A�R���[�g����ɃR���N���[�g�̃^���N�i�����߁j��ݒu���A�g�������^���N�Ɍq���ł����B�^���N�ɗ��܂��������A�n���ɖ��݂����p�C�v��ʂ��ĉ��~���̑䏊�╗�C�ɋ�������d�g�݂ɂȂ��Ă����B�������ȈՐ����V�X�e���Ƃ����킯���B
���̃V�X�e�����l�������̂́A���ېV�シ���ɐ��܂ꂽ�c�����B�ɂ������Ƃɂǂ������l�����������A�̋��𗣂�Ē������ɂ͔��R�Ƃ��Ȃ��B���������ʋZ�p��g�ɂ��A�y�؍H���̏p�ɒ����A�Ȃ������������̂ɂ���Ƃ����}���`�Ȑl�Ԃ������悤���B����̍�����d���Ŕh�����ꂽ����A�����̏����̖��������c��Ɍ����߂��A�킪�܂܂ȑc��̌����Ȃ�ɒ�Z���邱�ƂɂȂ����ƕ����Ă���B20���I�����ɑ��ŏ��߂Ď��]�Ԃ��w�����ď��A�����n�������f����|������~�݂��ׂ��^�����Ď��������A
�c����R������A���ŋߗׂ̏��[�i�����j�Ɏ���o���ĕ��c���������肵���~�j�~�j�p�Z����̂悤�Ȑl���������炵���B
�_�Ƃ̎d���ɂ͐肪�Ȃ��B�q�ǂ������͂��ꂼ��Ɏd����^�����A���̎d���͐�������ɂ��������Ď���ɓ���A�̗͂��K�v�Ȃ��̂ɂȂ��Ă����Ă����B
����͊ȒP�ȑ|���Ɏn�܂�A�����݁A�_��Ƃ̎�`���Ɛi�݁A�q���ɂƂ��Ă͈�ԓ���H���̏����ɏI���B���w���̂��뎄�ɗ^����ꂽ�̂́A�܂����O�a�y�̑|���A������
�܉E�q�啗�C�̊��������邱�Ƃ������B
�摜�ŕ�����悤�Ƀ|���v�̏㕔���L���J���Ă���B�����Ƀo�P�c��t�قǂ̐������A��������㉺�����邱�ƂŊW�ɂȂ�����ʂ��㉺����B�A�����Ĉ�˂̒��ɐL�т��p�C�v�̒����^��ɋ߂��Ȃ�A�����茳�܂ň����グ�Ă����B���S�C�̌����Ɠ������B��������ɐ��𗬂����Ƃ͂ł��邪�A���ɕK�v�Ƃ��ꂽ�̂́A�㕔�R���[�g���ɂ���^���N����t�ɂ��邱�Ƃ������B
��t�ɂ���ɂ͎�������㉺�ɂQ�O�O�������Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���q�̌������̂܂܂ŁA������̒[�����ƁA�����R���ݏグ�邱�Ƃ��ł���B�Ƃ��낪�����w�䂪�P�Q�O�Z���`�قǂ̃`�r���������́A������̔����̏��ɂ܂ł����肪�͂��Ȃ��B������K���A
��яオ���Ă݂���Ԃ牺���Ă݂���A�͂܂����ɉ��J�E���g���Ȃ���撣��----�B
�~�͂ƌ����������|���v���g�������Ă��܂��B��ʂɓ������ėZ�������Ƃ��琅���݂͎n�܂����B�������A���̃V�X�e�������邾���܂��ȕ��ŁA�q���̂���͗N��������ł��ė��߂���A��ׂŋ��ݏグ���肵�Ă����Ƃ����������炢������B
�i���Z���ɂȂ��āj
�̈�̎��ԂɁA�l�����߂Ă̈��͌����Ȃ�̂��̂��������B�����Ő搶�⋉�F�����������ƂɁA���̍��E�̘r�̈��͂́A����40kg���������I�ؚ��Ȑl�͂P�T�s���炢�����Ȃ������̂�����A����͏��̎q�ɂ���܂��������ׂ������̂悤���B
�������A���̂��̗��r�͂��̎K�т��|���v�Œb����ꂽ�̂��A�Ɣ[��������ꂽ�̂������B
���̐̂͂���ȘJ�������Đ��Ă����̂��Ɗ��S�Ԃ���
�B�Ⴍ���ĖS���Ȃ�����e��A�Ȃ̖��̕����������������e�Ɋ��ӂ��ׂ����낤�B�������ō�����֎Ԃɐ�؍ނ��ڂ��ă`�������ƒ���ړ��ł��邵�A�d���X�[�c�P�[�X���^�Ԃ��Ƃ��ł���̂�����B
���R�̕�炵573 2021.2.22
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �̂ǂ��Ɖ߂���
�n�k����O���o�����B
�̂ǂ��Ɖ߂���
�n�k����O���o�����B
�Ƌ�̓]�|�h�~��͍ς�ł���B��펞�����o�����X�g�ƍs�����X�g�̓N���[�[�b�g�̒��ɓ\���Ă���B
�������̔��~�̓^���N���܂߂��700L�A���d�r�A�}�b�`�ȂǑ����Ă���B�g�C���͒���@������B��g��œ��������Ǝϐ������ł���B����͓c�ɕ�炵�Ȃ�ł͂̂��́B
�����ǁA���ƖY����ۂ����Ƃ��B���������̖�̂��Ƃ�Y��Ă����B����Ȃ��l�Ԃ��B����l�Ԃ͒���Ȃ����̂Ȃ̂��B
�����̂��Ƃ����l����̂͗ǂ��Ȃ��B�̎����Ȃ̂ɓ��k�V�������^�s���Ă��Ȃ��B���N�̎��͐V�e�X�g�A�R���i�ЁA�����Ēn�k�ƍГ�������ǁA�������̌o���������̐g�̂����Ŕ��y���鎞������A�Ɖ����������B
�l���Ă݂�ƍ���̈�Ԃ̖��́u�ÈŁv�Ɓu��d�v�������B
��_�W�H��k�ЁA���k��k�Ћ��ɖ��邢���ԂɋN�������炻�̌�̑Ή����ł�������ǁA����̒n�k�͐^�钆�ɋ߂��A���ꂱ���u�����̈Łv�ƌĂԂ̂��A�Ɩ��ȂƂ���Ŋ��S�����B����̂͐����肾���B
���Ɣ��d�@�ɂ��Ē��ׂĂ݂��B�@��ɂ���Ă͌��z��@����h�@�ɔ�����悤���B�R���Ƃ��ĈȑO�͌y���������������A���܂�K�X�J�Z�b�g���g����@�������悤���B�C���o�[�^�[���̋@�������B�d�������肵�Ă��āA�ƒ����Ƃɉ����ăp�\�R�����g����炵���B�l�i�͂�����܂��܂ŁA
����ɒ���I�Ɏ����^�]���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���\�����e�i���X��Ƃ���ςȂ悤���B
��펞�ɋN���肤��S�Ăɔ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�o�����X����---�Ǝv���B
�ߑO�V�����A�H����ۂ�Ȃ��瑊�_�Ƙb�����B�����A���������^�n�k�A���邢�͈�s�O��������ő�n�k���N������A�����͂ǂ��������炢���̂����B�@���Ԃ��Ɖ��肵�Ă܂��A
�@�@�K�\�����^���ɂ���B�i���������炢�����^���ɂ��悤�j
�@�@�H�����o���ɍs���B
�@�@���������낵�Ă���----�J�[�h���g���Ȃ��Ȃ邩������Ȃ�����B
����Ȋy�����Ȃ���b�����킵���B
�i�����́B�^���ɏZ��ł������A���Ƃ̐퓬��Ԃɑ����������Ƃ��������B�F�l�m�l�̂��A�ꍇ���ɒ������߂��������B
�p�S�[���̂͐����̂��̂��A�������ً̋}���Ԃ��o���������炩�B�j
���炾��Ɠߐ{�R�̐��n�������Ă����A�N�����\�ɏo�Ă�����ɖ��N����������B
���̂����̓I�I�n�N�`���E�B�����������ǂ��炩�������ƃn�[�g�}�[�N�ɂȂ����̂ɁB
���낻��k�A�s�̎����ɓ���B�n�N�`���E�������_�C�G�b�g���A�������̔�s�ɔ����ċg�����n�߂�̂��R�����炢����B
����܂ŋ��N�̉Đ��܂�̎q�ǂ��̔������A�e�Ɠ������炢�̑̂ɐ����ł���������B |
 |
���R�̕�炵572 2021.2.17
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
�@
 2021�N2��13���@�ߌ�11��08���@�n�k�u���@�l7.3 �@�@�k�x5��������
2021�N2��13���@�ߌ�11��08���@�n�k�u���@�l7.3 �@�@�k�x5��������
�E�Q�����Ă����Ƃ���������Ȃ�̗h��Ŕ�ыN���A�R���g���[���Ɏ��L���ăe���r�̃X�C�b�`����ꂽ���A
�@��u�m�g�j�̉�ʂ��o�Ă̂���d�����B
�E�Èł̂Ȃ��A�R���g���[������ɂ����܂܁A�ǂɗ�������ėh�ꂪ���܂�̂�҂����B
�E�͂��߂�20�b�͔����Ȃ��ėh��A����ɑ���30�b�̓s�b�`�ׂ̍�����⋭�����ėh��B
�E����10�b�ԁA�傫�ȏc�h��B
�E���̌��10�b�Ԃ͑傫�ȏc�h��ɁA�g��̉��h�ꂪ��������B
�@���傤�ǃG���x�[�^�[�ɏ���ď㉺���鎞�Ɋ����镂�g���Ɏ��Ă����B�ӂ킟�ӂ킟�B
�E�����炭1���߂��h�ꂽ���낤�B���k��k�Ђ̎��͂R�����h�ꂽ�̂ŁA������v���ƒZ���B
�E�����d���ɓ������A����𗊂�ɂ낤��������C�̂悤�ɉ��{�����Ă��B
�E�茳���Â����A���W�I���o���Ă��ēd�r��g�ݍ��݃j���[�X�������A����قǑ傫�Ȓn�k�ł͂Ȃ��悤
�@�Ȃ̂ň��S����B
�E���邾���̗e��Ɉ��p���𗭂߂��B���p�̐��̔��~��2�k�~12�{����B
�E�Ⓚ�ɁA�①�ɂ̃h�A���J���Ȃ��łƌ����Ă������B
�E�g�C���p�Ƃ��Ă����C�̃o�X�^�u�����ς��ɐ��𗭂߂��B��400�k�B
�E�V���b�^�[���グ�āA���ӂ̗l�q�������������A�h�ЃT�C�����͕��������A�Â܂�Ԃ����܂܁B
�@�@���ƂĂ��Y�킾�����B���̋�35�����炢�̂��Ⴂ�ꏊ�ɃI���I�����̎O�c�����������B
�E11��55���A��肠�������v�Ȃ悤�Ȃ̂ŁA�Q�悤���B�Q�悤�B
�E�ߑO�Q��48���A��2���Ԕ��̒�d�̌�A�p���p���p�[���ƃC���^�[�t�H���̉������Ēʓd�����B�����A�������B
�E���邭�Ȃ��āA�Ƃ̎��͂��m�F�����B�����������B
�n�k���N���Ă���ʓd���A��������܂ʼn��������̂�����Y�^�Ƃ��ď����Ă������Ƃɂ���B��_�W�H��k�ЁA���k��k�Ђƌo���������A�h��͍���ԏ������Ƃ������̂́A��d�Ő^���ÂƂ�����
�ɂ́A�s�����������Ă���B
��펞�ɍs�����ׂ����ƂƁA�����o�����X�g�͏������Ă��邪�A��������悤�ȏꍇ�A���̃��X�g�ʂ�ɓ����邩�A���߂čl���Ă݂��B�ǂ���������������Ȃ��B���������ӎu�Ȃ�̗͂��K�v�ɂȂ�Ɗ������n�k�̎��̒��������B
�y���ȁz
���W�I�ƈꏏ�ɕۑ������������V�i�̊��d�r�̃p�b�N����菜���Ă��Ȃ������̂ŁA��Ԏ�����B�����d�������ƂQ����̂ɁA�X�C�ɗ����Ă��܂����B�ł����h���̂����Ă���ƁA���_�����܂��āA���������B
�ʓd�Ђ̂��Ƃ�Y��āA������m�F���Ȃ������B�e�����Ɩ����ɉ����d�����K�v�B�@
�y��閾���āz
�n�k���������̂m�g�j�j���[�X���Ă��Ă͕�����Ȃ������B���҂����o�Ȃ�����������̒n�k�ő����Ȕ�Q���������悤���B�V�����A�ݗ������^�s��~�ɂȂ�A�f�����d���L��ɂ킽���ċN�������悤���B���₲�a�l��������Ƒ������邾�낤�B�����A�������肤����B
�ߏ��ɏZ�ވ�l��炵�̗F�l�̂��@�����������ɍs�����B�݂��ɖ������m�F�������A�F�l�̋{�錧�ɂ��邲���Ƃ͂�͂��Q�ɑ������炵�����A�u���k��k�Ђقǂł͂Ȃ��v�Ƃ̂��ƁB
�F�l�Ƙb�����B�u�V���b�^�[���J���ĊO��������A�������ʐ^���ÁB�ł�����l�ł͂Ȃ��āA�݂�Ȃ���d�ō���Ȃ�A�ꏏ�ɍ�������Ǝv������--�v�u�������A�������ˁv�B
���R�̕�炵571 2021.2.14
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �Ԃ����̂�����
�Ԃ����̂�����
�Ԃ����̂����Ƃ̂悤�ɁA�s���N�ŏ_�炩�ŁA
�L����̓����݂����ɂӂ�ӂ킵�Ă���B
���N�̂����ƁA���̂����ƁB
�����Ȃ�ƁA�J�T�J�T����肶��肵�āA
�X�g�b�L���O�𗚂�����
�����Ƃ����Ԃɓ`�����Ă��܂��B
����Ȃ����Ƃ��A���҂��҂��B
���@�Z�����̂������B
�ɂ���ɂ���A�����Ⴎ���Ⴕ�āA��G��͈�������
�������̈�T�ԂŁA���̔��̂悤�Ȃ����Ƃ�
�}�V���}���̂悤�Ȃ����ƂɂȂ����B |
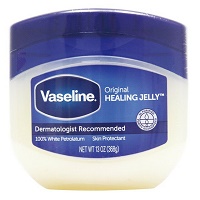
�摜�͊y�V���炨�肵�܂����B |
���R�̕�炵570 2021.2.13
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �@�V�C�^�P�������� �@�V�C�^�P��������
 |
�~���i�ǂj�ł��B
�߂��ɂ͔���������܂��B
���̂܂܂��ƐH���͂قƂ�ǂ���сB
��ɓ����ɂ͑傫�ڂɁA���X�`�p�ɂ͍א�ɂ��ėⓀ����Ɩ����ς��Ȃ��B
���Ƌۏ��͔|�B���V�C�^�P�̖��̗ǂ��Ƃ�����I
�@ |
���N���O�܂ŁA��̎����|���Ď��O�̃V�C�^�P���͔|���Ă����B
�ʐ�i�P���ɐ�j�͂�t�̒��ɕ�����@�V�C�^�P�̋��ł����ށ@�Q�����@���ĂĎ��X��������---���̎菇�ŁB
�H�ׂ���Ȃ��قǂ̃V�C�^�P���o�Ă��āA�ߏ��ɔz���ĕ�����------���̍��̓V�C�^�P�O���ɖZ���������B |
���k��k�Ђ̉e���ŁA���s�ł͌��؍͔|�̃V�C�^�P��
�A���˔\�����Z�x�̊���Ă���̂ŏo�ׂł��Ȃ��B�y��ɟ��ݍ����˔\���A�т̒��̌͂�t���ςݏd�Ȃ������t�y�ɒ~�ς��Ďc��A�e�����o�Ă���B����n����w�肵�A���̒��͔̍|�_�Ƃ̂�����
���ł�����I�[�o�[�����ꍇ�A�A�ѐӔC���i�Ёj���ďo����߂ɂȂ�B
���̐��N�A����ƌʔ_�Ƃ��ƂɌ������s���A�ׂ̎s�ł悤�₭�o�ׂł���_�Ƃ��o�Ă����B���̃V�C�^�P�ׂ͗̎s�܂ŏo�����Ĕ������߂����́B
�ق��A�ڂ�O�t�Ȃǂ����̗J���ڂɑ����B�t�̖��͎����œE�݂ɍs�������Ȃ��悤���B
 �@ �@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
2021.2.�Ȗ،�HP
���R�̕�炵569 2021.2.8
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �@�_�C�������h
�E�v�����Z�X�ɏ�肻���˂� �@�_�C�������h
�E�v�����Z�X�ɏ�肻���˂�
���t���߂��Ă��Q���̓ߐ{�͂܂��܂��~�̐^������B���͗뉺���x�ɂ܂ʼn�����A��̎d���͂ł��Ȃ��B���R�ɂ���l�Ƃ��a�������Q���A���܂��ɓ���Ⴂ�Ƃ������Ƃ������āA�~���ɏo�悤�Ƙb����v�����͈̂��N12�����߂̒��̂��Ƃ������B
�ǂ��炩�炾�������u�������N���[�Y�D�ɏ���Ēg�����Ƃ���ւ������v�Ƙb���͏����ɐi�݁A�c�A�[�̒T���͎��̎d���ɂȂ����B�o���͂P�����{�A�A���͂Q�����{�ɁB
���l�̊X����x���Ă݂����A���؊X�Ńv���̖������\���悤----�O��������đI�̂́A
�u���l����I�ɔ������߂���A���`�܂ʼn�������c�A�[�ŏ�D�\��̑D�̓_�C�������h�v�����Z�X�B�����͂Q�T�ԁB
�@�@�@
2020�N�����߂��܂ł̐��T�ԁA���̒��̃o�[�`�����ȗ����y����A���Ԃ����������Ȃ����B��͂藷������������A���`�͂��łɍs�������Ƃ�����B����ȗ��R��t���ė\��͂܂����������\����L�����Z�������B
����ɕv�͐��������B�u���v�������ɂȂ�����A�ǂ����悤�H�v��k�Ɂu�����C�ɓ����o���ꂽ��A�Ȃ�ׂ��D���痣��ė����j�����Ȃ���̗͂̏��Ղ�h���B��э��ނƂ��ɂȂɂ��������̂��������ق��������B���ݑ܂ł��������ǁB�����ւ͔�э���ő̂������Ă��Ă����C������B�O�̂��ߔ�э��ނ̂͑������A�����炾�Ǝ�̍���܂��B�v�ƌ������̂��L�����Z���̌㉟���������̂�---�B
�����Ē��߂���Ȃ��Q���A�_�C�������h�v�����Z�X���̉^���͂��̒ʂ�B
����̂��Ƃ������B�v�̊w������̗F�l�����[���𑗂��Ă����B
�ނ͒��N�N���X��̊����������Ă���Ă������Ȑl�B
�u�Ȃ���N�㔼����F�m�ǂ������A�I���Ƃ��邱�Ƃ��ł��Ȃ���Ԃł��B���̖Y�ꂪ�Ђǂ��Ȃ�A���f�\�͂��ቺ���Ă��܂����B��l�Ő������邱�Ƃ͍���ɂȂ�܂����B���������ăN���X��͋x����Ă��������B�v
���������e�������B
�u�܂��A�Q���ł����ԂɂȂ�܂�����A���A�ł���悤�މ�ł͂Ȃ��x��Ƃ����Ē�������---�v
���̈Ӗ�������̂́A�ǂ������Ȃ̂��A�F�m�lj����߂�����{�̏��l����ƁA�����錾�t���Ȃ��B
�Ȃ���p���Ȃ�������A�������̓����p�ӂ���A�ǂꂩ��I�ԂƐV�����i�F�������A����ɕ��R�ȓ��������Ԕ��ɂ����ĕ��ꍞ�߂�A�Ƃ����N��Ŗ����Ȃ����B���ꂽ�w偂̑��̂悤�ȁA���킴�킵�����������Ă���̂��������B���̒w偂̑��̂ǂ������A������������Ȃ�������Ă��āA�Ђ���Ɠ��݊O���Ɠޗ��̒ꂩ������Ȃ��B��Ԃ����قƂ��l���w偂̎��𐂂炵�Ă����A�Ȃ�Ă��Ƃ͋N�������ɂȂ����A�����������ɑ����w偂̎������^�V�A���Ă��܂���������Ȃ��B
�@
�����͗��t�B�@�_���̋N�_�̓��B�@�O�͐Ⴞ�B�@�ǙT�̓��̂��������ĐH�ׂĂ���B
�@
�@�@�@�@�@���R�̕�炵568
2021.2.3
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
�@
 ���ł̂₢�@------�@�o���͈ɉꗬ�E�҂̗�
���ł̂₢�@------�@�o���͈ɉꗬ�E�҂̗�

�@
 |
���̕t���Ă��Ȃ��Y�_�����D���B�L���b�v���Ђ˂�ƃV���p�[���ƒY�_����юU��B���̑u�₩������D���B��x�Ɉ��߂Ȃ����������������
�߂ė①�ɂɕۑ����Ă����A�c������ނ܂Łu�����Y�_��������v�Ƃ��������������K���ȋC���ł�����B
�i�䂪�Ƃ̗①�ɂ�25�N�O�̃��B���e�[�W���́B��₷���ƂɈꐶ�����ŁA�_�C������ɃZ�b�g���Ă����Ă��A�①���̂��̂����̊Ԃɂ������Ă����肷��B�����ƁA�����ň����������Ɨ①��
���@�����������Č̏Ⴕ�������B�����߂͂�߂悤�j�B
���C�ɓ���͈ɉ�̓V�R���i���j���B
�l�[�~���O�������ȁB�����ɂ����@��������ꂽ�悤�Ɍ��C�ɂȂ肻��������B
���̑̑��̂��ƁA�①���Ɂi�����|����
�j�u�����c�蔼���̃y�b�g�{�g��������ƁA�₦�����Ă�������Ă����A��������ɑꂪ�����悤�ɁB�Ȃ��͂܂�ł��B��[�̓V���V�����Ɛ���Ă���B���A�ʔ����`�Ƃ����̂܂܈���ł��܂�����-----�B
���̂��̐�[���A�̂ǂ̉��Ɏh�����Ă��܂����ł͂Ȃ����B
�������A�����̂ށA�����~�܂�A������������A���܂������A�V����-----
�т�����̌��t���W�߂Ă݂Ă��A���̎��̋��������܂�\���ł������ɂ��Ȃ��B
��ÂɂȂ��čl����A���������ނƂ��̉��ŗZ�����Ƃ��B������ł����@�����肻�������A���v���o���Ă��Q�Ăӂ��߂��A�������������������o���Ă��Ȃ��B
���������^�V�A�u���������ΕX�ŎE�l�������v�Ȃ�ăh���}�������Ɛ̂Ɍ������Ƃ��������ȁA�Ǝv���o���A�����J�Ƀl�b�g�Ō������Ă݂��B
�����Ɏ~�߂��Ԃ̃X�g�b�p�[���A���͕X�������B�Ƃ����l�^�������B
�ǂ����������z������l�����{�ɂ����悤�ŁA�F�X�Ȏ��������Đ�����X�̋������v���Ă݂�A�Ƃ������L����
�������������B
������D��S�������Ă����^�V�A���̕X������Ė����Ă݂�Ƃ��������͂��Ȃ����낤�ȁA���Ȃ���ˁB
����A���Ȃ���B
�@ |
**
2021.1.30�@�s���Ŋ����҂��v78�l�ɂ܂ő����Ă����B�N������N�n�ɂ����Ă̑����������Ɍ������B�l���ɑ��銴���Ґ��̊����́A
��N��ʂ��Ė�1500�l�Ɉ�l�B���̊�����傫���Ƃ݂邩�A�܂��܂����S�ƌ��邩�́A���̐l�̐��i�ɂ�邾�낤�B
�����A�s�̂g�o�Łu100�Έȏ�̏��������������v�Ƃ̕������Ă���Ă��B�F�l�̂��ꂳ���傤�ǂ��̔N��Ȃ̂ŁA�X���ɂȂ�̂�҂����˂ēd�b���Ă݂���A���C���Ƃ̂��ƁB���S�����B����ǂ����s���̂ǂ����ŊY�����鏗�����ꂵ��ł���Ƒz������ƐȂ��Ȃ�B
�@�@�@�@ ���R�̕�炵567
2021.1.30
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �@���_���Z�܂��̂́u�O���[���Q�C�u���X�v
�@���_���Z�܂��̂́u�O���[���Q�C�u���X�v
�z�̌����͂˕Ԃ��Ȃ���x��悤�ɔ�ь����A��ɂ��߂��V�W���J���͂킪�Ƃ̎��_�B�a���̎c���̂悤�ɁA�V�����H��̂悤�ɁA������Α�����قNJ������B�t�ފ݂��߂�������Ɉ�x�ڂ̕���������̂ŁA�V�����Z�܂����������Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ������ɂ����B���炵�^�]�ƌ����킯���B
�V�W���E�J���́A���t���߂����r�����L�юn�߂邱�납��A�����ő��̏ꏊ���A��@�A�Őf���Ĕ�щ��B���Ă���Ƃ܂��Y�������ɓ���A���ɂ��鎓�i�ȁj�ɏ���A���k���Ă���B�z�E�����\�E���̂���
�B
*�@�X�Y���ƃV�W���E�J�����r����ƁA���X�Y���̕����̂��傫���ċC�����r���A�����̓�����������̕����ɍ���Ȃ��ƂȂ�ƁA�{�苶���Ė\����f���\�͂��ӂ邤�̂ł��B�v���ʂ�ɂȂ�Ȃ��ƁA���ɂ͕��Q�߂������Ƃ܂ł��ł����̂ŁA�V�W���E�J���̈琗���Ԓ��͋C�̋x�܂�Ђ܂�����܂���B
�X�Y�����ǂ�ȍs���ɑ��邩�́A���̃y�[�W�̉��̕��ɂ���A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���R�̕�炵519�@�@2020.6.13�@�u�X�Y���̂����߂ɑς����˂āv
�����ɏڂ��������Ă��܂��B�����̂�����͓ǂ�ł��������B�V�W���E�J���͂��l�D��������̂ł��B
 �~���ł��Ȃ������̂��A�N�}�o�v�@----�@����V���@2021.1.23�̋L�����
�~���ł��Ȃ������̂��A�N�}�o�v�@----�@����V���@2021.1.23�̋L�����
22���ߑO�V��15������A�Z�s�̎R�тŃN�}��ڌ������ƁA�ԂŒʋΓr���̒j�����x�@���ɒʕ��B�����R���ۂɂ��ƁA�ʏ�N�}��11������S���̊Ԃ͓~�����Ă���Ƃ���A���ۂ́u�h�{�s���œ~�����x��Ă��邩������Ȃ��v�Ƃ��Ă���B
�����ɂ��ƁA�N�}�̑̒��͖�50�Z���`�B������ӂɂ͖��Ƃ��_�݂��Ă���B�ڌ���A�N�}�͗����������Ƃ����B
�N�}�̎�ȃG�T�ƂȂ�h���O�����s�삾�������߁A���ۂ͍�N�X���A�N�}�̏o�v����11���܂ő����\��������ƒ��ӊ��N���Ă����B���ۂ́u�X�тȂǃN�}���������ȏꏊ�ł͋C�����Ăق����v�Ƃ��Ă���B19�N�P���ɂ͑����s���ŃN�}���ڌ����ꂽ�Ⴊ����B |
�F���ڌ����ꂽ�u�v�́A�אڂ��鎚�̖��O�ŁA�Ƃ���̋�����3�L������T�L���B�т͌q�����Ă���̂ŁA��Ɍ���Ȃ��Ƃ�����Ȃ��B�������ɍ�N�̏H�͍��܂łɂȂ������قǂ̕s�삾�����B�т̒��̓��H������ƁA�����Ȃ玊�鏊�ɂǂ肪�����Ă��āA���̗����c�{��������Ă��邩�̂悤�ɒɂ��̂ɁA
�y�ɐG�炸�ɗ����ŕ����邭�炢�������B
�̒�50�Z���`�ƌ����A�t���܂�̎q�F���A�Ă��z���Ă��H���s���ł��̂܂ܐ��b�ɂ܂Ő������Ȃ�����
�̂��낤�B�ܔM�̉Ă��ŕ����A�H�ɂ͗���ɂ��Ă����ǂ�̎��ɗ����A���ܐϐ�10�Z���`�̂Ȃ��ŁA�ǂ�����Đ������тĂ���̂��낤�B
�~���ł��Ȃ��F���~�̗т̐�����������a�����߂Ă�����Ă���----�����ɂ����g���̉e�����łĂ���̂��B
���Ƃ��Ɓu�F���������Ă����F���g�̂��߂̏ꏊ�v��l�Ԃ���J���i�o�������炱���A�s����̖����Ȃ����F�����R�ɍ~��Ă���̂��B
�@
���R�̕�炵566 2021.1.27
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
�@
 ���ƂP�O���ŏt�����̂�����
���ƂP�O���ŏt�����̂�����
 �P��22���@�����I������
�P��22���@�����I������
�����̓}�C�i�X�T���B�܂��܂��̊������B
���H���ς܂����_��������Ɛ^�ʖڂȊ�ł����������B
�u�l�A����V�����H����Ă�����āA�ƂĂ��������v�B���₨��B
�u�_�C���̎w�ւȂ���Ȃ��ȁv�Ƃ����ȂƁA�H�����ɓ���Ċ�ԕv��------���̑g�ݍ��킹�͓����n���̐l�ԂȂ̂��B�����炵���Ԃ���̂��B�@�i������
�̂̓J�[�{���t�@�C�o�[���̃m�M�X�i�v����j�Ǝ��m�R�j
 �P��21���@�c��ڂɔ�����
�P��21���@�c��ڂɔ�����
�ߐ{�̎R���璷����������邱�ƂP�O�L���A���n�̈�Ԓ[�܂ŗp�����ɏo���������B�����ɐ�������ߐ{�A�R��������ꏊ�ŁA�ߖ��グ���B
�u�~�߂āI�~�߂āA������荶�A���ɉ���āI�v

���ڂɂ̓w�C���[���i�q�������[����ɂ��ēc��ڂɕ��ׂĂ���j������������������ł���悤�Ɍ��������A�����݂͂�Ȕ����������B
�Ԃ��������Ɏ~�߂Ă��A�߂Â��Ă݂Ă��A�݂�Ȓm��������Ă���B���₢�≡�������Ă���̂͌h�����Ă��邩�炾���ǁB���̂����D��S�̋�����
�����肶��Ƃ��ɂ���Ă��āA������Řb�������Ă����B�u��v
���ɏZ��ł�������́A����������Ȃǖ��̒��̏o�����������B���̔������c��ڂ�400�H�߂�������B
��O�̓c��ڂɂ̓R�n�N�`���E�����ނ낵�A�������ɂ̓I�I�n�N�`���E���Q��𐬂��Ă���B�H������������A���Ⴊ��œy���@�肩��������B���܂����Ă݂���B����Ȍi�F��������Ȃ�čK���B
�������A�u�ɕ����Ԕ����v�Ƃ����������ɂ��X�e���I�^�C�v�̌i�F�ł͂Ȃ��āA�����h���h���ɉ����Ȃ���A�����q���̐V���H�ׂĂ���p�́A�����������Ă��ăt�c�[�̒��ƕς�肪�Ȃ��B
 �t���b�v�i�r�j�������Ē������� �t���b�v�i�r�j�������Ē�������
 �P��20���@�������@�}�C�i�X�X��
�P��20���@�������@�}�C�i�X�X��
�g�i���S���́u�������v���v���o�����ЂƁA�n�C�^�b�`���܂��傤�B���̉̂��āA�c�ɂ̒��̊�����ς��E��ł���������v���o���B�������L���Ƃ̒��͊����͂ЂƂ����₦���Ă��āA�䏊�ɕX���������̂�����B�c��������p�ɐݒu���������͓���t���A�����Ђ˂��Ă��o�Ă��Ȃ��B���𗭂߂Ă���傫�ȃ^���N�ɕ��ۂ�˂����݁A�\�ʂ̕X�������Đ��ʊ�ɐ������A�X�̍��Ԃ�D���Ď����������Ă����B���̌�̊�Ƃ�����n�C�W�ɕ����Ȃ����炢�܂��������B�����A���w�����j�B
���̈�T�Ԃ́A���ɒ��̋C�����o���������Ƃ��Ȃ��قǒႢ�B���Ȃ݂ɌߑO�U���P�T���A�N�����̊O�C������T�ԕ����ς���ƁA�}�C�i�X5���B
����ȓ~�͒m��Ȃ��B��͂ق�̂�����Ƃ����~��A�����͂ǂ�����B�ʔ����Ȃ��B
 �P��19���@�\�[�V�����E�f�B�X�^���V���O
�P��19���@�\�[�V�����E�f�B�X�^���V���O
������̂��Ƃ��Î��������Ă���ƁA���̖�肪���̒��ɑ��B���A���m�Ȏp�𑨂��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă���悤�ȋC������B
���݂̏��������B������R���i�����ǂ̃j���[�X�����������A�����Ґ��̑����Ɉ���J���Ă���ƁA�܂�ŃR���i�Ђ̂Ȃ��ł��������Ă���C�ɂȂ��Ă����B
���������͓��R�̋`�������A�����̐l���ɂ͂���ȊO�̕���������B�R���i�Ђ̍Œ��ɁA���邢�͂��̌�ɂǂ��������������邩���l���邱�Ƃ��厖���낤�B
�\�[�V�����f�B�X�^���V���O----���l�Ƃ̋��������B---- �����̐��_�̂Ȃ��ŁA������Ƃ̋������͂���B
�o�����X��Y��Ȃ��悤�ɂ��悤
���R�̕�炵564 2021.1.22
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 ���ꂩ��Q�U�N�ɂȂ�B
���ꂩ��Q�U�N�ɂȂ�B
��_�W�H��k�Жu���@1995�N1��17���@�ߑO5��46��52�b�@�]���҂�6,434�l
�����A���̎��Ԃɖڂ��J���Ďv���o���Ă����B
�����ł��܂��Â��A���łƂ������Ȃ��T���S�U���B�ˑR�˂��グ��悤�Ȓn�k���N�����B���̌�̉E�������Ԃ�́A���܂��炱�Ƃ����������Ȃ��B��������A�v�̎d�������Z���ɂ߂�P�����A�ǂ̂悤�ȏ�Ԃɂ��邩�͑z�����Ă������������Ȃ��B�����֑�n�k���N�����B
�Y��悤�Ƃ���قǎv�������B�߂��݂��ꂵ�݂��A����͐l���̑�햡�B�Î邱�Ƃ̓���͂��邪�A���̎v���o�����ɕ����Đ�����ق����y�ɂȂ�B�n�k�ɂ��ē`����ׂ����Ƃ͑�������ǁA������@�ɂQ�U�N�ԕ��Ă������Ƃ������Ă������ƍl�����B�����Ȃ��Ƃ��̎��̌Z�v�w�̓����͒N�̋L���ɂ��c��Ȃ����낤����B
�����R�n�̎R���Ɏ��̐��܂ꂽ��������B�N�V�����ƌ��������̐e�ʂ����l���Z��ł���B
���̂Ȃ��̏]�Z�̘b���������B�]�Z�ɂ͎q�����S�l�����B3�Ԗڂ̑��q�i�]���E���Ƃ������j�����̑�w�ɒʂ��A���ɂ̊C�����ɉ��h���Ă����B���̉��h�́A��シ���Ɍ��Ă�ꂽ�̂Ȃ���̖ؑ������Ɖ��ŁA���̒n�k�ɂ͂ЂƂ��܂���Ȃ����ꗎ�����Ƃ����B�����Č}�����Ⴗ���鎀�B
���O�̎�---�s�𗝂��B��T�Ԍ�ɂ͈����z���\�肾�����̂ɁB
���̍����̒��Ŏ��҂d�ɒ������Ƃ͂ƂĂ��ł��Ȃ��B
���Z���a�̎R�ɏZ��ł����B
�ړ������������ē��������Ȃ��]�Z����A�����āA�Z�v�w�͘a�̎R������������ŕ��ɂ̌���֍s���A���ꂫ�̒�����A�]����T���o�����B
�Z�v�w�͐l�ڂɗ����ʂ悤�A�ѕz�ɕ�����㕔���Ȃɉ������A�����Ȃ̂ɗ�[�������Ȃ��瑖�����B�R�z���͌��₪����̂ŕ��ɂ���܂������k��ڎw���A�R�A�̗�����T���Ȃ���ۈ�������āA�]�Z�̑҂Ƃ֑��q�����͂��邱�Ƃ��ł����B��e�͑��q�̋A���҂���сA��T�Ԃœ������^�����ɂȂ�����
��������B
���ꂫ�̂Ȃ��̂���̂��A�ǂ̂悤�Ɉ�������Ă����̂��B���S�f�f���͂ǂ������̂��B�⑰����̂��Ԃʼn^�Ԃ��Ǝ��̂́A�@���ɒ�G���Ȃ��Ƃ������̂́A��������댯������B
������S�ɁA�q�������̐e�ɕԂ������Ƃ����v���ŁA�Ђ�����߂������B���������A�R���z���悤�ƁB
���̈��@�����̒��A�삯������悤�ɉ߂����R���ԁB�Z�v�w�͂��̎������N���������A����ȏ��������Č��Ȃ������B
���̌Z���A���͂������̐��̂��̂ł͂Ȃ��B
���q�����������̕����A��N�S���Ȃ����B
�����{��k�Ё@2011�N�R���P�P���@�ߌ�Q��46��18�b�@�]���ҍs���s���Ҋ֘A���Ґ��Q���l�߂�
�㔼�l���̂Q���ǂ����̓�̑�n�k�B���݂R�ڂ��p�����B
�@�@ �@�@�@�@��̋��Ƀt�L�m�g�E�������� �@�@�@�@��̋��Ƀt�L�m�g�E��������
���R�̕�炵563 2021.1.17
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �I�`�̖����b
�I�`�̖����b
 |
 |
���������w�����Ă���̂��w���q�i���傢���j�B
���Ő�̂͐d�A����g����Ő܂�͕̂����A��G�c�ɑ傫���Ƒ����ŕ�������B
��������ꍇ�͔��N�Q�����Ċ������B�q�ǂ��̍��ɂ͊��������邽�߂̖؏������������B�����ɖ�ǔL���q�����Y���----���Ƃ�
�����L�т��B
�E�F���͂���Ȃɂ��V�����Ȕw���q�B |
�ނ����ނ����B
����Ƃ���ɂ�������Ƃ������Z��ł��܂����B������A����������͎R�֎Ċ���ɁA��������͐���ɏo�����܂����B
����������͔w���q�i���傢���j�����ς��ɎĂ�����A�d���ɂ�낯�Ȃ���ƂɋA����܂����B
�Ƃ��낪�A�����߂��Ƃ����̂ɁA�������ɐ���ɏo�������������A�܂��A���Ă��Ă��܂���B
����������́A��������̋A��������Ƒ҂��Ă��܂������A�����肪���Â��Ȃ��Ă��ẮA�������ɐS�z�ɂȂ��Ă��܂��B
��ւƉ���⓹���A�����̐���ɋC��t���Ȃ���A����������͂��������T���ɍs���܂����B
���낷���ف[�ف[�B�t�N���E�����Ă��܂��B
�������炨������ׂ�ɂ��Ⴊ�ݍ��݁A�������Ǝ�����Ă���̂������܂����B
�u�������A�Ȃɂ��Ă��H�@�܂��I���ւH�v
�u�������B����Ȃ��A�����炸���Ɛ��Ă����B�Ȃ�ł�������ւ�A������Ƃ��̉��ꂪ�����ւ�̂�v
�I�`�i�C�b�A�ł����B
���̏ꍇ�́u�Ċ���v�Ƃ́A���C�̕������ɂ�����A�䏊�Ŏϐ���������͘F���ŔR�₵���肷�镰�����W�߂邱�Ƃ������B���R�ɂ͓���n�������āA�W���̋������Y�Ƃ��ĊǗ�����Ă����B���邢�͂��̂���������́A���̗��R�𗘗p���钇�Ԃɓ���Ă��炦���A���l�̎R�ɗ����Ă���͂���E���W�߂Ă����̂�������Ȃ��B
�ߔN�����������Ă��Ȃ��Ȃ����̂́A���̗��R�̊Ǘ����s���͂��Ȃ��Ȃ������Ƃ������̈�炵���B���̒n�ɉz���Ă��ď��߂Ă̏H�A�ԏ��̎��͂�T���Ă��āA�n���̂ЂƂɏ�ꂽ�B�u���`��ȂƂ��ɐ�����Ƃ�v�B
�������A���܂��ɐ̂Ȃ���́u���R�̌b�݂͒n���̐l�̋��L���Y�B�����������͏����v�B���̊��K���c���Ă��āA�t�̎R��H�̃L�m�R�̎����ɂ́A���m��ʐl�����荞��ł��đ܂����ς����n���Ă���̂��������邱�Ƃ�����B��������̒�ɂ܂œ��荞�Ēm����B�����q�ƃL�m�R�̂�ɂ͏��ĂȂ��B
*
��N�̓��L�ɁA�����ɂ���u�h�q�����q�v�̖��X�̖��O���������菑���Ă��܂�����A���̂R�O����ɂ͂��̓X����u�����Ă��������v���[�����͂��A�l�b�g�̉�ʂ��J���邽�тɐ�`�摜�����M����Ă���悤�ɂȂ����B
����A�u����A�����Ȃ��v�Ə������̂ŁA���̂�����܂�����Ђ���̃v�����[�V�������[�����͂���������Ȃ��B���̊���̂��ƁA��V���{�b�g�����邮�����ď����W�߂Ă���炵���B
�@
���R�̕�炵562 2021.1.15
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �݂艺����ꂽ�Z�q�P
�݂艺����ꂽ�Z�q�P
�u���`��v�ƌ����Ėڂ��o�߂��B�܂̗����ЂƂӂ��j�Ɏc���Ă���B��̉����N�����̂��B
��u�����ɋꂵ���A�Èłɖڂ������ɂ��������Ďv���o�������Ƃ��������B
���̏�ɂ͎o���O�l����B���̂������T���炢���玚��ǂݎn�߁A���w�Z�ɓ��鍠�ɂ͂��łɂЂ炪�ȕ������炷��ǂ�ł����悤���B
�U�̎������������A�N�̗��ꂽ�o�������甃���Ă��Ă��ꂽ�G�{��ǂ�ő勃���ɋ������̂��B�����ċ����ė܂�����邭�炢�������B���܂�
���̊G�{�̐F��������A�G�{�����������̎�G��A��q�̊O�ɍL����H�̌i�F�܂Ŏv���o�����Ƃ��ł���B
�钆�ɋ����Ȃ���N�����̂́A�S�̒�̒�ɉB��Ă����L�����ł̂Ȃ�����h���Ă�������B����A���̊G�{�̌����}���قŎ�Ă��ēǂ��炾�낤�B
�@�@�@�@�@�w���{���b�I�x�؉������@��g���N���ɏ����@�w�Z�R�P�R�ƃA�}���W���N�x
�k�ނ����������Ƃ������Z��ł��܂����B�������͎R�֎Ă���ɁA�����͐���ɁB��ォ��Z������Ă��܂����B�Z�������A�����������A�������ƐH�ׂ悤�ƕ������ƁA�Ȃ���������������������̎q�����܂�Ă����̂ł��B�Z�q�P�Ɩ��t����ꂽ���̎q�͂₪�Ĕ��������ɂȂ�A�������ʼn̂��Ȃ�����ɋ@��D��悤�ɂȂ�܂����B
������A�������Ƃ����͉Z�q�P�Ɂu�N�����Ă��ˌ����J���Ă͂����Ȃ��v�ƌ��������A�P�̉œ��蓹����ɒ��֏o�����܂��B�Ƃ��낪�A�P�̓A�}���W���N�ɂ܂�܂��x����A�g����ݔ�����Ċ`�̖ɒ݂艺�����Ă��܂��܂��B�l
���{�e�n�ɓ����悤�Ȗ��b���c���Ă��āA���̂��Ƃ̓W�J�ɂ͂��낢��ȕω�������悤�����A���炷���͂����܂ł����o���Ă��Ȃ��B�����A�Z�q�P���������ł��킢�����ŁA�ꂵ���قNj��������Ƃ������L���Ɏc���Ă����B
 ���̏ꍇ�u�^�K�Z�v���B���܂ɓ��̉w�̂��X�ɏo��B�����������D���������B ���̏ꍇ�u�^�K�Z�v���B���܂ɓ��̉w�̂��X�ɏo��B�����������D���������B
���̖��b�́A�������A���̒����琶�܂ꂽ�����Y�`����A�o�_�_�b�̂Ȃ��̃��}�^�m�I���`�`���i---��ォ�產������Ă���-----�X�T�m�I�m�~�R�g�̓N�V�i�_�q�����~���A���㌕����ɓ����----�j�Ɏ��Ă���B�������ꑱ���Ă���A��ォ��쉺�ւƐl���̑厖������Ă���B���ꂪ�l�̐��̈ڂ낢�ɏd�Ȃ邩��B
���Ԃ͈꒼���ɗ���Ă��āA�����͂��̐���𖢗��Ɍ������ĕ����Ă���B�w�ɂ���͉̂ߋ����B���܂܂ł����l���Ă����B���Ԏ��ōl����ƁA�{���㗬�������ߋ��ŁA���ꂭ���鐅�������̎p���낤�B�����������Ƃ��̏�ɂƂǂ܂��Ă��āA�ڂ��㗬�Ɍ����Ă���ƁA����܂ł̃C���[�W�Ƃ��Ẳߋ��Ɩ������A���̗���̒��œ]�����āA�㗬�������̎p�Ɍ����Ă���B�����͉ߋ����B�V�������Ƃ͏�ɖ����������Ă���ƁB
�������猻�݁A�ߋ��ւƗ���鐅�����Ԃ͖������猻�݂ɗ���Ă��邱�Ƃ����������邾�����B
�@
�w�Z�R�P�R�ƃA�}���W���N�x�̌㔼�F
�y�P�͒��ǂ����Ă���j���g���A�Ƃ�сA�J���X�ɏ������܂����B���̂̂��A���҂ǂ�ɉœ��肵�āA�K���ɕ�炵�܂����z�Ƃ��B�߂ł����߂ł����B
�y�A�}�m�W���N�@�V�S�z
�@�E�킴�Ɛl�ɋt�炤����������l�B�ނ��܂���B�Ђ˂���ҁB
�@�E���Ԑ��b�ɏo�Ă��鈫���S�B���܂˂����܂��A���l�̐S��T��̂ɒ�����B���܂Ⴍ�B
�@�����Ƃ��ƁA������Ď��Ɏ��Ă��Ȃ��H
�@�E�m���ۂȂǂ̕��@���_�ɓ��݂����Ă��鏬�S�B�@
�@�@ �@�ޗǎ������@�V�������@��������i9���I�j�ޗǍ��������قg�o��� �@�ޗǎ������@�V�������@��������i9���I�j�ޗǍ��������قg�o���
�@�����̋C���̓}�C�i�X�X���B�������������ɂȂ肻�����B
���R�̕�炵561 2021.1.12
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �����̋C���̓}�C�i�X6���@
�����̋C���̓}�C�i�X6���@
�{���A1�s3���͍�N�t�ɑ����Q��ڂً̋}���Ԑ錾�o�����B(2021.1.8)
�Ȗ،��̊����Ґ��@�P��7�����ݗv2104�l�@7���̐V�K�����҉ߋ��ō���130�l�B��������ł̗×{�Ґ���500�l�ȏ�B
�@�@�@*�@�Ȗ،��̊����́A�X�e�[�W�S�ɔ����Ă���B���ɕa���ғ�����50���@�z����10.1���B
�@�@�@�@�@���łɉF�s�{�s�͎s�Ǝ��ً̋}���Ԑ錾���o�����B
�R���i�Ђł́A���ꊴ��������×{�ƂȂ����Ƃ��ɂ��A�F�l�m�l�ɒ��ړI�ȏ��������߂�킯�ɂ͂����Ȃ��B���������������𗊂߂邭�炢���낤�B�@�@
�����ŁA����̂��߂̏������n�߂��B���_����l�ł�������悤�ɁA�u���Ă���ꏊ���ꏏ�Ɋm�F����B��ɐ��퉻�o�C�A�X�������鑊�_�A����`�Ȋ�����Ă���A���̏Ɏ������ׂ�����A�ȂǂƂ͍l�������Ȃ��悤���B
�h�앞�̑���ɂȂ邲�ݑ�100���@�S�����200�Z�b�g�@���e�B�b�V���@������@���M�i�咆���j�@���Ŗ�@�}�X�N�@�^�I���@�o�X�^�I���@�p�W���}�@�V�����[�L���b�v
�@�Y�_���ȂǁB�@���ꂩ��---�O�̂��ߎ����ނB
�����Ȃ���C�������B��l�Ƃ�����҂̘g�g�݂ɓ���̂ŁA�����炭���@�����Ă��炦��Ƃ͎v���B
���╪����Ȃ��B�s���̕a�@�͑����a�����̑����N��������Ԃ炵���B�������Ă����ɉz�������Ƃ͂Ȃ��B
�l�p�Ƃ��ē������_�f�O�a�x(SpO2)�Ɩ��������A�̌����邱�ƂȂ��v���p���X�I�L�V���[�^�[�ipulse
oximeter�j�����߂邩�ǂ����A�v�Ē��B�i5��~����2���~���炢�j
 �@�@�摜�͊y�V���炨�肵�܂����B
�@�@�摜�͊y�V���炨�肵�܂����B
�O�͖��邢�z�˂��ɖ����Ă���̂ɁA�ߑO10���ɂȂ��Ă��C���̓}�C�i�X�Q���̂܂܁B
�X�C�X�A�O�����f�������h�ŋ��߂��A���v�z�����̂b�c�̂����A���C�ɓ���́u�O�����f�������h�]�́v���ƒ��ɋ����n��悤�ȉ��ł������B�C�����������肷��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@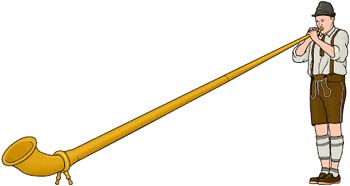 �@�@�A���v�z���� �@�@�A���v�z����
���R�̕�炵560 2021.1.8
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
 ���͂̊ց@----�@����������Ȃ��Ƃ���֍s����
���͂̊ց@----�@����������Ȃ��Ƃ���֍s����
�N���N�n�����ƂȂ����߂����A�Ȃ������Ղ��܂��Ă����B���̐����ԁA���̋C�����}�C�i�X�T���O��œ������}�C�i�X�̂܂܂������B�^�~���������A��ɂ����o���Ȃ���������������������B
���C�̊ɂ��A�u�C�U���Ƀh���C�u���邩�v�Ƒ��_�B�u�N�����Ȃ��Ƃ���͂ǂ��H�v�u���͂̊ւȂ炨���炭�v
�����̂悤�ɁA�������َq�ʕ����ٓ��������ďo�����Ă����B
 ���͂̊�
���͂̊�
���͂̊ւ́A�l���ցi�˂��������j�A�ܗ��ցi�Ȃ����̂����j�ƂƂ��ɉ��B�O�ւ̂ЂƂB
���̔��͂̊ւ́A�ޗǎ��ォ�畽�����ゲ��܂Ől�╨���̉������Ǘ�����@�\���ʂ����Ă����B
���B����Ƌ��̓s�����ԓ��R���̗v�Ղɒu���ꂽ�֖�Ƃ��Ė������B�u�̖��̒n�v�Ƃ��Ă��悭�m���Ă���B
���Ƃ��Ώ����m�ԁB���\2�N�i1689�j5�����{�i���̗��6����{�j�A���s�䂩��̒n�E�V�s���Łu�c�ꖇ�A���ė�����������ȁv�Ɖr��œ��R����k�サ�A���͂̒n�ɂ��ǂ蒅�����m�Ԃ́u���͂̊ւɂ�����ė��������܂�ʁv�Ƃ݂��̂��֑��ݓ��ꂽ������
�w���̍ד��x�ɋL���Ă���B
���̒n�ł̋��̑]�ǂ̋�Ɂu�K�̉Ԃ��������Ɋւ̐��ꒅ���ȁv�B
�@�@�_���̎n�܂���ے����A��̜͂߂�t���K�̉Ԃ���u�₩�ɉr��ł���B
�E�s���� ���ƂƂ��� ����������
�H�������� ���͂̊ց@�i�\���@�t�j
�@�@�\���@�t�͔��͂̊ւ܂ŗ������킯�ł͂Ȃ��A�u���ɏo��v�ƌ����ċ��̉Ƃ̒�Ŋ����ɏĂ��A�����ɂ����������Ă����悤�ȗl�q�ł��̉̂��I�����Ɠ`����Ă���B
 |
���������݂����������Ă݂��B��g�B
�u�������Ε��ӂ��܁T�ɍ`�悵�ƕS�M��M�����ǂ��T�v�Ƃ���A
����Ɂu�������ɐ����ĐS�̂܁T�ɂȂ邯��ǐS�ɖ��f�������Ă͂Ȃ�Ȃ��@������藈�N�̂��Ƃ��悭�悭�l���Ă�肻���Ȃ�ʗl�\���̒��ӂ����Ă����Ȃ����v�Ƃ������B�@�@ |
�ߐ{�̎R���݂�������Ԃ��Đ����ɂӂ��킵���i�F���B���̍��˂͓��k�V�����B��ԗ�20�����炢���B

���R�̕�炵559 2021.1.5
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@
 �V�����N�����₩�ł���܂��悤��
�V�����N�����₩�ł���܂��悤��
 ���͗z���B�z�̌������߂č����������B
���͗z���B�z�̌������߂č����������B
 ���K�_�i�Ȃ܂͂��j
���K�_�i�Ȃ܂͂��j
��̉摜�́A2011�N��A���̖�ɁA�H�c���̒j�������ɂ���^�R�_�Ђŏo������Ȃ܂͂��B
�͂�鉓�����痷�����A��̍~�肵�����ɂ��ǂ남�ǂ낵�����ʂ����A�}���薪�𒅂āA�����̉ƁX��K�˂ĉ��_��-----�����M�̂ЂƂ̗��K�_���B���������Ж���͂炤�ƌ����Ă���B�S�̖ʂ͐l�ԂƂ͈قȂ���̂ł���Ƃ̕\�����낤���B
�K�ꂽ�Ƃ̎q�ǂ��ɕ��i�̐����ԓx��q�ˁA���邢�͖J�ߎ���e�F�s������Ɨ@�����肷��B���̌��t�����̂܂ܑ�l�ł��鎩���ɂ��͂˕Ԃ��Ă����̂�������䂢�B���ʂ����Ă���ƕ������Ă��Ă��A�g�߂ɐ_�������Ă���Ǝv�킸���Ƃ����肵���قǔ��͂��������B�����炱�ڂꗎ����������E�����l�́A�K�^�������Ă���Ƃ��������`��������B
���N���A���₩�Ȉ�N�ł���܂��悤�ɁB
�u���i�ʂ�v�̐����������ɑ��҂̓w�͂Ɏx�����Ă���̂��B���ӂ�Y��Ȃ���N�ɂ��悤�B
�u�R���i��v�̐������A���܂ł̕�炵�������Ĕے肷����̂łȂ��A�V�����l�ԊW��z���w�j�ɖ��������̂ł���܂��悤�ɁB
�@���R�̕�炵558 2021.1.1
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���R�̕�炵
2020�N1������ 2020�N�P�Q���܂�
�@ |


 ������܂ł̓��b�Z���Ԃ����Ă����
������܂ł̓��b�Z���Ԃ����Ă����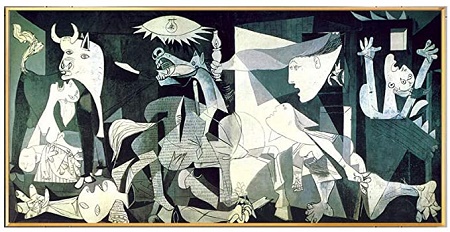 �@
�@
�@
�@

 �@�A�C�X�����h�|�s�[�̕c�i�d���90���j
�@�A�C�X�����h�|�s�[�̕c�i�d���90���j


 �@�͔���T���Ă�����A�~�~�Y�����Ȃ����ƃL�W������Ă����B
�@�͔���T���Ă�����A�~�~�Y�����Ȃ����ƃL�W������Ă����B



 �Ⴂ���� Wheellroader �̓C�P�����B���N�ɂȂ����p�͏a���ĂȂ��Ȃ��̂��́B�@
�Ⴂ���� Wheellroader �̓C�P�����B���N�ɂȂ����p�͏a���ĂȂ��Ȃ��̂��́B�@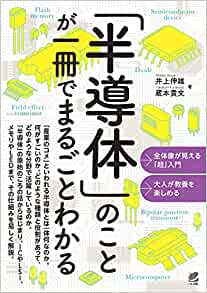 ��� �L�Y �A ���{ �M�� (��) �@�x���o�Ł@2021.11.25��
��� �L�Y �A ���{ �M�� (��) �@�x���o�Ł@2021.11.25��









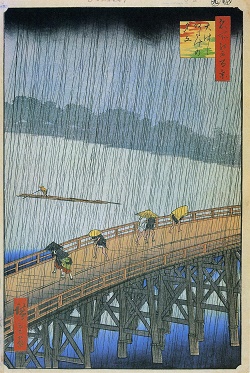 �@�̐�L�d�̖����]�˕S�i���́u��͂��������̗[���v
�@�̐�L�d�̖����]�˕S�i���́u��͂��������̗[���v �@�H�F�̔��͂̊ց@���E�̍������������낢
�@�H�F�̔��͂̊ց@���E�̍������������낢 �@
�@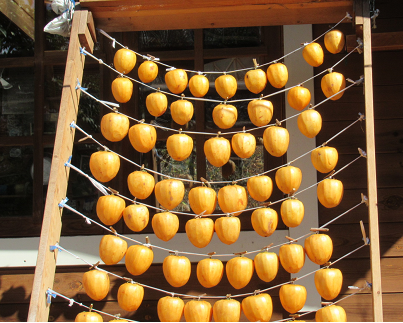 �@�I���`�@�E�B�X�L�[�ŏa���Ă����������B
�@�I���`�@�E�B�X�L�[�ŏa���Ă����������B
 �@�g���[�Ɏ�܂�����ƁA�����^�яo���ĕ֗��B
�@�g���[�Ɏ�܂�����ƁA�����^�яo���ĕ֗��B
 �@���̓u���[�x���[�A�E�̓I�I�f�}���@��̖��g�t���Ă����B
�@���̓u���[�x���[�A�E�̓I�I�f�}���@��̖��g�t���Ă����B






 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@
�@









 �@�H�i�g���[���d�˂āB�����^�ъȒP�B
�@�H�i�g���[���d�˂āB�����^�ъȒP�B �R�P�I�g�M�� �@�Ԍa1�Z���`
�R�P�I�g�M�� �@�Ԍa1�Z���` �@�q�}�����̉Ԏ�@245��
�@�q�}�����̉Ԏ�@245�� �@�ЂƂ�60�~
�@�ЂƂ�60�~

 �@�A�����J�V�I���@�L�N��
�@�A�����J�V�I���@�L�N��



 �������G�ꂿ������B �J�ɔG�ꂽ賂��H�U�������Ă���B
�������G�ꂿ������B �J�ɔG�ꂽ賂��H�U�������Ă���B 

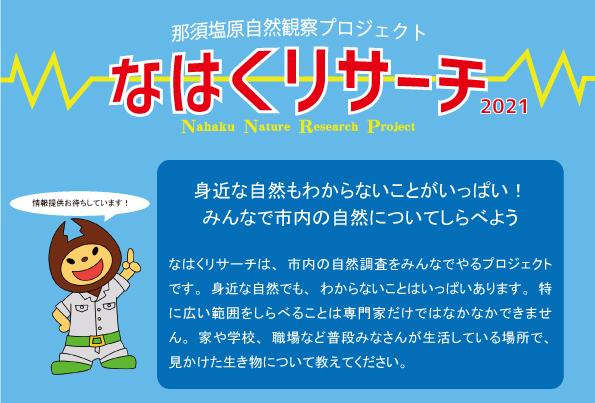

 �@���E�͂ǂ�ȂɍL���̂��낤�B
�@���E�͂ǂ�ȂɍL���̂��낤�B �@�@
�@�@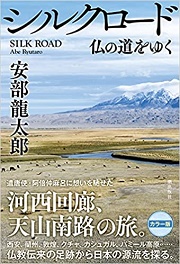


 �@�z���X�^�C����̋�
�@�z���X�^�C����̋�

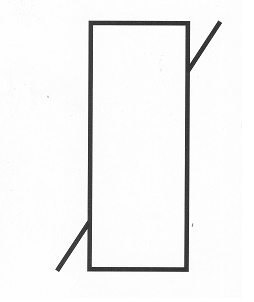

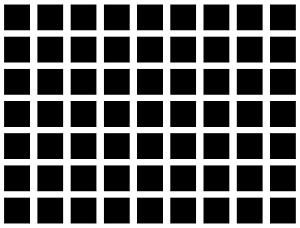 �@
�@
 �@���̃j�b�R�E�L�X�Q�͂�⑾�߁B
�@���̃j�b�R�E�L�X�Q�͂�⑾�߁B









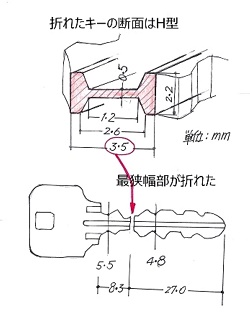
 �@
�@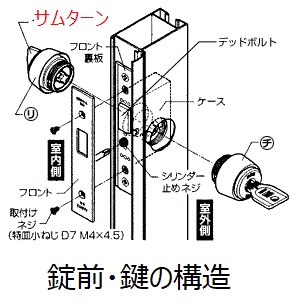
 �@�@
�@�@
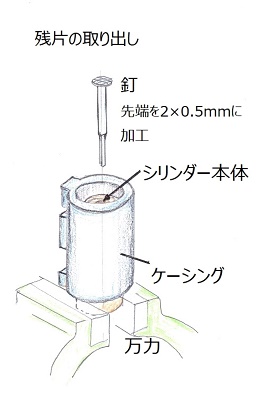
 �@
�@






 �@
�@ �@�@�@�����Ƃ����Ԃɋa���W�܂��Ă����@�@�@�@�@�@�@�G���C�I�\�[���Ɋ��ݕt���ĉ^�ڂ��Ƃ��Ă���a����
�@�@�@�����Ƃ����Ԃɋa���W�܂��Ă����@�@�@�@�@�@�@�G���C�I�\�[���Ɋ��ݕt���ĉ^�ڂ��Ƃ��Ă���a���� �@
�@
 �@
�@ �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@






 �t�����h�E �@�����͂P�O�Z���`�ق�
�t�����h�E �@�����͂P�O�Z���`�ق� 
 �@��
�@�� �n���g���m�I �i�t�Ղ̔��j
�n���g���m�I �i�t�Ղ̔��j



























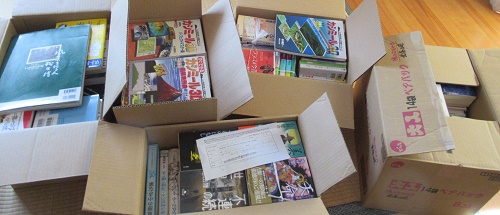



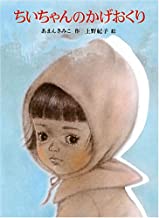
 �h�C�c�A�u���b�P���R�C�ۊϑ��W�]�䂩��̒���(
wikipedia����q���܂����j
�h�C�c�A�u���b�P���R�C�ۊϑ��W�]�䂩��̒���(
wikipedia����q���܂����j





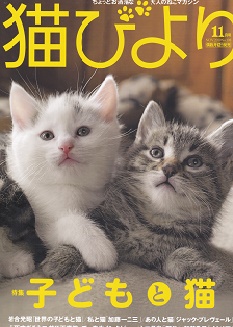


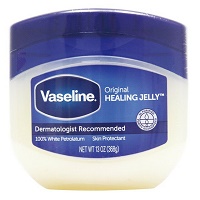

 �@
�@






 �t���b�v�i�r�j�������Ē�������
�t���b�v�i�r�j�������Ē������� �@�@�@�@��̋��Ƀt�L�m�g�E��������
�@�@�@�@��̋��Ƀt�L�m�g�E��������

 ���̏ꍇ�u�^�K�Z�v���B���܂ɓ��̉w�̂��X�ɏo��B�����������D���������B
���̏ꍇ�u�^�K�Z�v���B���܂ɓ��̉w�̂��X�ɏo��B�����������D���������B �@�ޗǎ������@�V�������@��������i9���I�j�ޗǍ��������قg�o���
�@�ޗǎ������@�V�������@��������i9���I�j�ޗǍ��������قg�o��� �@�@�摜�͊y�V���炨�肵�܂����B
�@�@�摜�͊y�V���炨�肵�܂����B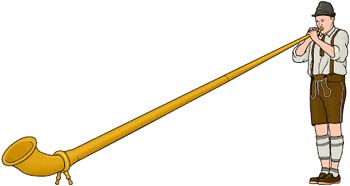 �@�@�A���v�z����
�@�@�A���v�z���� ���͂̊�
���͂̊�

 ���͗z���B�z�̌������߂č����������B
���͗z���B�z�̌������߂č����������B ���K�_�i�Ȃ܂͂��j
���K�_�i�Ȃ܂͂��j