|
『丘の上のジェーン』読後感 モンゴメリ作 木村由利子訳
角川文庫初版 2024.9.1記
 Gay
Street 60番地。家族の再生のものがたり----場所の意味するもの、
属する家庭を求めるジェーンそして自立 Gay
Street 60番地。家族の再生のものがたり----場所の意味するもの、
属する家庭を求めるジェーンそして自立
この作品は、物語のなかで[家]が重要な役割を果たすのを暗示するように住所から始まっている。ファンタジーの要素が少なく、現実から始まる書き出しはモンゴメリ作品に共通しているもので効果的だ。
やや古びていて、時代から取り残されそうになっているお城じみたレンガ造りの家。暗くてすすけた古い家。この家に主人公のジェーンが住んでいる。
この家はこれまでのモンゴメリの作品にあるように「屋号、名前を持たない」これは何を象徴しているのか。
家とはなにか。それは住む人に働きかけ、住む人の人間性を育み、五感を涵養し、人間が本来持っているはずの感覚を呼び覚ます働きをするものだと思う。愛情を受け、与えることで「自分であることを肯定し、他者との関係性を築きあげること」ができ、「人生に立ち向かう勇気を手に入れる場所」であろう。
名前を持たない家に住む----
----「私はこの家のものじゃないわ」家、すなわち家族の集合からの疎外感を感じるジェーンは言う。
家は地域のコミュニティに所属するものだが、孤立しているGay Street 60番地では家が正常に機能せず、住む人たちが双方向に影響しあっていない。家は人生の多くの時間を過ごし、家族と人生を共有する舞台であり、家族という他者を尊重し理解し、関係を築く場所なのに。
Gay
Street 60番地では、故ロバート・ケネディ夫人の意思が家の法律として働いている。母親を除い
た家族から愛情を受け取れないジェーンの自我の発達は望むべくもない。従ってジェーンは自己肯定感が低く、自分の内面に自己を自律するものを持っている自覚もない。母ロビンは、その母から歪んだ愛情を受けている。真綿で首を絞められるような危機的状況において本来培われるべき判断力を持ち合わせていない。
一方、ジェーンが父親と夏を過ごすランタン丘の家は、自然の中のたたずまいや海の存在が詳しく描写されている。描写にはその後の展開への必然があり、家族を支える家としての役目を担おうとしているのが見て取れる。人間は労働することで生きていく指針を手に入れることができるのかもしれない。ランタン丘で、父との関係を深く持ち、働き、友人と共に遊びジェーンは 自己を育て、
自立していく。
一人の女の子の能力が開花していくさまを見るのは楽しい。
 島の自然の描写の美しさ 島の自然の描写の美しさ
細かな表現がなされていて、この作品には特に海の描写が多くみられる。『赤毛のアン』には海の描写が少ないが、島に住む人間にとって海は島の原風景であろう。自然描写があると場面がよりリアルになり引きしまる。風景が人間の心と会話し、語りかけてくる。人の心を映し出し、情感をゆすぶる。自然描写をストーリーの中で効果的に使っていて、作者の「美しいものは美しい」という言葉が聞こえてきそうだ。
しかし、時代は移り始めていた。戦後の一時の好況が過ぎ去り不況の中でより現実的な表現が歓迎されるようになる。社会の格差やそのなかの生活の苦しみや犯罪などの、今目の前にある現象を、無駄を省いた文体で表現する変化が起きていた。モンゴメリのリリシズムはやや時代遅れになりつつあり、それを自覚していたモンゴメリの表現への模索を感じることがある。
「アン」の自然への向き合い方は、身近なはずの海や動物の描写が少なく人間中心主義で、自然を自分に近づけようとしている。反面「ジェーン」は自然中心主義。自分たちが自然に入り込
もうとしている。アンとジェーンの行動のベクトルは反対のように思える。
 描かれた当時の社会の様子は 描かれた当時の社会の様子は
『 丘の上のジェーン』は1937年発表された。執筆当時の設定では、ロバート・ケネディが、その父から譲り受けた財産を1930年代の世界恐慌を乗り越え、引き続き財産を保持できていたことになる。どうやって財産を築いたかの記述が無いので、背景を探りようがない。
第一次世界大戦と、それに続く第二次世界大戦の戦間期にあったこの時代。戦後の復興と経済の立ち直りの時期は短く、その後に来る不況にも耐えることができたのは、祖父の経済面の能力によるものか。大恐慌、自然災害、貧困の負のスパイラルに巻き込まれ、次なる戦争への足音が聞こえ始めていた不穏な時期だったはずだ。
農家の暮らしの描写が中心で、性別に役割を分担しないと生活を支えることが出来なかった『赤毛のアン』の時代に比較して、経済活動が活発になり、社会に格差が生じてきた階層社会の在り方を見ることができるこの作品は、違った側面を読者に見せてくれる。
 当の祖母の性格と行動は、いかにして形作られたのか。 当の祖母の性格と行動は、いかにして形作られたのか。
独善で、強圧的な性格が、どのように形作られたのかは想像するしかない。ムア大佐の娘とあるが、ムア大佐は書かれた時代にはその名前だけで通用する人物だったのか。意外にも綺麗で社交的だった若い頃の祖母は、はじめの結婚相手を愛していないが、
その間に三人の子供を持った。金持ちの二番目の夫(ロバートケネディ)と結婚してからは、夫に抑えられないほどの愛情を感じている。夫にも妻にも特別な魅力があったのだろう。
祖母の娘への偏愛と支配欲は、自己を娘に投影したものなのか、亡き夫への愛情の変移なのか。祖母のように他人を攻撃する人間は、内面に弱点を抱えていて、攻撃することで自分を守っている。ではその弱点とはなにか。亡き夫への愛情なのか。愛情がなぜ他者攻撃に繋がるのか。影のように自分の母に付き添うガートルートの存在が不気味だ。
 祖母は娘のロビンを溺愛し、愛情という首枷をはめ
、時に拘束している。孫のジェーンは祖母から愛情を受け取ることはなく、存在を否定され続けている、現代なら精神的虐待に値する行動だろう。 祖母は娘のロビンを溺愛し、愛情という首枷をはめ
、時に拘束している。孫のジェーンは祖母から愛情を受け取ることはなく、存在を否定され続けている、現代なら精神的虐待に値する行動だろう。
祖母のその行動は、何らかに抑圧されたものからくるのか。娘ロビンが第一次世界大戦からの帰還兵アンドリュ
ー・スチュアートと駆け落ち同然で結婚したことから生じたものなのか。これだけでは無い気がする。
祖父を愛した祖母の愛情の対象は、祖父との間の一人娘ロビンだ。ここまでは理解できるが、なぜその愛情が暴走するのか。
娘の精神・肉体も独占したい母を、ある時娘は裏切った。あやつり人形のようだった娘ロビンがこのような激情を発露させたことに驚く母、そして娘。しかし娘との関係を持ち続けたい母は、仕送りを続ける。娘の自立を妨げる母と娘の関係性とが、夫との三角関係にもつれこみ、そのはざまで揺れる父アンドリュ
ー・スチュアートがどう行動するのか。これは母系家族化している現代にも通じる娘―その母との関係にも通じる。
祖母と祖父との関係が見えてこない。祖母の心の中では祖父(夫)は死んでいないのではないか。記憶のなかで生き、時に生者を動かす----祖父への愛情の代襲として美しい娘に重ねているのかもしれない。
 男女の愛は続くのか
言葉の行き違いや誤解が生まれる。 男女の愛は続くのか
言葉の行き違いや誤解が生まれる。
危機的な状況で結ばれた男女の仲は長続きしないとはよく聞くこと。第一次世界大戦から除隊したばかりで「現実の生」に飢えていたアンドリューと、お蚕ぐるみで過保護なロビンが恋に落ちた。天才と称されるほどの頭脳を持ちながらも、どこか子供じみた性格のアンドリューと、一世一代の駆け落ちを決心したロビン。ここまでは良かった。しかし結婚とは現実の連続だ。判断力にバイアスがかかった状態で、相手を見極め将来を予測することはまことに難しい。
気になることがある。父アンドリューが妻ロビンを評するのに常に「美しさ」をことあげすることだ。内面を評価する言葉は少ない。外面は変化するもので、高揚した気分が落ち着くと新しく見えてくるものがあり、現実から逃避する行動をとることもあるだろう。「生活」がのしかかることに気づくまでそう時間がかからない。
そのうえ、義理の姉の立場のアイリーンが生活に口をはさむ。それに気づかない夫と、毅然とした態度を取る気概の無い妻と。夫は、男は、常に世俗を離れて自分の意思のおもむくままに生きたがる生物だ。甘やかされた母と、いろいろな意味で子供だった父。そこへ祖母が食い込んでくる。
そ れに加えるに「父アンドリューの冗談好き、茶化す」性格が二人の間に立ちはだかる。確固たる自分を持つ人間は、冗談を投げかけられても茶化されても柔軟に耐えられるが、妻のロビンに取ってはストレスだった可能性がおおいにある。
「仕事か私か」、「子供か自分か」を互いに投げかける夫婦の姿は、現代に通じるものがある。
 蜜月が過ぎて 心が離れていく二人 どうしようもなく動かせない心。 蜜月が過ぎて 心が離れていく二人 どうしようもなく動かせない心。
それは妻のロビンが妊娠したことに始まる。若い妻の妊娠に伴う精神、肉体の変化を二人はうまく乗り越えられない。現代なら「ホルモンの変化」と理由付けできるが、おそらく書かれた当時にはそういう認識はなかったのだろう。
女性は妊娠すると出産や育児に向けての準備として、性ホルモンの分泌が盛んになる。黄体ホルモンは普段の10倍、卵胞ホルモンは妊娠しない女性が一生かかっても浴びない量を妊娠期間だけで産出する。さらに出産時オキシトシンが分泌され、分泌は授乳中にも続く----このホルモンは陣痛促進剤としても働くが、特徴的なのは「脳」に作用すること。
相手を絶対的に信じ愛するホルモンがオキシトシン。授乳するたび母親は我が子への愛情を深めていく。これはあらかじめ脳にプログラムされた作用らしい。
しかし問題は「他者に対して排他的に、時に攻撃的になる働き」があること。その対象には父親さえも含まれる。母親の脳には自分+赤ん坊」と「他者」の間に柵が強く張り巡らされることもある。
ところが父親はなかなか「自分が父親になった」という自覚が湧いてこない。さらに不幸なことに、父アンドリューは妻ロビンの態度を見て「自分に注目してほしい、構って欲しい」というやや子供めいた感情を持ち始めたていた。
(* 脳科学者池谷裕二東大教授の
著作数冊を参照しました。)
 父アンドリューの「茶化す癖、冗談でやり過ごす性格」が裏目にでた。私の友人にもそういう人がいる。真面目に話そうとすると、話題の方向を変えて茶化す。これにはとても不愉快になる。同じことが母ロビンに起きた。一心に何かに没頭している人間を茶化すほど危険なことはない。感情が行き違い、互いの心が離れていく。互いの意地と頑固さが相乗作用として働き、妻には赤ん坊への独占欲、自己愛の強さが噴出してくる。 父アンドリューの「茶化す癖、冗談でやり過ごす性格」が裏目にでた。私の友人にもそういう人がいる。真面目に話そうとすると、話題の方向を変えて茶化す。これにはとても不愉快になる。同じことが母ロビンに起きた。一心に何かに没頭している人間を茶化すほど危険なことはない。感情が行き違い、互いの心が離れていく。互いの意地と頑固さが相乗作用として働き、妻には赤ん坊への独占欲、自己愛の強さが噴出してくる。
そこへ夫アンドリューの姉の存在が立ちはだかる。本来当事者が考えるべき事案に口をはさむ。こういう存在は、自分に確固たる自信がない人間にとっては有害でしかない。相変わらずその悪意に気づかない夫アンドリュー。現実が見えないのか。
どうだろうか、作者モンゴメリも産後夫の無理解に悩み、子供へ執着し、孤独な思いをしたのかもしれない。アイリーンの人物造形に女性作家ならではの視点が見て取れる。
---裏に悪意を持つ過剰な親切は疑わしい----愛情を保つには努力が必要で、その場に留まるためには全力で走らなければならないこともあるだろう。二人にはそれが出来なかった。
 女の子を選んだタイタス姉妹 ---- 自分たちで育て上げたいという原欲求 女の子を選んだタイタス姉妹 ---- 自分たちで育て上げたいという原欲求
人間に対する作者モンゴメリの観察眼に、いつもながら感嘆する。女性作家ならではの心の動きが興味深い。
エムおばさんの「母さんはどうしてる?相変わらずきれいでおばかさんかい?」
人間の本質を探り当てるエムおばさんと、天下国家を論じながらも現実にある問題が見えない、直視しない父との対比が目立つシーンだ。
 隣家の共同住宅に住む孤児「ジョディ」の存在の意味するもの 隣家の共同住宅に住む孤児「ジョディ」の存在の意味するもの
アンに比類される存在として本物の生きた友人「ジョディ」が置かれた。『アンの娘リラ』での戦争の後方支援と言った組織に表わされたように、モンゴメリは「女たちの協力と共闘」を夢見たのではないだろうか。教会の婦人会をリードし、地域の学生たちの舞台演出を手伝い、女性が力を合わせると地域も国家も動く可能性があることを認識していたと考えられる。これを精神的な孤児・ジェーンの次に現実の孤児ジョディを登場させ、二人の成長を重ねようとしたのかもしれない。時代を予測し、これからのカナダ社会を生きる読者を明確に想定し、主人公を作り出したのではないか。
 死んだと思わされていた父と、ジェーンと 死んだと思わされていた父と、ジェーンと
厳しい環境に育った主人公が、男性の理解者が現れて人生が展開していく。これは『赤毛のアン』のマシュー、『エミリーシリーズ』のカーペンター先生
の存在に共通していよう。父親の知性の導きと、島の隣人たちのまっすぐジェーンの存在を認める態度でジェーンは輝き始める。女の子が性格、能力、社会性が花開いていく様子を見るのは喜ばしい。
自分に自信が持てるようになり、主体的に行動し主張できるようになる。
父との関係で印象的なシーンがある。車が故障して干し草を積んである納屋で夜を過ごす羽目に陥った夜の出来事だ。父とジェーンが心のうちを開き、より父を理解できるようになった。
(このシーンは、『エミリーはのぼる』第12章 乾草堆の下で 村岡花子訳 新潮社刊のある場面と似ている。
)
<https://kemanso.sakura.ne.jp/anne-aurora.htm>
「エミリーとイルゼは行き暮れて、乾燥堆の下で夜を明かすことになった。
北極光が現れ、エミリーは自身の芸術性に目覚め確信する。」
父とジェーンが身体を寄せ、体温を感じるほどの近さで感応し合う。このシーンは心に響く。現代のあまりにも簡単に人とつながれるようになった結果、一つ一つのつながりの価値が低下しているのではないか、という疑問が湧いてくる。
 いい香りのクローバ
ー いい香りのクローバ
ー
父とジェーンがその上に寝たクローバー(スイート・メリロット) 白い花はクイーン・アン
しかし、父親とここまで性格、思考、嗜好が似ていて共感でき、父を理想とする男性像を描き続けると、ジェーンの結婚に対する姿勢に影響を及ぼすのではないか。父を越える相手を見つけるのは難しいし、それを継続するのはさらに難しい。
(追記:全き父を持った娘は、男性に対して正当な評価ができる。夫婦の関係を「積み上げていくもの」「努力を忘れないもの」と認識し、相手を信頼し人間と人間の関係を築き上げることができる。こういう側面
もあるかもしれない。)
 両親と共にトロントで暮らすジェーンの将来は。属する場所を見つけた。 両親と共にトロントで暮らすジェーンの将来は。属する場所を見つけた。
家は主婦の手で育っていくものようやく家族となった三人がトロントでどういう生活を送るのか。家族の未来はどう展開するのか。
父親と母親が以後どういう夫婦に育つか。それは互いの理解と努力と寛容さがものを言うだろう。家を支えるものを----衣食住と愛情を----ジェーンは手に入れた。家の機能はさらに進化していく。両親を感化することで、家族の未来が変化していく。
祖母と伯母から両親を取り戻し、新しい家族を作り上げる努力がなされる----そこに父と母の参加があるか。あると信じたい。
家の描写で始まり、トロントでの新しい生活に相応しい小さな家を見つけるシーンで作品が着地するのは、いかにもこの作品にふさわしい。
「あのねえ、パパ----ぴったりの家を知っているの」----「さすがだね」パパは言った。
ではジェーンの才能がどう開花するのか。ちょうどジェーンが成長期にかかるころ、第二次世界大戦後が始まる。背後から国を支えるのか、父に似たジャーナリストの能力が目覚めるのか、あるいは数学好きとあるように、理系の職業を目指して、新しいカナダの社会に適応し貢献するのか。
なにかに挑戦する人間に成長するだろう。
 モンゴメリ作品に見られる「説話的定型」にあるような、読者の既視感を刺激する物語ではなくて、新し
くトロントという都会と変化する時代の中で書かれたこの物語は、モンゴメリの作品のなかでも新機軸を打ち出されたもの。「人工物と自然の対比」だけでは言い表せないものがありそうだ。 モンゴメリ作品に見られる「説話的定型」にあるような、読者の既視感を刺激する物語ではなくて、新し
くトロントという都会と変化する時代の中で書かれたこの物語は、モンゴメリの作品のなかでも新機軸を打ち出されたもの。「人工物と自然の対比」だけでは言い表せないものがありそうだ。
作者モンゴメリが、主人公ジェーンが激動する社会の中でどう成長して欲しいと考えたのかが鍵になる。その後の展開を見通していただろうに、病に倒れて続編が書かれなかったのが惜しい。
 夫ユーアンの精神は不安定のままで、モンゴメリはそれを世間に糊塗するためになみなみならぬ努力が必要だった。加えて長男チェスターの放埓な暮らし、追い打ちかけるような出版社との裁判が控えていた。人生の重圧がのしかかり、睡眠薬や鎮静剤のお世話になる----牧師の妻でありながら、キリスト教の教えが、自分の魂の救済には繋がらなかったという絶望感----だからこそ、「父とジェーンの間の聖書への思い」を書き表す必要があったのではないか。 夫ユーアンの精神は不安定のままで、モンゴメリはそれを世間に糊塗するためになみなみならぬ努力が必要だった。加えて長男チェスターの放埓な暮らし、追い打ちかけるような出版社との裁判が控えていた。人生の重圧がのしかかり、睡眠薬や鎮静剤のお世話になる----牧師の妻でありながら、キリスト教の教えが、自分の魂の救済には繋がらなかったという絶望感----だからこそ、「父とジェーンの間の聖書への思い」を書き表す必要があったのではないか。
かねて『丘の上のジェーン』が、モンゴメリにとっての転換期の作品になると感じていた。作品が発表されたのが1937年。モンゴメリ63歳。人生の
終盤近くになり、新しい主人公を産み出すには十分な社会経験を積んだ時期だ。
病に倒れて続編が書かれなかったことが残念だ。
 作品に書かれていないこと
さらに考えよう。 ああ、キーボードが一人歩きする。 作品に書かれていないこと
さらに考えよう。 ああ、キーボードが一人歩きする。
一番に、気に入らない相手と結婚した娘の子供=ジェーンを、単にこの理由だけで嫌うだろうかという疑問がある。この場合は、自分に反抗した娘を嫌悪の対象とするはずで、自分が感じる喪失感を反抗できない弱い対象ににぶつけ、いたぶってみたいという人間の「原初の感情」を発露させているように見える。祖母は自分の自分の性格の弱さを自覚している。それを隠すことで自分を守ろうとしているのではないか。
この作品が書かれた時期のモンゴメリの精神状態が、祖母の性格に反映しているのかもしれない? 私はそうは思わない。モンゴメリほどの知性のある人間なら、自分の暴力性を隠す知恵や技巧があるはず。裏と表を使い分け、負の部分を書き表すことを「恥」だと考えるはず。
残された膨大な日記にあるように、体面を保ち書かれた文によって自分がどう見られるかを熟知していたはずだ
。長年同居して介護し見送った祖母の口ぐせの「世の中の人がどう言うだろうね」が、モンゴメリ自身の体に沁み込んでいると思う。(恥---なんと日本的な表現)
しかしその使い分けができなかったとしたら、精神の抑えがきかないほど現実から乖離した状態にあったということか。これはこれで非常に悲しく、いたわしいことだ。自分の性格をいくつかに乖離させることは、必ず身体に影響があるものだ
。あるいは祖母の抑圧的な性格が、孫のモンゴメリにも遺伝していたとも考えられよう。
娘ロビンを軸に、祖母と目覚めた後のジェーンは対応している。ネガとポジのようなもの。根底の部分での性格----その意思の強さ、誰かを愛
したい、愛されたい。直截な態度を取り、本来性格は明るいこと、ジェーンの方向は違えども何かをしてあげたい気持ちが強いことなどから見て取れよう。いつか双方が理解しあえる機会があると考えたい。双方の折り目の部分に何が起きたのか、これこにそ想像力をかきたてられる。
そのほかの疑問:祖母の二番目の結婚相手のロバート・ケネディ(アイルランド系か?)の性格。富豪の彼が三人の子持ちの祖母を結婚相手に選んだ理由。祖母の夫への愛情の中身
。人間相手に命令し従わせることができるか、それを可能にした両者の性格と立場。
モンゴメリ作品によくみられるが、母ロビンをはじめとして、娘ガートルード、息子の妻たちの登場する女性たちに「顔」が感じられない。これは作者モンゴメリの成育歴の影響かもしれない。
2024.9.1記
『丘の上のジェーン』L.M.モンゴメリ作 木村由利子訳 角川文庫 平成23年8月25日初版
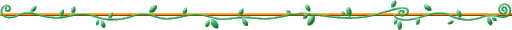 |
 ジェーンが植えたフロックス
ジェーンが植えたフロックス  いい香りのクローバ
ー
いい香りのクローバ
ー