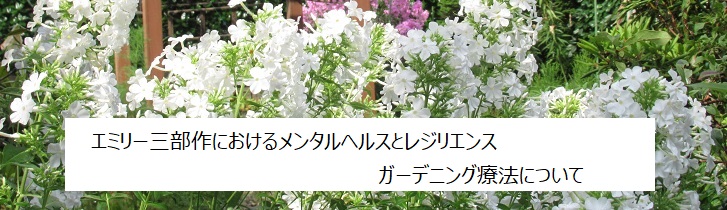|
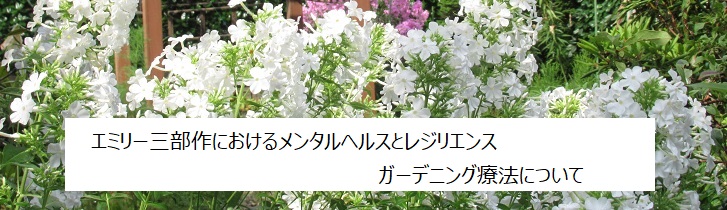
----ディーンは行ってしまった。庭は急に寂しくなった。薄い水色の薄暮の中に白い草夾竹桃の花(whitephlox)が
そちらこちらに幽霊のように咲いている。----『エミリーはのぼる』 第6章シュールーズベリーの生活 村岡花子訳
 ノートルダム清心女子大学名誉教授赤松佳子先生の論文がThe Journal of L.M.
Montgomery Studiesに掲載された。 ノートルダム清心女子大学名誉教授赤松佳子先生の論文がThe Journal of L.M.
Montgomery Studiesに掲載された。
赤松先生は日本におけるモンゴメリ研究の第一人者。
原題は、「エミリー三部作におけるメンタルヘルスとレジリエンス ガーデニング療法について」
【Mental Health and Resilience in the Emily Trilogy: Emily Byrd
Starr and Cousin Jimmy through the Lens of GardenTherapy】
( The Journal of L.M.
Montgomery Studies <
Landing Page | Journal of L.M. Montgomery Studies >で検索し、
上のarticle へ。 さらに論文の題名で探してください。)
 論文を拝読して
論文を拝読して
【エミリー三部作におけるメンタルヘルスとレジリエンス ガーデニング療法について】
この論文を読み触発されて感じたことや考えたことを記録しておきたい。
1 庭や植物によるレジリエンス
2 農業の楽天性
3 レジリエンスとは 不可逆的な災害時に際して
4 気になっていたこと 翻訳文なかの会話文----ジェンダー意識と共に
5 今一番興味を惹かれること----日本文学への評価が高まる
 1.庭や植物によるレジリエンス
1.庭や植物によるレジリエンス
最近注目されているこの考え方は、経済発展するのに合わせて社会のひずみが大きくなり、解決の難しい問題を引き起こしてきた人間中心主義に疑問を投げかけるものではないだろうか。自然—人間社会は相反するものではなくて、互いに補完するものだろう。
論文にあるエミリーの大きな喪失とは。
エミリーは父の死とともに、深い相互理解に根ざした関係性で育んできたものを喪失した。父の死ののち、くじ引きという思慮に欠けた方法でニュームーン農場に連れてこられ、さらに書くこと=創造性を発揮することを禁じられた。主にこの二点が挙げられる。
論文におけるエミリーの「心理的下降」から、変化を伴って回復させたものは何だろう。
ニュームーン農場の、それぞれが孤独な心を抱えている人の間に投げ入れられたエミリー。この孤独を癒し、心理的下降を引き上げるのに必要なのは、自然との語らいと相互の働きかけだった。
その手助けをしたのは、いとこのジミーさんが作り上げ、エミリーもそれに協力する「庭」の存在で、植物を育て樹々を愛で、小さい命を育てる喜びを得たこと。身体を遣い指先に土地を感じることがいかに子供の心を癒してくれたか。
人間は「社会的動物」なので、帰属する社会を必要とする。庭と人の結びつきは小さな社会でもある。その中で「自分には価値がある、できる」と自己肯定感を持つことから、人生に立ち向かう勇気を得ることができる。自分を認めることで自信を持ち達成感を得ることができる。さらに広い社会へと進む勇気を手に入れることができた。それがエミリーの言葉による表現へと結びついていく。
広く社会性を求める時期に来たエミリーは、一番身近な関係性---疑似家族を必要とした。年齢相当の社会を構築するのに、テディ、イルゼ、のちにペリーが登場する。それぞれが孤独を抱える4人の組み合わせが興味深い。
芸術家と法曹を目指すペリーの、他の三人との実生活における感覚の違いが、この小説の進行に大きく影響しているからだ。読者を立ち止まらせ、考えさせ、比較させることで4人の特性が際立ってくる。
 2.植物によるレジリエンスと農業の楽天性
2.植物によるレジリエンスと農業の楽天性
都市部であれ当地のような田舎であれ、そこに住む人たちが、いかに小さな自然を庭先などに作り上げているかを、感嘆しながら見ることが多い。
人はこうやって自然の切れ端を自分の手に載せて、精神の安定を得、疲労からの回復を願っているものなのだと知ることができる。
近所に多く見られる移住者向けの市民農園からもそれを見て取れる。ドイツのクラインガルデン、ロシアのダーチャも良い例になる。人はなんと地面にしゃがみ込み、土とともに作業することを望んでいることか。
私はいま、ここまでの人生で、種を蒔き自分で作り上げ手を入れてきた「庭」と共にあったことをつくづくありがたいことだと感じている。
モンゴメリは、アンシリーズのほかに、『丘の上のジェーン』に見られるように、題名に地名を被せている。その思いはどこにあったのだろう。
土地に根を下ろし、植物を育て帰属先としての地名を冠する---そのことによる自身の救いを表わしているのではないだろうか。
かねて農業にたずさわる人達の「楽天性」について感じることが多かった。個人的にはそれを「農業の楽観主義」と呼んでいる。途方もない辛抱強さ、努力しても自然は忖度してくれない。しかし手を動かすほかない。その時間を積み重ねるうちに諦観を身に付け、運命論者めいてくる。
日々命を吹き込む作業は、自身の心の再生を信じることに繋がる。農業経営はもちろん、労が多く経済的成功を目指さざるを得ないが、その間にも命を育てる喜びを感じることが多い。
まして「庭づくり」は純粋に心のおもむくままに行う作業だ。それを通して人はいかに多くのものを受け取ることができるか。
しかし自然に耽溺しすぎると自閉的になる恐れがあり、社会的生活から離れすぎると孤独感に結びつくこともある。人は社会的動物であることからは逃れられない。
ある時、自分としてはこれ以上ないという庭を作り上げたとき、通りがかりの人がこう話しているのが聞こえてきた。
「こんなに庭づくりに精力を傾けている作り主は、精神的に寂しさや孤独感を抱えているのじゃないかな」。
そうかもしれない。庭は作り手のあるじ、身体をゆだね、自分のものと感じる領域なのだから。
ではモンゴメリ本人は、庭づくりで孤独や葛藤を乗り越えられたのだろうか。あまりに強いストレスを受け続けていると、自然との対話によるレジリエンスには限りがあるように思う。モンゴメリの孤独の内部には、自然への惑溺に対する精神の揺れがあったではないか。庭にレジリエンスを求めても、それ以上に現実は厳しかったのだろう。
ジミーさんは自作の詩を朗読することで、心を解き放った。エミリーは、自分の身体を定点として植物と触れあい、精神を引き上げながら変化させ、書くことによってアルプスの頂きを目指すようになった。
ジミーさんの虚飾を削ぎ落した精神と、エミリーの孤独が癒され表現欲が呼応した歳月は、庭を造ることを通じての精神のよみがえりに結びついた時間だ。
ガーデニングを通じておのれの内部へと旅をするに従って、他人を尊重することを身に付け、他人との違いが際立ってくる。自己を肯定できれば、他人も肯定することが出来よう。自然+自己のありさまに対してベクトルが乱反射し、かつ変化し新たなフェーズに入ることができる。
更に考えた。自然だけでなく音楽や絵画などの精神活動によって人間はレジリエンスできるはずだ。それらを受け入れる側には、どのような変化=可能性があるのだろう。
では、レジリエンスが不可能なほどの外的、内的ストレスを受けた場合については、どうだろう。
 3. 論文に提示されたレジリエンスとは? 「回復力」と「復元力」
3. 論文に提示されたレジリエンスとは? 「回復力」と「復元力」
物理的に外部から加わった力によって変性した物質がはね返す力(元に戻ろうとする力)を言い、元の状態に戻る、あるいは変化しながら回復し状況に適応できる力を言う。主体と対象によりレジリエンスの方法が違うのは当然だろう。
社会のシステムの多様化から、自然災害などから回復する過程に見られるレジリエンスは多様で、人間の忍耐力が要求される。気候変動からのレジリエンスも大きな問題だ。外来種の繁栄によって、自然界の生態が変化していく。それに対するレジリエンスも努力はなされていても難しい。
現代の日本における不可逆的な重大災害、地震、洪水などに対するレジリエンスは可能だろうか。
回復力とは。
適応し、変化することに重点を置いている。自尊感情や自己肯定感を持ちながらも、 他者からの肯定的評価が必要とされるよう。自分を認め、他人から認められる----他者との関係性が重要で、環境に適応するために自己変容が求められる。自己変容を可能にするのは、他者との関係性を持てる時。これらは相互に影響しあう。
人はどこで学ぶのか。知の存在は認知や共感力に基づくもので広義には生き抜く知恵を言う。過去から学び人とは何かを知り、知恵によって変化するもの。これからの社会に生かす----良い方向へ向かうとの楽観性が基盤にある。
現代ははモンゴメリの時代よりもはるかに、人類が危機的状況にあるのは間違いない。転換期の今、危機を生き抜き次世代に命をつなぐために人の特性を考え、どう生きるべきか探ろう。
危機の在り方は増幅し、拡大していく、はたして人間のレジリエンス能力は対応できるのか。
相互に影響しあう危機と人間の持つ力。それは複雑に絡まり合い高巻きし登りあるいは下
り、問題と答え?が堂々巡りする。まるでさかさまに螺旋階段を上下しているかのように。
状況に対応する努力をなされるにしてもどこへ行くのか。
日本における大災害時に見られたが、命を脅かされるような状況に十分なサポートがあるかが問題で、他者に共感するより、自分自身を守ることに専念する利己的行動は他者との関係性とを失うだろう。
ひとりひとりが考える、楽観的に前向きに考える。ただし民主主義は多数決を原理とする。多数決だけで新たな危機が襲ってきたら、解決できるだろうか。そしてヒトはそこから学ぶことができるのだろうか。
グローーバル、ナショナル、ローカルのどの段階であれ、相互理解、認める、許すことが要求される。多様性を認めつながる。これはまことに難しく、理想にしかすぎないかもしれない。現在の世界における感染症の蔓延や戦争状態をレジリエンスする方法は見つけにくい。
 参考:レジスタンスとの違いは。抵抗 vs. 回復 参考:レジスタンスとの違いは。抵抗 vs. 回復
レジスタンスは、ショックやストレスに対して主に市民的抵抗を意味することが多く、統治者や占領軍に「抵抗する」能力を指すのに対し、レジリエンスは、ショックを受けた後に「しなやかに回復する」力、能動的に適応し成長すること。過去から現在への変化への適応。
 4.話題は飛ぶ。翻訳における会話文---ジェンダーの意識を持って読むこと。
4.話題は飛ぶ。翻訳における会話文---ジェンダーの意識を持って読むこと。
ここ数年、翻訳における会話文について考えることが多かった。
たとえば、村岡花子訳の『赤毛のアンシリーズ』、『エミリー三部作』ほかに付いて考えてみると、翻訳された会話文によって、話者の性格、生育歴、知性などが読み取れ、さらにその話者の社会的地位も現れてくることが多い。
アンの話す言葉には、揺らぎやためらいが少なく、貴種流離譚だけでは説明のつかない品格がある。これは訳者の村岡花子さんが、英語話者の中で学びカナダの文化を吸収し精神に取り入れつつも、日本人としてのアイデンティティを失わないように努力なされてきた結果としての訳文だからだろう。
日本文化を理解したうえでの翻訳は、創作の要素まで持つのではないか。これが村岡訳を後世の翻訳家が越えるのに難しい部分だと考えている。
小説は人間を通して時代を書く。作品はその時代の記憶で、訳語はその時代の政治形態、宗教、社会の在り方も含め、訳者の教養に裏打ちされたものになる。
訳された会話文には、訳者のもつ社会的規範が滲み込んでいるのが読み取れる。他訳を参照してみても、アン、またはエミリーの会話文は女性性を強調しているように感じるが、我われ読者はいつかその訳文を受け取り、アンやエミリーの性格を形作っていくことになる。無自覚の偏見や固定観念に惑わされることもある。
翻訳には秘められた政治性があることを覚えておきたい。特にアンシリーズには人種や宗教に対する偏見、優劣の思いが散見される。その裏にある作者、訳者の意図は自覚的だったのか。
 5.一番興味があることについて 5.一番興味があることについて
最近、特に英語圏で日本文学に対する興味が湧きおこり評価が高まってきている。
英ブッカー賞の最終候補に残った川上弘美氏の『大きな鳥にさらわれないよう』
(英訳:Under the Eye of the Big
Bird、翻訳:米田雅早氏)
英ダガー賞には(英国推理作家協会賞)『ババヤガの夜』王谷晶氏。(書名が間違っていました。Nさんありがとうございます。)
小川洋子氏の「密やかな結晶」2020年にブッカー国際賞の最終候補6作品に入った。
日独の言語で書く多和田葉子氏は、ドイツの権威ある文学賞「クライスト賞」を受賞。
2018年には、「献灯使」で「全米図書賞」の翻訳文学部門で受賞。
柳美里氏の『JR上野駅公園口』「全米図書賞」翻訳文学部門を2020年に受賞。
川上未映子氏は2022年、ブッカー国際賞の候補となった。
更にノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロの作品は言うまでもない。『日の名残り』『私を離さないで』、『遠い山並みの光』など。これらの作品を数え上げてみると、現代の日本文学は多彩な状況にある。
日本文学への評価が高まったその理由はどこに求められるだろう。静謐、記憶のあいまいさ、忘却、時の流れ、自然崇拝、細部に神が宿る、声なき声、読者が既に知っていたことを言語化したなど。日本人の精神性に惹かれているのだろうか。
比較して考えたいことがある。
第二次世界大戦の後、日本がいまだ混乱期から抜け切れていない1950年代に発表された『赤毛のアン』がなぜ熱狂的に受けいれれられたのか。村岡花子訳のすばらしさは言うまでもないが、それを必要とした何かが、日本の側にあったはずだ。
出版事業の復興には、明るく前向きなアンが必要とされた。父権主義的な社会からの解放、女性の自立を賛美する、生活の細部に美しいものを見つけようとする態度。これらがおおいに受け入れられるきっかけとなったのではないかと思う。
(「女の子で」ありながらその位置に安住することなく努力を続けるアンと、その後の二次的存在であることを強いられるアンの自覚のない苦しみを読み取れた読者は当時どのくらいいたのだろう。)
新訳も引き続き発刊され続けているのに加え、この春から新しくアニメが放映されている。さまざま「アン」関係の書籍が発行され、グッズが販売され、ミュージカルも上演されている。アン関係ビジネスが盛んである、アン本が日本人に受け入れられている理由はこれだけではないだろう。
海外の文学作品が日本語に訳され、アンが受け入れられた戦後の時代と、日本文学が(おもに)英語に翻訳され続けている現代の状況の背景には、相違点は
もちろんあるにせよある共通点があるように感じる。読書文化が確立されていたかに注目してみたい。
2025.8.10
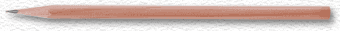
 追記 赤松先生へお尋ねしたこと。
追記 赤松先生へお尋ねしたこと。
 エミリ・ディキンソンの詩を論文の題辞に置かれた赤松先生のお思いはどこにあるのでしょう。
エミリ・ディキンソンの詩を論文の題辞に置かれた赤松先生のお思いはどこにあるのでしょう。
A loss of something ever felt I—
The first that I could recollect
Bereft I was—of what I knew not
Too young that any should suspect
—Emily Dickinson Fr1072, ll. 1–41
失ったのは特定できないもの。幼いころから感じている孤独感あるいは死別感、むりやり剝ぎ取られた何か。精神的に充足できない世界を引きずってきて生きてきたのに、さらに何かを失う恐怖。静かな変容。冷たい火。構造色として並ぶ言葉の群れ。
ディキンソンの詩は多重な意味を含みます。読者の自由な解釈はどこまで許されるのでしょうか。
還元する----詩に寄り添うか、自身に詩を組み込むか。
ある望みを抱いています。年齢を重ねるに連れ、作者が無意識に表現しようとしたことの真髄をくみ取ることができるようになると。
論文を拝読し、暑い夏の日、こんなことを考えていました。
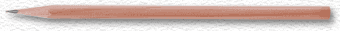
さらに。
 題辞に置かれたエミリ・ディキンソンの詩についてのお考えを伺い、赤松先生の感覚の鋭さに感嘆しました。
題辞に置かれたエミリ・ディキンソンの詩についてのお考えを伺い、赤松先生の感覚の鋭さに感嘆しました。
ずっと感じていた「農業の楽天性」をはっきり言語化してくださって理解が進みました。
さて、感想に「絵画や音楽にもレジリエンスの力があるのではないか」と書きましたが、それより重要なセラピーがあるのを遅まきながら気づきました。
あまりにも目の前にあるので、却って見えなかったこと。それは「アニマルセラピー」。
動物と触れ合うことによって、精神の回復を促進する方法です。リラックスし多幸感をもたらす、ストレス解消する、精神が安定する、自己肯定感を得られる、さらに行動する意欲が湧いてくる。
特に情緒豊かな哺乳類との交流を通じて、自分を認め他者を信頼できるようになるといわれています。
馬を通じたアニマルセラピーは、古くから行われていますし、高齢者施設では入所者に動物との触れあい(セラピードッグやセラピーキャットの存在)を通じて精神的な安定をもたらし、医療、福祉、教育など、さまざまな分野で活用されているようです。
作品のなかで、(やや発達障害?ミゾジニー?子供のころ何を失った?)マシュウに取っての牛や馬、ジミーさんの牛や豚、馬がその役割を果たしていると考えています。
エミリー三部作の中の猫。そして肝心なモンゴメリの猫も。この猫の存在は大きいですね。
毎朝、デッキに隣の酪農農家の猫がやってきます。餌を与え、撫でて可愛がると気分が充足したのか、自宅に帰ります。私の心もふわふわとした嬉しさで一杯。
----これはアニマルセラピーそのものでしょう。
暑い夏を、この新しい視点で作品群を読み返すことにします。発見があるかもしれません。
 |