 『赤毛のアンから黒髪のエミリーへ』拝読しました。 『赤毛のアンから黒髪のエミリーへ』拝読しました。
 退官記念の御著著をいただいて一年経ちました。通読ののち、より内容を理解するには、ある時間を置いたほうが、身に迫ってくる確かな感触を得られるのではないかと考え、この冬の寒さを味方にして熟読いたしました。 退官記念の御著著をいただいて一年経ちました。通読ののち、より内容を理解するには、ある時間を置いたほうが、身に迫ってくる確かな感触を得られるのではないかと考え、この冬の寒さを味方にして熟読いたしました。
改めて感じたのは、赤松先生の作者モンゴメリとその作品に対する尊敬の念でした。
行間から浮かび上がってくるのは、自らの来し方を顧み、自身のベースを深く知ることが、作品を理解する助けになるということでした。他人を観察し内省し、普遍的な真実に行きつくべく今を知り未来を思う。そしてその未来を愛することができるかを己に問う。モンゴメリに寄り添い生き方に共鳴してきた真摯なお気持ちが、この本全編に溢れていました。赤松先生が人生を積み重ね努力を続けてこられたからこそ、モンゴメリの努力、苦しみ、家族間のトラブルがより理解できるまでの精神の高みに到達なさった。こう考えました。
人の世は歳月の積み重ね。病のうちに亡くなったモンゴメリの人生を思うとき、その年齢に近づく赤松先生がどのようにモンゴメリの精神と共振なさるかを深く知りたい。その望みが満たされました。
 ついで感じたのはアンシリーズ本と自分との一体化です。シリーズのなかのどの本を手に取っても、何度も読み返しているので、次の展開は当然予想がつき、読んだ当時の記憶が再現できるのです。 ついで感じたのはアンシリーズ本と自分との一体化です。シリーズのなかのどの本を手に取っても、何度も読み返しているので、次の展開は当然予想がつき、読んだ当時の記憶が再現できるのです。
鑑賞者が一つの作品を一つの世界として認識するのは、作品を作り上げる人(著者)だけでなく、それを読み、心に容れる人の力も必要とするのでしょう。鑑賞者が著者とともに世界を作り上げ、新しく己を知ることが、生きていく推進力として働きます。
 アンの想像力は自然=具象から見えないものを見る力を持ちます。具体から帰属する場所を見つけるアンの努力と生き方は、「家」をテーマに開けていきました。 アンの想像力は自然=具象から見えないものを見る力を持ちます。具体から帰属する場所を見つけるアンの努力と生き方は、「家」をテーマに開けていきました。
日本の古語で、「庭」は家の前の開けた場所の意味。開けた場所とは人が生きていく場所の象徴です。その場所に名前を付ける---日本昔話に伝わるように、日本の古代では、名前には霊が宿り、名前を知られることは相手に屈し支配されることだとされています。
アンが名付けた自然はアンの身のうちに同化し、その場所で生きるアンの精神を成熟させたのでしょう。
 自立とは、相互に依存しつつ自分自身を知り行動すること。これを教えられました。 自立とは、相互に依存しつつ自分自身を知り行動すること。これを教えられました。
マリラと二人、マシューの死を悼み、心のうちをさらけ出すマリラの姿を見て、アンは愛を確信します。愛されている安心感を持ち、相互扶助の関係を受け入れられるようになる----この自己肯定はその後の人生への起爆剤としても働くことでしょう。
アンを愛することで、受け入れがたい自分を認め許すことができたマリラ。悲しみとともに連帯が生じます。マリラの成長をしみじみ感じるこのシーンは美しく、アンが家長としての意識を持ち始めるのはこのころからでしょうか。
(最近亡くなった大江健三郎氏の言葉に「想像力とは他人の存在を想像すること」とありました。この言葉を、他人と協調するからこそ、自分自身も育てることができるのだと理解しました。後述しますが、相容れない他人を認めることも想像力の働きで、登場人物の中でも理解できない人を洞察すること、すなわち他者への理解力を養う能力を育むのもその想像力がなせるわざなのでしょう。ただし想像力を駆使することには責任が伴いますが。
孤児として引き取られたアンには、性格形成に影響を及ぼす「家庭」の中での兄弟間の葛藤がありません。マシューとマリラの二人の注目と愛を一身に受け、アンがアンらしく成長できたこと。それまで厳しい環境に育ったアンに取って幸いなことでした。兄弟間の順列は時に大きく性格に影響しますから。
 限嗣相続制について。 限嗣相続制について。
かねてこの相続制度に強い興味を持っていました。モンゴメリは祖母が死亡したのち、住んでいた家を出なければならなかった----帰属すべき家を失う----このことがモンゴメリ自身の結婚への動機づけになったとも考えられます。父権主義のあの時代、女性が一人で生きていくのは難しく、結婚していること、子供を持っていること、これが一人前の女性としてのタグであったかと思います。
『赤毛のアン』で、マニラがグリーンゲイブルスを相続していることから、法的に相続させる方法のほかに、特定の個人に(血縁がある、ない)相続させることも可能だったか、その方法は?という疑問が湧いてきます。マリラは家屋敷と畑を相続した。これは女性としては当時稀有なことだったのではありませんか。マリラが相続できたのは、マシュウがそのように手続きをしておいたからでしょうか。浮世離れしたところのあるマシュウにとって、それを行動に移すことは難しいことだったと推測できます。
生活費すべてを小作料で賄うには、農作物の価格が安定し、一定の収入があることが求められます。同じ時代、状況の日本の農家と比較すると、アンの教師としての給料に手を付けなくてもグリーンゲイブルスでの生活は豊かです、豊かに見えるように描かれています。
 作品の舞台となったのは、19世紀後半から20世紀の早い時期。当時の日本は明治20年から30年代で、列強に押されて日清戦争に走り、日露戦争に流れが加速していく時期でした。 作品の舞台となったのは、19世紀後半から20世紀の早い時期。当時の日本は明治20年から30年代で、列強に押されて日清戦争に走り、日露戦争に流れが加速していく時期でした。
二つの国の農家の暮らしを比較すると、日本の大地主制に苦しむ小作人の生活と、本に描かれた島の農家の豊かさと文化レベルの高さとの違いには驚くばかりです。
カナダの東の島に入植し、宗主国への恭順の意識を持ちつつ歴史を自らの手で作り上げた島の人々と、日本の大地主制=階級社会で貧困にあえぐ農民の対比に、農家出身の私は、ひたすら寄り添い思いを巡らすことしかできません。
19世紀後半の日本の農村の暮らしは、大地主と小作、都会と田舎の社会格差が大きく、子供に教育の機会が与えられず、女の子の身売りもあり時に餓死する人も出ています。現在の中国の、弾圧されている地方の状況にも似ているかもしれません。
 当時の結婚の形態----そこに確固たる女性の意思があったのでしょうか。戦前の日本では、家長の命令により結婚相手(結婚する相手の属する家と血脈)を決められてしまうことが普通に行われていました。 当時の結婚の形態----そこに確固たる女性の意思があったのでしょうか。戦前の日本では、家長の命令により結婚相手(結婚する相手の属する家と血脈)を決められてしまうことが普通に行われていました。
小説を書く時、家は重要なモチーフになります。守られている、帰属する、飛び立つ場所としての家をモンゴメリは自戒の意味も込めて描いたのではないか、と思わされました。
ついで湧いてきたのは、「相続した家屋を持たないモンゴメリが、暮らしを転々としながら人生を送ったことが、後年の精神不安定に結びついた一つの遠因ではないか」という疑問です。モンゴメリには産土に根ざし、生産者・正統住民としての住まいを求める精神が長く息づいていたのではないか。家に向かう精神のくびきをどうはねのけたのか。これは深く考えてみる必要がありそうです。
 エミリー三部作 エミリー三部作
この三部作はモンゴメリの自伝的作品で、主人公エミリーは作者の投影として書かれ、自身の体験も、文学に対する強い思いもエミリーに重ねたと考えます。
『赤毛のアン』シリーズに対して、エミリーシリーズの根底に流れるものは同じでも、伏流水が地上に現れる ---
その現れ方がそれぞれ違うのが印象的でした。読むにつれこれら三部作は、作者が子供のころから自覚していた、文学への探求心を具現した作品だとの印象を強く持ちました。はじめからシリーズで書くと決心してことに当たったモンゴメリの決意が感じ取れます。
だが、現実は厳しかった。夫ユーアンが赴任した教区での、牧師夫人としての役割を果たし、夫の不調を対外的に隠し続け、子育ての難しさ
が表面化する、と次々に問題が立ちはだかります。
自身の牧師夫人という立場と、信仰への不信感とも言える疎外感が、精神の安定を欠く遠因になったかもしれません。
そのせいでしょうか。最終作『エミリーの求めるもの』の終わり方、終わらせ方に違和感を覚えるのです。エミリーが作者自身の投影だとしたら、この不安定さは作者のその時期の精神状態から来たのもかもしれません。
 三部作は、モンゴメリ自身が成熟期の50代を迎え自分の精神を培ったものを知り、昔ながらの習俗を描きつつ、周囲の人間を観察し内省し今を知る努力が実った結果、形として現れたものと思います。 三部作は、モンゴメリ自身が成熟期の50代を迎え自分の精神を培ったものを知り、昔ながらの習俗を描きつつ、周囲の人間を観察し内省し今を知る努力が実った結果、形として現れたものと思います。
自己実現へのロールモデルとしてエミリーの成長を描写することは、のちの時代の少女や若い女性たちに「希望を持て」というメッセージとなったことでしょう。
アンとエミリーの背景にあるもの----長く伝わってきたものには、理由があるようです。
作品には民族的、歴史的アプローチ、先住民との確執、入植者同士の、フランス対イギリスの対立、そして本国イギリスとの関係という視点があまり描かれていないとの印象があります。
これはもちろん『赤毛のアン』がリアリズム小説、社会派小説ではないことからの必然です。しかし社会の中で評価されるのが小説で、この二つは切り離すことができないものでしょう。
しかし、高い知性を持つモンゴメリが、その問題に気付いていないわけがありません。人間の愚かさをも余さず描く社会派小説でない。だからこそ小説として
の緩さ、弱さがあり、時に少女小説、こども向けの本というとらえ方をされることもありました。
(のちに戦争の歴史を、日常の暮らしの中から掘り起こし、記録した文学との評価が定まってきたのは、まったく正しいことだったと思います。)
人は見ようとするものを見ます----アンやエミリーののなかに自分を見つけようとします。その性格、暮らしぶり、他人との関係性、受け取る側にとってそれは融通無碍に変化し、読者が社会に適応し、適応しつつおのれを肯定する助けになるのです。読者は主人公の人生を掬い取り自分の心に蓄積します。自分が過去に体験し経験したことを作品の内容と擦り合わせることができる楽しさを味わいます---記憶や経験は個人を作りあげるものです。作品を評論するのではなくて、主観的な受け取り方をすることから読書は始まります。
カナダの歴史全般の知識があれば、よりアンシリーズへの理解が深まると考えるのは短絡に過ぎますか。作品は作品そのもので評価されるべきか、設定されている時代や背景を知るとより理解が深まると考えるかどうか。これでいつも悩みます。
 世界で、特に日本でアンシリーズのファンが多いのはなぜか。これは世界で特有の出来事なのか。日本の読者がアンやエミリーをどう受け入れたかを考えてみます。 世界で、特に日本でアンシリーズのファンが多いのはなぜか。これは世界で特有の出来事なのか。日本の読者がアンやエミリーをどう受け入れたかを考えてみます。
同時代の日本の農村の暮らし(小作農、極度の貧困)と比較してみると、モンゴメリ作品には先住民との対立や入植した農民の貧困を描かれていません。日本のそれに比べてはるかに豊かです。しかし日本の農村と同じく宗教間の対立、農業収入が気候に左右される、村の文化的な催しなど共通した部分が多いようです。
小説は読者を納得させるものでなければなりません。宗教的な価値観を持つことは、戦後の日本でも継承されてきたことです。父権主義社会においても、宗教行事も含め地域社会を動かす女性の力が大きかったとはいえ、アンが進学をあきらめたように、個人の犠牲によって家族運営ができるイメージは、戦後村岡訳が発表された時代においても、日本の社会で肯定されていた生き方でした。
家族のために義務を(愛を伴ったとは言え)果たし苦境を乗り越え教師としての資格を手に入れたアンの生き方が、日本の女性に魅力的に受け入れられました。家族のために犠牲になるか、それとも自分の意思を通すか。この両方の生き方を肯定してくれるのが『赤毛のアン』の生き方。日本女性がアンの中に見出したものは、自立と自己犠牲。占領国アメリカに対する「憧れと反発」もあったことでしょう。
そこに日本の伝統的価値観と儒教的保守主義が絡まります。
戦後、新しい日本は、アンのようなモデルを必要としていました。西洋文化を日本に取り込む、これは明治の文明開化にも匹敵し、精神構造の根底に通じるものがあるとの印象を持つのです。
過去のある時代を探り現在と対照することは、結果として現在の社会のあり方や問題をあぶりだしてくれる。興味深いことです。
 特に村岡訳が果たした役割。 特に村岡訳が果たした役割。
翻訳されたものを読む行動は、翻訳者の身体から泉のように湧き出る言葉を掬い取る営み。
心意伝承=何世代もの人間が、その土地に住み続けた人々の、翻訳不可能な意識の揺らぎ。これを翻訳するのは至難のわざです。翻訳は、訳者が原作をどのように解釈したかを紹介する働きで、原作から派生したものではなく、ひとつの作品です。
村岡花子はその成育歴や環境から、カナダの作者モンゴメリの作品を訳すのに適任でした。文化のはざまに生き、日本人としてのIDを持っていたものの、その立ち位置から前後左右に揺れているのを感じます。その揺れは小さいものの、読者はその揺れはばに共鳴し、溶け込みながら自分の世界を作り上げることができたのです。
民主化され、言語表現が自由になる以前、戦時中に訳されたこと、これはあの時代において奇跡に近いことでした。
 母語と翻訳すべき言語を平等に扱い、両者を繋げる、あるいは対立があれば和解させる役割を果たすのが翻訳者。われわれ一般読者と異なり、作品に対峙するに、全く違った次元に立っているのかもしれません。あるいは翻訳者は英語を母語として生きてきた人々でないと分からない、微妙な差異を感じることができる特別な能力を持っているのでしょうか。その差異を感じることができたのが村岡花子さん。表現方法というより、精神にカナダが息づいていたのが村岡花子さん。自己がカナダとの関係によって支えられている----文化によって自己のあり方が異なる----これは他の翻訳者にはないことで、息を吐くように表現する----それを読者は呼吸することができる----この喜びは何物にも代えられないことでした。 母語と翻訳すべき言語を平等に扱い、両者を繋げる、あるいは対立があれば和解させる役割を果たすのが翻訳者。われわれ一般読者と異なり、作品に対峙するに、全く違った次元に立っているのかもしれません。あるいは翻訳者は英語を母語として生きてきた人々でないと分からない、微妙な差異を感じることができる特別な能力を持っているのでしょうか。その差異を感じることができたのが村岡花子さん。表現方法というより、精神にカナダが息づいていたのが村岡花子さん。自己がカナダとの関係によって支えられている----文化によって自己のあり方が異なる----これは他の翻訳者にはないことで、息を吐くように表現する----それを読者は呼吸することができる----この喜びは何物にも代えられないことでした。
ここらへんで『アンと言う少女』ネットフリックス のアンが目の前にちらつき、立ちはだかります。映像の持つ力の大きさには驚くばかりで、深層に入り込んでしまった「ネットフリックスのアン」をどう扱うか。受け入れるか、追い出すか?
この映画に描かれたのは、現代カナダ人の思いが作り上げたアンの新しい側面ではないか。アンの怒りは助けを求める声なの
だから。 |
 ある人物の個性を描くには、個を立たせる方法と、全体の中で占める位置で表す表現方法があります。前者はごく当たり前の描き方ですが、後者は周囲の人間像をジグソーパズルの一つのピースとして表現し、その人たちに囲まれたある個人を表現する方法です。『赤毛のアン』ではまずリンド夫人が、そしてマシュウ、マリラの順で登場し、アンを取り巻いて彼女の性格を際立たせる働きをします。自分が他者を認識するのではなくて、他者が呼ぶ自己が生じる動きに結びつきます。この方法を初めての作品に取り入れたのは、モンゴメリの天与の才能がなせるものか。自己のイメージを他人の目によって作り上げる方法なのでしょう。 ある人物の個性を描くには、個を立たせる方法と、全体の中で占める位置で表す表現方法があります。前者はごく当たり前の描き方ですが、後者は周囲の人間像をジグソーパズルの一つのピースとして表現し、その人たちに囲まれたある個人を表現する方法です。『赤毛のアン』ではまずリンド夫人が、そしてマシュウ、マリラの順で登場し、アンを取り巻いて彼女の性格を際立たせる働きをします。自分が他者を認識するのではなくて、他者が呼ぶ自己が生じる動きに結びつきます。この方法を初めての作品に取り入れたのは、モンゴメリの天与の才能がなせるものか。自己のイメージを他人の目によって作り上げる方法なのでしょう。
ではこのジグソーパズルを、はめ込んだままひっくり返してみましょう。
自分はなぜこの人物が嫌いなのか、反感を持つのか、興味を持つのか、という点から人物を考えてみます。例えばジョーシー・パイ。ジョーシーは正直です。他人を傷つけても心に痛みを感じません。人として文化に矯正される以前の人間の姿を具現しています。嫉妬し、独善で、他人との関係にガードを作りません。悪意はあるものの人間の原型のようなピュアな人間です。
嫌い、反感をもつ。これらから自分の精神をのぞき込むことができる。この逆転現象ともいえる構造をもう少し観察してみたいと思っています。
|
読書は他者との出会い。未知だったものを感じ、知る営み。登場人物と自分との共通点を探るのは確かに楽しい。しかし自分に似ていて共感できる部分がある、親近感を持つ。これでその作品を評価するのは、自分から遠くにあるもの、理解できない人の性格を知ろうとする努力を怠ることになろう。自己愛に浸り、自己同一化することは読書が能動的でなくなる。他者の気持ちを洞察する知的な行動こそ読書の喜びではないか。 2023.5.5追記 |
 時代区分においての読者の特徴があるか。 時代区分においての読者の特徴があるか。
戦後日本を再建し新しい社会を形作るという課題に対し、村岡訳の、逆境に打ち勝ち自分の人生を決めようとする前向きで楽観的なアンが歓迎されました。躍動的な社会にアンの活発な性格が受け入れられました。
以後、生活が豊かになるにつれ、衣食住の描写に関して、アンに描かれた暮らしの細部を再現しようする動き、憧れが募ってきます。
既述しましたが、アンから二つの生き方が読み取れます。
『赤毛のアン』『アンの青春』あたりまで自立しよう、女の子も男の子並みに生きられると説きます----なんと素晴らしい!自立しておのれの人生を生きなさい。生活の細部に注目し充足していきなさい。男子に負けるな、男子に勝ちを譲りなさい。アンの結婚生活を是とする日本女性VS働く女性。この双方の考え方が両立した時代で、そのまま現在に至ります。
未来を描く小説が未来を書いているわけではない。過去を書いた小説が過去を論じたわけではない。どちらも目の前にあるけれど、見ようとしていないものを時間や空間をずらしつつ描いている「現代の小説」なのだ、という印象を受けます。
 男女差別に対する反感を持ちつつ、変えようもない差別を肯定して受け入れるしかない----混乱の中に女性は生きていました。さらに高度成長期には社会が個の家族形態を採用し、専業主婦として生きるには、結局母の立場に埋没するしかない時代が続きました。性別役割分業の時代です。
家父長的な、ジェンダー不平等な社会で生きることを強いられました。 男女差別に対する反感を持ちつつ、変えようもない差別を肯定して受け入れるしかない----混乱の中に女性は生きていました。さらに高度成長期には社会が個の家族形態を採用し、専業主婦として生きるには、結局母の立場に埋没するしかない時代が続きました。性別役割分業の時代です。
家父長的な、ジェンダー不平等な社会で生きることを強いられました。
1980年代から個人の自由度が大きくなります。多様性が増すとともに、不安感や閉塞感が表面化してきました。アンシリーズの結婚生活の描写が喜んで受け入れられたのは、自身を肯定することに繋がるからか。対して社会参加している女性に取っては「結婚したアンは面白くない」との意見が多く、働く自分と「結婚したアン」の二律背反の感情を持てあましていた女性が多くいたはずです。
救いは、モンゴメリ日記が当時の社会情勢をくまなく記述していることから、再評価されてきたことでしょう。
第一次二次世界大戦において、(カナダが独立しているかどうかも含め)モンゴメリの日記(日誌)の資料としての貴重さが再認識される。歴史の記録者としての役割に注目されています。
 20世紀終盤から21世紀に入り、世界経済が停滞した期間が長く続きます。日々の細かい部分を充足させることが生活の満足につながる。衣食住の細部を再現する動きが加速してきました。この時期、料理、ハンドメイドなどのアンの暮らしの解説本が雪崩を打って発表されています。 20世紀終盤から21世紀に入り、世界経済が停滞した期間が長く続きます。日々の細かい部分を充足させることが生活の満足につながる。衣食住の細部を再現する動きが加速してきました。この時期、料理、ハンドメイドなどのアンの暮らしの解説本が雪崩を打って発表されています。
そして、いま社会が変わろうとしています。
SDGSへの流れ、コロナ禍、ウクライナ侵攻と続きます。これまで世界はグローバル化が進むと信じられてきました。ところが現在のアメリカ=韓国=日本の関係を見ても、経済の安全保障が重要視され、国と国の対立が際立ってきています。国境を意識する時代が始まったのかもしれません。EU創設以来30年、結束もほころびが見え始めました。
 これからアンの世界がどう受け入れられるか。昔の暮らしに対するノスタルジアに浸るか、生きていく活力を得る文学として享受されるか。階層化する社会で、日々の暮らしの細部に喜びを見出すか。戦争の記録として、戦時を支える努力や市民の暮らしを描写した『日誌』に価値が置かれるようになるか。それはひとえ社会の変遷に対応する読者の姿勢によるのではないでしょうか。 これからアンの世界がどう受け入れられるか。昔の暮らしに対するノスタルジアに浸るか、生きていく活力を得る文学として享受されるか。階層化する社会で、日々の暮らしの細部に喜びを見出すか。戦争の記録として、戦時を支える努力や市民の暮らしを描写した『日誌』に価値が置かれるようになるか。それはひとえ社会の変遷に対応する読者の姿勢によるのではないでしょうか。
新訳が次々に送り出されます。これはモンゴメリ+新翻訳者がそれとなく差し出す「生きる本質」に気付くチャンスともとらえられましょう。他訳を参考にし、
翻訳者がおのれの言葉を醸し表現できる時代は多様性に満ちているもの。
英語、英文学、歴史といった教養は重層的です。今後翻訳は世の中のあり方に合わせて変化していく。それを肯定的に受け取ることが、思索を深くできるきっかけになりますように。
本とは何か、読書する目的は何か。
本は、どれを選択しても自分にとって思索を巡らす糧となります。
多くの読者に支持される作品は、それぞれの時代を生きる読者の内面を投影している部分があると信じ、主観性を持ちつつ主人公、読者ともに成長し、次第に「読み」に客観性を帯びてくることが興味深いところです。
本の魅力は、読み返すたびに発見があることです。自身の成長とともに見えてくる新しい知見をわがものにする---さまざまな段階で違った視点をもつことは、結果その時の自分と向き合うことなのでしょう。
自身が持つ問題意識を鏡として映し出す----言葉とは恐ろしい、文学とは深く静かで炎のように燃えさかるものです。こんな印象を持ちました。
さまざま書き連ねました。
この冬、雪が降りしきる中、御著作を手にさまざま思いを巡らしました。こういう機会を与えてくださったことを、感謝いたします。
他人と共生し、人が生きることを徹底的に肯定しているアンと、自分の意思を自分で支え行動に移すエミリーとは、底辺で結びついているものです。それを掬い取る読者に幸あれ。
これからも、モンゴメリ研究においては日本での第一人者であるとの矜持を持ちながら、ご活躍ください。
今年は、すこし自由な時間がおできになりますように。
開き始めた庭のコブシの花を眺めながら春の日々を迎えようとしています。
赤松先生 2023.3.26. Yama
 追記 追記
疑問があります。
1 アンは容姿にコンプレックスを持っていたが、「女の子」であることにコンプレックスを感じていたか。
2. アンはなぜ、メアリ・ヴァンスを引き取らなかったか。
『あしながおじさん』のジュディはなぜ孤児院の運営に関わらなかったのか。(赤松144P)この意見に重なりますが、「理想としている結婚」を体現したミスコーネリアに、メアリ・ヴァンスの庇護者としての役割を与えるためだったのか。
3. アンはなぜあのように正統派の英語を話せるのか。
貴種流離譚(若い神や英雄が他郷をさまよいながら試練を克服した結果、尊い存在となるとする説話の一類型 折口信夫による)では解説できない点が気にかかります。アンは文学のエッセンスを抽出する能力に恵まれたのか。
貴種流離譚を説いて血筋の尊さを示唆しているが、成育歴とそれまで読破した文学作品だけでは、その理由を説明できないと思うのです。(快読『赤毛のアン』菱田信彦著 彩流社刊164p)
4. アン・シャーリーはアン・シャーリーたるべく日々演じていた部分があるだろうか。
5. エミリーとテディ 結婚すると不孝になるか(赤松204p)
上記の『あしながおじさん』のジュディとあしながおじさんは、対等な関係ではありません。同じようにエミリーとディーンも対等ではありません。
高村光太郎と千恵子。この関係性を考えると、芸術家のテディとエミリーが結婚して、互いを尊重しあい能力を高めあえるか疑問です。エミリーの精神的な成長は読み取れます。しかしテディは? 他の人間の存在を尊重し、自我と他我と調整できるか? 自我を矯めることができるか、あるいは芸術家はその必要を感じないのか。----テディの成長は記述されていません。独立的自己観と相互依存的自己観とのせめぎ合いが見られると想像します。
再度書きますが、大江健三郎氏の言葉に「想像力とは他人の存在を想像すること」。想像力が創造力に結びつけば作品が生まれます。しかし現実は厳しいものでしょう。二人の間に「子供」が入り込むと関係性は大きく変化します。男性性と女性性の間には、深いい溝があります。しわ寄せがくるのは、フレキシブルな脳を持つ女性であろうかと。
Just
Like a Man. と嘆くエミリーを見たくありません。
6.
ミスコーネリアの結婚は「経済的に自立している+相手を自分の家に迎えいれる」「相手と対等になれる」」からか。このミスコーネリアの結婚が、モンゴメリの結婚観の現れであると。(赤松162p)
私も同様に、個人的にはアンシリーズの中で一番好ましい結婚の方法とあり方は、このミスコーネリアの結婚だと考えます。
7. モンゴメリの筆のなかに、無意識の男性至上主義を書きこんだ部分があったか。本人自身が気づかないうちに男社会に期待される少女像に誘導されているか。(これは作者モンゴメリが、それと自覚していたとしても、逃れられなかった社会のあり方とそこからの圧力があったと考えます。)
ただし、現在の人間が過去のある国のある状態を批判することはできません。その社会は当時、歴史的経緯を経てそのように在ったのですから。人びとの心性は時代を超えて変わらないものがある一方で、時代によって大きく異なるものもあるでしょう。過去から何かを学び取ろうとするとき、これを常に頭の片隅に置いておいたほうがより正確に捉えられるのではないかと思います。
8. 植物好きとして、庭に注目してみます。原作によるとグリーンゲイブルスには、モンゴメリが理想とした庭を映し出したバリー家のような花壇はありません。マリラに取っての充実した生は、果樹園の収穫(実)に象徴されているようです。マリラの潔癖な性格からか、実用にならない花を植えることはなかったようですが、マリラの女性性が養われるにつれ花が植えられていくのに気づきます。
9. ひらめきと直感。この違いは?もたらされる条件は?
ああ、またおしゃべりが過ぎました。でもあれこれ考えていると時が素早く過ぎていくようです。
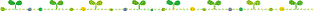 |
 『赤毛のアンから黒髪のエミリーへ』拝読しました。
『赤毛のアンから黒髪のエミリーへ』拝読しました。